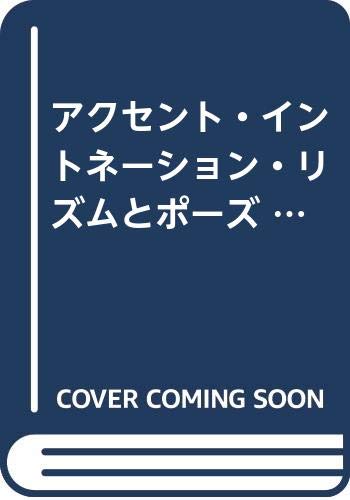8 0 0 0 OA 音声言語医学領域の用語とその解説 (III)
- 著者
- 廣瀬 肇
- 出版者
- 日本音声言語医学会
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.149-153, 1991-01-25 (Released:2010-06-22)
7 0 0 0 OA 変声期の音声と身体発育について
- 著者
- 斉田 晴仁 岡本 途也 今泉 敏 廣瀬 肇
- 出版者
- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.4, pp.596-605, 1990-04-20 (Released:2008-03-19)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2 4
Past studies on the relationship between mutational voice change and body growth were generally made on grouped subjects and no exact longitudinal observation was performed. In the present report, a longitudinal study was made on 100 young male students in their puberty, in which voice recordings and measurements of physical parameters including body height and weight were performed twice for each subject with yearly interval. Information on subjective evaluation of voice abnormality was also obtained from each subject. The recorded voice samples were subjected to subsequent analysis for obtaining fundamental frequency (F0) and formant values. The following results were obtained.1. A negative correlation in the rate of change was observed between F0 and physical parameters such as body height and weight, and sitting height.2. It was suggested that the mutational period consisted of the rapid and slow phases. The rate of growth in body height and sitting height was more significant in the rapid phase. 3. Subjective voice abnormality and physical growths such as the development of the laryngeal prominence were often noted even before the rapid phase. After the rapid phase was over, all the cases showed secondary sexual characteristics including the laryngeal prominence.4. Before and during the rapid phase, there was a tendency for the values of F1 and F2 to increase, while that of F3 to decrease. After the rapid phases was over, there was a trend that F1 and F2 increased, while F3 remained unchanged.
1 0 0 0 OA 機能性発声障害
1 0 0 0 OA 海域利用調整の法律問題について
- 著者
- 廣瀬 肇
- 出版者
- 公益社団法人 日本航海学会
- 雑誌
- 航海 (ISSN:24331198)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, pp.55-65, 1988-06-25 (Released:2017-07-12)
1 0 0 0 OA Wallenberg症候群と嚥下障害
- 著者
- 廣瀬 肇 望月 高行
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.274-282, 2005-10-15 (Released:2011-03-18)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2
最近経験したWallenberg症候群の1例を中心に耳鼻咽喉科医としての立場から嚥下障害とその対策について考察した。今後, 脳血管障害の頻度の増加が予想されWallenberg症候群に直面する機会も稀ではないと考える。本症の病態をよく理解し, 適応があれば積極的な手術的治療に踏み切る必要があり, その手技についての知識と経験を備えていくことが耳鼻咽喉科専門医に求められるところである。嚥下障害の病態は複雑であり, その対策にあたっては, 学際的アプローチに加え患者の家族の理解と協力が不可欠である。各医療施設においても, 耳鼻咽喉科医をはじめ, 各科の医師およびコメディカル専門職員の協力に基づくチームアプローチによって嚥下障害診療の実をあげていくことが肝要である。嚥下機能の改善は患者のQOLの向上に直結するもので, 耳鼻咽喉科医として今後ますますこの問題に積極的に取り組んでいくべきである。
1 0 0 0 アクセント・イントネーション・リズムとポーズ
- 著者
- 国広哲弥 廣瀬肇 河野守夫編
- 出版者
- 三省堂
- 巻号頁・発行日
- 1997
1 0 0 0 OA 運動障害性構音障害
- 著者
- 廣瀬 肇
- 出版者
- 日本口腔・咽頭科学会
- 雑誌
- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.25-30, 1991-03-31 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 13
Motor speech disorders (dysarthria) comprise a group of speech disorders resulting from disturbances in muscular control due to impairment of any of the basic motor processes involved in the execution of speech. During the period of 10 years from 1980 to 1989, the incidence of motor speech disorders in the author's clinic was 16.7% (248 out of total of 1, 485 patients with language and speech disorders). In clinical practice, it is quite important not to overlook progressive neurological diseases, such as bulbar palsy . In this paper, points of clinical examination are described together with perceptual and acoustic methods of evaluation of pathological speech. The importance of total rehabilitation of dysarthric subjects is emphasized, and the use of different types of speech aids is recommended.
1 0 0 0 OA 声帯ポリープ術後の声の衛生
- 著者
- 山口 宏也 四倉 淑枝 佐多 弘策 渡辺 陽子 廣瀬 肇 角田 晃一 大石 公直
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.232-238, 1988-07-25 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2
目的; 喉頭ポリープの術後成績を左右する因子のうち「声の衛生」に注目し術後成績との相関を検討した.対象: 過去3年間に (全身麻酔下で) 手術を行い, 術後3カ月以上経過を観察し得た50症例 (男女比, 24: 26) である.方法; 職業, 病悩期間, 喫煙歴のほか声の乱用, 誤用の有無について詳しく問診した.改善度は術前, 術後の聴覚印象, 局所所見, 各種音響分析結果や患者の満足度などで総合的に判定した.結論; 病悩期間1年未満と1年以上とでは術後成績上有意義差は認められなかった.問診から誘因あるいは原因として48例 (96%) に何らかの声の乱用, 誤用が認められた.47例が1~24カ月で治癒.術後, 声の衛生を守った方が3カ月以内に治癒し易いこと, および守らないと治癒まで4カ月以上かかることが統計上有意であった.喉頭ポリープの手術的治療に声の衛生の重要性を強調したい.
1 0 0 0 OA 神経疾患と音声障害
- 著者
- 廣瀬 肇
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.5, pp.508-514, 1998-10-15 (Released:2011-03-18)
- 参考文献数
- 21
耳鼻咽喉科の境界領域として神経内科領域が注目されている。神経疾患に伴う耳鼻咽喉科的症状には多くのものがあるが, ここでは音声障害をとりあげて概説した。音声障害を来す神経疾患のうち, とくにパーキンソン病, 脳血管障害, 運動ニューロン疾患, 小脳疾患, 多系統萎縮症, 重症筋無力症についてそれぞれの音声医学的問題点に言及した。さらに最近, 中枢神経障害に起因するジストニアとして理解されている痙攣性発声障害について, その治療を中心に述べた。
1 0 0 0 OA 発声機能検査施行上, ガイドラインについて
1 0 0 0 OA 一側性大脳半球病変における麻痺性 (運動障害性) 構音障害の話しことばの特徴
- 著者
- 遠藤 教子 福迫 陽子 物井 寿子 辰巳 格 熊井 和子 河村 満 廣瀬 肇
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.129-136, 1986-04-25 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 10
一側性大脳半球病変における麻痺性 (運動障害性) 構音障害患者26例 (左大脳半球病変群14例, 右大脳半球病変群12例) および, 正常者13例の発話サンプルについて, 5名の評定者が, 聴覚印象に基づき評価した結果, 以下の知見が得られた.1) 今回対象とした麻痺性構音障害群における評価成績は, 正常群とは明らかに異なっており, 話しことばの障害があると判定されたが, 障害の程度は全般に軽度であった.2) 障害の特徴は, 仮性球麻痺と類似していたが, 重症度など異なる面もみられた.3) 障害側を比較すると, 概して左大脳半球病変群の方が重度の障害を示した.4) 病変の大きさと話しことばの重症度との関係は, 明らかではなかった.5) 従来, 大脳半球病変による麻痺性構音障害は, 病変が両側性の場合に出現するとされていたが, 今回の結果は一側性病変でも出現し得るということを示唆するものであった.
1 0 0 0 OA 痙攣性発声障害に対する音声訓練
- 著者
- 小林 範子 廣瀬 肇 小池 三奈子 原 由紀 山口 宏也
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.4, pp.348-354, 2001-10-20 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 4 2
痙攣性発声障害 (SD) に対する音声訓練の有効性を検討するために, SDと診断された患者17名に対して訓練を実施した.喉頭の過緊張の軽減に有効とされる6種類の訓練手法と発話速度低下の訓練を組み合わせて使用した.音声症状の評価は, 3名の言語聴覚士による「喉詰めの度合い」の聴覚印象評価によって行った.17名のうち9名が音声の改善と結果に対する患者自身の満足に基づいて訓練を終了し, 2名が通院困難のために訓練中止, 6名が音声改善中のために訓練継続という結果であった.訓練終了例の年齢, 病悩期間, 訓練回数, 初診時の重症度には共通点が認められなかった.重度の音声症状が軽度にまで改善して訓練を終了したものが4例あった.「ため息発声」, 「気息声」, および発話速度低下訓練が多くの症例に有効な訓練手法であった.本研究の結果は, SDに対する治療法の一つとしての音声訓練の有効性と訓練の実施方法を示唆するものと思われる.
1 0 0 0 OA 中枢神経疾患と音声障害
- 著者
- 廣瀬 肇
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.121-128, 2001-04-20 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 53
- 被引用文献数
- 1 1
中枢神経疾患の臨床症状として構音・プロソディの障害とともに音声障害の存在が注目されている.わが国において, これらの障害は一括して運動障害性構音障害と呼ばれることが多い.ここでは各種の疾患における音声症状について最近の報告を中心に概説した.
- 著者
- 福迫 陽子 遠藤 教子 紺野 加奈江 長谷川 和子 辰巳 格 正木 信夫 河村 満 塩田 純一 廣瀬 肇
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.209-217, 1990
- 被引用文献数
- 2 2
脳血管障害後の痙性麻痺性構音障害患者のうち, 2ヵ月以上言語訓練をうけた24例 (平均年齢61.6歳) の言語訓練後の話しことばの変化を聴覚印象法 (日本音声言語医学会検査法検討委員会による基準) を用いて評価し, 以下の結果を得た.<BR>(1) 0.5以上の評価点の低下 (改善) が認められた上位7項目は, 順に「明瞭度」「母音の誤り」「子音の誤り」「異常度」「発話の程度―遅い」「段々小さくなる」「抑揚に乏しい」であった.<BR>(2) 重症度 (異常度+明瞭度の和) は24例中16例, 約7割に何らかの改善が認められた.<BR>(3) 一方, 「音・音節がバラバラに聞こえる」「努力性」「速さの程度―遅い」などでは評価点の上昇 (悪化) も認められた.<BR>(4) 症状の変化は症例によって多様であった.
1 0 0 0 変声障害 ─機能性発声障害と捉えてよいか─
- 著者
- 廣瀬 肇
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本気管食道科学会
- 雑誌
- 日本気管食道科学会会報 (ISSN:00290645)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.434-434, 2008-08-10 (Released:2008-08-25)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2 3
- 著者
- 廣瀬 肇
- 出版者
- 東京法令出版
- 雑誌
- 捜査研究 (ISSN:02868490)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.10, pp.89-99, 2005-10
- 著者
- 廣瀬 肇
- 出版者
- 東京法令出版
- 雑誌
- 捜査研究 (ISSN:02868490)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.48-59, 2009-03