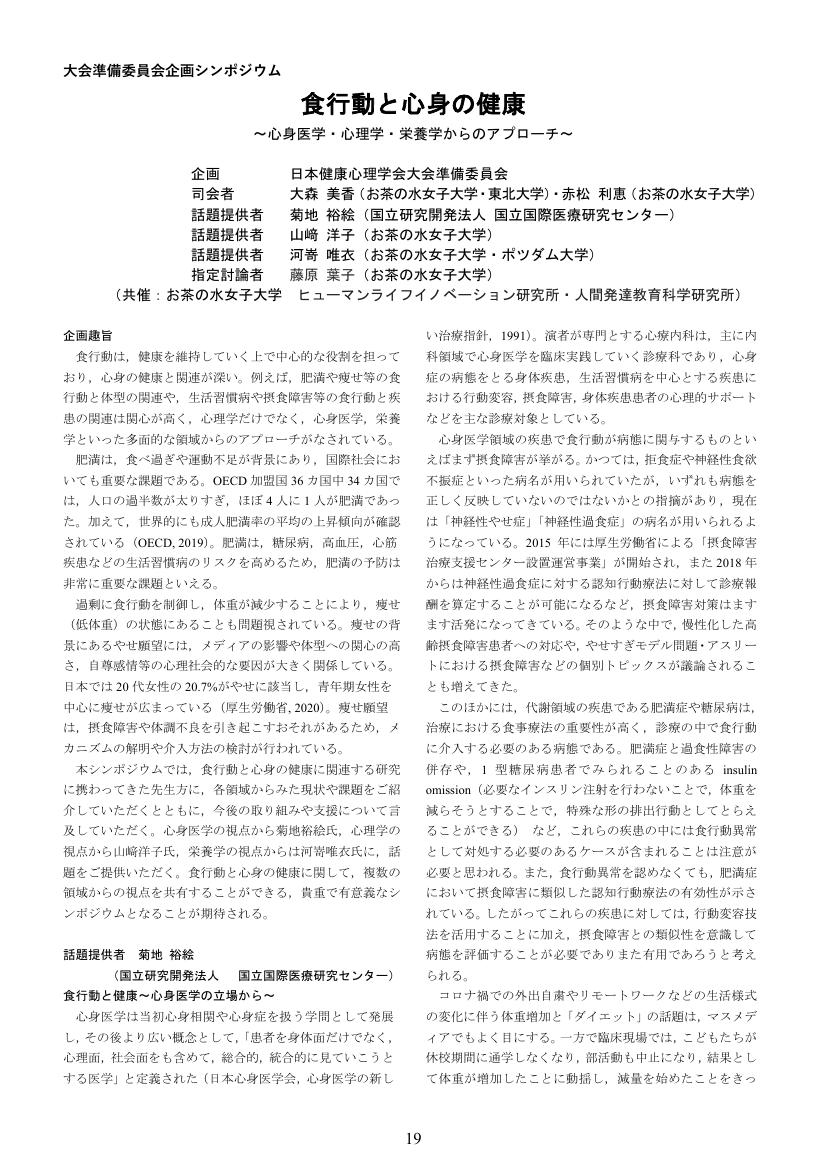19 0 0 0 OA サリンによる神経学的後遺症
- 著者
- 菊地 裕絵
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.80-83, 2016 (Released:2018-02-08)
- 参考文献数
- 7
サリンはアセチルコリンエステラーゼ阻害作用を有する毒性物質である。コリンエステラーゼ活性は 3 ヵ月で回復するとされるものの,慢性的に持続するもしくは新たに生じる所見や症状も報告されている。サリンによる長期的な影響は,1994 年の松本サリン事件および 1995 年の東京地下鉄サリン事件の被害者の複数年にわたるフォローアップを通して調査が行われており,身体症状では全身倦怠感やめまいといった症状のほか,眼が疲れやすい,見えにくいといった眼症状が比較的高率に認められている。また慢性期の検査所見としては,重心動揺検査や眼科検査での異常が報告されている。サリンによる慢性期の身体症状のなかには,何らかの身体的異常所見を伴い,神経学的後遺症としてとらえられうるものがあると推察され,引き続き,病態生理や機序の解明が求められる。一方で外傷体験に伴う心理的要因の関与は身体的要因と排他的なものではないこと踏まえても,被害者の慢性期の身体症状について心身両面からの視点を持つことは重要である。
10 0 0 0 OA 心身医学的アプローチが有効であった身体表現性障害を合併した食物アレルギーの1例
- 著者
- 西原 智恵 菊地 裕絵 安藤 哲也 岩永 知秋 須藤 信行
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.264-271, 2017 (Released:2017-03-01)
- 参考文献数
- 7
食物アレルギーは多様な症状をきたしうるが, 心理的要因や併存しうる身体表現性障害を考慮した診療が行われなければ, 症状が遷延し重篤となりうる. 今回, 食物アレルギーと身体表現性障害を併存し, 身体的介入のみを受けたため多彩な症状が遷延し, 高度な生活障害に至った症例を経験した. 心身医学的介入が症状の改善に有効であったため報告する. 症例 : 40代, 女性. 2年前よりさまざまな食品を摂取した後に発疹, 腹部膨満, 四肢脱力, 情緒不安定などの症状が出現するようになった. 複数の医療機関で食物アレルギーが疑われ, 穀物・果物全般の除去を指導されたが症状は持続. 精査を希望しアレルギー科を受診した際, 四肢脱力をきたし緊急入院となった. 評価では, 食物アレルギー症状以外の症状を説明できる器質的異常を認めず, 身体表現性障害の合併が疑われた. 入院下の行動制限, 外来での情動への対処や自己主張の指導により, 身体表現性障害症状は改善し, 食物アレルギー症状も自制内となった.
2 0 0 0 OA 食行動と心身の健康 ~心身医学・心理学・栄養学からのアプローチ~
- 著者
- 日本健康心理学会大会準備委員会 大森 美香 赤松 利恵 菊地 裕絵 山﨑 洋子 河嵜 唯衣 藤原 葉子
- 出版者
- 一般社団法人 日本健康心理学会
- 雑誌
- 日本健康心理学会大会発表論文集 34 (ISSN:21898812)
- 巻号頁・発行日
- pp.19-20, 2021-11-15 (Released:2022-10-05)
- 著者
- 井上 建 小坂 浩隆 岡崎 玲子 飯田 直子 磯部 昌憲 稲田 修士 岡田 あゆみ 岡本 百合 香山 雪彦 河合 啓介 河野 次郎 菊地 裕絵 木村 大 越野 由紀 小林 聡幸 清水 真理子 庄司 保子 髙倉 修 高宮 静男 竹林 淳和 林田 麻衣子 樋口 文宏 細木 瑞穂 水田 桂子 米良 貴嗣 山内 常生 山崎 允宏 和田 良久 北島 翼 大谷 良子 永田 利彦 作田 亮一
- 出版者
- 日本摂食障害学会
- 雑誌
- 日本摂食障害学会雑誌 (ISSN:24360139)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.3-12, 2023-10-05 (Released:2023-10-05)
- 参考文献数
- 19
COVID-19パンデミック下,摂⾷障害患者における社会からの孤立,受診控え,症状の悪化,さらに新規患者の増加などが報告された。そこで我々は,2019,2020,2021年の神経性やせ症(Anorexia Nervosa: AN)および回避/制限性食物摂取障害(Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder: ARFID)の新規患者数,入院患者数,性別,年齢層,COVID-19の影響の有無について,国内で摂食障害を専門的に診療している医療機関に対して調査を依頼した。すべての項目に回答のあった28施設の結果について集計・解析した。ANの新規・入院患者数はそれぞれ,2019年は400人,266人,2020年は480人,300人,2021年は610人,309人であった。一方,ARFIDの新規・入院患者数はそれぞれ,2019年は70人,15人,2020年は97人,22人,2021年は112人,17人であった。AN,ARFIDともに2019年と比較して2020年,2021年は新規患者数,入院患者数ともに増加し,これは10代でより顕著であった。さらにANにおいては20代の患者も増加していた。COVID-19 パンデミック下にARFID 患者数の増加が示されたことは重要な知見であると考えた。
1 0 0 0 OA 肥満の心身医学領域のトピック —認知行動療法・スティグマ—
- 著者
- 山崎 允宏 菊地 裕絵
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.242-248, 2021 (Released:2021-04-01)
- 参考文献数
- 43
肥満は, 発症および経過にさまざまな心理社会的因子が関わる, 代表的な 「心身症」 である. 肥満に対してはこれまで行動療法を含むさまざまな治療が試みられてきたが, 治療からの脱落や減量した体重の維持が大きな問題となっている. 治療からの脱落や減量した体重の維持に影響を及ぼす肥満患者に特有の認知的特性が明らかになってきており, 肥満に対する認知行動療法 (personalized cognitive-behavioral therapy for obesity : CBT-OB) が注目されている. また, 最近では肥満に対するスティグマの話題が, 医療の世界を超えた社会問題となっており, 患者の医学的アウトカムとの関連も明らかになってきている. このような背景から, 今後肥満治療に対する心身医学の役割はますます大きくなっていくものと考えられる.
1 0 0 0 摂食障害患者における自殺
- 著者
- 菊地 裕絵
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.8, pp.796-800, 2016
<p>摂食障害では疾患に伴う身体的・心理的苦痛や社会機能の低下といったQOLの障害にとどまらず, 死の転帰をとることもある. 自殺は主要な死因の一つであり, 神経性やせ症での自殺による死亡率は1.24/千人年, 自殺による標準化死亡比は31.0であり, 神経性大食症ではそれぞれ0.30/千人年, 7.5と報告されている. 精神疾患の中では, 統合失調症, 大うつ病性障害, 双極性障害, 物質依存に次ぎ, 自殺による死亡率が高い. 摂食障害の中での自殺リスク要因としては排出行動・併存精神疾患の存在, 重症度などが挙げられているが, 軽症例でも自殺リスクは一般人口より高い. また, 摂食障害患者では自殺の意図を伴わない自傷行為が自殺例数に比して他の精神疾患より多いと指摘されているが, 繰り返す自傷行為が周囲の人間の疲弊や治療者の自殺リスクの過小評価につながらないよう注意が必要である.</p>
1 0 0 0 OA 受験生と心療内科
- 著者
- 富田 吉敏 菊地 裕絵 安藤 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.8, pp.849-855, 2017 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 6
大学受験は重要なライフイベントだが受験ストレスにより不調を訴える受験生は多い. 筆者は4年間で当科を受診した大学受験生を10例経験した. 現役高校生が9例で, そのうち7例が女性であった. 半数が頭痛を訴え, 8例が検査上で不安を認めた.治療前, 受験終了で症状は軽快すること, 受験ストレスで症状を生じた自身の特徴を把握することが将来的に重要であることを筆者は説明. その後, 受容・傾聴の姿勢で, つらい事柄を吐露させるベンチレーションをコーピングとした対応をとり, ほとんどが受験終了とともに軽快した. 受験ストレスによって心身へ影響がでる機序こそが心身相関であり, その理解を促す心身医学的治療は, 現状を受け止め, 症状の悪化を防止し, 目標を達成する一助を果たしている. 本報告は心身が消耗した予備校生たちを “受験生症候群” とした報告のように, 大学受験で心身が不調となり心療内科を受診した受験生の特徴と治療経過をまとめたものである.