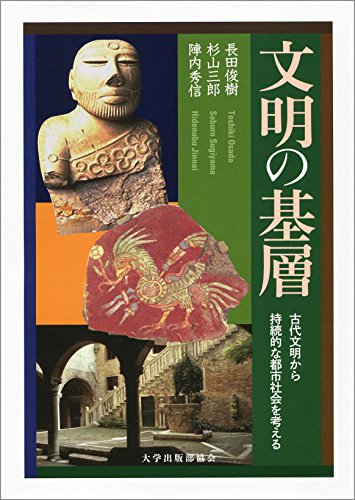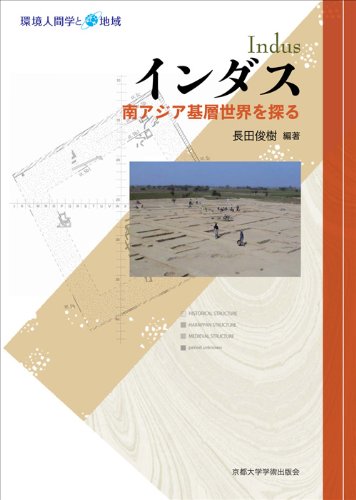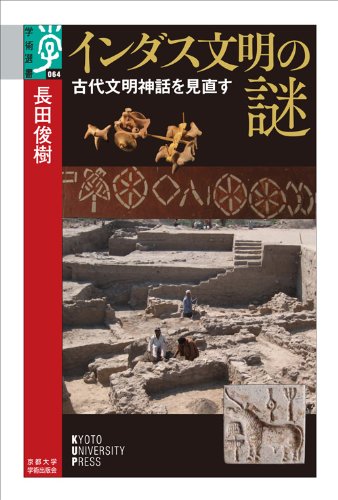- 著者
- 長田 俊樹
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.179-226, 2001-03-31
さいきん、インドにおいて、ヒンドゥー・ナショナリズムの高まりのなかで、「アーリヤ人侵入説」に異議が唱えられている。そこで、小論では言語学、インド文献学、考古学の立場から、その「アーリヤ人侵入説」を検討する。
- 著者
- 長田 俊樹
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.179-226, 2001-03
さいきん、インドにおいて、ヒンドゥー・ナショナリズムの高まりのなかで、「アーリヤ人侵入説」に異議が唱えられている。そこで、小論では言語学、インド文献学、考古学の立場から、その「アーリヤ人侵入説」を検討する。まず、言語学からいえば、もし「アーリヤ人侵入説」が成り立たないとしたら、「印欧祖語=サンスクリット語説」もしくは「印欧祖語インド原郷説」が想定されるが、いずれも、Hock(1999a)によって否定されている。また、インド文献学では、リグ・ヴェーダの成立年代問題など、たぶんに解釈の問題であって、インド文献学がこたえをだすことはない。考古学による証拠では、インダス文明が崩壊した時期における「アーリヤ人」の「大量移住」の痕跡はみとめられず、反「アーリヤ人侵入説」の根拠となっている。結論をいえば、じゅうらいの「アーリヤ人侵入説」は見直しが必要である。「アーリヤ人」は「インド・アーリヤ祖語」を話す人々」とすべきで、かれらが同一民族・同一人種を形成している必要はけっしてない。また、「侵入」も「小規模な波状的な移住」とすべきで、年代についても紀元前一五〇〇年ごろと特定すべき積極的な根拠はない。
3 0 0 0 OA 比較言語学・遠隔系統論・多角比較 : 大野教授の反論を読んで
- 著者
- 長田 俊樹
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.404-373, 1998-02-27
『日本研究』第十三集において、われわれは大野教授の「日本語=タミル語同系説」を検証した。それに対し、大野教授は『日本研究』第十五集でわれわれの検証に反論を提示した。そこで、今回この反論を含め、再び大野説を検証した。
- 著者
- 長田 俊樹
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.248-243, 1996-03-31
2 0 0 0 日本の生活文化の通文化性に関する総合的研究
- 著者
- 白幡 洋三郎 村井 康彦 井上 章一 小野 芳彦 山地 征典 園田 英弘 村井 康彦 飯田 経夫 山折 哲雄 イクトット スラジャヤ 長田 俊樹 白幡 洋三郎 セルチュク エセンベル
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 国際学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1994
平成6年度は、イスラム文化圏における日本の生活文化の受容調査であり、対象国としてトルコを選び、イズミール、アンカラ、イスタンブールを中心に調査を行った。トルコはイスラム文化圏とはいえ、近代化に一定の成功をおさめた国であり、生活用品の分野においては先進国と同様の工業製品がみられるものの、日本製品はきわめて少なかった。また親日国であるといわれているにもかかわらず、教養・実用・趣味・娯楽等の分野においても日本にかかわりのあるものは意外なほどに見つからなかった。むしろ西洋、とくにドイツとの関係が著しいことが確認できた。このことにより、トルコをイスラム文化圏と見るとともに、西洋文化圏もしくは西洋文化に強く左右されている文化圏と見て、日本文化とのかかわりを考察すべきであろう。平成7年度の対象地域は南アジア・東南アジアであった。ベトナムにおいては、ベトナム戦争終結後、社会主義政権が新たな経済政策をとり、その安定的発展によって民衆の生活に新しい展開が生まれている。その新しい展開の中に日本の伝統的な文化に属す茶道・華道なども、一定の受容が見られる。しかしとりわけ日本の生活文化としては、現代の大衆文化と見てよい電化製品の普及やカラオケ・コンピュータゲームなど娯楽分野での受け容れがきわめて顕著に見られた。また、もともとは中国経由で入ってきた盆栽が、日本語のBONSAIとして広まっている。すなわち中国経由の既存文化が、外からの刺激(日本の文化)によって新しい展開を見せている点で注目される。文化の盛衰を構造的に分析する材料として重要だと考えられる。またインドにおいては、日本の生活文化の進出はきわめて低調であり、大衆文化としてほとんど受け入れられていないことがわかった。華道や俳句では、知識人を核にした富裕層にのみ愛好会や同好会の形で存在している程度である。これは国民の所得水準によって規定されているものと考えられ、日本の生活文化の普及を大衆レベルでの異文化受容と考えた場合、経済的な要因が大きな困難となる実例であろう。タイにおいては、広い分野での日本の生活文化の受容が見られる。とくに日本の食品や生活用品はすでに広く生活の中に定着している。日本食やインスタントめんなどは、日本の手を放れ自前で独自の加工を施したものも豊富に出回っている。マンガは日本のものが翻訳されて各種出版されており、タイ人の手によるタイ語ならびに中国語の漫画が出回るほどになっている。娯楽や実用・趣味の分野でも日本の生活文化は広く受容されていることがあきらかとなった。平成8年度の調査地域である旧社会主義圏では、生活必需品のレベルでの日本の生活文化受容が見られたものの、それ以外での、「教養」「精神」「趣味」「娯楽」など、経済的な余裕に左右される分野での受容は乏しいことが明らかとなった。この地域では、社会主義政権の崩壊後、生活は不安定になったが、一方で西側諸国からの物資・情報が、以前より広範に流入している。従って、旧社会主義政権下にくらべて「異文化」の受容は進んではいるものの、その範囲は狭い。テレビ、冷蔵庫、オ-ディオ機器などの電化製品では、高価な日本製はあこがれの的だが、日本製を装ったものが市場に流通しており、特異な日本の生活文化受容が見られる。社会主義政権の崩壊に急激な暴力革命が伴ったル-マニアでは、経済復興が遅れており、国民生活に余裕がなく、日本製品に限らず西側の製品全般が贅沢品とみなされ、これらの需要は低迷している。華道・茶道・盆栽・俳句などの教養分野は、わずかに一握りのインテリ層に受容され、禅や宗教など精神文化の領域は表面にはまったく現れていない。日本の生活文化を大衆レベルでの海外への進出からとらえると、受容する側の生活水準に規定されることが明らかになった。したがって、文化の通文化性に関しても、その文化項目固有の「通文化性」は、受け入れる側の経済的、文化的状況に大きく左右されるといえるであろう。
1 0 0 0 OA インド東部稲作民の自然観ームンダ人の事例を中心に
- 著者
- 長田 俊樹
- 出版者
- 日本熱帯生態学会
- 雑誌
- Tropics (ISSN:0917415X)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1+2, pp.147-151, 1998 (Released:2009-03-31)
- 参考文献数
- 7
The Munda people, who lives in the Chotanagpur plateau in eastern India, is a ricecultivator. This paper is to investigate the Munda’s view on Nature. I begin to discuss the concept of soul in Mundari, which is very complicated. In the correspondence to the word ‘soul’ in English, we have four words; e.g. ji, roa, raisi, wnbul. The words roa and raisi are used only for humanbeings, domesticated animals; i.e., cows and goats, and main crops; i.e., rices and finger millets. Further, I found the paratlelism between human’s or ancestoral soul and rice’s soul in the myths and rituals. This is an important idea to understand the Munda’s view on Nafire. Moreover, the Munda people prays God for successful rice cultivation in the agrarian rituds. These ue singbonga (Sun God), buru bonga (Mountain God) and ikir bonga (River God). All is belonging to the nature. It means that the rice-ancestor-nature complex can be found in the Munda microcosmos. ln conclusion it seems to me that the Munda culture also contains a typical feature of pan-Asian rice culture. We need a comparative study on Asian rice culture in this respect.
1 0 0 0 OA 農耕儀礼と動物の血(上) : 『播磨国風土記』の記述とその引用をめぐって
- 著者
- 長田 俊樹
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.81-123, 2000-02-29
『播磨国風土記』の一節に、動物の血、とりわけ鹿の血を稲作儀礼としてもちいる記述がある。この一節は、折口信夫など、おおくの学者が引用している。そこで、この引用がだれによって、どのようにおこなわれてきたのか、検証するのがこの小論の目的である。
1 0 0 0 IR A Field Study Collecting Cultivated Crops and Useful Plants in Sagaing Region of Myanmar in 2014
- 著者
- 土門 英司 Min San Thein 竹井 恵美子 長田 俊樹 河瀬 眞琴
- 出版者
- 国立研究開発法人農業生物資源研究所
- 雑誌
- 植物遺伝資源探索導入調査報告書 = Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources (ISSN:24347485)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.343-365, 2016-01
本報は2014年11月にャンマーのザガイン地方域,とくにナガ族居住山地を対象に実施した植物遺伝資源に関する共同現地調査隊の報告である.今までに行なってきた東南アジアの山村での現地調査や観察の結果,他地域との交流が活発ではなく多様な在来作物・有用植物遺伝資源の収集が期待されるナガ族居住地域を対象に選んだ.本調査隊はカムティ郡区およびラヘー郡区のナガ族山村を訪問し,GPS情報,方名,農作業法,調理法等の利用法とともに植物遺伝資源を収集した.山地の傾斜地では焼畑が共通して営まれ,主要食用作物であるイネとともに,モロコシ,ハトムギ,トウモロコシ,シコクビエ,フジマメ,タケアズキ,ダイズ,キャッサバ,シャロット,トマト,エゴマ,トウガラシ,ローゼル,ニガウリ,ササゲ,ヘチマ,カボチャ,サトイモ類,ヤマイモ類,背の高いアカザ類,カミメボウキ,ナギナタコウジュ類,カラシナ,バナナ,ショウガ等が栽培されていた.現地調査隊はイネ29点,トウモロコシ6点,ササゲ5点,トウガラシ類5点,サンショウ類4点,インゲンマメ4点,ハトムギ3点,アワ3点,タケアズキ3点,ダイズ3点,アカザ類3点,エゴマ3点他,計102点を収集し,これらはミャンマーと日本の両国のジーンバンクで保存されることとなった.調査した作物の方名は多様で,特にラヘー郡区で顕著であった.また,ザガイン地方域の山地の焼畑で栽培される作物の種類はカチン州,ラオス中北部,インド・ナガランド州の山地の焼畑で栽培されるものとの共通性が高く,これらの地域の人々が「東南アジア農耕文化基本複合」を共有していることが示唆された.ザガイン地方域の山地には多様な作物の地方品種が残存している一方,現在急速に進んでいる社会経済的な変革によって農業生物多様性が滅失すると考えられる.この地域の作物遺伝資源を可及的速やかに収集し研究すべきであると結論した.
1 0 0 0 OA <フォーラム4.>「日本語=タミル語同系説」の周辺をめぐって
- 著者
- 長田 俊樹
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.184-169, 1996-03-31
筆者は、主に言語学以外の自然人類学や考古学、そして民族学の立場から、大野教授の「日本語=タミル語同系説」を検討した結果、次のような問題点が明らかとなった。
1 0 0 0 文明の基層 : 古代文明から持続的な都市社会を考える
- 著者
- 長田俊樹 杉山三郎 陣内秀信著
- 出版者
- 東京大学出版会 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2015
1 0 0 0 インダス : 南アジア基層世界を探る
1 0 0 0 OA カンキツの分類と種の起源・伝播の解明-田中標本の解析と人文・社会学的調査ー
- 著者
- 北島 宣 山本 雅史 伊藤 謙 米森 敬三 深尾 葉子 安冨 歩 中崎 鉄也 山崎 安津 清水 徳朗 中野 道治 岳 修平 林 維真 鐘 國芳 中野 道治 長田 俊樹 渡邉 和男 河瀬 真琴 山下 満智子 前山 和範 中村 彰宏
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2016-04-01
ウンシュウミカン、カボス、などの両親が明らかとなり、多くの日本在来カンキツは、キシュウミカン、ユズ、タチバナに起源していることが明らかとなった。キシュウミカンは中国江西省の「南豊蜜橘」に由来することが示された。タチバナは台湾に起源し、沖縄を経て本土に伝播したと考えられ、タチバナの沖縄系統はシークワーサーとの交雑によって生じたことが示唆された。田中長三郎のカンキツ標本を整理してデジタル入力を行い、検索機能も付加してアーカイブ化を行った。田中長三郎の自筆スケッチなどの資料を蒐集・整理してデジタル化を行うとともに、和歌山県橘本神社のカンキツ博物館「常世館」に展示し、広く一般に公開した。
1 0 0 0 OA <フォーラム>比較言語学・遠隔系統論・多角比較 : 大野教授の反論を読んで
- 著者
- 長田 俊樹
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.404-373, 1998-02-27
『日本研究』第十三集において、われわれは大野教授の「日本語=タミル語同系説」を検証した。それに対し、大野教授は『日本研究』第十五集でわれわれの検証に反論を提示した。そこで、今回この反論を含め、再び大野説を検証した。
1 0 0 0 OA 日本語系統論はなぜはやらなくなったのか―日本語系統論の現在・過去・未来―
- 著者
- 長田 俊樹
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本語系統論の現在Perspectives on the Origins of the Japanese Language = Perspectives on the Origins of the Japanese Language (ISSN:13466585)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.373-418, 2003-12-26
1 0 0 0 インダス文明の謎 : 古代文明神話を見直す
1 0 0 0 日本人はキリスト教をどのように受容したか
- 著者
- 山折哲雄 長田俊樹編
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 巻号頁・発行日
- 1998
- 著者
- 長田 俊樹
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.179-226, 2001-03-31
さいきん、インドにおいて、ヒンドゥー・ナショナリズムの高まりのなかで、「アーリヤ人侵入説」に異議が唱えられている。そこで、小論では言語学、インド文献学、考古学の立場から、その「アーリヤ人侵入説」を検討する。
1 0 0 0 OA 日本語の混淆言語説
- 著者
- 長田 俊樹
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 表現における越境と混淆 = Border Transgression and Intermixture in Artistic Expression (ISSN:13466585)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.169-182, 2005-09-01
1 0 0 0 IR 農耕儀礼と動物の血(上) : 『播磨国風土記』の記述とその引用をめぐって
- 著者
- 長田 俊樹
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.81-123, 2000-02-29
『播磨国風土記』の一節に、動物の血、とりわけ鹿の血を稲作儀礼としてもちいる記述がある。この一節は、折口信夫など、おおくの学者が引用している。そこで、この引用がだれによって、どのようにおこなわれてきたのか、検証するのがこの小論の目的である。 引用した例をみると、おおきく三つの分野がある。それは民俗・民族学、日本史・考古学、そして比較神話学である。民俗・民族学者はこの一節と現代にのこる日本の民俗やアジア諸国の民俗とむすびつけてきた。一方、日本史・考古学分野では、日本の歴史にそって、同様な民俗をみつけだそうとしてきた。さらに、神話学者はハイヌウェレ型神話との関連を指摘した。それぞれの見解には納得できるものがふくまれているが、欠点もあった。(以上、『日本研究』第20集掲載) 結論として、筆者はこれを稲作儀礼として、アジア諸国の稲作文化域を想定しながら、コンセンサスのえられる見解を今後とも模索したい。そのさいには、あらかじめ想定された演繹法ではなく、帰納法で結論をみちびく所存である。また、試論として東南アジアでおこなわれる水牛供犠との関連性についてその可能性を指摘した。
- 著者
- 長田 俊樹
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.248-243, 1996-03