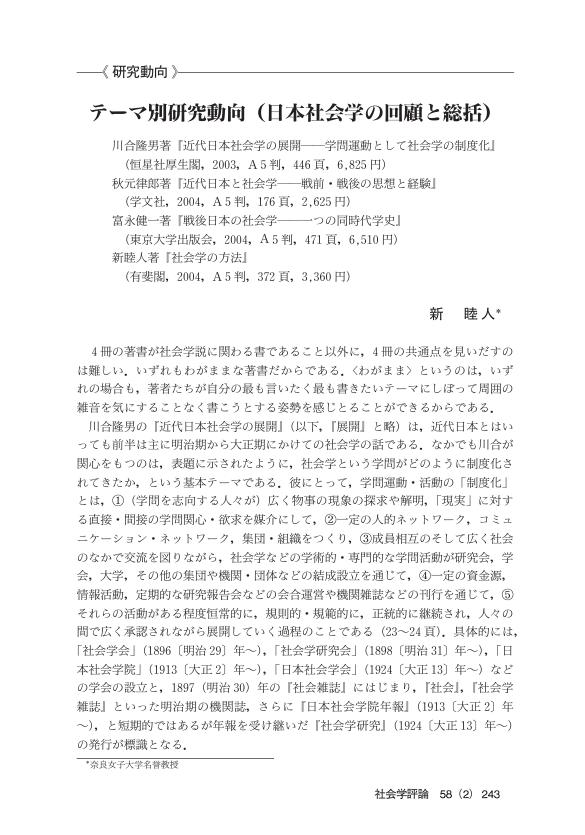1 0 0 0 書評 桑原桃音著『大正期の結婚相談 : 家と恋愛にゆらぐ人びと』
- 著者
- 大塚 明子
- 出版者
- 日本社会学会 ; 1950-
- 雑誌
- 社会学評論 = Japanese sociological review (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.150-152, 2018
- 著者
- 今田 絵里香
- 出版者
- 日本社会学会 ; 1950-
- 雑誌
- 社会学評論 = Japanese sociological review (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.148-150, 2018
- 著者
- 澤井 敦
- 出版者
- 日本社会学会 ; 1950-
- 雑誌
- 社会学評論 = Japanese sociological review (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.157-159, 2018
1 0 0 0 書評 田中大介編『ネットワークシティ : 現代インフラの社会学』
- 著者
- 三浦 倫平
- 出版者
- 日本社会学会 ; 1950-
- 雑誌
- 社会学評論 = Japanese sociological review (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.152-154, 2018
- 著者
- 石井クンツ 昌子
- 出版者
- 日本社会学会 ; 1950-
- 雑誌
- 社会学評論 = Japanese sociological review (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.264-266, 2018
- 著者
- 鷹田 佳典
- 出版者
- 日本社会学会 ; 1950-
- 雑誌
- 社会学評論 = Japanese sociological review (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.125-142, 2018
- 著者
- 城戸 浩太郎 杉 政孝
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.74-100, 1954-01-30
- 被引用文献数
- 1
In this article, which is a part of a series of reports based on the results of a field research in Tokyo, the writers attempt to analyse the characteristics of the structure of social consciousness of a modern urban population in Japan. This analysis is based on attitude measurements using two scales ; one designed to measure the authoritarian tendency in personality structure which has been affected by the traditional Japanese value-attitude system and which played an important role as a psychological basis of Japanese fascism : the other is designed to measure politico-economic orientation based on a socialistic-nonsocialistic dichotomy. The various means scores of these two scales are compared statistically, for each occupational group, different age categories, educational levels and political party allegiances.<BR>The main findings are as follows : 1) As for occupational differences, students and industrial workers are the most socialistic groups in politicoeconomic orientation, but industrial workers reveal more authoritarian and traditional tendencies than students, who are the most non-authoritarian group. The artisan group is most authoritarian and more nonsocialistic. The artisan group reveals a somewhat similar pattern of consciousness to that of the small entrepreneurs and manegrerial and executive types who constitute the most anti-socialistic groups. These groups have played an important role as active psychological supporters of Japanese fascism in the World War II. The white-collar groups as a whole shows similar mean scores on both scales, but groups within the white-collar category differ in their characteristic consciousness.<BR>2) There is a positive correlation between authoritarian and non-socialistic attitudes and age. The higher the level of education, the more non-authoritarian and socialistic the sample becomes.<BR>3) As for the political party allegiance, the supporters of <I>Jiyuto</I> (Liberal Party) and <I>Kaishinto</I> (Progressive Party) are the most authoritarian and non-socialistic, the supporters of the Left Socialist Party are most nonauthoritarian and socialistic. The Right Socialist Party adherents are rather similar to the conservative party supporters.<BR>4) The writers computed the multiple regression equations to both scales in relation to the underlying sociological variables such as age and occupation in order to determine the degree of association between these variables and manifest attitudes. Though the multiple correlation coefficients are not very high, it is demonstrated that occupation and standard of living have been stronger determining factors in politico-economic orientation and age and educational levels stronger determining factors in relationship to authoritarian tendencies.
1 0 0 0 OA 或るサムプリング調査の報告
- 著者
- 安田 三郎
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.114-130, 1953-09-25 (Released:2009-11-11)
This article is a preliminary report of a joint survery conducted in 1952 by seven investigators including the authors.The questionnaire used consisted of six sections, e.g. : (a) items relating to the authoritarian personality, (b) politico-economic orientation, (c) class identification, (d) social grading of occupation, (e) spatial mobility, (f) face-sheet.The population from which the sample for this survey was drawn is the adult male population of approximately 2, 500, 000 individuals living in the urban districts of the Tokyo metropolis.Considerations which entered into the decision concerning sample size were : (a) the precision of the estimate, (b) the precision of the test of significance, and (c) the limitation of the time and financial resources. The size thus determined wes 700.Stratified sub-sampling and double sampling were used. The population was divided into 70 strata according to the type of industry and social characteristics of each districts. One primary sampling unit (cho or chôme-street) from each stratum was selected by probability-proportionately and from there 70 primary sampling units 40 male adults in proportion to the size of each stratum were obtained. These adults were again stratified according to age, occupation, and the characteristics of their dwelling place, and the final sample of 700 was obtained at a sampling ratio of 4.5 Population from which the sample was drawn was inferred from the registry of family cards.Fieldwork was conducted through the use of the house-to-house interview method and 534 person's in the sample (%) were interviewed. In order to estimate the effect of failure to interview a portion of the sample, the age-and occupation-composition of the non-interviewed group was examined and the “quasi-re-survey” method was utilized. This examination shows that deviation due to non-interviewing of a portion of the sample was negligible.The theoretical framework and the results of this survey will be reported in the following issues by individual invertigators.
1 0 0 0 OA 橋爪大三郎著『性愛論』
- 著者
- 加藤 秀一
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.361-370, 1997-12-30 (Released:2010-04-23)
踏み込んだ検討に移る前に, まず本書の内容を概観しておこう。『性愛論』は, 先にその一部を引用した短い序章を別とすれば, 全部で6つの章から成っている (以下, 「」内の部分は基本的に引用であり, 〈 〉の部分は, 著者の主張を評者の解釈を経て要約したことを示す。短い引用箇所については, あまりにも煩瑣になることを避けるため, 当該ページの挙示は省略する) 。第1章「猥褻論」と第3章「性関係論」は, もともとひとつながりの論文として書かれたものであり, 内容的に連続している。ここでは〈社会空間は性愛現象と非性愛現象とに分離している〉という社会存立の「公理」が解説されている。中にはさまれた第2章「性別論」では, 「規範としての性別」の成り立ちが原理的に説明されている。以上3つの章は, 性愛という現象に関する著者の見方の最も基礎的な部分を述べた, 原理論的な部分である。これに対し, 第4章「性愛倫理」ではキリスト教における性愛観の変遷が簡単に跡づけられ, 第5章「性愛倫理の模造」は, 戦後日本における性愛関係書のベストセラーの内容分析にあてられている。これら二つの章は前半で示された原理論的視点から歴史的事象を分析する応用編といえるだろう。さらに一書の締めくくりとして, 「性愛世界の彼岸」と名づけられた終章が置かれている。これら全編にわたって評者が疑問としたい点は多いが, 紙数の制約から, 本稿では本書の前半部分で展開された原理論的内容に視野を限定して, その中心線をたどりなおしてみることにしたい。上に記したように, 著者が提示する最も基本的な認識枠は, 〈性愛領域/非性愛領域〉という対である。これが「人間社会」に普遍的に妥当する分析枠として提示される。他方, 「性愛」の領域が限局されると同時に, その外部では, 「言語と権力」という他の媒介の流通性が高まる, とされる。次の箇所は, 本書のこのような理論的要諦を示しているだろう。「血縁に基づく親族秩序は, 事実としての性交渉や性愛関係の広がりを, ある一定の正当化手続によって婚姻とみなされるようになった配偶関係のなかに封じこめる。そしてまた逆に, そうした婚姻を間に挟んで水平に拡がる人びとの相互関係を, 性愛への志向を脱色され言語的・権力的な作用へと純化されたものとする。こうして社会空間は, 全域的な一種の透明性を獲得する。この透明性は, より遠隔に対してはたらく普遍的な作用力, すなわち言語や権力のはたらきを, 当該空間の端から端にまで容易に到達できるようなものとする (111頁) 。ここから直ちに二つの問題が生じる。第一に「性愛領域」の内容 (「非性愛領域」の内容に比重が置かれないのは, 本書のテーマからして当然であるから, 本稿では問わない), 第二にそれと非性愛領域との関係づけである。大まかに言って著者は, 第一の問題に対してはLévi-Straussの提示した概念法を再構成することで答え, 第二の問題に対しては独自の分析を展開している。こうした意味で, 本書は Lévi-Straussの親族構造論における方法と理論を拡張して, 性現象一般の普遍的構造の記述をめざす企てである, と言えるだろう。本書そのもののなかにはその通りの表現はみられないが, その中心的なアイデアをより厳密に展開したといえる別の論考 (「親族・家族・社会シスデム-人類学的交換理論の論理とその拡張」, 『橋爪大三郎コレクションII 性空間論』勁草書房) がその傍証となるだろう。評者の疑問は, 先の二つの問題-相互に切り離せるものではないから, 二重の, とするべきか-の全域に関わっている。第一に, 「性愛領域」に直接的な身体関係としての「性交渉」から, 「家族~親族」といった社会制度までが含まれているが, それを「性愛」の名の下に一括りにすることへの疑問。評者の見解では, ここでは橋爪氏は, Lévi-Straussの誤謬を拡大再生産してしまっていると思う。これと関連して第二に, 橋爪氏は, 「性愛領域」に含まれた諸制度にすでに流通している権力作用をうまく理論に織り込むことができなくなってしまった。以下, これらの問題について検討していく。
1 0 0 0 構造主義の認識モデル : レヴィ=ストロースの場合
- 著者
- 上野 千鶴子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.2-17, 1975-11-30
レヴイ=ストロースの構造主義は、一九五八年『構造人類学』に見る公認の教義から、その客観的な構造を剔抉されなくてはならない。私見では、彼のアプローチは、階梯モデル、同型説、システム論的思考を特徴とする、合理主義的理解の方法の一典型であり、この観点からは「メタ=ストラクチャー」は、当該の事象を、より一般的・整合的な構造のうちに置換する上位モデルと解される。だとすれば、メタ=ストラクチャーを無意識の実在に等置する先験主義からも、これに発達を拒否する無時間モデルからも、私たちは免れることができる。彼自身及び彼の祖述家達の、方法をめぐる様々な錯綜した議論よりも、彼自身の構造分析の実際が、何よりも雄弁にそれを実証している<BR>すなわち、メタ=ストラクチャーは、文字通り「系の系」として上位構造なのであり、理解とは、この構造を構成する手続きそのものなのである。これが、認識の発達モデルを提供するピアジェの構造主義が主張することであり、同時に、構造主義的思潮を、西欧合理主義の伝統の最も多産な果実とする方途である。
1 0 0 0 OA 「理論形成はいかにして可能か」を問う諸視点
- 著者
- 舩橋 晴俊
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.4-24, 2006-06-30 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1
「理論形成はいかにして可能か」を問うためには, まず, 理論の役割とは何か, 理論の基本性格をいかに分類するかを考える必要がある.理論の役割には, 「規則性の発見と説明」「意味の発見」「規範理論の諸問題の解明」の3つがあり, 社会学理論は, 基本性格の差異に注目するならば, 「中範囲の理論」「基礎理論」「原理論」「規範理論」「メタ理論」の5つに分類することができる.理論形成を支える諸要因として, 学説研究, 実証研究, 問題意識と価値理念, メタ理論的な信念, 他の研究者との相互作用, 現実の社会問題との直面を提示できるが, これらが理論形成において果たす作用の比重は, 理論のタイプによって異なる.中範囲の理論や特定領域の基礎理論においては, 実証を通しての理論形成という方向づけに基づいた「T字型の研究戦略」が理論形成に有効であろう.この研究戦略に基づいて創造的な理論形成を達成したいくつもの先例が存在する.これに対して, 原理論においては, 独自の問題意識に基づいて, 先行研究の蓄積から鍵になる概念や論理を発掘し再編成することによって創造的な理論形成を成し遂げうるということが, 存立構造論によって例証される.中範囲の理論においては, 相対的に通常科学的な理論形成の比重が大きいのに対して, より根底的な水準の基礎理論や原理論においては, 認識の前提としての観点と価値理念の再定義を伴う科学革命的な理論形成が重要な意義を有する.
- 著者
- 笹島 秀晃
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.106-121, 2016
- 被引用文献数
- 2
<p>都心衰退地区に形成される芸術家街は, ジェントリフィケーションの契機となることが知られてきた. 芸術家の存在は, 不動産開発や飲食業・文化産業の集積を促し, その過程において地価は高騰し居住者階層は移り変わる. 先行研究では, ジェントリフィケーションのメカニズムを分析するにあたって, おもに不動産業者や消費者としての中産階級に注目してきた. ところが, 重要なアクターであるはずの美術作品の展示・売買を行う画廊については十分な分析がなされてこなかった. 本稿の目的は, 芸術家街を契機とするジェントリフィケーションのメカニズムを, 画廊の集積過程に着目して分析することである. 具体的な検討事例は, 1965年から71年の間に芸術家街から画廊街へと転換した, アメリカ合衆国ニューヨーク市SoHo地区である. 芸術家街であるSoHo地区に画廊が集積した要因は, 安価な地価や広い室内空間を備えた未利用の工場建築物の存在だけではなかった. むしろ, ニューヨーク市における美術業界の構造変動の中で, 画廊経営者が自身の美術的立場を明確にする際に準拠した, 芸術家街の表象という文化的要因が重要であったことを明らかにする.</p>
- 著者
- 野村 佳絵子 黒田 浩一郎
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.449-467, 2005-03-31
- 被引用文献数
- 1
日本では, 1970年代の半ば頃から, 人びとの健康への関心が高まり, それまでよりも多くの人びとが健康を維持・増進するための行動を心がけるようになったといわれている.周知のとおり, これらの現象は「健康ブーム」と呼ばれている.医療社会学では, このような「ブーム」の背景に, 「健康至上主義」の高まりを想定している.しかし, 「健康ブーム」も「健康至上主義」の高まりも, それらの存在を裏付ける証拠はいまのところ存在しない.そこで, 本論では, 書籍ベストセラーが人びとの意識や関心を反映しているとの仮定のもとに, 健康に関するベストセラーの戦後の変遷を分析することを通して, 人びとの健康についての意識の程度やあり方の変化を探った.その結果, 健康に関する本のベストセラーは1970年代の半ばに初めて登場したわけではなく, 1950年代後半から今日まで, そう変わらない頻度で現れていることが見出された.また, 「健康ブーム」といわれる時期の初期およびその直前には, 医学をわかりやすく解説する啓蒙書がベストセラーになっていることが発見された.したがって, 1950年代後半から今日まで, 人びとの健康への関心の程度にはそれほど変化がないということになる.また, 「健康ブーム」とされる時期に特徴的なことは, 健康への関心の高さではなく, むしろ, 健康に良いと信じられていることに対する批判的な意識の高まりではないかと推測される.
- 著者
- 山村 賢明
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.35-52, 1966
Our problem is—what is meant by the word mother in Japanese culture? What meaning is the mother presumed to have for the self in Japan? We took up a radio program called "Haha o Kataru" to grasp the meaning of the Japanese mother. In this program, many persons who are well-known in the mass conmunication world talk about their own mothers for fifteen minutes. We got one hundred and forty-four broadcasting tapes. From the point of view of our analysis whether the facts they told are true or not is unimportant, though interpretations or meaning they imputed are significant.<br>Three fifths of the subjects who spoke about their mothers are male. Sixty per cent of them are public entertainers, thirty-three per cent are intellectuals or artists, seven per cent have other occupations. A half of their mothers are already dead.<br>By analyzing themes appearing in their talks and their interpretation of them, we think we can construct the following conceptions of the mother.<br>1. The mother is essentially a valuable person.<br>2. The mother sacrifices herself to the child and the husband, and so doing she finds her life worth living.<br>3. The child can take advantage of such a mother (amaeru).<br>4. The mother may provoke guilt feelings within the child, especially after her death.<br>5. The mother is a poychological prop and stay for the child; and his achievement or what he is is looked upon what he owes to her.<br>6. The mother may be the motive for the child's achievements. (The child strives in his life in order to make his mother happy, and the child expects his own achievement to be appraised by her.)<br>7. The mother is sentimentalized or emotionalized as the object of the child's lifelong attachment. The word 'mother' (okâsan, ofukuro) itself induces specific sentimental reaction.
1 0 0 0 片瀬一男著『若者の戦後史――軍国少年からロスジェネまで』
- 著者
- 浅野 智彦
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.347-348, 2016
1 0 0 0 OA 家族社会学における構築主義的アプローチの展望
- 著者
- 松木 洋人
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.25-37, 2017 (Released:2018-06-30)
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 1
日本の家族社会学における構築主義的アプローチは, 近代家族をモデルとして家族を定義する核家族論的な研究枠組みの刷新が求められるという学説史的文脈のなかで受容された. その結果として, 構築主義的アプローチへの期待は, このアプローチが人々は家族をどのように定義しているのかに目を向けることによって, 「家族とは何か」を問うという点に寄せられることになった. しかし, 人々による家族の定義を分析の対象とする初期の研究例は, その文脈依存的な多様性を明らかにするものではあっても, 新たにどのような家族の定義が可能なのかを提示したり, 「家族とは何か」という問いに答えを与えたりするものにはなりえなかった. また, これらの研究が, 人々が家族を定義するために用いるレトリックに焦点を当てたことは, 多くの家族社会学者の研究関心との乖離をもたらすことになった. このため, 家族社会学においては, 構築主義的アプローチによる経験的研究の蓄積が進まず, アプローチの空疎化が生じた. このような状況から脱却するためには, 家族の定義ではなく, 人々の家族生活における経験に注目すること, そして, 家族の変動という家族社会学のいわば根本問題と結びつくことによって, 構築主義的アプローチが家族社会学的な関心を共有した研究を展開することが重要になる.
1 0 0 0 OA 戦後日本社会学とマルクス主義
- 著者
- 河村 望
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.34-43, 1966-12-10 (Released:2010-12-10)
By the defeat “Nipponshugi shakaigaku” (Japanese national sociology) which had been dominaht under the absolute Tenno system, practically lost its power, and in its place empirical and positive sociology, influenced by American sociology, prospered. Notwithstanding that this positive sociology and Marxism thory fundamentally are hostile to each other, criticism from the Marxist side of sociology was not sufficiently made in those days, and sociology akin to Marxism only dealt with the confrontation of the non-scientific Tenno system's ideology.About 1950 the theory of “structural=functional analysis” of American sociologists such as Parsons and Merton began to be introduced, and after 1955 the apposition between sociology and Marxism became clear as the theory of “mass society” lost ground. At this stage there appeared those who stood for the “critical absorption” of Marxism within sociology. They were discontented with the non-historical and super-class theory of American sociology and psychology, so they intended to develop positive sociology accepting Marxism as a grand framework. But they eventually couldn't deduce more than the protection of the past sociological method and the denial of Marxism.If we call these people “arbitrationists”, those who “absorb critically” the empirical thory of sociology from a Marxist view and intend to develop Marxism “creatively” can be called “revisionism”. It was after 1960 that this standpoint became clear as one current, and it has been greatly influenced by the revival of sociology in the sociolist states of East Europe and the U. S. S. R. and the opinion of Marxist sociology which is distinguished from a materialistic conception of history. Lately by introducing theories of “industrialized society” and “modernization” into the field of sociology, an attempt to confront Marxist theory extensively has been made.When I make a future observation from the above current, it is presumed that in so far as the attack on or revision of Marxism is made in the name of sociology, apposition between sociology and Marxism will strengthen thier hostile relation as an ideological apposition in Japan, too. In this trend Marxist sociology will make its revisionistic character clearer. And the ideological conflict between them will be continued unabel sociology as the bourgeois ideology is completely extinguished by the ruin of the bourgeoisie.
1 0 0 0 OA テーマ別研究動向(日本社会学の回顧と総括)
- 著者
- 新 睦人
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.243-253, 2007-09-30 (Released:2010-04-01)
1 0 0 0 OA 庄司武史著『清水幾太郎――異彩の学匠の思想と実践』
- 著者
- 奥村 隆
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.513-514, 2016 (Released:2018-03-31)
1 0 0 0 OA 高田昭彦著『政策としてのコミュニティ――武蔵野市にみる市民と行政のパートナーシップ』
- 著者
- 玉野 和志
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.511-513, 2016 (Released:2018-03-31)