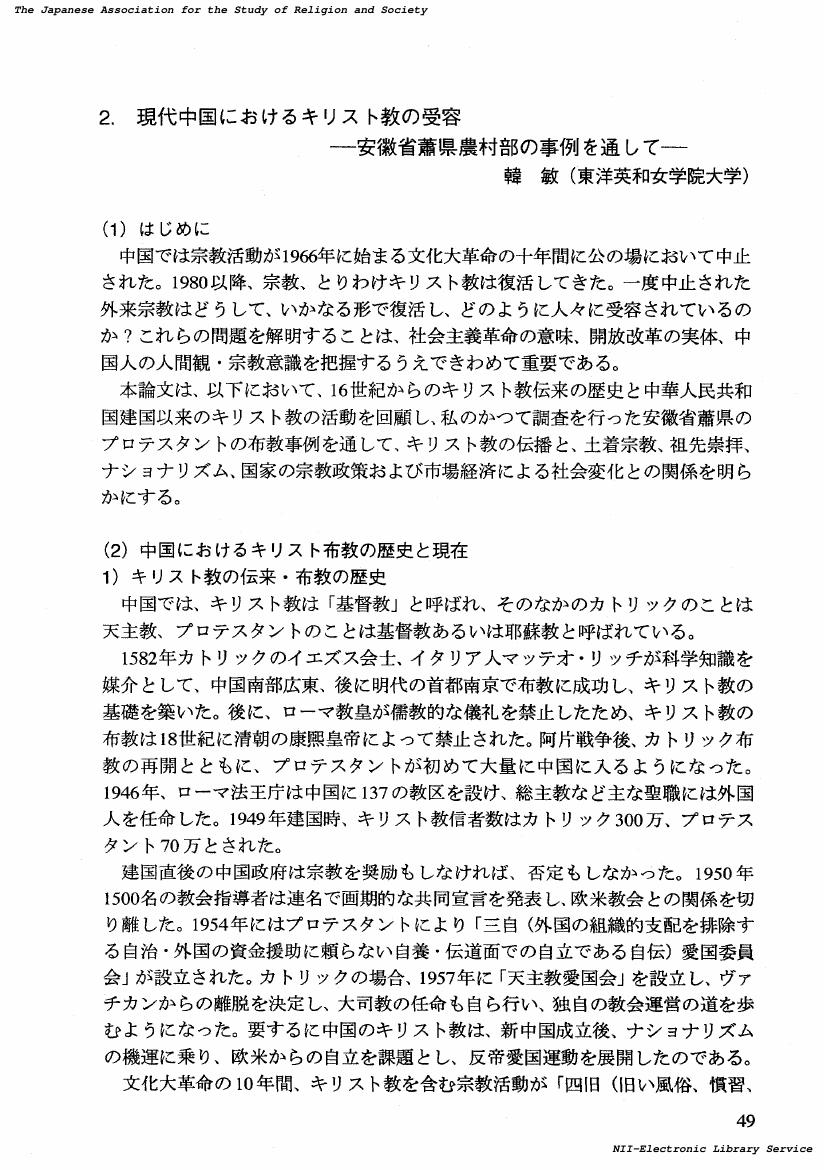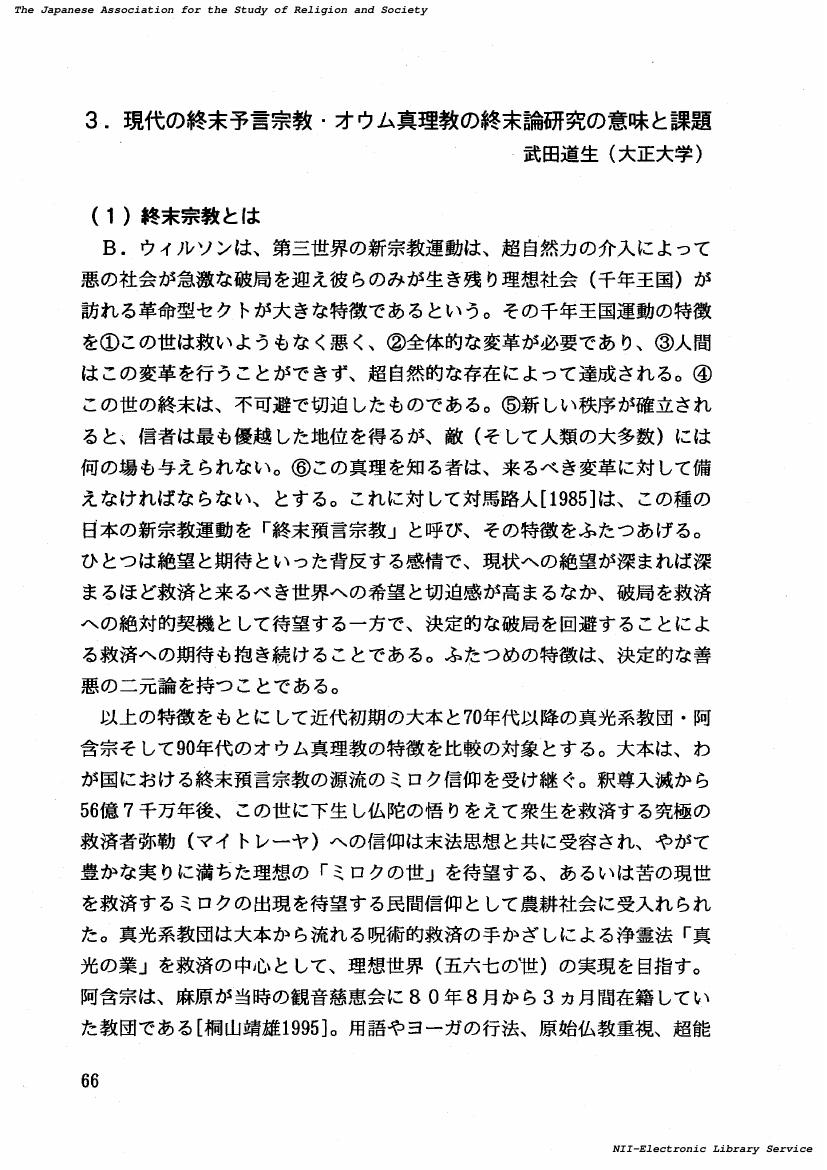- 著者
- 藤原 潤子
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.45-68, 2008
本稿は、現代ロシアにおける宗教的求道の特徴について、歴史観との関係から論じるものである。ソ連崩壊後のロシアにおいて、ナショナリズムはしばしば正教ナショナリズムの形を取って現れる。しかしロシア正教会は実は一枚岩ではない。歴史的状況との関連の中で、教団類型論におけるチャーチ的な教会(モスクワ総主教を長とする)の他に、旧教、カタコンベなどと呼ばれるセクトが現れたからである。本稿では、求道の過程で幾度も所属教会を変えていった正教徒夫妻のライフヒストリーを事例として取り上げ、その求道がまさに「真のロシア史」への探求だったことを示す。彼らにとって何が「真の歴史」かという問題は、どこに「真の聖性」があるのかという問題と切り離せない。新たな宗派との出会いを通じてロシア史をめぐる問題の新たな局面が開ける度に、彼らは自らが正しいと信じる「歴史」を選択していったのである。
- 著者
- 星野 智子
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.Suppl, pp.83-89, 1998-03-01 (Released:2017-07-18)
3 0 0 0 OA 近現代ベトナムにおける宗教と社会活動―新宗教カオダイ教の事例から―
- 著者
- 北澤 直宏
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.47-61, 2017-06-03 (Released:2019-05-31)
- 参考文献数
- 23
本稿は、ベトナムの新宗教カオダイ教による社会活動を半世紀にわたり分析することで、教団が維持・拡大してきた要因を明らかにするものである。1920年代、フランス植民地下のベトナム南部で誕生したカオダイ教は、設立直後から善行を重視し、組織的な社会活動を展開してきた。しかし、教団発行の活動報告書を基に1940年代以降の活動内容及び費用の変遷を追っていくと、国家制度や社会の変化に伴い教団の社会活動が拡大してきた点は事実とは言え、実際に多くの資金・労力が投じられてきたのは、教団内の福利厚生の充実や関連施設の整備であった点が判明する。その理由として、①不安定な時期に教団存続を図る上では、富と力の誇示が不可欠であった点、②明確な布教手段を持たない教団が新たな人員を獲得するためには、政府をはじめとする教団内外に自らの権威を示す必要があった点を挙げることができる。
3 0 0 0 OA (書評へのリプライ)塚田穂高著『宗教と政治の転轍点―保守合同と政教一致の宗教社会学―』
- 著者
- 塚田 穂高
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.92-93, 2016-06-11 (Released:2018-07-20)
- 参考文献数
- 3
3 0 0 0 OA 宗教/ジェンダー・イデオロギーによる「家族」の構築 : 統一教会女性信者を事例に
- 著者
- 櫻井 義秀
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.43-65, 2003-06-14
本稿では、統一教会信者の入信・教化過程をジェンダー論の視点から考察する。ジェンダー秩序の形成が女性信者の宗教実践、教団戦略とどのように関連しているのかを明らかにすることで、従来「マインド・コントロール」として告発されている心理的・社会的影響力行使の中身と意味が明らかになるのではないかと考えている。以下の知見を得た。未婚・既婚を問わず、女性信者の入信・教化の過程において、統一教会は自己啓発・運勢鑑定の装いの下に、統一教会独特の家族観を問題解決の方法として提示する。信者はこのようなイデオロギーを宗教実践において内面化し、最終的な救済財である祝福を目指す。信者が活動に熱心になればなるほど、現実の家族と教団が提示する「真の家庭」という理想の家族像に乖離、葛藤が生じる。教団はその克服を信者に促し、信者はそこに信仰の意義を見いだした。なお、本稿では世界基督教統一神霊協会の略称「統一教会」を用いる。
- 著者
- 中田 考
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.220-228, 2007-06-09
- 著者
- 真鍋 祐子
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.46-67, 1996
<p>1970年11月13日、ソウルにある零細裁縫工場の労働者であった全泰壹は、勤労基準法の遵守を叫ぶ示威の最中、抗議のための焼身自殺を遂げた。体制をはじめとする他者たちに向けて演じられた彼の死は、60年代以降の飛躍的な経済成長め裏側で生存権を剥奪された民衆が、初めて歴史の主体として登場した事件と評される。伝統的な儒教の孝倫理に背く自殺という手段が敢行されたにもかかわらず、むしろ「冤魂」をめぐる両義性のゆえに、彼は韓国の民衆運動において尊崇されるべき殉教者のモデル、すなわち「烈士」に祀られた。本稿はその神話化過程を分析する試みであり、趙英来著『全泰壹評伝』(1983年)を資料とする。著者の析出した全泰壹闘争の在り方からは自己スティグマ化による価値逆転の過程が見出され、また生と死に関する記述から「民族民主主義」のための供犠としての意味づけが示唆された。ゆえに、それは80年代へ通ずる殉教者神話となりえたのだろう。</p>
- 著者
- 樫村 愛子
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.122-129, 2000-06-17
2 0 0 0 OA 地方寺院の僧侶による葬儀実践の模索―法話に注目して―
- 著者
- 磯部 美紀
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.49-63, 2021-06-05 (Released:2023-06-24)
- 参考文献数
- 36
近年の日本においては、宗教家を介在させない葬儀が一つの葬儀形態として受容されている。また、「故人らしさ」を反映させた個性的な葬儀を望む人々もいる。今や、葬儀に僧侶が関与することは自明ではなくなりつつある。本稿では、このような葬儀を取り巻く状況の変化を受けて、僧侶が自らの役割をどのような点に見出し、いかに葬儀実践を模索しているのかを、新潟県で行われた仏式葬儀を事例に論じる。特に、法話(僧侶によって行われる説法)に注目する。法話の内容を分析すると、故人の生き様を反映させた個別化された要素と、仏教儀礼として定型化された要素が確認できる。この事例研究を通して、両要素は相反するものではなく、相互補完的な関係にあることが示された。法話実践の分析により、僧侶が個性的な葬儀を称賛する現代的ニーズに対応しつつ、同時に死別に際して必要とされる仏法に基づく物語を人々に提供する具体的様相が明らかになった。
2 0 0 0 OA ニクラス・ルーマンの「世俗化」論―近代社会における宗教の存立問題―
- 著者
- 畠中 茉莉子
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.33-47, 2021-06-05 (Released:2023-06-24)
- 参考文献数
- 23
ルーマンは宗教を社会の一つの機能システムとして描きつつも、その存立を自明視はせず、近代社会における宗教の存立の可否を問い続けた。彼の世俗化論はこの問いを中心的な主題としたものである。彼の世俗化論には1977年版、2000年版という複数のテキストがあり、前者から後者へと至る間に宗教に対する彼の見方は変化した。この変容の詳細はまだ解明されていない。その解明が本稿の主眼である。当初、彼は宗教としてキリスト教の教会組織を念頭に置いていた。その後彼は同時代の神学者と宗教社会学者の問題提起を通じて、現代の拡散した宗教的現象において示されている宗教性とは何かという問いに出会う。この問いに向き合う中で彼の宗教をめぐる視点は拡大した。彼は現代の様々な宗教的現象への関心を示す。それらは伝統的な組織の内には収まらない。そのためルーマンは、現代の宗教性を一つの自立した宗教システムとして描くための理論的概念を模索したのである。
- 著者
- 村上 興匡
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.116-123, 2002-06-29 (Released:2017-07-18)
- 著者
- 韓 敏
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.Suppl, pp.49-55, 1999-03-01 (Released:2017-07-18)
2 0 0 0 OA 純心女子学園をめぐる原爆の語り : 永井隆からローマ教皇へ
- 著者
- 四條 知恵
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.19-33, 2012-06-16 (Released:2017-07-18)
キリスト教の信仰に影響された特徴的な語りが長崎で生まれた。この背景には、永井隆という人物の影響があるとされる。カトリック教徒であった医学博士永井隆は1951年に病没するまでの間に旺盛な執筆活動を行い、現在も長崎の原爆の象徴として一般に語られる人物であるが、『長崎の鐘』[1949]に代表される彼の著作に見られる原爆に対する独特な思想〔燔祭説:原爆死を神への犠牲(燔祭)と捉える考え方〕は、占領軍への親和性や原爆投下責任の隠蔽、さらには長崎における原爆の記憶を発信する上での消極性につながるなどとして批判を受けてきた。しかしながら、そこでは永井の思想が与えた影響力は常に前提とされ、実際の受容状況が測られることはなかったといえる。本稿では、純心女子学園を対象に、原子爆弾による甚大な被害がどのよう語られてきたのかを考察することで、燔祭説の受容と戦後65年間にもたらされた変化を提示する。
- 著者
- 武田 道生
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.Suppl, pp.66-72, 1997-03-01 (Released:2017-07-18)
2 0 0 0 OA 現代日本における葬送と自然―「自然に還る」というイメージをめぐって―
- 著者
- 内田 安紀
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.15-29, 2017-06-03 (Released:2019-05-31)
- 参考文献数
- 29
本稿は、1990年代以降に顕著な現象として見られる葬送と自然の接近について、その背景と意味を考察するものである。1991年の「自然葬」の登場、そして1999年の樹木葬の登場と普及から推測できるように、現代の日本社会では葬送の領域において自然的要素が求められるようになっている。本稿ではなぜ現代社会において葬送と自然が接近しているのか、またそのような文脈における「自然」は新しい葬送の受容者にとってどのような意味を持つのかを問う。前者に関して言えるのは、現代社会においては葬送の領域に「個人化」現象が見られ、そこでは共有されうる死生観や価値観が失われており、その空白地帯に「自然」の要素がはまり込んだということである。後者に関して実際の樹木葬墓地での調査結果から見えてくるのは、そのような「自然」は受容者にとっては表層的なものであり、彼らの個人性と他者との共同性を媒介する一つの資源となっていたということである。
- 著者
- 小田 亮
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- no.11, 2005-06-11
2 0 0 0 OA マレーシアにおける徳教の教団的展開
- 著者
- 黄 蘊
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.75-103, 2007-06-09 (Released:2017-07-18)
- 被引用文献数
- 1
本稿は、マレーシアの華人教団徳教の展開過程に注目し、徳教の教団的拡大とその存在の様相について考察しようとするものである。徳教は、20世紀前半中国の潮州地方に誕生した扶鸞結社であり、戦後潮州系商人によって、マレーシアなど東南アジアの華人社会に伝播され、以来教団的展開を続けてきた。今日、徳教は大きな組織力を発展させ、マレーシアにおいて最も知られる華人新興宗教の一つに数えられている。一方、その教団活動は、扶鸞や世俗的サービスの提供を中心にしており、完全なる宗教制度が確立されていない。そのため、徳教団体は、厳格な意味でいう宗教教団と一般の華人アソシエーションの中間に位置するようなものと位置付けられる。徳教のこうした展開は、その主な担い手となる商人階層の性格や移民社会の社会状況と大きく係わっている。本稿は、徳教展開の社会的文脈とその担い手たちの思考、行動に注目し、徳教の教団的展開の様相を明らかにすることを試みる。
2 0 0 0 OA 地球とのつながりを強固にする―日本におけるラスタファーライの受容について―
- 著者
- 神本 秀爾
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.33-47, 2015-06-13 (Released:2018-05-31)
- 参考文献数
- 20
本研究の目的は、文化人類学的見地から、日本人ラスタのラスタファーライへの参入経緯と、彼らの解釈および実践の傾向を明らかにし、日本におけるラスタファーライの受容のされ方について考察することである。第2節では、日本におけるラスタファーライの概略を記述する。第3節では、日本におけるラスタファーライの展開を3期に分け、それぞれの時期における日本人ラスタたちの参入と探求の過程を論じる。第4節では、日本における解釈の特徴を、「『自然』の重視」「セラシエ崇敬の弱さ」「外見の重視」の3つの視点から分析する。以上を通じて、本稿では、日本人ラスタの多くは、それぞれの時代に流行しているレゲエを介してジャマイカのラスタファーライに接近しながらも、その受容に際しては、ラスタファーライそのものや、ラスタファーライの拠って立つ、聖書に根ざした救済観を相対化し、地球への愛着とも呼ぶべき思想につくりかえていると結論づけた。
- 著者
- 松本 久史
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.200-201, 2006-06-03 (Released:2017-07-18)
2 0 0 0 OA 3.夫婦別性導入をめぐる議論 : 家族と伝統を問う視座(グローバル化とアイデンティティ,テーマセッション3,「宗教と社会」学会・創立20周年記念企画,2012年度学術大会・テーマセッション記録)
- 著者
- 薄井 篤子
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.205-207, 2013-06-15 (Released:2017-07-18)