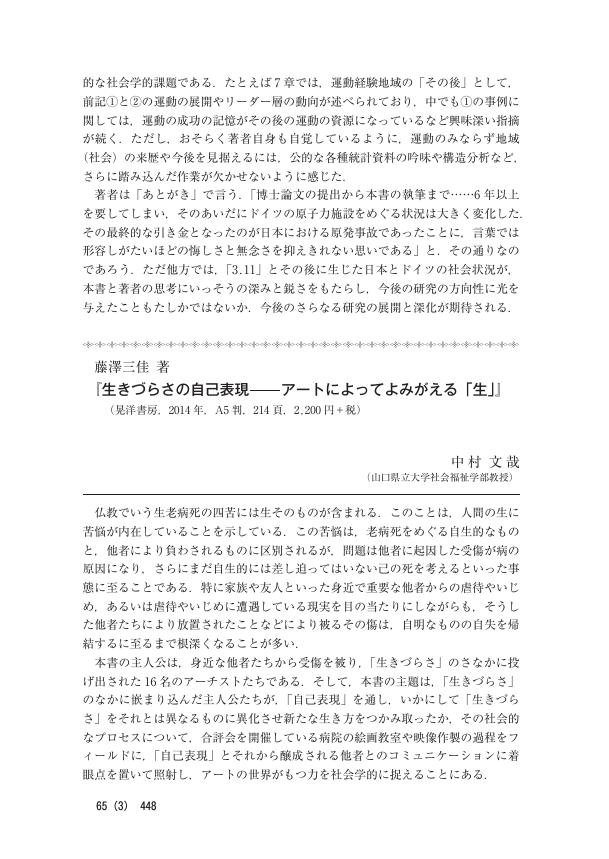- 著者
- 中村 英代
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.498-515, 2015
<p>本稿の目的は, 薬物依存からの回復支援施設であるダルク (Drug Addict Rehabilitation Center : DARC) では, 何が目指され, 何が行われているのかを考察することにある.</p><p>薬物問題の歴史は古く, 国内外で社会問題として存在し続けている. 薬物依存に対する介入/支援の代表的なものには, 専門家主導による司法モデルと医学モデルとがあるが, そのどちらのアプローチでもなく, 薬物依存症者自身が主導している介入/支援がある. それが本稿で考察するダルクだ. ダルクは, 薬物依存の当事者が1985年に創立して以来, 薬物依存者同士の共同生活を通して薬物依存者たちの回復を支援してきた. 薬物依存の当事者が運営している点, 12ステップ・プログラムを中心に据えている点, 日本独自に展開した施設である点にダルクの特徴がある.</p><p>本稿では, 2011年4月以降, 首都圏に立地する2つのダルクを中心にフィールドワークとインタビュー (31名) を行ってきた. 調査の結果, ダルクとは, 我々が暮らす現代社会の原理とは異なる原理に基づいて営まれている共同体であることが明らかになった. 具体的には, 人類学者のG.ベイトソンの議論を補助線として, ダルクとは「ひとつの変数 (金, 人望, 権力など) の最大化」を抑制する共同体であることを, 結論として提示する.</p>
- 著者
- 水津 嘉克 佐藤 恵
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.534-551, 2015
<p>「犯罪被害者遺族」「自死遺族」が現代の社会において直面せざるをえない困難性について, 論じることが本稿の課題である. 一見まったく異なった存在であると認識されている両者が直面せざるをえない, しかし他の遺族とは異なる「生きづらさ」とはどのようなものなのか. まずは素朴に彼らがどのような存在なのかを数的データで確認する. 数値が示す内容とは裏腹に, そうした犯罪や自死によって生み出される「犯罪被害者遺族」「自死遺族」の存在についてわれわれはあまりに知らない. このように「犯罪被害者遺族」「自死遺族」が毎年一定数確実に生じているにもかかわらず, その存在が顕在化することのない社会を本稿では「生きづらさを生き埋めにする社会」とする. そうした社会は彼らを「曖昧な包摂」のもとに置く社会である. そこでの当事者にとっての「現実」とは, 「自責の念」「親密な人びととの問題」「死別を受け入れることの困難性」としてとらえられるだろう. そしてこれらの「現実」は, 社会 (世間) にとっての「現実」とのあいだに大きな乖離を生ぜしめることになるのである. このようなリアリティの乖離は, 相互作用場面において彼らをダブルバインド的状況に追いやることになり, その結果, 彼らは「沈黙」を選択せざるをえないという「生きづらさ」を抱えることになる. 彼らが他の遺族とは異なるかたちで直面せざるをえない困難性がここに日々再生産される結果となる.</p>
1 0 0 0 理論とその外部 : 初期アルチュセールの理論的位相とその転回
- 著者
- 今野 晃
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.207-223, 2011-09-30
1965年の『マルクスのために』『資本論を読む』の出版により, アルチュセールは構造主義の代表として脚光を浴びる. こうした情況の中, アルチュセールは「重層的決定」概念を提起した. この概念は, 一般に「社会は政治, イデオロギーや経済等の諸要素が絡み合って現象する」ことを意味する概念として受容された. しかし, 彼がこの概念で提起した問題は, 通俗的見解に納まらない. 本稿においては, まず彼がこの概念を提起したコンテクストを綿密に追い, その意義を明確にする. ここで重要なのは, この「重層的決定」が社会的現実の多様性をいかにして捉えようとしたかである. この考察によって彼の理論が相矛盾する解釈, 熱烈な評価と同時に激しい批判を引き起こしたか明確にできる. 次に, この重層的決定との関連において, 彼がその後提起した「徴候的読解」を考察する. しかし, この2つの概念にはあるズレがあった. このズレは, その後のアルチュセールの「理論的転回」の本質を明確にするであろう. ただし, ここで明確になるズレは, 彼の理論に固有なものというよりも, すべての社会学的な認識や理論が必然的に直面しなければならないアポリアでもある. アルチュセールの理論的転回を見ることで, 我々はこのアポリアを明確にすることができるだろう.
1 0 0 0 法的論理の自律性と二重性 : 不法行為責任の意味をめぐる争い
- 著者
- 常松 淳
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.152-169, 2007-09-30
日本の法の世界では,「要件=効果」モデルを核心とする「法的思考」に収まる形で"ナマの"紛争を再構成することが自らの活動を法的なものにすると考えられている.民事訴訟において裁判官は,この枠組みに即して権利(不法行為責任の場合なら損害賠償請求権)の有無を判断することになるわけである.このような法的枠組みと,紛争当事者からの非‐法的な期待や意味付けとが齟齬を来すとき,社会からの自律を標榜する法は一体いかなる仕方でこれに対処しているのか? 本論文は,不法行為責任をめぐる近年の特徴的な事例――制裁的な慰謝料・懲罰的損害賠償を求めた裁判や,死亡した被害者の命日払いでの定期金(分割払い)方式による賠償請求――の分析を通じて,この問いに答えようとするものである.これらのケースは,法専門家によって広く共有された諸前提――不法行為制度が果たすべき目的に関する設定や,定期金方式を認めることの意義など――と相容れない要素を含んだ請求がなされた点で共通するが,前者は全面的に退けられ後者は(一部の訴訟に限っては)認められた.法の条件プログラム化がもたらす「(裁判官の)決定の結果に対する注意と責任からの解放」(N. Luhmann)という規範的想定と,法専門家に共有された制度目的論が,諸判決で示された法的判断の背後において特徴的な仕方で利用されている.
1 0 0 0 近隣交際ネットワークと運動参加
- 著者
- 大畑 裕嗣
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.4, pp.406-419,495-494, 1985-03-31
- 被引用文献数
- 2 1
本稿の課題は、大都市近郊のニュータウンにおいて生起した住民運動への賃貸集合住宅居住者の参加メカニズムを、近隣交際ネットワークへの統合を参加への肯定的要因として位置づけつつ、解明することにある。「統合仮説」「紐帯数仮説」「中心性仮説」「政治的企業家仮説」と、参加径路についての二つの仮説が提示される。中層住宅においては、「統合」「紐帯数」「中心性」の各仮説は概して検証された。高層住宅においては「紐帯数」「中心性」の各仮説は棄却されたが、この結果の食い違いは「政治的企業家仮説」を補完的に導入することにより解釈が可能なものだった。参加径路については、多様な径路を想定した「複線仮説」が支持された。
1 0 0 0 宗教市場理論の射程 : 世俗化論争の新たな一局面
- 著者
- 沼尻 正之
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.230-246, 2002-09-30
本稿は, 近年ロドニー・スタークらアメリカの宗教社会学者たちにより提唱されている, 従来の世俗化論争の枠組を越えた, 新たな宗教社会学理論, およびその理論的基礎に基づいて展開されている宗教市場理論について検証することを目的としている.以下ではまずはじめに, 彼らが反世俗化論を唱える際の理論的根拠に関して, 宗教の定義の問題, 剥奪理論との関係についての議論を取り上げて論じる.次に, 彼らによる宗教変動の理論を, 宗教集団の類型論 (チャーチ・セクト・カルト), 宗教・呪術・科学の三者の関係についての議論, 宗教変動の三要素 (世俗化・リバイバル・宗教的刷新) を取り上げて説明する.その上で更に, 彼らの宗教市場理論について検討する.合理的選択理論などを基礎とする, この宗教市場モデルは, 一般の市場の場合と同様に宗教も, 多元主義的状況でその活発さを増すという考え方に基づくものであるが, この視点をとることで, 現代社会における伝統宗教の盛衰や, カルト的新宗教の台頭状況などが, どのように整合的に説明できるかを示す.最後に, こうした理論の持ついくつかの問題点を挙げ, それらを克服するために今後どのような課題があるのかを考察することで, 彼らの理論の持つ射程を明らかにしたい.
- 著者
- 阿藤 誠
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.91-97, 1981-03-31
In the recent issue of this Journal, Mr.Yoshiki Kikuchi wrote about the rapid fertility decline since 1973 in Japan. He implied in it that the recent low fertility in Japan, measured by total fertility rates, reflected the decrease in birth intention of the average married couple toward less than two children. Based on the assumption that fertility behavior of Japanese women changed fundamentally in 1970's, he attempted population projections in which he assumed women would have only 1. 5 children on average in the future Japan.<BR>In my judgement, such argument is totally unwarranted. There has been no significant change in the legal status and the extent of actual prevalence of birth control measures in around early 1970's. In this respect Japanese situation is completely different from the Western countries where the diffusion of modern contraceptive methods and the liberalization of induced abortion presumably contributed to the recent fertility decline there.<BR>No evidence has shown that Japanese married couples have changed their fertility dramatically toward less than two children. Mean number of children ever born for 1955-1965 marriage cohorts were almost invariably about 2.2 and the total intended number of children was also 2.2 on average for more recent marriage cohorts.<BR>Although such social and economic changes as industrialization, urbanization, the rising aspirations for living, and the rise of educational level, may have been conducive to the long-run low fertility in Japan, they cannot explain the recent abrupt decline in period fertility rates. Also, there has been no significant change in married women's status either within or out of home.<BR>The major reason for the recent decline in period fertility rates is the simultaneous rise in the mean age at marriage for both sexes since 1973, which is, in turn, not only due to the abrupt shrinkage of the size of younger age cohorts in the marriage market after the "baby boom" cohort, but also due to the recent rise in the proportion of women entering colleges. Fragmentary data seem to indicate that marital fertility itself has declined recently, but this should be interpreted not as the decline in completed fertility but as the temporal decline due to the spacing of childbearing.
1 0 0 0 OA 園井ゆり著『里親制度の家族社会学――養育家族の可能性』
- 著者
- 和泉 広恵
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.616-618, 2015 (Released:2016-03-31)
1 0 0 0 OA 映像の共有と諸権利
- 著者
- 内田 順子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.504-520, 2015 (Released:2016-03-31)
- 参考文献数
- 23
本稿は, 国立歴史民俗博物館が実施している民俗研究のための映像制作を事例として, 「映像を保存・活用する」際の諸課題について考察するものである. 長期的な展望をもって映像を制作し, 保存し, 活用するには, メディア変換などの技術的な問題, 著作権・肖像権などの法的問題, アーカイブの構築などの映像を共有するしくみに関する問題などを解決していく必要がある. 民俗研究を目的として制作された映像は, 研究者と, 研究対象となる地域の人びととの協働によってつくられるものであるため, その協働の関係性は, 映像そのものに色濃く反映される. そのような映像を保存・活用する際には, 著作権・肖像権に関する一般的な検討とは別に, 倫理的な問題として検討しなければならない事柄がある. その点が, 一般的な映像の保存・活用と異なるところである.
- 著者
- 北島 義和
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.395-411, 2015
1 0 0 0 君主のスペクタクルの知覚様式 : 20世紀初期の日本の事例から
- 著者
- 右田 裕規
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.379-394, 2015
- 著者
- 安達 智史
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.346-363, 2015
- 著者
- 三原 武司
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.364-378, 2015
1 0 0 0 OA 国家のリスケーリングと都市のガバナンス
- 著者
- 丸山 真央
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.476-488, 2012-03-31 (Released:2013-11-22)
- 参考文献数
- 47
2000年代以降, 都市研究で「国家のリスケーリング」論が影響力をもつようになっている. これは, グローバルやリージョナルな経済・政治統合が進むなかで国家諸機構の機能や影響力がその地理的スケール上の編成を変化させることに注目し, 都市やそのガバナンスの変化との関連を明らかにするものである. 「都市」は, 従来の都市研究でしばしば所与の空間的単位とみなされてきたが, 「地理的スケール上の編成の変化 (リスケーリング)」という発想を採り入れることで, それが資本や国家のスケール的編成と相互規定的に生産される地理的スケールのひとつであり, それゆえ今日, 「都市」というスケールをどう定義するかということそれ自体が「スケールの政治」の争点になっていることが明らかになる. 本稿では, この視角による都市研究の基本的な問題構制と成果を整理し, グローバル化とネオリベラリズムのもとでの都市ガバナンスの変化を捉えるのに有益であることを示す. そのうえで「平成の大合併」をめぐる地方都市の事例の簡単な分析を行う. 基礎自治体の合併は, 既存の「地域/都市」スケールのガバナンスを担う政治行政機構を再編して, 新たな「地域/都市」スケールでガバナンスを組織しなおす「国家のリスケーリング」のひとつだが, 事例分析から, 日本でこれがどのような政治経済的な力学で進められたのかを明らかにする. あわせてこの視角による都市研究の課題を引き出し整理する.
1 0 0 0 OA 早瀬利雄・馬場明男編 現代アメリカ社会学
- 著者
- 阿閉 吉男
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.109-111, 1954-10-20 (Released:2009-11-11)
- 著者
- 上藤 文湖
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.369-384, 2006-09-30
ドイツでは移民法成立に向け, 数年にわたり外国人の社会への統合が論じられるなか, たびたび〈多文化社会〉が論争となってきた.多文化社会を現実として肯定し外国人の統合を推進するのか, これを幻想として否定するのか.論争はこうした二重性をもっている.1980年以降ベルリンでは, 国家レベルに先行して文化的多様化が進行し, 外国人の包摂への取り組みとドイツ社会の変革を志向する政策が進んでいった.そして1989年以前には, 〈多文化社会〉はその現実が争われ, 東西ドイツの分断という政治的状況が, 現実としての〈多文化社会〉に対する肯定と否定双方を生んでいった.しかし東西ドイツが統合し大量の難民を受け入れた1990年以降, 現実として多文化が受容されはじめる.そして1998年の〈多文化社会〉論争では, 〈指導文化〉とされるドイツ文化と多文化の関係が論じられたが, 文化的多様性に対する一定の承認のもと, 文化的多様性の認知としての〈多文化社会〉から, どのような成員がどのような共通の基盤のもとで社会を形成するのかを問う〈多文化社会〉へと, その議論が変化したのである.ベルリンにおける〈多文化社会〉をめぐる議論は, 外国人によって社会が問われ変化していくことを示している.都市における〈多文化社会〉をめぐる葛藤は, 都市という空間の中で外国人と社会との関係が構築されていくプロセスの中に位置づけられる.
- 著者
- 佐藤 成基
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.348-363, 2009-12-31
- 被引用文献数
- 1
1990年代以後,欧米先進諸国の移民統合政策が変化してきている.それまでの「デニズンシップ」や「多文化主義」に傾斜した政策が後退し,「統合」という概念により重点が置かれるようになっている.それは一見,「グローバル化」時代のトレンドと矛盾するように見える.本稿は,このような最近の変化を,19世紀以来の国民国家形成とグローバルな移民の拡大との歴史的な連関関係のなかで考察してみる.国民国家は,19世紀以来200年間のグローバルな変容のなかで形成/再形成され,またグローバルに波及してきた.そのようななかで国民国家は,移民を包摂・排除しながらその制度とアイデンティティを構築してきた.本稿は,その歴史的過程を明らかにしたうえで,最近の欧米先進諸国の「市民的」な移民統合政策への変化が,「異質」なエスノ文化的背景をもった移民系住民を包摂するかたちで国民国家を再編成しようとする,新たな「ネーション・ビルディング」への模索であるということを主張する.最後に,こうした最近の欧米先進諸国における変化から日本の状況を簡単に検討する.
- 著者
- 山本 薫子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.450-451, 2014 (Released:2015-12-31)
1 0 0 0 OA 藤澤三佳著『生きづらさの自己表現――アートによってよみがえる「生」』
- 著者
- 中村 文哉
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.448-450, 2014 (Released:2015-12-31)
1 0 0 0 OA 連帯と承認をめぐる理念の生成と変容
- 著者
- 伊藤 美登里
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.409-425, 2014 (Released:2015-12-31)
- 参考文献数
- 26
U.ベックは, ローカル次元において連帯と承認を作り出す仕組みとして市民労働という政策理念を提案した. この理念が現実社会との関連でいかに変容したか, 他方で社会においてはいかなる変化がもたらされているか, これらを考察することが本稿の目的である.研究の結果次のようなことが判明した. 市民労働の政策理念は, 政策的実践に移される過程で, ある部分が市民参加に, 別の部分が市民労働という名のワークフェア政策としてのモデル事業に採用され, 分裂していった. 現在の市民労働と市民参加は, ベックの市民労働の構成要素をそれぞれ部分的に継承しつつ, 中間集団や福祉国家の機能を部分的に代替している. 政策的実践としての市民労働と市民参加の存在は, 「家事労働」「市民参加」「ケア活動」といった概念の境界を流動化したが, 「職業労働」概念の境界は相対的に強固なままである.ベックの市民労働には, 元来, 社会変革の意図が含まれていた. すなわち, この政策理念は, 職業労働と市民参加と家事労働やケア活動の境界を流動化し, それらの活動すべてを包括するような方向, すなわち労働概念の意味変容へ向かうことを意図して提案された試みであった. しかし, 現状においては, そもそもの批判対象であった職業労働の構造を強化する政策にこの市民労働の名称が使われている. 他方, 市民参加においては, 部分的にではあるが, 市民労働の政策理念が生かされ一定の成果をあげている.