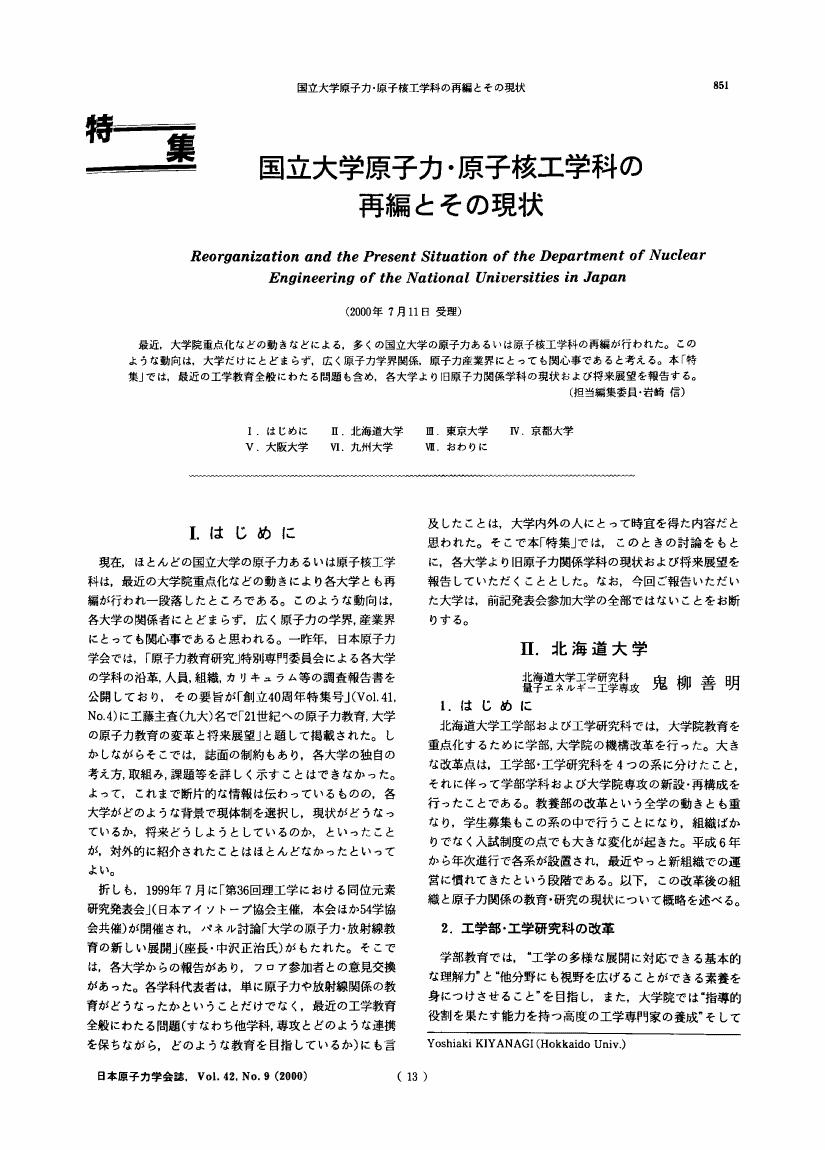- 著者
- 崎田 裕子
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.6, pp.388-391, 2014
<p> 事故後約3年が経過し,自然放射線より高い放射線と向きあって暮らす,という日本で初めての状況に福島の方々は直面しており,リスクコミュニケーションの重要性が高まっている。しかし,事故後の放射線量の違い,除染の進捗による低減状況の違いなども影響し,避難継続地域,帰還準備地域,日常生活を取り戻そうとする地域など,地域の状況は多様化し,リスクとの向き合い方は,一人ひとりがどう決断するかにかかっている。また,個人の決断は勿論ながら,地域性に応じた対応や,除染だけではなく復興やこれからの暮らしや地域づくりなど,地域社会の将来像とも密接につながってきている。</p><p> 科学的知見と社会的知見を総合化して地域による柔軟性を確保しながら,放射線を低減し 環境回復を実現しつつ放射線と暮らす方々を,社会がどう支えてゆくのか。住民自身の視点と,それを支える社会システムづくりの視点の両面から,今とこれからの福島を展望する。</p>
- 著者
- 山根 史博 大垣 英明 浅野 耕太
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会 年会・大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.30, 2009
原子力関連施設の建設は周辺地域に様々な経済的影響を及ぼす。本研究はそうした影響を定量的に評価し、地域にとっての施設建設の経済効率性を検証するものである。今回は、前回大会でのコメントを基に、むつ小川原地域を対象とした地価分析のリバイスを行った。また、分析が間に合えば、家賃の分析結果についても報告する予定である。
1 0 0 0 グレタ・トゥーンベリさんの国連スピーチに対する各国の医学生の反応
- 著者
- 妹尾 優希
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.29_2, 2020
- 著者
- Dunzik-Gougar Mary Lou
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.8, pp.561-562, 2021
1 0 0 0 今後の研究開発に関する視点
- 著者
- 藤田 玲子
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.7, pp.509-510, 2021 (Released:2021-07-10)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 JETにおけるDT実験
- 著者
- 伊藤 早苗 伊藤 公孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.6, pp.500-505, 1992
1 0 0 0 OA 電力系統の安定運用のために 再生可能エネルギー大量導入時の基幹系統への影響
- 著者
- 北内 義弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.7, pp.535-539, 2019 (Released:2020-04-02)
- 参考文献数
- 2
電力系統の安定運用のためには,系統セキュリティの維持が重要である。本稿では,まず交流送電と発電機および系統セキュリティを維持するために必要な三つの要素(周波数,電圧,系統安定度)について概説し,大容量発電機の系統セキュリティへの貢献について述べる。さらに大容量電源脱落時の周波数低下および再生可能エネルギー発電大量導入時の電力系統の系統安定度に与える影響について,電力系統シミュレータを用いた試験結果について紹介する。
1 0 0 0 最新核データを用いた反射体効果に関する高速炉ベンチマーク計算
- 著者
- 福島 昌宏 石川 眞 沼田 一幸 神 智之
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会 年会・大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, 2012
最新核データを用いて、ステンレス反射体付き炉心及び天然ウランブランケット付き炉心に対する高速炉ベンチマーク計算を実施し、反射体効果に関する分析を実施した。
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.217, 2012
- 著者
- 山路 昭雄 沼田 茂生 斉藤 鉄夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.6, pp.555-563, 1987
A design method is described for the Fe compensational shield which is located around a straight duct in concrete shield wall against γ radiation to compensate the lowering of shielding efficiency caused by the duct. The method has been applied to the configuration, where the source area is not viewed through the duct from the detector point at the duct exit. The form of the compensational shield was determined depending on the wall thickness, the duct diameter, the incident angle of γ-ray beam to the wall, and the densities of the concrete and Fe. An experiment for the compensational shield was performed in the Dry Shielding Facility at JRR-4. The measured dose rates behind the wall were reduced effectively by the compensational shield, so that the maximum dose rates became only slightly higher than that of the bulk shield wall and the dose rates higher than the maximum dose rate for bulk shield wall were restricted only in the area near the duct exit. The experimental results have been analyzed using a multigroup γ-ray single scattering code G33YSN.
1 0 0 0 粒子型燃料を用いたガス冷却加速器駆動核変換システムの検討
- 著者
- 篠原 正憲 佐々 敏信 滝塚 貴和 金子 義彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会 年会・大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, pp.186, 2005
Heガス冷却加速器駆動核変換システムの核特性解析を基に、除熱特性解析を実施し、最適炉心を決定した。その結果、燃料最高温度は燃料及び構造材の許容温度制限を達成でき、その炉心は半径115cmとすることで初期実効増倍率0.95、初装荷燃料4000kgとなり、年間で1GWeの軽水炉12基分(290kg)のMAを核変換できることが分かった。
1 0 0 0 OA 国立大学原子力・原子核工学科の再編とその現状
- 著者
- 鬼柳 善明 田中 知 今西 信嗣 竹田 敏一 工藤 和彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.9, pp.851-867, 2000-09-30 (Released:2009-04-21)
- 著者
- 澤田 哲生
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.1-2, 2021 (Released:2021-02-10)
- 著者
- 佐藤 修彰 渋谷 昌孝 諸根 正年
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会 年会・大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.559, 2012
濃縮機器等からのウランのフッ化揮発除染における廃棄物安定化処理に関して、五フッ化ヨウ素とカルシウム化合物との反応を調べ、フッ素およびヨウ素の固定について検討した。
1 0 0 0 ストレス抱える原発周辺住民
- 著者
- 松村 健次
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 = Journal of the Atomic Energy Society of Japan (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.7, 2008-07-01
1 0 0 0 複数の分析者による不具合事象の原因分類結果のばらつき評価
- 著者
- 高川 健一 宮崎 孝正 五福 明夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会 年会・大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.372, 2008
原子炉施設情報公開ライブラリーに公開された情報を、原子力安全システム研究所が考案した原因分類により、複数の「一般大衆」と「専門家」の分析者による分類結果のばらつきを評価したところ、両者ともばらつきが見られたが、そのばらつきの傾向に類似性の有るものと無いものに区分できた。
1 0 0 0 福島第一原発事故後の原子力防災訓練における住民避難と参加
- 著者
- 川本 義海 川上 祥代 柏 貴子
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会 年会・大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, 2012
本稿は平成24年3月に敦賀市で実施された福井県原子力防災総合訓練を事例として、福島第一原発事故をふまえた最初の防災訓練の中でもとくに住民の避難と参加の状況に着目し、従前の訓練と今回の訓練の内容および意識の変化を整理・把握する。具体的には、敦賀原発から5キロ圏の全住民を対象とした避難訓練当日の避難対象地区およびオフサイトセンターなどの現場視察、訓練直後に県が参加者に対して実施したアンケートの結果概要、訓練前後の報道記事および訓練後約2ヶ月時の避難対象地区区長などへのアンケートをもとに、今回の訓練から得られた成果と課題を明らかにする。これらにより、今後国の正式な防災指針の見直しを受けて策定されることになる県の原子力防災計画策定の一助とすべき現状を共有化することを目的とする。
- 著者
- 竹田 周平 町田 秀夫 佐藤 親宏 西野 正一郎 宮田 浩一
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会 年会・大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.411, 2008
BWRクラス1配管を対象に,製造欠陥の疲労き裂進展による破損確率のみならず,SCCにより発生したき裂のSCCき裂進展による破損確率ならびに減肉による破損確率を評価した。
1 0 0 0 エネルギー政策における国民的議論とは何だったのか
- 著者
- 八木 絵香
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 = Journal of the Atomic Energy Society of Japan (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.29-34, 2013-01-01
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2
<p> エネルギー・環境戦略に関する「国民的議論」において,世界初の試みとなった政府主催の「討論型世論調査」。これらの結果に接した人々,特に筆者が出会う原子力分野の人々に少なくない感想は,「あれは『特殊な』人達の声で,サイレントマジョリティの考え方は違う」というものである。本当に討論型世論調査で示された国民の声は「特殊な」人々の声なのだろうか。その結果はどう読み解かれるべきだったのか。このような観点から,2012年夏のエネルギー・環境戦略に関する国民的議論を振り返り,今後のエネルギー政策の具現化に向けて,改めて原子力専門家が問われる役割について解説する。</p>
- 著者
- 田辺 文也
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会 年会・大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.348, 2008
JCO臨界事故は、臨界質量制限値を大幅に超える量の製品硝酸ウラニル溶液の均一化工程を実施するにあたって、形状制限によって臨界管理されている純硝酸ウラニル溶液貯塔に替えて形状制限されていない沈殿槽を使用したことにより発生したが、原因のひとつとして、この作業手順変更が職制上の上司である職場長の許可を求めることなく現場作業チームにより計画、実行されたことがあげられる。これは主に、JCOで長年に亘って実施された改善提案制度において、現場作業員に対して実施済改善提案の提出が原則である旨が徹底的に指導され、かつそれがより高い褒賞内容にも結びついていたこともあり、職制上の上司の許可なく手順を変更して作業を実行することが常態化し、改善提案制度衰退後もその風潮が維持されたところからきたものである。