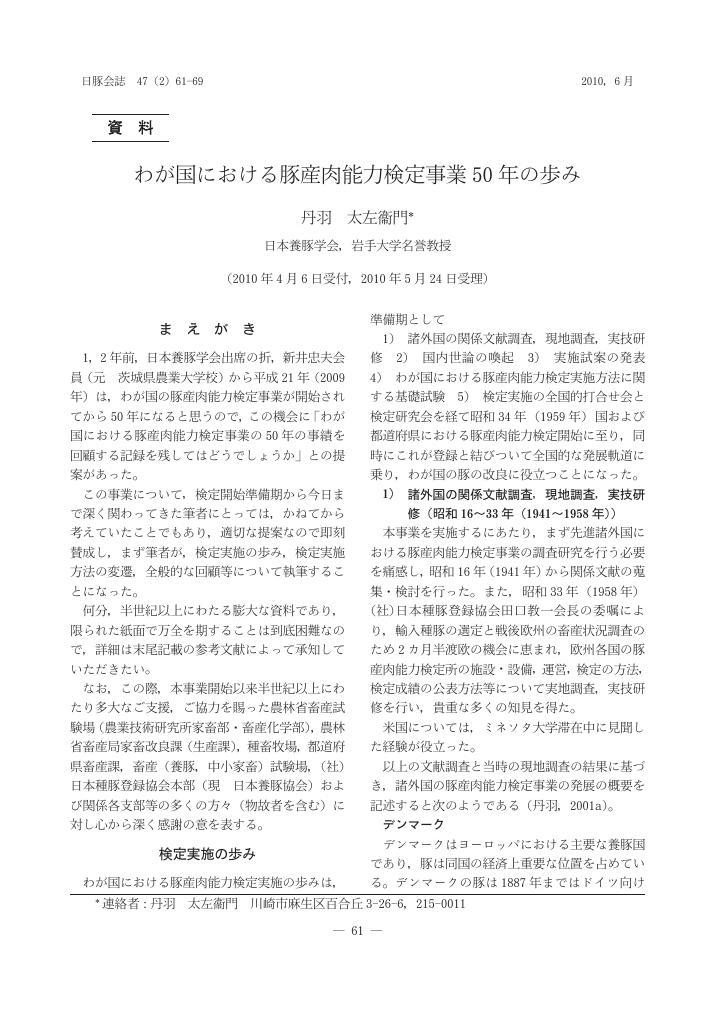1 0 0 0 OA 日本養豚研究会10年の歩み
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.89-94, 1974-09-30 (Released:2011-06-08)
1 0 0 0 茨城県の畜産事情
- 著者
- 海老原 五郎
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚学会誌 (ISSN:0913882X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.191-196, 1988
1 0 0 0 茨城県における系統豚の利用について
- 著者
- 新井 忠夫
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚学会誌 (ISSN:0913882X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.247-250, 1987
1 0 0 0 中国豚の優秀な品種特性とその世界の養豚業への貢献
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚学会誌 (ISSN:0913882X)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.1-10, 1993-03
- 著者
- 脇屋 裕一郎 大曲 秀明 立石 千恵 河原 弘文 宮崎 秀雄 永渕 成樹 井上 寛暁 松本 光史 山崎 信
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚学会誌 (ISSN:0913882X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.207-212, 2014
二酸化炭素等温室効果ガス濃度の上昇に起因して地球温暖化が進行しており,夏季における我が国の養豚は影響を受ける可能性が指摘されている(高田ら,2008)。それによると,2060年の夏季には北海道を除いたほとんどの地域で日増体量が低下し,特に関東以西では日増体量の15~30%の低下が予測されている。また,平成22年度の夏季は,我が国の多くの地点で平均気温が統計開始以来最も高い記録的猛暑となり,家畜の生産に影響が出たことは記憶に新しい(農林水産省,2012)。これらのことから,豚肉生産における暑熱対策技術の確立は全国的にも重要な課題と考えられる。暑熱環境下で飼養成績を改善する手段として,飼料中のエネルギー含量を調整する取組が行われており,COFFEYら(1982)やKATSUMATAら(1996)は,飼料に油脂を添加することで,暑熱環境下の肥育豚の飼養成績が改善されるとしている。しかし,KATSUMATAら(1996)は,油脂を配合することで背脂肪厚が増加することを報告しており,油脂添加と併せて背脂肪厚を抑制できる技術の確立を検討する必要がある。著者ら(脇屋ら,2009; 2010)は,佐賀県の特産農産物である茶の製茶工程で発生する加工残さの機能性に注目し,その給与試験を行っている。それによると,慣行飼料に対して重量比で肥育前期2%,肥育後期1%添加することで,抗酸化成分であるカテキン等による肥育豚の背脂肪厚低減効果を確認しており,油脂添加のような脂肪蓄積が促進される条件下でも背脂肪厚の抑制が期待できる。
1 0 0 0 発育,枝肉形質および肉質からみたアグーの品種特性について
<p>沖縄県の在来豚であるアグーは,西洋系品種の普及により一時期,絶滅の危機に瀕していたものの,肉質に優れていることが評価され,ブランド豚として注目を集めている。しかしながら,その肉質についての知見は少ない。そこで,本研究では,アグーの品種特性を明らかにするため,アグー16頭(雌6頭,去勢10頭)と国内で広く用いられている三元交雑種(LWD)(デュロック種雄×F1交雑種雌;ランドレース×大ヨークシャー)18頭(雌9頭,去勢9頭)を110 kgまで肥育し,発育,枝肉形質および肉質について調査を行った。発育と枝肉形質に関連する項目については,一日増体量,枝肉歩留りおよびロース面積は,アグーがLWDよりも有意に低かったのに対し,背脂肪厚はアグーが有意に厚かった。肉質に関連する項目については,加熱前の保水性は,アグーがLWDよりも有意に劣ったのに対し,加熱時の保水性を示す加熱損失率は,アグーが有意に優れていた。さらに,筋肉内脂肪含量と圧搾肉汁率もアグーがLWDよりも有意に高かった。背脂肪内層の脂肪酸組成において,アグーはLWDと比べて,一価不飽和脂肪酸含量が有意に高く,多価不飽和肪酸は有意に低かった。さらにアグーの脂肪融点は,LWDよりも有意に低かった。これらの結果から,アグーは国内で広く用いられているLWDと比べて発育や産肉量は劣るものの,特徴的な肉質を持つことが明らかとなった。</p>
1 0 0 0 OA 豚パルボウイルスの消毒効果
我々はこれまでに,飼料用玄米と規格外カンショを配合した飼料を肥育豚に給与することを想定して飼養試験をおこなってきた。その結果,玄米とカンショを肥育後期豚に併給するときの配合割合は,それぞれ50%程度と20∼25%程度がよいと結論づけている。また,茨城県内ではカンショ加工残さの飼料化がおこなわれている。そこで本実験では,実証試験として,茨城県内の養豚生産者の一般管理下において,飼料用玄米50%とカンショ加工残さ(試験1:干し芋残さ,試験2:芋ようかん残さ)22.5%を配合した飼料を肥育後期豚(体重65 kgから120 kg)へ給与し,飼養成績および肉質に及ぼす影響をトウモロコシ主体の市販飼料と比較して検討した。試験1では,日増体重が飼料用玄米とカンショ加工残さの併給により高くなったが(P<0.05),試験2では差が無かった。背脂肪内層の脂肪酸組成は,試験1および試験2で,飼料用玄米とカンショ加工残さの併給により一価不飽和脂肪酸割合が高くなり,多価不飽和脂肪酸割合は低くなった(P<0.05)。以上の結果より,飼料用米およびカンショ加工残さの併給は,実際の養豚生産者の飼養管理下において,トウモロコシ主体の市販飼料と遜色ない飼養成績を示し,脂肪酸組成に影響を及ぼすことが明らかになった。
1 0 0 0 OA 豚におけるストレス制御につといて
- 著者
- M. ROGIERS 北野 訓敏
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.83-95, 1973-08-31 (Released:2011-06-08)
- 参考文献数
- 12
以上要約しますと, 豚は離乳から肥育豚舎に行くまで度々移動させられたり, 精神的に障害をうけるので, 相当な精神的なストレスを受けるため, Selye によって報告されている“適応症候群”にまで進行することが考えられます。このため異化作用は促進して胃腸障害を引き起すことになると思われます。消化管に関連した数多くの臨床的障害は離乳後に典型的に発生するものであり, その障害は下痢症, 出血性腸炎, 成長の停止, 飼料効率の低下であります。消化管にみられる病理解剖学的病変は, 離乳後と同様に実験的ストレスを与えた場合にも観察されました。離乳後の損失を出来るだけ少なくする方法としては, 広範囲に適用される抗生物質の多量に入った所謂“ストレス飼料”を投与することが必要であります。また, アザペロンの様な精神安定剤は良好な治療効果を示すことが出来ます。アザペロンは豚の精神的平衡を維持し, 発生が予測される胃腸障害を予防するものであり, その原因的治療剤としてすぐれた薬剤であると考えられます。
1 0 0 0 OA 太湖豚の高子数の特性及びその生理機能について
1 0 0 0 OA 豚精液の低温保存に関する研究
- 著者
- 糟谷 泰 河部 和雄
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.22-26, 1976-05-31 (Released:2011-06-08)
- 参考文献数
- 18
豚精液の低温保存に適する保存液を調製するための基礎資料を得る目的で, 分離採取濃厚精液および保存液構成々分として一般的に用られている9物質の水溶液について, その浸透圧とpHを測定した。1. 分離採取濃厚精液の浸透圧は300~320mOsm/lで, 同一個体内においても採取毎にこの程度の変動があった。2. 保存液の至適浸透圧と考えられる300mOsm/lの浸透圧となる各水溶液の濃度はブドウ糖-5.4%, 脱脂粉乳-10.8%, トリス-3.6%, クエン酸-6%, Na2HPO4・12H2O-4.8%, KH2PO4-2.4%, 重炭酸%Na-1.4%, クエン酸Na-3.2%, グリシン-2.3%であった。3. 分離採取濃厚精液のpHは7.2~7.7と弱アルカリ性を示し, 同一個体内においても採取毎にこの程度の変動があった。4. 保存液構成々分の各水溶液のpHは, ブドウ糖, 脱脂粉乳, グリシン, クエン酸がそれぞれ5.8, 6.6, 6.1, 2<と酸性を示し, トリス, Na2HP4・12H2O, 重炭酸Na, クエン酸Naがそれぞれ10.8, 9.2, 8.6, 8.1とアルカリ性を示した。
1 0 0 0 OA わが国における豚産肉能力検定事業50年の歩み
- 著者
- 山本 朱美 高橋 栄二 古川 智子 伊藤 稔 石川 雄治 山内 克彦 山田 未知 古谷 修
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚学会誌 = The Japanese journal of swine science (ISSN:0913882X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.1-7, 2002-03-10
- 被引用文献数
- 20
肉豚に、欠乏するアミノ酸を添加した低タンパク質飼料を給与し、尿量、糞尿への窒素排泄量およびアンモニア発生量に対する影響を調べた。体重約35kgの去勢豚12頭を代謝ケージに収容し、標準タンパク質飼料(CP16.4%、標準CP区)またはアミノ酸添加低タンパク質飼料(CP10.9%、低CP区)をそれぞれ6頭に28日間にわたり不断給与した。試験開始後8~12日目に窒素出納試験を実施し、また、28日目に糞および尿を採取してアンモニアの発生量を調べた。その結果、増体量、飼料摂取量および飼料要求率ではCP水準による差は認められなかったが、飲水量は低CP区で標準CP区の約87%と少なくなり、尿量は低CP区で67%に低減する傾向を示した。また、糞および尿への窒素排泄量は、低CP区では標準CP区に比較してそれぞれ82%および50%に、また、総窒素排泄量は62%に減った。さらに、糞尿混合物からの発生アンモニア濃度は、混合1日目で、低CP区は標準CP区の36%と著しく低くなった。以上の結果より、飼料中のアミノ酸バランスを整えた低CP飼料を肉豚に給与すれば、発育成績は損なわずに、糞尿への窒素排泄量が減るばかりでなく、尿量およびアンモニア発生量も低減されることが示された。
- 著者
- 桑原 康 長内 尚 相木 寛史 間野 伸宏 佐伯 真魚 小牧 弘
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚学会誌 = The Japanese journal of swine science (ISSN:0913882X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.160-164, 2012-12-26
ブタは臓器形態や生理代謝が人と類似している面のある動物である。特に実験用小型ブタ(ミニブタ)は小型で飼育管理も取り扱いやすく,1960年頃から(BUSTAD, 1966),実験動物として医薬品の開発研究などに利用されてきた。我が国でも小型イノシシと肉用豚種との交雑や肉用豚種における小型個体の選抜育種など多様な手法により(田中,2001),これまでにNIBS系,クラウン系,ユカタン系,およびマイクロ系などのミニブタの系統が作出されている。NIBS系はピットマンムーア系ミニブタ,タイワン小耳種,およびゲッチンゲン系ミニブタをかけ合わせ,約10年かけて平均体重が20kg程度となるように作出された均整のとれた形態を有する系統である(斉藤,2004)。またクラウン系は,ゲッチンゲン系ミニブタとオーミニ系ミニブタのF1およびランドレース種と大ヨークシャー種のF1を交雑することにより作出された(金剛ら,2008)。ユカタン系はメキシコ原産で皮膚は濃茶で体毛は殆ど認められない平均体重40kgになる系統である。マイクロ系は,富士マイクラ株式会社によって複数の系統の交配の結果作られた小型ミニブタであり,平均体重は10kg程度である。ミニブタは現在も様々な研究機関で開発が進められており,日本大学生物資源科学部飼養学研究室においてもNIBS系とマイクロ系を掛け合わせた平均体重30kgの体色が白色のミニブタ(NU系)を作出している。しかし,各系統の母系関係については不明な点が多い。そこで本研究では,各ミニブタ系統の母系起源を探ることを目的として,当研究室が作出したNU系を含む我が国で入手可能な6系統のミニブタを対象にミトコンドリアDNA(以下mtDNA)非コード(D-loop)領域の塩基配列を決定し,分子系統解析を行った。
1 0 0 0 OA 産肉能力検定のページ
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.69-69, 1970-04-30 (Released:2011-06-08)
- 著者
- 丹羽 美次 中西 五十
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚学会誌 = The Japanese journal of swine science (ISSN:0913882X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.157-165, 2002-09-20
- 被引用文献数
- 6 4
食品製造副産物の有効利用を促進するため、パスタ屑を加えた飼料およびパン屑、豆腐粕を主体とするサイレージを調製し、これを肉豚に給与して発育増体や肉質等への影響について検討した。試験は体重約30kgのLD交雑種(肥育試験I)および42kgのLWD交雑種(肥育試験II)を使用し、平均体重105kg到達までとした。供試飼料はトウモロコシ主体の対照区、パスタ屑を約40%含有するパスタ区、パン屑および豆腐粕を乾物中約76%(肥育試験I)、または約90%(肥育試験II)含有するパン屑・豆腐粕区の3区を設けた。その結果、パン屑・豆腐粕区は両試験とも対照区を超える日増体量を示し、パスタ区についても肥育試験Iでは対照区と比較して若干低い値を示したものの、肥育試験IIではむしろ良好な発育となった。屠殺解体後の枝肉の状況では、枝肉歩留、背脂肪の厚さ、肉および脂肪色等において各試験区間に有意さは認められなかった。体脂肪への影響について、パスタ区の背脂肪は飽和脂肪酸を多く含有し融点の高い脂肪となったが、パン屑・豆腐粕区では融点が低下するものの、軟脂とされる状況ではなかった。以上のことから、供試した副産物を主体とする飼料において、通常の配合飼料と同等の肉豚生産が可能と考えられる。
1 0 0 0 豚閉鎖集団において線形計画を用いた制限付き選抜法の比較
- 著者
- 佐藤 正寛
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚学会誌 = The Japanese journal of swine science (ISSN:0913882X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.136-140, 2007-09-10
- 被引用文献数
- 3
豚系統造成規模の集団において、線形計画法を用いて雌雄毎に制限を付加して候補個体を選抜した場合(方法1)と雌雄同時に制限を付加し選抜した場合(方法2)における選抜個体の推定育種価(EBV)をモンテ・カルロ法によるコンピュータシミュレーションにより比較した。繁殖集団の大きさは、雄8頭雌40頭、雄10頭雌50頭、雄12頭雌60頭の3通りとし、基礎集団(GO)を含む2形質3世代分の無作為選抜記録を発生させた。一腹あたりの育成頭数は雄1頭雌2頭とした。G2において、形質2の改良量を0に制限し、形質1の改良量を最大にする選抜を実施した。形質1におけるEBVの平均は、いずれの集団においても方法1より方法2が大きく、形質2では方法間に違いはみられなかった。集団のサイズが大きくなるにつれ、形質1におけるEBVの平均はいずれの方法においても大きくなった。しかし、形質2のそれには集団のサイズによる違いや傾向はみられなかった。以上の結果から、豚系統造成規模の集団では、雌雄毎に制限を付加するよりも、雌雄同時に制限を付加して候補個体を選抜することが望ましいと結論づけた。
1 0 0 0 ブタ凍結精液の融解後精子生存率が受胎率及び胎子数に及ぼす影響
- 著者
- 門脇 宏 鈴木 啓一 日野 正浩
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚学会誌 = The Japanese journal of swine science (ISSN:0913882X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.20-24, 2001-03-10
- 被引用文献数
- 2
融解後生存率の異なるブタ凍結精液を用いて人工授精を行い,受胎率及び一腹あたりの胎子数または産子数を調査した。供試精液は宮城県畜試で実施中の雄型選抜試験の第4世代12頭のデュロック種雄豚から採取した。凍結ストローの作成は豚凍結精液利用技術マニュアルに準拠した。ただし,前処理液および融解液にはモデナ液を利用した。凍結操作はプログラムフリーザーを用いた方法で行った。凍結融解後の生存率が異なる精液を用いて人工授精を行い,28-44日(平均33.7±5.5日)後にと殺して胎子数を調べた。受胎率および一腹胎子数は,精子生存率45-55%の精液を用いた場合は58.3%および6.4頭であったのに対し,生存率70-80%の精液では91.7%および9.4頭と高い傾向を示し,融解後の精子生存率の高い精液を用いることによって受胎率および胎子数が改善される可能性が示唆された。また,融解後生存率の高い(60%以上)の凍結・融解精液を用いて野外受胎試験を行った結果は,受胎率46.2%および産子数7.8頭であった。
1 0 0 0 付着部材を利用したふん尿分離豚舎汚水からのリン回収
- 著者
- 川村 英輔 田邊 眞 高田 陽 室田 佳昭 白石 昭彦 高柳 典弘 鶴橋 亨 鈴木 一好 西村 修
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚学会誌 = The Japanese journal of swine science (ISSN:0913882X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.117-127, 2012-09-28
- 被引用文献数
- 1
反応槽下部からの曝気によりpHを調整し,反応槽内に浸積させたステンレス製の付着部材表面にMAPを成長させて結晶状のリンを回収した。使用した付着部材は,直径と高さが異なる4種類のステンレス製の網カゴを4重にしたものを用いた。ふん尿分離豚舎汚水及びふん尿分離豚舎汚水を脱水機にて脱水処理した脱水ろ液を供試した。豚舎汚水を用いた場合,リン結晶化率は,平均で66%を示し,結晶化リン量あたり回収リン量(リン回収効率)は,平均で8.2%となった。一方,脱水ろ液を用いた場合,リン結晶化率は,平均で83%を示し,リン回収効率は,平均で26.7%となった。また,両汚水の付着部材へのリン負荷量を2.0kg/m2とした場合,豚舎汚水は0.7~0.9kg/m2,脱水ろ液は3.0kg/m2のMAPが回収可能であった。これは,付着部材表面積を拡大したことと豚舎汚水を脱水処理することでSSが低減し,pHの上昇度合いが高まり,リン結晶化率が改善し付着部材表面での結晶成長が促進されたことによるものと考えられた。
1 0 0 0 OA 新生豚の血漿カテコールアミン濃度に対する寒冷の影響
- 著者
- 宮腰 裕 太田 達郎 咲山 久美子
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.192-195, 1986-12-30 (Released:2011-06-08)
- 参考文献数
- 10
1腹6頭の子豚 (Landrace×Hampshire) を実験に用い, 2日齢から14日齢までの間に, 寒冷ストレスおよび取扱いのストレスをそれぞれ2回負荷して, 血漿カテコールアミン濃度を測定し, 平常時の値と比較した。実験時の子豚の直腸温, 吸乳量およびヘマトクリット値は日齢に伴う正常な変動を示し, また, 血漿グルコース濃度には与えられたストレスによると思われる変化が認められなかった。7日齢以前のストレス負荷時における血漿中のノルエピネフリン (NE) およびエピネフリン (E) の値は平常よりも高い傾向を示したが, 10日齢以降ではその傾向が明らかではなかった。NE/E比はストレス負荷時の値が平常時よりも有意に高く (P<0.05), また寒冷ストレス時の値が取扱いストレス時の値よりも高かった。以上のことから新生期におけるストレスに対する血中カテコールアミン放出反応が認められ, 特に寒冷ストレスに対してはノルエピネフリン濃度が相対的に高くなることが示された。