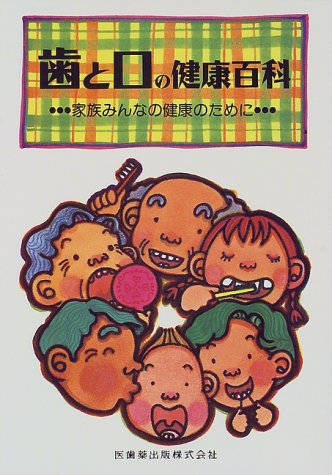2 0 0 0 OA 超音波霧化現象の可視化解析
- 著者
- 土屋 活美 林 秀哉 藤原 和久 松浦 一雄
- 出版者
- 日本エアロゾル学会
- 雑誌
- エアロゾル研究 (ISSN:09122834)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.11-17, 2011 (Released:2011-04-12)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
It has been claimed in the literature that selective ethanol separation from ethanol-water solution can be made through ultrasonic atomization. The causes of separation were explained in terms of parametric decay instability of capillary waves, accumulating acoustic energy in a highly localized surface of the capillary wave and effecting ultrasonic atomization. In this study, the atomization process is examined visually with some mechanistic view, and the dynamics of interfacial oscillations occurring along the perturbed protrusion or conical “liquid column/fountain jet” over the ultrasonic transducer are analyzed by high-speed imaging. It is found that the atomization process could be initiated by a sudden increase in surface roughness of microscale, which would be viewed as localized surface patches of two-dimensional capillary waves, often associated with contraction expansion sequence of surface to-pology. Such surface patches could bring further instability in generating a swarm of liquid droplets of microscale around the expanded phase of liquid column.
- 著者
- 松浦 一雄
- 出版者
- 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 = Journal of the Brewing Society of Japan (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, no.5, pp.310-317, 2013-05-15
超音波霧化分離法を利用した高濃度・純米清酒が初めて発売されて,13年が経過した。その間,NEDO事業などによってバイオエタノールの精製装置として開発を継続し,その分離効率は飛躍的に高まってきた。平成18年の酒税法改正によって,清酒のアルコール濃度は22容量%を超えてはならないとされたため,上述の清酒は販売が中断されたものの,酒類以外の実用化例が実現し論文数も世界的に増加し普及の速度が高まっている。本項では,酒類を起点として開発が開始され,あたらしい溶液分離方法として確立しつつある超音波霧化分離法について,その実用面に力点を置き概説した。
2 0 0 0 歯内療法 : 歯髄保存の限界を求めて
- 著者
- 下野正基 飯島国好編集
- 出版者
- 医歯薬出版
- 巻号頁・発行日
- 1993
2 0 0 0 歯周病のメインテナンス治療
- 著者
- 加藤煕 畠山善行 船越栄次著
- 出版者
- 医歯薬出版
- 巻号頁・発行日
- 2000
2 0 0 0 歯と口の健康百科 : 家族みんなの健康のために
- 著者
- 伊藤公一 [ほか] 編集
- 出版者
- 医歯薬出版
- 巻号頁・発行日
- 1998
2 0 0 0 OA 日本の大学における国際交流担当職員の業務と専門性 : 大学職員のライフストーリーから
- 著者
- 渡部 留美 WATANABE Rumi
- 出版者
- 名古屋大学高等研究教育センター
- 雑誌
- 名古屋高等教育研究 (ISSN:13482459)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.123-142, 2013-03 (Released:2013-04-24)
本稿では、日本の大学で国際交流担当部署に従事する専任職員の専門性について、ライフストーリーを用いて明らかにする。ある2 大学(私立大学)に勤務する職員2名に対し、就職するまでに経験していたこと、就職してから業務上または業務外で経験して身につけたことなどを学生やスタッフとの関わりのなかで日常業務にどのように活かしているのか語ってもらった。2名共、国際交流担当の専門職として入職したわけではないが、学生の国際交流や大学の国際化について信念をもって、ときには悩みながら、ときにはやりがいを感じながら業務に取り組んでいる様子を捉えることができた。国際交流担当職員の専門職化、職能開発などが必要とされている議論があるなかで、職員個々の思いや体験についての調査はまだ十分になされていない。職員の職場における体験の語りをどのように捉え、職員の能力開発、広くは大学の国際化戦略や大学経営に繋げていくかが今後の課題である。This study explains the specialties of full-time staff at an international exchange division in a Japanese university through their life experiences. We interviewed staff at two private universities; they described their experiences before becoming staff members, learning from experiences on and off the job, and how these events supplemented practices applicable to their current work. Furthermore, they discussed student services and university internationalization strategies. Although not holding administrative positions, the staff members perform administrative duties, experiencing both difficulty and fulfillment, while retaining their convictions regarding university international exchange and internationalization. Although research addresses the necessity of development and specialization of international exchange instructors, there is insufficient qualitative research concerning the thoughts and experiences of individual staff members. We must create connections so that their stories can inform university internationalization strategies and management as well as future professional development capabilities.
2 0 0 0 IR 古英語・中英語における「空主語」の認可と消失 : 話題卓立言語から主語卓立言語へ
- 著者
- 縄田 裕幸
- 出版者
- 島根大学
- 雑誌
- 島根大学教育学部紀要. 教育科学・人文・社会科学・自然科学 (ISSN:18808581)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.101-110, 2012-12-25
2 0 0 0 OA 言語情報の構造化・体系化から文化へ
- 著者
- 平澤 洋一 松永 公博
- 出版者
- 情報文化学会
- 雑誌
- 情報文化学会誌 (ISSN:13406531)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.24-31, 2015-08-17
どの授業においても,同一教場内には学力・意欲・理解力の異なる学習者が混在する。一方で,学ぶべき学習内容も多い。小さな領域から大きな領域までを首尾一貫して説明できる理論があれば理想である。言語学でいえば,音韻論,文法論,語彙論,意味論,語源論,言語生活論,コミュニケーション論,言語史,比較言語学,言語地理学,文化言語学,言語心理学,計量言語学などの領域を結びつける理論の確立が待たれる。本稿では,言語情報の構造化・体系化を行うことで(1)教場内における学習者の理解と教育コミュニケーションを高め, (2)その構造化・体系化の方法論を磨くことで情報文化の構造化・体系化に近づけるための問題点とその打開策を検討する。
2 0 0 0 台湾における日本研究 : 国際学術ネットワークと台湾の日本研究者
- 著者
- 岡崎 幸司
- 出版者
- 立命館大学人文学会
- 雑誌
- 立命館文學 = The journal of cultural sciences (ISSN:02877015)
- 巻号頁・発行日
- no.640, pp.360-350, 2014-12
2 0 0 0 IR 調査研究シリーズ(111)ドイツにおける日本研究および日本語教育について
- 著者
- 奥山 文幸
- 出版者
- 熊本学園大学付属海外事情研究所
- 雑誌
- 海外事情研究 (ISSN:02870932)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.55-73, 2015-09
- 著者
- 李 世暉
- 出版者
- 国立政治大学国際関係研究センター
- 雑誌
- 問題と研究 : アジア太平洋研究専門誌 (ISSN:02887738)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.39-66, 2016-01
2 0 0 0 第5回「東アジア日本研究フォーラム」会議実録
- 著者
- 徐 興慶
- 出版者
- 国立政治大学国際関係研究センター
- 雑誌
- 問題と研究 : アジア太平洋研究専門誌 (ISSN:02887738)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.67-76, 2016-01
2 0 0 0 「国際日本学」研究にむけて : 日本の外から日本研究を考える
- 著者
- 辻本 雅史
- 出版者
- 日本思想史研究会
- 雑誌
- 日本思想史研究会会報 = The annual of history of Japanese thought (ISSN:02873338)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.1-4, 2016-03
- 出版者
- 神戸大学国際文化学部日本文化論大講座
- 雑誌
- 日本文化論年報 (ISSN:13476475)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.129-138,1-9, 2016-03
- 著者
- 岡崎 幸司
- 出版者
- 立命館大学人文学会
- 雑誌
- 立命館文學 = The journal of cultural sciences (ISSN:02877015)
- 巻号頁・発行日
- no.647, pp.996-988, 2016-03
- 著者
- 佐野 洋 サノ ヒロシ SANO Hiroshi
- 出版者
- 東京外国語大学国際日本研究センター
- 雑誌
- 日本語・日本学研究 / 東京外国語大学国際日本研究センター [編] (Journal for Japanese studies) (ISSN:21860769)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.233-242, 2016-03-31
- 著者
- 中沢 綾
- 出版者
- 日本図書館協会
- 雑誌
- 図書館雑誌 = The Library journal (ISSN:03854000)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.7, pp.418-419, 2016-07
2 0 0 0 IR 美術史は全球化しうるか? : 極東の視点からする批判的注釈
- 著者
- 稲賀 繁美
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.105-128, 2017-01
学術としての「美術史学」は全球化(globalize)できるか。この話題に関して、2005年にアイルランドのコークで国際会議が開かれ、報告書が2007年に刊行された。筆者は日本から唯一この企画への参加を求められ、コメントを提出した。本稿はこれを日本語に翻訳し、必要な増補を加えたものである。すでに原典刊行から8年を経過し、「全球化」は日本にも浸透をみせている話題である。だがなぜか日本での議論は希薄であり、また従来と同じく、一時の流行として処理され、日本美術史などの専門領域からは、問題意識が共有されるには至っていない。そうした状況に鑑み、本稿を研究ノートとして日本語でも読めるかたちで提供する。 本稿は、全球化について、①アカデミックな学問分野としての制度上の問題、②日本美術史、あるいは東洋美術史という対象の枠組の問題、③学術上の手続きの問題、④基本的な鍵術語(key term)の概念規定と、その翻訳可能性、という4点に重点を絞り、日本や東洋の学術に必ずしも通じていない西洋の美術史研究者を対象として、基本的な情報提供をおこなう。
2 0 0 0 福島県郡山市医療施設における検診ツアーの現状と地理的特性
- 著者
- 三原 昌巳
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.21-21, 2010
「予防医学の時代」に健康増進や疾病予防を目的にした旅行(ヘルスツーリズム・医療ツーリズム)に関心が集まっている。その一つである、ここ数年で急成長した検診ツアーは、医療施設(主に病院)・旅行会社・宿泊施設(旅館やホテル)が提携することによって積極的な広報活動を行い、顧客を呼び込もうとする新しい試みである。このような動きは地理学的な観点からみると、患者の居住する地域つまり受療圏が非常に広範囲であることに加え、都市部の患者が地方へ受診に向かうという行動は従来の受療行動からすれば一般的ではないといえる。これまでの地理学では居住地と医療施設間の物理的移動に着目しながら地域医療における患者のアクセシビリティについて検討がなされてきたが、患者にとって地理的障壁はもはや存立しないのだろうか。予防医学の推進によって、医療施設までの距離や移動時間といった地理的要素は重要視されなくなったのか。こうした問題意識を踏まえ、本発表では福島県郡山市内の医療施設で実施されているPET(ペット)検診ツアーを事例にし、PET検診ツアー成立までの過程、検診ツアー参加者の特徴を述べると同時にその地理的特性を明らかにしたい。具体的な調査方法としては、現地調査を2010年6月~8月にかけて実施した。クリニック、受入れ旅館・観光協会、旅行会社3社などを対象に聞取り調査や資料収集を行った。PETは、ポジトロン・エミッション・トモグラフィー(Positron Emission Tomography/陽電子放射断層撮影装置)の略語で、日本人の3大死因のトップを占めるがんの早期発見の切り札として、近年注目される検査方法の一つである。しかし、1台数億円と言われる高額なPET(またはPET-CT)機器に加え、検査薬の製造室や空調設備までを兼備しようとすると、大規模な医療施設でさえPETの導入はしづらいものであった。このため当初は全国的にもPETを導入する医療施設はわずかで、とくに人口の多い都市部において受診予約がとりにくい状況が続いていた。検診ツアーは、このような状況を察知した旅行会社によって企画された。廉価なツアー価格設定が可能な飛行機での移動が専らで、名古屋、羽田、大阪などの空港から出発し、目的地は北海道、九州・沖縄などであった。20万円前後の価格にもかかわらず、異例のヒット商品となったと言われる。しかし2006年以降、人気は下火になり、PETを導入した医療施設には倒産する所もみられた。郡山市内の対象クリニックでは、2004年4月からPET(PET-CTを含む)を導入し、保険適用診療と自由診療のがん検査を開始した。クリニック開設以来、PET検診の周知のため、県内外各地での市民公開講座による住民向けの啓蒙活動と、PET講習会による医療提供者側への普及活動を継続的に実施している。同時に、2005年から同県二本松市岳温泉の旅館・首都圏各地の旅行会社と提携し、検診パックツアーを提供している。岳温泉は、「湯治場」の歴史を持ち温泉地として繁栄してきたが、バブル崩壊後の宿泊客減少に歯止めがかからず2004年ごろから健康保養型温泉地への転換を図った。起伏に富む安達太良山系の自然環境を活かし、主に50代以上の中高年層を対象にしたヘルスツーリズムの取組みによって地域づくりを実施している。検診ツアー受入れ旅館では、地域のこのような取組みもツアー参加者に提供しており、旅行の付加価値を高めている。申込み窓口である旅行会社は首都圏を中心に数社あり、各顧客層に応じて商品の告知と勧誘を行っている。対象クリニックではPET検診ブームが終焉した後も自由診療による患者が多く来院しており、PET機器は高い稼働率を維持している。このうち、検診ツアー参加者をみると、東京・群馬を中心に埼玉・千葉・神奈川など首都圏に居住する50~70代が多いことが分かった。検診ツアー普及初期は遠方の医療施設も選択されたが、PET導入の医療施設が増加するに従って都市部でも受診しやすくなり、交通至便な医療施設が選択されるようになった。一方、郡山市は県内で交通の要所、また首都圏からのアクセスの良さを背景に、検診時・宿泊旅館での付加サービスや検診後のケアを充実させ顧客の定着を図った。検診後のケアでは、何らかの異常が発見された場合には再検査や治療などの再診を、異常が発見されなかった場合でも健康管理のために定期的な検診を行う。このため、旅行商品として売り出されたものの、継続的な通院を必然的に伴う医療サービスの特質ゆえ居住地近郊の医療施設での受診が選択されやすいことが分かった。