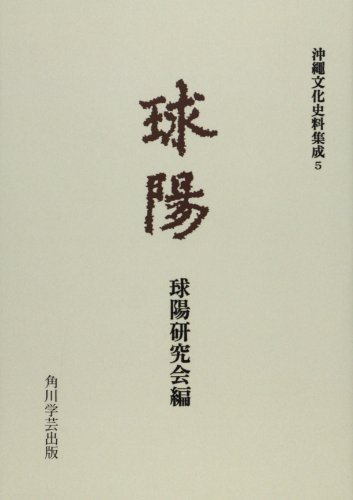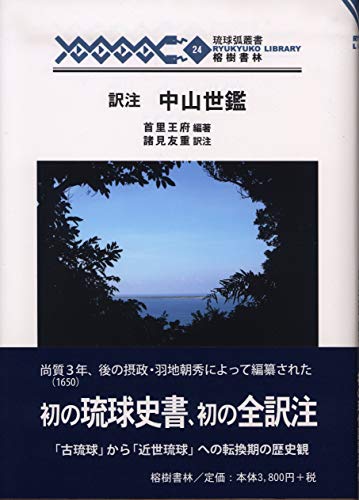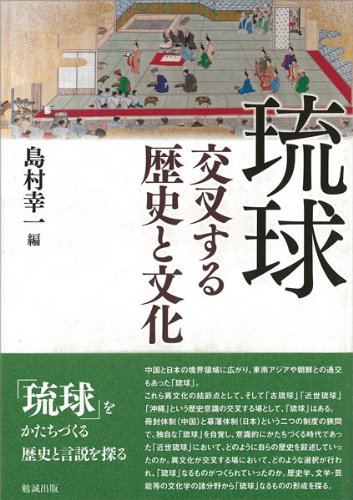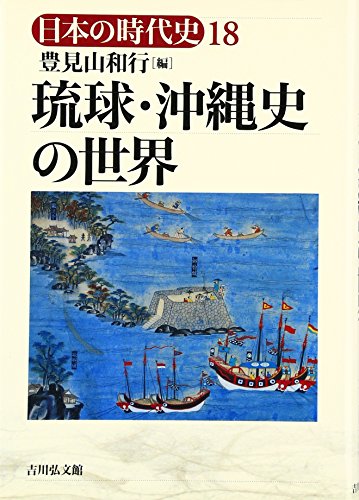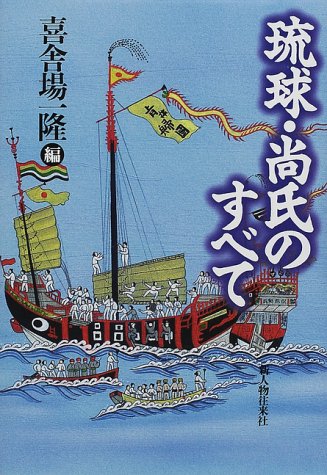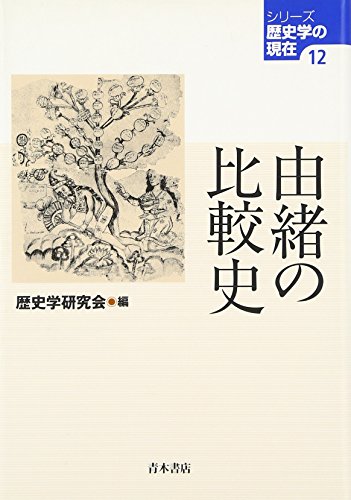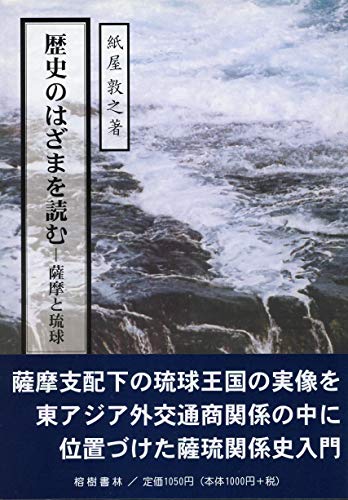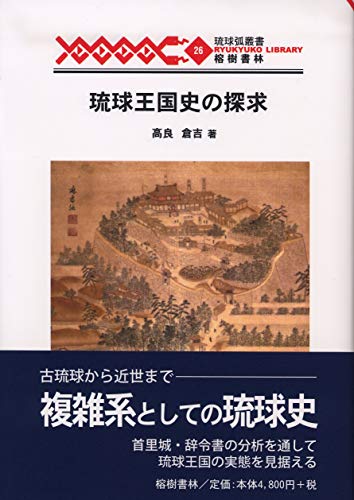- 著者
- 春日 昭夫
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)
- 巻号頁・発行日
- no.702, pp.62-63, 2018-12-24
—ポルチェベーラ高架橋の事故原因をどうみていますか。 大勢が亡くなっているので軽はずみなことは言えませんし、原因の特定は難しい作業になると思いますが、ケーブルの破断を事故のきっかけだとみるのが自然でしょうね。 日本でも、似たような形式のプレ…
- 著者
- 笹島 保弘
- 出版者
- 日本味と匂学会
- 雑誌
- 日本味と匂学会誌 (ISSN:13404806)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.189-195, 2009
香りと味ということでイタリアンシェフの立場から現場の事例を紹介する。低温からニンニクとエキストラバージンオイルを加熱するとえも言えない良いにおいがする。そして、いい香りとはその食材の味のポテンシャルとある面で平衡している。ニンニクオイル、塩でトマトを煮詰めていくようなトマトソースは、イタリア人にとって日本人の一番だしに値するようだ。一方、ハーブは香りというより味を変える目的で使われている。同様に高価な白トリュフはそのものが持つ香り・味でなく、トリュフをかけた料理の味が際立ち、おいしくなるという理由で用いられる。
1 0 0 0 OA Report on Survey of Japanese Postal System
- 著者
- Prepared by Civil Communications Section
- 巻号頁・発行日
- 1949
- 著者
- 大藤 修
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.p67-132, 1992-03
本稿は、近世農民層の葬送・法事および先祖祭祀のあり方と、その際の家、同族、親族、地域住民の関与の仕方と役割、それをめぐる諸観念、規範などについての考究を課題とする。同族結合が強い段階では死者の葬送・供養や先祖祭祀も同族の長を中心に同族団の儀礼として執行されていたようであるが、個々の家が自立性を強めるに伴い、家がその執行主体となり、独自に墓碑、位牌、過去帳などを作るようになる。生前の生活および死後の魂の安穏が家によって基本的に保障されるようになった段階では、家を保ち先祖の祭祀を絶やさないことが絶対的な規範として子孫に要請される。だが、家での生活が親類や地域共同体の相互扶助によって成り立っていたのと同様、死者の葬送、霊魂の供養も、親類や地域共同体がその保障を補完する機能を果たしていた。葬式・法事の営み方に当主の直系尊属、配偶者か直系卑属、傍系親かによって格差をつけていた例もみられる。休業・服忌の期間は、父母の死去の場合とりわけ長く設定している所が多い。他家に養子あるいは嫁として入った者も、葬儀はもちろん年忌法要にも参加し、弔い上げによって祖霊=神に昇華するまでは親の霊の面倒をみるのが子としての務めであった。弔い上げ後は家の継承者によってその家の先祖として代々祭祀されていく。直系家族制のもとにおいては歴代の家長夫婦がその家の正規の先祖であり、単身のまま生家で死去すれば無縁仏として扱われる。生前は家長・主婦として家を支え、死後はその家の先祖として子孫に祭られるというのが現世と来世を通じた正規の人生コースとされており、再婚の多さは正規の人生コースに復させる意味ももっていたと思われる。家の成員の霊魂の間には家の構造に規定された差別の体系が形づくられていたが、と同時に、家を基盤に広く成立、成熟した先祖観は社会的にも差別を生み出す契機をはらみ、その一方で天皇へ結びつく性格も有した。
1 0 0 0 家譜資料
- 出版者
- 那覇市企画部市史編集室
- 巻号頁・発行日
- 1976
1 0 0 0 球陽
- 著者
- [鄭秉哲ほか原編] 球陽研究会編
- 出版者
- 角川グループパブリッシング (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2011
1 0 0 0 琉球 : 交叉する歴史と文化
1 0 0 0 琉中歴史関係論文集 : 琉中歴史関係国際学術会議
- 著者
- 琉中歴史関係国際学術会議実行委員会[編]
- 出版者
- 琉中歴史関係国際学術会議実行委員会
- 巻号頁・発行日
- 1989