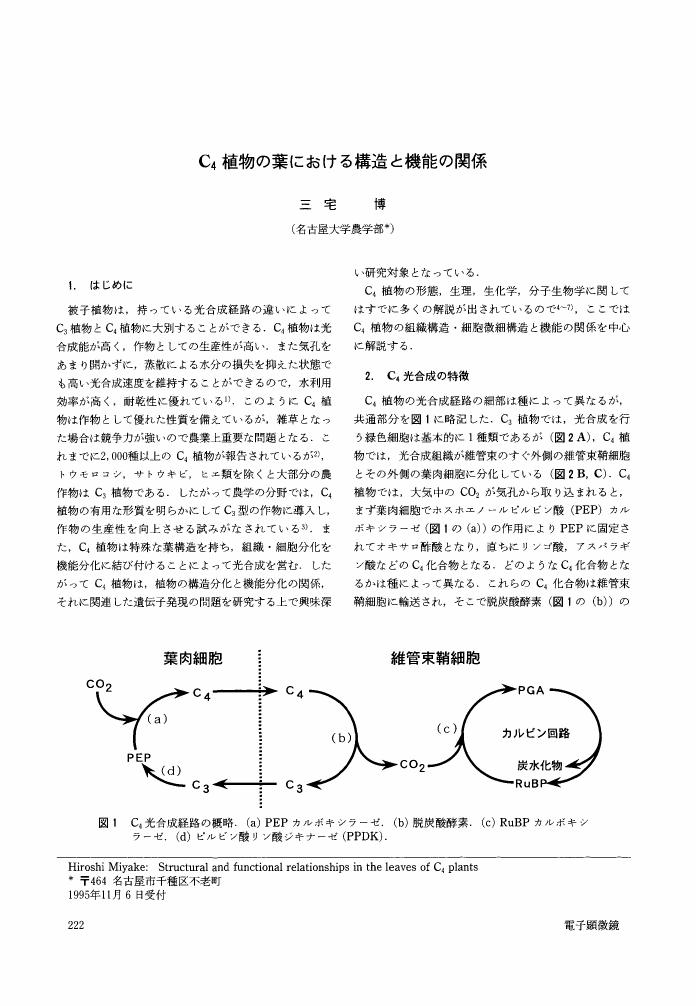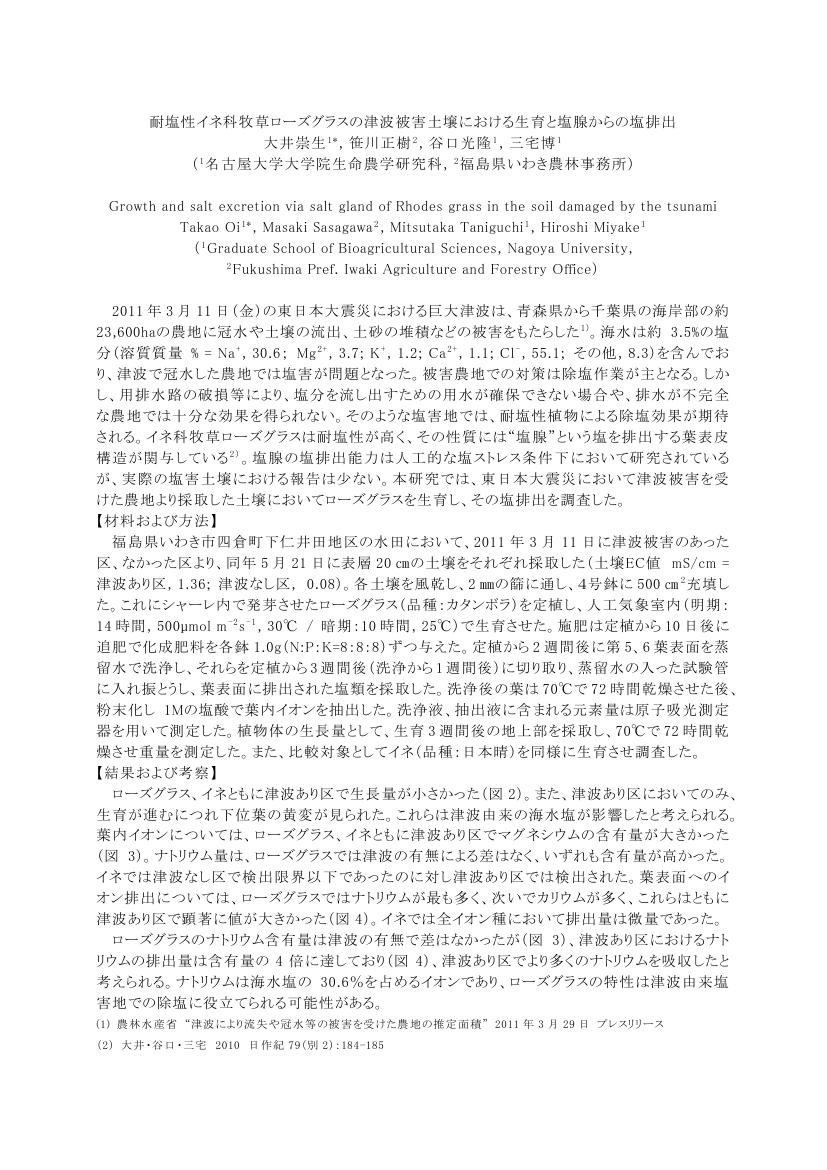2 0 0 0 OA C4植物の葉における構造と機能の関係
- 著者
- 三宅 博
- 出版者
- 公益社団法人 日本顕微鏡学会
- 雑誌
- 電子顕微鏡 (ISSN:04170326)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.222-228, 1996-03-31 (Released:2009-06-12)
- 参考文献数
- 32
- 著者
- 前田 英三 三宅 博
- 出版者
- 日本作物学会
- 雑誌
- 日本作物學會紀事 (ISSN:00111848)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.340-351, 1996-06-05
- 被引用文献数
- 1
イネの反足細胞は, 卵細胞から離れ珠心側壁に接して存在する. 多くの裂片をもつ巨大な異常核, 粗面小胞体, 細胞壁内向突起などが, 開花直後のイネ反足細胞内に観察された. 細胞核の裂片は核質の小さな架橋により連結しており, プラスチドやミトコンドリアや粗面小胞体を含む細胞質の一部を取り囲んでいる. 珠心細胞と接する反足細胞の細胞壁には, よく発達した内向突起が見られる. 粗面小胞体の先端が細胞壁内向突起と融合している場合も観察される. 反足細胞付近の珠心細胞は, すでに退化しはじめている. これらの細胞構造及びリボゾームを表面に伴った小胞の行動などから, 珠心細胞から胚嚢内中心細胞へのアポプラスチックな物質輸送に関する反足細胞の役割につき考察した. また, 胚嚢内の物質の移動経路についても, 簡単に述べた.
1 0 0 0 OA 建築確認申請手数料の成立過程
- 著者
- 三宅 博史 藤賀 雅人
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.66, pp.883-886, 2021-06-20 (Released:2021-06-20)
- 参考文献数
- 8
This paper studied the enacting process of the Application fee for Building confirmation. Conclusion of this study is as follows; 1) In the process of enacting the Building Standards Law, the maximum amount and the maximum amount above a certain scale were added to the article after the legal examination. 2) In the process of enacting the Enforcement Order, detailed provisions were established with eight levels of area classification. 3) In order to make the maximum upper limit equal to the conventional amount, the area scale of the corresponding category was set too small as a standard for the future.
- 著者
- 伊豆田 猛 大津 源 三宅 博 戸塚 績
- 出版者
- Japan Society for Atmospheric Environment
- 雑誌
- 大気汚染学会誌 (ISSN:03867064)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.1-8, 1994
3品種 (ユキコマチ, コメット, ホワイトチェリッシユ) のハツカダイコン (Raphanus sativus L.) に, 播種10日後から, 0.15μl・l-1のオゾンを, 1日当たり4時間 (10: 00~14: 00), 5日間/週で, 野外に設置したオープントップチャンバー (OTC) を用いて暴露した。播種17日後に, 植物を収穫し, 葉面積と乾重量を測定した。また, 播種13日後の個体に, 0.15μl・l-1のオゾンを4時間暴露し, ガス交換速度を測定した。<BR>個体当たりの乾物生長に基づいたオゾン感受性は, ユキコマチ>コメット>ホワイトチェリシュの順に高かった。また, 純同化率および平均純光合成阻害率におけるオゾン感受性も同様な傾向が認められた。ユキコマチのオゾン吸収速度は, 他の2品種と有意な差はなかったため, オゾン吸収速度の違いによって, 純光合成速度におけるオゾン感受性の品種間差異は説明できなかった。これに対して, 単位オゾン吸収量当たりのCO<SUB>2</SUB>吸収量の阻害率は, 各品種間で異なり, ユキコマチ>コメヅト>ホワイトチェリッシュの順に高かった。<BR>以上の結果より, ハッカダイコンにおいては, 乾物生長に基づいたオゾン感受性の品種間差異に, 単位オゾン吸収量当りの純光合成阻害率が関与していると考えられた。
- 著者
- 大井 崇生 笹川 正樹 谷口 光隆 三宅 博
- 出版者
- 日本作物學會
- 雑誌
- 日本作物學會紀事 (ISSN:00111848)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.4, pp.378-385, 2013
- 被引用文献数
- 3
ローズグラスは体内に取り込んだ塩類を排出する塩腺を有し,耐塩性が高いことが知られるイネ科牧草である.本研究では,津波被災農地の土壌を用いてローズグラスの耐塩性および塩排出能力を検討した.福島県いわき市において,2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震に伴う津波被災のなかった地点,あった地点の農地より土壌を採取して実験に用いた.採取地のうち四倉町の津波あり地点では,土壌EC値および土壌中交換性Na<sup>+</sup>量がともに高い値を示した.この土壌を用いてローズグラスおよびイネを人工気象室内で21日間生育させた.両作物ともに津波あり地点の土壌において生育阻害が現れたが,ローズグラスでは地上部乾物重の減少率はイネよりも小さく,また可視障害も少なく,さらに長期間の生育が可能と考えられた.葉身内のイオン含有量を測定すると,ローズグラスでは津波の有無に関わらず高いNa<sup>+</sup>含有量を示した.加えて津波あり地点の土壌において,ローズグラスでは葉身や葉鞘の表面に水滴または結晶状の排出物が観察された.1週間あたりの葉身からのイオン排出量を測定すると,葉身の含有量の4倍のNa<sup>+</sup>が排出されることが確認された.また,生育後の土壌中交換性Na<sup>+</sup>の減少量はイネよりもローズグラスの方が大きい傾向があった.以上より,ローズグラスは津波被災農地における転作利用や除塩に役立つ可能性が示唆された.
- 著者
- 山本 竜也 三宅 博行 山口 秀樹 吉澤 望
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)
- 巻号頁・発行日
- no.783, pp.451-461, 2021-05
- 被引用文献数
- 1
<p>While improvements in the energy-saving performance of buildings are required, productivity improvements and health management are also getting more necessary due to work style reforms. This trend demands the development of new methods which enable us to quantitatively assess the physiological and psychological quality of the built environment from the design stage. In terms of the light and visual environment, spaciousness is one of the factors that affect the comfort, intellectual productivity, and health of users of interiors.</p><p>In this research, definition of "spaciousness" by Inui will be used, but the purpose of this study was to propose a comprehensive quantitative spaciousness evaluation index of the interiors, including spaces of different sizes and shapes, considering various factors related to light and visual environment.</p><p>In recent years, technological developments have made complex data processing possible and expanded the range of experiment methods. VR technology is one of them, and there are many merits of using it in promoting spaciousness evaluation, such as to virtually compare spaces that are separated from each other by a great distance. This research aims to verify the validity of using VR with HMDs for spaciousness evaluation, through subject experiments in six real spaces with different volumes and usages. Volumes ranged from a minimum of 35 m<sup>3</sup> to a maximum of 1,969 m<sup>3</sup>, and vertical illuminance ranged from 30 lx to 720 lx at the subject's observation position. Openings were blocked from line of sight and daylight was shut off by closing the blinds. VR spaces with several lighting environments for each space were reproduced. In experiments using ME method, we compared and verified the cases where the real space and the VR space were used as the reference stimulus for the comparative stimulus of the real space. Major findings are as follows:</p><p> 1) In order to verify how well the VR space could reproduce the real space from the point of view of the optical environment, we compared the luminance of the targeted real space and the VR space, and found that high-luminance parts could not be reproduced on HMD: Oculus Quest, which has an output limit of approximately 100 cd/m<sup>2</sup> or higher in luminance. However, the overall luminance balance, including main parts such as the floor, walls, and ceiling, could be well reproduced on VR display.</p><p> 2) There were no statistically significant differences (5% level) in 62 pairs among 65 pairs. As to the remaining 3 pairs, the light source had a large effect on the reproducibility of luminance and the relative error from the real space was relatively large. In particular, when the subject's evaluations were divided around 2.0, as in Experiment III, where the reference stimulus was 120lx and the comparative stimulus was 30lx, a reversal phenomenon occurs in which the average luminance of the real space of 30 lx including the light source is larger than that of the VR space of 120 lx including the light source due to the influence of the large light source. In conclusion, it is approximately possible to use the VR space, which does not cause luminance problems, as a reference stimulus for spaciousness evaluation.</p>
1 0 0 0 OA 三宅博士古稀祝賀会記念誌
- 著者
- 三宅博士古稀祝賀会 編
- 出版者
- 三宅博士古稀祝賀会
- 巻号頁・発行日
- 1929
1 0 0 0 OA ヘルマン・ヘッセの最後の作品『ガラス玉遊戯』 : 「覚醒」への道
- 著者
- 三宅 博子 Hiroko Miyake
- 雑誌
- 人文論究 (ISSN:02866773)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.204-216, 1996-05-20
- 著者
- 三宅 博史
- 出版者
- 東京市政調査会
- 雑誌
- 都市問題 (ISSN:03873382)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.7, pp.110-112, 2005-07
1 0 0 0 OA 「平成の市町村合併」の影響に関する総合的研究
- 著者
- 西尾 勝 新藤 宗幸 三宅 博史 五石 敬路 高井 正 棚橋 匡 木村 佳弘 川手 摂 田中 暁子 萬野 利恵 畑野 勇 小石川 裕介
- 出版者
- 公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2010
本研究は、「平成の市町村合併」が一段落した現時点において、「平成の市町村合併」がなにをもたらしたのかについて、多面的に把握するために、地域区分変更に関する国際比較を行うとともに、行政(職員数、職種別職員数、行政組織、施設)、財政(普通会計、特別会計、公営企業)及び住民負担、政治(議会議員及び首長の属性)について、それぞれデータベースを作成した。併せて、中央省庁、都道府県、市町村の合併事務担当者などにヒアリング調査を行った。「合併」の効果と喧伝された諸事項は、非合併自治体との比較ではあまり見ることはできなかった。また、行政と住民の距離感が開くなどの「合併の弊害」と想定された項目に対する定数特例や選挙区、地域自治組織などの諸措置は、措置自体の時限性や行政改革の帰結として、事実上剥落していった。以上の分析結果から、「平成の市町村合併」とは、「究極の行財政改革」を市町村に推進させるためのツールであった、と評価できる。
1 0 0 0 作物の形態制御に関するIn vivoとIn vitroの比較研究
イネについて、in vivoにおける受精胚の発達様式と、in vitroであるカルスの再分化過程を詳細に比較したが、in vitroでの不定胚形成は認められなかった。アブサイシン酸(ABA)や高濃度の糖はカルスの再分化を促進した。数種イネ科作物を異なった土壌水分条件下で生育させ、根の形態を比較した結果、乾燥条件下で皮層内厚壁組織の発達が顕著であった。+ABAやブラシノライドがイネ科作物やマメ科牧草の老化種子の発芽促進効果を持つことを明らかにした。熱量計を用いて種子の活性を迅速かつ非破壊的に判別する方法を開発した。高温・乾燥などの異常環境下で生育させたイネの生殖器官に現れる形態異常を明らかにし、ジベレリン(GA)とABAの関与を推察した。イネの花粉と葯内緒組織の発達過程を調べ、タペ-ト肥大が発生する際には、当初は小胞子の細胞も活性化することを明らかにした。リンゴの胚珠内胚培養、葯培養からの不定胚発生、葉カルスからの再分化について最適条件を明らかにした。またリンゴ台木マルバカイドウの胚珠内胚培養を行い、高蔗糖濃度の培地で胚の生長が起こり、GAを含む培地に移すことにより実生を得ることができた。イネカルスやダイズ懸濁培養からプロトプラストを分離し、電気的に融合させ、融合過程の微細構造を明らかにした。レ-ザ光による植物細胞への色素導入を行い、生細胞に色素が導入されていることを確認した。マツバボタンの緑色カルスにおける葉緑体のグラナ構造を観察し、カルス内に維管策鞘が分化するとそこではグラナ形成が抑制されることを明らかにした。シコクビエのジャイアントド-ムからの花芽形成に成功した。またジャイアントド-ムとバミュ-ダグラスの体細胞胚の微細構造を明らかにした。Nicotiana glutinosaのカルスより分化能を持つ細胞のみを分離して継代培養することに成功した。このカルス系統の組織構造と遊離アミノ酸含量の特徴を明らかにした。
1 0 0 0 OA 耐塩性イネ科牧草ローズグラスの津波被害土壌における生育と塩腺からの塩排出
1 0 0 0 OA 南アジア周縁地域から日本への人的移動とネットワーク形成
本研究では、在日バングラデシュ人と在日ネパール人を中心に、韓国(東アジア)とタイ(東南アジア)のバングラデシュ人とネパール人についても調査した。その結果、日本の各コミュニティーが日本を越えたネットワークを形成していることが判明した。一方、当初想定していた南アジア出身者としての両コミュニティーの結びつきは見られなかった。また、タイについては、東アジア(日本と韓国)とは異なったネットワークのあり方が見られた。これは、東南アジアに位置する(すなわち、国内にイスラム教徒がいる)仏教国という側面が影響していると思われる。