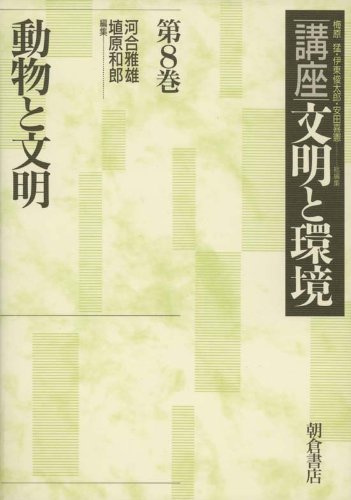31 0 0 0 OA 再考・奥州藤原氏四代の遺体
- 著者
- 埴原 和郎
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.11-33, 1996-03-31
奥州藤原家四代の遺体(ミイラ)については、一九五〇(昭和二五)年の調査に参加された長谷部言人、鈴木尚、古畑種基氏らによる詳細な報告があるものの、現在もなお疑問のまま残されている問題が多い。
12 0 0 0 OA 寒冷気候とモンゴロイドの成立
- 著者
- 埴原 和郎
- 出版者
- Japan Association for Quaternary Research
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.265-269, 1974-02-28 (Released:2009-08-21)
In this paper, the author discussed man's adaptation to the cold and formation of the northern Mongoloids in the light of human adaptability to the climatic conditions.It is widely known that the mammals generally show several adaptations to the climate, among which the most effective factors seem to be the light and the temperature. For instance, in the field of mammalian ecology, the rules proposed by GLOGER, BERGMANN and ALLEN are generally accepted, and they can be also applied on microevolution of the human populations to some extent. Thus, it is said that the Caucasoids have adapted to the cold and moist climate with low radiation of ultraviolet rays, and the Negroids to the environment with high temperature and excessive radiation of ultraviolet rays. In parallel to this, the Mongoloids are regarded as having adapted to the very low temperature and dry weather.However, adaptation in this direction has likely occurred in or just after the latest stage of the Upper Paleolithic, because the Mongoloids from this stage such as the Upper Cave Men show almost no evidence of adaptation to the extremely cold temperature.In this respect, the modern Mongoloids living in the arctic areas may be regarded as the people who acquired their adaptability to the cold in relatively recent stages of evolution. On the other hand, we can find some other populations who retain more or less archaic characters of the Mongoloids in peripheral areas of the Asian and the American Continents, and even in the sub-arctic areas.For instance, the Ainu has so far been attributed their origin to the Caucasian stock. Several recent findings on their blood composition, dermatoglyphics and dental characteristics, however, show close affinity to the Mongoloids.On the other hand, the Ainu still shows unique characteristics in quite rich beard and body hairs, relatively thin subcutaneous fat, partially projected facial bones, etc., and these characteristics do not show high degree of adaptability to the cold climate.On the basis of these fact, it is quite likely that the Ainu might be one of branches of the Mongoloid stock who has less experience to live under the extremely cold environment, and still retains some archaic characters compared with the neighbouring populations. Naturally, this hypothesis should be checked by several other data from the fields of anthropology, prehistory, geology, and other related sciences.
4 0 0 0 地球環境の変動と文明の盛衰ー新たな文明のパラダイムを求めてー
平成2年9月14日に平成3年度より出発する重点領域研究「地球環境の変動と文明の盛衰」(104 文明と環境)の第1回研究打合わせ会を京都市で実施した。出席者は研究代表者伊東俊太郎ほか13名。全体的な研究計画の打合わせと,今後の基本方針の確認ならびにニュ-スレタ-用の座談を実施した。平成2年12月1日,雑誌ニュ-トン12月号(教育社刊)誌上にて本重点領域研究にかかわる特集を組み,発表した。重点領域研究の広報活動の一環として研究計画の概要を朝日新聞11月6日付,毎日新聞1月3日付,日本経済新聞2月11日付に発表した。平成3年2月21日,ニュ-スレタ-「文明と環境」出発準備号を刊行し,関係者に配布した。内容は対談梅原猛・伊東俊太郎,座談安田喜憲ほか5名,特集,速水融ほかで31ペ-ジの構成である。大変好評で,日本経済新聞3月21日付にも紹介され,多くの研究者,企業関係者から問い合わせが殺到した。平成3年2月28日,第2回研究打合わせ連絡会を京都市で開催した。出席者は伊東俊太郎ほか重点領域計画研究関係者58名であった。午前中全体集会を実施し,午後分科会に分かれて,今後の研究方針について話し合った。今回の研究打合わせにより,58名もの参加者を得たことは,4月以降の本格的な出発に明かるい希望を抱かせた。平成3年3月8日,文部省にて重点領域研究審査会を実施し,公募研究の候補を選定した。
2 0 0 0 OA シミュレーションによる古代日本への渡来者の数の推定
- 著者
- 埴原 和郎
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.3, pp.391-403, 1987 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 30 33
主として弥生時代から初期歴史時代にかけての日本への渡来者は,先住の縄文人に対して文化的にも身体的にも多大の影響を与えたと考えられる.この点について,以前は否定的見解もあったが,現在では渡来そのものを否定する研究者はいないと思われる.しかし渡来者の土着集団への影響については見解の相違が大きく,まだ定説を得るに至っていない.ある研究者は渡来者の影響が無視しうる程度という一方で,他の研究者は少なからぬ影響があったことを想定している.しかしこれらはいずれも科学的根拠をもたず,想像の域を出ていない.このような現状を考えると,どれほどの集団が渡来したかという問題を放置しておくわけにいかず,渡来者の数を推定することは極めて重要な問題となる.しかし実際にそれを行うには多くの困難が伴う.その解決法のーつとして,この研究では2種のモデル,すなわち人口増加モデルと形態変化モデルによるシミュレーションを試みた.人口増加モデルは,弥生時代初期から7世紀にいたる約1000年間の人口増加率の特異性に基づき,この期間に渡来した集団の数を推定する方法である.また形態変化モデルは,弥生時代から古墳時代にいたる頭骨形態の変化に基づく方法であるが,基準となる集団を西北九州型弥生人および南九州古墳人(内藤芳篤による)とした.一方,渡来系と思われる北九州型弥生人と土着系の西北九州型弥生人の計測値に基づき,混血率を変化させながら仮想集団の計測値を推定し,これらと古墳人集団との類似係数ならびに距離を計算した.その結果,最も高い類似性を示す仮想集団の混血率を採用し,渡来人の数を推定した.これら2種のモデルによるシミュレーションはほぼ同じ結果を示したが,それらは予想をはるかに越える多数の渡来者があったことを示唆している.おそらく,この結果は常識外とも受け取られるであろうが,一方で日本人の形質や日本文化の多様性を考えると,相当に多数の渡来者があったと考えざるをえない点もある.今後,モデルをさらに精密化して研究を続ける必要があることはいうまでもないが,予想を越える数の渡来者が日本に入ったということを念頭に入れて,関連諸分野の研究を進めることも必要かと思われる.ただし,今回得られた結果を機械的に採用することは危険であり,私としても,おおよその見当がついたという程度に考えていることをつけ加えておきたい.
2 0 0 0 OA 日本人のルーツ
- 著者
- 埴原 和郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.11, pp.923-931, 1993-11-25 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 8 8
本稿で紹介した日本人集団の二重構造モデルは従来の諸説を比較検討し, また最近の研究成果に基づく統計学的分析によってえられた一つの仮説である. このモデルの要点は次のとおりである.(1) 現代日本人の祖先集団は東南アジア系のいわゆる原モンゴロイドで, 旧石器時代から日本列島に住み, 縄文人を生じた.(2) 弥生時代から8世紀ころにかけて北アジア系の集団が日本列島に渡来し, 大陸の高度な文化をもたらすとともに, 在来の東南アジア系 (縄文系) 集団に強い遺伝的ならびに文化的影響を与えた.(3) 東南・北アジア系の2集団は日本列島内で徐々に混血したが, その過程は現在も進行中で, 日本人は今も heterogeneity, つまり二重構造を保っている.以上の観点からさらに次のことが導かれる.(1) 日本人集団の二重構造性は, 弥生時代以降とくに顕著になった.(2) 弥生時代から現代にかけてみられる日本人集団の地域性は, 上記2系統の混血の割合, ならびに文化的影響の程度が地域によって異なるために生じた. 身体形質や文化における東・西日本の差, 遺伝的勾配なども北アジア系 (渡来系) 集団の影響の大小によるところが大きいと思われる.(3) アイヌと沖縄系集団の間の強い類似性は, 両者とも東南アジア系集団を祖先とし, しかも北アジア系集団の影響が本土集団に比較してきわめて少なかったという共通要因による. 換言すれば, 弥生時代以降著しく変化したのは本土集団であった.(4) 古代から中世にかけてエミシ, ハヤトなどと呼ばれた集団は, 本土集団とアイヌ・沖縄系集団が今日のように分離する前の段階にあったもので, その中間的形質をもっていたと考えられる.
2 0 0 0 OA 二重構造モデル: 日本人集団の形成に関わる一仮説
- 著者
- 埴原 和郎
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (ISSN:09187960)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.5, pp.455-477, 1994 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 105
- 被引用文献数
- 3 3
この論文は, 沖縄人およびアイヌを含む日本人集団の形成史を単一の仮説で説明する二重構造モデルを提唱するものである。このモデルは次の点を想定する。すなわち, 日本列島の最初の居住者は後期旧石器時代に移動してきた東南アジア系の集団で, 縄文人はその子孫である。弥生時代になって第2の移動の波が北アジアから押し寄せたため, これら2系統の集団は列島内で徐々に混血した。この混血の過程は現在も続いており, 日本人集団の二重構造性は今もなお解消されていない。したがって身体•文化の両面にみられる日本の地域性-たとえば東西日本の差など-は, 混血または文化の混合の程度が地域によって異なるために生じたと説明することができる。またこのモデルは, 日本人の形質•文化にみられるさまざまな現象を説明するのみならず, イヌやハツカネズミなど, 人間以外の動物を対象とする研究結果にも適合する。同時に, このモデルによって日本の本土, 沖縄およびアイヌ系各集団の系統関係も矛盾なく説明することができる。
2 0 0 0 IR 再考・奥州藤原氏四代の遺体
- 著者
- 埴原 和郎
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.11-33, 1996-03
- 被引用文献数
- 1
奥州藤原家四代の遺体(ミイラ)については、一九五〇(昭和二五)年の調査に参加された長谷部言人、鈴木尚、古畑種基氏らによる詳細な報告があるものの、現在もなお疑問のまま残されている問題が多い。筆者は鈴木尚氏の頭骨計測データを借用して新たに種々の統計学的検討を行い、また中尊寺の好意により短時間ながら遺体を直接観察する機会を得たので、その結果を報告して先人の研究の補遺としたい。この論文では次の点に触れる。一、 遺体の固定―基衡と秀衡の遺体がいつの時代かに入れ替わったという疑問について、少なくとも生物学的観点から結論を出すことは困難である。また一部の特徴には寺伝どおりでよいのではないかと思える点もあるので、この問題は今のところ保留としておいた方がよさそうに思える。二、 遺体のミイラ化の問題―遺体は自然にミイラ化したものと考えられるが、ごく簡単な吸湿処置がとられたという可能性が高い。三、 奥州藤原家の出自―藤原家はもともと京都方面の出身という可能性が高い。四、 エミシの人種的系統―古代・中世に奥州に住んでいたエミシは、現代的な意味でのアイヌでもなく和人でもなく、東北地方に残存していた縄文系集団が徐々に"和人化"しつつあった移行段階の集団であったと思われる。藤原家四代に見られる"貴族化"現象―特に鼻部の繊細化(貴族化)が著しいが、顔の輪郭や下顎骨の形態は日本人の一般集団に近いので、近世の徳川将軍や一部の大名に比較すれば貴族化の程度は弱かったと思われる。
2 0 0 0 OA 歯における類モーコ形質群-とくにアイヌの歯について
- 著者
- 埴原 和郎
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.1, pp.3-17, 1970 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 6 13
私はさきに,モーコ系人種の乳歯に共通して,他の人種よりとくに多く現われる形質を分析し,これらをまとめて乳歯の類モーコ形質群とよんだ(埴原,1966).同様な形質群は当然,永久歯にも存在すると予想されるが,現在のところ永久歯では,上顎切歯のシャベル型,下顎第1大臼歯の第6咬頭,第7咬頭ならびにprotostylid がこのような形質群の構成要素として考えられる.同時に,上顎第1大臼歯の CARABELLI 結節は乳歯と同様に Caucasoid に多く出現するので,これはコーカソイド形質群とよばれるべきものと考えられる.この論文では,このような形質群を基礎としてアイヌの歯冠形質の特徴を分析した.とくにシャベル型に関しては従来の肉眼的分類の代りに,切歯の舌側面窩の深さを直接計測する方法を試みた.今回対象としたアイヌの歯は少数ではあるが,家系調査の結果,ほとんど純血と考えてよい集団である.一般にアイヌでは,乳歯,永久歯ともに類モーコ形質群の頻度が高く,とくに日本人(和人)に近い特徴を示す.シャベル型の程度はやや弱いが,白人に比較するとかなり強いといえる.一方,白人に多い CARABELLI結節はアイヌには少なく,この点でもアイヌはモーコ系人種に近い.アイヌの歯に関してはさらに資料を追加しているので,今后は和人との混血集団に重点をおき,また資料数を増加して集団遺伝学的分析を行なう予定である.
1 0 0 0 OA 上顎中切歯のシャベル型に関する家系的研究
- 著者
- 埴原 和郎 増田 哲男 田中 武史
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.1, pp.107-112, 1975 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 6 7
切歯のシャベル型についてはHRDLICKA(1920)が最初に記載していらい,とくにモンゴロイドに高い頻度で現われ,人種特徴を示す形質として注目されてきた。この形質に関する遺伝学的研究も多く,強い遺伝子支配をうけていることは多くの研究者が一致する点である。しかしその遺伝様式については,常染色体性単純優性遺伝説,劣性遺伝説,複対立遺伝子説,polygene説などがあり,研究者の意見はまちまちである。従来,多くの研究者はHRDLICKAの分類にしたがって,シャベル型を発達の程度に応じていくつかのカテゴリーにわけ,これを非連続形質であるかのようにとりあつかってきた。しかし実際には,シャベル型の程度は連続的に変化するものであり,量的形質を非連続形質として分析しようとしたところに無理があったものと思われる。私ども(HANIHARA et al.,1970)は,さきにDAHLBERG and MIKKELSEN (1947)が試みたように,切歯舌側面窩の深さを計測したところ,この形質はほとんど完全に正規分布曲線に一致して連続的に変化することを知った。また同時に,肉眼によるシャベル型の分類がこの計測値の大小ときわめてよく一致することから,舌側面窩の深さをもってシャベル型の発達の程度を代表させることが可能であることがたしかめられー。てのような点から,従来非連続形質としてシャベル型を分類し,その資料から遺伝様式を分析しようとした試みは,理論的に無理であったといえる。今回の研究はこのような観点から,上顎中切歯の舌側面窩の深さを資料として遺伝学的分析を試みたものである。したがって研究の中心はシャベル型の遺伝様式よりも,家族内における遺伝率(heritability)の推定におかれた。まず日本人の一般集団におけるこの計測の平均値は,男性•女性ともに約1mmであり(男女合計の平均値は1.00mm),この値はPima Indian の 1.2mmよりは浅いが,米白人の0.42mmならびに米黒人の0.49mmよりははるかに深く,モンゴロイドの特徴をよく現わしている。また日本人双生児での値もほぼ同様である(Table1)。注目すべきことは,一卵性双生児間の相関係数がきわめて高く,二卵性双生児間ではやや低くなるが,なお高度に有意である点である。このことは,従来いわれていたように,シャベル型に対する遺伝子支配がきわめて強いことを示している。家族内の比較のための資料は日本人41家族よりえられたが,親と子との相関は,母•娘の組合せを除いてきわあて高く,遺伝性の強いことを示している。父•息子,母•息子および父•娘の組合せでは,遺伝率はいずれも0.8をこえる。田中克己(1960)によると,日本人集団では智能の遺伝率は約0.5,身長のそれは0.52-0.67であるというが,これらの形質に比較して,シャベル型の遺伝率はきわめて高いといえる。また試みに,両親間の相関係数を計算すると0に近いので,今回推定した遺伝率の信頼性は高いと考えられる。母•娘間の遺伝率が低い理由はよくわからないが,兄弟間に比して異性同胞間ならびに姉妹間の相関係数がやや低いことと関係しているかもしれない。しかしこの形質が性染色体上の遺伝子に連関をもっているかどうかという問題については,さらに資料を加え,詳細に分析する必要がある。
1 0 0 0 日本人の起源-7-旧石器人の血を受けついだ縄文人
- 著者
- 埴原 和郎
- 出版者
- 朝日新聞社
- 雑誌
- 科学朝日 (ISSN:03684741)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.10, pp.p105-108, 1983-10
1 0 0 0 日本人のルーツ
- 著者
- 埴原 和郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.11, pp.923-931, 1993
- 被引用文献数
- 8
本稿で紹介した日本人集団の二重構造モデルは従来の諸説を比較検討し, また最近の研究成果に基づく統計学的分析によってえられた一つの仮説である. このモデルの要点は次のとおりである.<br>(1) 現代日本人の祖先集団は東南アジア系のいわゆる原モンゴロイドで, 旧石器時代から日本列島に住み, 縄文人を生じた.<br>(2) 弥生時代から8世紀ころにかけて北アジア系の集団が日本列島に渡来し, 大陸の高度な文化をもたらすとともに, 在来の東南アジア系 (縄文系) 集団に強い遺伝的ならびに文化的影響を与えた.<br>(3) 東南・北アジア系の2集団は日本列島内で徐々に混血したが, その過程は現在も進行中で, 日本人は今も heterogeneity, つまり二重構造を保っている.<br>以上の観点からさらに次のことが導かれる.<br>(1) 日本人集団の二重構造性は, 弥生時代以降とくに顕著になった.<br>(2) 弥生時代から現代にかけてみられる日本人集団の地域性は, 上記2系統の混血の割合, ならびに文化的影響の程度が地域によって異なるために生じた. 身体形質や文化における東・西日本の差, 遺伝的勾配なども北アジア系 (渡来系) 集団の影響の大小によるところが大きいと思われる.<br>(3) アイヌと沖縄系集団の間の強い類似性は, 両者とも東南アジア系集団を祖先とし, しかも北アジア系集団の影響が本土集団に比較してきわめて少なかったという共通要因による. 換言すれば, 弥生時代以降著しく変化したのは本土集団であった.<br>(4) 古代から中世にかけてエミシ, ハヤトなどと呼ばれた集団は, 本土集団とアイヌ・沖縄系集団が今日のように分離する前の段階にあったもので, その中間的形質をもっていたと考えられる.
1 0 0 0 人類の進化史 : 20世紀の総括
1 0 0 0 OA 縄文時代人の顎顔面形態
- 著者
- 塩野 幸一 伊藤 学而 犬塚 勝昭 埴原 和郎
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.3, pp.259-268, 1982-07-15 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 5 3
多くの歯科疾患に共通する病因として,歯と顎骨の大きさの不調和(discrepancy)の問題があることが INOUE(1980)によって指摘されている。この discrepancy の頻度は,HANIHARAetal.(1980)によれば,後期縄文時代人では8.9%こ過ぎなかったが,中世時代人で32.0%と増加し,現代人にいたっては63.1%の高率を示すという。ITO(1980)は日本人古人骨を対象として個体における discrepancy の大きさを計測し,その平均値が後期縄文時代人では+7.7mm であったものが,現代人においては-2.6mm となっていることを示し,また(+)側から(-)側へうつった時期は鎌倉時代以前であるとしている。Discrepancy はヒトの咬合の小進化の表現と考えられ,具体的には顎骨の退化が歯のそれよりも先行することによると考えられている。そのため顎顔面形態の変化の経過を明らかにすることが,discrepancy の成立と増大の過程を知るためには特に重要である。このような観点から KAMEGAI(1980)は,中世時代人の顎顔面形態の計測を行い,この時代の上下顎骨が現代人におけるよりも大きかったことを報告している。本研究は,discrepancy の増大してきた過程を知るために,顎顔面の時代的な推移を調査したものの一部であって,とくに後期縄文時代に関するものである。資料は,東京大学総合研究資料館所蔵の後期縄文時代人頭骨327体のうち,比較的保存状態がよく,生前の咬合状態の再現が可能な16体を使用した。これを歯科矯正学領域で用いられている側貌頭部X線規格写真計測法により分析し,KAMEGAI etal.(1980)による鎌倉および室町時代人と,SEINo et al.(1980)による現代人についての結果と比較した。顔面頭蓋の大きさ,上顎骨の前後径,上下顎骨の前後的位置には後期縄文時代人と現代人との間にほとんど差がなかった。しかし,顎骨骨体部の変化が著しくないにもかかわらず,現代人においては歯槽基底部の長径の短縮が認められた。後期縄文時代人の下顎骨は現代人に比較すると非常によく発達していて,とくに下顎枝,下顎体は現代人より大きく,また顎角も現代人より小さかった。このことは,後期縄文時代では咀嚼筋の機能が大であったことを示唆するものと考えられ,逆に,現代人における下顎骨の縮小は,食生態の変化に伴う咀嚼機能の低下によるものと思われる。上下顎前歯については後期縄文時代人では鎌倉時代人や現代人と比べて著しく直立しており,一方,現代人では著明な唇側傾斜が認められた。このことは上下顎歯槽基底部の前後的な縮小と関連するものと思われる。結論的には後期縄文時代の,まだあまり退化の進んでいない顎顔面形態は,頻度8.9%,平均値+7.7mm という discrepancy の小さかったことを表す値とよく一致するものと思われる。
1 0 0 0 墓に副葬された石鍛に関する統計学的検討
- 著者
- 埴原 和郎 岡村 道雄
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.2, pp.137-143, 1981
この研究は,墓壙内とそれ以外の場所で発見された石鏃の特徴を統計学的に分析し,副葬された石鏃が特別に製作されたものかどうかを検討したものである。<br>分析のために使用した石鏃は,北海道上磯郡木古内町•縄文時代晩期札苅(さつかり)遺跡より出土したもので,1つの墓壙より出土したもの57例,墓壙外より出土したもの62例である。<br>各石鏃について6種の計測を行ない,それらの平均値の差を検定したところ,全長および先端長以外では有意の差は認められなかった。このことから,墓壙内外の石鏃が同一母集団に属すること,ならびに墓壙外のものには,使用によって先端が破損したものや再加工されたものが含まれるために,全長ならびに先端長が短くなったことを示すものと考えられる。<br>次に各計測値の分散の差を検定したところ,墓壙内の分散は墓壙外の分散より有意に小さいことが明らかとなった。この結果は,墓壙に副葬された石壙が,何らかの基準に基づいて人為的に選択されたことを反映していると考えられる。<br>以上のことから,副葬された石壙は1)日常使用品のなかから未使用品,又は比較的新しいもので,しかも大きさならびに形態が比較的よく揃うように選択されたものか,2)副葬用として特別に製作あるいは形状がととのえられたものか,あるいは,3)その混合物から構成されていることが推測された。
1 0 0 0 骨を読む : ある人類学者の体験
1 0 0 0 OA 判別函數による日本人長骨の性別判定法
- 著者
- 埴原 和郎
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.187-196, 1958-08-30 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 27 30
Sexual diagnosis of skeleton is a very important problem in the held of anthropology as well as in that of legal medicine. We have a great many methods for this purpose, but there are few of them that express our satis-faction as far as objectivity, simplicity and correctness are concerned. Considering all of these points of view, it may be affirmed, at least in the present state, that the best way is synthetic estimation by multiple measurements.
1 0 0 0 OA 再考・奥州藤原氏四代の遺体
- 著者
- 埴原 和郎
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.11-33, 1996-03-31 (Released:2016-06-01)
奥州藤原家四代の遺体(ミイラ)については、一九五〇(昭和二五)年の調査に参加された長谷部言人、鈴木尚、古畑種基氏らによる詳細な報告があるものの、現在もなお疑問のまま残されている問題が多い。 筆者は鈴木尚氏の頭骨計測データを借用して新たに種々の統計学的検討を行い、また中尊寺の好意により短時間ながら遺体を直接観察する機会を得たので、その結果を報告して先人の研究の補遺としたい。この論文では次の点に触れる。 一、 遺体の固定―基衡と秀衡の遺体がいつの時代かに入れ替わったという疑問について、少なくとも生物学的観点から結論を出すことは困難である。また一部の特徴には寺伝どおりでよいのではないかと思える点もあるので、この問題は今のところ保留としておいた方がよさそうに思える。 二、 遺体のミイラ化の問題―遺体は自然にミイラ化したものと考えられるが、ごく簡単な吸湿処置がとられたという可能性が高い。 三、 奥州藤原家の出自―藤原家はもともと京都方面の出身という可能性が高い。 四、 エミシの人種的系統―古代・中世に奥州に住んでいたエミシは、現代的な意味でのアイヌでもなく和人でもなく、東北地方に残存していた縄文系集団が徐々に”和人化”しつつあった移行段階の集団であったと思われる。 藤原家四代に見られる”貴族化”現象―特に鼻部の繊細化(貴族化)が著しいが、顔の輪郭や下顎骨の形態は日本人の一般集団に近いので、近世の徳川将軍や一部の大名に比較すれば貴族化の程度は弱かったと思われる。
1 0 0 0 IR 再考・奥州藤原氏四代の遺体
- 著者
- 埴原 和郎
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.11-33, 1996-03-31
奥州藤原家四代の遺体(ミイラ)については、一九五〇(昭和二五)年の調査に参加された長谷部言人、鈴木尚、古畑種基氏らによる詳細な報告があるものの、現在もなお疑問のまま残されている問題が多い。 筆者は鈴木尚氏の頭骨計測データを借用して新たに種々の統計学的検討を行い、また中尊寺の好意により短時間ながら遺体を直接観察する機会を得たので、その結果を報告して先人の研究の補遺としたい。この論文では次の点に触れる。一、 遺体の固定―基衡と秀衡の遺体がいつの時代かに入れ替わったという疑問について、少なくとも生物学的観点から結論を出すことは困難である。また一部の特徴には寺伝どおりでよいのではないかと思える点もあるので、この問題は今のところ保留としておいた方がよさそうに思える。二、 遺体のミイラ化の問題―遺体は自然にミイラ化したものと考えられるが、ごく簡単な吸湿処置がとられたという可能性が高い。三、 奥州藤原家の出自―藤原家はもともと京都方面の出身という可能性が高い。四、 エミシの人種的系統―古代・中世に奥州に住んでいたエミシは、現代的な意味でのアイヌでもなく和人でもなく、東北地方に残存していた縄文系集団が徐々に"和人化"しつつあった移行段階の集団であったと思われる。藤原家四代に見られる"貴族化"現象―特に鼻部の繊細化(貴族化)が著しいが、顔の輪郭や下顎骨の形態は日本人の一般集団に近いので、近世の徳川将軍や一部の大名に比較すれば貴族化の程度は弱かったと思われる。
1 0 0 0 動物と文明
- 著者
- 河合雅雄 埴原和郎編
- 出版者
- 朝倉書店
- 巻号頁・発行日
- 1995
1 0 0 0 人類の食生活と咀嚼器官の退化に関する研究
昭和60年度より3年間にわたる研究を通じて, 人類の食生活と咀嚼器官の退化に関する, 現代人および古人骨についての膨大な資料を蓄積した. これらについての一次データと基礎統計については7冊の資料集としてまとめた. ここでは3年間にわたる研究結果の概要を示すが, 収集した資料の量が多いため, 今後さらに解析作業を継続し, より高次の, 詳細な結論に到達したい. 現在までに得られた主な結論は次の通りである.1.咀嚼杆能量は節電位の積分値として表現することが可能であり, 一般集団の調査のための実用的な方法として活用することができる.2.一般集団におけるスクリーニングに際しては, チューインガム法による咀嚼能力の測定が可能であり, そのための実用的な手法を開発した.3.沖縄県宮古地方で7地区の食料品の流通調査を行ったところ, この地方では現在食生活の都市化がきわめて急速に進行しつつあり, すでに全島にわたる均一化が進んでいることが知られた.4.個人群の解析により, 繊維性食品の摂取や咀嚼杆能量が咀嚼器官の退化と発達の低下に重大な影響を与えていることが確認された.5.地区世代別の群についての解析では, 骨格型要因, 咀嚼杆能量, 偏食, 繊維性食品, 流し込み食事などが咀嚼器官の発達の低下に強く関連していることが知られた.6.古人骨の調査では, 北海道, サハリンなどに抜歯風習があったことが知られた. このことと関連して, 古人骨調査が咀嚼器官の退化や歯科疾患の研究のみではなく, 文化と形質との相互関係を知るためにも有効であることが知られた.7.今後の方向として時代的, 民族学的研究, 臨床的, 保健学的研究, 文化と形質の相互関係などが示唆された.