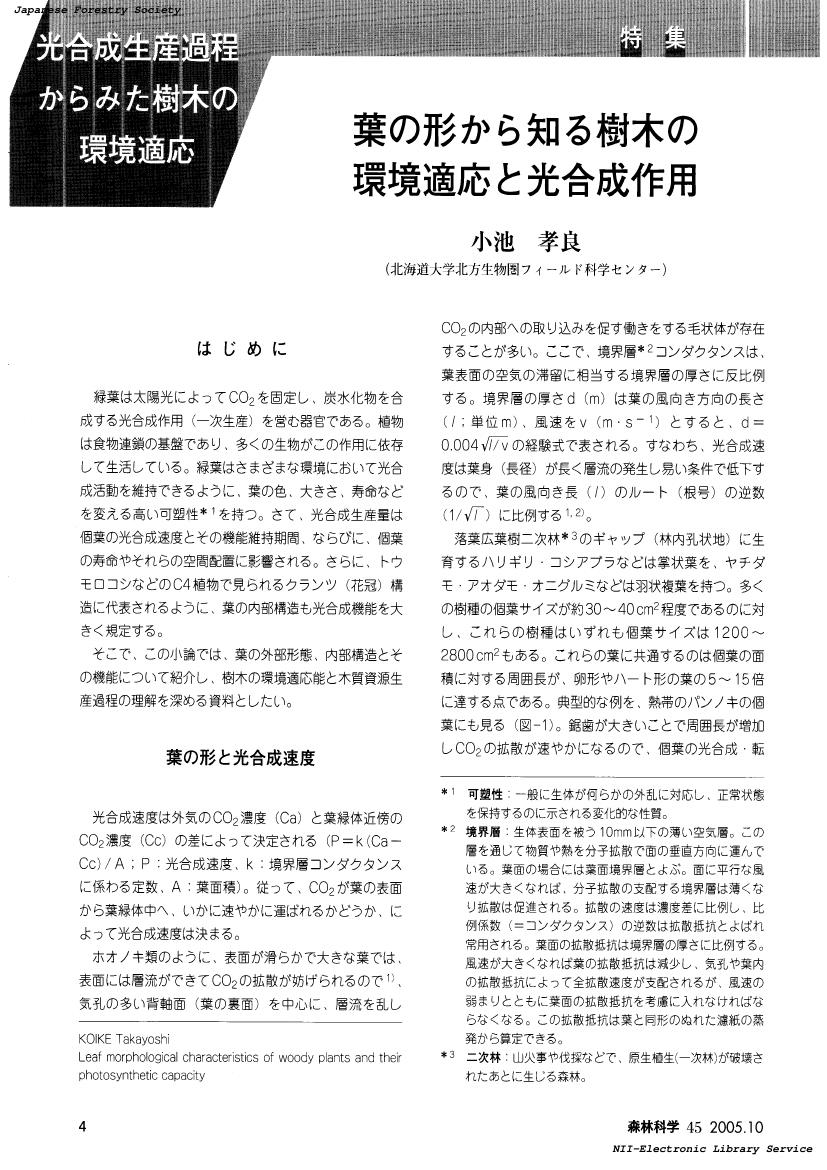2 0 0 0 森林樹木・林冠におけるガス交換
光合成速度のピークは6月下旬で8-16umol・m^<-2>s^<-1>低下は樹種に特徴的。CO2付加では針葉樹材の細胞内腔が増加した。成熟林の1998〜2000年の現存量成長量は0.44、0.60、0.48tC・ha^<-1>yr^<-1>であった。総胸高断面積は32322.8m^2、平均胸高断面積は14.4m^2・ha^<-1>であった。総現存量は59626.9tC、平均現存量は26.6tC・ha^<-1>であった。1999〜2001年の平均NEPは258 gC m^<-2> y^<-1>土壌から大気へ放出される炭素フラックスは平均580 gC m^<-2> y^<-1>でNEPの二倍以上を示した。GEPは838 gC m^<-2> y^<-1>でありGEPに占めるNEPの割合はおよそ30%であった。幹呼吸量は土壌呼吸速度の11〜20%に相当した。GEPの算出に幹呼吸を入れると929 gC m^<-2> y^<-1>となり、樹木葉(含枝呼吸)の総光合成速度に相当した。リタートラップによると土壌還元量は三年間平均で118 gC m^<-2> y^<-1>であり、GEP(929 gC m^<-2> y^<-1>)の約13%であった。枯死による炭素還元量は79 gC m^<-2> y^<-1>であった。地上から地下部への炭素転流量は549 gC m^<-2> y^<-1>であった。植生から土壌へ流入する炭素フラックスは533 gC m^<-2> y^<-1>であった。GEPの約57%の炭素が根系を経て土壌へと供給された。河川への炭素放出は溶存有機炭素(DOC)、溶存無機炭素(DIC)、粒状有機炭素(POC)に大別される。全溶存炭素濃度濃度は4.1±1.8 gC m^<-2> y^<-1>で、DICの占める割合は約67%でありDOCとPOCは同程度で、流域からの炭素流出量はNEPの1.6%で約254 gC m^<-2> y^<-1>炭素が蓄積された。このうち108 gC m^<-2> y^<-1>(43%)が植生に146 gC m^<-2> y^<-1>(57%)が土壌へ蓄積された。
1 0 0 0 OA 大気汚染が植物—昆虫間のコミュニケーションを阻害する ─植物由来揮発性物質の役割─
広葉樹の花成は花成ホルモンをコードする遺伝子(<i>FT</i>)が葉で発現することで誘導される。しかし開花年の不規則な広葉樹における<i>FT</i></i>遺伝子発現の年変動については、その発現制御が日長等の即時的な環境シグナルでは説明できず、過去の環境刺激がゲノムに記録され、遺伝子に対してエピジェネティックに発現制御していると考えられた。本報告では、ブナの<i>FT</i>遺伝子の塩基配列の特徴を調べ、DNAメチル化の潜在的な可能性を検討した。またDNAメチル化率を調べ、<i>FT</i>遺伝子のDNAメチル化を介したエピジェネティック制御の可能性を検討した。ブナの<i>FT</i>遺伝子のTATA配列はシトシン塩基を含まず、RNAポリメラーゼ結合におけるDNAメチル化の制御はないと考えられた。日長誘導型の転写因子(CO)の結合が推定されるcis配列は、連年開花型のポプラ、オレンジ、リンゴ、ブドウ、ユーカリに比べてブナでは数多くのシトシンを含んだ。よってブナの<i>FT</i>遺伝子は連年開花型の樹種に比べてDNAメチル化による発現制御の可能性が潜在的に大きいと考えられ、ブナの花成周期の不規性と関連が示唆された。発表ではDNAメチル化率についても報告する予定である。
1 0 0 0 OA 葉の形から知る樹木の環境適応と光合成作用
- 著者
- 小池 孝良
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 森林科学 (ISSN:09171908)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.4-10, 2005-10-01 (Released:2017-07-26)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA カラマツ針葉の光合成活性と分光反射指標の関係
- 著者
- 中路 達郎 武田 知己 向井 譲 小池 孝良 小熊 宏之 藤沼 康実
- 出版者
- 一般社団法人日本森林学会
- 雑誌
- 日本林學會誌 (ISSN:0021485X)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.3, pp.205-213, 2003-08-16
- 被引用文献数
- 3
4年生ニホンカラマツ(Larix kaempferi Sarg.)植林地において,夏季の葉群の分光反射率と,純光合成速度,クロロフィル蛍光および葉内色素の日変化を同時に観測し,葉内色素量や光合成活性と分光反射指標(NDVIおよびPRI)の関係を検討した。日変動を示したNDVIとPRIはともに,葉内のクロロフィル濃度や総カロテノイド濃度と有意な相関関係になかった。NDVIは,純光合成速度との間には正の相関が認められたが,弱光条件下では,その関係にばらつきが生じた。PRIはキサントフィルサイクルの酸化還元状態を反映し,光合成における光利用効率と光化学系II量子収率の日変動との間に正の相関関係にあった。光合成活性との間の相関係数は,NDVIよりもPRIで高い値が得られた。以上の結果より,カラマツの光合成の日変化に注目した場合,リモートセンシングによって得られるPRIは,光合成の光利用効率を評価する指標として有効であることが明らかになった。
- 著者
- 米倉 哲志 本田 雪絵 Oksanen Elina 吉留 雅俊 渡邊 誠 船田 良 小池 孝良 伊豆田 猛
- 出版者
- 公益社団法人大気環境学会
- 雑誌
- 大気環境学会誌 (ISSN:13414178)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.6, pp.333-351, 2001-11-10
- 被引用文献数
- 3
3年生のブナ(Fagus crenata Blume)苗のガス交換速度, 葉の水ポテンシャル, 光合成系IIの最大光量子収率(F_v/F_m), クロロフィル含量, 葉の微細構造および年輪幅に対するオゾンと水ストレスの単独および複合影響を調べた。自然光型ファイトトロン内に浄化空気を導入した浄化区と60nmol・mol^<-1>のオゾンを毎日7時間(11 : 00〜18 : 00)にわたって導入したオゾン区を設け, 各ガス処理区において, 3日毎に250mL灌水した土壌湿潤区と175mL灌水した水ストレス区を設定した。これらの4処理区において, ブナ苗を156日間(1999年5月10日〜10月12日)にわたって育成した。水ストレス処理によって, 葉の水ポテンシャルが7月以降に有意に低下し, ブナ苗の葉における純光合成速度(A_<350>), 気孔コンダクタンスおよび蒸散速度が8月以降に有意に低下した。また, 葉緑体内のプラスト顆粒が水ストレス処理によって有意に大きくなった。オゾン処理は, ブナ苗のA_<350>, CO_2固定効率, 最大純光合成速度, F_v/F_mおよび年輪幅を有意に低下させた。このオゾンによるA_<350>の低下は, まずRuBPカルボキシラーゼ/オキシゲナーゼ(Rubisco)含量の低下によって引き起こされ, その後はRubisco含量の低下と共に, RuBPの再生能力や光化学系活性の低下によると考えられた。また, 葉緑体内のプラスト顆粒がオゾン処理によって有意に大きくなったが, デンプン粒は有意に小さくなった。葉のガス交換速度, 葉の微細構造および年輪幅においてオゾンと水ストレスの有意な交互効果は認められなかったが, 両ストレスは相加的に作用し, 純光合成速度や年輪幅を著しく低下させた。
1 0 0 0 森林生態系での降雨に伴う溶存元素の動態と渓流水質形成に関する研究
本研究は大きく次の3つの課題について調査した。1. 降水の移動に伴う溶存元素の垂直的変化森林にインプットされた林外雨は樹冠に遮断されるために、土壌へ到達する水量は林外雨量の80%に減少し、水質も大きく変化することを、スギ・ヒノキの壮齢林、ミズナラおよびコナラの優占する落葉広葉樹林で調査した。また、下層植生による影響も大きいことを明らかにした。樹冠を通過することによる濃度増加の要因を樹体に付着した物質からの(乾性沈着)の洗脱と樹体からの溶脱の割合から解析した。2. 土壌水の水質形成土壌系での水質変化を明らかにするため、イオン交換樹脂を用いて、水溶性塩基の移動量を調査した。また、土壌中の窒素無機化が土壌水質に及ぼす影響を調査した。3. 渓流の水質形成渓流の水質形成のメカニズムを明らかにするため、枝打ちや間伐が渓流水の水質形成に及ぼす影響を調査した。また、降水量と渓流水の水質の関係を調査した。森林生態系での主に流出経路としての渓流水質は、土壌層および母材を通過する過程で、溶存物質の吸着や溶出によって物理化学的な平衡状態になる。森林は降雨量の変化にかかわらず水質を一定に保つ機能があることを明らかにした。
冷温帯葉落広葉樹の光合成生産機能を,森林を構成する高木の機能を樹冠レベルで評価するとともに,ギャップ更新稚樹や低木層構成樹種の光合成特性を基礎に考察した。樹冠部の光合成特性は林冠層をやや越えた高さ24mの樹冠観測タワーを用いて測定した。上層木の開葉と共に林床へ到達する光量は減少し,落葉とともに増加した。また,CO_2濃度の垂直変化は,風のない日中に樹冠部位では約320ppmまで低下し,夕方には林床付近で約560ppmに達した。高木層の開葉は雪解けの約1週間後から始まり樹冠基部から先端に向かって進行した。シラカンバやケヤマハンノキなどの散孔材樹種の開葉が早く,ハリギリやヤチダモなどの環孔材では約2週間遅かった。初夏には全ての樹種の樹冠部位での光合成速度は高かったが,真夏には樹冠のやや内部に位置する葉の光合成速度が最高であった。落葉が始まる初秋には先駆種であるシラカンバとケヤマハンノキの光合成速度は高かったが,全体としては樹冠部位での光合成速度に樹種間の差はなかった。樹冠下部の葉では集光機能を代表するクロロフィルb量が多く,また,窒素のクロロフィルへの分配量も多かった。林床では上層木の葉が展開して林冠が閉鎖する前に葉を展開し終える樹種や,上層木が落葉しても葉を保持し降霜まで緑葉を維持する樹種が存在した。林床に生育する稚樹では,光飽和での光合成速度(最大光合成速度)は大きな年変動を示した。この原因として春先の乾燥により厚く小さな葉が形成されることが考えられ,葉内部でのCO_2拡散抵抗が最大光合成速度を律速することが示唆された。窒素は最大光合成速度と高い正の相関を持つことから,非破壊で同一葉の機能を推定できる窒素計測器を導入することによって樹冠全体の光合成生産を非破壊で推定できる。
1 0 0 0 OA 北方森林生態系における窒素ミッシングリングの完全解明と窒素動態の評価
寒冷地の森林帯では窒素供給源が不明である。この「窒素ミッシングリンク」と呼ばれる「謎」を解明するため,東シベリア・永久凍土帯のグイマツ林床と北欧森林限界帯のスプールス林あるいはカンパ林で現地調査をおこない,土壌が持つ窒素固定能を探った。現地土壌微生物群集は土壌環境を反映した条件下で強いアセチレン還元を示した。16S rDNAを標的としたDGGE菌相解析では,Clostridium属細菌およびDugnella属細菌(γ-Proteobacteria綱)の活動が示唆され,植生によって主要な機能性菌相が大きく異なった。森林限界付近の森林土壌ではアセチレン還元力が小さく,逆に森林のない亜北極ツンドラ土壌で高いことが分かった。森林限界に近い北方林では,生態系全体の物質循環スケールが土壌単生窒素固定細菌による特徴的アセチレン還元能を制御し,ピースや菌根菌を系全体でのより協働的な窒素固定と樹木への効率的窒素供給が行われていることが強く示唆された。