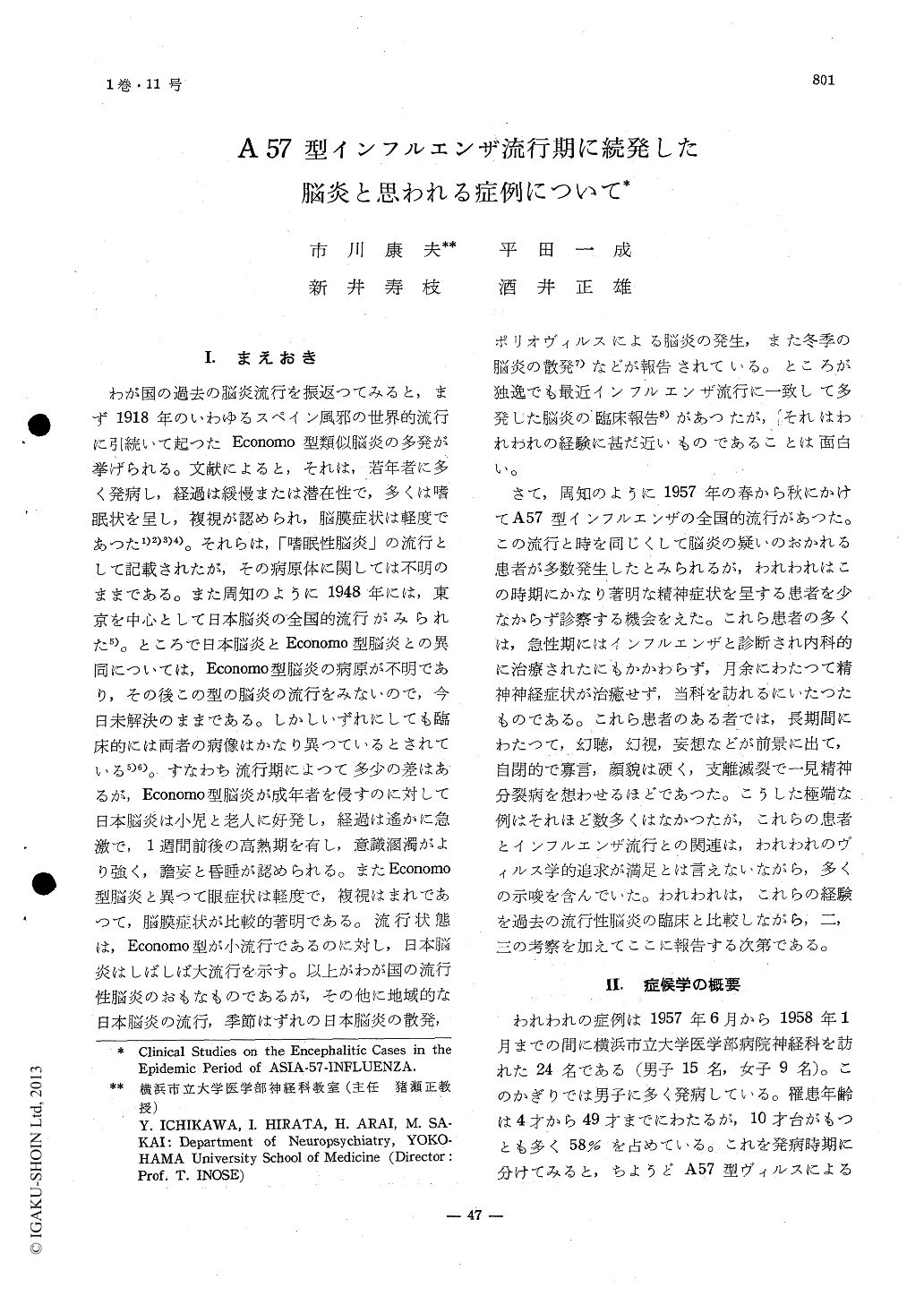4 0 0 0 OA フランス山間地域における牛肉の伝統性とブランド化—「ファングラ・ド・メザン」の事例から—
- 著者
- 市川 康夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.115-126, 2015 (Released:2015-12-29)
- 参考文献数
- 7
本研究の目的は,産地競争下にあるフランス山間地域の畜産において,地理的表示制度の認証を獲得したローカル産品が地域においてどのように生産され,いかにしてその伝統性や品質が保持されているのかを,ファングラ牛のブランド化過程より明らかにすることである.ファングラ牛は,地域の記憶にあったかつての伝統的飼育をあえて現代に導入し,伝統性と固有性を地理的表示範囲と伝統飼育に求めることでブランド化が実現した.極めてローカルな範囲で消費および流通するファングラ牛は,ラベルが乱立する現代において他地域においても示唆的な事例といえる.
3 0 0 0 OA 中山間農業地域における広域的地域営農の存立形態 ——長野県飯島町を事例に——
- 著者
- 市川 康夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.4, pp.324-344, 2011-07-01 (Released:2015-09-28)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 6 5
本稿は,長野県飯島町を事例に農業集落という限られた範囲を超えて設立された広域的地域営農の存立形態を,それを構成する多様な主体の役割やそれら相互の連関の分析から明らかにすることを目的としている.研究対象地域では,農業従事者の高齢化が進み,農外就業機会に恵まれていることから小規模兼業農家が多く存在している.また,中山間農業地域で特徴的な傾斜地水田が卓越していることから,草刈りを中心とした畦畔管理が,飯島町の農業生産性向上を阻害している.この地域では,複数の農業集落から構成される地区を単位に,多様な主体を取り込んだ広域的地域営農が展開している.各主体がそれぞれの役割を担いながら相互に連携していること,さらに小規模兼業農家や高齢者,非農家の労働力を農作業・農地管理作業に積極的に活用することが,広域的地域営農存立の重要な基盤となっている.
Ⅰ.まえおき わが国の過去の脳炎流行を振返つてみると,まず1918年のいわゆるスペイン風邪の世界的流行に引続いて起つたEconomo型類似脳炎の多発が挙げられる。文献によると,それは,若年者に多く発病し,経過は緩慢または潜在性で,多くは嗜眠状を呈し,複視が認められ,脳膜症状は軽度であつた1)2)3)4)。それらは,「嗜眠性脳炎」の流行として記載されたが,その病原体に関しては不明のままである。また周知のように1948年には,東京を中心として日本脳炎の全国的流行がみられた5)。ところで日本脳炎とEconomo型脳炎との異同については,Economo型脳炎の病原が不明であり,その後この型の脳炎の流行をみないので,今日未解決のままである。しかしいずれにしても臨床的には両者の病像はかなり異つているとされている5)6)。すなわち流行期によつて多少の差はあるが,Economo型脳炎が成年者を侵すのに対して日本脳炎は小児と老人に好発し,経過は遙かに急激で,1週間前後の高熱期を有し,意識溷濁がより強く,譫妄と昏睡が認められる。またEconomo型脳炎と異つて眼症状は軽度で,複視はまれであつて,脳膜症状が比較的著明である。流行状態は,Economo型が小流行であるのに対し,日本脳炎はしばしば大流行を示す。以上がわが国の流行性脳炎のおもなものであるが,その他に地域的な日本脳炎の流行,季節はずれの日本脳炎の散発,ポリオヴィルスによる脳炎の発生,また冬季の脳炎の散発7)などが報告されている。ところが独逸でも最近インフルエンザ流行に一致して多発した脳炎の臨床報告8)があつたが,それはわれわれの経験に甚だ近いものであることは面白い。 さて,周知のように1957年の春から秋にかけてA57型インフルエンザの全国的流行があつた。この流行と時を同じくして脳炎の疑いのおかれる患者が多数発生したとみられるが,われわれはこの時期にかなり著明な精神症状を呈する患者を少なからず診察する機会をえた。これら患者の多くは,急性期にはインフルエンザと診断され内科的に治療されたにもかかわらず,月余にわたつて精神神経症状が治癒せず,当科を訪れるにいたつたものである。これら患者のある者では,長期間にわたつて,幻聴,幻視,妄想などが前景に出て,自閉的で寡言,顔貌は硬く,支離滅裂で一見精神分裂病を想わせるほどであつた。こうした極端な例はそれほど数多くはなかつたが,これらの患者とインフルエンザ流行との関連は,われわれのヴィルス学的追求が満足とは言えないながら,多くの示唆を含んでいた。われわれは,これらの経験を過去の流行性脳炎の臨床と比較しながら,二,三の考察を加えてここに報告する次第である。
- 著者
- 市川 康夫
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.101-119, 2017 (Released:2017-04-28)
- 参考文献数
- 73
1990年代以降,経済のグローバル化と世界を取り巻く農業の環境変化のなか,いかに農業・農村の価値を再び見出すかという課題において農業の多面的機能(Multifunctional Agriculture: MFA)は多くの議論を集めてきた。特に,WTO を中心とする貿易自由化交渉において,農業・農村に対する先進諸国の多額の補助金が国際ルールの削減対象となったことで,MFA はヨーロッパを中心とする農業への保護が必要な諸国に政治的に利用されてきた。本研究は,MFA をめぐる研究が蓄積されてきた英仏語圏の議論を中心に,その登場の背景と諸概念,フィールド研究への応用の点から整理し,その政治的文脈と理論的な背景を明確にすることを目的とした。MFA 論は,1990年代に提唱されたポスト生産主義論との関連のなかで発展してきた。特に生産主義/ポスト生産主義という二項対立や,ポスト生産主義論の抱える概念的な限界性は,MFA 論の拡大へと引き継がれ,理論的・概念的な研究を中心に議論が展開されてきた。一方,ポスト生産主義への批判点ともなっていた実証研究の不足は MFA 論でも同様であり,MFA 論の実践と応用をフィールド研究にいかに位置付けるかを,地理学者 Wilson の概念を中心に論じた。MFA 論の応用においては政策との関わりからその農家への影響を精査し,広い地域的フレームで捉えることが重要といえる。また,今後は地理的スケールや国ごとの政治的文脈の差異に着目し,マクロな文脈とミクロな農家との相互関係の解明が求められる。
2 0 0 0 OA 横浜における外国人居留地および中華街の変容
- 著者
- 齋藤 譲司 市川 康夫 山下 清海 Yamashita Kiyomi
- 出版者
- 地理空間学会
- 雑誌
- 地理空間 (ISSN:18829872)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.56-69, 2011
本稿では横浜における外国人居留地と横浜中華街の変容について報告する。横浜は開港から150 年間が経過した。その歴史を鑑みると,外国人居留地の建設に始まり,関東大震災や戦災,港湾機能の強化,華人の集住による中華街の形成など地域が目まぐるしく変化してきた。本稿では横浜開港の経緯について述べた後,外国人居留地の状況と変容,外国人向けの商店施設が集積した元町,最後に居留地の中で華人が集住して形成された横浜中華街について報告する。150 年の歴史の中で横浜の景観は大きく変容し,開港当時の景観や外国人居留地の様子を窺い知ることは難しい。しかし,19 世紀に描かれた絵地図と照らし合わせることで現在の景観と比較することが可能であった。近年では,「歴史を活かしたまちづくり」や「中華街街づくり協議会」が発足し,横浜の外国人居留地は新たな段階に進んでいる。
2 0 0 0 IR 需給チャネルからみた首都圏外縁部中心市街地の商業特性 : 茨城県水海道地域を事例に
1 0 0 0 OA 「大地に帰れ運動」にみるフランス農村のユートピア
- 著者
- 市川 康夫
- 出版者
- The Japan Association of Economic Geography
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.235-254, 2021-12-30 (Released:2022-12-30)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
本研究は,先進国農村で1960年代末より広く展開した「大地に帰れ運動( Back to the Land Movement)」において,農村がいかなる役割や機能を果たしてきたのかを,当事者の生活や意識,運動の展開過程の分析から明らかにすることを目的とした.「大地に帰れ運動」は,1968年の社会運動を契機として,都市や資本主義社会への批判や決別を目標に,1970年代と2000年代以降という「2つの波」を形成してきた.この2つの波の比較から,次のようなことが明らかとなった.まず,「大地に帰れ運動」において,農村という空間は,価値の再定義を行う「実験の場」として機能していた.それは,貨幣や労働,家族観や自然環境の価値を,共同体という社会実験から問い直す過程でもあった.そのなかで,農村は個人を解放する「逃避の場」から,エコロジーの実践とその社会共有の場へと役割を変化させてきた.カウンターカルチャーとしてのコミューン・共同体の背景には,常に批判対象としての主流社会の存在があった.また,「都市」というアンチテーゼに対する「農村」は重要な命題であり,「都市の否定的イメージ」と「理想郷としての農村」の対比が強く意識されていた.「大地に帰れ運動」は,社会への批判とエコロジーの実践をエネルギーに今日まで存続し,そのプロセスのなかから常に新たな価値が生み出され,消費されてきたと結論づけられる.
- 著者
- 市川 康夫
- 出版者
- 地理空間学会
- 雑誌
- 地理空間 (ISSN:18829872)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.185-202, 2014 (Released:2018-04-05)
本研究は,19世紀末の紀行文『旅はロバを連れて』(R. L. スティーブンソン著)に着目し,フランス中央高地におけるランドネとツーリズムの関係を文化的資源とのかかわりから論じたものである。スティーブンソンの道は,フランスランドネ連合(FFR)によるルート整備が契機となり,スティーブンソン組合の結成によって実現した。組合はEUや国,地域からの補助金によって成り立ち,さらに営利を主目的としないことでオルタナティブなツーリズムが形成された。一方,ランドネ旅行者は,文化的資源だけではなくランドネを通じて得られる自己の体験,あるいはイメージに旅の動機を向けていた。まだ見ぬ土地への何かを求める欲求,そしてテロワールを感じる場所としての山村イメージが,セヴェンヌのランドネへと旅行者を駆り立てている。スティーブンソンの道は,ランドネ旅行者と文化,自然,テロワールとの相互作用の過程にあるツーリズムということができよう。
- 著者
- 市川 康夫 中川 秀一 小川G. フロランス
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, 2018
フランス農村は、19世紀初頭から1970 年代までの100年以上に渡った「農村流出(exode rural)」の時代から、人口の地方分散と都市住民の流入による農村の「人口回帰」時代へと転換している。農村流出の契機は産業革命による農業の地位低下と農村手工業の衰退であったが、1980年代以降は、小都市や地方都市の発展、大都市の影響圏拡大によって地方の中小都市周辺部に位置する農村で人口が増加してきた。しかし、全ての農村で人口増がみられるわけではなく、とりわけ雇用力がある都市と近接する農村で人口の増加は顕著に表れる。本稿では、地方都市と近接する農村でも特に人口が増えている村を事例として取り上げ、移住者へのインタビューからフランス農村部における田園回帰の背景とその要因を探ることを目的とする。本調査が対象とするのは,フランスのジュラ山脈の縁辺に位置する山間の静かな農村地帯にあるカンティニ村(Quintigny)である。カンティニ村は、フランス東部フランシュ・コンテ地域圏のジュラ県にあり、ジュラ県庁所在地であるロン・ル・ソニエから約10km、車で20分ほどの距離に位置している。カンティニ村では、フランス全体の農村動向と同じく、19世紀末をピークに一貫して人口が減少してきたが、1980年代前後を境に、周辺地域からの流入によって人口が増加し、1975年に129人であった人口数は、2017年には262人と2倍以上になっている。隣村のレ・エトワール村は、「フランスで最も美しい村」に指定されており、観光客の来訪や移住者も多い。一方で、カンティニ村は目立った観光資源などは持たないが、移住者は静かな環境を求めて移住するものが多いことから、この点に魅力に感じて移り住むケースが多い。<br><br> カンティニ村への移住者は、20~30歳代の若年の子育て世代の流入が多く、自然が多い子育て環境や田園での静かな生活を求め、庭付き一戸建ての取得を目的に村に移住している。カンティニ村内は主たる産業を持っておらず、ワインのシャトーとワイン工場が2件あるがどちらも雇用数は10人程度と多くない。農家戸数も1950年代に26戸あったものが、現在では2戸になり、多くの農地はこれら農家に集約されたほか、移住者の住宅用地となっている。<br>本研究では、2017年8月にカンティニ村の村長に村における住宅開発と移住者受け入れ、コミュニティについて聞き取り調査をし、実際に移住をしてきた15軒の移住世帯に聞き取り調査およびアンケート調査を実施した。移住者には、移住年、家族構成、居住用式、居住経歴、移住の理由等、自由回答を多く含む内容で調査を行なった。<br> カンティニ村における移住者は、1980年代より徐々に増加し、特に2000年代以降に大きく増加している。カンティニ村における移住には2タイプあり、一つは村が用意した移住者用の住宅区画に新しい住宅を建設して移住するタイプ、もう一つは、②空き家となった古い農家建築を移住者が購入し、居住するタイプである。古い農家建築は築200~300年のものが多く、リフォームやリノベーションが必要となる。<br> 農村移住者の多くは、ジュラ県あるいはその周辺地域の出身者であり、知人からの口コミや不動産仲介からの紹介、友人からの勧めをつてにカンティニ村を選択していた。移住者の多くは、小都市ロン・ル・ソニエに職場を持っており、ここから通える範囲で住宅を探しており、かつ十分な広さと静かな環境、美しい自然・農村景観や農村建築を求めて移住を決めている。いずれも土地・住宅は購入であり、賃貸住宅や土地の借入はない。<br> 移住者がカンティニ村を評価する点としては、都市に近接しながらも今だに農村の風情や穏やかな環境、牧草地やワイン畑が広がる豊かな景観があること、美しい歴史地区の農村建築群、安価な住宅価格と広い土地、そして新しい住民を歓迎する村の雰囲気が挙げられている。そして、特に聞かれた点としては、主要な道路から外れてれおり、村内を通り抜ける車がないこと、村内に商店がワインセラーを除いて1件もないことに住民の多くは言及しており、「静寂」と「静けさ」を何よりの評価点として挙げている。また、多種多様な活動にみられるように、「村に活気がある」という点も多く聞かれた。また住民の仕事の多くは時間に余裕のある公務員であり、歴史建築を購入し自らリノヴェーションすることが可能であったこと定着の背景である。
1 0 0 0 OA フランス田園回帰にみる農村移住の展開ー 郊外農村の生活と山村のオルタナティブ農業
- 著者
- 市川 康夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2021年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.53, 2021 (Released:2021-03-29)
本報告では、フランスにおいて農村移住はいつ始まりどのように展開し、その特性はいかなるものなのかを提示したい。そのために、過去の文献や調査資料、公表データからフランス田園回帰の展開を整理し、実際の移住者たちについて都市郊外農村(ジュラ県)、山地農村(オート・ロワール県)での聞き取りからフランス農村移住の生活の実態とその特性をみることにしたい。 フランスの農村移住の展開は以下の「3つの波」に整理されると考える。第1の波は、1968年の五月革命が発端であり、運動に挫折した若者たちは,都市社会や資本主義から逃避し,理想郷を求めて南フランスの山村を目指した。ヒッピー文化に影響を受けていた彼らは,南仏のセヴェンヌ地方を中心に,孤立した農村廃墟や小集落に共同体を組織した。こうした、「反体制文化(カウンター・カルチャー)」としての農村移住によって、300〜500ほどの共同体が乱立し,そこで暮らす若者の総計は冬季におよそ5千〜1万人,夏季には3万〜5万人に上った。これは、「大地へ帰れ」運動と呼ばれ、1970年代にはエコロジー思想や有機農業の拡大とともに一般的な層にも農村移住は拡大した。 第2の波は、1980年代からの「家族による移住」の時代であり、農村移住における大衆化の時代ともいえる。都市化の影響が周辺農村において強くなったことで、郊外の田園化が進み、中流階級の子育て世代や教育水準の高い層が多く移住するようになり、都市にはない農村アメニティを「理想郷」とみなした。それ以外では、経済の停滞や失業率の増加によって、農村へと逃れる層も現れ、移住者の多様化も同時に進展した。 第3の波は、2000年代以降であり,「新たな自給自足経済」を求める人々の出現である。彼らはリベラル運動やラディカルな思想,アルテルモンディアリストやエコロジストであり,「新たな社会運動」に属する人々である。それと同時に、富裕層やベビブーマーの退職移動なども進んでいる。 フランスの田園回帰は全体で一様に進展しているわけではない。農村でも都市近郊農村や観光産業やリゾートに近接する地帯に偏っている。例えば、都市近郊ではパリやリヨンの大都市圏のほか、ブルターニュ地方などが該当する。海辺では、南仏地中海沿岸や大西洋岸のリゾート地域、あるいはアルプス地域の周辺農村も流入者が多い。農村移住は、社会階層によっても特徴が異なり、上級管理職・知的専門職が大都市との近接を重視するのに対し、ブルーカラー層は遠隔地への移住割合が高い。一方、退職後におけるこの傾向は全く逆になり、年収が高いほど遠くへの移住を求める特性を示す。 都市郊外農村として、ジュラ県の村を事例に挙げる。この村では、1970年代から人口回帰が始まり、当時から人口は約2倍にまで回復した。本調査では、1990年代以降の流入者を移住者と定義し、彼らにヒアリングを行った(12組)。その結果以下が明らかになった。移住者の多くは公務員職であり、いずれも同県か近隣の県の出身者である。彼らは、就職や結婚といったライフステージのなかで都市間の転居移動を経て、子どもの誕生や庭付き戸建ての取得を契機に理想の住環境を求めて事例村へと辿り着いている。彼らは、自主リフォームを行うものが多く、古い農村家屋を購入後、週末を利用して家屋や納屋を改修し、数年かけて移住を果たしていた。移住者が評価する農村は、「勤務地との近接性」、「住環境としての静けさ」であり、カンティニ村は若年カップルや子育て世代、戸建て住宅取得を目的とした中流階級の移住という、フランスの現代農村移住の典型をよく表した事例といえる。 山村に定着した移住者の事例として、オーベルニュ地方への就農者たちを取り上げたい。サンプルは少ないが、ライフヒストリーを含むロングインタビューを3組の移住農家に行った。フランスでも保守的なオーベルニュ地方にあって、彼らの就農は容易ではなく、農地の取得や拡大が困難であり、また政策的な援助や就農支援も不足しているなかでの移住と就農を経てきた。彼らに共通しているのは、いずれも大規模農業の正反対として、オルタナティブな農業のあり方を模索している点である。それは換言すれば農薬・化学肥料への対抗や自然栽培、独自の地方品種の採用や山村イメージの付加などを通じた「生産の質」の追求である。とりわけ、有機栽培、互助組織、マルシェ、生計へのツーリズムの導入は彼らにとって重要な意味を有している。彼らは、前述でいう第3の波に属する移住者であり、エコロジーや反グローバル化の思想を背景に有し、中央高地の山村という困難な場所であえてそれを実践することに、意義を見出しているともいえる。
1 0 0 0 土浦市田村地区におけるレンコン生産地域の存立基盤
- 著者
- 渡辺 隼矢 羽田 司 周 宇放 佐藤 壮太 張 楠楠 市川 康夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, 2017
<b>1.研究の背景</b> <br> 健康食品としてレンコンの需要は拡大傾向にある.こうしたレンコンを扱った地理学的研究では,産地形成の要因や農家の経営形態,土地条件とレンコン栽培の関係性が解明されている.しかし,農家の高齢化や離農に伴う農業労働力の不足が深刻化する近年において,レンコン生産地域を対象とした精緻な現地調査は管見の限り見当たらない. そこで本研究では土浦市田村地区を事例に,国内有数のレンコン生産地域である霞ヶ浦湖岸平野において継続するレンコン生産がいかに存立してきたのかを考察した.その際,生産から消費までを体系的にとらえる中で,レンコンの作物特性や農地の貸借関係,レンコンの販売戦略に着目して,レンコン生産地域の実態の把握を試みた.<br> <b>2.研究対象地域</b> <br> 茨城県南部に位置する土浦市はレンコンの生産量が日本一である.その中でも研究対象地域とした田村地区は,土浦市中心部から東へ約4kmに位置し,地区内の霞ヶ浦湖岸平野(沖積低地)には一面の蓮田が広がる.湖岸平野の土壌は主に粒径の細かいシルトや細砂から構成され,特に湖畔に近い低位面は反腐植土を含む柔らかな土壌となっている.この土壌条件はレンコン栽培に適しており,1940年代後半以降のコメからレンコンへの転作を促進する一翼となった.現在,レンコン生産は平野部高位面や谷津にも拡大し,2010年のレンコン栽培面積は127haとなっている.これは当地区内の経営耕地面積のうち87.8%を,田全体面積のうち98.5%を占める.<br><b></b> <b>3.調査結果<br></b> 本研究では,各農家の生産量や必要労働力,経営志向等を反映する指標として蓮田の貸借関係に着目し,当地区の農家を3類型に大別した.1つ目は借地型農家であり,3類型の中で最も経営規模の大きな農家群である.地区内外に蓮田の借地を持ち,当該類型の中でも経営規模が大きい農家は,外国人実習生を含む家族外労働力を導入している.2つ目の類型は自作地型農家である.家族内労働力のみで生産から出荷までの全工程が可能な1ha前後の自作地のみで営農しており,雇用労働力はみられなかった.3つ目の類型は地区内の借地型農家を中心に蓮田を貸与している貸地型農家である.貸地型農家では農業従事者の高齢化および農外就業者の増加による農業労働力の減少を契機として,レンコン生産の規模を縮小していた. <br> 他方,レンコンの流通においてはJA土浦による系統出荷が主な出荷形態となっていた.この系統出荷では東京市場の他,中京市場など東日本の地方都市へも積極的に出荷している.JA土浦にはかつての任意組合を単位とする複数のレンコン部会が存在し,各部会によって重点市場や販売戦略に差異がみられる.田村地区には田村蓮根部会と田村共撰部会との2つの部会が存在するが,前者に所属する農家が大半を占める.田村蓮根部会は,2004年にJA土浦に参画するまでは任意組合であり,現在も任意組合の頃の重点市場への出荷や独自の販売戦略を展開している.また,JA土浦管内のレンコンの洗浄および箱詰め作業を受託し,レンコン生産農家の出荷にかかる作業負担の軽減を目的としたJA土浦れんこんセンターが稼働し,農業労働力が不足している農家で利用が目立つ.JA土浦では系統出荷のほかに,レンコン加工にも積極的な取り組みがみられた.一方,農協を経由しない出荷の動きもみられ,個人や少人数による市場出荷,個人・小売店・飲食店への宅配,直売所の運営といった流通チャネルを駆使した個人出荷も存在する.
1 0 0 0 IR 北茨城市平潟町における漁業地域の構造変容
- 著者
- 市川 康夫 横山 貴史 杉野 弘明 水野 卓磨 橋本 暁子 木村 昌司 田林 明 ICHIKAWA Yasuo YOKOYAMA Takafumi SUGINO Hiroaki MIZUSHlMA Takuma HASHIMOTO Akiko KIMURA Masashi TABAYASHI Akira
- 出版者
- 筑波大学人文地理学・地誌学研究会
- 雑誌
- 地域研究年報 (ISSN:18800254)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.1-11,13-37, 2012
1 0 0 0 OA 中山道を歩くインバウンド・ツーリズム
- 著者
- 市川 康夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2017年度日本地理学会秋季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.100018, 2017 (Released:2017-10-26)
1.インバウンド観光における歩くツーリズム インバウンド・ツーリストの増加と訪日観光の多様化を背景に、日本の非都市部の自然や文化を目的とするインバウンド旅行者が増加している。なかでも観光者が増加している熊野古道や富士山、そして本研究が取り上げる中山道では、「歩く」という行為を通じて景観美や自然、あるいは精神的な体験を得ることがインバウンド・ツーリストに注目されている。これら「歩くツーリズム」における大きな特徴は、ヨーロッパや北米・オーストラリアなど欧米系ツーリストがその多くを占めている点である。ハイキングやランドネなど農山村地域を歩くことが文化的に受容されてきた欧米諸国のツーリストは、訪日観光でも日本独自の自然や文化に触れられる歩くツーリズムを求めるようになってきている。 本研究は、日本のインバウンド観光における歩くツーリズムの先駆的事例ともいえる中山道の文化観光を事例に、欧米系ツーリストの意識に注目しその背景にある観光需要や彼らの動機を明らかにすることを目的とする。 2.中山道を歩くインバウンド・ツーリストの台頭 本研究の対象は、中山道の長野県と岐阜県にまたがる木曽路の峠にあたる馬籠宿〜妻籠宿間にある山間部の街道である。元々、この地域は1980年代前後から欧米ツーリストには知られた存在であったが、ガイドブック「ロンリープラネット日本版」に中山道が上位にランキングされたことを契機に、現在では世界中から訪日者を集めるインバウンド観光地となっている。 インバウンド・ツーリストは名古屋や松本方面から中津川駅へとアクセスし、そこから徒歩をメインに落合宿を経て約8km離れた妻籠宿へと向かう。彼らは宿場町で1〜2泊し、妻籠宿と馬籠宿の間にある約7.3kmの山間街道を歩き馬籠宿へと向かう。この道中では江戸期の石畳の佇まいや峠の集落の街並みのほか、番所跡の茶屋、滝や森林の風情などが見所となっている。 馬籠〜妻籠宿を歩くツーリストは2015年で年間約4万人であり、その約47%が外国人である。特にバカンスシーズンの7〜9月になると外国人の割合は60%を超える。このインバウンド・ツーリストのうち全体の約92%は欧米系、うち全体の60%はヨーロッパからの観光者であり、アジア系は全体の5%と非常に少ない(番所跡でのハイカー調査2013年より)。馬籠宿は島崎藤村の故郷として、妻籠宿は全国に先駆けた集落・街並み保存運動の地として1970年代以降国内を中心に観光者を集めてきたが、両者ともに2000年代以降はその数を大きく減少させてきた。一方、減少する国内観光者と比例して増加してきたのが歩くツーリズムを目的とする欧米系ツーリストであり、2009年に峠を歩く外国人が5848人であったのが2015年には16,371人まで急増している。 4. 欧米系ツーリストが求めるもの 本研究では、観光ホスト側として宿泊施設、中津川市役所観光課、観光協会、妻籠宿の町並み保存会、住民に聞き取り調査を行い、さらにメインの調査として観光ゲストである欧米系ツーリスト55組(80人)にアンケート及び聞き取り調査を行った。観光者に対しては、国籍や観光行動といった基本的情報だけではなく、彼らがこの場所に求める要素をなるべく細かく収集しデータを整理した。その結果、以下なようなことが明らかになってきた。 まず欧米系ツーリストの職業に特徴があり、全体(80人)のうち①弁護士や医師、研究者や教員といった知識的な階層(26人)、そして②デザイナーや建築家、IT技術者などクリエイティブクラスの観光者(16人)が多い。彼らの意識をみると「普通と違う観光」、「典型的なインバウンド・ツーリズムに無いもの」を旅に求めて中山道を来訪していた。また中山道を歩く欧米系ツーリストは「静けさ」や「穏やかさ」、「都会からの逃避(都会と違う場所)」を求めており、彼らが典型的なインバウンド地である日本の都市型観光の喧騒に疲弊し、静かな環境や自然に身を置きたいという欲求を山間部の街道を歩くことへと向けていることがわかる。彼らが街道を歩く観光で高く評価した点をみると、①「山並み」、「木々(森林)」、「川・滝」といった比較的日本人にはありふれた山間部の自然的要素、そして②「棚田(水田)」、「農村景観」、「農村の生活」、「本物の農村(とその体験)」といった日本の農村部で一般的に見られるようないわば「普通の」景観に魅力を見出していた。そしてこれらは移動手段を歩くことに限定することで得られる体験であると多くの観光者は評価をしていた。欧米系ツーリストが過度に観光地化しておらずかつ典型的な訪日観光には無い場所、そして都会に無い静けさや自然を歩くツーリズムに求めたか観光形態が中山道における歩くツーリズムといえる。
- 著者
- 市川 康夫 中川 秀一 小川 G. フロランス
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.258-270, 2019 (Released:2019-07-03)
- 参考文献数
- 17
現在,西ヨーロッパ農村では,都市から農村への人口回帰が進展している.本研究は,フランスの人口増加農村を事例に,農村移住者の田園生活はどのようなものであり,その背景には何があるのかについて,彼らの意識に注目して論じた.カンティニ村の移住者増加は,通勤・通学地としての都市との結びつき,静かな環境,手頃な土地価格,古い農村家屋や景観の美しさが背景にあった.移住者の多くは自主リフォームを好むため,公務員など時間に余裕のある人々であった.彼らは,立地や環境だけではなく,村に活気があることを高く評価していた.カンティニ村は,住民同士の地域内でのコミュニケーションを重視する一方,それを必ずしも強制しない点が特徴といえる.