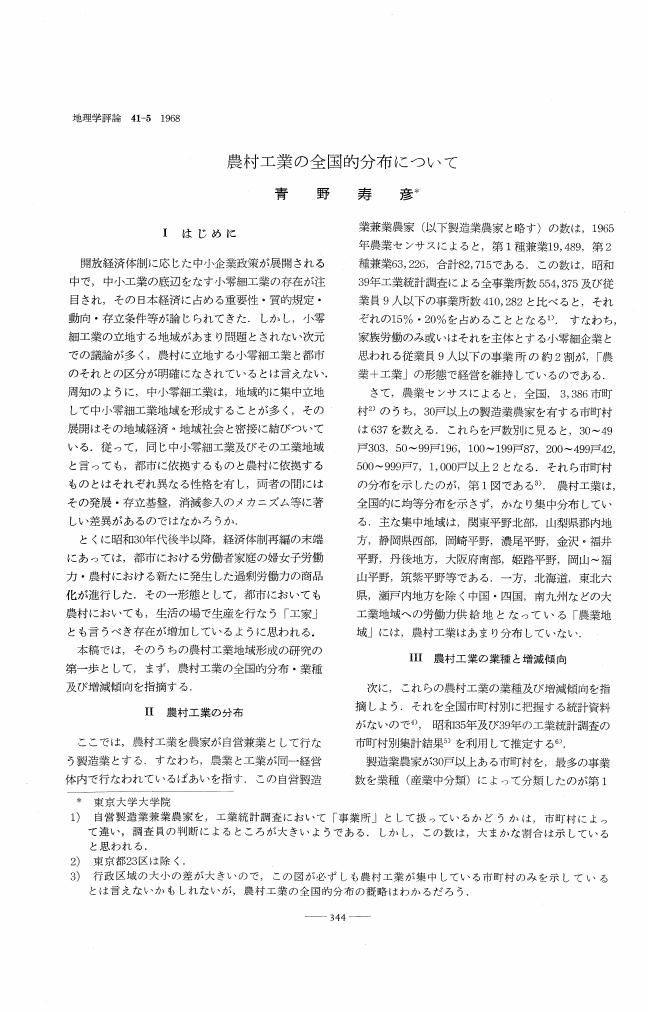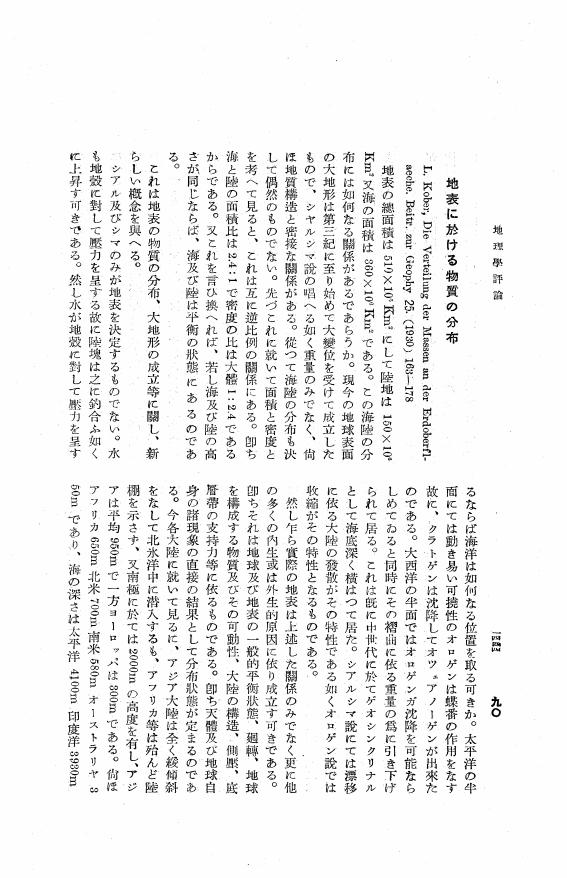1 0 0 0 OA 能登半島邑知地溝
- 著者
- 大塚 彌之助
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.8, pp.645-670, 1934-08-01 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 1
This paper will be published in English in the Bull. Earthquake Research Institute, Imp. Univ. Tokyo, at no distant date.
1 0 0 0 OA 大佐渡沿岸の海岸段丘
- 著者
- 太田 陽子
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.226-242, 1964-05-01 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 5 4
大佐渡沿岸には数段の海岸段丘が発達しており,それらは高度,連続性などから第1段丘 (160~220m), 第2段丘 (80~140m), 第3段丘 (60~120m), 第4段丘 (35~70m), 第5段丘 (25~40m) および第6段丘 (5~8m) の6段に大別される.とくに,二見半島から大佐渡西岸には発達が顕著であるが,東岸にはきわめて断片的に小平坦面として分布するにすぎない.これらの中で第3, 第4段丘はほぼ全域に巾広く,また第6段丘は狭いが島全体をとりまいて分布する.段丘面の性質は地域によりかなり異なっている.すなわち,西岸ではおもに外洋における海蝕作用による海成段丘として,真野湾沿岸ではやや内湾的な場所で多少堆積作用も働いた結果の海成段丘として形成された.東岸では,急崖下の小規模なおし出し状隆起扇状地の性格をもつ所が多い.国中平野では,第2, 第3段丘は金北山下の斜面を流下する諸河川によって堆積された隆起扇状地であるが,第4段丘は,比較的厚い浅海堆積層の堆積面として形成された.なお第6段丘は全地域において海成段丘であり,温暖な fauna を含む厚い海成冲積層からなる国中平野の冲積面に続いており,日本各地で認められている冲積世初期の海進に基く地形であろう.第4段丘は冲積世海進前の海面低下期に先立つ比較的明瞭な海進期に形成されたものと思われる. 段丘面の性質の地域的差異を生じた原因は,西が緩やかで東が急斜面をもっという大佐渡の非対称な地形と,西側が外洋に面し,国中平野側が内湾的であったというような,後背地の地形および前面の海況などがおもなものであったと考えられる.このように,背後の地形や海況に著しい差異がある所では,岩石的制約は,火山岩地域などのような抵抗性の大きい岩石地域における段丘面上の stack の存在などとして現われてはいるが,段丘の形成には二次的な意味をもつにすぎないと思われる. 段丘の高度は,東西方向では大きな差異はみられないが,南北方向では島の両端から中央部に向って高くなり,しかも古い段丘ほどその傾向が著しい.おそらく第1段丘形成時(あるいはその前から)から島の中央部に軸をもつ撓曲的性格の上昇運動がつづき,その間に全域にわたる海面変化が繰返されて現在のような段丘の配列をみたのであろう.地殻運動と海面変化との関係についてはまだわからないが,少なくとも段丘面の高度の地域的変化を生じた原因は上述の示差的な地殼運動であるらしい.
1 0 0 0 OA 大都市郊外地域における高齢者転入移動の特性 埼玉県所沢市の事例
- 著者
- 平井 誠
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.5, pp.289-309, 1999-05-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 3 3
大都市郊外地域における高齢者の転入移動の特性を明らかにするために,本稿は東京の郊外地域に位置する埼玉県所沢市への高齢者転入移動を移動者個人のレベルから分析し,移動の類型および移動の要因について考察を行つた.アンケート調査および聞取り調査によって得られた112件の高齢者転入移動の事例を検討した結果,以下の点が明らかとなった.高齢者転入移動を随伴移動者別に検討すると,移動者の属性,移動理由,移動パターンに差異が認められた。また,高齢者が主体的に行う「同居志向型」,「近居志向型」および子供世帯に随伴して行う「随伴型」という三つの移動の類型が見出だされた.「同居志向型」は70歳以上の女性に顕著であり,単独で子供世帯の下へ移動する.「近居志向型」は60歳代の比較的若い時期に夫婦で子供世帯の居住地の近隣に移動していた.三つの類型とも,とくに移動先の決定に際して子供世帯の影響を強く受けていた.親である高齢者とその子供の関係が,大都市郊外地域への高齢者転入移動と密接に関係していると結論される.
1 0 0 0 OA 気候地域の設定-その思潮と問題
- 著者
- 矢澤 大二
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.6, pp.357-374, 1980-06-01 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 154
- 被引用文献数
- 1 1
Many theories of climatic classification and of division of climatic regions of the world have been presented in general books on climatology and on physical geography. However, few reports trace the current of thoughts synthetically from the very root of studies up to the present. In the present paper the author has an object to follow the development of thoughts successively and point out how the thoughts of significance had been exploited and developed further. This paper consists of three parts ; namely, an examination of effective methods, a discussion of the problem of humid and arid boundary, and an examination of genetic methods. Effective methods since the 1840's are examined. Some earlier works by Hult, Supan, Köppen, de Martonne, Philipsson etc. were followed by several modern works by Blair, Trewartha, Creutzburg Troll, etc. Special attention is paid to make clear the current of thoughts, regarding representative standards for clamatic classification and for objective divisions into climatic regions. Then, the problem of the boundary between humid and arid regions are reviewed and examined. The concept of effective humidity originated in Linssers's earlier work has been developed by various successors, in order to make clear the water budget or the limit of arid region, indirectly. Physiogeographic consideration by A. Penck was a pioneer work of importance. After genealogic consideration of various methods for evaluating aridity of climate (indices such as Regenfaktor, indice d'aridité, quotient pluviothermique, precipitation effectiveness etc.) and their applicability to distinguish humid and arid climates, the author examines concisely the approach to the rational classification of climate introduced by Thornthwaite, and developed by his successors. It is also pointed out that there are two currents of thoughts regarding the main division of climatic regions of the world. One is to divide, except for the polar region, the world into humid and arid regions, then to subdivide the former into thermal zones and the latter into regions depending upon the degree of aridity. The other is, on the contrary, to divide the world into several thermal zones, and then to subdivide them into subregions, based upon the degree of aridity or humidity of climate. The standpoint of these approachs, therefore, are different to each other. Finally, genetic methods of classification of climate and their applicability to the presentation of climatic regions are examined. The root of such a current could be found in the early works on wind systems or windregions of the world introduced by Mühry, Wojeikof, Köppen, Hettner etc. during the latter half of the last century and the first half of this
1 0 0 0 OA 長野県蓼科の観光地化による入会林野利用の変容
- 著者
- 池 俊介
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.131-153, 1986-03-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 8 7
わが国にかつて広範に存在した入会林野は,主に明治以来の政府の入会林野解体政策によって,その多くが解体していった.しかし現在でも,近代的所有形態をとりつつも,実質的に入会林野としての性格を維持している例がかなり存在している.本稿では,財産区という所有形態で旧入会林野を維持し,観光事業に利用している二つの集落をとりあげ,旧入会林野の有効利用の実態を明らかにするとともに,財産区をめぐる諸問題についても考察した. その結果, (1) 1960年代からの白樺湖・蓼科高原の著しい観光地化の中で,財産区は土地貸付・直営観光事業によって莫大な収益を得,財産区民の生活水準の向上に利用されていること, (2) 観光地化による財産区の事務量増加の中で,人事面において問題を生じていること, (3) 財産区制度の矛盾により,財産管理面で観光地化による新来住民の存在が問題化していること, (4) 財産区収益の増大により,市当局の行政面での圧力が増す可能性が生じてきたこと,などが明らかとなった.
1 0 0 0 OA 農村工業の全国的分布について
- 著者
- 青野 寿彦
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.5, pp.344-349, 1968-05-01 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA ドイツの国境
- 著者
- 浮田 典良
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.1-13, 1994-01-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 37
Seit der Eröffnung der Berliner Mauer im November 1989 und der Vereinigung der beiden deutschen Staaten im Oktober 1990 hat man sich auch in Japan für das Phänomen der Staatsgrenze sehr interessiert. Bis etwa 1960 sind die Probleme der Staatsgrenze in der Regel nur von der Politischen Geographie untersucht worden. Die Staatsgrenzen behandelte man in den europäischen Ländern und auch in Japan hauptsächlich unter folgenden Gesichtspunkten: a) “frontier” and “boundary” (strategischer Aspekt). b) Grenzverlauf. (Handelt es sich um natürliche oder künstliche Grenzen?) c) Funktionen und Wirkungen der Grenzen. Seither haben die geographischen Untersuchungen über die Staatsgrenzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch Aspekte der Landschaftsforschung und der Sozialgeographie aufgegriffen. Man kann die Forschungsthemen in drei Gruppen gliedern. A. Analysen der Kulturlandschaft beiderseits der Staatsgrenze: Sie betreffen vor allem (1) die historische Gestaltung der Kulturlandschaft wie Flurformen und Siedlungsformen. Zum Beispiel findet man beiderseits der deutsch-niederländischen Grenze im Emsland unterschiedliche Formen der Moorkolonisation und der Kanalsiedlungen, die auf der topographischen Karte bemerkbar sind. (2) die Differenzierung der landwirtschaftlichen Bodennutzung unter dem Einfluϖ einer unterschiedlichen Agrarpolitik. Unter anderem findet man beiderseits der schweizerisch-österreichischen Grenze am Alpenrhein Weinbau nur auf der schweizerischen Seite. (3) die Unterschiede der Wirtschaftsstruktur beiderseits der Staatsgrenze. Beispiel: In der Oberrheinischen Tiefebene differiert die Erwerbstätigkeit der Bevölkerung auf der deutschen und französischen Seite erheblich. B. Untersuchungen der Beziehungen über die Staatsgrenzen: Sie gelten vor allem (1) den Grenzgängern oder Grenzpendlern. Zum Beispiel kommen von den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Österreich viele Grenzpendler nach Deutschland. Dagegen orientieren sich die Grenzpendler von Deutschland aus vor allem auf die Schweiz. (2) den zentralörtlichen Beziehungen. Beispiel: Der Einzugsbereich der Grenzstadt Flensburg reicht auch nach Dänemark hinein. Viele Leute kommen von dort nach Flensburg, um alkoholische Getränke, Schokoladen, Elektroartikel and andere Waren zu kaufen. (3) dem Fremdenverkehr. Der moderne Tourismus zeigt hohe absolute Zuwachsraten in der Form des grenzäberschreitenden Reiseverkehrs. C. Grenzäberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der räumlichen Entwicklungsplanung. Im Vordergrund stehen (1) die Verkehrsplanung and das Wirken zwischenstaatlicher Einrichtungen. Beim Neubau der Straϖen und anderer Verkehrswege wird oft eine grenzäberschreitende Zusammenarbeit nötig. Regionale oder kommunale Organisationen, wie EUREGIO Maas-Rhein und Regio Basiliensis gewinnen zunehmend Bedeutung. (2) Aspekt des Umweltschutzes. Die Umweltverschmutzung (tuft, Wasser) sensibilisiert in Grenzregionen zunehmend die durch “die andere Seite” belastete Bevölkerung. Für die Lösung der oft komplizierten technisch-ökonomischen Problem spielt die grenzäberschreitende Zusammenarbeit eine unentbehrliche Rolle.
1 0 0 0 OA 侵食輪廻説の歴史と日本の地形学への影響
- 著者
- 岡 義記
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.55-73, 1990-02-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 69
W. M. Davisの地形学は今世紀の前半に全盛時代を迎え,その影響力は今日にも及ぶ.しかし,その影響力ゆえに今日ほどDavisが酷評を受けている時代はない.Davis地形学の中心的概念であった侵食輪廻に焦点をあて,その意義を考え,その歴史的展開と日本の地形学の対応を歴史的に考察した. その結果,侵食輪廻説に含まれる空想とその前提にいくつかの矛盾があったために,それを放棄しなければならない歴史をたどったことを指摘した.また,日本では,その影響を強く受けていたが,侵食輪廻説の根底にある仮定にまでさかのぼる徹底した議論がみられなかったために,それに基づく古典的削剥年代学は温存される結果となったことなどを指摘することができた.
1 0 0 0 OA 長岡平野における地下水温の形成機構
- 著者
- 谷口 真人
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.11, pp.725-738, 1987-11-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 18 16
新潟県長岡平野における地下水温の形成機構を解明するために,地下水温の時空間分布の観測と熱移流を考慮:した数値解析を行なった.その結果,地下水温鉛直分布の季節変化パターンは特徴的な4つのタイプに分類され,その分布域も地域的な特徴を持つことが明らかになった.また,地下水流動による熱移流を考慮した数値解析により,これらの地域的差異が,地下水の涵養・流出・移流・揚水によって生じたものであることが明らかになった。地下水流動系の涵養域および流出域に出現するタイプは,それぞれ年間を通じた0.01m/dの下向きおよび上向きのフラックスの存在により,恒温層深度が鉛直一次元の熱伝導による計算値より約5m下方および上方へ移動する.河川近傍に出現するタイプは,水平熱移流の影響を受けて全層一様に温度変化する.市街地中心部に出現するタイプは冬期の消雪用揚水により,浅層の高温な地下水が水塊状に下方へ移動することにより説明できた.
1 0 0 0 OA 日本における水文学の発達
- 著者
- 山本 荘毅
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.7, pp.517-527, 1978-07-01 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 90
- 被引用文献数
- 1
The author summarized a history of development of groundwater hydrology in Japan. In general, the historical development of hydrology can be viewed through a series of periods and through series of events and articles such as number of books, papers and theories related to groundwater studies. Correlating to the historical division of Chow, Ven Te and that of Hida, N. et al., he proposed the division of development of groundwater hydrology in Japan as follows: a) Period of noninterference study (_??_1940), I-II1 b) Period of study of researcher's own free will ('40_??_'50), II2 c) Period of study under governmental readerships ('50_??_'55), II3 d) Period of cooperation with government and researcher ('55_??_'60), II3 e) Period of independant and free study ('60_??_date), IIISince these periods may overlap, their time division should not be considered exact. Generally speaking, all stages correspond to that of Chow's but those begin on about ten years later than those of western one. He tried to explain such a stage of development by political and socio-economic situations and stimulation of UNESCO's IHD. Because groundwater science is an interdisciplinal and practical science for needs of water resources in a country. Finally, he pointed out present problems of modern groundwater sciences on data with regards to accurracy, collection and coordinations, terminology and its redefinition, and groundwater law in Japan.
1 0 0 0 OA Martin Schwind 先生の逝去を悼む
- 著者
- 矢澤 大二
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.295-296, 1992-04-01 (Released:2008-12-25)
1 0 0 0 OA 計量地理学の新しい潮流
- 著者
- 奥野 隆史
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.8, pp.431-451, 2001-08-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 52
F. K. Schaeferの例外主義論文の発表以来,今日までに半世紀を経ている.その間, 1960年代前半の既存の統計手法の利用に始まり,その後地理学固有の概念・手法の重視が叫ばれ,それに伴い立地論のモデル展開や空間行動の計量分析などが盛んとなり,そのアブ面一チが集計的なものから非集計的なものへと変化していった・1970年代後半以後・際立った変革が技術と方法の両面に現れてきた.主なものはGISの発達とロにカルモデルの構築である.GISの計量地理学分析への結合は必ずしも十分ではないが,分析法のコンピュータプログラム化の遅れとともに,それの未開発部分の多さにもその原因がある.近年における分析法の開発の主点は,前代の空間プロセスのグローバル面のモデル化から,それのローカル性に焦点を当てたモデル化に移行されっっある.この移行は,地域個性の計量的解明を目指すとともに,空間的非定常性問題の解決を意図する動きといえる.それに関して, (1) 点パターンや空間的自己相関などの伝統的問題に対するローカル分析, (2) 空間的拡張法,空間的適応フィルタ法,多水準モデル法,地理的加重回帰法など多変量的問題状況に対するローカル分析について論評する.またこれらの分析と深く関わる可修正地域単位,実験的推測,地理的加重モデルなどの新しい研究動向にっいても言及する.
1 0 0 0 OA 高齢者の生活空間 社会関係からの視点
- 著者
- 仙田 裕子
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.7, pp.383-400, 1993-07-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 5 5
高齢者の生活の質を理解するためには,生活空間の把握が不可欠であると考え,本稿では余暇的活動を行なう際に取り結ぶ社会関係の空間的範囲(「関係空間」と称す)に焦点を当て,調査を行なった.調査地域には今後高齢化の進展が予想されている東京大都市圏の郊外地域(横浜市戸塚区秋葉町)を選定した.調査は,「関係空間」の広がりと属性との対応に関するアンケート調査と,ライフヒストリーとの対応に関するインテンシブな聞き取り調査の2段階に分けて行ない,その結果以下のことが判明した. (1)高齢者の「関係空間」の広がりは,高齢以前の生活空間によって規定されるが,身近な地域については高齢以後に形成される関係に規定される. (2)職住の空間的な分離や人口の流動性の高さといった郊外地域の特性は,加齢に伴った「関係空間」の変化を余儀なくする.高齢者はそうした空間的な変化に対しても適応する必要が生じている.
1 0 0 0 OA 地表に於ける物質の分布
- 著者
- 淡路 正三
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.9, pp.1444-1446, 1930-09-01 (Released:2008-12-24)
1 0 0 0 OA 渋谷繁華街の構造
- 著者
- 松沢 光雄
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.9, pp.618-624, 1966-09-01 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 2
(1) 渋谷繁華街を繁華街核心域(中心回遊路・回遊路内包域),回遊路外接域,周縁域の3地域に区分する. (2) 副都心を形成する新宿・渋谷・池袋の繁華街の構造上の共通点から,副都心構造の類型を導きだすことを試みた・しかし,副都心とよぼれる繁華街は,その数が少なく9特殊的事象と類型的事象との区別が困難である場合が多い.また,これら繁華街の構造および規模は,時代の経済事情に影響され装身具の流行(毛皮店)や,遊戯内容の変化等(トルコ風呂,スーパーマーケット,つり堀,レーシングカーなどの消長)の条件に反応すると思われる点もあって,固定的解釈をもつことは困難である.しかし,出来る限り,類型性をもつものを整理するようつとめた. (3) 繁華街構造の研究は,人間の快楽的要求と集落構造との関係の研究に外ならず,従って,心理学的立場からの考察が必要であるが,本論ではその面にはふれなかった.
1 0 0 0 OA 八ケ岳西麓原村における灌漑水利慣行の形成と新田開発(その1)
- 著者
- 五味 武臣
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.7, pp.484-490, 1972-07-01 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 27
1 0 0 0 OA 關東の交通網 2
- 著者
- 飯山 敏春 佐々木 彦一郎
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.4, pp.301-306, 1933-04-01 (Released:2008-12-24)
1 0 0 0 OA 東京付近の湿度分布と都心における湿度の経年変化について
- 著者
- 佐々倉 航三
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.9, pp.572-578, 1965-09-01 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 7
都市気候の一環として都市の内外における湿度差が論ぜられるが,東京付近においてはその差は概ね5%ぐらいであり,その原因は主として郊外の方に水張が大きいことにあることを明かにした.また都心における湿度の経年変化が80年間に6% ぐらい低落したことを示し,その原因が主として都心における気温の経年上昇にあることを明かにした.
1 0 0 0 OA 岩手県におけるブロイラー産業の発展と産地形成
- 著者
- 長坂 政信
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.239-257, 1988-03-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 1
岩手県におけるブロイラー産業は1960年代前半に大船渡市で開始され,その後半には県南地域に波及した.その担い手は飼料資本の地元飼料特約店であり,処理加工場を設立しつつ,地元の生産者を確保するために主に委託契約方式を採用してブロイラー飼養を行なわせた. 1960年代後半から70年代前半にかけ,次第に県北地域へとブロイラー産業は地域的に拡大した.その担い手は地元飼料商のほか,総合商社・飼料資本の子会社,単位農協地元農民など多様であった. 1970年代後半には大手のローカル・インテグレーターを中心に,種鶏・ふ卵場の設置,直営農場によるブロイラー飼養,荷受・卸売部門への進出を通して,生産から販売に至る一貫した自己完結型のインテグレーションを形成し,また飼養農家の強い生産意欲にも支えられて市場競争力を強め,南九州産地と並ぶ日本のブロイラー産業の生産地を確立した. 岩手県のブロイラー産業の主産地を形成している南東部地域と北部地域では,零細農家が収益の相対的優位性を最大の要因としてブロイラー飼養を選択し,また,複数のインテグレーターが地域の農業経営や農家経済の状況に対応して,ブロイラー産業への地域的条件整備の役割を果たしてきたという共通の存立基盤のあることが判明した.
1 0 0 0 OA 地理学と主題図
- 著者
- 中村 和郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.3, pp.155-168, 1998-03-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
In striking contrast to the long history of general maps, it was not until the latter half of the seventeenth century that thematic maps appeared. A. Hettner, (1927), who fully discussed the unique properties and importance of maps in geography, did not yet use the term “thematic maps, ” but stated instead that new types of maps had been introduced in the nineteenth century. A. Kircher (1665) and E. W. Happel (1685) were among the first thematic map makers. The contribution of E. Halley deserves special mention. His world map of trade winds and monsoons (1686) was the first map which used iconic symbols to depict wind directions, and even the seasonal reversal of the Indian monsoon was well demonstrated. Very few had ever used isolines before Halley, who made a chart of compass variations in 1701. Thematic maps made rapid progress in the eighteenth century, when maps of geology, biology, linguistics, population density, economics, administrative divisions, etc. were made. In the author's opinion, Alexander von Humboldt and Karl Ritter made full use of thematic maps to establish the firm foundation of modern geography. “Sechs Karten von Europa” by Ritter, attached to his book “Regional Geography of Europe, ” was the first printed atlas of thematic maps. An incredible amount of information concerning individual locations on the earth's surface was put into an orderly system of knowledge in the form of thematic maps. By making distribution maps of trees and shrubs and of cultivated plants, he delineated several natural regions which were almost parallel to the latitudinal zones. His famous definition of geography, that is, geography deals with the earth's surface as long as it is earthly filled (irdisch erfüllt), can be well understood through his intention to make various thematic maps, because comparable information must be collected for the whole region to complete a map. Halley's isoline map was followed only by those of Ph. Buache (1752) and J. I. Dupain-Triell (1791) until Humboldt made an isothermal chart in 1817. The isoline map is unique in that it can be made with a limited number of data. Humboldt used only 58 cities to produce his chart of a wide area in the Northern Hemisphere. In addition, isoline maps are also unique in that, once made, interpolation and extrapolation allow determination of the figure for every arbitrary point. With the aid of Humboldt, H. Berghaus, the eminent cartographer, published the “Physische Atlas” which included many thematic maps. It cannot be denied that Humboldt was also very keen to illustrate the regularities of physical phenomena and the interrelationships between them using thematic maps.Scrutiny of the history of modern geography from the viewpoint of thematic maps, discovering what type of map was developed for what purpose, etc., is a promising research area.For example, C. Darwin made a distribution map of coral reefs to test his subsidence theory explaining the formation of three types of coral reef. Emphasizing the shapes that maps can describe better than language, O. Peschel believed that a precisely prepared map could illustrate the hidden factors explaining the formation of fjords and other phenomena. F. Ratzel also recognized the importance of map representation in the science of “Anthropogeographie.” His movement theory was highly appreciated by the Kulturkreis school in cultural anthropology. L. Frobenius developed the culture-complex diffusion theory with the help of a number of thematic maps.K. Yanagita (1930), a Japanese folklorist, assembled more than three hundred parochial expressions for the word “snail” into a map. Identifying a concentric pattern with the center in Kyoto from a seemingly chaotic map, he concluded that the distribution pattern of some Japanese dialects resulted from a slow diffusion from the ancient cultural core.