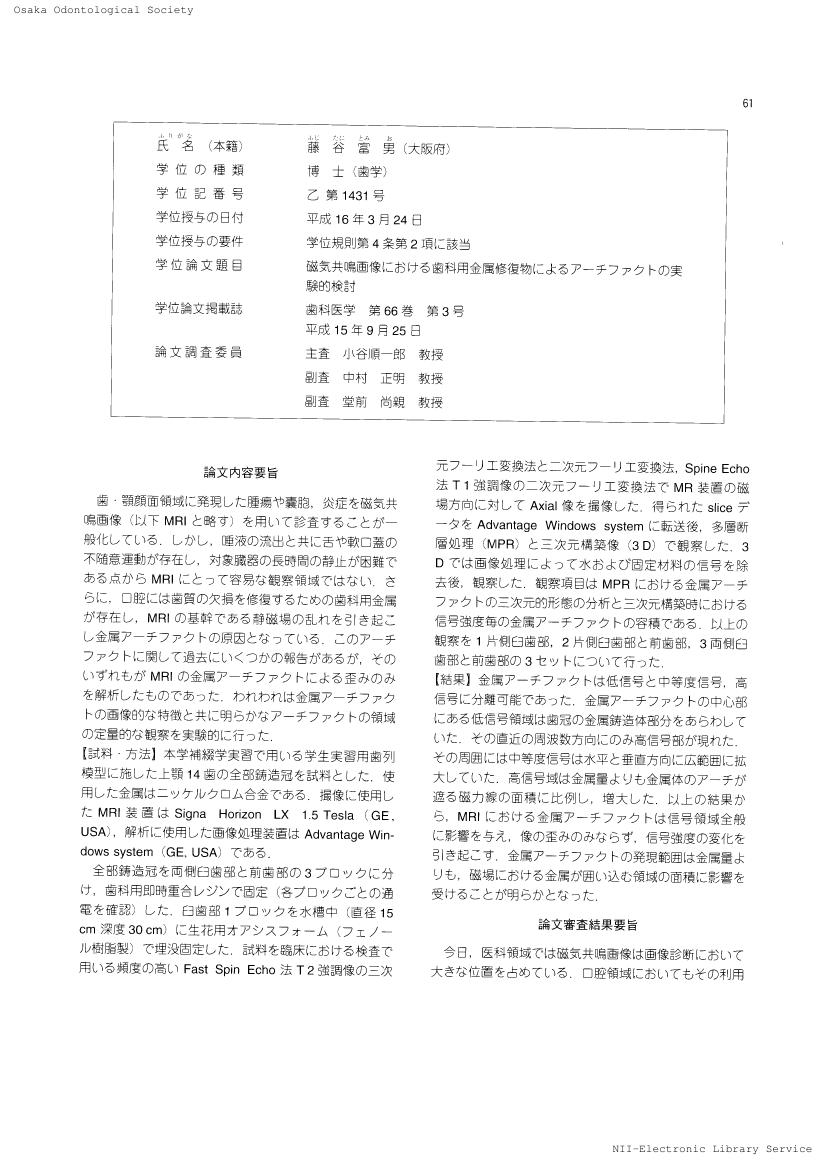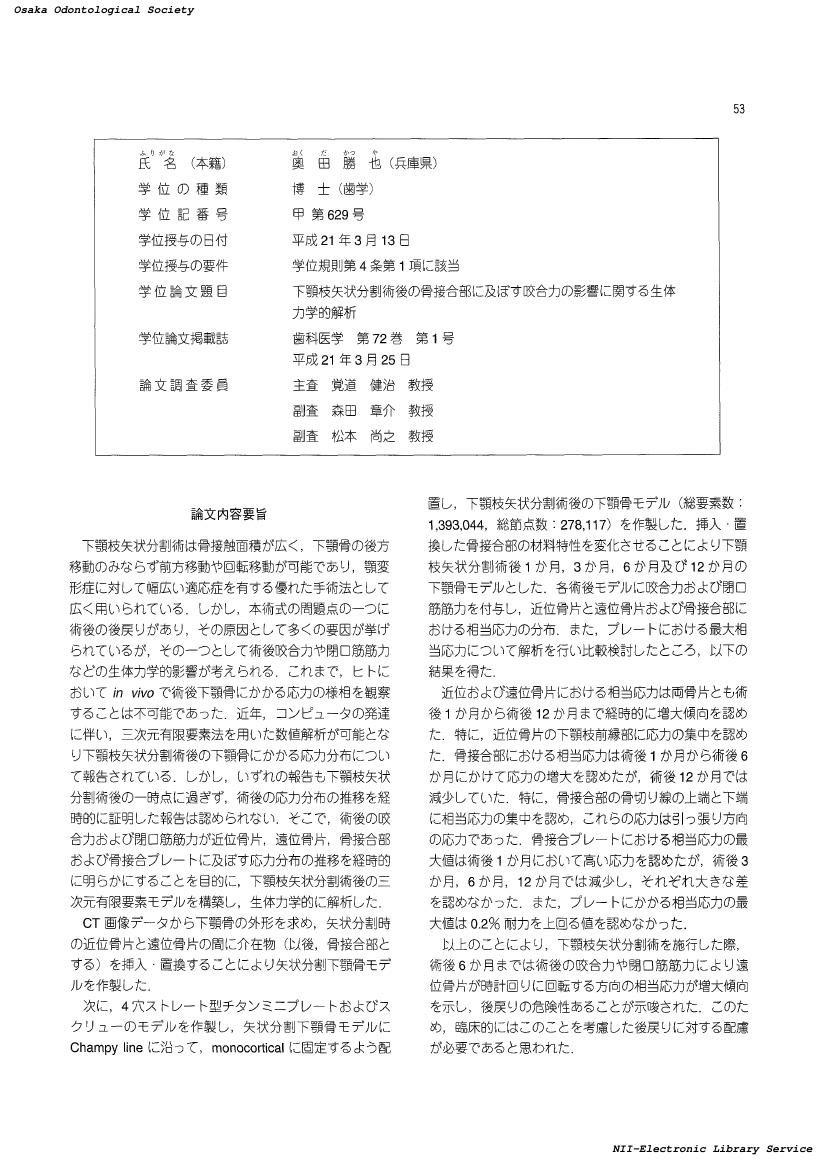1 0 0 0 TMD療法としての咬筋超音波照射の至適条件に関する研究
- 著者
- 貴島 真佐子
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.153-168, 1998
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 1
理学療法は, 筋や関節における機能障害の回復ならびに疼痛緩和に用いられる. 近年, 顎機能異常患者に対する理学療法, なかでも超音波治療は, 深部加熱効果を期待して障害を受けた咀嚼筋に応用されてきた. ところが, これまで明確な超音波照射条件は示されていない. 本研究では, 健常有歯顎者について, まず従来の照射条件(2.0, 1.5, 1.0W/cm<sup>2</sup>), 超音波診断装置による皮下(咬筋, 下顎枝)組織の横断面の計測について検討した. 次に無侵襲的な深部体温計測法を咬筋に応用し, 照射による咬筋深部温変化の再現性, 照射強度ならびに照射時間が咬筋深部温に及ぼす影響について検討した. 照射条件は, 照射強度を0.5, 0.75, 1.0W/cm<sup>2</sup>, 照射時間を5, 10分間の合計6条件で周波数3MHz, 連続波, ストローク法で照射した. さらに痛みに関するアンケートは, 5段階のLikert型スケールを応用し, 照射中, 後に採取した. 安静時熱平衡状態, 照射終了20分後, 60分後の3時点の測定温からΔT, 上昇率ならびに減衰率を求めた. そして得られた結果に基づいた照射条件である0.5W/cm<sup>2</sup>の10分間を顎機能異常患者に応用した. その結果, 1) 1.5W/cm^2以上の照射強度は痛みのため2分以上の照射は不可能であり, 咬筋には高い照射強度であることがわかった. 2) 咬筋表層は皮下3.3〜5.9mmに位置することから, 3MHzの照射ならびに深部温プローブの測定が可能であった. 3) 級内相関係数は0.75以上を示し, 照射による咬筋深部温変化の再現性が良好であった. 4) ΔTならびに上昇率は, 照射時間が長いほど高くなり, 減衰率は, 照射強度が高いほど高くなった. 5) 痛みに関するアンケート評価において, 1.0W/cm<sup>2</sup>では比較的早期に痛みを誘発するため, 咬筋に応用するには不適切であった. 6) 顎機能異常患者への超音波照射により咬筋の違和感・だるさと触診による圧痛は, 照射後60分後では軽減し, VASからも改善が認められた. 以上のことから, 超音波照射の至適条件は, 照射プローブの特性により機種ごとに異なる. しかし, 咬筋への超音波照剣による深部温計測と痛みに関するLikert型スケールの結果から, その至適条件がわかった.
1 0 0 0 OA インプラント体周囲骨欠損の新生骨形成過程におけるβ-TCPおよび多血小板血漿(PRP)の影響(大阪歯科大学大学院歯学研究科博士(歯学)学位論文内容要旨および論文審査結果要旨の公表)
- 著者
- 山口 貴史
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.2, pp.B56-B58, 2011-09-25 (Released:2017-06-08)
1 0 0 0 OA 磁気共鳴画像における歯科用金属修復物によるアーチファクトの実験的検討
- 著者
- 藤谷 富男
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.61-62, 2004-06-25 (Released:2017-05-15)
1 0 0 0 OA 巨舌症患者に対する舌縮小術術前後における音声学的機能評価
- 著者
- 森下 寛史 中嶋 正博 田中 克弥 覚道 健治 佐藤 正樹 川添 堯彬 杉立 光史 赤根 昌樹
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.227-231, 2005-06-25 (Released:2017-05-18)
われわれは舌縁部の咬傷を主訴に来院した58歳女性の巨舌症に対して舌縮小術を施行し, 術前後における音声機能を比較した.最大舌幅径は術前55mmから術後40mmに減少し, 舌縁部の歯の圧痕も消失した.また発語明瞭度検査および「杉スピーチアナライザー」を用いた音声分析の結果では術前と術後5か月とでは変化がみられず, 手術における機能障害は認められなかった.
1 0 0 0 OA 嚥下時における鼻呼吸動態の解析
- 著者
- 内貴 寛敬 小野 圭昭 小正 裕
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.51-63, 2004-03-25 (Released:2017-05-15)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 2
本研究は鼻呼吸動態の計測を利用し,臨床に応用可能な嚥下運動の臨床的検査法を検討することを目的とするものである.正常被験者に対して差圧型気流量計を用いて鼻呼吸動態,オトガイ舌骨筋筋活動,喉頭運動ならびに胸郭・腹部運動を計測することによって嚥下時の鼻呼吸動態を明らかにし,従来の検査法と比較検討した.鼻呼吸停止時間とオトガイ舌骨節筋活動時間,喉頭運動時間,胸郭運動停止時間ならびに腹部運動停止時間とを比較した結果,鼻呼吸停止時間は他のパラメータよりもばらつきが小さく,鼻呼吸停止時点ならびに開始時点を明確に特定することが容易であった.また,水至適嚥下量(20mL)において,鼻呼吸はオトガイ舌骨節筋活動開始時点および喉頭運動開始時点よりも遅れて停止し,オトガイ舌骨筋筋活動終了時点よりも遅く,喉頭運動終了時点よりも早く開始していた.至適嚥下量範囲内の嚥下では鼻呼吸動態とオトガイ舌骨節筋活動ならびに喉頭運動との間に顕著な差は認められなかった.至適嚥下量を越えると,鼻呼吸はオトガイ舌骨筋筋活動開始時点よりも遅れるが喉頭運動開始時点よりも早く停止し,オトガイ舌骨筋筋活動終了時点および喉頭運動終了時点よりも遅れて開始することが明らかとなった.以上の結果よリ,嚥下運動を評価するにあたり,鼻呼吸動態を計測することは他のパラメータよりも正確,簡便であり,嚥下運動の臨床的検査法として有用であると考える.
1 0 0 0 OA 下顎の開口動作に先行する開口筋筋活動に関する筋電図的研究
- 著者
- 岡田 正博 内田 愼爾
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.173-188, 1995-06-25 (Released:2017-03-09)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 3
咀嚼時に観察される開口筋の開口動作に先行する筋活動の動作学的な意義を明らかにするため, 咀嚼に比べ比較的単純で再現性に優れたopen-close-clench cycle (OCC運動)を被験運動とし, 開閉口運動速度, 咬みしめ力, 運動の繰り返しの有無, 歯の接触の有無, 歯根膜感覚の有無などの条件が外側翼突筋下頭(Lpt), 顎二腹筋前腹(Dig)の onsetに及ぼす影響について観察した. 有歯顎者のOCC運動では, Lpt, Digともに開口開始に先行する筋活動がみられ, それぞれの筋の onsetは, 開閉口相時間, 咬合相時間の変化によっては有意な変動を示さなかったものの, 咬みしめ力に対応する咬筋(Mm)平均筋活動量の変化によって有意に変動し, Mmの活動量が大きくなると開口筋 onsetはより先行する傾向を示した. 最大開口速度の変化は開口前の筋活動量に影響を及ぼした. 咬合相におけるMmの平均筋活動量が増すと, 開口筋の開口前に認められる筋活動が大きくなる傾向を示した. 開口筋の先行活動は, OCC運動のような繰り返し運動のみならず, 一度だけの咬みしめ後開口においても認められた. 歯を接触させない開閉口運動では, Lpt, Digともに開口に先行した活動が認められず, cycle timeの変化によってもOTは影響されなかった. 総義歯患者におけるOCC運動では, LptおよびDigの onsetが, 開口開始より先行したが, Mmの平均筋活動量の変化によって onsetは有意な変動を示さなかった. 以上の結果より, 開口筋 onsetの開口開始からの先行は, 下顎を開口方向に向けるための準備的活動であることが示唆され, これらは開口筋としての動作的特徴であることが示された. また, 開口筋 onsetを変化させる重要な要因は咬みしめ力であることが明らかとなったが, 総義歯患者では, 開口筋 onsetの調節性が有歯顎者に比較するとやや劣る傾向が示された.
1 0 0 0 OA 高野槙エタノール抽出液の口腔細菌に対する抗菌活性
- 著者
- 石田 哲也 福島 久典
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.139-146, 2008-06-25 (Released:2017-05-29)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
高野槙68%エタノール抽出液(試料A)の口腔細菌に対する抗菌域や性状を検索するとともに,精製を試みた.試料Aには夾雑物の混入が予測されたので,Sephacryl S-100によるゲル濾過を行った.溶出には0.05M Tris-HCl buffer(pH 7.5)を用いた.その結果,2つのピークが得られた.抗菌活性は両者に認められた.そこで試料A,第1ピーク,第2ピークの抗菌域を検討した.3者とも広い抗菌域(好気性ないし通性嫌気性菌ではStreptococcus oralis, Streptococcus sanguinis, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Actinomyces viscosus, Bacillus subtilis, Rothia mucilaginosa, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coliなど,偏性嫌気性菌ではPorphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Peptostreptococcus anaerobiusなど)を有し,ほぼ一致した.したがって,以後の実験には第2ピークの凍結乾燥標品(試料B)を供した.試料Bをそれぞれ0〜99.59%濃度のエタノールで溶解し,抗菌活性を測定した.その結果,エタノール濃度60%と70%をピークとする活性(16AU)がみられ,0%濃度でも4AUの活性が得られた.試料B水溶性画分の抗菌作用性は,指示菌(7.0×10^9/mL)と,試料Bをphosphate buffer salineで溶解させた活性画分(16AU)とを等量混ぜ合わせ,経時的に残存生菌数を測定した.生菌数は経時的に減少し,1時間後では5.0×10^2/mLであった.それゆえ試料B水溶性画分の抗菌活性は殺菌的であるといえる.抗菌活性の本体を知る目的で,chloroform-H_2O(1:1)に試料Bを溶解させ,活性を調べたところ,ほとんどの抗菌活性はchloroform層にみられた.ついで乾固させたchloroform層をacetonitrileで溶解してHPLCに供した.その結果,acetonitrileの高濃度画分に明瞭な抗菌活性がみられた.今後さらに解析を進め,抗菌成分を明らかにしたいと考えている.
1 0 0 0 OA 6411 嚥下時の下顎運動と口腔内圧, 咽頭圧の解析
- 著者
- 田中 栄士 小野 圭昭 権田 悦通
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.152-160, 2001-06-25 (Released:2017-04-20)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 5
本研究は水嚥下時の口腔期から咽頭期への嚥下動態を経時的に観察し, 口腔期から咽頭期にかけての嚥下機能を明らかにすることを目的とした, 嚥下機能に問題のない健康な成人男性8名を被験者とした各被験者に5から50mLの間で5mLごとの異なる量の水をランダムに口腔内に含ませ素早く嚥下する一回嚥下, ならびに, 嚥下量, 嚥下速度とも被験者任意で試行する連続嚥下を行わせ, 下顎運動と口腔および咽頭の嚥下圧を同時記録し, 口腔内圧, 中咽頭圧, 下咽頭圧ならびに, 各最大圧と下顎運動との時間的関係について分析を行った. その結果 1. 一回嚥下量の増加に伴って, 口腔内圧には差は認められず, 中咽頭圧ならびに下咽頭圧は有意に上昇した. 2. 一回嚥下では嚥下量の増加に伴って, 口腔期から咽頭期への移行時間を表す閉口点と最大中咽頭圧点の時間差ならびに最大口腔内圧点と最大中咽頭圧点の時間差に有意な減少が認められた. 3. 一回嚥下において, 大きな嚥下量(35〜50mL)で最大口腔内圧と最大中咽頭圧の発生時間に逆転現象がみられた. 4. 連続嚥下の各サイクルは, 最初と最後を除いて一回嚥下の動態と類似していた. 5. 嚥下量の近似した一回嚥下と連続嚥下を比較すると, 下顎運動との時間的パラメータにおいて連続嚥下の方が有意に小さな値を示した. 以上のことから, 嚥下運動は嚥下量や嚥下様式の違いによって一定の特徴を示し, 特に下顎運動と嚥下圧の関係は嚥下様式ごとに, それそれの協調活動を持つことが明らかとなり, 嚥下評価に下顎運動と嚥下圧を同時に測定することが有用であることが示唆された.
1 0 0 0 OA ベンチプレス動作時における顎口腔機能の様相
- 著者
- 鶴身 暁子 田中 昌博 川添 蕘彬
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.72-80, 2007-03-25 (Released:2017-05-25)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
本研究では身体活動時における顎口腔機能の役割を明らかにするために,動的な咬合接触および咬合接触圧分布と筋電図の同時計測を行い,健常有歯顎者のベンチプレス動作時の咬合接触と筋活動について検討した. 被検者は健常有歯顎者5名を選択した.被検者利き手側の側頭筋前部,咬筋,顎二腹筋前腹を対象筋とした. 咬合接触および咬合接触圧分布と筋電図の同時計測には,当講座で開発した同時計測システムを用い,咬合接触および咬合接触圧分布の測定には咬合接触圧用特注センサシートを用いた. 被検者に最大随意咬みしめおよび最大随意開口を指示し,3回の試行の咬合接触圧の最大値および筋電図包絡線の最大値を平均し,その値を個人の100%の値とした. 被検動作はベンチプレス動作とし,光による単刺激の合図に,可能な限りすばやくバーベルを挙上するよう指示した.被検者の最大挙上重量を100%とし,各重量時の側頭筋前部,咬筋および顎二腹筋の筋電図包絡線最大値に対する比率を計測したところ,ベンチプレス動作と顎口腔機能の関連において以下の結論を得た. 1.すべての被検者で約95%重量時において,咬筋筋電位の発現が20%を超えた. 2.約50%以下の重量時においては,全被検者で側頭筋前部および咬筋筋電位の発現が10%未満であった. 3.顎二腹筋の筋活動量は最大随意開口時とほぼ同程度であった. 4.すべての被検者の全試行において,最大咬みしめに至るような咬合接触値は認められなかった. 5.身体活動時において,挙上重量が個体の限界に近いほど,咀嚼筋が協力的に作用し,咬合接触の有無にかかわらず,下顎の固定に関与していることが示唆された.
- 著者
- 奥田 勝也
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.A53-A54, 2009-06-25 (Released:2017-06-01)
1 0 0 0 咀嚼運動と唾液分泌との関連性について
- 著者
- 西川 泰央 吉田 洋
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.123-132, 1995-04-25
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 5
ウレタン・クロラローズで麻酔したネコを用いて, 末梢入力に対する反射性の唾液(顎下腺唾液)分泌を調べるとともに, 咀嚼運動関連中枢である視床下部外側野, 扁桃体, 大脳皮質顔面野および大脳皮質咀嚼野への電気刺激による唾液分泌を調べて, 唾液分泌を含めた咀嚼運動への上位中枢の役割を検討した. 除脳動物を用いて口腔感覚による反射性の唾液分泌を調べたところ, 通常の咀嚼時に生ずるような非侵害刺激(触刺激および圧刺激)ではその分泌は少量であった. また, 上位中枢への電気刺激によって顎運動および舌運動が誘発されるとともに, 同側優位の唾液分泌が観察された. 唾液分泌量は非動化後も変化しなかったので, 咀嚼筋からの感覚情報は唾液分泌機序に関与しないことがわかった. さらに, 大脳皮質において, 一部の口腔内感覚投射部位と顎運動および唾液分泌に関連する局在部位とは, 小範囲で隣接しているかあるいは部分的に重なっていることが判明した. 以上の成績から, 上位中枢が反射唾液分泌に修飾作用を及ぼすとともに, 食物を咀嚼するために視床下部, 扁桃体および大脳皮質が活動し, 同時に口腔内からの感覚情報がこれらの上位中枢に達するとそこでの活動が高められ, その結果唾液分泌が促進されると考えられる.
1 0 0 0 笑顔への歯科からのアプローチ : 口唇周囲の変化からみた研究
1 0 0 0 咬合干渉付与時の自律神経機能について
- 著者
- 岩山 和史 小野 圭昭 小正 裕
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.81-90, 2007
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 2
本研究は,高さの異なる2種類の咬合干渉装置を付与し,対光反応を計測することにより,それぞれの咬合干渉が自律神経機能に及ぼす影響を明らかにし,その作用機序について検討した.<br> 被験者は,全身および顎口腔機能に自覚的,他覚的な異常の認められない成人被験者5名とした.自律神経機能の計測には,赤外線電子瞳孔計を用いた.付与する咬合干渉の高さは,2mmならびに100μmの2種類とした.実験は,下顎安静時と,咬合干渉装置を装着して最大咬みしめを行わせたときの2条件にて行った.分析は交感神経機能の指標である初期瞳孔径,ならびに副交感神経の指標である最大縮瞳速度をパラメータとして行った.その結果,以下の結論を得た.<br> 1.2mmの咬合干渉付与時,初期瞳孔径ならびに最大縮瞳速度は,すべての被験者において咬合干渉の有無による有意な差が認められ,咬合干渉付与時に散瞳傾向ならびに最大縮瞳速度の減少傾向が認められた.<br> 2.100μmの咬合干渉付与時,初期瞳孔径ならびに最大縮瞳速度は,1名の被験者においてのみ咬合干渉の有無による有意な差が認められ,その傾向は2mm干渉付与時と同様であった.他の4名の被験者においては有意な差は認められなかった.<br> 以上のことから,2mmの咬合干渉付与時には,すべての被験者において交感神経の興奮ならびに副交感神経の抑制が生じ,一方,100μmの咬合干渉付与時には,その反応性に個人差が存在した.これは,歯根膜感覚が自律神経機能に影響を及ぼすことは少なく,顎関節内の感覚受容器が刺激され,自律神経機能に変化が生じたと考えられる.
1 0 0 0 OA 高野槙エタノール抽出液から得られた抗菌活性画分の性状
- 著者
- 藤本 幸永 福島 久典
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.2, pp.48-55, 2011-09-25 (Released:2017-06-08)
- 参考文献数
- 34
高野槙68%エタノール抽出液の抗菌物質を部分精製するために,ヘキサン,ジイソプロピルエーテル,酢酸エチル,ブタノールで分画した.各層を乾固し,60%エタノールで溶解して抗菌活性を測定した.抗菌活性は,Staphylococcus aureus ATCC 12600を指示菌としてsoft agarとともに流し固めた平板上に,それぞれの試料の2培連続希釈液10μLずつを滴下して培養し,発育阻止が認められた最大希釈の逆数で表した.各活性画分はそれぞれSephadex^<TM>LH-20によるゲル濾過で分画した.またゲル濾過で得られた活性画分は高速液体クロマトグラフ分析に供した.さらに各抗菌活性画分の抗菌域についても検索した.最も強い抗菌活性が認められたのはジイソプロピルエーテル層(74.1%)で,ついでヘキサン層(19.7%),酢酸エチル層(6.2%)の順であった.ブタノール層と水層に活性はみられなかった.ヘキサン層をゲル濾過に供した結果,2つのピークが得られ,活性は第1ピークと第2ピークの間(Hb)にみられた.ジイソプロピルエーテル層のゲル濾過では3つのピークが得られ,抗菌活性は第1ピーク(Ea),第2ピーク(Eb)および低分子画分(Ec)に認められた.またHb,EbおよびEc画分について高速液体クロマトグラフで分析した結果,Hb,Eb画分では混在物のため抗菌活性のあるピークを分離することはできなかったが,Ec画分では4つのピークが得られ,活性は3番目のピークにみられた.したがって今後,このピークの成分について明らかにする予定である.Hb,Ea,EbおよびEc画分の通性嫌気性菌,好気性菌,真菌に対する抗菌域は,名画分間で相違がみられた.また嫌気性菌に対しても同様であった.これらの結果を総合してみると,高野槙68%エタノール抽出液は,極性,分子量,抗菌域の異なる抗菌物質を複数含んでいると考えられる.
- 著者
- 岡崎 全宏
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.A78-A79, 2009-06-25
- 著者
- 林 靖久
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.g31-g32, 1995-10-25
発癌には多くの要因が関与しているため, 臨床面からその因子を推定し因果関係を明らかにすることは非常に困難である. 現在, 飲酒・喫煙は多くの疫学的および臨床的研究から癌発生に大きく関与し, 口腔癌においても重要な発生因子であると認識されている. しかし, 口腔癌患者の口腔環境についての研究は癌治療が最優先されることや, 口腔癌の発生数が少ないことなどの理由から, ほとんど明らかにされていないのが現状である. 本研究は口腔癌患者の口腔環境の実態を, オルソパントモグラムを用いて分析し, 癌発生を効果的に予防する具体的な方法の手掛かりを探求するものである. 研究対象 1968年から1990年の23年間に扁平上皮癌と診断され初診時のオルソパントモグラムが保管されている, 口腔癌患者454例(下顎歯肉癌223例, 舌癌155例, 口底癌76例)を対象とした. 対照群は1992年5〜6月および11〜12月にかけて本学附属病院歯科放射線科でオルソパントモグラムが撮影された30歳以上の患者390例(腫瘍や嚢胞および炎症で歯や顎骨に著明な変化を認めないもの)である. 研究方法 歯の齲蝕罹患や処置の指標はDMFを参考にし, 一部を改変した. D: Decayは未処置齲蝕, M: Missingは齲蝕により喪失した歯, F: Fillingは処置された過去の齲蝕と定義されているが, 本研究での MissingはX線写真上での喪失歯を意味する. その評価項目は残存歯数, 未処置齲蝕歯率(未処置齲蝕歯数/残存歯数)とした. また歯周組織の重篤度を示す指標として, 歯槽骨の吸収度を植立歯の長さに対応させて0から4まで, 1)レベル0: 歯槽骨頂に白線が認められるか, あるいは歯槽骨の吸収がないもの, 2)レベル1: 歯槽骨頂の吸収が軽度にみられるもの, 3)レベル2: その吸収量が根尖側2/3付近まで, 4)レベル3: 根尖側1/3付近まで, 5)レベル4: レベル3を越える吸収, の5段階に分類した. この基準に従って, 各歯において最も重篤な骨吸収レベルを点数として与え(腫瘍による骨浸潤相当歯は除く), その合計点数を残存歯数で割った値(骨吸収得点合計/残存歯数)を個人の歯周組織の状態の指標とし, これを骨指数とした. これら4群(下顎歯肉, 舌, 口底, 対照の各群)の比較は, 性および年齢で層別化して平均値の一様性の判定を行った. その判定には分散分析を用い, 平均値の一様性に差が認められた場合(P<0.05)にのみ, 各2群間の平均値の差をt検定で検討した. 結果 1)未処置齲蝕率は, 対照群より癌群のほうがやや高い傾向をみたが, 統計的な有意差は認められなかった. 2)歯槽骨頂の吸収程度は, 癌群のほうが進行していた. なかでも口底癌は対照群と比較すると, その吸収程度はかなり進行していた(男性49歳以下群1%以下, 50歳群0.1%以下, 60歳群5%以下, 70歳以上群0.5%以下の危険率で有意差を認めた). 3)癌群中, 舌癌の歯槽骨頂の吸収程度は, 対照群と類似していた. 腫瘍の発生部位で発癌の刺激因子は異なると考えられ, とくに口底癌と下顎歯肉癌は, 歯周疾患の進行が発癌因子の一つと思われた. 以上より口腔癌にかける第一次予防の手掛かりは, 歯周疾患進行の制御と考えられた.
1 0 0 0 OA 6527 歯肉浸潤麻酔が唾液中のコルチゾールおよびクロモグラニンAの濃度に及ぼす影響
- 著者
- 上り口 晃成 青木 誠喜 森田 真功 田畑 勝彦 畦崎 泰男 前田 照太 井上 宏
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.248-254, 2002-12-25
- 被引用文献数
- 10
我々は唾液を経時的に採取しつつ,歯肉浸潤麻酔を行う試行と行わない試行を設定し,唾液中ストレスホルモンであるコルチゾールおよびクロモグラニンAの濃度変化を分析することで,疼痛刺激が唾液中ストレスホルモン濃度に与える影響を検討した.被検者として,健康な健常有歯顎者8名を用いた.実験は3日間行い,1日目は実験説明日とし,2日目と3日目に浸潤麻酔日とコントロール日をランダムに割り当てた.実験説明日は実験内容の説明と実験環境への順応を目的とした.コントロール日と浸潤麻酔日は同一時刻に実験を開始し,被検者を水平位にて10分間安静に保った後2分間の唾液採取と8分間の安静期間を交互に6回繰り返した.浸潤麻酔日においては,2回目の唾液採取直前である,安静開始後19分15秒から45秒までの30秒間,上顎中切歯歯肉頬移行部に浸潤麻酔を行った.採取した唾液は直ちに-50℃にて凍結し,ホルモン濃度を測定するまで保存した.濃度分析は凍結した唾液を解凍した後,3000rpmで30分間遠心分離し,EIA法にて測定した.統計解析として,危険率10%で浸潤麻酔の有無および時間を因子とした反復測定分散分析を行った.また,被検者ごとに異なる変化パターンを統合的に比較するため,各試行における変動係数を求め,危険率10%で浸潤麻酔の有無について対応のあるt検定を行った.分析の結果,歯肉浸潤麻酔による疼痛刺激は唾液中コルチゾール濃度およびクロモグラニンA濃度を上昇させるほど大きなストレスではないことが明らかとなった.また,唾液中コルチゾール濃度の経時的減少は水平位による安静効果がもたらしたと推察された.そして,経時的測定を行った唾液中コルチゾール濃度の変動係数を比較することで,歯肉浸潤麻酔によるストレスを評価できる可能性が示唆された.
1 0 0 0 日本人の歯の平均寿命に関する研究
- 著者
- 重松 佳樹 川崎 弘二 神原 正樹
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.287-295, 2000-12-25
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 1
ヒトの平均寿命(ゼロ歳平均余命)の延びに歯がどのように寄与しているのかを明らかにするため, 歯の平均寿命の年次推移について検討を加えた.ヒトの平均寿命および歯の平均寿命の年次推移は, 戦後どの年度においてもヒトの平均寿命は女性の方が男性に比べて長いのに対し, 歯の平均寿命はいずれの歯種においても女性の方が短かった.歯の平均寿命を歯種別に比較すると, 第二大臼歯が最も平均寿命が短く, 犬歯が最も長いという結果であり, 歯種による平均寿命の差は約14年であった.このことにより, 歯の平均寿命を配慮した歯種別保健指導の重要性が示された.また, ヒトの平均寿命および歯の平均寿命を平成5年の結果で比較すると, 男性では最も平均寿命の長い犬歯でヒトの平均寿命(76.2歳)と比較して約5年平均寿命が短く, 最も平均寿命の短い第二大臼歯では約20年も歯のない期間が存在することが明らかとなった.さらに, 女性においてはヒトの平均寿命(84.0歳)と歯の平均寿命の差が大きく, 犬歯で約14年, 第二大臼歯で約28年の差が認められ, 無歯で過ごす期間が男性に比べ長いことがわかった.つぎに, 昭和62年から平成5年までのヒトの平均寿命と歯の平均寿命の延び率を比較すると, ヒトの平均寿命の延び率に対し, 歯の平均寿命の伸び率は約2倍であった.これらの結果より, ヒトの平均寿命に対し女性の歯の平均寿命が短い原因の究明, 口腔保健指導および予防プログラムを各年齢階級別および歯種別に構築する必要があること, 歯の平均寿命の推移に関わる歯科医療および歯科保健状況の解明が, 今後の歯科保健施策の立案に必要であることが明らかとなった.
- 著者
- 筧 晋平
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.A47-A48, 2007