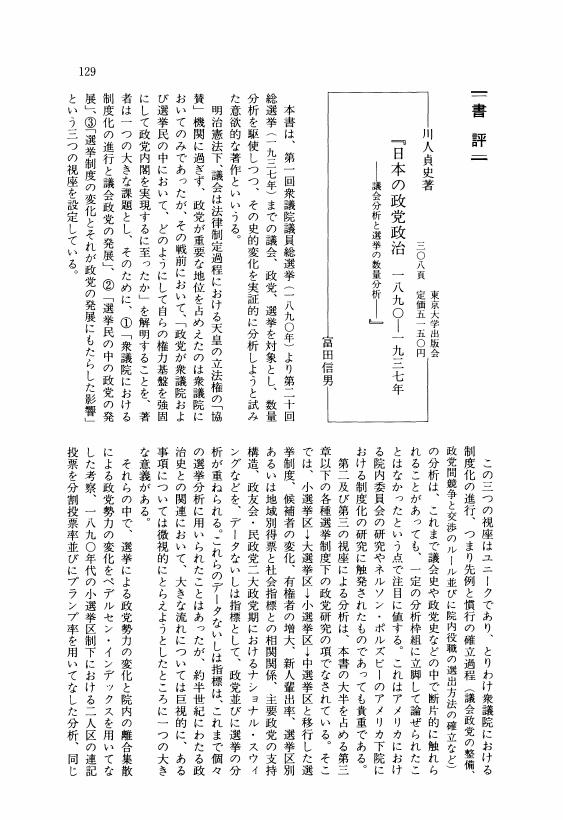2 0 0 0 OA 政治的保守主義の概念化と説明理論の提示
- 著者
- 西川 賢
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.88-98, 2012 (Released:2017-09-01)
- 参考文献数
- 71
本論文においては,第一に,政治的保守主義に関する有意な経験的実証研究を行うために,客観的に正当な根拠があると考えうる基準において,政治的保守主義を概念化することを試みる。第二に,先行研究を検討することでアメリカの共和党の保守化を対象にして,政治的保守化という現象の説明可能な三つの競合する理論を提示する。(1)政治的活動家に関する理論:これは共和党の保守化を保守主義の理念を媒介する政治的活動家の活動とそれを媒介する政治制度から説明する。(2)決定的選挙と政党再編に関する理論:この理論によれば共和党の保守化は決定的選挙とそれに伴う再編を通じて生じたものとして説明できる。(3)イシュー・エヴォリューション:これは共和党の保守化を個々の争点領域におけるイシュー・エヴォリューションが長期間にわたって重畳的に蓄積されて生じたものとして説明する。
2 0 0 0 OA 選挙研究における「政党支持」の現状と課題
- 著者
- 西澤 由隆
- 出版者
- Japanese Association of Electoral Studies
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.5-16,268, 1998-02-28 (Released:2009-01-22)
- 参考文献数
- 62
The concept of partisanship has been one of the central topics of the voting research in Japan as in other democratic countries. While whether the original concept of party identification developed in the U. S. is transportable to other countries is still under debate, the party support variable (measured by the question, “which party do you usually support?”) is often treated as functional equivalent to the party identification measure in Japan.This review article reminds researchers of Japanese voting study of a need for a careful look at the party support variable. It does so by going “back to the basics.” It evaluates the party support variable against the four basic assumptions of the original party identification concept: the sense of identification, its stability, its unidimensionality, and its transitiveness.Citing the existing works and drawing some new data, the article concludes that 1) the party support variable is not exactly measuring the sense of self-idenification with a party, 2) it is not as stable as its counterpart is assumed to be, 3) it is increasingly difficult to map the Japanese current political parties on the left-right uni-dimensional scale, and 4) whether its operational definition meets the transitiveness assumption is questionable.
2 0 0 0 衆議院選挙における退出と抗議
- 著者
- 木村 高宏
- 出版者
- Japanese Association of Electoral Studies
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.125-136,257, 2003
本稿では不満な有権者の棄権を,ハーシュマン(Hirschman, Albert O.)の提示した「退出」であると考える。この理論枠組みを敷衍して,不満な者の投票参加がいくつかの要因によって影響を受けるという仮説を検証する。<br>本稿の分析を通じて,不満であっても何らかの政治課題を重要だと考えれば投票し,あるいは,社会をよくするために何かができると考えれば投票する,という有権者の存在を示すことができた。このことは,有権者自身の態度形成を問題にしており,政策距離を中心に考える期待効用差からの研究に対して,有権者の政治を理解する能力が十分に成熟していない場合にも採用可能であるという利点があるだろう。また,分析において,政治的疎外感を示す質問と,「社会をよくする」というような有力感に関する質問とが,質的に異なることを示すことができた。
2 0 0 0 小泉解散の憲法学的検討
- 著者
- 高見 勝利
- 出版者
- Japanese Association of Electoral Studies
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.36-42,195, 2007
衆院において賛成多数で可決され,参院に送付された内閣提出法案が,参院で否決されたとき,内閣が,これを内閣不信任だとして,衆議院を解散することは,日本国憲法上,どう評価すべきかが,いわゆる小泉解散の最大の争点である。解散理由について,首相自身は,参院における法案否決を内閣に対する不信任だと受け止めたからだという以上のことは語っていない。が,「衆院が可決した法案を参院が否決した場合,衆院が出席議員の3分の2の特別多数で再可決すれば法案が成立するのだから,当該議席数確保のためにする解散は認められる」とする見解がある。しかし,解散理由として,再議決権を持ち出すことは,解散•総選挙の趣旨や議会政のあり方からして是認されないこと,小泉解散は不当な解散事例であり,「国民投票的」解散に途を拓いた事例として積極的に評価すべきではないこと等を指摘した。
2 0 0 0 一九九四年アメリカ中間選挙:共和党の勝因
- 著者
- 西澤 由隆
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.23-34,144, 1996
Using the 1994 American National Election Study data, this article tests five different hypotheses that attempt to explain the Republican victory at the 1994 Mid-term Congressional Election. Because the 1994 ANES data contains panel samples who responded at both 1992 and 1994 waves, it permits a researcher to study the reasons of the 1994 Republican vote gain from the previous election. The hypothesis tested here include: 1) Disapproval-of-Clinton-administration hypotheses, 2) personal-economic-condition hypothesis, 3) party-support-realignment hypothesis, 4) distrust-against-incumbent-candidates hypothesis, and 5) party-mobilization hypothesis. The cross-sectional analysis indicates that each factors, except for the personal economic condition, has statistically significant association with the vote choice while controlling for the effect of other factors. The panel analysis, however, suggests that the mobilization hypothesis only explains the Republican gain from the previous election. The analysis implies that unlike most journalistic accounts that tend to attribute the Republican victory to the change in voters' attitude and behavior, the electorate took only a passive role.
2 0 0 0 OA 中小政党の連立政権参加と有権者の投票行動
- 著者
- 鬼塚 尚子
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.113-127,206, 2002-02-28 (Released:2009-01-22)
- 参考文献数
- 27
近年我が国で実施された衆議院の選挙制度改革に際し,中小政党は次の三つの戦略-合同して大政党を作り政権奪取を目指す「合同戦略」,一貫して野党にとどまり「抵抗政党」としての存在をアピールする「非合同野党戦略」,自民党との連立政権に参加して与党としての政策実現や利益誘導を計る「非合同政権参加戦略」-を採ってこれに対処したと考えられる。しかし,第三の戦略を採った政党は選挙で苦戦していることが観察される。本研究ではこの理由として,(1)連立参加に伴う政策転換が潜在的な支持層の票を失わせること,(2)中小政党の与党としての業績は有権者に認知されにくいこと,(3)新選挙制度が自民党と連立を組む政党に不利に働くこと,(4)選挙協力を阻害する要因が自民党支持者側にあることを挙げ,個別に分析を行ったところ,おおむねそれぞれを肯定する結果を得た。
- 著者
- 前嶋 和弘
- 出版者
- Japanese Association of Electoral Studies
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.203-213,259, 2003
本論文は,連邦議会で2002年春,可決された選挙資金改革法案の決定要因を計量的に解明し,政治資金制度はどのような力学で決定されているか,分析する。同法は,現行の1974年連邦選挙運動法を改正し,党勢拡大を名目とする政党向け献金などを含めた現行の政治資金規制を受けない「ソフトマネー」を規制する一方で,個人献金の上限をこれまでの2倍に拡大する点などがうたわれている。分析では,「得票マージン差が少なく激戦区であるほど,法案に反対する」とした仮説などが実証された。しかし,「在職年数が長ければ長いほど,反対票を投じる確率が高い」とする仮説については,民主党の議員の場合には,検証されたが,共和党の議員の場合,在職年数につれて,法案に賛成する確率が高くなるなど,仮説で捉え切れなかった議員の論理などもいくつか,明らかになった。
2 0 0 0 OA 2002年ドイツ連邦議会選挙と投票行動
- 著者
- 河崎 健
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.17-27,171, 2004-02-28 (Released:2009-01-22)
- 参考文献数
- 33
シュレーダー政権初の国政選挙となった2002年総選挙はドイツ連邦共和国史上まれにみる与野党伯仲という結果になり,シュレーダー首相は辛くも続投することになった。過去4年間の政権の業績,首相の人気,野党の停滞状況にもかかわらず,シュレーダー政権が辛勝だったのは何故なのだろうか。マスコミは選挙直前の経済状況の悪化を大きな要因として挙げている。確かに経済運営に対する社民党への世論の評価は高くない。だが果たしてそれだけで十分に説明できるのであろうか。本稿では,短期的な経済動向のみならず,中長期的な政党支持の推移を追うことでシュレーダー政権支持の変化を分析する。具体的には,今回までの連邦議会選挙で実施された出口調査における男女差,年齢,職業,旧東西ドイツ地域間の差を見た上で,ドイツの投票行動に見られる中長期的な変化の特徴を考察してみたい。
- 著者
- 竹内 桂
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.35-46, 2016
本稿は,1974年の第10回参議院議員選挙の徳島地方区における保守系候補者の対立を検討する。徳島地方区では,三木武夫副総理の直系で現職だった久次米健太郎と,田中角栄総理の系統で新人の後藤田正晴との間で事実上の一騎打ちとなり,その争いは「阿波戦争」や「徳島戦争」などと称されるほど激しいものとなった。 本稿では,その争いの発端から選挙の結果までを対象に,①徳島地方区の自民党公認候補の決定過程,②公示までの動向,③選挙戦の展開を明らかにする。その上で,久次米が当選を果たした要因を検証する。さらに,この参院選が,三木武夫が権勢を誇っていた徳島県政の勢力図を変えていく契機となったことを指摘する。
2 0 0 0 日本社会党の盛衰をめぐる若干の考察:選挙戦術と政権•政策戦略
- 著者
- 谷 聖美
- 出版者
- Japanese Association of Electoral Studies
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.84-99,206, 2002
社会党は,60年代に入ると停滞し,その後は長期低落の道をたどった。この停滞と衰退をめぐってはさまざまな原因が指摘されてきた。なかでも,党の非現実的イデオロギーが党の適応力を奪ったという見方はもっとも一般的なものであった。<br>本稿は,衰退の原因をめぐる諸々の説明を逐一検討し,それらの多くが必ずしも説得力を持たないことを明らかにする。ついで,選挙におけるこの党の集票戦術を分析し,労組依存に安住して個人後援会などの集票組織の構築に努力しなかったことが衰退の一因であることを示す。さらに,片山•芦田内閣失敗の負の影響はあったものの,この党の連合戦略と政策展開は60年代中葉までは巷間いわれているよりもずっと現実的で,党が活力を失ったのは,そうした現実派が党内抗争で社会主義協会などの教条的左派に敗れたあとになってからのことであることを指摘した。
2 0 0 0 選挙制度の理念
- 著者
- 西平 重喜
- 出版者
- Japanese Association of Electoral Studies
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.5-18,224, 2005
選挙制度を議員の選出方法に限れば,小選挙区制と比例代表制の理念ははっきりしている。前者はなるべく狭い地域で選挙をして,選挙民が人柄のよく分かった代表を議会に送り出そうとする。後者は選挙民の意見の縮図を議会に作り出そうというものである。これ以外の選挙制度の理念は,この2つの制度を,それぞれの社会の実情に合わせようということで,やや違った次元の理念といえるだろう。<br>「政治改革から10年」の特集といえば,中選挙区制を廃止し並立制が採用されたのは,どんな理念によるものかが問題になる。この変更にあたっての論議の重点は,安定した政権の樹立や政権交替がしやすい選挙方法という点におかれた。あるいは少しでも中選挙区制による閉塞状態を動かしてみようという主張が強かったようだ。<br>ここではまず各選挙制度の理念や長所短所の検討から始める。そして最後に私の選挙制度についての理念である比例代表制の提案で結ぶ。
2 0 0 0 OA 戦後日本における1955年から1995年にかけての社会変動と社共支持
- 著者
- 栗田 宣義
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.122-138,188, 2000-02-28 (Released:2009-01-22)
- 参考文献数
- 36
「教育水準」「被雇用者」「消費財保有」「資産保有」といった4系統の社会経済カテゴリーの通時的変動をみると,1955年から1995年にかけての40年間における日本社会の変動は,(1)高学歴化,(2)被雇用者化,(3)消費財普及,(4)資産格差の持続,といった4点に要約できるが,この社会経済変動と社共支持率低落を関連づけ,インテリ左翼溶解仮説,労働者左翼溶解仮説,脱物質仮説,資産格差仮説からなる左翼主義逓減の説明モデルを提示する。SSMデータを用いた5時点のロジスティック回帰分析によれば,労働者左翼溶解仮説を除いては,ほぼ仮説の確認がなされた。かつて,1955年時点では,高学歴層,被雇用者層,消費財を持たない層,資産を持たない層が左翼主義であった。日本社会の変貌は左翼主義への支持を溶解,矮小化させ,40年後の1995年時点には,被雇用者層,資産を持たない層のみが左翼主義である構造にとって代わられたのである。社民党が左翼大衆政党としての歴史的使命を終えた構造的背景がここにある。
2 0 0 0 OA 書評
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.109-118, 1995-03-30 (Released:2009-01-22)
2 0 0 0 OA 書評
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.129-131, 1994-03-31 (Released:2009-01-22)
1 0 0 0 OA 大阪における感情的分極化
- 著者
- 善教 将大
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.18-32, 2021 (Released:2023-11-16)
- 参考文献数
- 29
本稿では筆者が実施した大阪市民を対象とする意識調査を用いた実証分析を通じて,大阪における感情的分極化の現状,原因,帰結の3点について検討する。地方政治の場において維新vs.反維新という激しい政治的対立が存在する大阪市は,日本で感情的分極化について議論する際,有用な知見を提示することが可能な事例の一つとして位置づけられる。本稿ではまず,地域レベルと個人レベルの分極化指数を求め,その水準を他国の事例などと比較することで大阪の分極化の現状を明らかにする。その上でメディアを通じた選択的接触の議論に基づき,2020年の住民投票期間中のメディア利用が政策選好や個人レベルの感情的分極化に与える因果効果を推定する。さらに個人レベルの分極化指数が,制度信頼,政治不信,市民間の相互不信に与える因果効果も分析し,感情的分極化が進展することの帰結についても考察する。
1 0 0 0 OA 選挙における「政府の失敗」 選挙公営費の支出配分の観点から
- 著者
- 安野 修右
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.58-71, 2021 (Released:2023-11-16)
- 参考文献数
- 40
日本の公職選挙法は,あらゆる選挙運動を禁止するという前提のもと,合法化された選挙運動には「選挙公営」の名のもと公的助成を行っている。この制度理念の背景には,国家が選挙過程を完全にコントロールすることで,選挙の公正を確保しようという戦前の思想がある。だが現在では,一連の規制枠組が日本の選挙過程を著しく非効率なものにしているという夥しい数の批判と証拠がある。にもかかわらず,選挙法の立法裁量権を掌握する現職国会議員は,この弊害を一向に改善しようとしない。この状態は,公共経済学で議論されている「政府の失敗」に類似している。そこで本研究では,まずこうした「政府の失敗」を生じさせうる日本の選挙運動規制の特徴について説明する。そのうえで現行の選挙公営費の配分が,現職国会議員の恣意的操作の結果として,選挙運動に使途を限定した政党助成とみなせるほど不平等になっている実態を明らかにする。
1 0 0 0 OA 経済は選挙結果に影響を与えるのか 都道府県の経済状況と安倍内閣下の衆議院選挙結果の分析
- 著者
- 清水 直樹
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.108-125, 2020 (Released:2023-11-16)
- 参考文献数
- 26
本稿の目的は,都道府県の経済データと2012,2014,2017年の衆議院選挙データを分析し,経済が選挙結果に与える影響を明らかにすることである。日本の経済投票に関する先行研究は,サーベイ・データによる研究が中心で,集計データによる研究が少ない。その理由として,第1に,時系列データの場合,選挙ごとに異なる政治状況や経済状況の影響を除去できないこと,第2に,地域間のクロスセッション・データの場合,地域特性や候補者特性の影響を除去できないことが挙げられる。本稿では,安倍内閣の下で実施された衆議院選挙のデータを利用し,その選挙に出馬している同じ候補者の得票率の差を計算したデータを用いることで政治状況や候補者特性などを除去する。そして,このデータを用いて,経済が選挙結果に与える影響を分析する。分析の結果,経済が選挙結果に与える影響は,かなり限定されたものであると結論付ける。
1 0 0 0 OA 地域間格差をめぐるエリートの平等観
- 著者
- 久保 慶明
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.53-67, 2020 (Released:2023-11-16)
- 参考文献数
- 73
本稿では,地方政治に関わるエリートの地域格差に対する認知,格差是正をめぐる争点態度,それらに応じたネットワークの相互関係を記述する。第一に,現代日本では地域格差があると認知するエリートが多く,その認知は政治参加の機会より結果の格差を感じる人ほど強い。ただし,首長や保守政治家の格差認知は相対的に弱い。第二に,中央の行政官僚に比べて政治家は,国政でも地方でも格差是正に積極的である。ただし,機会格差をめぐる党派的対立と結果格差をめぐる中央地方間の対立が存在する。第三に,エリートの接触パターンは,地域格差全体の是正に消極的な与党ネットワーク,機会格差の是正に積極的な野党ネットワーク,結果格差の是正に積極的な地方ネットワークの3つに整理できる。第四に,格差是正をめぐる争点態度は格差認知に規定される。ただし,結果格差をめぐる争点態度は財政規律の影響を受けている。
1 0 0 0 OA 地方議員のなり手不足問題をどう考えるか
- 著者
- 河村 和徳
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.25-38, 2020 (Released:2023-11-16)
- 参考文献数
- 23
近年,地方議員のなり手不足は深刻化しており,2019年統一地方選は,それが重要な政治争点であることを明らかにした。本稿では,総務省が立ち上げた研究会の議論の動向やNHKが実施した地方議員に対する悉皆調査の結果を踏まえ,この問題を議論する。総務省の研究会は,地方議員のなり手不足に多様な要因があることを指摘するが,それらの中で最も重要なものは,「地方議員の待遇の悪さ」と「個人の選挙資源に依存する選挙環境」である。町村レベルでは,過去の経緯などから議員報酬の基準が低く抑えられており,自前主義の選挙環境や近年の政治情勢の影響を受け,候補者の発掘は困難な状況にある。これを克服する上で有効なのは「政党中心の選挙への転換」であるが,これに対して警戒感を持つ地方議員は少なくなく,地方議員のなり手不足の解決は一筋縄ではいかないことが指摘できる。
1 0 0 0 OA 英国・BREXITをもたらした国民投票における投票行動 離脱投票者・3つの底流
- 著者
- 富崎 隆
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.5-21, 2018 (Released:2021-07-16)
- 参考文献数
- 16
2016年6月23日に実施されたEU離脱を問う国民投票は,離脱勝利という結果を得た。本稿は,この歴史的な結果をもたらした有権者の民意と投票行動について,BES (British Election Study)の世論調査データを使用し,データをできるだけ豊富な形で紹介すると共に,国民投票がこの結果に至った要因について分析を試みる。社会的属性,経済・移民・主権問題といった争点,政治不信,ナショナリズム,メディア接触,政治指導者評価等の規定要因について個別に検討した上で,それらの要因を包括的に含んだ多変量モデルを構築する。次に,離脱派勝利には,異なる有権者像をもつ3つの底流があったとする仮説を提示し,実証結果を示す。