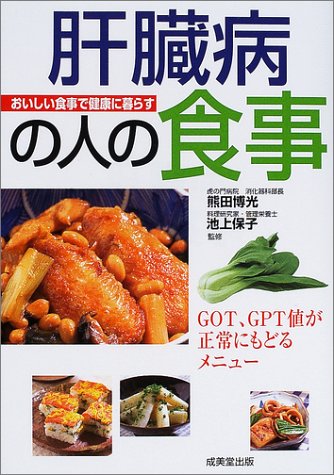- 著者
- Shintani E. Aoki S. Ishizuka N. Kanaya K. Kikukawa Y. Kuramashi Y. Okawa M. Taniguchi Y. Ukawa A. Yoshié T.
- 出版者
- American Physical Society
- 雑誌
- Physical review D (ISSN:15507998)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.014504, 2005-07
- 被引用文献数
- 47 51
We carry out a feasibility study for the lattice QCD calculation of the neutron electric dipole moment (NEDM) in the presence of the theta term. We develop the strategy to obtain the nucleon EDM from the CP- odd electromagnetic form factor F-3 at small theta, in which NEDM is given by lim(q2 -> 0 theta)F(3)(q(2))/(2m(N)), where q is the momentum transfer and m(N) is the nucleon mass. We first derive a formula which relates F-3, a matrix element of the electromagnetic current between nucleon states, with vacuum expectation values of nucleons and/ or the current. In the expansion of theta, the parity-odd part of the nucleon- current- nucleon three-point function contains contributions not only from the parity-odd form factors but also from the parity-even form factors multiplied by the parity-odd part of the nucleon two- point function, and, therefore, the latter contribution must be subtracted to extract F-3. We then perform an explicit lattice calculation employing the domain- wall quark action with the renormalization group improved gauge action in quenched QCD at a(-1) similar or equal to 2 GeV on a 16(3) x 32 x 16 lattice. At the quark mass m(f)a = 0: 03, corresponding to m(pi)/m(rho) similar or equal to 0:63, we accumulate 730 configurations, which allow us to extract the parityodd part in both two- and three- point functions. Employing two different Dirac gamma matrix projections, we show that a consistent value for F-3 cannot be obtained without the subtraction described above. We obtain F-3(q(2) similar or equal to 0:58 GeV2)/(2m(N))= -0:024(5) e . fm for the neutron and F-3(q(2) similar or equal to 0: 58 GeV2)/(2mN) = 0:021(6)e . fm for the proton.
2 0 0 0 肝臓病の人の食事 : GOT、GPT値が正常にもどるメニュー
- 著者
- 熊田博光 池上保子監修
- 出版者
- 成美堂出版
- 巻号頁・発行日
- 2002
2 0 0 0 MovieLens Dataにみる協調フィルタリングの失敗
- 著者
- 高橋 徹 小林 亜樹
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- 研究報告データベースシステム(DBS) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, no.26, pp.1-8, 2009-11-13
Web 情報システムにおける情報推薦では,協調フィルタリング技術がしばしば用いられている.本稿では,その推薦精度が必ずしも高くない理由について分析する.分析には,MovieLens Data Set を用いる.協調フィルタリング技術の,類似した嗜好を持つユーザは,未知の商品などのアイテムにおいても同様の嗜好を示す,という仮定がどの程度正しいか分析する.その結果,この仮定が成り立たない場合が相当程度ある事を明らかにし,また,cold-start 問題として知られる,嗜好が蓄積されていない状況と似ている事を指摘する.その後,これらの問題に対処するための考察を進める.Collaborative filtering techniques are often used to Information recommendation in the Web information system. In this paper, the reason why the recommendation precision is not always high is analyzed by using the Movie Lens data set. We think that collaborative filtering technique is based on a fundamental assumption. It is, if users had similar preference in an item set, it will be same as in other item sets. We show that the assumption is not approved in a respectable degree with similarity distribution histogram. Moreover, it is pointed out that the situation is similar to the cold-start situation, because of the same situation about user preference data is not available to collaborative filtering. Afterwards, it is considered to deal with these problems.
- 著者
- 寺田 敬志
- 出版者
- 日本臨床心理学会
- 雑誌
- 臨床心理学研究 (ISSN:00355496)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.p52-55, 1991-06
2 0 0 0 OA 2007年7月新潟県中越沖地震にみる災害リスクガバナンスの実践事例に関する調査報告
- 著者
- 永松伸吾
- 出版者
- 防災科学技術研究所
- 雑誌
- 防災科学技術研究所研究報告 (ISSN:13477471)
- 巻号頁・発行日
- no.72, 2008-02
2 0 0 0 OA モンテーニュとレトリックの伝統
- 著者
- 宇羽野 明子
- 出版者
- 政治思想学会
- 雑誌
- 政治思想研究 (ISSN:1346924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.77-94, 2001-05-10 (Released:2012-11-20)
2 0 0 0 OA 日清汽船株式会社三十年史及追補
- 出版者
- 日清汽船
- 巻号頁・発行日
- 1941
2 0 0 0 OA 第2回 NCの開発
- 著者
- 稲葉 清右衛門
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.483-483, 2004-04-05 (Released:2009-04-10)
- 著者
- 早乙女 理恵 宮里 智樹 玉城 史朗
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SAT, 衛星通信 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.299, pp.183-187, 2007-10-25
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 2
沖縄県は亜熱帯気候の島嶼地域であり、東西南北に広く島が点在している。そのため、高速インターネット網が行き届いていない地域(デジタル・ディバイド)が多くある。その地域を救済するには、Ka帯衛星通信WINDSやFWAの様な、高帯域化が容易な準ミリ波帯無線通信を使用することが必要となる。使用周波数帯はと周波数が高いため降雨による電波の減衰(降雨減衰)が無視できない。降雨減衰によっての通信品質の補償についての技術は、長年研究されてきた。しかしながら、衛星通信分野での研究は、Kuバンドがメインであった。したがって、Ka帯の地上波通信および衛星通信での降雨減衰特性の調査事例はまだほとんどない。18GHz帯と26GHz帯FWAを用いた伝搬実験が、津堅島と琉球大学間(約17Km)で行われ、貴重なデータを取得することが出来た。本研究では、実証実験を通して得られた知見を発展させて時系列解析手法を用いた降雨減衰特性ついて検討し、台風などの豪雨による比較的短時間の減衰特性モデルを提案する。
2 0 0 0 OA 笑い声の母音と諸言語の形容詞にふくまれている母音との共通性の研究
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1086, pp.64-68, 2001-04-09
世界中で年に6000万台売れる巨大商品となった、インクジェットプリンター。日本ではセイコーエプソン(長野県諏訪市)が1994年にこの方式を使った低価格のカラープリンターを大ヒットさせて以来、家庭でパソコンを使うには欠かせない周辺機器として定着した。
- 著者
- 高田 篤
- 出版者
- 日独文化研究所 ; 2008-
- 雑誌
- 文明と哲学 = Zivilisation und Philosophie : 日独文化研究所年報
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.74-85, 2012
2 0 0 0 アミ語の記述言語学的研究
4月にイギリスで行われた国際学会、International Conference on Tense,Aspect,Modality and Evidentialityにおいて、アミ語の動詞・名詞と状態アスペクトの関係について学会発表を行った。ここではフィールド調査によって得たデータをもとに、品詞とアスペクトの関係について論じた。その後帰国してすぐに、浜松で行われた学会The English Linguistic Society of Japan 4^<th> International Spring Forumに参加し、アミ語のデータも交えた複数の言語における使役文の特徴について、類型論的な研究発表をおこなった。また、5月には東京外国語大学で行われた第1回文法研究ワークショップ「『形容詞』をめぐる諸問題」で、上記のイギリスで発表した内容に改訂をくわえたものの発表を行った。7月には香港で行われたAssociation for Linguistic Typology 9^<th> Biennial Conferenceで、「雨降り」「肩たたき」などの複合語や、名詞を動詞に組み込む「抱合」と言われる現象について発表を行った。これらの現象では自動詞の主語と他動詞の目的語のみが許容され、他動詞の主語は許容されないという現象が世界各地の言語で見られる。この発表ではなぜそのような現象が世界の言語で現れるのか、その原因について考察を行った。11月には第143回言語学会において、『アミ語の母音連続と挿入規則』というタイトルの口頭発表を行った。この発表では、フィールド調査で得たデータをもとに、従来音素として考えられてきたアミ語の声門閉鎖音を音素ではないと分析し、音素同士の関係と挿入規則のみで声門閉鎖音の存在を説明する試みを行った。また、上記の発表活動と並行して、手持ちのデータの分析(音声データの書き起こしなど)と、博士論文の執筆を行った。
2 0 0 0 OA 夏休み工作のためのフィジカルコンピューティング : 付録:あから2010ペーパークラフト
- 雑誌
- 情報処理
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.8, 2011-07-15
2 0 0 0 OA 戦時下の少年犯罪とその防止
- 著者
- 刑務教誨司法保護事業研究所 編
- 出版者
- 大道書房
- 巻号頁・発行日
- 1942
2 0 0 0 OA フランス絶対王政期の軍隊と社会 : 補給問題を中心に
- 著者
- 佐々木 真
- 出版者
- 駒澤大学
- 雑誌
- 駒澤大學文學部研究紀要 (ISSN:04523636)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.A11-A35, 1998-03
2 0 0 0 OA スペイン継承戦争とフランドル地方
- 著者
- 佐々木 真
- 出版者
- 駒澤大学
- 雑誌
- 駒澤史学 (ISSN:04506928)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.82-100, 2002-07