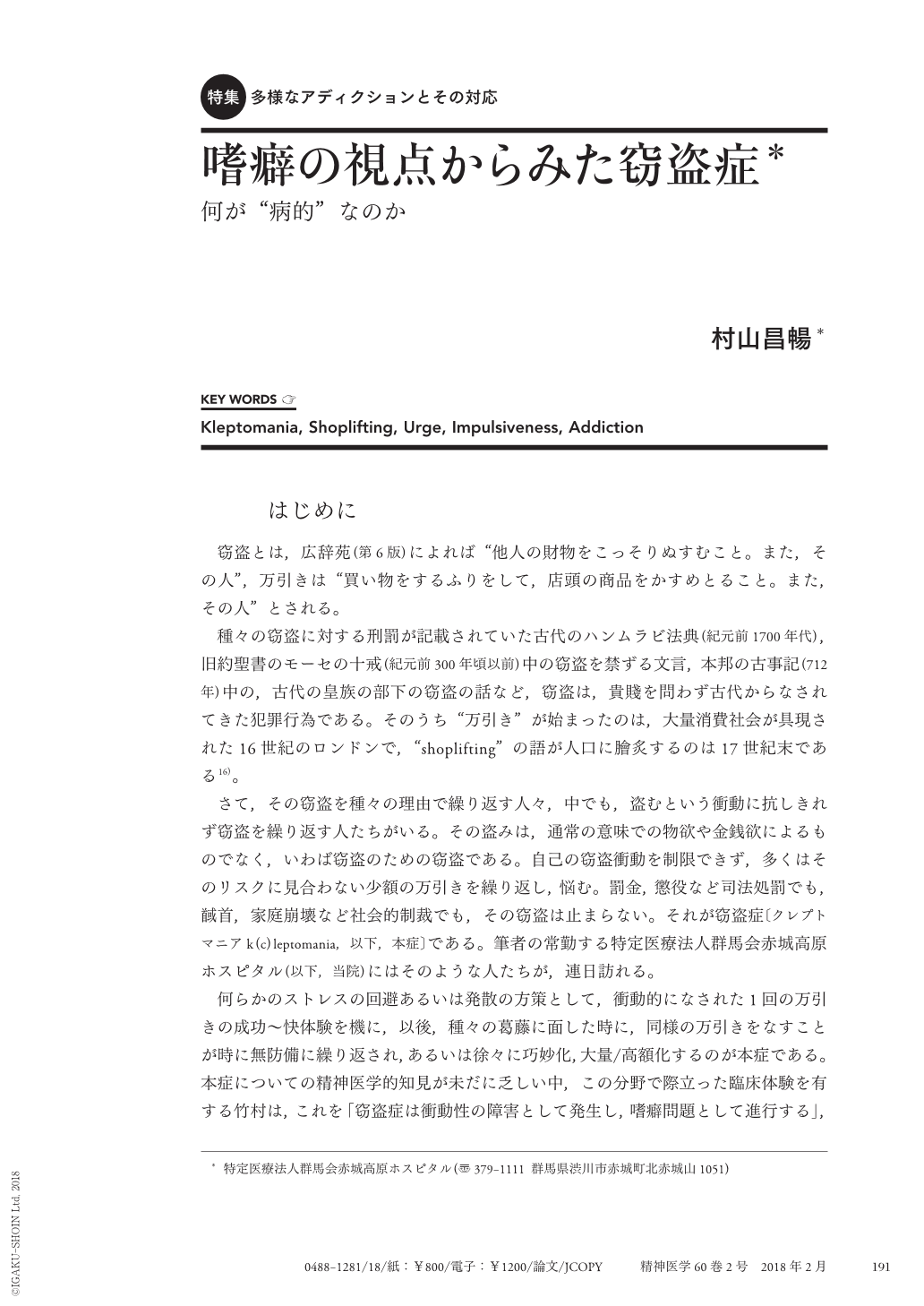1 0 0 0 OA 水滸伝 : 標註訓訳
1 0 0 0 OA 水滸伝 : 標註訓訳
1 0 0 0 OA 水滸伝 : 標註訓訳
1 0 0 0 OA 水滸伝 : 標註訓訳
1 0 0 0 OA 水滸伝 : 標註訓訳
1 0 0 0 OA 水滸伝 : 標註訓訳
1 0 0 0 OA 水滸伝 : 標註訓訳
1 0 0 0 OA 水滸伝 : 標註訓訳
1 0 0 0 OA 水滸伝 : 標註訓訳
1 0 0 0 OA 水滸伝 : 標註訓訳
- 著者
- Mona UCHIDA Aki OHMI Reina FUJIWARA Kenjiro FUKUSHIMA Akihiro DOI Kazushi AZUMA Hajime TSUJIMOTO
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.19-0605, (Released:2020-07-13)
- 被引用文献数
- 2
Two dogs with immune-mediated hemolytic anemia complicated with thromboembolism were presented. Both of the dogs were initially treated with immunosuppressive therapy in conjunction with dalteparin and clopidogrel. Although the immunosuppressive therapy was effective, peritoneal effusion due to thromboembolism was observed during the course of the disease in these dogs. After initiation of rivaroxaban treatment, peritoneal effusion decreased immediately in parallel with the normalization of D-dimer, antithrombin (AT), and thrombin-antithrombin complex (TAT). Hematochezia, cutaneous hemorrhage, and hematuria were observed as adverse events after administration of rivaroxaban in one case. Rivaroxaban was effective for the control of thromboembolism secondary to immune-mediated hemolytic anemia, and D-dimer, AT, and TAT were useful to monitor the status of thromboembolic disease in dogs.
1 0 0 0 OA 中切歯,側切歯および第一大臼歯の萌出パターンについて
- 著者
- 塩田 亜梨紗 翁長 美弥 恩田 智子 唐木 隆史 小平 裕恵 菊池 元宏 朝田 芳信
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.375-381, 2017-06-25 (Released:2018-07-23)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
下顎における中切歯,側切歯および第一大臼歯の萌出パターンに関して,1980年以前は下顎第一大臼歯が,1980年以降は下顎中切歯が最も早く萌出するとする報告が続き,1980年を境に下顎永久歯の萌出パターンが変化した可能性があることが示唆されていた。そこで,最新の中切歯,側切歯,第一大臼歯の萌出パターンを知ることを目的に,乳歯列期からHell man's Dental Age III B期までの患児105名を対象に,永久歯の萌出パターンを縦断調査したところ,以下の結果を得た。1.萌出パターンは,男女間差,左右間差は共に認めらなかったが,上下間に有意差を認めた。2.上顎で最も多かった萌出パターンは【6(第一大臼歯)1(中切歯)2(側切歯)】,下顎で最も多かった萌出パターンは【162】であった。3.上顎は【126】と【162】間,下顎は【162】と【612】間に有意差を認めなかった。4.下顎中切歯が最初に萌出した群と下顎第一大臼歯が最初に萌出した群間における歯冠近遠心径を比較したところ,上顎側切歯において有意差を認めた。以上のように,少なくとも下顎で最初に萌出する歯種に有意差は認めず,萌出パターンに関しては現時点で変化したと断定するのは時期尚早であることが示唆された。また,歯冠近遠心径と萌出順序の関連性も疑われるが,さらに継続して研究を続ける必要があることが示唆された。
1 0 0 0 OA 小児における口唇閉鎖力と齲蝕の罹患ならびに口唇閉鎖習慣に関連する臨床研究
- 著者
- 岸 岳宏 塩野 康裕 佐伯 桂 谷口 礼 森川 和政 牧 憲司
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.458-466, 2017-11-25 (Released:2018-11-25)
- 参考文献数
- 34
咬合誘導や矯正治療の領域において,口腔周囲の軟組織の客観的な評価方法については一般的な手法として普及している評価方法は確立されていない。そこで我々は客観的評価の確立や臨床病態把握への応用を目的として,正常咬合児と上顎前突児の口唇閉鎖力について多方位的に測定を行った。あわせて舌圧にも着目し比較検討を行った。また,齲蝕の罹患状況とアンケート調査による患児の日常的な口唇閉鎖習慣状況についても評価を行った。調査の対象は九州歯科大学付属病院を受診した8 歳から11 歳までの小児期の患者から正常咬合者15 名,上顎前突者15 名とした。多方位口唇閉鎖測定装置の結果から,正常咬合児の方が総合的な口唇閉鎖力が上顎前突児に比較して有意に大きいことが分かった。両群間に多方位的な口唇閉鎖力の有意な差は認められなかった。舌圧の測定からも両群間に有意な差は認められなかった。舌圧と口唇閉鎖総合力の相関についても相関関係を認められなかった。齲蝕の罹患状況については正常咬合児と上顎前突児に有意差を認めなかった。総合口唇閉鎖力と齲蝕の罹患状況の相関関係は正常咬合児が相関関係を認めなかったのに対して,上顎前突児では負の相関関係が認められた。質問紙調査による口唇閉鎖習慣の評価では,上顎前突児は日常的に口が開きやすいことが分かり,アレルギー体質と上顎前突の関連は認められなかった。以上の結果から,上顎前突児の口唇閉鎖力は上口唇と下口唇の多方位的な口唇閉鎖力の不釣合いよりも,口唇全体の総合的な口唇閉鎖力の脆弱さにより関連していることが今回の研究より示唆された。また,上顎前突児は口唇閉鎖力の脆弱さが齲蝕の罹患原因の一つになっていることが示唆された。質問紙調査では上顎前突児が必ずしも鼻閉による口唇閉鎖不全を伴わない事が示唆された。
1 0 0 0 OA 上顎前歯部埋伏過剰歯が上顎中切歯に及ぼす影響について
- 著者
- 佐野 哲文
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.419-426, 2017-11-25 (Released:2018-11-25)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
埋伏過剰歯は上顎前歯部に好発し,歯列不正などの一因となりうる。しかし,埋伏過剰歯が隣在歯の位置にどのような影響を及ぼすかについての検討は不十分である。そこで,conebeam computed tomography (CBCT)画像をもとに埋伏過剰歯と上顎中切歯の位置関係について統計学的に検討した。 平成25 年10 月から1 年1 か月の間に,上顎前歯部埋伏過剰歯と診断された5~8 歳の小児34 名の34 歯を用いた。 評価項目として,埋伏過剰歯の歯軸方向,垂直的位置,中切歯歯軸傾斜角度,埋伏過剰歯と中切歯間および埋伏過剰歯と口蓋部骨表面間の距離を検討した。 埋伏過剰歯の垂直的位置は,上顎歯槽骨頂から鼻腔底下縁最上方点と最下方点を結ぶ直線(鼻腔底下縁線)までの距離を3 等分し,鼻腔底下縁線から上,中,下位の範囲1/3 をそれぞれPosition 1, 2, 3 とした。 また埋伏過剰歯に近い上顎中切歯を患側中切歯,反対側を健側中切歯とした。矢状面断における鼻腔底下縁線を基準線とし,患側または健側中切歯の歯軸となす角度を各々患側・健側中切歯歯軸傾斜角度とした。 埋伏過剰歯は,逆生と順生が各々24 例と10 例であった。患側中切歯歯軸角度と健側のそれとの間には,有意な差があった。患側と健側の中切歯歯軸傾斜角度の差は各Position 間では有意な差はなかった。 埋伏過剰歯と中切歯間の距離は,埋伏過剰歯がPosition 2 に存在する例と比較してPosition 3 に存在する例で有意に大きかった。また埋伏過剰歯と口蓋部骨表面間の距離は,埋伏過剰歯がPosition 1 に存在する例はPosition 3 に存在する例より有意に大きかった。
1 0 0 0 OA 乳歯列期における上唇小帯の形態と付着位置に関する調査研究
- 著者
- 鈴木 冴沙 髙原 梢 酒井 暢世 鈴木 伸江 稲永 詠子 菊池 元宏 朝田 芳信
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.444-450, 2019-11-25 (Released:2020-01-31)
- 参考文献数
- 24
著者らは上唇小帯の切除に対する治療方針決定の一助となることを目的に,3 歳から5 歳までの幼稚園児あるいは保育園児448 名を対象に,上唇小帯の形態と付着位置の変化について正常型および異常型(以下Ⅰ型からⅤ型)に分類したところ,以下の結果を得た。1 .上唇小帯の正常型と異常型の出現率は,すべての年齢において正常型は異常型に比べて高値を示したが,増齢的に正常型の割合は減少した。2 .各異常型の出現率は,Ⅰ型がすべての年齢において最も高かった。Ⅱ型はすべての年齢においてⅠ型に次いで高く,増齢的な増減の方向性は認められなかった。Ⅲ型は,増齢的に倍以上に増加した。Ⅳ型は増齢的な増減の方向性は認められなかった。Ⅴ型は5 歳で出現が認められた。3 .正常型と異常型(Ⅰ型,Ⅱ型,高位付着肥厚型)の出現率は,3 歳において正常型が有意に高く,高位付着肥厚型が有意に低く,5 歳において高位付着肥厚型の出現率が有意に高い傾向にあった。 これらより,3 歳では異常型の主体がⅠ型とⅡ型であり,変動しにくい型であるⅣ型とⅤ型ではないことから,上唇小帯異常が認められたとしても経過観察を行うことが適切であると考えられた。5 歳では高位付着肥厚型の出現率が高い傾向にあるため,上唇小帯異常が継続する可能性が考えられることから,永久前歯交換期に認められる正中離開や口唇閉鎖機能に影響を及ぼすことを念頭に置いた対応が求められることが示唆された。
1 0 0 0 OA 農作物の自動潅水制御に向けたニューラルネットワークを用いたQ学習
- 著者
- 難波 脩人 辻 順平 能登 正人
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第33回全国大会(2019)
- 巻号頁・発行日
- pp.1F3OS17a04, 2019 (Released:2019-06-01)
近年,熟練農家の知見を再現するために教師あり学習を用いた研究が盛んにおこなわれている.一方で,農業のような複雑な要因が絡む作業において農家が行っている農作業が最適かどうか判断することは困難であり,農家の知見から集めた訓練データを用いて学習した結果が最適解かどうかの判断は難しい.我々は熟練農家の知見に依存せずに学習を実行する強化学習によって栽培の最適化を行うことを目的とした.植物に対して強化学習を適用する際に重要な点として状態の定義があげられる.植物の状態は時間とともに変化することから同じ状態は1試行の中に1度しか現れず,Qテーブルを作成することが現実的ではない.また,植物は短期間に何度も栽培できないため,学習に必要なデータが十分に集まらず,学習が収束しない恐れがある. 本研究ではQ関数の作成にニューラルネットワークによる関数近似を用いる手法を採用した.さらに,学習が収束しない可能性を考慮し,experience replayによる過去の経験を再利用することでデータ数の少なさをカバーした.結果として,植物は自らの背丈に合わせて潅水量を決定する行動をとる様子が確認できた.
1 0 0 0 OA 社会と組織の脱中心化と機微情報認識について
- 著者
- 小笠原 泰
- 出版者
- 一般社団法人 経営情報学会
- 雑誌
- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2017年春季全国研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.209-212, 2017 (Released:2017-05-31)
SNSやUberに代表されるE2Eのマッチングプラットフォーム、技術としてはブロックチェーンに代表されるような脱中心的なシステムの一般化によって、末端と末端によって支えられるアーキテクチュア内における信頼構造が「シェア」をキーワードとして確立されていく中で、その信頼によって享受されるメリットに相応して、参加者のプライバシーに関する認識がどのように変化し、延いては、その信頼構造を維持するシステムの形態がどのようになるかについての詩論的考察を行う。
1 0 0 0 竹林再生のための乳酸発酵用高速竹粉製造機の開発
- 著者
- 佐野 孝志 仁多見 俊夫 酒井 秀夫
- 出版者
- 森林利用学会
- 雑誌
- 森林利用学会誌 (ISSN:13423134)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.34.37, 2019-01-31 (Released:2019-03-08)
- 参考文献数
- 10
本研究は林業界の課題となっている竹林の放置・荒廃の問題に着目し,その利用によって地域資源として再生を図るべく,竹から乳酸発酵竹粉を製造する高性能機械を開発した。製造された竹粉は,300-400μm程度の粒度で,内部に多孔質を持ち,竹由来の乳酸菌が生息する。この乳酸発酵竹粉を農業資材としての効果の実証をし,売れる商品としてのビジネスモデルを構築した。機械の製造能力300tに対し,年間50t の製造販売で,販売価格を現在の市況価格300 円/kg を200 円/kg に下げても136万円の粗利となる。年間100t になれば年間747万円の粗利で,約2年で機械費1500万円が回収出来ることになる。竹林伐採(1次)・竹粉製造(2次)・竹粉販売(3次)の6次産業化を実践し,将来は工業製品までの用途開発を進めて,バイオマス活用の新事業創出による地域活性化に役立つ可能性があり,開発した機械はトラック搭載してモバイル機構化し,林道上で竹粉化処理も検討に値する。
1 0 0 0 嗜癖の視点からみた窃盗症—何が“病的”なのか
はじめに 窃盗とは,広辞苑(第6版)によれば“他人の財物をこっそりぬすむこと。また,その人”,万引きは“買い物をするふりをして,店頭の商品をかすめとること。また,その人”とされる。 種々の窃盗に対する刑罰が記載されていた古代のハンムラビ法典(紀元前1700年代),旧約聖書のモーセの十戒(紀元前300年頃以前)中の窃盗を禁ずる文言,本邦の古事記(712年)中の,古代の皇族の部下の窃盗の話など,窃盗は,貴賤を問わず古代からなされてきた犯罪行為である。そのうち“万引き”が始まったのは,大量消費社会が具現された16世紀のロンドンで,“shoplifting”の語が人口に膾炙するのは17世紀末である16)。 さて,その窃盗を種々の理由で繰り返す人々,中でも,盗むという衝動に抗しきれず窃盗を繰り返す人たちがいる。その盗みは,通常の意味での物欲や金銭欲によるものでなく,いわば窃盗のための窃盗である。自己の窃盗衝動を制限できず,多くはそのリスクに見合わない少額の万引きを繰り返し,悩む。罰金,懲役など司法処罰でも,馘首,家庭崩壊など社会的制裁でも,その窃盗は止まらない。それが窃盗症〔クレプトマニアk(c)leptomania,以下,本症〕である。筆者の常勤する特定医療法人群馬会赤城高原ホスピタル(以下,当院)にはそのような人たちが,連日訪れる。 何らかのストレスの回避あるいは発散の方策として,衝動的になされた1回の万引きの成功〜快体験を機に,以後,種々の葛藤に面した時に,同様の万引きをなすことが時に無防備に繰り返され,あるいは徐々に巧妙化,大量/高額化するのが本症である。本症についての精神医学的知見が未だに乏しい中,この分野で際立った臨床体験を有する竹村は,これを「窃盗症は衝動性の障害として発生し,嗜癖問題として進行する」,と表現している20)。 現在,本症に対しては,Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(DSM)とInternational Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems(ICD)での診断基準が広く使われている。両者は,合併症,鑑別診断での違いもあるが,内容の大部分は共通しており,ともにこの“当人の立場に鑑みて,割に合わない”,“異常な衝動性”およびその衝動性による問題行動が“繰り返し現れる”という“病的な習慣性”に焦点を当てた診断基準であると考える4,24)。 本稿では,過去の国内外の代表的なテキストや,現在の国際的診断基準におけるこの障害の記述を振り返りながら,また,当院での臨床体験も踏まえ,本症の本質を論じてみたい。 本症は,ギャンブル障害,インターネット使用障害,買い物嗜癖,性嗜癖,摂食障害などとともに,精神医学的には行動嗜癖の一つとされる。精神障害としての常習窃盗,クレプトマニアは古くからある病名であるが,行動嗜癖の中でも最も治療体験と研究の蓄積が少なく,実態の解明が遅れている。当院とその関連医療施設の京橋メンタルクリニックでは,常習窃盗症例の登録システムを構築しており,両医療施設で筆者らが診療しあるいは相談にかかわった症例は2008年1月から2017年10月の9年10か月で1,700例に達した。なお,クレプトマニアの邦訳名としては,“病的窃盗”,“窃盗癖”などが使われてきたが,アメリカ精神医学会による『DSM-5精神疾患の診断・統計のマニュアル』(2013)では,日本精神神経学会によって新しく“窃盗症”が採用された。以下,本稿でもこの“窃盗症”を用いるものとする4)。 一般的に常習窃盗は,①経済的利益のために金目の物品や金銭を盗む職業的犯罪者,②飢えて食物や生活必需品を盗む貧困者,③金があるのに些細なものを盗む病的窃盗者,の三種類に大別される。もちろん現実にはこれら三種の境界型,混在型,移行途上型など分類困難なタイプや,これら以外の熱狂的なコレクター(収集狂,蒐集嗜癖)や知的障害による常習窃盗も存在する。日常用語になった感のある日本語の“窃盗癖”は,広く②,③型両者の常習窃盗を意味し,必ずしも③型窃盗と同等ではない。本稿では,窃盗症は③型窃盗の一部であって,DSM-5の診断基準によって精神障害と診断される常習窃盗とする21)。