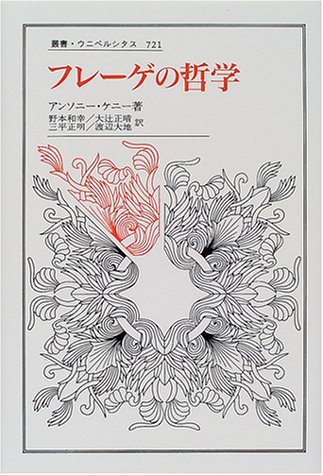1 0 0 0 OA 朝日新聞大阪本社所蔵 「富士倉庫資料」(写真) -インドシナ関係解説-
- 著者
- 菊池 陽子
- 出版者
- 早稲田大学アジア太平洋研究センター
- 雑誌
- 研究資料シリーズ (ISSN:21851301)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.14-86, 2017-03-31
朝日新聞大阪本社所蔵 「富士倉庫資料」(写真) 東南アジア関係一覧
1 0 0 0 古記録にみる歌謡記事
- 著者
- 辻 浩和
- 出版者
- 日本歌謡学会
- 雑誌
- 日本歌謡研究 (ISSN:03873218)
- 巻号頁・発行日
- no.59, pp.1-11, 2019-12
1 0 0 0 OA 刑罰権の及ぶ範囲と罪刑法定主義
- 著者
- 稲垣 悠一
- 出版者
- 専修大学法科大学院
- 雑誌
- 専修ロージャーナル = Senshu Law Journal (ISSN:18806708)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.115-165, 2014-12-19
1 0 0 0 OA (1)大学理学専攻科教育における現状と課題
- 著者
- 加藤 竜吾
- 出版者
- 東京理科大学
- 雑誌
- 理学専攻科雑誌 (ISSN:02864487)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.29-32, 1997-10-31
本稿では、大学専攻科の課程に着目し、特に戦後大学理学部に設置されている理学専攻科の現状とその役割、又、理学系を中心に現在整備が進みつつある大学院との関係について、調査、研究を行った結果についてまとめ今後21世紀における大学理学専攻科のあり方について述べてみたい。なお、本研究は数学や数学教育に関する研究ではありませんが、数学等理数系教員養成教育のあり方ということで、理学専攻科との関わりが深い理数研における発表としてお許し頂きたく、又、創立40周年を迎える理数研の歴史的資料の一助となればと思います。この要旨は、本年7月の月例会と8月の日数教群馬大会高専大学部会での発表資料をまとめ直したものです。
- 著者
- 南條 壮汰 佐藤 夏雄 穂積 裕太 細川 敬祐 片岡 龍峰 三好 由純 大山 伸一郎 尾崎 光紀 塩川 和夫 栗田 怜
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-13
国際宇宙ステーション(International Space Station: ISS)に搭載されたデジタル一眼レフカメラ(デジカメ)を用いて、オーロラの連続カラー画像が撮影されており、NASA のウェブサイトで公開されている。我々は、それらの画像の中でも、オーロラの高さ構造を同定できる地球をリム方向に撮影した画像を解析的研究に活用することを提案してきた [Nanjo et al., 2020, submitted]。ISS は約 90 分の周期で地球を周回しているため、MLT 方向に 4-5 時間程度のオーロラの大規模な構造をスナップショットとして観測することができる。大規模構造の一例として、オーロラオーバルの朝側領域において、輝度の高い領域が波を打ったような構造になるオメガバンドが広く知られている。これまでに、オーロラを真下/真上から撮影する様々な地上/衛星観測によりオメガ構造の西側(夜側)は東側(朝側)に対して輝度が高くなることが指摘されている [e.g. Opgenoorth et al., 1994; Amm et al., 2005]。しかし、これらの観測はオーロラを二次元的に捉えるため、高さ構造については明らかにされてこなかった。ISS のリム方向デジカメ観測では、オーロラを斜めに捉えているため、高さ構造を識別できる。その結果、いくつかの事例でオメガ構造の明るい領域の西端と暗い領域の境界線上に、南北方向に 300-600 km 伸びる高さ 200-300 km 程度の壁状のディスクリートオーロラ( “Great Wall” )が存在することがわかった。図に示す通り、Great Wall は、底部が緑色で、上部が赤色に発光する。また、Great Wall は南北半球で共通する現象であることもわかった。磁力線方向に伸びる赤と緑の発光は、広いエネルギー帯の電子が加速されていることを意味するが、これは Amm et al. (2005) の UV 観測で見積もられた降り込みエネルギーの 2-5 keV という狭い範囲の数値とは一致しないものである。これは、彼らが用いた観測機器の時空間分解能が低く、Great Wall の部分を切り分けることが難しかったためであると考えられる。また、オメガ構造の内部では、活発な脈動オーロラが観測されることが多いが、THEMIS 衛星との同時観測により、これらがコーラス波動との波動粒子相互作用により降り込む典型的な脈動オーロラであることがわかった。大会では、オメガ構造に現れる Great Wall を作る電子のエネルギー帯やそれらから示唆される磁気圏-電離圏結合系の電流系ついて議論を行う予定である。
1 0 0 0 OA 国際宇宙ステーションからのデジカメ観測が示唆する脈動オーロラの広域空間特性
- 著者
- 南條 壮汰 穂積 裕太 細川 敬祐 片岡 龍峰 三好 由純 大山 伸一郎 尾崎 光紀 塩川 和夫 栗田 怜
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-13
国際宇宙ステーション(International Space Station: ISS)から、デジタル一眼レフカメラ(デジカメ)を用いて都市や海洋、大気などの様子が撮影され、連続カラー画像が NASA のウェブサイトで公開されている。我々は、公開されている画像の中にオーロラが含まれているものを抽出し、背景として写っている街明かりをマーカーにして地理座標上に投影することによって、オーロラの研究、特に脈動オーロラの広域特性の解析に活用することを提案してきた [Nanjo et al., 2020, submitted]。この ISS からのデジカメ観測は 1 秒以下の時間分解能と、地上全天カメラ 3-4 台分の広い視野を持ち、約10分の間にローカルタイム方向に 4-5 時間分に相当する領域を俯瞰的に撮像することができる。脈動オーロラの明滅周期は 2-40 秒、空間スケールは数 10 km 程度であるため、投影されたデジカメ画像によって、脈動オーロラの時間変動・空間変動の双方を十分に分解することが可能である。本研究では、複数の脈動オーロライベントについて投影された連続画像から明滅周期を導出し、その MLT 依存性についての解析を行ったが、明滅周期が MLT に依存しているという傾向を、すべてのイベントに共通するものとして見いだすことはできなかった。次に、デジカメ画像が RGB の 3 チャネルを持つことに着目し、色の違いについての解析を行った。オーロラの色と RGB チャネルの関係は、最も明るい酸素原子の発光である 557.7 nm が G チャネルに対応し、427.8 nm を代表とする窒素分子のバンド発光が B チャネルに対応すると考えられる。窒素分子を発光させる電子のエネルギーは、酸素原子を発光させる電子のそれに比べて相対的に高いため、B チャネルと G チャネルの輝度の比(B/G 比)を用いて降込電子の特性エネルギーに関する情報が得られるのではないかと考え、複数例について B/G 比の解析を行った。その結果、B/G の比は、1) ディスクリートオーロラの領域よりも脈動オーロラの領域において高くなること、2) 脈動オーロラの OFF-time (暗いタイミング)に対して ON-time (明るいタイミング)で高くなること、3) 真夜中よりも朝側の MLT で高くなること、がわかった。これらの結果は、脈動オーロラ電子のエネルギーについてこれまでに知られている傾向と一致するものであり、デジカメで得られた B/G 比を降込電子エネルギーのプロキシとして使用できることを示唆している。本大会では、ここで得られた結果の背景にあるプロセスを、脈動オーロラとの関連が指摘されているコーラス波動の特性を踏まえて議論する。
1 0 0 0 フレーゲの哲学
- 著者
- アンソニー・ケニー [著] 野本和幸 [ほか] 訳
- 出版者
- 法政大学出版局
- 巻号頁・発行日
- 2001
1 0 0 0 OA コギトと超越論的主観性
- 著者
- 斎藤 慶典
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, no.48, pp.1-18, 1997-05-01 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 6
古代から現代にいたるまでの哲学は、自我ないし人格の問題を、それぞれの時代に応じて、その時代に特有の概念装置を通して、思い考えかつ生きていた。自我・人格は、ときに「魂」であり、「小宇宙」であり、また「社会契約」の主体であり、「知覚の束」であった等々。自我の同一性という古くまた新しい問題をめぐって、「実体」「因果」「反省」等の概念が交錯する。これらの思考の遺産を、今日的状況の中から、 (ときに東洋的思考の伝統との接点をさぐりながら) 、あらためて根底にたちかえって検討してみたい。
1 0 0 0 OA 大学運動部のあり方 ―「文武両道」のためのプログラム―
- 雑誌
- 九州情報大学研究論集 = Bulletin Kyushu Institute of Information Sciences
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.111-115, 2015-03
1 0 0 0 OA 日本文化論から見る日本語表現の論理(第Ⅲ部 文献研究)
- 著者
- 小野 正樹
- 出版者
- 日本語コミュニケーション研究会
- 雑誌
- 日本語コミュニケーション研究論集 (ISSN:21865655)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.87-96, 2018
1 0 0 0 宮中仏事に関する覚書--中世前期を中心に
- 著者
- 海老名 尚
- 出版者
- 学習院大学
- 雑誌
- 学習院大学文学部研究年報 (ISSN:04331117)
- 巻号頁・発行日
- no.40, pp.p63-118, 1993
1 0 0 0 IR 和辻哲郎の言語哲学 : 「日本語で哲学する」ことの前提認識をめぐって
- 著者
- 飯嶋 裕治
- 出版者
- 九州大学哲学会
- 雑誌
- 哲学論文集 (ISSN:0285774X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.61-84, 2015-09
1 0 0 0 IR 哲学と二つの言語
- 著者
- 清水 真木
- 出版者
- 明治大学教養論集刊行会
- 雑誌
- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)
- 巻号頁・発行日
- no.436, pp.1-19, 2008-09
日本語の「哲学」という名詞、そして、明治以降、「哲学」という言葉によって日本語に置き換えられてきた西洋近代各国語の語彙に含まれるphilosophy、philosophieなどの言葉が使われる文脈は、大きく二つに分かたれる。すなわち、一方において、「哲学」は、専門的な学問分野としての哲学を指し示すために使用される。しかし、他方において、「哲学」という言葉が、通俗的な意味を担う場面もまた、少なくはない。たとえば、「あの人には哲学がない」「松下幸之助の経営哲学」などの表現に含まれる「哲学」という言葉は、哲学史を構成する哲学、つまり、学問としての哲学、あるいは学問的であることを目指す活動としての哲学を意味するものではない。
1 0 0 0 IR 言語と哲学--日本語の哲学的効用
- 著者
- 雨宮 民雄 Tamio Amemiya
- 出版者
- 東京海洋大学
- 雑誌
- 東京海洋大学研究報告 (ISSN:18800912)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.5-12, 2007-03
東京海洋大学海洋科学部海洋政策文化学科
1 0 0 0 IR 日本語の七層と現象学的優位 --日本語で哲学する--(前)
- 著者
- 平田 俊博
- 出版者
- 京都大学大学院文学研究科日本哲学史研究室
- 雑誌
- 日本哲学史研究 : 京都大学大学院文学研究科日本哲学史研究室紀要 = Studies in Japanese Philosophy : Nihon Tetsugakushi Kenkyu
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.1-19, 2005-09-05
1 0 0 0 IR 日本語と哲学--日本語の形而上学的性格
- 著者
- 奥村 一郎
- 出版者
- 上智大学神学会
- 雑誌
- カトリック研究 (ISSN:03873005)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.p251-280, 1976-12
1 0 0 0 IR 日本語における哲学的思考の可能性について (1)
- 著者
- 下野 正俊
- 出版者
- 国士舘大学哲学会
- 雑誌
- 国士舘哲学 (ISSN:13432389)
- 巻号頁・発行日
- no.2, 1998-03
- 著者
- 渡辺 治
- 出版者
- 校倉書房
- 雑誌
- 歴史評論 (ISSN:03868907)
- 巻号頁・発行日
- no.711, pp.69-78, 2009-07
- 著者
- 早稲田 みな子
- 出版者
- 社団法人 東洋音楽学会
- 雑誌
- 東洋音楽研究 (ISSN:00393851)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.67, pp.61-80,L7, 2002
The contact that immigrants maintained with their homeland is one of the important determinants of the immigrant culture. However, this factor has been rarely emphasized in the studies on immigrant cultures as well as on Japanese Americans. The studies on immigrant cultures tended to focus on the interplay of cultural elements originating from the host society and those the immigrants bring from their home, while the studies on Japanese Americans tended to emphasize a process of Japanese American's Americanization, acculturation, and their upward movement toward the America's middle class through the successive generations. This study attempts to focus on the element undervalued in these past studies —a tie between immigrants and their home culture —to gain new insights into the Japanese American musical culture in pre-World War II southern California.<br>The Japanese immigrants in pre-World War II southern California maintained close contact with their home culture through the successive waves of touring Japanese artists from Japan who performed and/or taught their musical arts in the United States. This study views these Japanese performance artists as “cultural ambassadors, ” and examines their roles and influences in the immigrant community.<br>There were two major forces that attracted a large number of touring Japanese artists to the United States. One was the Japanese artists' own ambitions to achieve some success outside Japan. The other was the Japanese immigrants' strong attachment and longing for their home country. Coming from nationalist Japan of the Meiji period (1868-1912) and encountering racism and cultural conflict in the foreign country, the Japanese immigrants reinforced their Japanese identity and looked toward Japan as their authentic cultural model.<br>In this pro-Japan immigrant community, the touring Japanese artists played the following three major roles to affect the immigrant musical culture:<br>1) The role as a provider of contemporary Japanese musical arts and entertainment.<br>Through the overseas performances by the Japanese artists, Japanese immigrants were able to enjoy the musical arts and entertainment that were popular in Japan at that time, and thus, they could maintain an intimate cultural tie with “contemporary” Japan.<br>2) The role as a teacher and promoter of Japanese performance arts.<br>Some of the Japanese artists not only performed, but also taught their arts to the Japanese immigrants, and sometimes even organized the local performance groups within the immigrant community. There were artists who were invited from Japan as instructors for the immigrant-based performance groups. The Japanese artists, thus, greatly contributed to the development of Japanese performance arts among the immigrants, and enhanced Japanese culture within the immigrant community.<br>3) The role as a catalyst for the immigrants' acceptance of western musical culture.<br>Although the majority of the Japanese immigrants were yet unfamiliar with western art music, they paid a great deal of attention to the Japanese professionals of western art music who performed in the United States, because the immigrants highly regarded those artists as the Japanese elites successfully assimilated into western culture. Through these Japanese professionals, the immigrants gained access to western musical culture in the United States, and also raised their self-confidence and pride as Japanese.
1 0 0 0 IR セントルイス万博に見る日本ブランドの萌芽
- 著者
- 楠元 町子
- 出版者
- 愛知淑徳大学文学部
- 雑誌
- 愛知淑徳大学論集 文学部・文学研究科篇 (ISSN:13495496)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.55-68, 2011