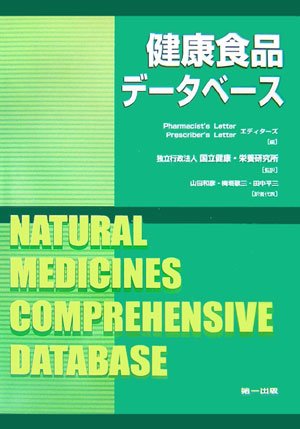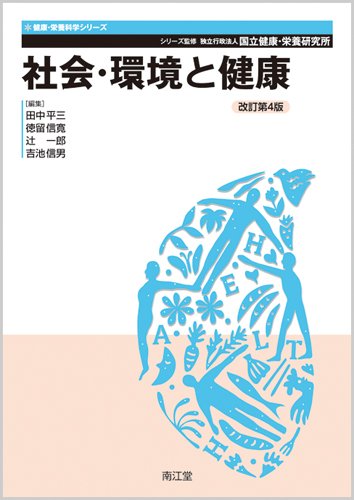4 0 0 0 OA オッズ比と相対危険の関係
- 著者
- 横山 徹爾 田中 平三
- 出版者
- 社団法人 日本循環器管理研究協議会
- 雑誌
- 日本循環器管理研究協議会雑誌 (ISSN:09147284)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.36-39, 1998-01-30 (Released:2009-10-16)
- 参考文献数
- 6
3 0 0 0 OA 出生順位の初潮に及ぼす影響について
- 著者
- 阪本 州弘 大和田 国夫 庄司 博延 田中 平三
- 出版者
- The Japanese Society for Hygiene
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.446-452, 1970-12-30 (Released:2009-02-17)
- 参考文献数
- 6
A study was made on the relationship between birth order and menarche age of 1715 females students of high school and college in Osaka Prefecture in 1968. Results are as follows:1) The median of menarche age for birth order was 13 years and 1 month in the groups of one or two siblings with no relation of birth order. In 3 or over 4 sibling groups, however, the median of menarche age increased with an increase of birth order as follows; the median was 13 years, 13 years and 1 month, and 13 years and 4 months for the group of first, second and third birth order respectively.2) The distribution of the menarche age was analysed by the model in which was composed of 3 parameters of m, σ and λ; m was mean age in the complete stage of the preparation for menarche, σ was variance of the age and λ was the force of effect of external stimulation for menarche appearance.In a single sibling m was 12 years and 8 months, in two siblings group m was 12 years and 6 months, and 12 years and 10 months for first and second birth order respectively, therefore, the latter was 4 months later than the former. In the 3 siblings group, m became later with an increase of birth order as follows; 12 years and 7 months, 12 years and 6 months, 12 years and 9 months for the fiirst, second and third birth order respectively. λ was remarkably high in one sibling group and in the youngest for over two siblings groups.
3 0 0 0 OA 加齢に伴う味覚の感受性の変動に関する研究
- 著者
- 大和田 国夫 田中 平三 伊東 正明 政田 喜代子
- 出版者
- The Japanese Society for Hygiene
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.243-247, 1972-06-28 (Released:2009-02-17)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 10 5
This paper is concerned with studying the developmental changes which occur in sensitivity to the 4 primary taste qualities viz. sweet (sucrose), sour (citric acid), bitter (quinine sulfate) and salty (sodium chloride).Results are as follows:1. Taste threshold values and difference threshold values for the 4 taste qualities increased with age and showed a peak at the age of 60. These values slightly decreased at the age of 70.2. An increase of salty taste threshold values with aging were more marked than other taste threshold values.3. Either sex failed to reveal significant differences for taste sensitivity.4. Significant differences in taste threshold, especially bitter taste, were observed between smokers and non-smokers.5. False dentures (complete) appeared to influence slightly taste threshold values.
- 著者
- 土田 満 伊達 ちぐさ 中山 健夫 山本 卓 井上 真奈美 山口 百子 岩谷 昌子 陳 浩 田中 平三
- 出版者
- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.35-44, 1991 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 1 2
健康な20歳代男子5人を被験者として, 連続3日間, ナトリウム (Na), カリウム (K), カルシウム (Ca), リン (P), マグネシウム (Mg), 亜鉛 (Zn) の出納実験を行った。この結果に基づいて, 摂取量と糞中, 尿中排泄量または血清中濃度との相関を解析した。1) 出納実験より, Na, K, Pは摂取量の大部分が尿中へ排泄されていた。摂取量に対する尿中への排泄率はNaが85%と最も高く, Pが84%, Kが74%であった。逆にCa, Mg, Znは糞中へ排泄される割合が高く, 尿中への排泄率はCaが38%, Mgは25%と低かった。 Znのそれは7.1%であった。2) 摂取量と糞中排泄量との相関を検討してみると, Kのみが統計学的に有意の正相関を示した。3) 摂取量と尿中排泄量との間には, Na (r=0.974) とK (r=0.891) が統計学的に有意な正相関を示した。4) 各ミネラルの摂取量と血清中濃度との間には, 統計学的に有意な相関関係が認められなかった。5) Na, K, Ca, P, Mg, Znの尿中, 糞中の量, 血清中濃度から各ミネラル摂取量を推定するには, 尿中クロール排泄量からの方法がよく知られている。今回の実験では, これをNa, Kの24時間尿中排泄量から求める方法の有用についても示した。
1 0 0 0 OA 第38回大会特別講演1「疫学と健診の接点」
- 著者
- 田中 平三
- 出版者
- 一般社団法人 日本総合健診医学会
- 雑誌
- 総合健診 (ISSN:13470086)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.62, 2010 (Released:2015-03-15)
1 0 0 0 OA 日本総合健診医学会第38回大会―特別講演1― 疫学と健診の接点
- 著者
- 田中 平三
- 出版者
- 一般社団法人 日本総合健診医学会
- 雑誌
- 総合健診 (ISSN:13470086)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.6, pp.649-656, 2010 (Released:2013-08-01)
- 参考文献数
- 14
According to UK National Screening Committee, screening is a public health service in which members of a defined population, who do not necessarily perceive that they are at risk of, or are already affected by, a disease or its complications, are asked a question or offered a test to identify those who are more likely to be helped than harmed by further tests or treatment to reduce the risk of disease or its complications. In Japan, the screening program to detect and control risk factors for stroke and coronary heart disease are established. Sensitivity, specificity and ROC curves should be applied to a test with continuous variable and a detectable preclinical phase of cancer. The only design that effectively eliminates the effect of lead time, length time, overdiagnosis and selection biases is the randomized controlled trial, but only if person-years mortality is used as the endpoint. In Japan, practically, the case-control study is a second-best method. In screening, those who are approached to participate are not patients and most of them do not become patients. The screener must build up a core of ethical principles that govern the relationship between screenee and screener like that between patient and physician.
1 0 0 0 OA 栄養疫学における総エネルギー摂取量に対する解釈と取り扱い方
- 著者
- 田中 平三 横山 徹爾
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.316-320, 1997-08-10 (Released:2010-02-22)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2 3
1 0 0 0 健康食品データベース
- 著者
- Pharmacist's Letter Prescriber's Letterエディターズ編 山田和彦 梅垣敬三 田中平三訳者代表
- 出版者
- 第一出版
- 巻号頁・発行日
- 2007
1 0 0 0 社会・環境と健康
- 著者
- 田中平三 [ほか] 編集
- 出版者
- 南江堂
- 巻号頁・発行日
- 2014
健康な成人男子6名(年齢21〜26歳、身長160〜176cm、体重57〜63.5kg)をバランス・スタディーの対象者とした。食塩以外の栄養素は、すべて対象者の栄養所要量を満足させており、摂取食品群の構成も片寄りのないように工夫された基本食を作成した。この基本食を用いて食塩の摂取量が4レベル(1日当たり10g、7g、4g、1.5g)となるように使用する調味料の量を調整して、4種の実験食とした。6名の対象者を2群に分け、一方には10g食塩食を4日間、7g食塩食を7日間、4g食塩食を7日間、1.5g食塩食を10日間、最後に7g食塩食を4日間、合計32日間連続摂取させた。他方には10g食塩食を4日間、7g食塩食を11日間、4g食塩食を10日間、最後に7g食塩食を4日間、合計29日間摂取させた。実験食摂取期間中は、連日蓄尿した。また、7g食塩食と4g食塩食摂取時の最後の2日間には、バランス・スタディーを実施した。すなわち、体外へ排泄されたナトリウムを求めるため、尿へ排泄されたものと共に、この48時間に皮膚と便から排泄されたナトリウムを含むミネラルを全て収集した。実験食摂取中は3〜4日間隔で採血し、一般生化学検査と共に血中ミネラル類、レニン活性、アンギオテンシン、アルドステロン、抗利尿ホルモン等を測定した。ナトリウム出納は、7g食塩食、4g食塩食摂取時はほぼ零平衡を示したが、1.5g食塩食ではやや負出納を示した。血中成分の中では、アルドステロンは4g食塩食摂取時までは大きい変化は認められなかったが、1.5g食塩食摂取時には200%近くにまで上昇した。また、カルシウム摂取量は全実験食で一定であったにもかかわらず、尿中カルシウム排泄量は食塩摂取量が低いほど低下し、日本人にとって不足しやすいといわれているカルシウム摂取の面からは、食塩摂取量は低いほど望ましいことが示された。これらを総合すれば、わが国における成人1日当たり食塩最適摂取量は、4g付近にあるのではないかと推察された。
平成10年度〜12年度にかけて「在宅ケアにおける基本的な日常生活行動の自立支援のためのケアプランと評価方法」について研究を行った。平成10年度に日常生活行動の自立を可能にする条件を分析した。結果は2ヵ月で改善可能な内容は着替え、服薬行動、痛み、介護者の心身の疲労であった。同年にケアプランの実施の有無とプラン修正によるニーズ解決を分析した。その結果、ニーズ解決率の高い順位は(1)ケアプランを必要に応じて修正し実施、(2)ケアプラン実施、(3)実施しない、の順であること、ケアプランの修正要因は利用者条件、サービス提供条件、ケアマネージャーの順であった。平成11年度には日常生活行動変化のアウトカム項目をアメリカ合衆国のメディケア機関で義務化されていたOASIS(The Outcome Assessment Information Set)を中心に我々が開発していた日本版在宅ケアアセスメント用紙を組み合せて、在宅ケアの評価を行い、それに基づきケアプランを5機関で行った。平成12年度にはアウトカム項目を確定し、自立度変化とケアプロセスの内容、満足度を評価し、プランを立てて実施後に再度アウトカムとプランを評価する方法の開発、サービス提供者の能力開発と組織力向上の評価方法を開発し、マニュアル化した。なお、利用者アウトカムに関しては、フィンランドとの共同研究を行った。