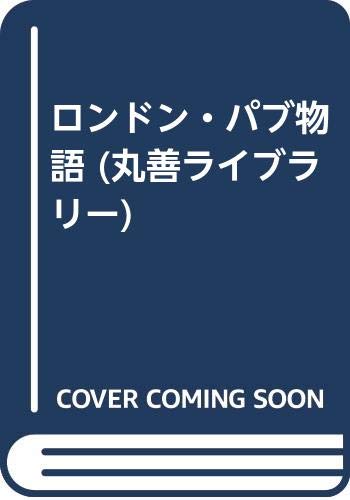1 0 0 0 OA ChatGPTを活用した地場商品開発の実践的取り組み
- 著者
- 原田 紹臣 永井 雅章 櫻井 崇光 吉田 恭平 石原 孝雄 家戸 敬太郎
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- AI・データサイエンス論文集 (ISSN:24359262)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.3, pp.233-244, 2023 (Released:2023-11-14)
- 参考文献数
- 47
藍子の皿ねぶりとして知られている藻食魚類のアイゴは,美味として珍重されている未利用魚の一種である.一方,モクライ(藻食らい)としても知られており,磯枯れの原因の一つとして考えられている.本稿では,徳島県美波町における地域活性化及び沿岸域の磯焼け対策の一つとしてのアイゴを用いた地場商品の開発と,その際にChatGPTを実践的に活用して考察されたChatGPTの適用性等について報告している.なお,アイゴ料理の試食を通じた官能検査の結果,燻製,リゾット等が高評価であった.一方,被験者の属性によって,料理の嗜好が異なる傾向であることが分かった.また,一般的に課題であったアンケート調査における自由記述文(意見)の分析に対してChatGPTを活用したところ,妥当性のある分析結果を簡易に得られる可能性が示唆された.
1 0 0 0 内臓脂肪の蓄積と生活習慣との関連
- 著者
- 石原 孝子
- 出版者
- 一般社団法人 日本地域看護学会
- 雑誌
- 日本地域看護学会誌 (ISSN:13469657)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.7-14, 2010
- 被引用文献数
- 1
肥満の中でも腹腔内脂肪の貯留による肥満は内臓脂肪型肥満と呼ばれ,動脈硬化性疾患を惹起するリスク要因のひとつである.内臓脂肪の蓄積は生活習慣の結果であると考えられ,具体的な生活習慣を明らかにすることが重要である.そこで,腹部CT検査を含む人間ドック受診者3,659名を対象に,まず年齢・性別と内臓脂肪面積との関連を検討し,対象を40〜60代の中高年に絞って(男性1,677名,女性1,187名)内臓脂肪面積と生活習慣項目について,分散分析と多重比較を用いて関連要因を探った.その結果,内臓脂肪の蓄積には,睡眠の質や時間,満腹まで食べる,外食が多い,塩分が多い,動物性脂肪の摂取が多く植物性食品の摂取が少ない,といった食習慣,飲酒や喫煙などの嗜好習慣が影響していることが示唆された.内臓脂肪に関連するとされる運動については,男性は頻度による差がみられたが,女性は明確な差異がなかった.結論として,内臓脂肪の蓄積には,食事摂取量および飲酒量の過多,睡眠の質の低下や長時間ないし短時間の睡眠,動物性食品に偏った食事,運動不足が影響していた.
1 0 0 0 OA 技術者倫理教育はなぜ必要か
- 著者
- 石原 孝二
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.10, pp.626-629, 2004-10-01 (Released:2008-04-17)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 3 3
1 0 0 0 IR リチャード三世像の変遷 : 文学と歴史の狭間で
- 著者
- 石原 孝哉 イシハラ コウサイ Ishihara Kosai
- 出版者
- 駒澤大学外国語部
- 雑誌
- 論集 (ISSN:03899837)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.33-57, 2004-03
- 著者
- 石原 孝二
- 出版者
- 金剛出版
- 雑誌
- 臨床心理学 = Japanese journal of clinical psychology (ISSN:13459171)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.294-297, 2017-05
- 著者
- 石原 孝二
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 年次大会講演資料集
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, 2009
1 0 0 0 IR 『トロイラスとクレシダ』論(2) ‐無限と価値をめぐって‐
- 著者
- 石原孝哉
- 出版者
- 駒澤大学外国語部
- 雑誌
- 論集 (ISSN:03899837)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, 1981-02
1 0 0 0 OA 多角的視座からの「感情」現象の哲学的解明を通じた価値倫理学の新たな基礎づけの試み
「感情」現象をあらためて哲学的に吟味することを通して、倫理的価値の発生する根源的な場所を明らかにし、ひいては新たな価値倫理学の基礎づけを試みること、それが本研究の目標であった。われわれは、現象学、中世哲学、心の哲学、分析哲学、現象学的精神病理学、精神分析という、各研究分担者の専門的視座から持ち寄られたたさまざまな「感情」研究の成果を相互に批判的に比較検討することを通じて、人間存在にとっての感情現象の根本的意義(謎にみちたこの世界において行為し受苦するわれわれにとっての感情現象の根本的意義)を明らかにする多様な成果を上げることができた。これにより上記目標の核心部分は達成されたと言いうるだろう。
- 著者
- 石原 孝尚 Takayoshi Ishihara 吉備国際大学社会学部スポーツ社会学科 Department of Sports Sociology School of Sociology KIBI International University
- 出版者
- 高梁学園吉備国際大学
- 雑誌
- 吉備国際大学研究紀要 社会学部 (ISSN:18836607)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.45-49, 2010
1 0 0 0 OA シェイクスピアと超自然 : 妖精をめぐって(兼谷先生追悼号)
- 著者
- 石原 孝哉
- 出版者
- 駒澤大学
- 雑誌
- 論集 (ISSN:03899837)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.23-45, 1988-09
1 0 0 0 行為と認知の統合理論の基礎
本研究プロジェクトは、認知と行為の総合理論の基礎を据えることを目的として発足し、行為の合理性の分析を軸として、隣接諸学との関連をも視野に入れた研究を行ってきた。認知と行為の関連は、古くは「知と徳」の問題として、あるいはカントにおいて「理論理性と実践理性」の問題として問われ続けてきたように、哲学の中心的な問いの一つである。本研究プロジェクトでは、研究成果報告書第I部に見られるように、プラトンの対話篇を素材としたシンポジウム及びその背景となった研究において、生全体の認知と、そのもとに営まれる行為との関連のありさまを、哲学的思索の根源的な形態において理解しようとした。また、「プラグマティズムと人間学的哲学」シンポジウムにおいては、外国人研究者の協力も得て、日本及び東アジアの思想とヨーロッパにおける合理性概念の検討を行った。ともすれば、近代ヨーロッパに起源をもつ合理性概念にのみ着目してきた従来の哲学研究を、このような形でいったん相対化することは、合理性概念そのものの深化にとって不可欠である。さらに、シャーバー氏のセミナー及びシンポジウムでは、道徳的実在論に焦点を当て、より直接的に行為の合理性理解の可能性を問題にした。また、研究成果報告書第II部では、行為の合理性の分析と並んで、本研究プロジェクトのもう一つの柱である、哲学的な合理性概念と隣接諸学との関連にかかわる諸問題が論じられている。それらは社会生物学やフレーゲの論理思想、キリスト教信仰、認知科学、メレオトポロジー、技術者倫理と、一見バラバラな素材を取り扱っているように見えるが、それらはいずれも価値と人間の行為の合理性を軸とした認知と行為の問題の解明に他ならない。認知と行為の関連の問題は、さまざまなヴァリエーションをもって問われ続けてきた哲学の根本的な問題群であり、さらにその根底には人間とは何か、あるいは何であるべきかという問いが潜んでいる。これについてはさらに別のプロジェクトによって研究の継続を期することにしたい。
1 0 0 0 リスク論を軸とした科学技術倫理の基礎研究
本研究ではまず、科学技術に関するリスク-便益分析の方法について批判的に検討し、リスク論に社会的公平性を組み込む可能性について検討した。第二に、ナノテクノロジー、遺伝子組換え農作物等の科学技術倫理の諸問題をリスク評価とリスクコミュニケーションの観点から分析した。第三に、リスク論に関して理論的な研究を行った。さらにリスク論と民主主義的意思決定について検討した。第四に、技術者倫理教育の中にリスク評価の方法を導入することを試みた。まず費用便益分析に基づくリスク論は、懸念を伴う科学技術を正当化するための手段として用いられることがあることを、内分泌攪乱物質等を例として確認した。また研究分担者の黒田はナノテクノロジーの社会的意味に関する海外の資料の調査を行い、アスベスト被害との類似性等について検討した。また藏田は遺伝子組換え農作物に関わる倫理問題について検討し、科学外の要因が遺伝子組換え農作物に関する議論の中で重要な役割を果たすことを確認した。そしてリスク論に関する理論的研究として、まず予防原則の哲学的・倫理学的・社会的・政治的意味について検討し、その多面性を明らかにした。他に企業におけるリスク管理(内部統制)に関する調査も行った。リスク論に関する哲学的研究としては、確率論とベイズ主義の哲学的含意に関する研究と、リスク論の科学哲学的含意の検討、リスク下における合理的な意思決定に関する研究を行った。またリスク評価と民主主義的な意思決定に際して、参加型テクノロジーアセスメントや、双方向型のコミュニケーションによって、リスクに関する民主主義的決定モデルが可能となることを確認した。また技術者倫理教育に関して、研究分担者の間で情報交換を行い、上記の成果を技術者倫理教育に導入することを試みた。
1 0 0 0 OA 科学技術リスク論の倫理学的研究
- 著者
- 石原 孝二
- 出版者
- 北海道大学文学研究科= The Faculty of Letters, Hokkaido University
- 雑誌
- 北海道大学文学研究科紀要 (ISSN:13460277)
- 巻号頁・発行日
- no.106, pp.1-16, 2002
- 著者
- 石原 孝二
- 出版者
- 北海道大學文學部 = The Faculty of Letters, Hokkaido University
- 雑誌
- 北海道大学文学部紀要 (ISSN:04376668)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.1-14, 1999-11