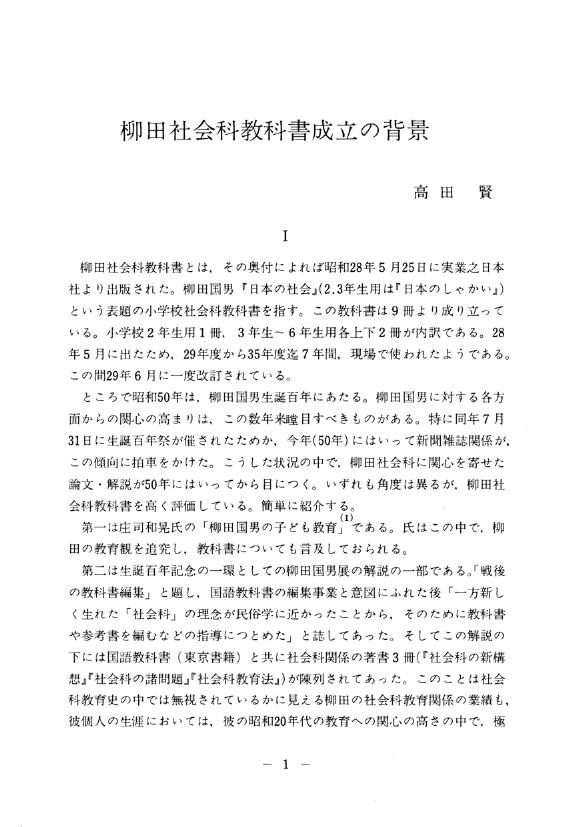6 0 0 0 OA 抗体ベンチャー(イーベック)
- 著者
- 高田 賢蔵
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.40-46, 2012-01-30 (Released:2012-04-27)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1
我々の体内では微生物などの外来抗原に低濃度で繰り返し暴露されることにより、これら外来抗原に対する結合活性の高い抗体産生リンパ球が選択的に増幅する親和性成熟が常に起こっている。従って、ヒト血液リンパ球は高活性抗体ソースとして優れている。イーベックではヒト血液リンパ球にEBウイルスを感染させることによりその増殖、抗体産生を誘導し、そこから目的とする抗体産生リンパ球を分離し抗体を作製する独自の技術を開発した。本稿では、イーベックの抗体技術と製薬企業とのライセンス経験について紹介する。
4 0 0 0 OA 柳田社会科教科書成立の背景
- 著者
- 高田 賢
- 出版者
- 日本社会科教育学会
- 雑誌
- 社会科教育研究 (ISSN:09158154)
- 巻号頁・発行日
- vol.1976, no.37, pp.1-10, 1976 (Released:2016-12-01)
2 0 0 0 OA ワレンベルグ症候群に伴う感覚障害に対するアプローチ
- 著者
- 高田 賢一 川田 雅与 加藤 貴志 井野邊 純一
- 出版者
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会
- 雑誌
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 第39回九州理学療法士・作業療法士合同学会 (ISSN:09152032)
- 巻号頁・発行日
- pp.165, 2017 (Released:2017-12-01)
- 著者
- 高田 賢一
- 出版者
- 一般財団法人日本英文学会
- 雑誌
- 英文學研究 (ISSN:00393649)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, 1985-12-01
2 0 0 0 OA 4. ウイルスの潜伏と誘発
- 著者
- 高田 賢蔵
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.111-117, 1990-02-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 20
2 0 0 0 20世紀アメリカ児童文学における子ども像と環境意識の変容
本研究の目的は、20世紀アメリカ児童文学における子ども像と自然環境意識の変容の歴史を解明することである。そこから得られた結論の第1は、自然環境の破壊と公害の先進国であるアメリカは、児童文学の分野において人間と自然環境の調和を真剣に考える先進国でもあるということである。結論の第2は、子どもが社会改革の可能性を秘めた存在であるという点である。第3の結論は、20世紀アメリカ児童文学、特に動物物語における子ども像と環境意識の歴史的変遷を『オズの魔法使い』を始めとする主要な作品に即して解明することにより、アメリカの児童文学が未来の社会を担う子どもたちに対して、新たな自然観、さらに自然環境への対応方法を提示してきたことが明らかとなった。すなわち、自然は人間が支配することのできない他者であるとの認識を持つことの必要性である。第4の結論は、児童文学に焦点を絞ることにより、自然・環境意識の変遷、レイチェル・カーソンのいう「驚きの感覚」を持つ子どもと自然環境との関連の歴史的特質、そして児童文学作家たちの環境意識の変容を明らかにしたことである。つまり本研究は、子どもと自然環境の角度から考察したアメリカ研究なのである。今後の課題は、子どもと自然環境の関わりを重視する新たなアメリカ児童文学史の構想であり、児童文学と環境教育との結びつきを視野に入れた研究へと幅を広げる必要性ではないだろうか。今後、このような考えに基づき、さらに多くの作家・作品を対象とすれば、その研究は国内外の最先端の研究と位置づけることが可能になると思われる。
1 0 0 0 OA 可変正則化パラメータを用いた phase-field 延性破壊モデル
- 著者
- 韓 霽珂 西 紳之介 高田 賢治 村松 眞由 大宮 正毅 小川 賢介 生出 佳 小林 卓哉 村田 真伸 森口 周二 寺田 賢二郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本計算工学会
- 雑誌
- 日本計算工学会論文集 (ISSN:13478826)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, pp.20200005, 2020-04-15 (Released:2020-04-15)
- 参考文献数
- 36
近年,亀裂・進展の解析手法の一つとして,phase-field破壊モデルが注目を集めている.phase-field脆性破壊モデルは既に多くの実績が報告されている一方で,延性材料を適切に表現するphase-field破壊モデルは発展途上である.phase-field破壊モデルにおいて,拡散き裂の幅を表す正則化パラメータは破壊開始の制御に用いられ,これが大きいほど破壊開始が早くなる.これは正則化パラメータが大きい場合には,その分だけき裂近似領域も大きくなるため,1に近いphase-fieldパラメータの分布も拡大し,それに応じて荷重--変位関係のピーク値が小さくなることが原因として考えられる.本研究では,正則化パラメータの性質を考慮し,通常は定数として扱われる正則化パラメータの代わりに,蓄積塑性ひずみの大きさに応じて変化する可変正則化パラメータを提案する.これにより,塑性域と正則化パラメータによって規定されるき裂周辺の損傷域が関連づけられ,塑性変形の影響を考慮した損傷の計算が可能となる.提案モデルの表現性能を調査するためにいくつかの解析を行った.可変正則化パラメータの導入により,塑性変形の進行とともにき裂周辺の損傷域が大きくなる傾向が捉えられ,弾性域から塑性域を経てき裂に発展するといった遷移過程に特徴づけられる延性破壊を表現できることを確認した.ベンチマーク問題の解析等の数値解析を通して,き裂の進展方向を適切に予測できること,および可変正則化パラメータを介して延性の制御が可能になることを例示した.また,金属供試体を用いた実験の再現解析では,実験結果と整合する結果が得られることも確認した.
1 0 0 0 OA 新潟県岩船郡粟島におけるクロノビタキの観察記録
- 著者
- 高田 賢一郎
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.112-113, 2009-05-01 (Released:2009-05-20)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- 蔵口 雅彦 湯元 美樹 高田 賢治 津田 邦男
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. ED, 電子デバイス (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.81, pp.37-40, 2009-06-04
- 参考文献数
- 8
GaN系電子デバイスにおいて特性向上を図るため、ゲートリセス構造が有望である。窒化物半導体ではウエットエッチングによる精密なエッチングが難しいため、リセス構造形成のためには低ダメージなドライエッチング技術が求められる。本研究では、BCl_3とCl_2の混合ガスを用いたICP-RIEにより、エッチングの低ダメージ化を検討した。その結果、BCl_3とCl_2の混合ガスにより低バイアスパワーで表面モフォロジーが維持できることが分かった。また、表面モフォロジーが維持できる範囲内では、Cl_2/BCl_3比を高くすることでAlGaNを効率よくエッチングができ、BとClの半導体層への侵入量を抑制できることが分かった。
- 著者
- 金澤 成美 山本 隆昭 高田 賢二 藤井 元太郎 石橋 抄織 佐藤 嘉晃 原口 直子 今井 徹 中村 進治
- 出版者
- 日本矯正歯科学会
- 雑誌
- Orthodontic waves : journal of the Japanese Orthodontic Society : 日本矯正歯科学会雑誌 (ISSN:13440241)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.92-102, 1998
- 被引用文献数
- 31
1981年4月から1996年3月までの15年間に北海道大学歯学部附属病院矯正科を来院した矯正患者を調査対象に, 経時的推移を調査し以下の結果を得た.1. 過去15年間の来院患者総数は4, 559名で, 1981年から1990年までは増加していたが, その後の患者数は減少していた.2. 性別では, 男性 : 女性が1 : 1.5と女性が多く, また年齢が高くなるに伴い女性が増加していた.3. 初診時年齢は経時的に年齢が高くなる傾向にあり, 成長期の患者が減少し, 永久歯列期の患者が増加していた.4. 来院動機では審美障害が最も多く, 次いで咀嚼障害であった.また, 顎関節症を主訴とする患者が近年は増加していた.5. 来院経路では, 自意が減少し, 院内他科や他の医療機関からの紹介が増加していた.6. 不正咬合の種類では, occlusal anomaliesが74.2%, space anomaliesが78.7%であった.前者では, 反対咬合が40.5%, 上顎前突が13.6%であったが, 経時的に反対咬合は減少していた.後者では前歯部叢生が62.8%と多く, 経時的に前歯部叢生が増加している傾向が認められた.7. 顎顔面領域の先天異常では, 口唇口蓋裂の占める割合が高かったが, 人数では経時的に減少していた.8. 外科的矯正治療患者の割合は全体の約16%を占め, 反対咬合症例が圧倒的に多かった.9. 顎関節症状を有する患者は増加する傾向にあり, 特に女性の占める割合が高かった.
1 0 0 0 OA 〈日本幻想〉の研究-表象と反表象のダイナミックス
英米文学および英米文化の研究を通じて、英米圏における〈日本幻想〉の胚胎・生成とインパクトの諸相を総合的かつ具体的に検証することをめざした。(ただし、課題の性格上、日本文学に関する研究も含まれる。)理論的には表象論を基底に据え、コロニアリズム/ポストコロニアリズムにおける「接触界域」(contact zone)論を踏まえつつ、日本表象に内在する複雑なダイナミズムを明らかにした。具体的には、言説としての〈日本幻想〉生成のプロセスを複数のテーマ設定によって分析した。これらのテーマは、連続的な生成プロセスであり、明瞭な区分を与えることは困難であるが、このプロセス全体を通じて、所定の個別化された〈日本幻想〉が産出・消費されてきたものと考える。
1 0 0 0 アメリカ大陸を中心としたがん研究先進グループとの研究交流
- 著者
- 山本 雅 渡邊 俊樹 吉田 光昭 平井 久丸 本間 好 中地 敬 永渕 昭良 土屋 永寿 田中 信之 立松 正衛 高田 賢蔵 澁谷 均 斉藤 泉 内山 卓 今井 浩三 井上 純一郎 伊藤 彬 正井 久雄 村上 洋太 西村 善文 畠山 昌則 永田 宏次 中畑 龍俊 千田 和広 永井 義之 森本 幾夫 達家 雅明 仙波 憲太郎 菅村 和夫 渋谷 正史 佐々木 卓也 川畑 正博 垣塚 彰 石崎 寛治 秋山 徹 矢守 隆夫 吉田 純 浜田 洋文 成宮 周 中村 祐輔 月田 承一郎 谷口 維紹 竹縄 忠臣 曽根 三郎 伊藤 嘉明 浅野 茂隆
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 国際学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1994
近年、がん遺伝子、がん抑制遺伝子の研究が進み、がんを遺伝子ならびにその産物の機能に基づいて理解することが可能になった。それと共に、細胞増殖のためのシグナル伝達機構、細胞周期制御の機構、そして細胞死の分子機構の解明が進んだ。また細胞間相互作用の細胞社会学的研究や細胞表面蛋白質の分子生物学的研究に基づく、がん転移の機構についての知見が集積してきた。一方で、がん関連遺伝子の探索を包含するゲノムプロジェクトの急展開が見られている。また、ウイルス発がんに関してもEBウイルスとヒトがん発症の関連で新しい進展が見られた。このようながんの基礎研究が進んでいる中、遺伝子治療のためのベクター開発や、細胞増殖制御機構に関する知見に基づいた、がんの新しい診断法や治療法の開発が急速に推し進められている。さらには、論理的ながんの予防法を確立するための分子疫学的研究が注目されている。このような、基礎研究の急激な進展、基礎から臨床研究に向けた情報の発信とそれを受けた臨床応用への試みが期待されている状況で、本国際学術研究では、これらの課題についての研究が先進的に進んでいる米国を中心とした北米大陸に、我が国の第一線の研究者を派遣し、研究室訪問や学会発表による、情報交換、情報収集、共同研究を促進させた。一つには、がん遺伝子産物の機能解析とシグナル伝達・転写調節、がん抑制遺伝子産物と細胞周期調節、細胞死、化学発がんの分子機構、ウイルス発がん、細胞接着とがん転移、genetic instability等の基礎研究分野のうち、急速な展開を見せている研究領域で交流をはかった。また一方で、治療診断のためには、遺伝子治療やがん遺伝子・がん抑制遺伝子産物の分子構造に基づく抗がん剤の設計を重点課題としながら、抗がん剤のスクリーニングや放射線治療、免疫療法に関しても研究者を派遣した。さらにがん予防に向けた分子疫学の領域でも交流を図った。そのために、平成6年度は米国・カナダに17名、平成7年度は米国に19名、平成8年度は米国に15名を派遣し、有効に情報交換を行った。その中からは、共同研究へと進んだ交流もあり、成果をあげつつある。本学術研究では、文部省科学研究費がん重点研究の総括班からの助言を得ながら、がん研究の基盤を形成する上述のような広範ながん研究を網羅しつつも、いくつかの重点課題を設定した。その一つは、いわゆるがん生物の領域に相当する基礎生物学に近いもので、がん細胞の増殖や細胞間相互作用等の分子機構の急激な展開を見せる研究課題である。二つ目の課題は、物理化学の分野との共同して進められる課題で、シグナル伝達分子や細胞周期制御因子の作用機構・高次構造に基づいて、論理的に新規抗がん剤を設計する試みである。この課題では、がん治療薬開発を目的とした蛋白質のNMR解析、X線結晶構造解析を推進する構造生物学者が分担者に加わった。三つ目は、極めて注目度の高い遺伝子治療法開発に関する研究課題である。レトロウイルスベクター、アデノウイルスベクターの開発に関わる基礎側研究者、臨床医師、免疫学者が参画した。我が国のがん研究のレベルは近年飛躍的に向上し、世界をリ-ドする立場になってきていると言えよう。しかしながら、上記研究課題を効率良く遂行するためには、今後もがん研究を旺盛に進めている米国等の研究者と交流を深める必要がある。また、ゲノムプロジェクトや発生工学的手法による、がん関連遺伝子研究の進展によって生じる新しい課題をも的確に把握し研究を進める必要があり、そのためにも本国際学術研究が重要な役割を果たしていくと考えられる。