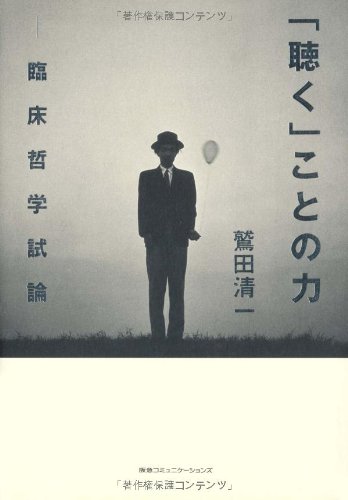8 0 0 0 OA 『「聴く」ことの力 : 臨床哲学試論』合評会報告
- 著者
- 鷲田 清一
- 出版者
- 大阪大学大学院文学研究科臨床哲学研究室
- 雑誌
- 臨床哲学 (ISSN:13499904)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.77-82, 2000-03-15
5 0 0 0 OA 思考のエシックス : 反・方法主義論
3 0 0 0 物語と同一性
- 著者
- 鷲田 清一
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.44-47, 1998
2 0 0 0 垂直のファッション, 水平のファッション
- 著者
- 鷲田清一
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- デザイン モード ファッション
- 巻号頁・発行日
- 1996
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 第12章 インダストリーの精神と真空恐怖
- 著者
- 鷲田 清一
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本人の労働と遊び・歴史と現状 = Japanese at Work and Play: An Historical Analysis to the Present
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.171-179, 1998-08-06
- 著者
- 鷲田 清一
- 出版者
- 朝日新聞出版
- 雑誌
- 小説tripper : トリッパー
- 巻号頁・発行日
- pp.370-386, 2015
2 0 0 0 OA 多重的なものとしての身体
- 著者
- 鷲田 清一
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, no.63, pp.45-60_L4, 2012 (Released:2012-10-16)
- 参考文献数
- 6
Is “my” body really my possession? Unraveling this problem leaves us with two questions: Whose body is it? Is the body a possession? We can rephrase these questions in the words of Gabriel Marcel, author of Being and Having, who asked “Do I have a body? Or am I a body?” These problems in the field of “bio-ethics”, be they at the level of principle or at the level of legal procedure, invariably involve questions of ownership. We must then once again return the facticity of our body to the border between “being” and “having”. At the same time, we must sever the link between the concept of “property”, which has long been viewed as self-evident, and that of “disposability”. The view that one not only owns one's body but, in addition, every last bit of that body is at one's disposal attests to the fact that we have been held captive by the gaze of self-ownership in modern society.
2 0 0 0 OA <ある>と<もつ> : 「所有」という概念についての試論(1)
- 著者
- 鷲田 清一 ワシダ キヨカズ Washida Kiyokazu
- 出版者
- 大阪大学文学部
- 雑誌
- 待兼山論叢. 哲学篇 (ISSN:03874818)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.1-15, 1992-12
1 0 0 0 都市と野生の思考
- 著者
- 鷲田清一 山極寿一著
- 出版者
- 集英社 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2017
1 0 0 0 「聴く」ことの力 : 臨床哲学試論
1 0 0 0 〈健康〉と現代社会
- 著者
- 鷲田 清一
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 = The Journal of Japanese Physical Therapy Association (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.8, 2004-12-20
古代以来,西洋各地域の言語が複雑に交叉し分岐してきた歴史のなかで,「癒す,治す」(heal/heilen)や「健康」(health)という語が,「全体」(whole)や「聖なる」(holy/heilig)という語と同族語として生成してきたという事実は,われわれをさまざまな想いへといざなう。傷が癒える過程,病を治す過程に,テクノロジーというものがこのうえなく深く介入するようになった現代社会では,<健康>でないもの,つまり病や傷は,局所(=部分)に原因をもつそれとしてとらえられる。また,それは生体の機能不全という視点からみられ,病に侵され傷を負っているという状態が,そのひとにおけるなにか別の意味の現われ(たとえば「罪業」や「試練」)としてとらえられることもない。これは治す側の問題である。他方,患者の付添人からすれば,患部の状態以上に(どんな苦しみなのかといった)患者自身がどういう状態にいるかが気がかりなところであり,また苦しみからの解放を祈ったり,「苦しみとともにする」(sympathyの語源である)ために何かを絶ったりする。そこにはhealとwholeとholyのからみあいがはっきりある。Healがwholeと切り結ぶところまでは分かるとして,なぜholyとまでつながるかというと,そこでは付添人は想いをそのひとの生のなかだけでなく生の彼方にまでもはせるからである。そのひとがいなくなるという事態,さらには身体の生を超えたそのひとの存在の意味にまで,である。つまり,治す側は身体の生の内部をみている。付き添う側は身体の生をあふれ出ているものをみている。そして,付き添う側の想いは「治療過程」の外側に置かれる。付き添うひとの気持ちはわかるが,病気を治すということはそういうことではない,と。その裏返しとして,<健康>もまた,器官や四肢の集合体としてとらえられた身体が総じて故障がないこととしてイメージされ,ふだんから血液検査やレントゲン撮影によって生体の機能不全のチェックをするという対処を求められる。健康が,身体の生の,治療するところのない「正常」な状態とされるのである。健康か不健康かの区別が医療機関での「健康診断」に託されるのだ。こうしてひとの身体は,医療テクノロジーの高度な装置のなかにますます深く挿入されていった。医療の行為や制度を断罪しようというのではない。<健康>が身体の「正常」に還元されている事態が,<健康>のイメージをどれほど損なっているかを,あらためて考えたいのである。たとえば医療テクノロジーの「暴走」を口にするひとがいる。「暴走」は,医療のあるべき様態を超えてしまっているということの表現であろう。が,しかし,われわれが自身の「よりよき」生を求めてそれに依存することにしてきた医療テクノロジーがもはや「人間的」でないかどうかは,われわれが「人間的」ということで何を考えてきたかという,歴史的な文化の問題である。<健康>の問題を身体の「正常」に還元する見方のひとつの問題は,それが個人の生を,生なきもの,つまり器官のモザイクー「死のモザイク」として表象させるというところにあるが,その見方のもうひとつの問題は,<健康>への視点をもっぱらひとの身体の内部に向け,そのことで他者との交通という場面を見えなくさせてしまうという点にある。こういうときはこういう草を煎じて飲むとか,こういうときはここのつぼを押すとか,かつて日常世界のなかにあった「相互治療」の文化は,民間医療,素人医療として,公的な医療機関のなかに呑み込まれ,消えた。身体と身体とのあいだの交通を超個人的なシステムが代行するようになることで,ひとは自分の身体のあり方への判断力のみならず,他の身体への通路をも見失いかけている。おおよそこのような視点から,今回,<健康>というテーマをめぐって,次のような問題を考えてみたい。「正常」でなくとも<健康>であるような生のあり方とはどういうものか。ひとは中年にさしかかると,ちょうど若いひとたちが自分の体格や身なりや身体感覚に強い関心をもつのとおなじくらいに熱っぽく,自分の「体調」や「健康体操」について語りはじめるそういえば,老人の「健康談議」を「老人の猥談」と揶揄するひとたちがいるが,ひとはなぜ,これほど<健康>に,あるいは自分の身体の状態に,熱い関心をもつようになったのか。身体に熱中するというよりも,「健康な身体」という観念,「正常値」という観念に,と言ったほうが正確ではあろうが。(当日の講演内容は次号に掲載予定です)
1 0 0 0 OA 着衣する身体と女性の周縁化
- 著者
- 武田 佐知子 池田 忍 脇田 晴子 太田 妙子 堤 一昭 井本 恭子 千葉 泉 福岡 まどか 三好 恵真子 宮原 暁 住村 欣範 深尾 葉子 生田 美智子 松村 耕光 藤元 優子 宮本 マラシー 竹村 景子 中本 香 藤原 克美 古谷 大輔 村澤 博人 鷲田 清一
- 出版者
- 大阪大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2006
本研究の成果は大きく分けて二つある。一つは、従来のカタログ的な着衣研究ではなく、個別地域の具体的な文脈から引き離さず、着衣、身体、女性の関係を読み解くための共通の枠組を構築し、ローカルな視点とグローバルな視点の接合によって開ける多様性のなかの着衣研究の可能性を提示したことである。男性身体の周縁に位置づけられた女性身体の可変性、着衣による身体のイコン化と増殖現象、共同体による着衣身体の共有と変換、ジェンダー秩序のなかで受容される女性身体の意味とその操作、そして既存の共同体の集合的に実践や意識/無意識が、視覚表象と深く関わり相互交渉がなされていることを明らかにした。二つめは、日本では「着衣する身体の政治学」と題し、タイでは「着衣する身体と異性装-日・タイの比較-」と題した国際シンポジウムを開催し、単に抽象的、モデル的に着衣研究の事例を理解するのではなく、現場に即した肌に触れる知を通して、実践知と暗黙知を提示したことである。
1 0 0 0 OA 食のほころび : あるいは、食べることと食べさせてもらうこと
- 著者
- 鷲田 清一
- 出版者
- 大阪大学大学院文学研究科臨床哲学研究室
- 雑誌
- 臨床哲学 (ISSN:13499904)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.107-119, 2002-06-10