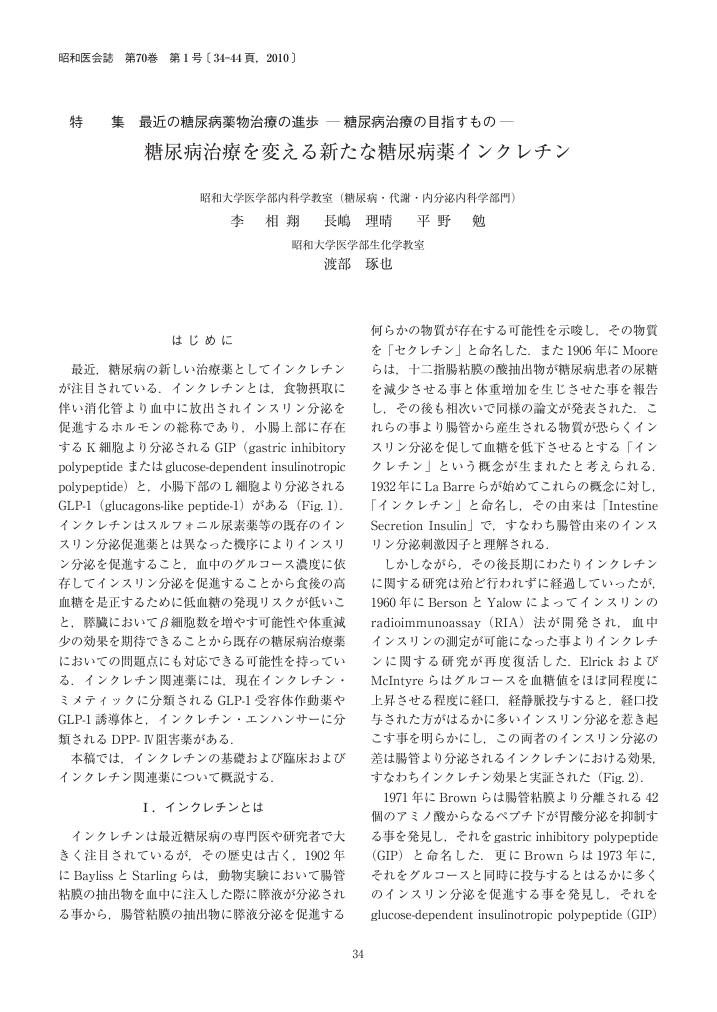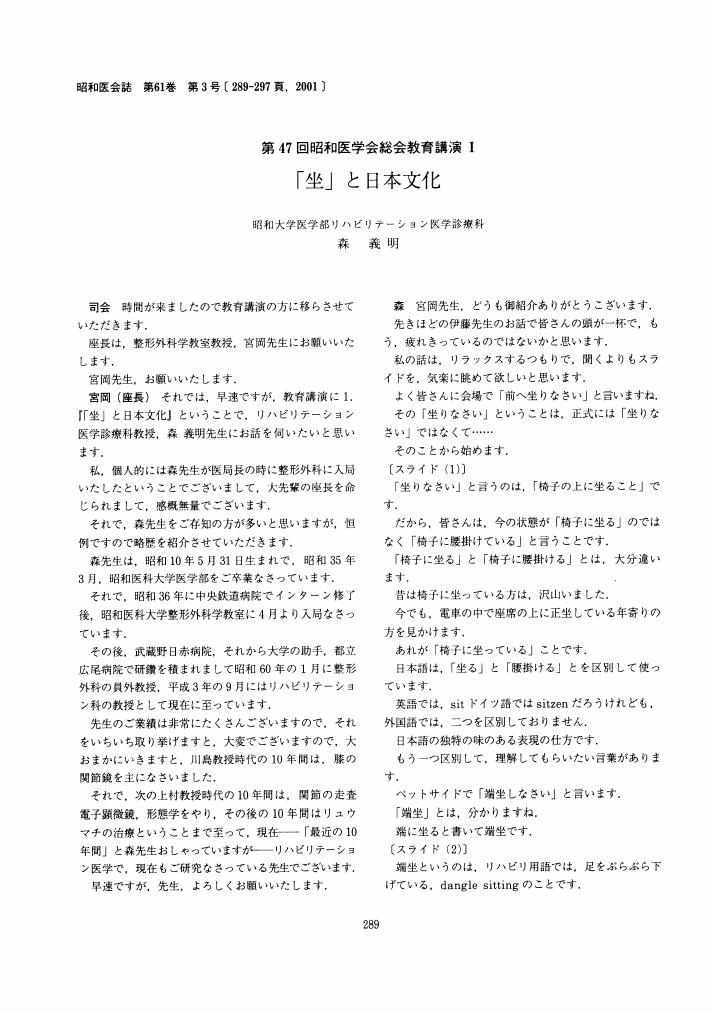1 0 0 0 患者の至適温度条件に関する研究:―病室の温熱環境と患者の温冷感―
- 著者
- 松井 住仁
- 出版者
- The Showa University Society
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.271-284, 1981
- 被引用文献数
- 3 1
入院患者の至適温熱環境を求めるため, 内科病棟において1年間温湿度測定, 患者への温冷感等のアンケート調査及びカルテ調査を実施し, 以下の知見をえた.至適温度は秋22~23℃, 冬20~21℃, 春21~22℃, 夏24~25℃, と季節差があった.若年者は, よりより凉しい室温でより涼しく, より暖かい室温でより暖かく感じる傾向にあった.温熱環境に対して類似の温冷感申告を呈する傾向を有す患者を1群として, 5群の疾患群に分類した.この傾向から疾患毎の至適温度を求めることが望ましいと考えた.夏の冷房しすぎ, 冬の暖房しすぎ等, 冷暖房時期, 時間, 実施方法について再考の余地を認めた.湿度感においても季節差があり, 特に冬は乾燥感の申告が増加していた.患者は病室内温熱環境の変化に対して, 衣服, 寝具等によって個々に体温調節を行っており, これによって現在一般的な空調設備は満足しえるものと考えられたが, 個々調節不能な重症者, 幼児等では依然問題が残されている.
1 0 0 0 腹部CT検査で術前に診断された魚骨による小腸穿孔の1症例
- 著者
- 梅本 岳宏 幕内 幹男 武内 聖
- 出版者
- The Showa University Society
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.47-51, 2006
- 被引用文献数
- 1
症例は69歳男性.平成14年9月25日右下腹部痛が出現した.痛みは一時軽快したが, 27日夜から28日朝にかけて痛みが増悪し, 近医を受診した.虫垂炎と診断され, 抗生剤を処方されて帰宅した.その後症状は一時軽快したが, 9月30日再び右下腹部痛が出現し再診した.限局性腹膜炎の診断で手術目的にて同日当院に紹介入院となった.腹部単純X線ではfree airや異物陰影は認められず, 腹部CT検査で右下腹部にlow densityの腫瘤を認め, 内部に直線状のhigh densityの異物陰影が認められた.魚骨による消化管穿孔と診断し, 同日緊急手術を行った.開腹すると中等量の膿性腹水を認め。Treitz靱帯から220cmの部位に, 腸間膜側に穿孔する長さ2.5cmの針状の魚骨を認めた.小腸部分切除術と洗浄ドレナージ術を施行した.本症例は患者からの病歴聴取と腹部CT像の注意深い読影によって術前診断が可能であった.
1 0 0 0 OA 局所疼痛に対する針作用の実験的研究
- 著者
- 木下 晴都
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.405-409, 1981-08-28 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 2
モルモットの坐骨神経を切断して, 1~2週間経過した後の腓腹筋では, 強縮後減弱した短縮高の回復過程に対する施針の促進作用は出現しなくなった.このように除神経によって針効果が消失したことは, 強縮後の減弱した短縮高回復を促進する針の作用は, 軸索反射によることの一つの確証となる.強縮後の短縮高の回復過程を指標として, 施針刺激の条件を検索した結果, 3mmの浅刺では施針の効果は出現せず, 10mmの深刺で効果が現れた.施針の数を1本としても, 3本としても, また針の太さを0.65mm, 0.25mm, 0.13mmとしても, あるいは針を20分間刺しておく置針としても, 直ちに針を抜く単刺としても, 針の強縮後の減弱した短縮高の回復促進作用には変化はみられなかった.なお強縮前に施針した場合には針作用は出現しなかった.
1 0 0 0 中高校生における皮下脂肪厚と初潮との関係:特にその地方差について
- 著者
- 野井 信男
- 出版者
- The Showa University Society
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.501-512, 1978
Subcutaneous adipose tissue (SAT) in 36 parts of the body was examined on 92 junior high school girl subjects in Tokyo, and 167 junior and senior high school girls in Okinawa. During their menarche years, the thickness and distribution of SAT were studied and the following results were obtained :<BR>1) Before menarche, the thickness of SAT on most parts of body was thicker in Tokyo girls than in Okinawa girls, and was especially predominant on the hip, abdomen and the proximal parts of the extremities of Tokyo girls. However, no geography related differences were seen around the nipple and waist.<BR>2) On the premenarche girls in Tokyo, the thickness of SAT was largest primarily at the lower halves of the hip, secondarily at the upper hip and upper posterior thigh, followed by the middle region of the thigh and waist, and the nipple, calf and navel in that order. This distribution pattern of SAT seemed to be nearly the same on the premenarche girls in Okinawa ; although the thickness of SAT around the nipples of Okinawa girls was equal to that in the middle thigh and waist, while on the calf it was thinner than in Tokyo girls.<BR>3) The thickness of SAT in the nipple part proceeded to increase for one year in Tokyo girls and for 2.5-3.5 years in Okinawa girls after menarche. It reached the thickness of hip, middle thigh and waist SAT in Tokyo girls, and matched the largest parts in Okinawa girls.<BR>4) On the post-menarche girls, the thickness of SAT increased strikingly in the thigh, calf and proximal parts of the upper extremities during 1-2 years after menarche in Tokyo, while in Okinawa the thickness gradually enlarged during 3-4 years after menarche and reached the same values as those of Tokyo girls. The thickness of SAT which was seen in the post-menarche girls in Tokyo was greater than in Okinawa in the shoulder, abdomen, hip, anterior parts of the lower extremities and posterior parts of the legs.<BR>5) In the post-menarche years, the development of thickness of SAT was a rapid type in Tokyo and a gradual type of Okinawa. The former seemed to be close to the type seen in Kagoshima prefecture which was reported by Kawamura (1954) .<BR>These facts suggest that the differences in development of thickness of SAT in young girls during their post-menarche years is one of the effects of regional environment differences.
1 0 0 0 OA H2受容体拮抗剤による精神障害の1例
- 著者
- 成田 和広 鈴木 和雄 李 雨元 相田 貞継 普光江 嘉広 村上 雅彦 草野 満夫
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.112-115, 1996-02-28 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 9
症例は68歳, 男性, 上腹部痛による急性腹症にて入院.上部消化管内視鏡検査にて, 胃体部から前庭部に浅いびらんが多発しており, 急性胃粘膜病変と診断された.絶飲食のもと, ファモチジン20mgを12時間毎に投与開始したところ, 翌日より幻覚, 見当識障害, 夜間徘徊等の異常行動出現した.精神障害症状が持続するため4日目にファモチジンを中止したところ, 24時間以内に速やかに同症状が消失した, H2受容体拮抗剤の副作用に, 可逆性の錯乱状態があるが報告例は少ない.本剤の使用頻度は増加傾向にあり, 日常容易に処方され, その副作用は忘れがちである.状況によっては本例のような副作用の出現もあり, 注意深い使用が必要と思われた.
1 0 0 0 OA 小児細菌性赤痢より分離した緑膿菌の血清型別について
1 0 0 0 顔面表情筋(眼輪筋および口輪筋)の支配神経に関する研究
1 0 0 0 OA 顔面表情筋(眼輪筋および口輪筋)の支配神経に関する研究
- 著者
- 塩澤 佳 吉本 信也 三川 信之 森山 浩志 大塚 成人
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.6, pp.656-661, 2012 (Released:2013-10-10)
- 参考文献数
- 20
顔面神経が顔面表情筋にいたる微小解剖,すなわち表情筋における顔面神経末梢枝の分布,交通についてはほとんど報告がない.今回われわれは,顔面表情筋,特に眼輪筋と口輪筋を支配する顔面神経末梢枝の分布と走行について精査を行ったので報告する.対象は日本人の成人解剖体20体の顔面片側20側,平均年齢87.36(60歳~102歳)で,その内訳は男性10体,女10体,左側10例,右側10例である.方法は顔面神経を耳前部皮膚切開より展開し茎乳突孔から同神経本幹を剖出し,末梢枝については,顕微鏡を用いながら表情筋にいたるまで走行を追い観察した.同神経の枝すべてについて観察を行ったが,特に頬骨枝と頬筋枝について眼輪筋と口輪筋への分布を中心にそれぞれの走行,分布について探求した.その結果,頬骨枝は眼輪筋にすべて分布していたが,25体中8体で口輪筋に分布していた.また頬筋枝も全例で口輪筋に分布していたが,25体中5体で眼輪筋への分布を認めた.顔面表情筋のなかでも,特に重要な働きをする眼輪筋と口輪筋は,教科書的には,眼輪筋が顔面神経の側頭枝と頬骨枝,口輪筋が顔面神経の頬筋枝(あるいは頬筋枝と下顎縁枝)が支配神経と記載されている.今回,顔面神経末梢枝の眼輪筋と口輪筋に停止する解剖と走行について精査を行った結果,従来の成書にはない多数の破格が認められ,その運動も代償している可能性が考えられた.
1 0 0 0 OA 大腸癌治癒切除症例における静脈侵襲の検討
- 著者
- 横川 京児 河村 正敏 新井 一成 塩川 章 太田 秀一
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.419-428, 1991-08-28 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1
大腸癌の予後を左右する重要な因子に血行性転移があげられる.特に肝転移は予後に大きく関与しており, 静脈侵襲の程度を観察することにより, 肝転移の危険性を予測することが十分可能であると考えられる.今回著者らは, 進行大腸癌治癒切除症例における静脈侵襲状況をVictria blue-H・E染色を用い観察し, 静脈侵襲の有無, 侵襲程度, 侵襲部位および侵襲静脈径を検索し, これらの肝転移への関与, ならびにその臨床病理学的意義を検討した.対象は, 教室における過去8年間 (1981.1~1988.12) の初発大腸進行癌切除症例378例中単発大腸癌治癒切除症例220例である.静脈侵襲陽性は141例 (64.1%) であり, これらの静脈侵襲頻度をv1; 1~2個, v2; 3~6個, v3; 7個以上, に分け, また, 侵襲静脈径を各症例の最も太い静脈径によりS・M・L群に分類し検討した.侵襲頻度別にみるとv1: 80例 (56.7%) , v2: 48例 (34.0%) , v3: 13例 (9.3%) , 侵襲径ではS群: 18例 (12.8%) , M群: 95例 (67.4%) , L群: 28例 (19.9%) であり, 両者の問に相関関係がみられ, 侵襲頻度が多いものほど, 侵襲径の大きい群に属した.v (+) 例では中分化癌, a2+Sが有意に高率であった.静脈侵襲頻度, 侵襲静脈径と占居部位, 組織型, 深達度およびリンパ節転移との問に相関をみられなかったが, リンパ管侵襲のうち1y3とに相関関係を認めた.予後の検討では, v (-) , v (+) 症例の5生率はそれぞれ84.2%, 58.6%と有意差がみられ, 静脈侵襲頻度が高い症例ほど, また静脈侵襲径が太いほど予後不良であった.肝再発は17例 (7.7%) にみられ, うち16例がv (+) であった.静脈侵襲頻度別にみると, v0: 1.2%, v1: 5.0%, v2: 12.5%, v3: 46.2%, 侵襲静脈径別では, S群: 5.6%, M群: 7.4%, L群: 28.6%, また, 漿膜下層静脈侵襲の有無で比較すると, ssv (+) : 16.3%, ssv (-) : 3.6%であり, 静脈侵襲頻度の高いもの, 侵襲静脈径の太いもの, ssv (+) で有意に肝再発がみられた (p<0.05) .また, 占居部位, 組織型, リンパ管侵襲およびリンパ節転移では相関関係がみられず, 深達度のみに肝再発との相関関係を認めた.以上, 大腸癌における静脈侵襲状況は術後肝再発を予測するうえできわめて重要であり, これらの危険因子の大きい症例では治癒切除症例であっても厳重な経過観察が必要であると考えられた.
1 0 0 0 OA 植込み型心電ループレコーダーによる失神診断
- 著者
- 小林 洋一
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.6, pp.564-575, 2011-12-28 (Released:2012-08-03)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA EMRからESDへ
- 著者
- 大圃 研
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.3-9, 2011-02-28 (Released:2011-09-01)
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 OA IgA腎症と口蓋扁桃の関連に関する検討
- 著者
- 森 智昭 金井 英倫 寺崎 雅子 門田 哲弥 嶋根 俊和 三邉 武幸
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.5, pp.547-552, 2012 (Released:2013-06-07)
- 参考文献数
- 17
背景:IgA腎症は慢性糸球体腎炎のうち,糸球体メサンギウム細胞・基質の増殖性変化と,メサンギウム領域へのIgAを主体とする沈着物を認める疾患である.近年IgA腎症患者に口蓋扁桃摘出術とステロイドパルス療法を行う扁摘パルス療法の有効性が注目されている.またIgA腎症患者の口蓋扁桃では,慢性扁桃炎患者の口蓋扁桃と比較して病理組織学的に異なった特徴を示すとされている.対象,方法:昭和大学藤が丘病院腎臓内科で2007年から2008年にIgA腎症と診断され,口蓋扁桃摘出術を施行した49例の口蓋扁桃の病理組織学的特徴について検討した.結果:IgA腎症患者の口蓋扁桃では,リンパ濾胞の大きさが大小様々で境界が不明瞭となる,濾胞間領域も不規則に拡大,上皮では上皮間に形質細胞系細胞が増加・充満するといった特徴を各項目で半数以上の症例で認められた.結論:IgA腎症患者の口蓋扁桃には特徴的所見を高率に認めた.これらの特徴とIgA腎症の病態との関連は明らかではなく,今後の検討課題と考えられる.
1 0 0 0 OA MRIによる鼻腔容積の検討
- 著者
- 土佐 泰祥
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.148-157, 1992-04-28 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 29
今日, 鼻副鼻腔炎の原因として鼻腔形態異常が重視されてきており, また口唇口蓋裂患者の術後に鼻閉感を訴える場合があり, 鼻腔形態や鼻腔容積の異常が鼻腔通気度・鼻閉感に影響していることが考えられている.しかし, 鼻腔形態について詳細に調査した報告は少なく, 鼻腔容積についての報告はみあたらなかった.今回, 鼻腔領域疾患の診断・治療あるいは口唇口蓋裂患者の術前・術後の検討への応用の前段階として, 8~23歳の健康ボランティア69例 (男性: 17例, 女性: 52例) 平均年齢16.3±4.1歳に, MRIを用いて鼻腔領域の撮影を行ない, 鼻腔容積を求め, 年齢・身長・体重に対する相関関係について調査・検討を加えた.使用機種は, シーメンス社製のマグネトームM10で, 1.0テスラの磁場強度の超伝導型装置で, 撮像条件はT1強調像, 繰り返し時間TR 600msec, TE 19msecのshortスピンエコー法で, スライス幅は3mmまたは4mmでギャップレスとし, 断層面は横断面を撮影した.鼻腔としては, 前方は梨状口部まで, 後方は後鼻孔部まで, 側方は上・中・下鼻甲介および鼻道を含み, 前頭洞・上顎洞などの開口部までとし, 上方は脳頭蓋の一部まで, 下方は口蓋の上面までとした.横断面の基準線としては, 正中矢状断面像で鼻根部最陥凹点と橋延髄移行部を結んだ線を選んだ.これはCTでよく用いられるCMラインとほぼ一致するからである.鼻腔容積は, 各々の横断面の断面積をMRI装置付属のディスプレイコンソールを用いて直接トレースし, スライス幅を掛けて柱状の容積を出し, これらを積み重ねて容積を算出した.8~23歳の対象を5つの年齢群 (1) 8~10歳, (2) 11~13歳, (3) 14~16歳, (4) 17~19歳, (5) 20~23歳に分けた.鼻腔容積・身長・体重の平均を年齢群別でみると, 身長・体重の伸びは16歳ころでほぼプラトーとなっているのに比べ, 鼻腔容積の増加は, 20歳ころまで続いていた.統計学的解析として, 鼻腔容積と年齢, 身長, 体重, について, ピアソンの相関係数・回帰直線を求め, 有意の相関係数・回帰直線を得た (p<0.05) .また, 男性群と女性群との間で相関係数と回帰直線の傾きで有意の差を認めなかった.統計学的処理では鼻腔容積に対して年齢, 身長, 体重で比較的強い相関関係が認められ, 体重との相関に比べ身長との相関がより強いという結果を得た.
1 0 0 0 OA 1.「ヘリコバクター・ピロリ感染症」
- 著者
- 高橋 信一
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.6, pp.550-555, 2003-12-28 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 大動脈弓から直接分岐する左椎骨動脈の1例
- 著者
- 丸井 輝美 力武 諒子 柴田 昌和 江連 博光 伊藤 純治 鈴木 雅隆 後藤 昇
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.259-263, 2005-06-28 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 11
2003年度昭和大学医学部解剖学実習で, 58歳男性 (癌性悪液質・下咽頭癌により死亡) のご遺体で大動脈弓から左椎骨動脈が直接分岐する例に遭遇したので報告する.本例はAdachi-Williams-中川分類のC型に相当し, Adachiの報告では日本人の出現頻度は約5%で, 当大学の本年度解剖実習では30体中1例 (出現頻度: 3%) であった.本例は, 大動脈弓の第一枝として腕頭動脈が起始, 第二枝として左総頚動脈が分岐し, 第三枝として左椎骨動脈が大動脈弓から分岐していた.また, 左椎骨動脈は第4頚椎の横突孔に入り上行していた.一般的に左鎖骨下動脈は大動脈弓からの第三枝として起始しているが, 本例では第四枝として起始していた.
1 0 0 0 OA 糖尿病治療を変える新たな糖尿病薬インクレチン
1 0 0 0 OA クローン病の緩解導入, 再燃時における大腸内視鏡検査の有用性
- 著者
- 船津 康裕 神長 憲宏 浦上 尚之 千野 晶子 岩重 元栄 遠藤 豊 藤田 力也
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.84-93, 2001-02-28 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 24
クローン病の治療方針を決める指標として大腸内視鏡所見が応用可能かどうかについて臨床検討を行った.対象は成分栄養療法を行った, 大腸及び終末回腸に病変を有する23例のクローン病症例 (大腸型9例, 小腸大腸型10例, 小腸型4例) である.目的はクローン病の活動性の指標であるIOIBD, CDAI, 血沈 (ESR) , CRPと, 胃潰瘍病期分類に準じた内視鏡的潰瘍stage分類の比較を行い, 内視鏡検査の有用性を検討した.IOIBD, CDAIおよびCRP, ESRの緩解までの期間と, 内視鏡所見で潰瘍が治癒するまでの期間とを比較すると, 緩解が得られた時点での内視鏡像は治癒過程期16例 (H1stage1例, H1H2stage1例, H2stage2例, H2S1stage12例) , 瘢痕期7例 (S1stage4例, SIS2stage2例, S2stage1例) であり, 全ての潰瘍が瘢痕化 (S2stage) するには, さらに数ヶ月の期間を要した.次に緩解持続期間と緩解時の内視鏡stageの関連を検討した.S2stage (23.6±31.0月: 11例) まで改善した症例の方が, S1S2stage (7.6±6.3ヶ月: 7例) , S1stage (3.6±1.7ヶ月: 5例) までの症例に比べ有意に緩解持続期間が長かった (p<0.05) .また臨床的に緩解期と診断されていても, 内視鏡的にはすでに潰瘍が出現している症例が多かった.以上のことから, クローン病では長期間の緩解を持続させるためにはS2 stageまで治療を継続させることが重要であり, それにはより長い治療期間が必要である.また再燃に先行して内視鏡的増悪が確認できた症例が多く, 他の指標に比べ内視鏡検査は再燃の早期発見に有用であった.大腸内視鏡検査でクローン病の腸管病変を評価することは, 治療方針を決定するうえで非常に有用であった.
1 0 0 0 OA 「坐」と日本文化
- 著者
- 森 義明
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.289-297, 2001-06-28 (Released:2010-09-09)
1 0 0 0 OA ヒト胎児の顔面表情筋と顔面神経分布について
- 著者
- 島田 茂孝 後藤 昇 島田 和幸 保阪 善昭
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.322-332, 2001-06-28 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 11
成人の顔面表情筋とそれらの筋に分布する顔面神経についての詳細な報告は多い.しかし新生児や乳児期における報告は少ない.この研究の目的は, 高胎齢児の顔面表情筋の発達分化とそれに伴う顔面神経の発達と分布を観察し, 各胎齢ごとに肉眼解剖的な観察により出生直後の新生児や乳児期の形態的な特徴をとらえることにある.表情筋の分化発達をみると, 27胎週齢頃からは, 閉瞼する際に働く筋や口唇周囲の筋の分化発達はよく, 眉毛や眉間, 鼻部に付く筋の分化発達は弱い.また同時期になると顔面神経本幹から分岐した末梢の枝である側頭枝, 頬骨枝, 頬筋枝, 下顎縁枝, 頸枝の各枝の識別は容易となり, 各枝の末梢分布は頬骨枝, 頬筋枝, 下顎縁枝, 頸枝では, それぞれの各表情筋群に分布することが容易に観察できたが, 側頭枝, 特に後方枝の末梢分布を肉眼で観察するのは困難だった.すなわち前頭部, 鼻部周辺の筋とその神経は分化発達が弱く, 閉瞼する際に働く眼輪筋や口唇周囲につく筋とそれらの筋に分布する神経は各部に細かく分化発達して, 表情筋の分化発達はその支配する顔面神経の発達と関係が深い.
- 著者
- 岩波 明
- 出版者
- 昭和大学昭和医学会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.4, pp.367-372, 2009-08