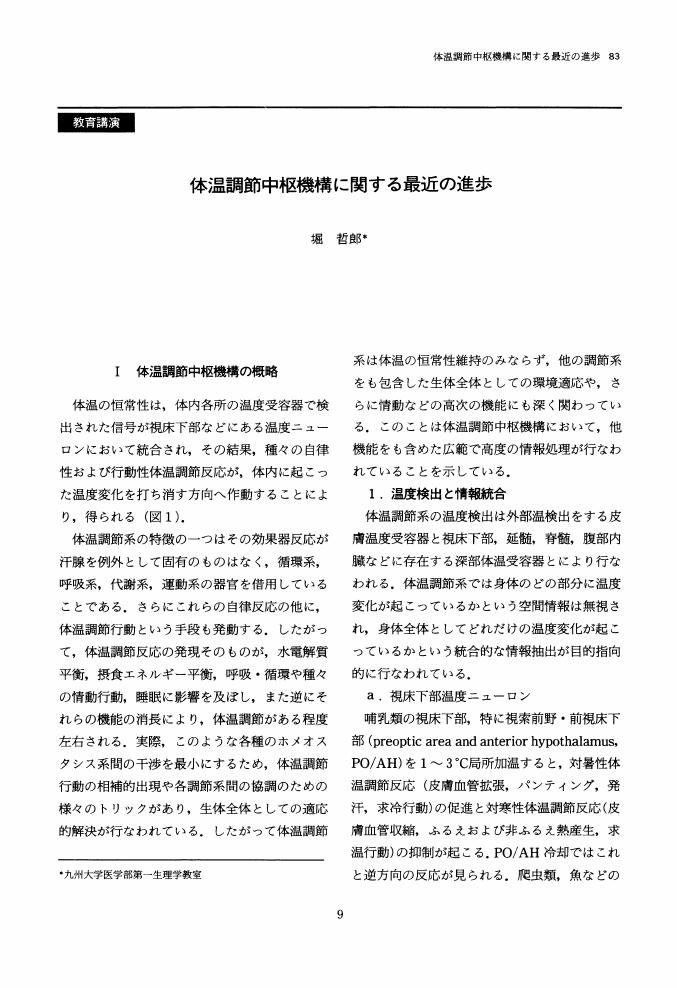1 0 0 0 OA 日本における筋弛緩拮抗と残存の状況
- 著者
- 中塚 逸央
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.205-211, 2013 (Released:2013-05-16)
- 参考文献数
- 14
筋弛緩モニターなしでロクロニウムを使用した全身麻酔手術後にネオスチグミンまたはスガマデクスを投与して筋弛緩を拮抗し,四連反応比<0.9となる残存筋弛緩の発生率を調査した.筋弛緩拮抗後,筋弛緩からの回復を主観的に確認した後に抜管した直後の残存筋弛緩はネオスチグミン群では23.9%の患者に見られたが,スガマデクスを用いた場合は4.3%と有意に少なかった.ネオスチグミン群での残存筋弛緩の要因として,高齢者,ロクロニウムの追加投与量が多い例,ネオスチグミンの投与量が少ない例やロクロニウムの最終投与からネオスチグミンの投与までの時間が短い例を認めたが,スガマデクスでの残存筋弛緩の要因としてはっきりしたものはなかった.
1 0 0 0 OA エホバの証人の帝王切開術における酸素供給量の変化
- 著者
- 原 哲也 稲冨 千亜紀 小出 史子 前川 拓治 趙 成三 澄川 耕二
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.316-320, 2009-05-15 (Released:2009-06-18)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
エホバの証人に対する帝王切開術の麻酔を, 動脈圧心拍出量 (APCO) から算出した酸素供給量を指標として管理した. 患者は40歳代の女性. 身長150cm, 体重56kg. 子宮筋腫合併高齢出産であったが, 宗教的信条から輸血を拒否したため, 帝王切開術が予定された. 麻酔は0.5%高比重ブピバカインによる脊髄くも膜下麻酔で行い第4胸髄レベル以下の知覚低下を得た. 術後鎮痛は0.2%ロピバカインによる持続硬膜外麻酔で行った. 同種血および自己血輸血は行わず, 貧血による酸素供給量の減少に対して, 輸液および昇圧薬で心拍出量を増加させ代償した. APCOの測定は低侵襲であり, 酸素供給量を指標とした麻酔管理に有用であった.
1 0 0 0 OA CVCセミナーを現場に活かすために
- 著者
- 松島 久雄 湯浅 晴之 徳嶺 譲芳
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.232-235, 2019-03-15 (Released:2019-04-19)
- 参考文献数
- 7
中心静脈穿刺による合併症をなくすことを目的としたCVCセミナーは,超音波ガイド法の理論を学習し,シミュレータを用いて実践できるセミナーとして発展してきた.しかしながら,CVCセミナーの受講者が現場の医療安全に貢献できているかというと,十分とは言えない状況である.CVCセミナーの受講者が習得したスキルを現場で活かすために,セミナーの変革が求められている.
1 0 0 0 OA 術後の抜管に要する時間への影響因子─麻酔薬の種類か麻酔科医の熟練度か─
- 著者
- 福島 東浩 澁谷 有香 小林 秀嗣 西川 正子 庄司 和広
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.1-8, 2019-01-15 (Released:2019-02-14)
セボフルラン(SEV)よりもデスフルラン(DES)の方が早く覚醒するといわれるが,実臨床では吸入麻酔の種類より麻酔科医の熟練度の方が影響を与えている可能性がある.本研究の多変量解析の結果,抜管までの時間はDES使用より(HR 1.17,[95%信頼区間 1.01-1.34],p=0.04),麻酔科医の熟練度の方が強く関連していた(研修医+指導医;参照,卒後6-9年;HR 1.59,[1.24-2.05,p<0.001],卒後10年;HR 1.53,[1.20-1.97,p=0.001]).抜管までの時間はDES使用で若干の短縮が認められたが,麻酔科医の熟練度の影響の方が大きいことが示唆された.
1 0 0 0 OA 突然の停電に遭遇して
- 著者
- 安江 雄一 濱部 奈穂 日生下 由紀 園田 俊二 香河 清和 谷上 博信
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.142-147, 2013 (Released:2013-03-12)
- 参考文献数
- 5
当院では2010年12月,業務中に突然の停電を経験した.自家発電設備は問題なく機能したが,停電発生後約1時間,原因特定や復旧のめどがまったく立たない状態であった.その間,患者搬送のエレベーターが使用できず,術後患者の管理に問題となった.この経験から,復旧のめどを含めた情報収集が重要であり,自家発電装置の性能や備蓄燃料は病院ごとにばらばらで場合によっては停電中の業務に支障が出うること,各機器の電源種別を決めておかないと思わぬ機器が動かず困る可能性があること,自家発電に切り替わるときに数十秒の停電となるため再起動が必要となる機器があり,その際実際に適切に操作できること,これらを平時より確認し,手順化しておくことが重要と思われた.
1 0 0 0 OA 脊髄鎮痛と交感神経
- 著者
- 西川 精宣
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5, pp.717-726, 2010 (Released:2010-12-24)
- 参考文献数
- 38
交感神経系は自律性生理機能に大きくかかわっているが,痛みの発生や持続にも関与しており,特に難治性疼痛の治療を考えるうえで検討すべき領域である.脊髄鎮痛,つまり薬剤の脊髄くも膜下投与と硬膜外投与を含んだ主として脊髄への直接効果による鎮痛法は,薬剤投与量の減量,副作用の軽減や作用時間の延長を期待できる.ネオスチグミンを除き,交感神経抑制が同時に生じる薬剤が多いが,少なくとも末梢交感神経遮断は痛覚過敏減弱にあまり影響していないようである.体内埋め込み型のくも膜下カテーテル注入装置は難治性疼痛治療の新たな展開をもたらす可能性があり,脊髄レベルでの交感神経遮断の役割を明らかにしていくことは意義があると考える.
1 0 0 0 OA 体表心電図を心筋活動電位から理解する
- 著者
- 田中 義文
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.124-132, 2014 (Released:2014-02-26)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 2
心電図の成書は1930年代に完成され,標準12誘導,アイントホーフェンの正三角形,平均電気軸の理論が紹介されている.その後,心筋活動電位,イオンチャネルなどの知見,心腔内マッピングなどの発展はあるものの,成書としてはいまだに1930年代の説明が踏襲されている.本稿では細胞外電位は心筋活動電位と極性が逆転している性質を利用して,心内膜側活動電位から心外膜側活動電位の引き算結果が第II誘導体表心電図であることを解説した.また,種々の心外膜側活動電位を変化させて,異常心電図の発生原理について言及した.
1 0 0 0 OA 頚椎後方手術後に脳神経麻痺による嚥下障害を生じた3症例
- 著者
- 平山 三智子 西川 光一
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.7, pp.943-947, 2012 (Released:2013-02-12)
- 参考文献数
- 10
頚椎後方手術後に,脳神経麻痺による嚥下および構音障害を生じた3症例を経験した.3症例とも術後に舌偏位が認められ,末梢性の舌下神経麻痺と診断された.1症例のみ迷走神経麻痺によるカーテン徴候を合併していた.嚥下および構音障害は術後2週間から3ヵ月間に改善し,以降も良好に経過している.脳神経麻痺の原因には,舌下,迷走神経を栄養する上行咽頭動脈の挿管チューブによる血流障害,術操作による直接障害,頚部の牽引に伴う神経の伸展による障害が疑われた.頚椎後方手術後の脳神経麻痺の発生はまれであるが,術後の嚥下障害や構音障害の原因となることを医療従事者が十分認識し,誤嚥の予防に取り組むことが必要である.
1 0 0 0 産科救急への対応
- 著者
- 照井 克生
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.718-725, 2018
<p>産科救急の対象には,産科疾患(出血,羊水塞栓症,子癇など)に加えて,妊娠に関連して増加・重症化する疾患(肺塞栓症,周産期心筋症,肺高血圧症など),産科麻酔で発生しやすい区域麻酔合併症(高位区域麻酔や局所麻酔薬中毒など)がある.産科救急への対応においては,産科病態や妊娠中の生理学的・解剖学的・薬理学的変化を理解して,産科医や他科と連携し,妊娠週数と胎児の状態に応じて治療する必要がある.妊婦の心肺蘇生においては子宮左方転位や死戦期帝王切開などの意義を理解しつつ,質の高いCPRを行う.</p>
1 0 0 0 OA サイコオンコロジーと漢方
- 著者
- 恵紙 英昭
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.5, pp.722-730, 2014 (Released:2014-10-25)
- 参考文献数
- 12
ヒトと漢方薬は自然の生き物という共通点がある.漢方においては患者の診断・治療とは全人的治療であるという考えが根底にあり,薬と身体との対話(反応)を大切にしている.これは精神科治療(サイコオンコロジー領域)にも共通しており,細かく患者の訴えを聴取し,生活環境,食生活,嗜好,生活リズム,家庭生活,人間関係などの情報を得て治療を行っている.患者とのコミュニケーションでは,傾聴,つらさを共感する姿勢,安心感と情緒的サポートが大切であり,繊細さを求められる.それを多職種という緩和ケアチームで実践することが大切である.構成生薬の薬能・薬性を考えながら処方するが,治療者は患者の「食べられなくなったら死ぬのではないか」という恐怖と不安を十分に理解し,消化器症状を軽減しながら治療することを忘れずに薬物を投与することを意識した方がよいと考える.本稿では,症例を呈示して漢方薬の有用性を示したい.
1 0 0 0 OA 体温調節中枢機構に関する最近の進歩
- 著者
- 堀 哲郎
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.83-94, 1989-03-15 (Released:2008-12-11)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA 私立総合大学の経営と医学部付属病院(手術室)の収益性について
- 著者
- 西山 純一
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.345-349, 2019-05-15 (Released:2019-06-19)
- 参考文献数
- 13
私立総合大学医学部である当施設は,学校法人収入で付属病院収入が学生納付金や補助金を上回っている.内訳では手術・集中治療の収益が高く,効率的手術室運営が大学経営に大きく寄与している.大学は元来収益性とは無縁だが,本学は付属病院の事業性を無視できず,経営が医療収入に依存した構造となっている.一方,手術・集中治療領域の収益は病院収入の多くを占め,多施設で手術室を有効利用し件数を増加させる工夫がされているが,近年,ロボット手術などの低侵襲手術やハイブリッド手術室などの高機能手術室が求められ,手術室運営の効率化ならびに手術患者の安全管理に,部屋・機器・人の限定や患者の高齢化・ハイリスク化といった新たな課題を投げかけている.
1 0 0 0 OA 侵襲と生体防御反応の展開
- 著者
- 小川 龍
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.9, pp.691-694, 1994-11-15 (Released:2008-12-11)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 麻酔中に遭遇した無カタラーゼ血液症の1症例
- 著者
- 濱田 良一 濱田 文香 松岡 秀美 伊藤 寛之 石崎 卓 一色 淳
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.63-66, 1998
71歳,男性の喉頭全摘術麻酔中に,メトヘモグロビン血症を発症した無カタラーゼ血液症を経験した.1.5%過酸化水素300mlで口腔粘膜を消毒したところ,経皮的酸素飽和度の低下(SpO<sub>2</sub>:80%)とPaO<sub>2</sub> (235mmHg)との解離,術野血液の黒褐色変化,メトヘモグロビンの増加(11%)などを認めた.メトヘモグロビン血症と診断し,アスコルビン酸2,000mgを静注した.術後口腔粘膜の浮腫と潰瘍,溶血性貧血(Hb 7.7g/dl),および肝障害(総ビリルビン5.6mg/dl)を生じた.赤血球酵素活性検査により,母親と子供3人も遺伝的低カタラーゼ血液症があり,本症例は無症候型の無カタラーゼ血液症と診断された.
1 0 0 0 星状神経節ブロックによるCO2換気応答の抑制
- 著者
- 大堀 久 津田 喬子
- 出版者
- THE JAPAN SOCIETY FOR CLINICAL ANESTHESIA
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.7-13, 1997
星状神経節ブロック(SGB)後の1回換気量減少の機序を明らかにする目的で,SGB療法中の患者を対象にSGB前,後の二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)換気応答をReadの再呼吸法を応用して解析した.対照群として健常者に,生理食塩水の星状神経節部注入を行ない同様の検討をした.終末呼気CO<sub>2</sub>分圧を横軸に,1回換気量あるいは分時換気量を縦軸にとり,比較したところ,局麻薬によるSGB後には傾きが減少した.しかし生理食塩水の注入では一定の傾向を認めなかった.SGBはCO<sub>2</sub>換気応答を抑制し,それが安静時1回換気量,分時換気量,SpO<sub>2</sub>の減少の一因である可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA ロクロニウムからの筋弛緩回復と拮抗の実際
- 著者
- 中塚 秀輝 佐藤 健治
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.5, pp.836-846, 2008-09-12 (Released:2008-10-17)
- 参考文献数
- 26
ロクロニウムは効果発現が速いことを特徴とするステロイド系の中時間作用性筋弛緩薬であり, 筋弛緩効果からの回復を考えるときには, 揮発性吸入麻酔薬など筋弛緩薬の効果を増強する因子の影響を考慮する必要がある. 抗コリンエステラーゼ薬により筋弛緩作用の拮抗が可能であるが, 筋弛緩からの必要十分な回復の判断は難しく, 拮抗薬の投与時期とその副作用には注意が必要であり, 筋弛緩モニターによる管理を要する. スガマデクスはロクロニウムを直接包接することで筋弛緩作用を拮抗する直接的筋弛緩拮抗薬である. 臨床試験では深い筋弛緩状態からの迅速な拮抗も可能であり, 重篤な副作用もみられていない. 臨床使用可能になれば, 術中・術後の患者の安全性に寄与すると考えられ, 今後の発展が期待される.
1 0 0 0 OA 全身麻酔後に生じた耳下腺炎の1例
- 著者
- 中江 裕里 高橋 俊彦 宮部 雅幸 並木 昭義
- 出版者
- THE JAPAN SOCIETY FOR CLINICAL ANESTHESIA
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.189-192, 1993-03-15 (Released:2008-12-11)
- 参考文献数
- 15
軽度の耳下腺腫脹と著明な血清アミラーゼ値の上昇により術後耳下腺炎と診断された症例を経験した.耳下腺の腫脹は手術後1日目から6日間持続したが,炎症症状を欠き,局部の冷却湿布と通常の上腹部手術術後管理に準じた抗生剤および輸液管理により軽快した.耳下腺腫脹の原因としては手術中のバツキングによる腹圧上昇,気管内チューブによる咽頭反射の亢進による唾液腺の静脈うっ血に起因する耳下腺管の閉塞が考えられた.術後耳下腺炎はまれな合併症であるが,日常の麻酔管理における操作が原因となりうることを常に銘記すべきと思われた.
1 0 0 0 OA 透析患者における術前経口補水療法の有用性と安全性の検討
- 著者
- 中川 博美 佐和 貞治
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.148-155, 2017-03-15 (Released:2017-04-21)
- 参考文献数
- 19
透析患者において,術前摂取水分・電解質の安全域の狭さと胃内容排出遅延の可能性に留意し,術前経口補水療法(以下,ORT)の安全性と有用性を検討した.透析患者の一般予定手術症例200例を対象とし,ORT群と輸液群で麻酔導入前の血清電解質・血糖値,水分負荷指標として手術後の体重増加率を比較した.また,胃幽門部断面積と胃液量から麻酔導入時の胃内容を評価した.ORT群では摂取した水分量,電解質と糖は輸液群より多かったが,電解質異常や高血糖症を呈した症例数は輸液群より有意に少なかった.体重増加率と胃内容量は両群間で差がなかった.透析患者でも術前ORTは安全で有効な体液管理法である.
- 著者
- 高橋 敬蔵 坂本 勇人 高橋 俊一 奥富 信博 山中 郁男
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.3, pp.130-138, 1982
Pancuronium およびその生体内代謝産物は Spectrofluorimetric metbod によれば overall として測定される. また Pancuronium は蛋白結合, 脂肪溶解により不活性化される. したがって血中 Pancuronium の濃度そのものが効果を示すと解釈することは困難である. 著者らはマグヌス法において蛙腹直筋の Acetylcholine による収縮に及ぼす血清量 (蛋白量) ならびに Pancuronium の影響を検討した結果, 血清蛋白量の増加に伴って Pancuronium の不活性化が著しく, 蛋白濃度が1.4g/dl以上では72%以上の抑制がみられた. 成人に4mgの Pancuronium Bromide を bolus に静脈内投与後5分に0.48, 30分0.4, 60分0.3 (μg/ml) に相当する生物学的活性濃度を認めた.
1 0 0 0 OA 人工知能と自動麻酔・自動アシスト麻酔
- 著者
- 増井 健一
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.410-414, 2018-05-15 (Released:2018-06-23)
2016年はAlphaGo(Google DeepMind)がプロの高段囲碁棋士に勝利したニュースや公道での車の自動運転実験のニュースなど,自ら学習する人工知能のニュースが多い1年であった.麻酔の分野で人工知能に関連することというと「自動麻酔」が思い浮かぶ.現状でも麻酔薬の設定濃度が維持される自動システムが存在する.全身麻酔薬の効果を一定に維持するように薬剤投与を行う「自動麻酔」システムには,精度を保った脳波モニタリングと連続した実測濃度測定が必要となる.コンピュータのアシストによる麻酔管理は,麻酔科医の欠点を補い医療の質を向上させると考えられる.