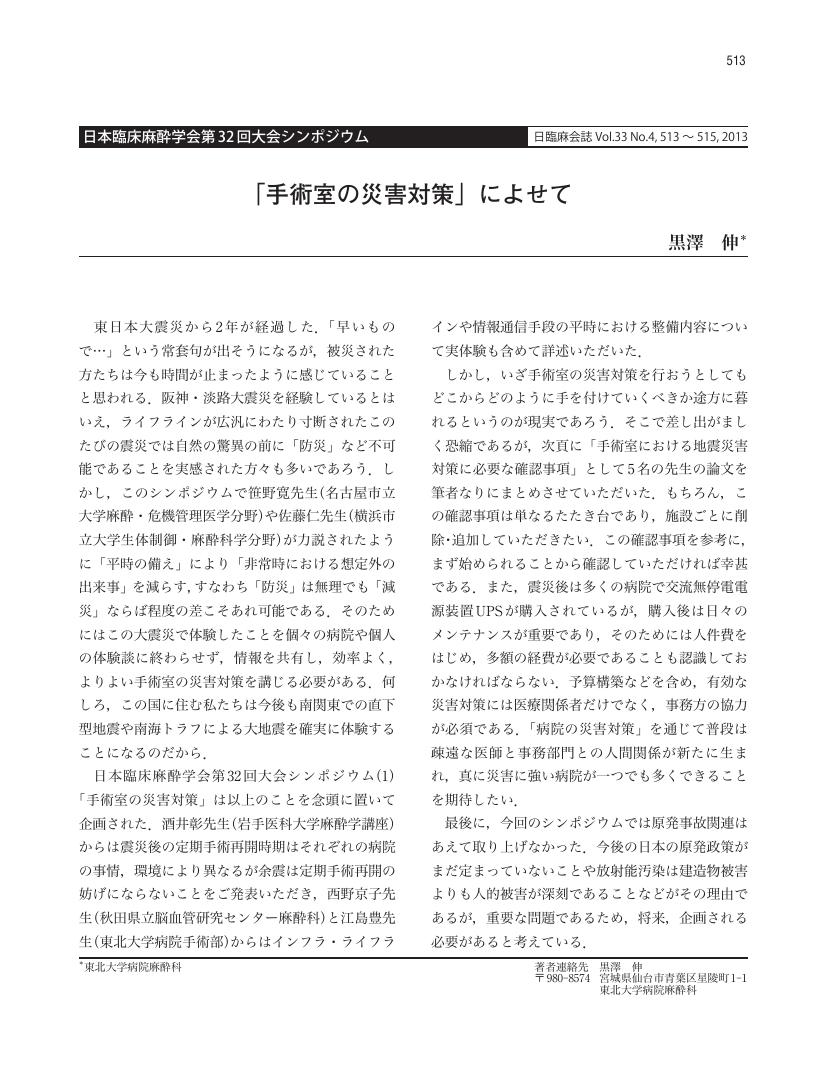1 0 0 0 OA 無痛分娩は誰が担当するべきか—麻酔科医が無痛分娩に携わるうえで生じる問題点とその解決法—
- 著者
- 奥富 俊之
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.159-164, 2008 (Released:2008-02-16)
- 参考文献数
- 3
麻酔科医からすれば, 無痛分娩は麻酔行為であるから, その担当者は当然麻酔科医と思うかもしれない. しかし実際に産科麻酔を実践するには, 麻酔科学の基礎知識や麻酔技術はいうまでもなく, 麻酔が母親の出産体験や, その後の家族の育児にどのようにかかわるのか, 自然の分娩経過にどのような影響を及ぼすのか, あるいは担当産科医の分娩管理にどのように影響を及ぼすのかを考慮し, 家族, 産科医, 新生児科医, 助産師など妊婦を取り巻く人々と良好なコミュニケーションをとりながら, 妊婦にいかに安全で快適な環境を提供できるかを考えていく必要がある. そのためには産科麻酔科医というサブスペシャルティーの確立が望まれる.
1 0 0 0 OA 周術期管理チームと薬剤師
- 著者
- 柴田 ゆうか 河本 昌志 木平 健治
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, pp.523-530, 2014 (Released:2014-09-06)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 1
手術室薬剤師業務は事故防止と薬品適正管理の観点から始まり,薬剤師の一元管理による薬品管理強化に貢献した.しかし薬物療法の適正使用への貢献において薬剤師の専門性が遺憾なく発揮されているとは言い難い.また多くの病院で薬剤師が充足しているとはいえない状況があり,いまだ手術室への薬剤師配置ができないところもある.手術室における薬剤師の参画を進展するためには,周術期医療における薬剤師業務の指針の作成や診療報酬上のインセンティブなど手術室への薬剤師配置のための環境整備が今後の課題である.
1 0 0 0 OA 頸部持続硬膜外麻酔中の血漿リドカイン濃度
- 著者
- 佐藤 紀 宮部 雅幸 川真田 樹人 中江 裕里 表 圭一 並木 昭義
- 出版者
- THE JAPAN SOCIETY FOR CLINICAL ANESTHESIA
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.9, pp.616-619, 1995-11-15 (Released:2008-12-11)
- 参考文献数
- 6
咽喉頭全摘出術患者10名にリドカインを用いて頸部硬膜外麻酔を施行し,反復投与による血漿リドカイン濃度の推移を検討した.笑気酸素-セボフルランを用いた全身麻酔下で,初回に20万倍エピネフリン添加2%リドカイン3mg/kgを投与し,1時間後より1時間ごとに20万倍エピネフリン添加1.5%リドカインを循環動態に応じて1~2mg/kg追加投与した.初回投与後,血漿リドカイン濃度は15分でピークに達し,追加投与直前の1時間後に最低となった.初回投与3.5時間後に2.6±0.6 (SD) μg/mlに達した後は,およそこの血漿中濃度で安定した.長時間にわたる頸部手術における頸部硬膜外麻酔併用全身麻酔では,安全なリドカイン血漿濃度を維持できることが示された.
1 0 0 0 OA リドカインテープによる表在痛と深部痛の痙痛閾値の変化
- 著者
- 藤本 淳 木田 景子 宇野 太啓 池邊 晴美 谷口 一男 野口 隆之
- 出版者
- THE JAPAN SOCIETY FOR CLINICAL ANESTHESIA
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.6, pp.400-403, 1999-07-15 (Released:2008-12-11)
- 参考文献数
- 11
貼付用リドカインテープ(ペンレス®)は,患者に疼痛を与えない局所麻酔を目的として開発されたテープ剤である.今回,健康成人ボランティア20人を対象として,リドカインテープによる表在痛及び深部痛の疼痛閾値の変化を測定し,プラセボと比較して評価した.表在痛の疼痛閾値はリドカインテープ群がプラセボ群に比較して有意な上昇を示したが,深部痛では両群間に有意差はみられなかった.リドカインテープは表在痛に対して有効であり,使用法が簡便であることや患者の苦痛を伴わないことから有用な鎮痛法であると思われた.一方,深部痛に対しては有効性は認められなかったが,貼付法•貼付時間の点からさらに検討の必要があると思われた.
- 著者
- 松木 明知
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.427-440, 2005
華岡青洲 (1760~1835) は江戸時代後期の医師であるが, 1804年に麻沸散を用いて, 世界で初めて全身麻酔を行ったことで広く知られている. しかし青洲自身記録や著書を書かなかったため, 多くのことが謎として未解決のまま残されている. 例えば彼の末娘の名前や生没年はまったくわからなかった.<br> 著者は青洲と同じ麻沸散を作り, 動物実験を繰り返し, 麻沸散開発の経緯を明らかにした. また華岡家の菩提寺であった地蔵寺の過去帳を発見して, 青洲のこれまで知られていなかった兄弟, 子女の名前や没年を明らかにした. 青洲の思想 「内外合一活物窮理」 は現代の医学においても通用する.
1 0 0 0 OA レミフェンタニル clinical pearls and pitfalls
- 著者
- 木山 秀哉
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.375-386, 2008 (Released:2008-06-07)
- 参考文献数
- 23
長時間持続投与してもcontext-sensitive half-timeが延長しない独特の薬物動態学的特徴を有するレミフェンタニルは, 術後の呼吸抑制を懸念することなく高いオピオイド濃度を維持する麻酔を可能にした. 併用する就眠鎮静薬や筋弛緩薬の必要量が減るなど, バランス麻酔の概念が変化している. 術中の循環動態の安定と, 麻酔終了時の迅速な自発呼吸回復が得られる利点がある. 一方, 筋強直や声門閉鎖に起因する換気困難, 鎮静薬の過少投与による術中覚醒を防ぐことが重要になる. 局所麻酔, 長時間作用性オピオイド, ケタミン等を適切に組み合わせることで, 術後鎮痛への円滑な移行と術後痛覚過敏の防止を図る. 静脈麻酔を安全に行ううえで, チェックリストの使用を推奨する.
- 著者
- 中村 達雄
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 = The Journal of Japan Society for Clinical Anesthesia (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.507-512, 2013-07-13
- 参考文献数
- 14
人工神経管(PGA-C tube)を用いた再生医学の臨床応用が2002年より始まっている.この再生医療を支えるのが<I>in situ</I> Tissue Engineering(生体内再生)の概念である.<I>in situ</I> Tissue Engineeringは欠損した組織を生体内のその部位(<I>in situ</I>)で再生させる手法で世界に先駆けて本邦で提唱された.末梢神経は再生能力を有するが,人工神経PGA-C tubeは神経再生の「場」をPGAチューブの内腔に有する医療器具である.これまでに再建した末梢神経は合計300本を超え,また神経因性疼痛に対しても効果があることが判明し,新たな治療法として期待が高まっている.
1 0 0 0 OA 「手術室の災害対策」によせて
- 著者
- 黒澤 伸
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.513-515, 2013 (Released:2013-09-13)
- 著者
- 伊藤 志保 藤原 淳 趙 崇至
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.096-100, 2013 (Released:2013-03-12)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
頚部悪性腫瘍の気管浸潤や,頚部膿瘍,急性喉頭蓋炎による呼吸困難に対して,ECMO補助下に気管切開術の麻酔管理を安全に行った.高度気道狭窄を伴う症例の全身麻酔下での気管切開術は,麻酔導入時に容易に気道閉塞を起こす可能性がある.このため,慎重な気道確保が必要であり可能な場合はECMO補助下での気道確保を考慮すべきであると考える.
- 著者
- 佐藤 裕
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.598-605, 2013 (Released:2013-09-13)
- 参考文献数
- 6
本稿で取り上げる神経ブロックは,腰神経叢の主要分枝をブロックすることで下肢の手術麻酔および術後鎮痛,ペインクリニックに頻用される代表的なものである.まず腰神経叢の解剖を概説し,次いで各神経ブロックの手技のポイントを述べる.
1 0 0 0 OA 心肺蘇生法の機序と問題点
- 著者
- 新井 達潤
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.9, pp.395-406, 2004 (Released:2005-05-27)
- 参考文献数
- 45
科学的観点に立った心肺蘇生法(CPR)の開発は1900年代に入ってから始まり, 現在実施されている心肺蘇生法の基本骨格は1960年頃には完成した. 米国心臓協会(AHA)はこれらを総合し, 1974年に最初の心肺蘇生法ガイドラインを出版した. その後絶えず改善を重ね, 2000年には第5版(G2000)を出版した. G2000は蘇生に関する世界的協議会ILCOR(International Liaison Committee On Resuscitation)との緊密な連携のもとに作られたもので, 蘇生における世界的ガイドラインと考えて矛盾はない. AHAのガイドラインはヒトでの有効性が科学的に証明されたもののみを採用し, とくにG2000はEvidence-based medicineの立場を強調している. しかし, 必ずしも科学的には証明できないまま経験的有効性から採り入れられている部分もあり, また, 一般市民をも対象とするため妥協せざるを得ない部分もみられる. 本稿では現在のG2000を基準とした心肺蘇生法が, どのような考えのもとに作られ発展してきたか, また, どのような問題点を含んでいるのか, とくに作用機序の面から考察する.
1 0 0 0 OA 脊髄くも膜下麻酔による脊髄栄養血管損傷─大根動脈損傷による対麻痺発生の危険性─
- 著者
- 赤石 敏 小圷 知明 黒澤 伸 佐藤 大三 加藤 正人
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.7, pp.1008-1019, 2011 (Released:2011-12-13)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
脊髄くも膜下麻酔後に高位胸髄レベルの対麻痺が発生する医療事故が1960年代以降,日本でも少なくとも数十例発生している.一般的にTh9~10に入ることが多いAdamkiewicz動脈(大根動脈;arteria radicularis magna)は日本人の約0.5%の頻度で脊髄くも膜下麻酔が施行されるL3~5から脊髄に入ってくる.くも膜下腔に穿刺針を深く刺し過ぎると,馬尾神経損傷以外に,この動脈を損傷して不可逆的な高位対麻痺が発生する危険性がある.これを回避する最も重要なポイントは,必要以上に深く穿刺針をくも膜下腔に挿入しないことであると思われる.脊髄くも膜下麻酔を施行するすべての医師はこのことを常に念頭に置いておく必要がある.
1 0 0 0 OA 内頸静脈穿刺時に冠動脈スパズムの発生が疑われた腹部大動脈瘤破裂の1症例
- 著者
- 今泉 均 角田 一眞 渡辺 明彦 升田 好樹
- 出版者
- THE JAPAN SOCIETY FOR CLINICAL ANESTHESIA
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.343-347, 1988-07-15 (Released:2008-12-11)
- 参考文献数
- 12
虚血性心疾患の既往のない, 69歳男性の腹部大動脈瘤破裂の緊急手術前に, 中心静脈カテーテル挿入のため右内頸静脈穿刺時, 突然STの上昇と共に徐脈, 血圧低下を認めた. 腹部大動脈瘤患者では高率に冠動脈疾患を合併することから, 冠動脈硬化による冠動脈血管の tonus の亢進した状態下に, 中心静脈穿刺時の迷走神経刺激が誘因となって冠動脈スパズムが発生したものと考えられた.明らかな虚血性心疾患の既往がなくても全身的に高度な動脈硬化性疾患を有する患者の麻酔管理においては, 冠動脈硬化病変の存在並びに冠動脈血管の tonus の亢進によって, 冠スパズムや重症な不整脈の発生し易いことを十分に念頭におくべきである.
1 0 0 0 OA 疼痛治療に難渋したミュンヒハウゼン症候群の1例
- 著者
- 星 拓男 須賀 明彦 熊谷 恵 宮部 雅幸 佐藤 重仁
- 出版者
- THE JAPAN SOCIETY FOR CLINICAL ANESTHESIA
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.7, pp.609-612, 1996-09-15 (Released:2008-12-11)
- 参考文献数
- 8
患者は24歳女性.誤って漂白剤を浴び,アルカリ腐食性角膜潰瘍のため入院した.入院後,角膜穿孔と角膜移植を繰り返し,合計7回の角膜移植を受けた.この間痛みは,角膜の状態悪化とともに増悪し,ブプレノルフィンの筋注を最高1日6回まで必要とした.しかし薬物血中濃度から内服が守られていないことがわかり,痛みを訴える一方で,安静を守らないなど不審な点も多く,心理的要因を疑い精神科を受診したところ虚偽性障害が疑われた.薬物療法,面接,行動療法を行なったところ,それまでの痛みはブプレノルフィンを筋注して欲しいための嘘であったことがわかった.慢性痛を訴える患者では,チーム医療および精神科的アプローチの重要性を痛感した.
1 0 0 0 OA 観察研究
- 著者
- 田中 優 川口 昌彦
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.7, pp.676-680, 2016-11-15 (Released:2016-12-09)
- 参考文献数
- 11
観察研究には,コホート研究,横断研究,ケースコントロール研究,ケースシリーズ研究,記述研究がある.各々の研究デザインの良いところとそうでないところが存在する.観察研究はバイアスがあり,知っておかないと,論文の内容について誤解を生じる可能性がある.結果に影響を与えるものに偶然誤差,系統誤差,結果-原因,交絡があり各々調整方法がある.こういったことを踏まえて論文を読んでいけば大きな誤解は防げると思われる.
1 0 0 0 OA 術野消毒に用いた10%ポビドンヨードによる接触性皮膚炎
- 著者
- 原 哲也 穐山 大治 戸坂 真也 趙 成三 澄川 耕二
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.9, pp.531-534, 2004 (Released:2005-05-27)
- 参考文献数
- 9
術野の消毒に用いた10%ポビドンヨードによる接触性皮膚炎に対する損害賠償調停申立事件を経験した. 全身麻酔下の手術のために術野を10%ポビドンヨードで消毒し, 拭き取りは行わずに手術を開始した. 終刀後, 右鼠径部に線状小発赤を発見した. 発赤部に対し治療を行うも, 瘢痕を形成し固定した. 退院後, 国と主治医を相手に右鼠径部の病変に対する損害賠償が請求され, 調停の結果, 賠償金の支払いにより和解した. 液状のポビドンヨードとの長時間接触により接触性皮膚炎をきたす可能性がある. 比較的まれな合併症であっても医事紛争に至る例もあり, 日常的な医療行為にも細心の注意が必要である.
1 0 0 0 脊髄小脳変性症患者の気管喉頭分離術の麻酔経験
- 著者
- 酒井 一介 澄川 耕二
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 = The Journal of Japan Society for Clinical Anesthesia (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.470-473, 2008-04-28
- 参考文献数
- 10
脊髄小脳変性症患者の気管喉頭分離術の麻酔を経験した. 既往歴として声帯の外転障害による上気道の閉塞があり, 気道管理に配慮を要した. 喉頭展開時に観察された声門に異常は明らかでなかったが, 細径の気管チューブでなければ気管挿管は困難であった. 脊髄小脳変性症など多系統萎縮症では, 後輪状披裂筋の麻痺のため上気道の閉塞が起こることがある. 全身麻酔を行う場合には, 声門部の狭窄に注意し, 細径の気管チューブを準備するとともに, 経皮的気管穿刺や気管切開などの準備が必要である.
1 0 0 0 OA ブプレノルフィン持続皮下注入法による術後疼痛管理
- 著者
- 飯田 豊 鬼束 惇義 片桐 義文
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.36-39, 2010-01-15 (Released:2010-02-19)
- 参考文献数
- 10
当科では, 消化器外科手術後疼痛管理をブプレノルフィン持続皮下注入 (Bu皮下注) で施行している. 従来施行してきたモルヒネ持続硬膜外注入 (Mo硬膜外注) と比較検討したところ, 鎮痛効果, 補助鎮痛薬使用回数, ガス排泄までの日数には差を認めなかった. 膀胱内留置バルーン抜去までの日数はBu皮下注の方が短かった. 帰室時PaCO2はMo硬膜外注の方が高値であった. Bu皮下注でみられた副作用は投与中止により速やかに軽快した. Bu持続皮下注入は手技的にも簡便で安全であり, 呼吸抑制も少ないため有用な術後疼痛管理法である.
1 0 0 0 OA 宗教上の理由による輸血拒否
- 著者
- 山田 卓生
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.303-308, 2006 (Released:2006-05-26)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 4 2
宗教上の理由で輸血を拒否する患者に対し, いかに対処するべきかは, この30年の間医療関係者を悩ませてきた. とりわけ外科手術における輸血の必要性は言うまでもないが, 他方でインフォームドコンセントの考え方によれば, 明白な意思に反する輸血をするわけにはいかない. 当初は輸血拒否に当惑したが, 徐々に患者の意思を尊重するようになってきた. 意思を無視して輸血をすれば, たとえ快方に向かっても損害賠償の義務があるとする最高裁判決も出た. 子供についてどうするか, とくに, 親が自己の信仰に基づき子供への輸血を拒否することを認めるべきかが争われている.
1 0 0 0 OA 麻酔科開業の現状と今後 —保険医療制度下における麻酔科開業医のあり方—
- 著者
- 梅垣 裕
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.507-517, 2005 (Released:2005-09-28)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1 1
2002年現在, わが国では推定約312万件以上の麻酔が行われ, そのうち約188万件以上が全身麻酔により行われている. しかしそれに対応する, 手術室で麻酔業務に携わる麻酔科医数は, 2002年時点でわずか6,087人に過ぎない. 従来の主たる業務を手術室の麻酔とし, これを保険医療制度下で行う麻酔科開業は事実上困難であった. 近年, 厚生労働省は麻酔科開業医の出張麻酔を保険医療における対診と認め始めた. しかし, 自治体によってはいまだ出張麻酔を主たる業務とする麻酔科診療所開設に門戸が閉ざされており, 出張麻酔開業医はまだまだ少数にすぎない. 現在, 麻酔科医の就業には多様な形態がみられる. そのなかで保険医療機関としての麻酔科開業は, 唯一麻酔科医が病院との間で雇用関係ではなく, 対等の立場で業務を行えるものである. 出張麻酔を主とした麻酔科開業は, 現在の麻酔科のマンパワー不足をただちに解消に結びつけるものとは思われない. しかし長期的展望からみると, 麻酔科医の将来設計の一選択肢となり, 麻酔科を志す医師を増やし, かつ手術室の麻酔業務からの離脱を食い止める一つの方策であると考える.