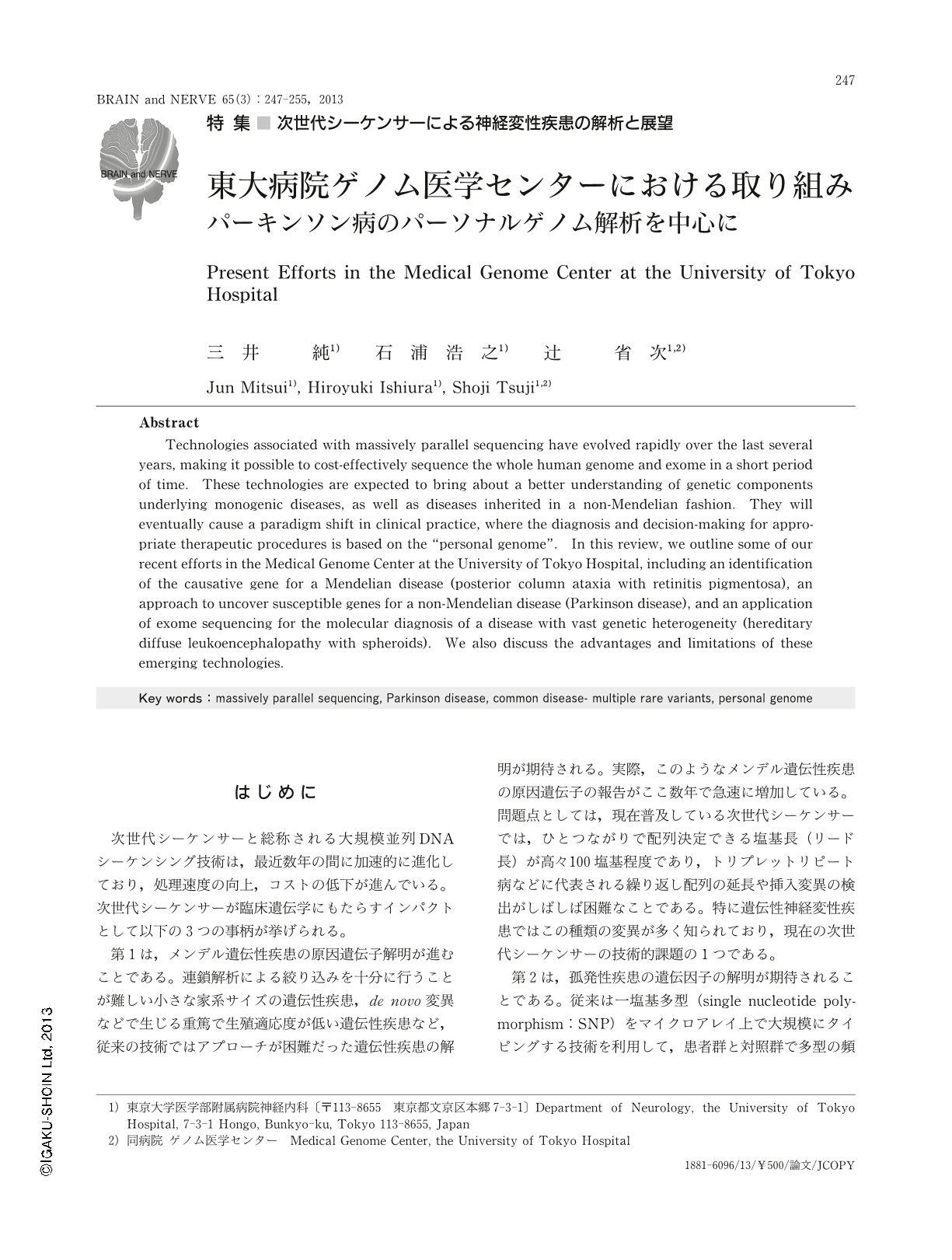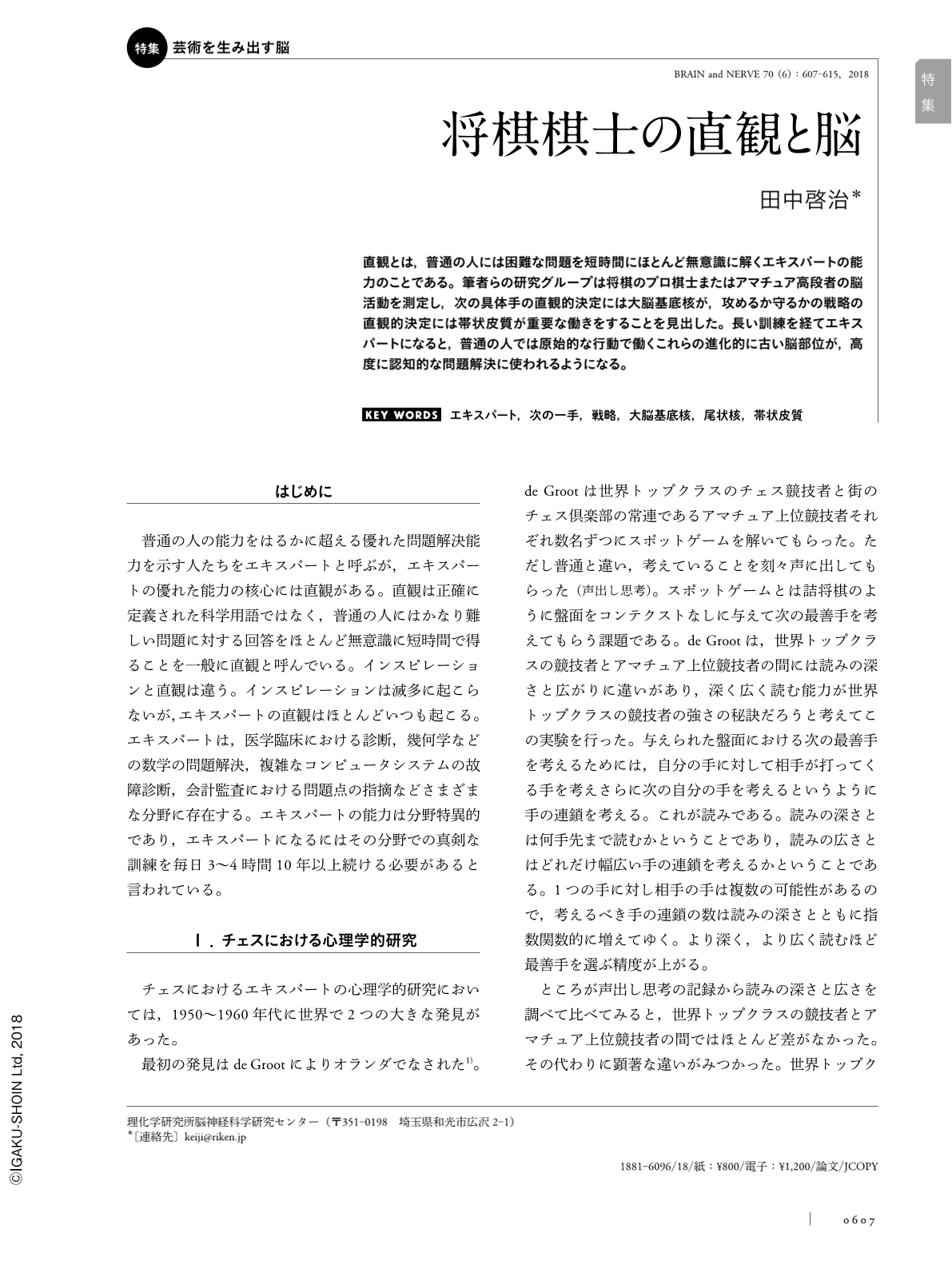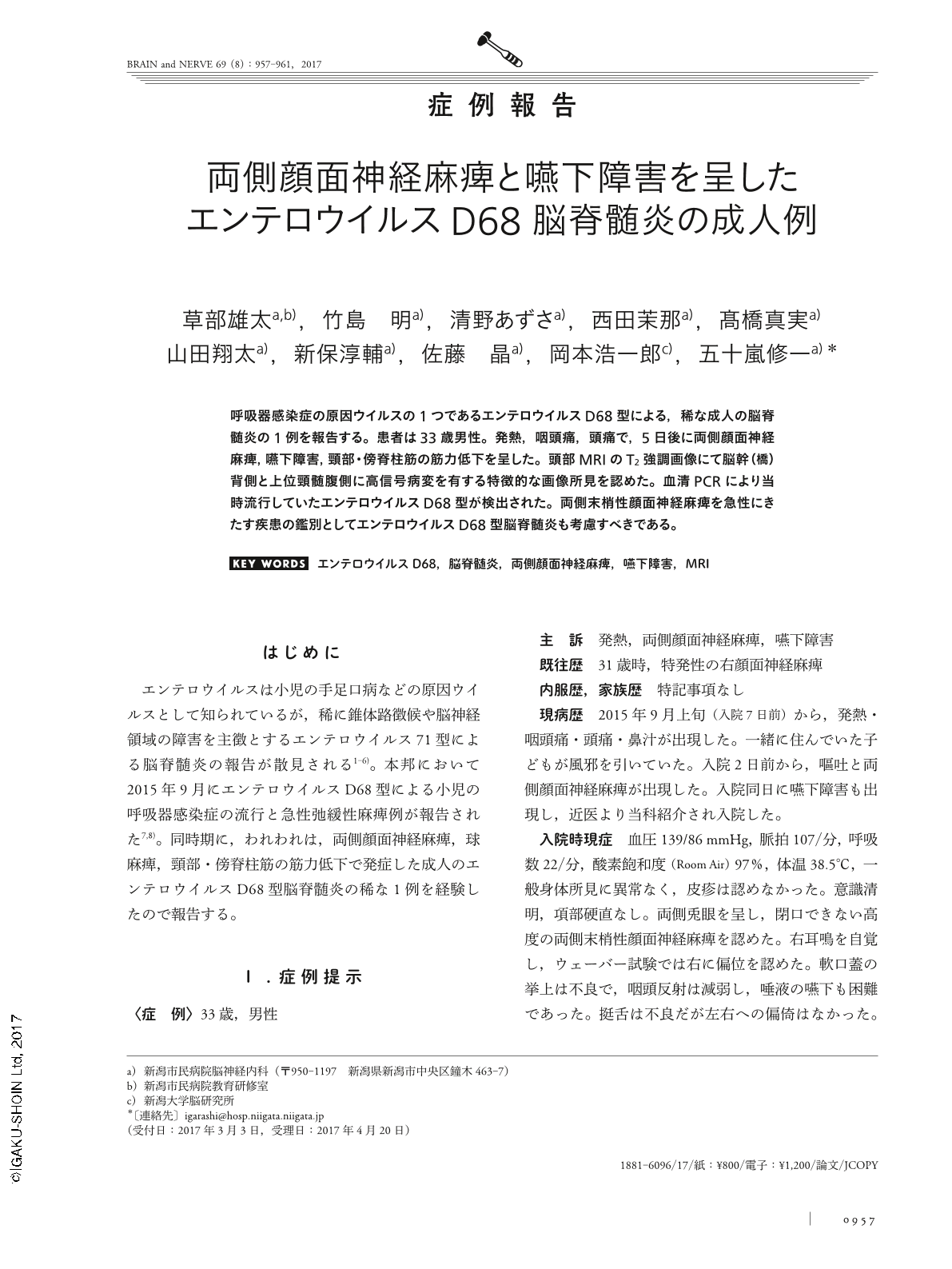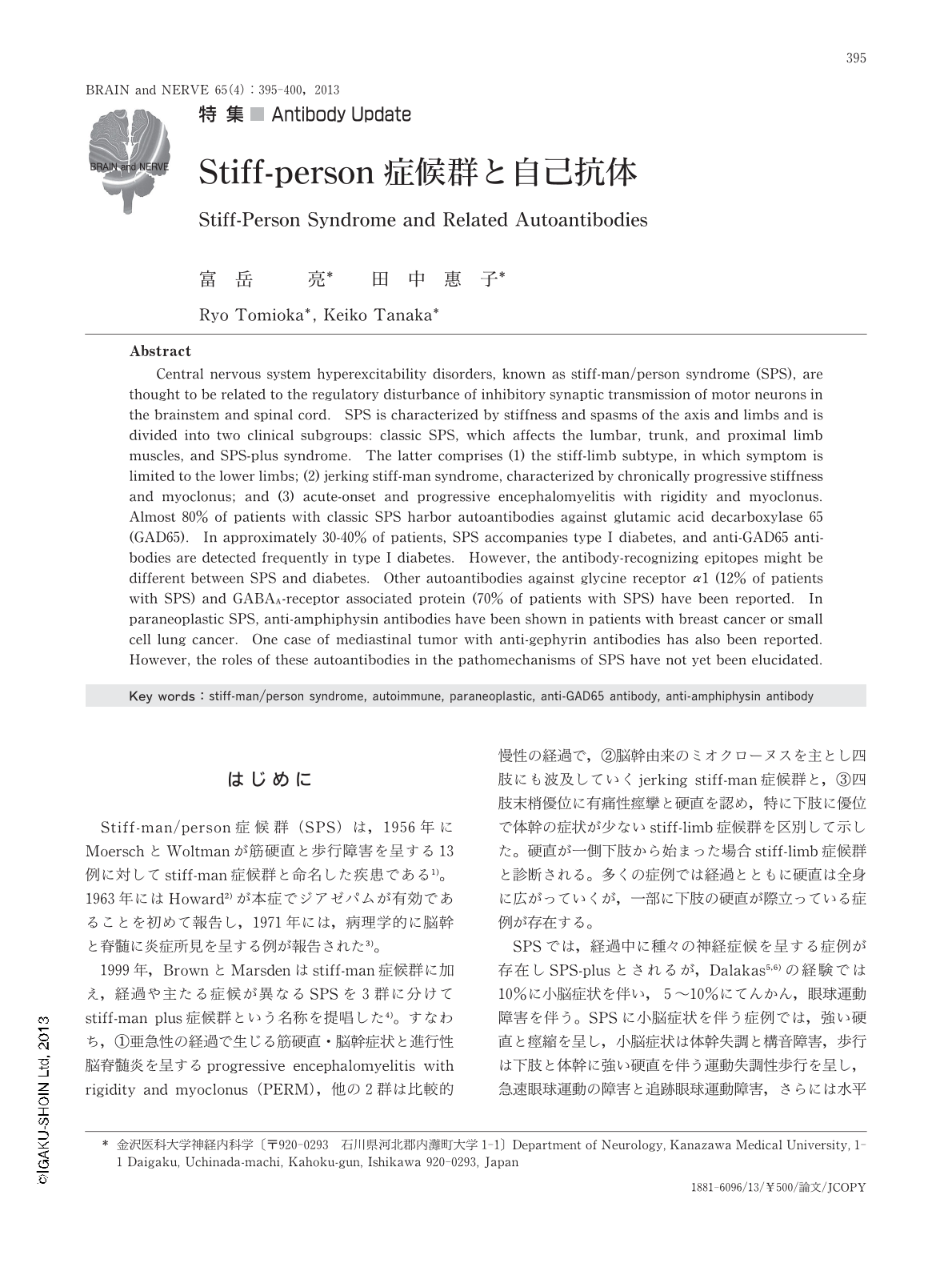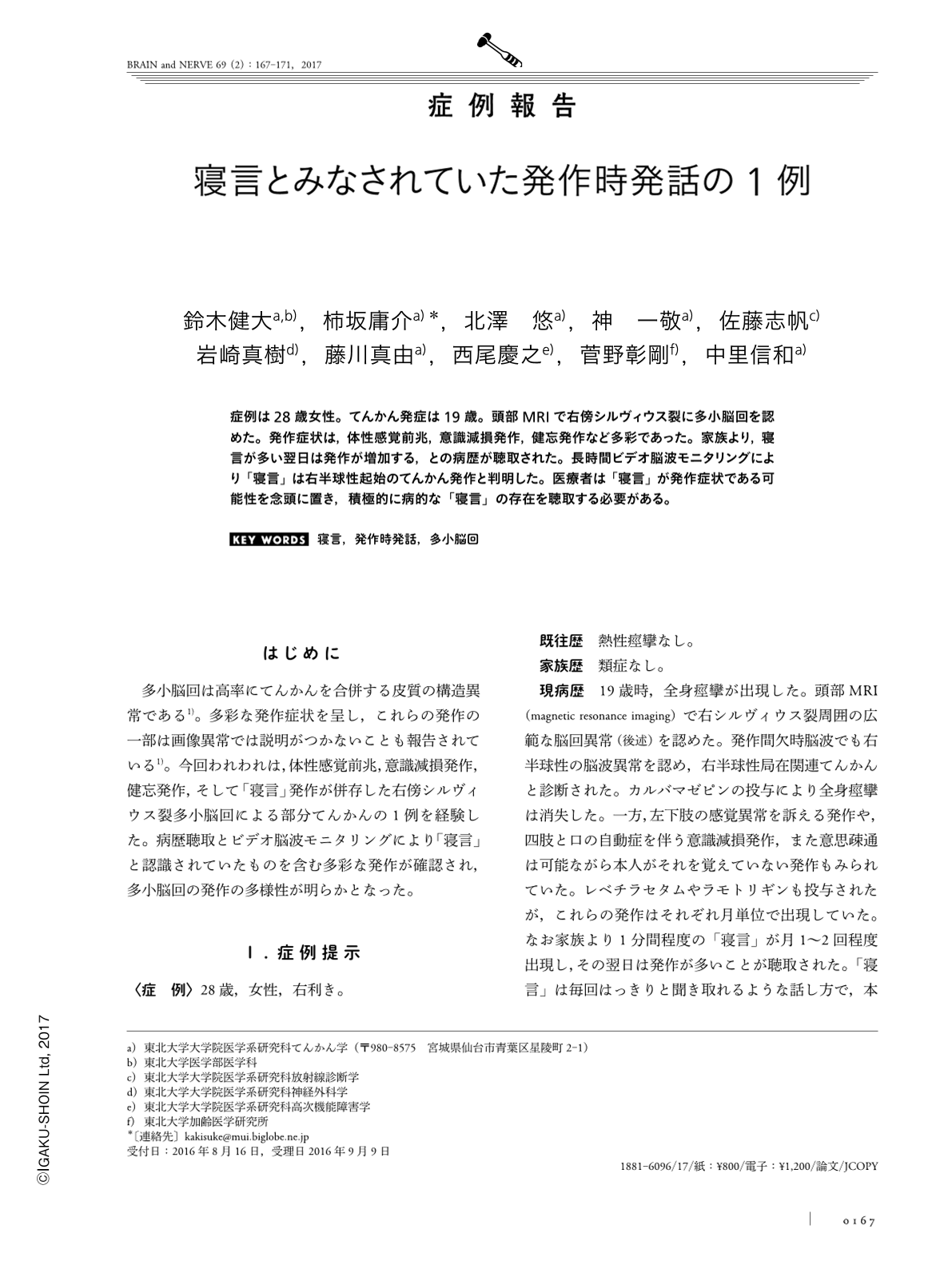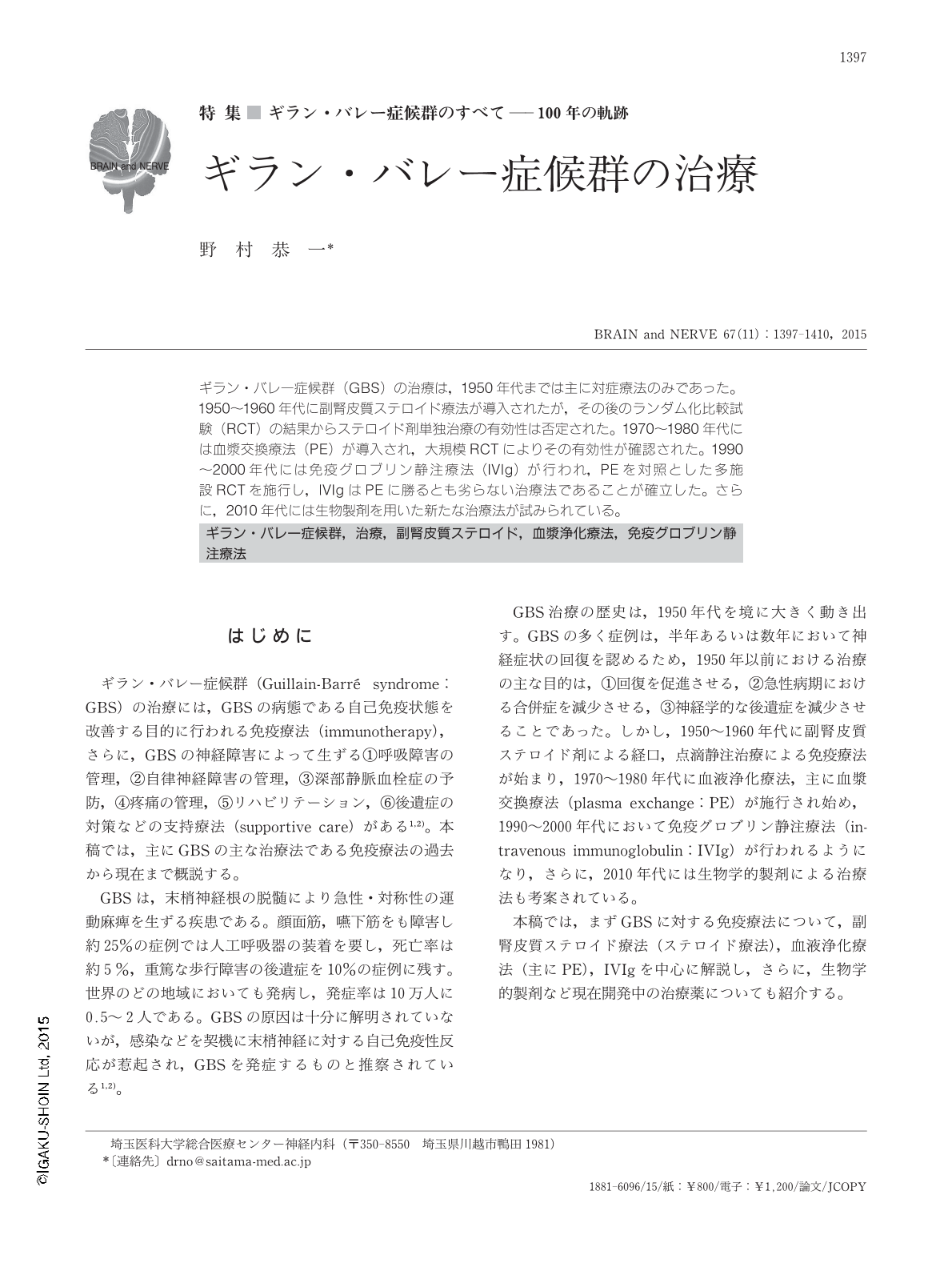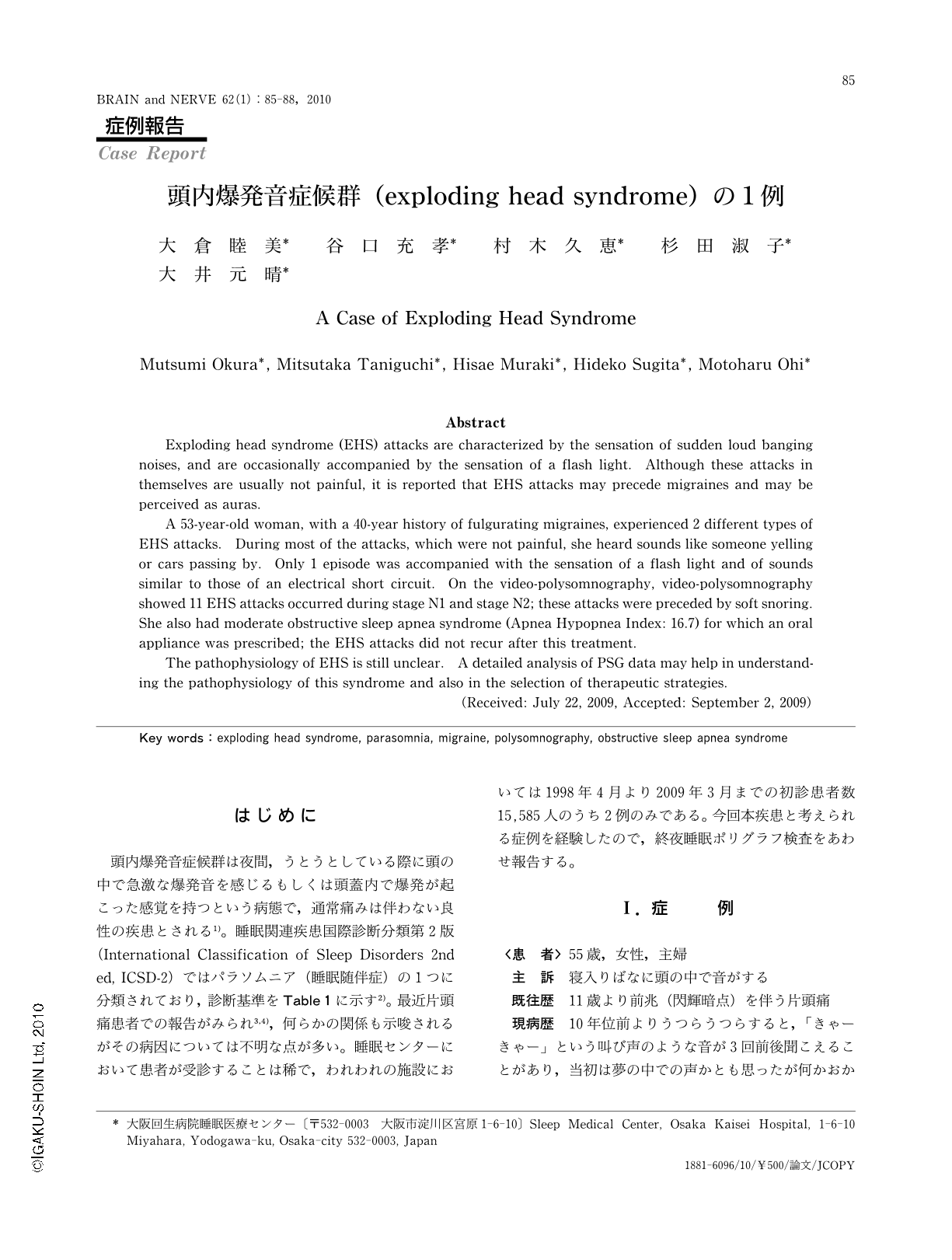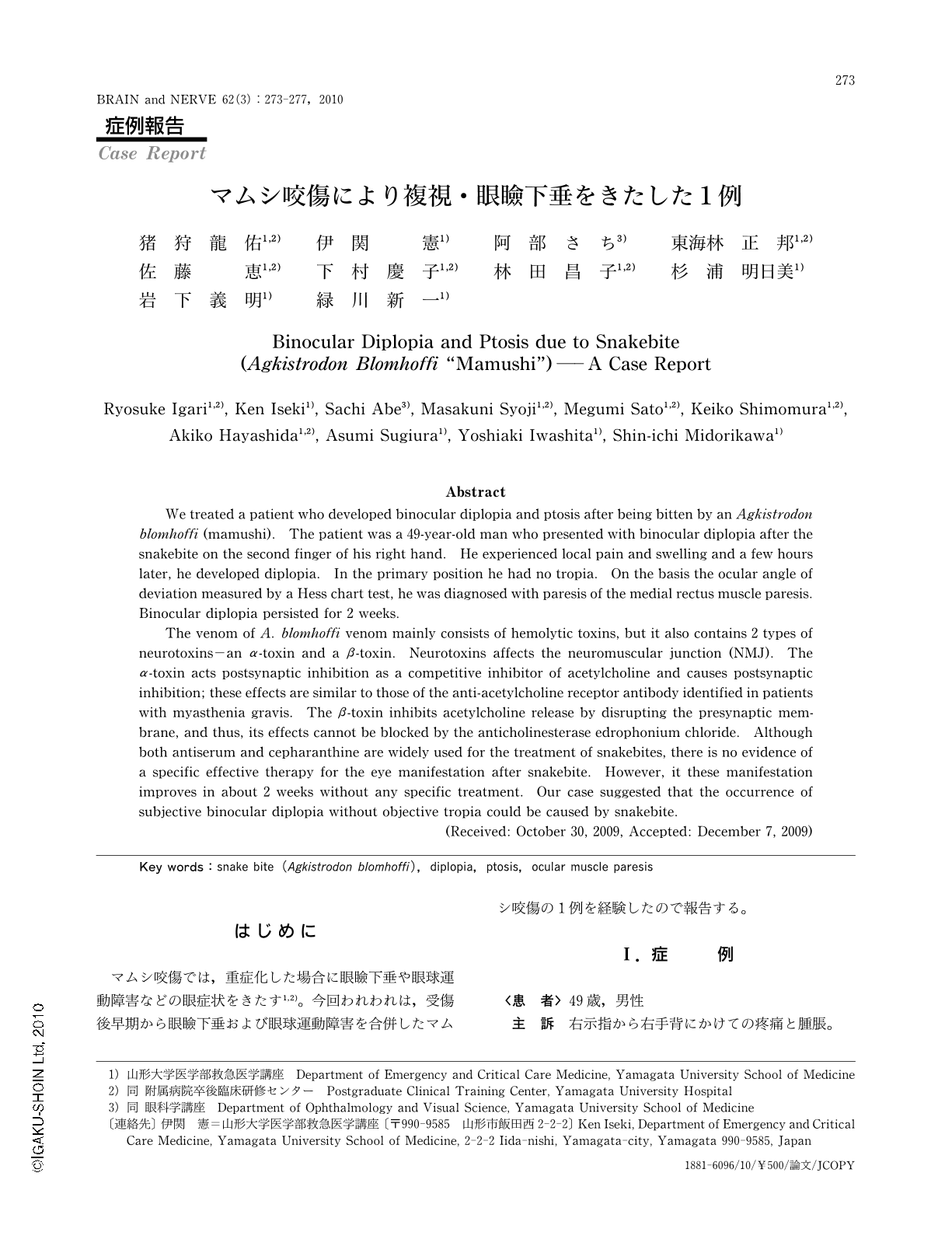はじめに 次世代シーケンサーと総称される大規模並列DNAシーケンシング技術は,最近数年の間に加速的に進化しており,処理速度の向上,コストの低下が進んでいる。次世代シーケンサーが臨床遺伝学にもたらすインパクトとして以下の3つの事柄が挙げられる。 第1は,メンデル遺伝性疾患の原因遺伝子解明が進むことである。連鎖解析による絞り込みを十分に行うことが難しい小さな家系サイズの遺伝性疾患,de novo変異などで生じる重篤で生殖適応度が低い遺伝性疾患など,従来の技術ではアプローチが困難だった遺伝性疾患の解明が期待される。実際,このようなメンデル遺伝性疾患の原因遺伝子の報告がここ数年で急速に増加している。問題点としては,現在普及している次世代シーケンサーでは,ひとつながりで配列決定できる塩基長(リード長)が高々100塩基程度であり,トリプレットリピート病などに代表される繰り返し配列の延長や挿入変異の検出がしばしば困難なことである。特に遺伝性神経変性疾患ではこの種類の変異が多く知られており,現在の次世代シーケンサーの技術的課題の1つである。 第2は,孤発性疾患の遺伝因子の解明が期待されることである。従来は一塩基多型(single nucleotide polymorphism:SNP)をマイクロアレイ上で大規模にタイピングする技術を利用して,患者群と対照群で多型の頻度を比較することで疾患と関連する感受性遺伝子探索が行われてきた。候補となる遺伝子・領域だけではなく,全ゲノム上の多型を広範囲に探索できることから,このアプローチは全ゲノム関連解析(genome-wide association study:GWAS)と呼ばれ,多くの疾患で検討が行われた。新たな発見も多かったが,孤発性疾患の遺伝因子の大部分が解明できるのではないかという期待には届かず,まだ解明されていない遺伝因子(missing heritability)が残されている1)。 多型マーカーと連鎖不平衡にある疾患感受性アレルを関連解析で検出する手法は,比較的少数の創始者に由来する疾患感受性アレルが,患者群に広く分布するという構造を持つ集団(common disease-common variants仮説)に対しては強い検出力を示すが,多数の独立した疾患感受性アレルが個々には稀に患者群に分布するという集団の遺伝的構造(common disease-multiple rare variants仮説)に対しては検出が困難になる。また,多型タイピングでは検出できないコピー数変異などの構造変異が寄与している可能性もある。今後,孤発性疾患における遺伝因子の解明を進めていくためには,パーソナルゲノム解析に基づく網羅的な変異の同定が大きな手掛かりになるであろう。 第3に,臨床における遺伝子診断の汎用化が挙げられる。神経内科領域の臨床では遺伝性疾患の占める割合が相対的に高く,需要も高いことから普及が期待される。特に原因遺伝子が多様な表現型・疾患群の遺伝子診断において高い効果を発揮するであろう。問題点としては,上述のように遺伝性神経筋疾患にみられる繰り返し配列の延長(優性遺伝性脊髄小脳変性症の多く,歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症,ハンチントン病,球脊髄性筋萎縮症,筋強直性ジストロフィー,フリードライヒ運動失調症,9p21に連鎖する筋萎縮性側索硬化症・前頭側頭型認知症,眼咽頭筋ジストロフィーなど)の検出は短いリード長では困難であり,フラグメント解析やサザン・ブロッティング解析を併用する必要がある。また,現状ではコスト・パフォーマンスの点からエクソーム解析が選択されることが多いと考えられるが,コピー数変異(遺伝性神経疾患ではAPP,SNCA,PMP22,MPZなどのコピー数変異による遺伝性疾患が報告されている)や大きな欠失・重複変異(デュシェンヌ・ベッカー型筋ジストロフィーにおけるDMDや常染色体劣性遺伝若年性パーキンソニズムにおけるPARK2の欠失・重複変異など)において,エクソーム解析では検出力が十分でない可能性があり適応に注意が必要である。 本稿では,以上3点について概説し,いくつかの具体例を挙げる。最後に2011年度に東京大学医学部附属病院の新たな組織として発足したゲノム医学センターの紹介と今後の展望を述べる。
2 0 0 0 将棋棋士の直観と脳
- 著者
- 草部 雄太 竹島 明 清野 あずさ 西田 茉那 髙橋 真実 山田 翔太 新保 淳輔 佐藤 晶 岡本 浩一郎 五十嵐 修一
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- BRAIN and NERVE-神経研究の進歩 (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.8, pp.957-961, 2017-08-01
呼吸器感染症の原因ウイルスの1つであるエンテロウイルスD68型による,稀な成人の脳脊髄炎の1例を報告する。患者は33歳男性。発熱,咽頭痛,頭痛で,5日後に両側顔面神経麻痺,嚥下障害,頸部・傍脊柱筋の筋力低下を呈した。頭部MRIのT2強調画像にて脳幹(橋)背側と上位頸髄腹側に高信号病変を有する特徴的な画像所見を認めた。血清PCRにより当時流行していたエンテロウイルスD68型が検出された。両側末梢性顔面神経麻痺を急性にきたす疾患の鑑別としてエンテロウイルスD68型脳脊髄炎も考慮すべきである。
2 0 0 0 Stiff-person症候群と自己抗体
- 著者
- 富岳 亮 田中 惠子
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- BRAIN and NERVE-神経研究の進歩 (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.395-400, 2013-04-01
はじめに Stiff-man/person症候群(SPS)は,1956年にMoerschとWoltmanが筋硬直と歩行障害を呈する13例に対してstiff-man症候群と命名した疾患である1)。1963年にはHoward2)が本症でジアゼパムが有効であることを初めて報告し,1971年には,病理学的に脳幹と脊髄に炎症所見を呈する例が報告された3)。 1999年,BrownとMarsdenはstiff-man症候群に加え,経過や主たる症候が異なるSPSを3群に分けてstiff-man plus症候群という名称を提唱した4)。すなわち,①亜急性の経過で生じる筋硬直・脳幹症状と進行性脳脊髄炎を呈するprogressive encephalomyelitis with rigidity and myoclonus(PERM),他の2群は比較的慢性の経過で,②脳幹由来のミオクローヌスを主とし四肢にも波及していくjerking stiff-man症候群と,③四肢末梢優位に有痛性痙攣と硬直を認め,特に下肢に優位で体幹の症状が少ないstiff-limb症候群を区別して示した。硬直が一側下肢から始まった場合stiff-limb症候群と診断される。多くの症例では経過とともに硬直は全身に広がっていくが,一部に下肢の硬直が際立っている症例が存在する。 SPSでは,経過中に種々の神経症候を呈する症例が存在しSPS-plusとされるが,Dalakas5,6)の経験では10%に小脳症状を伴い,5~10%にてんかん,眼球運動障害を伴う。SPSに小脳症状を伴う症例では,強い硬直と痙縮を呈し,小脳症状は体幹失調と構音障害,歩行は下肢と体幹に強い硬直を伴う運動失調性歩行を呈し,急速眼球運動の障害と追跡眼球運動障害,さらには水平注視時の眼振を認めた。以上のように,SPSは古典的なstiff-man症候群に加え,stiff-man plus症候群,さらに傍腫瘍症候群としてのSPSが加わり徐々に本症候群の概念が確立されていった。 本症では神経組織に炎症所見を生じる例があることから,ステロイドホルモン投与7),血漿交換療法が試行され8),奏効する例が報告されたことより,自己免疫学的機序の可能性について検討が加えられた。Solimena, De Camilliら9,10)はSPSの約60%にグルタミン酸脱炭酸酵素(glutamate decarboxylase:GAD)に対する自己抗体の存在を見出した。また,悪性腫瘍を背景とし,SPSを呈する傍腫瘍性神経症候群で抗アンフィフィシン(amphiphysin)I抗体が検出された例が報告され11),縦隔腫瘍にSPSを合併した1例でゲフィリン(gephyrin)抗体が見出されたとの報告もある12)。
- 著者
- 松井 尚子 田中 惠子 梶 龍兒
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- Brain and nerve (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.357-362, 2018-04
2 0 0 0 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の診断と治療
- 著者
- 倉恒 弘彦
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- BRAIN and NERVE-神経研究の進歩 (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.11-18, 2018-01-01
本稿では,プライマリ・ケアを担っている医療機関において利用されることを目的に厚生労働科学研究班より2016年3月に改訂された筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)臨床診断基準を紹介するとともに,ME/CFS診療が行われている代表的な医療機関において現在実施されている治療法やその予後についても解説する。
2 0 0 0 抗血小板療法 : 再発予防update (特集 あしたの脳梗塞)
- 著者
- 内山 真一郎
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- Brain and nerve : 神経研究の進歩 (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.7, pp.771-782, 2013-07
- 著者
- 岩波 久威 小鷹 昌明 平田 幸一
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- Brain and nerve (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.169-171, 2007-02
2 0 0 0 このヒトに聞く 脳神経画像診断の歴史を振り返る
- 著者
- 佐野 圭司 岩田 誠
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- Brain and nerve (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.6, pp.616-625, 2011-06
- 著者
- 大倉 睦美 谷口 充孝 村木 久恵
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- Brain and nerve (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.85-88, 2010-01
1 0 0 0 1913―茂吉・プルースト・ヤスパース
はじめに 河村 いまから100年前の1913年は,歌人で精神科医でもある斎藤茂吉(1882-1953)が最初の歌集『赤光』を出版した年です。同時に,フランスではマルセル・プルースト(Marcel Proust;1871-1922)が『失われた時を求めて』を出版しています。『失われた~』は,匂いが記憶を呼び覚ますという神経学的な背景を持った文学作品です。このように1913年は文学が,神経学または精神医学とかなり接近していた時代だったともいえると思います。 また,同じ年に,カール・ヤスパース(Karl Theodor Jaspers;1883-1969)が『精神病理学原論』を書いています。この本は,岩田先生から教えていただいたのですが,のちの精神医学,神経学に大変な影響を与えた本です。本対談はこの辺りをテーマにすれば,岩田先生から楽しいお話が伺えるのではないかと思い,企画しました。どうぞ,よろしくお願いいたします。
- 著者
- 山村 隆 小野 紘彦 佐藤 和貴郎
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- Brain and nerve (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.35-40, 2018-01
1 0 0 0 顔認知の脳内メカニズム―上側頭溝の機能を中心として
はじめに 本総説では顔認知に関わる脳領域を,機能的磁気共鳴画像(functional magnetic resonance imaging:fMRI)による脳賦活検査で調べた研究について述べる。fMRIは脳血流の変化をblood-oxygen-level-dependent(BOLD)コントラストとして計測し画像化する手法で,1990年にOgawaら1)が世界で最初に報告した技術である。この手法を用いた脳賦活検査により,脳機能を非侵襲的かつボクセル単位で計測することが可能になった。また,計測された脳画像を扱う解析ソフトウェアの技術的進歩も目覚ましいものがある。脳賦活検査の基本的手法は,認知的差分法(cognitive subtraction)といわれるものである。これはある精神状態とほかの精神状態でそれぞれ脳画像を取った場合,2枚の差分画像には2つの精神状態の差異が反映されているという理論である。この方法は神経細胞の応答を直接測定しているものではないが,非侵襲性という点において現在の神経科学領域では欠かせない実験方法となっている2)。 顔認知に関わる脳機能は,顔自体に対する反応,表情の認識に関わる反応,顔の動きに対する反応,顔の記憶や有名人顔に対する反応など広範囲にわたっている。最近では顔の印象や信頼できるかどうかなど,顔認知の社会的側面への興味も広がっている。研究対象となる脳領域も後頭葉,側頭葉,前頭葉,辺縁系などにわたっている。したがって,脳全体の活動を比較的自由に計測することができるfMRIは,このような研究目的には最適な手法といえる。本稿では顔に対する脳内の反応を,主に側頭葉外側面に位置する上側頭溝(superior temporal sulcus:STS)の活動として計測した研究について代表的なものを取り上げる。この領域は顔認知の中でも,視線の向きや表情の変化などに関係していることが知られている3)。またfMRIが普及する以前からサルの実験では,顔に対するSTS領域の神経応答が積極的に調べられていた4)。STSの働きを多面的に論じた総説では,この領域が運動知覚,言語処理,心の理論,聴覚視覚統合,顔認知のそれぞれに関係していると述べられている5)。STSを左右半球と前半・後半の4領域に分けて認知機能との関係を調べた結果では,左前半は言語処理に,左後半は顔認知と聴覚視覚統合に,右前半は言語処理に,右後半は顔認知と運動知覚にそれぞれ関係していた。 このようなSTSの多機能性は,STSと同時に活動が亢進する脳領域が広範囲にわたることと関連している5)。すなわち,STS後半部は同時に紡錘状回などの賦活を伴うことで顔認知処理を遂行し,一方MT/V5領域の活動を伴うことで運動知覚処理を遂行するということである。最近では心の理論に関わるミラー・ニューロン・システムへの情報入力が,STSを通じて行われていると考えられている6)。本総説ではSTSの機能を顔認知に限って論考し,STSの前部・後部による機能差についても検討する。本総説が医学,心理学,教育学など広い領域の読者において,顔認知研究に対する理解を深めることに役立てば幸いである。また本論文はメタ解析の手法を用いたものではなく,必ずしも該当するすべての研究報告を網羅してはいない。紡錘状回(fusiform face area:FFA)や扁桃体(amygdala)などの活動も顔認知には重要であるが本総説では触れないこととする。
1 0 0 0 寝言とみなされていた発作時発話の1例
- 著者
- 鈴木 健大 柿坂 庸介 北澤 悠 神 一敬 佐藤 志帆 岩崎 真樹 藤川 真由 西尾 慶之 菅野 彰剛 中里 信和
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- pp.167-171, 2017-02-01
症例は28歳女性。てんかん発症は19歳。頭部MRIで右傍シルヴィウス裂に多小脳回を認めた。発作症状は,体性感覚前兆,意識減損発作,健忘発作など多彩であった。家族より,寝言が多い翌日は発作が増加する,との病歴が聴取された。長時間ビデオ脳波モニタリングにより「寝言」は右半球性起始のてんかん発作と判明した。医療者は「寝言」が発作症状である可能性を念頭に置き,積極的に病的な「寝言」の存在を聴取する必要がある。
「こんな本があったら」と,かねて願っていた本が出版された。勘違い,手落ち,不手際,不覚,思い込み,などさまざまな誤りは,神ならぬ人にとって避けて通れない性である。しかし,医療には,誤りは許されず,細心の注意と配慮が求められる。 誤り(誤診)の原因は,患者側にある場合と診察者側にある場合とがある。本書の序論に相当する「誤診(診断エラー)の原因と対策」の章では,原因を①無過失エラー,②システム関連エラー,③認知エラーの3種に類型化し,さらにそれらを細分した分類を引用し,本書で扱われている各症例の誤診原因をこの分類と照合させている。本序論は必読の価値がある。
2015(平成27)年11月末に開催された第33回日本神経治療学会総会(会長:祖父江元・名古屋大学教授)において,「症例から学ぶ」というユニークなセッション(座長:鈴木正彦・東京慈恵会医科大学准教授)に参加した。「神経内科診療のピットフォール:誤診症例から学ぶ」という副題がついており,春日井市総合保健医療センターの平山幹生先生(以下,著者)が演者であった。 臨床医学のみならず基礎医学にも通じた該博な知識の持ち主でいらっしゃる著者が,どのような症例提示をされるか,興味津々であったが,予想に違わず,その内容は大変示唆に富む教育的なものであった。自ら経験された診断エラーや診断遅延の症例を紹介し,その要因を分析し,対策についても述べられた。講演の最後に紹介されたのが,この『見逃し症例から学ぶ 神経症状の“診”極めかた』であり,講演で提示された症例も含めた,教訓に富む症例の集大成らしい,ということで,早速入手し,じっくりと味わうように通読した。
1 0 0 0 自閉症サヴァンと獲得性サヴァンの神経基盤
はじめに 深刻な精神神経障害によるハンディキャップを持ちながらも,一方で突出した「才能の小島(island of talent)」を持つ患者を,「サヴァン症候群(savant syndrome)」1,2)と呼ぶ。サヴァン症候群はごく稀にしかみられないものの,その存在は古くから知られていた。1887年にDownが記述した,先天的な知能低下にもかかわらず類い稀な才能を併せ持った複数の症例は,サヴァン症候群に関する最初期の報告である。その際Downは,その逆説的な才能を強調して,idiot-savant(白痴の天才)と名付けた3)。彼らの才能は,音楽,絵画,彫刻,計算,記憶など多岐に及び,しかもすべての症例に重度の精神遅滞や認知障害が併存していた。また,映画「レインマン」に登場するレイモンド・バビットのモデルとなったキム・ピークは,脳梁欠損などの深刻な中枢神経系の異常が存在するにもかかわらず,過去に読んだ約9,000冊の書物の内容を正確に記憶しているという驚異的な能力を具えたサヴァンとして知られている4)。これまでに,サヴァン症候群の症例は数多く報告されているが,彼らの認知過程や神経基盤の解明に向けた研究が行われるようになったのは比較的最近のことである。サヴァン症候群に出現する驚異的な才能は,従来の高次脳機能における障害や欠陥という概念だけでは説明することができないものであり,彼らの認知過程と神経基盤の詳細を明らかにすることは,われわれの脳内の情報処理過程を解明するためにも大きな役割を占めるものと思われる4,5)。
1 0 0 0 ギラン・バレー症候群の治療
ギラン・バレー症候群(GBS)の治療は,1950年代までは主に対症療法のみであった。1950〜1960年代に副腎皮質ステロイド療法が導入されたが,その後のランダム化比較試験(RCT)の結果からステロイド剤単独治療の有効性は否定された。1970〜1980年代には血漿交換療法(PE)が導入され,大規模RCTによりその有効性が確認された。1990〜2000年代には免疫グロブリン静注療法(IVIg)が行われ,PEを対照とした多施設RCTを施行し,IVIgはPEに勝るとも劣らない治療法であることが確立した。さらに,2010年代には生物製剤を用いた新たな治療法が試みられている。
はじめに 頭内爆発音症候群は夜間,うとうとしている際に頭の中で急激な爆発音を感じるもしくは頭蓋内で爆発が起こった感覚を持つという病態で,通常痛みは伴わない良性の疾患とされる1)。睡眠関連疾患国際診断分類第2版(International Classification of Sleep Disorders 2nd ed, ICSD-2)ではパラソムニア(睡眠随伴症)の1つに分類されており,診断基準をTable1に示す2)。最近片頭痛患者での報告がみられ3,4),何らかの関係も示唆されるがその病因については不明な点が多い。睡眠センターにおいて患者が受診することは稀で,われわれの施設においては1998年4月より2009年3月までの初診患者数15,585人のうち2例のみである。今回本疾患と考えられる症例を経験したので,終夜睡眠ポリグラフ検査をあわせ報告する。