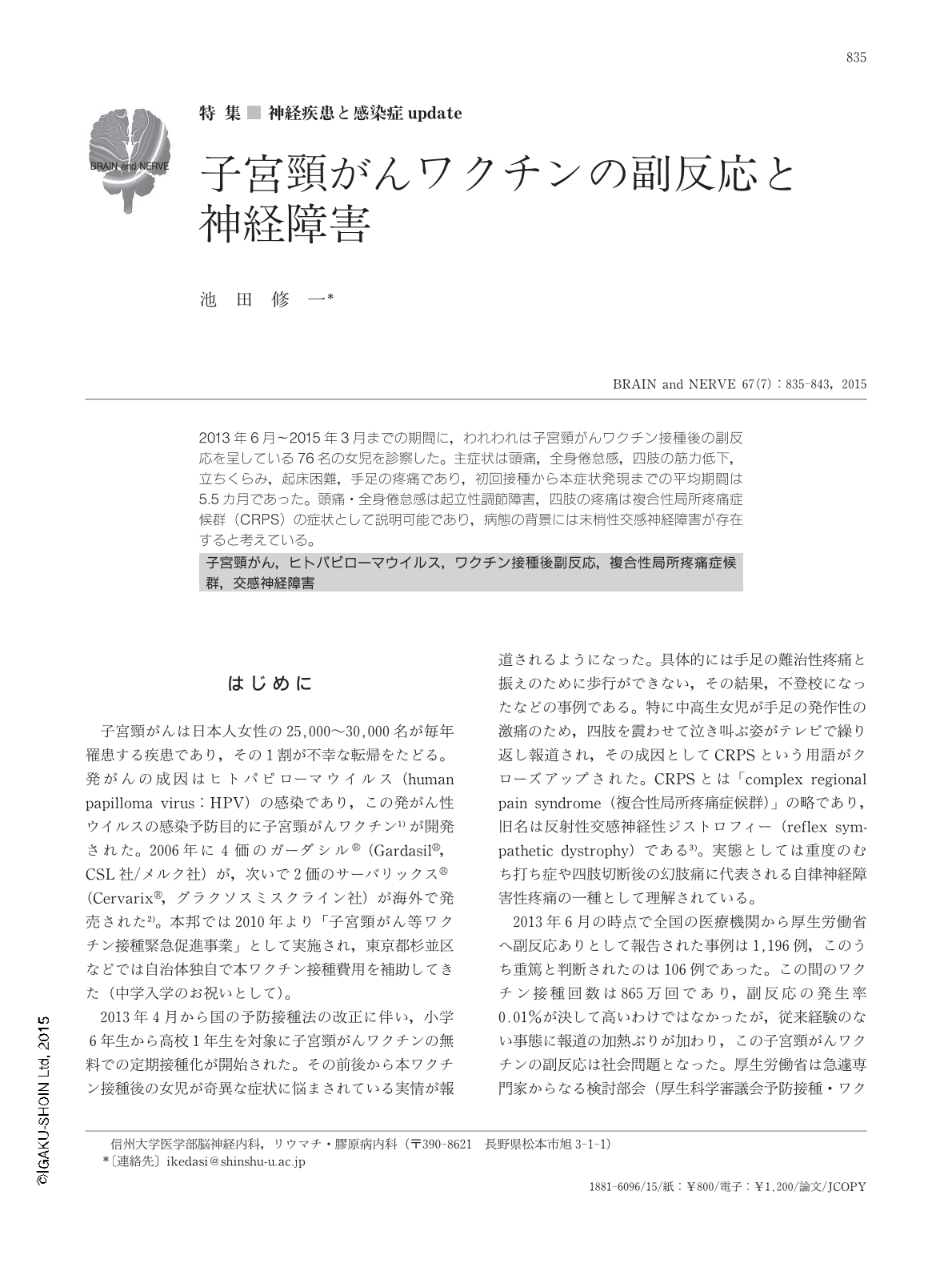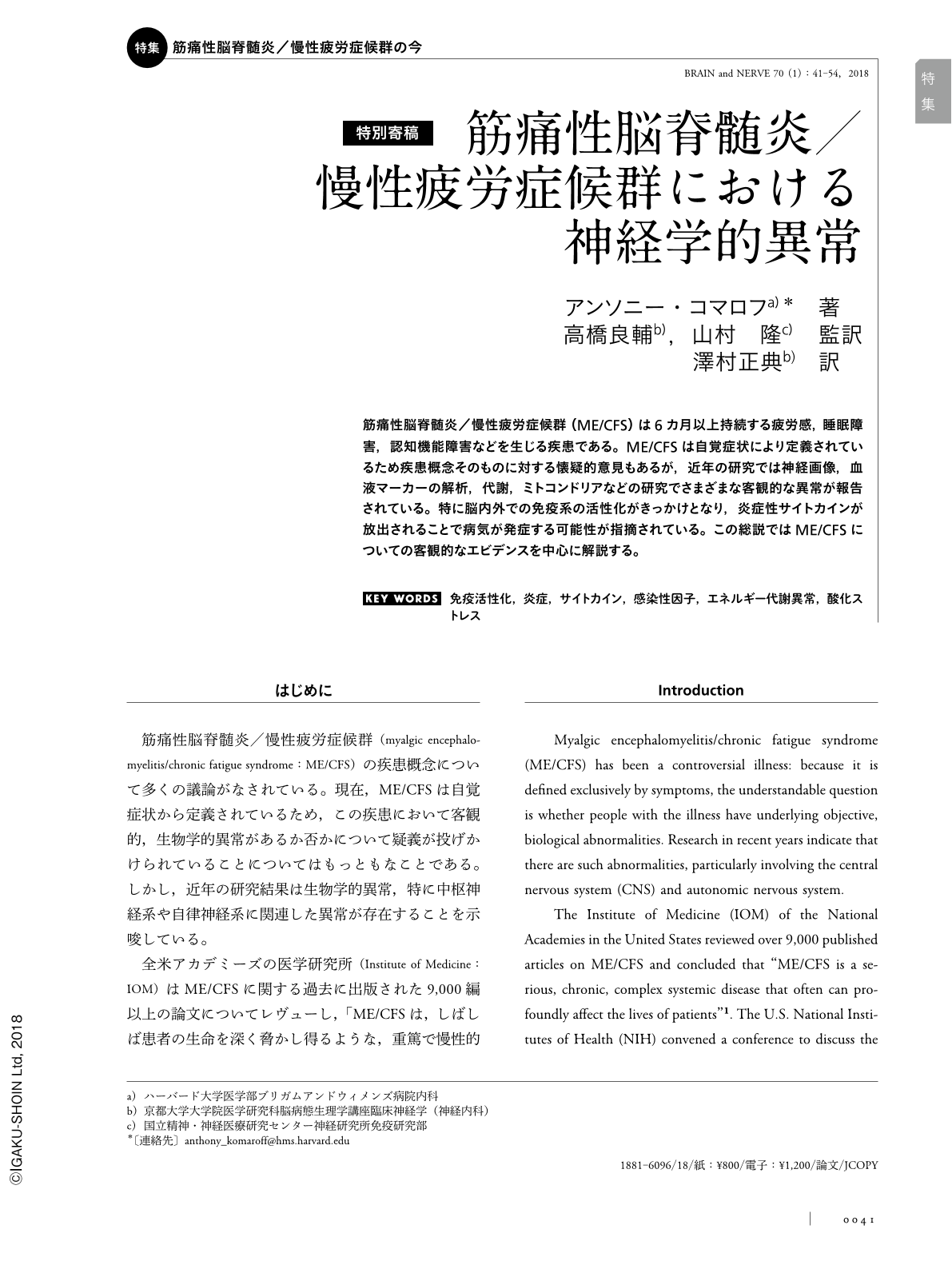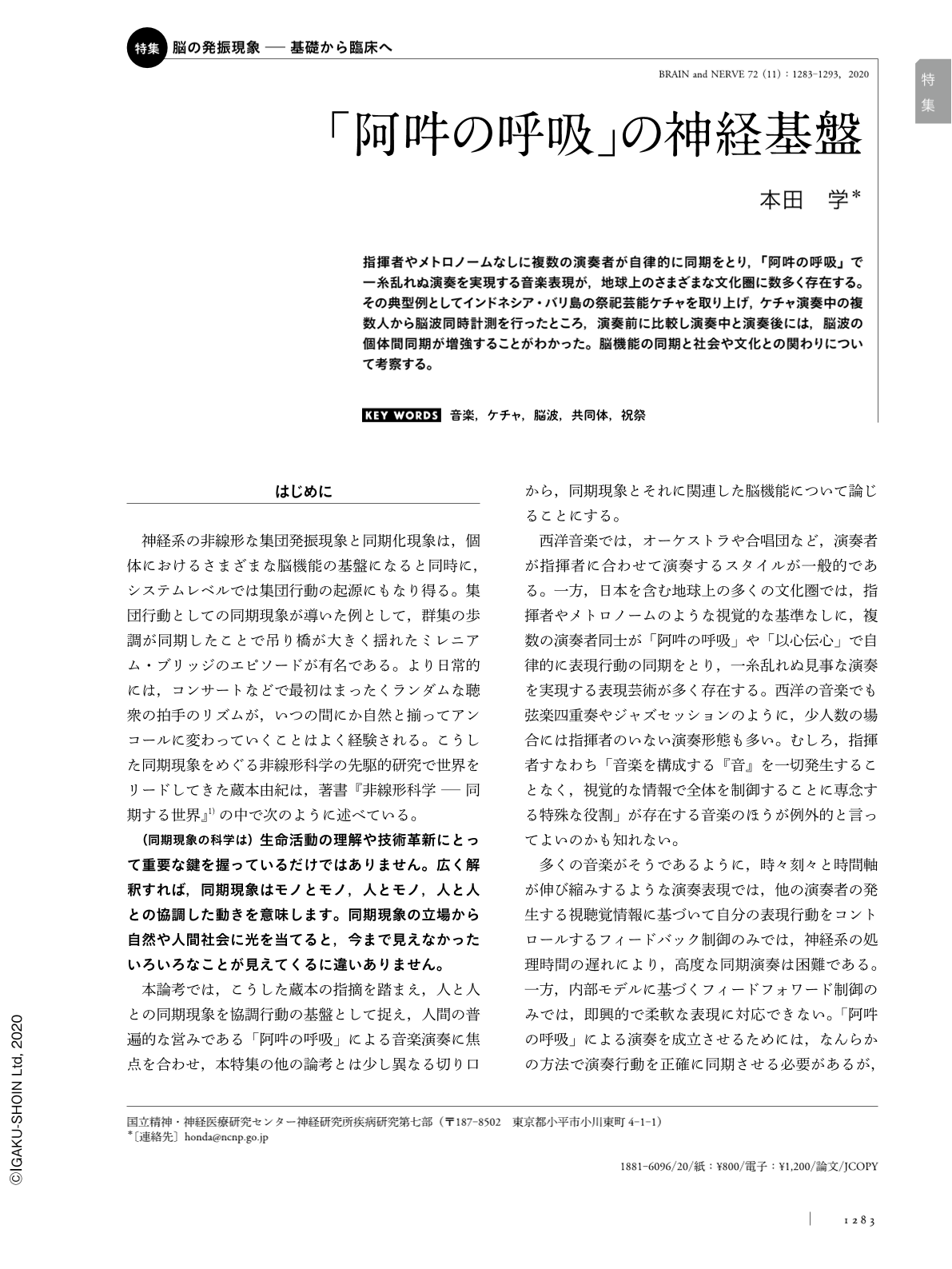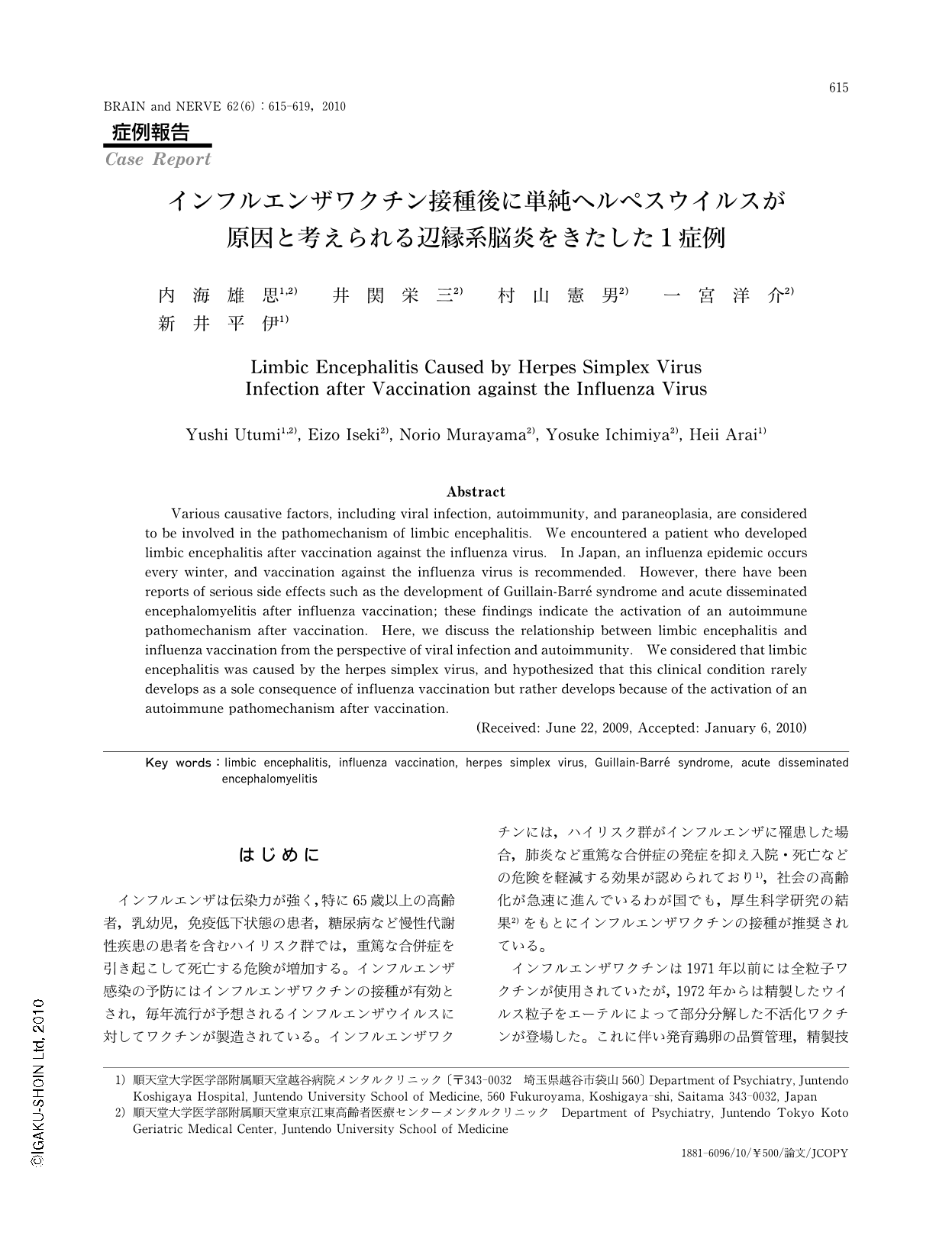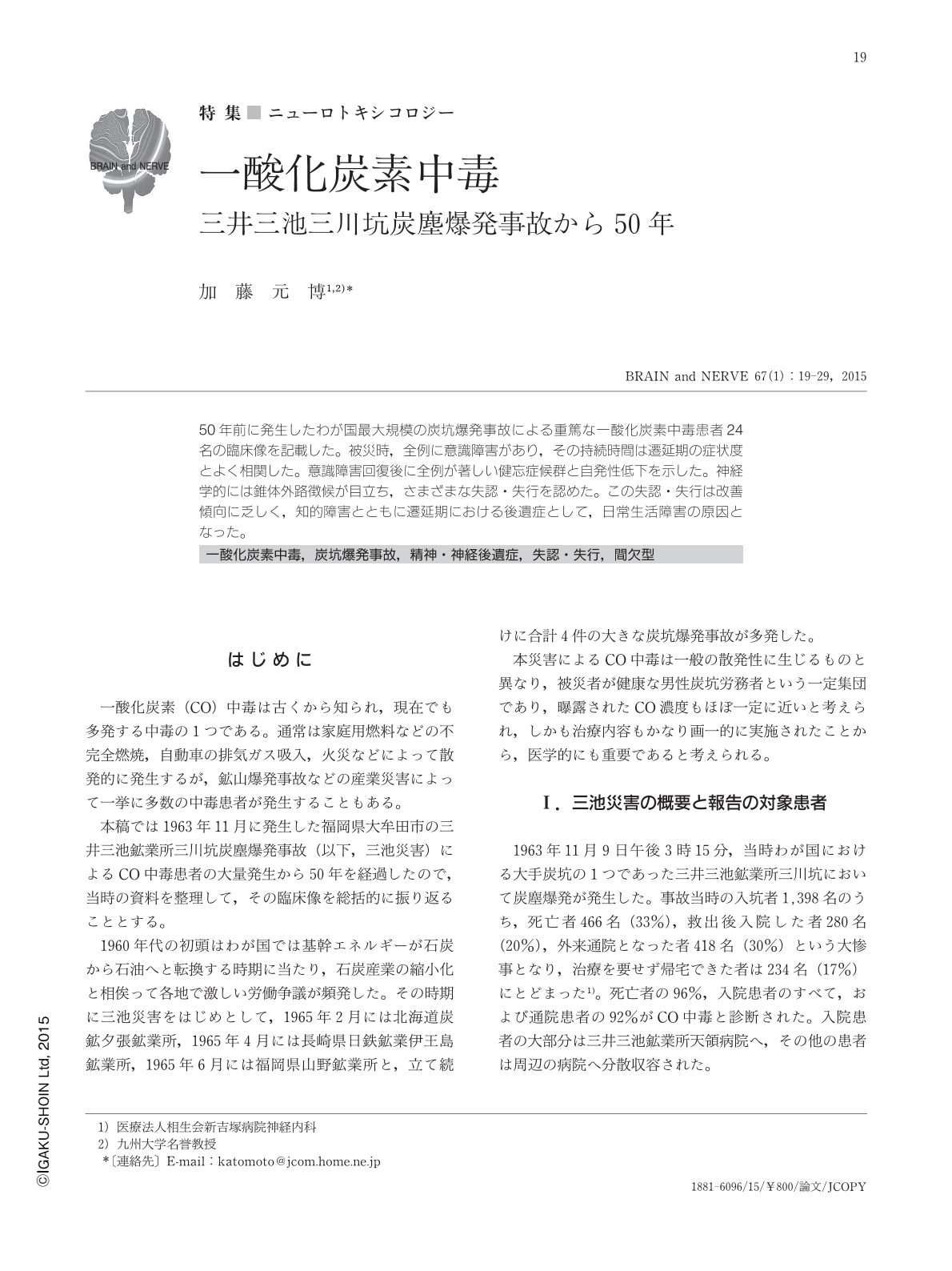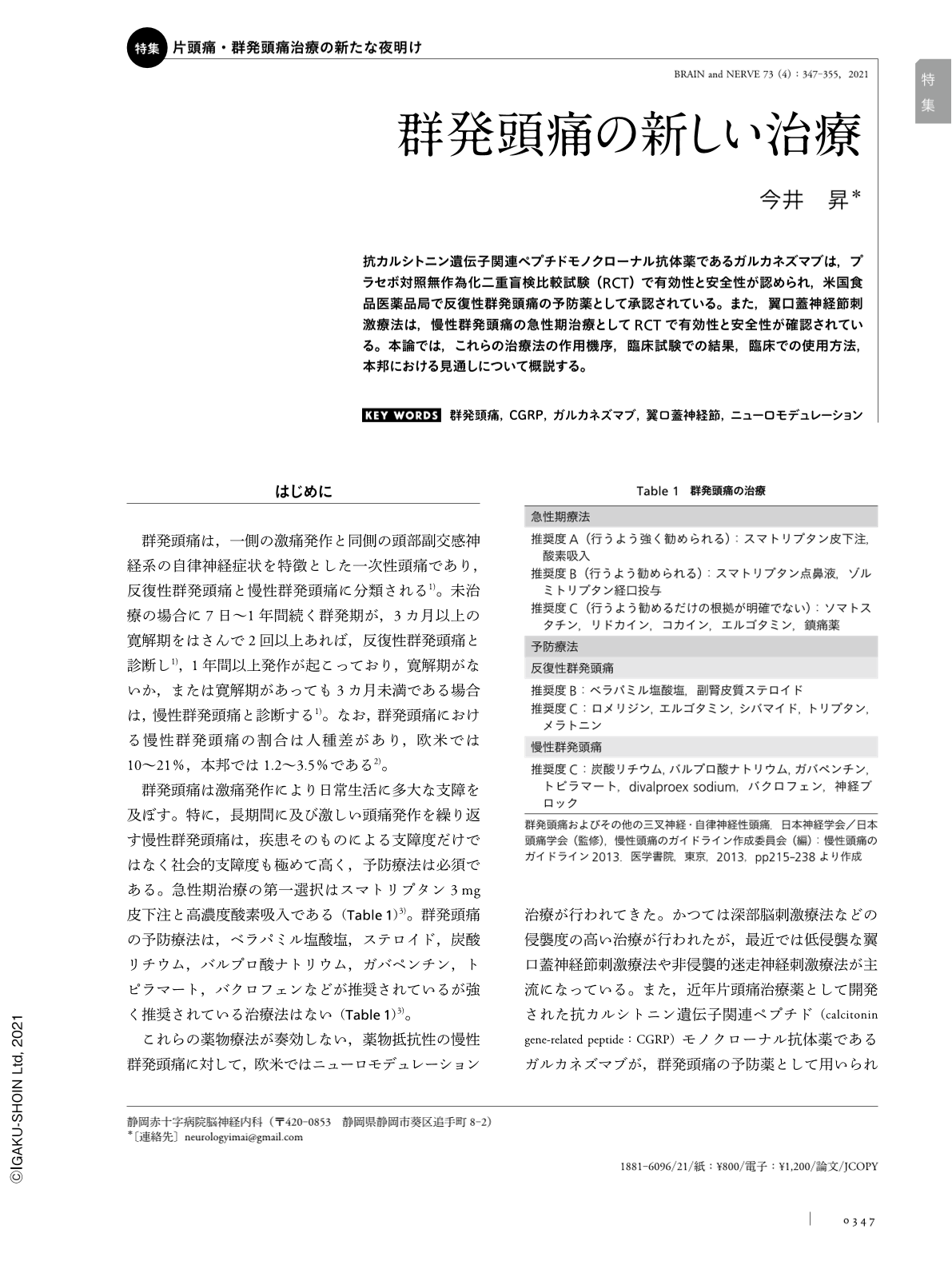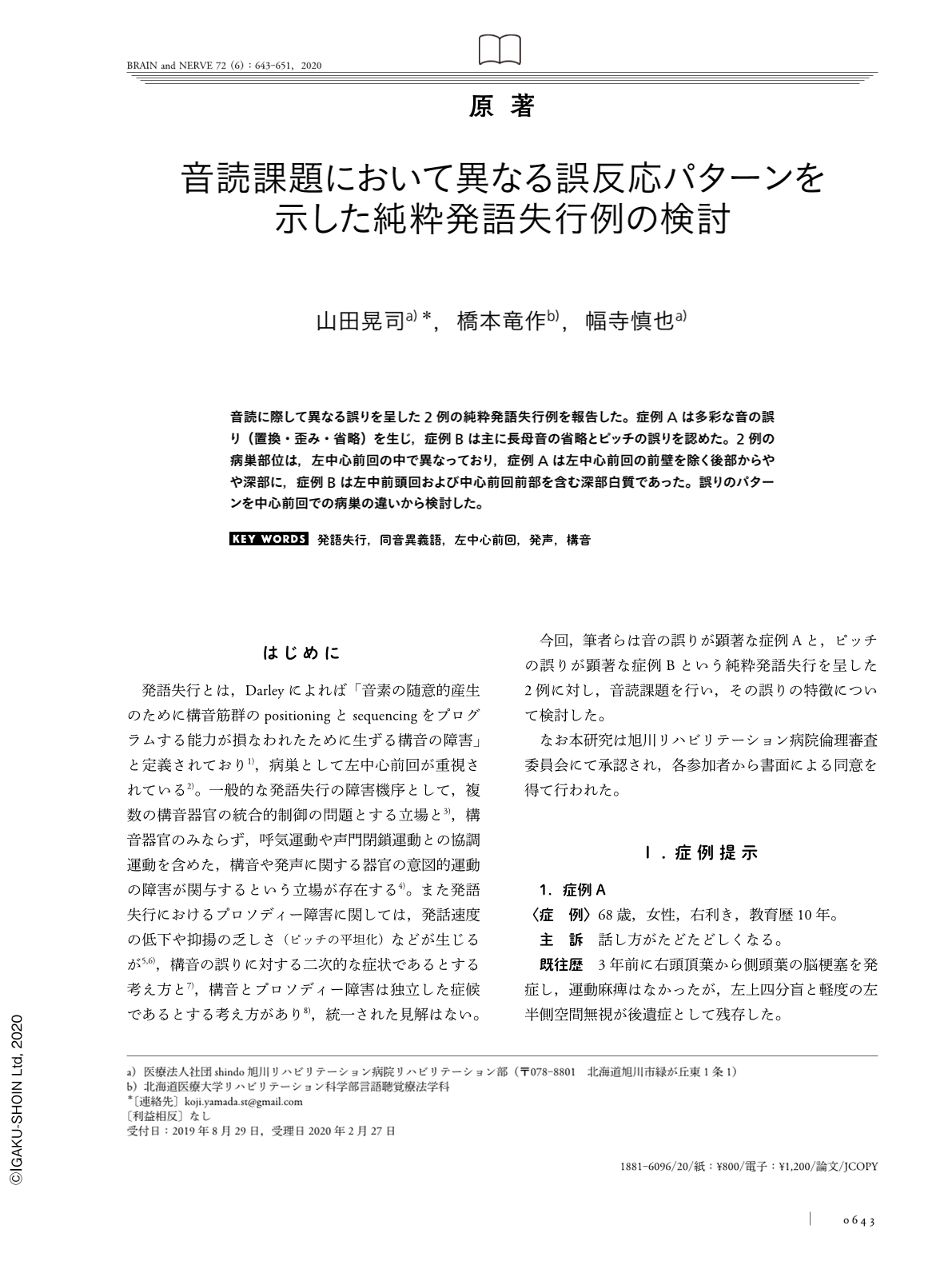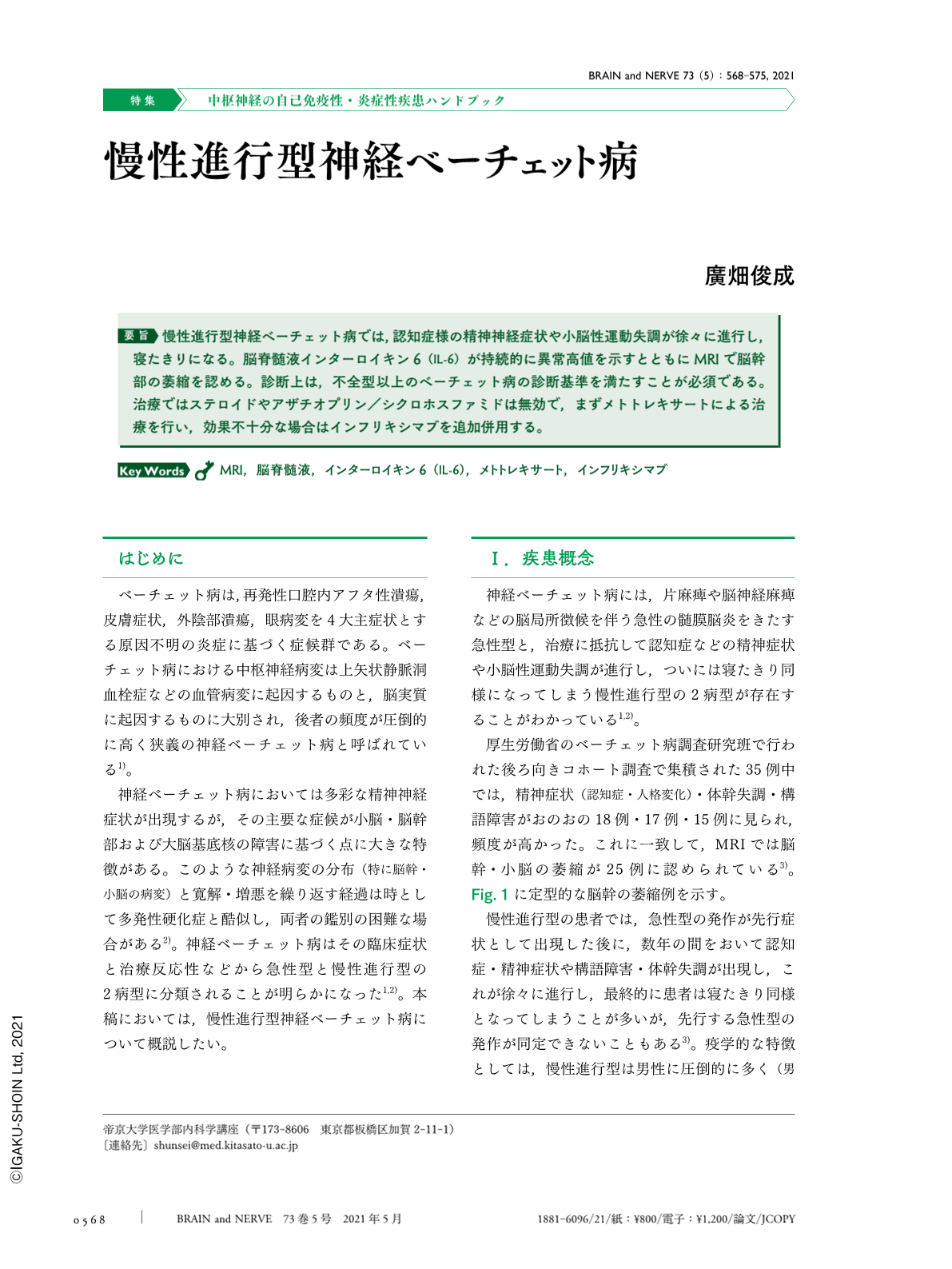46 0 0 0 子宮頸がんワクチンの副反応と神経障害
- 著者
- 池田 修一
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- BRAIN and NERVE-神経研究の進歩 (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.7, pp.835-843, 2015-07-01
2013年6月〜2015年3月までの期間に,われわれは子宮頸がんワクチン接種後の副反応を呈している76名の女児を診察した。主症状は頭痛,全身倦怠感,四肢の筋力低下,立ちくらみ,起床困難,手足の疼痛であり,初回接種から本症状発現までの平均期間は5.5カ月であった。頭痛・全身倦怠感は起立性調節障害,四肢の疼痛は複合性局所疼痛症候群(CRPS)の症状として説明可能であり,病態の背景には末梢性交感神経障害が存在すると考えている。
21 0 0 0 長期指圧マッサージにて発症した頭蓋内椎骨動脈解離による両側小脳梗塞
はじめに 脳梗塞の原因の1つとして脳動脈解離は重要であり,近年MRI画像の発達により診断される症例が増加している1)。スポーツや激しい咳,転落や自動車事故,ヨガ,トランポリン,アーチェリー,カイロプラクティスなどの外傷に伴う急激な頭部の後屈や回旋によって誘発される椎骨動脈解離は,頭蓋外に発生する場合が多い。一方,特発性の場合には頭蓋内が多い2)。 5年間指圧マッサージを受けていた症例において,指圧中に突然の頭痛とめまいで小脳梗塞を発症し,three-dimensional computed tomographic angiography(3D-CTA)の所見から頭蓋内椎骨動脈解離と診断した。軽微な圧迫においても,繰り返されることにより誘発される頭蓋内動脈解離の危険性を強調したいので報告する。
18 0 0 0 自己免疫性脳症のスペクトラムとびまん性脳障害の神経症候学
- 著者
- 牧 美充 髙嶋 博
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- BRAIN and NERVE-神経研究の進歩 (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.10, pp.1131-1141, 2017-10-01
多くの橋本脳症の患者がgive-way weaknessや解剖学的には説明しづらい異常感覚を呈していることをわれわれは見出した。それらは身体表現性障害(いわゆるヒステリー)で特徴的とされる身体症状に類似しており,脳梗塞のような局所的な障害で引き起こされる症状とは切り離されて考えられてきた。そのような神経症候が出現するためには,びまん性,多巣性に濃淡を持った微小病変を蓄積させることができる自己免疫性脳症のような病態を想定する必要がある。このような考え方で,われわれは「びまん性脳障害による神経症候」という新しい診断概念に到達し,実臨床では多くの患者を見出している。今回,抗ガングリオニックアセチルコリン受容体抗体関連脳症,子宮頸がんワクチン接種後に発生した脳症,またはスティッフ・パーソン症候群でも同様の症候がみられることを報告する。自己免疫性脳症の臨床では,抗体の存在だけでなく,自己免疫性脳症による「びまん性脳障害」という概念が重要であり,この新しい診断概念を用いることで診断が困難な自己免疫性脳症の軽症例であっても容易に診断が可能となる。
13 0 0 0 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群と脳内神経炎症
- 著者
- 中富 康仁 倉恒 弘彦 渡辺 恭良
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- BRAIN and NERVE-神経研究の進歩 (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.19-25, 2018-01-01
筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)は,慢性で深刻な原因不明の疲労,認知機能障害や,慢性的で広範な疼痛を特徴とする疾患である。われわれは世界で初めてME/CFS患者における脳内神経炎症をポジトロンエミッション断層撮影(PET)によって明らかにした。神経炎症は患者の広範な脳領域に存在し,神経心理学的症状の重症度と関連していた。現在,診断法および治療の開発につなげる研究がスタートしている。
12 0 0 0 自己免疫性脳炎・脳症における運動異常症
- 著者
- 田代 雄一 髙嶋 博
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- BRAIN and NERVE-神経研究の進歩 (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.12, pp.1387-1399, 2017-12-01
自己免疫性脳症は,臨床的および免疫学的に多様な疾患である。少なくとも20種類の自己免疫性脳炎・脳症が報告されており,最も一般的なタイプは橋本脳症と思われる。患者はしばしば機能的,心因性の運動障害または身体表現性障害を示すと誤って診断されることがわかっている。自己免疫性脳症患者は,主に運動障害,覚醒障害,感覚異常,および振戦,筋緊張亢進,または不随意運動などの不随意運動を中心に運動障害を示した。さらに,記憶喪失,心因性非てんかん性発作,解離性健忘症,てんかん,または自律神経症状を観察した。自己免疫性脳症を診断するために,われわれは,脳の障害の部位別の組合せによりびまん性脳障害を検出する方法を提案する。びまん性脳障害では文字どおり,麻痺,運動の滑らかさ障害,不随意運動,持続困難な運動症状,痛みなどの感覚異常,記憶の低下や学習能力低下などの高次脳機能障害,視覚異常などの視覚処理系の障害がみられる。これらの複合的な脳障害は自己免疫性脳症の全脳に散在性に存在する病変部位と合致する。3系統以上の脳由来の神経症候は,おおよそ「びまん性脳障害」を示し得る。はっきりと局在がわからない神経症候は,一般的な神経学的理解では,転換性障害または機能的(心因性)運動障害に分類される傾向があるので,医師は自己免疫性脳症を除外することなく,心因性神経障害と診断するべきではない。 *本論文中に掲載されている二次元コード部分をクリックすると,付録動画を視聴することができます(公開期間:2020年11月末まで)。
8 0 0 0 【特別寄稿】筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群における神経学的異常
- 著者
- コマロフ アンソニー 高橋 良輔 山村 隆 澤村 正典
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- pp.41-54, 2018-01-01
筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)は6カ月以上持続する疲労感,睡眠障害,認知機能障害などを生じる疾患である。ME/CFSは自覚症状により定義されているため疾患概念そのものに対する懐疑的意見もあるが,近年の研究では神経画像,血液マーカーの解析,代謝,ミトコンドリアなどの研究でさまざまな客観的な異常が報告されている。特に脳内外での免疫系の活性化がきっかけとなり,炎症性サイトカインが放出されることで病気が発症する可能性が指摘されている。この総説ではME/CFSについての客観的なエビデンスを中心に解説する。
- 著者
- 林 拓也
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- Brain and nerve : 神経研究の進歩 (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.33-39, 2014-01
5 0 0 0 「阿吽の呼吸」の神経基盤
はじめに インフルエンザは伝染力が強く,特に65歳以上の高齢者,乳幼児,免疫低下状態の患者,糖尿病など慢性代謝性疾患の患者を含むハイリスク群では,重篤な合併症を引き起こして死亡する危険が増加する。インフルエンザ感染の予防にはインフルエンザワクチンの接種が有効とされ,毎年流行が予想されるインフルエンザウイルスに対してワクチンが製造されている。インフルエンザワクチンには,ハイリスク群がインフルエンザに罹患した場合,肺炎など重篤な合併症の発症を抑え入院・死亡などの危険を軽減する効果が認められており1),社会の高齢化が急速に進んでいるわが国でも,厚生科学研究の結果2)をもとにインフルエンザワクチンの接種が推奨されている。 インフルエンザワクチンは1971年以前には全粒子ワクチンが使用されていたが,1972年からは精製したウイルス粒子をエーテルによって部分分解した不活化ワクチンが登場した。これに伴い発育鶏卵の品質管理,精製技術の改良や発熱物質の除去などの技術的進歩によって,発熱や神経系の副作用は大幅に減少した。しかしながら,極めて稀ではあるが,Guillain-Barre症候群(Guillain-Barre syndrome:GBS)やacute disseminated encephalomyelitis(ADEM)など自己免疫機序が推定される脳神経障害を生じて後遺症を残す例も報告されている3,4)。 今回われわれは,インフルエンザワクチン接種後に単純ヘルペスウイルスによると考えられる辺縁系脳炎をきたした症例を経験した。インフルエンザワクチン接種後に生ずる脳神経障害は重篤な後遺症を残しかねず,最悪の場合死に至ることもある。これらを未然に防ぐためにも,インフルエンザワクチン接種後の副作用の発症機序を個々の症例ごとに検討することは重要である。
4 0 0 0 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の脳科学研究
- 著者
- 渡辺 恭良
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- BRAIN and NERVE-神経研究の進歩 (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.11, pp.1193-1201, 2018-11-01
筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)は,原因不明の激しい疲労・倦怠感とともに,労作後に増悪する極度の倦怠感,微熱,疼痛,脱力,認知機能障害,睡眠障害などの多彩な症状が長期にわたり継続し,日常生活や社会生活に支障をきたす疾患である。私たちは,この疾患に対し,血液因子や機能検査による客観的な疾患バイオマーカーを探索するとともに,PETやMRI,MEGなどを用いたイメージング研究により,ME/CFSの脳科学を推進してきた。
3 0 0 0 一酸化炭素中毒—三井三池三川坑炭塵爆発事故から50年
3 0 0 0 群発頭痛の新しい治療
3 0 0 0 パーキンソン病におけるプラセボ効果
はじめに プラセボ(placebo)効果は,薬理学的に作用が期待できない偽薬にもかかわらず,何らかの臨床的効果が得られることを示す。一般には,良い治療効果が出現した場合に用いられるが,副作用としてみられる場合もある1)。偽薬によって副作用が出現する場合には,ノセボ(nocebo)効果とも呼ばれる。薬物以外の治療手段においてもプラセボという言葉は繁用されており,シャム手術に対してもプラセボ手術と呼称されている。 プラセボ(placebo)の語源はラテン語で,‘I shall please'(私は喜ばせるでしょう)を意味するとされている1)。このプラセボ効果は,歴史的観点からは,おそらくは近代的医学の発展前には治療効果の本質であった可能性すらあるのではないだろうか。現代の日常診療の中でさえ,実際の医学的治療におけるかなりの部分を占めている可能性が高い。しかし,プラセボを治療薬の1つとして位置づけ得るかに関しては,人道的見地からも,また客観的治療効果の面からも批判がある。Hrobjartssonら(2001)の論文2)は良く知られている。プラセボが使用された100編以上の臨床試験データをレビューした結果,痛み以外の症状を改善する十分な証拠は得られなかったと述べ,新薬開発のための臨床試験以外に治療手段としての偽薬を使用することを批判している。一方で,実地臨床の場において,プラセボ効果が特に顕著であると広く実感されている疾患がある。疼痛,抑うつ,パーキンソン病である3)。本稿では,パーキンソン病におけるプラセボ効果に焦点を当て,その効果が本質的に病態を改善しているらしい臨床的知見や,プラセボ効果とドパミンに関する基礎医学的研究成果などについて述べたい。
3 0 0 0 音読課題において異なる誤反応パターンを示した純粋発語失行例の検討
3 0 0 0 脳神経内科領域における医学教育の難しさと課題
はじめに 脳神経内科学の教育には,他の診療科の教育とは異なる難しさが学ぶ側,教える側のいずれにもあるように思います。まず学ぶ側には「脳神経系は難しい」という苦手意識を持つ者が多いですし,教える側も脳神経内科学という広範な領域を限られた時間の中で「いかに教えるか,何を教えるか(how to teach,what to teach)」は非常に難しく,その教育を担当することに戸惑いを覚える医師も多いように思います。しかし,もし臨床現場で教育を担当する医師と基礎の神経科学教育を担う教官,さらに最新の臨床教育の理論や方法を研究する医学教育のエキスパートが,より密接に連携すれば,その教育効果は非常に大きなものになるのではないでしょうか。 こうした背景を踏まえつつ,神経科学の基礎・臨床教育において,学ぶ側,教える側にどのような特殊性があるのか,これからどのような教育を行っていくべきかを議論することを目的として,本連載を企画しました。連載開始にあたり本稿ではまず脳神経内科学教育を困難にしている学ぶ側の要因を検討し,本連載で取り上げるべき教育課題について議論したいと思います。
3 0 0 0 大脳皮質の単位回路
- 著者
- 中里 良彦 田村 直俊 池田 桂 田中 愛 山元 敏正
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- BRAIN and NERVE-神経研究の進歩 (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.263-270, 2016-03-01
Isolated body lateropulsion(iBL)とは,脳梗塞急性期に前庭症状や小脳症状などの神経症候を伴わず,体軸の一側への傾斜と転倒傾向のみが臨床症候として認められることである。iBLは脊髄小脳路,外側前庭脊髄路,前庭視床路,歯状核赤核視床路,視床皮質路のいずれの経路がどこで障害されても生じる可能性がある。本稿では,延髄,橋,中脳,小脳,視床,大脳において,どの病巣部位でiBLが生じるかを概説する。
2 0 0 0 抗自律神経節アセチルコリン受容体抗体と自己免疫性自律神経節障害
- 著者
- 中根 俊成 渡利 茉里 安東 由喜雄
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- BRAIN and NERVE-神経研究の進歩 (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.383-393, 2018-04-01
自己免疫性自律神経節障害(AAG)では抗ニコチン性自律神経節アセチルコリン受容体(gAChR)抗体の出現を血清中に認める。gAChRの構成サブユニットはα3とβ4であり,いずれかもしくはいずれに対しても自己抗体の産生が認められる。この抗gAChR抗体がAAGの病因であることを証明するin vitro実験は既に報告されており,患者血清IgGによる疾患移送もなされている。われわれは本邦におけるAAGの臨床像として,①慢性経過の症例が多い,②広範な自律神経障害を示すことが多いが,部分的自律神経障害(体位性起立性頻脈症候群,慢性偽性腸閉塞症など)の症例でも陽性と呈することがある,③extra-autonomic manifestations(自律神経外症状)として中枢神経症状(精神症状,記銘力障害など),内分泌障害などを呈することがある,④一部の症例において悪性腫瘍,膠原病などの自己免疫疾患の併存がみられる,などを報告してきた。これら以外の未解決の事項としてAAGと同じく自律神経障害を病態の主座とするニューロパチー(急性自律感覚ニューロパチーなど)が同じ疾患スペクトラム上にあるものか,異なるものか,が挙げられる。われわれはこれらの病像にアプローチするために他のニコチン性AChRサブユニットに対する自己抗体の検出についても研究を進めている。
2 0 0 0 ALSの軸索イオンチャネル障害
はじめに 筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)は進行性に,上位および下位運動ニューロンに系統変性を来す代表的な神経難病である。その臨床症状の特徴として,筋萎縮とともに線維束性収縮(fasciculation)が挙げられる。線維束性収縮は古典的に下位運動ニューロン徴候とされてきたが,多くの神経原性筋萎縮性疾患の中で実際に広範な線維束性収縮を認めるものはALSのみであり,脊髄性筋萎縮症,頸椎症性筋萎縮症や軸索変性型ニューロパチーにおいて,線維束性収縮は稀にしかみられない。このことは線維束性収縮が筋萎縮性疾患の中でALSにかなり特異的に生じており,ALSにおける運動ニューロン死に関与している可能性を示唆している。 線維束性収縮は運動単位(運動神経軸索)の自発発射により生じる1)。したがって,ALSにおける軸索興奮性は増大していることが推定される。ほかに線維束性収縮を特徴とする代表的疾患として,Isaacs症候群と多巣性運動ニューロパチーが挙げられる。Isaacs症候群は軸索の電位依存性Kチャネルに対する自己抗体が原因であることが確立されており,この疾患でみられる線維束性収縮やミオキミアは,Kチャネルの機能低下に起因する軸索の自発あるいは反復発射である2)。K電流は基本的に外向き(outward)の電流であり,陽イオン(K+)が軸索外に出ることにより膜電位は過分極側に偏位する。すなわちK電流は,軸索興奮性にとって抑制性のコンダクタンスであるといえる。多巣性運動ニューロパチーにおける線維束性収縮のメカニズムは明らかではないが,病変部軸索の静止膜電位が脱分極側に偏位していることが仮説として提唱されている3)。軸索の自発発射を来す興奮性増大のメカニズムとして,①Naチャネル(特に持続性Naチャネル;下記参照)の活性化,②Kチャネルの機能低下,③静止膜電位の脱分極側への偏位,などが挙げられ,ALSにおける軸索興奮性にどのメカニズムが関与しているかが注目されてきた。 1990年代に英国国立神経研究所のHugh Bostockにより開発された,threshold tracking法を用いた軸索機能検査法は,1990年代後半から臨床応用が広まり,NaあるいはKチャネル機能を含めた軸索特性を非侵襲的に評価することが可能になった4,5)。この手法は,これまでパッチクランプなどの観血的な方法でしか得られなかった軸索イオンチャネルに関する情報を,簡便に得ることができる画期的な手法として普及しつつあり,英国,日本,豪州などの研究グループにより多くの報告がなされるようになっている6)。本稿ではこの方法を用いてALSにおける軸索興奮性の変化について,これまでに得られた知見について概説する。結論を先に述べると,ALSでは持続性Na電流の増大と,K電流の減少という2つの軸索特性の変化が存在し,相乗的に軸索興奮性を増大させて線維束性収縮の発生に関与していると考えられる。