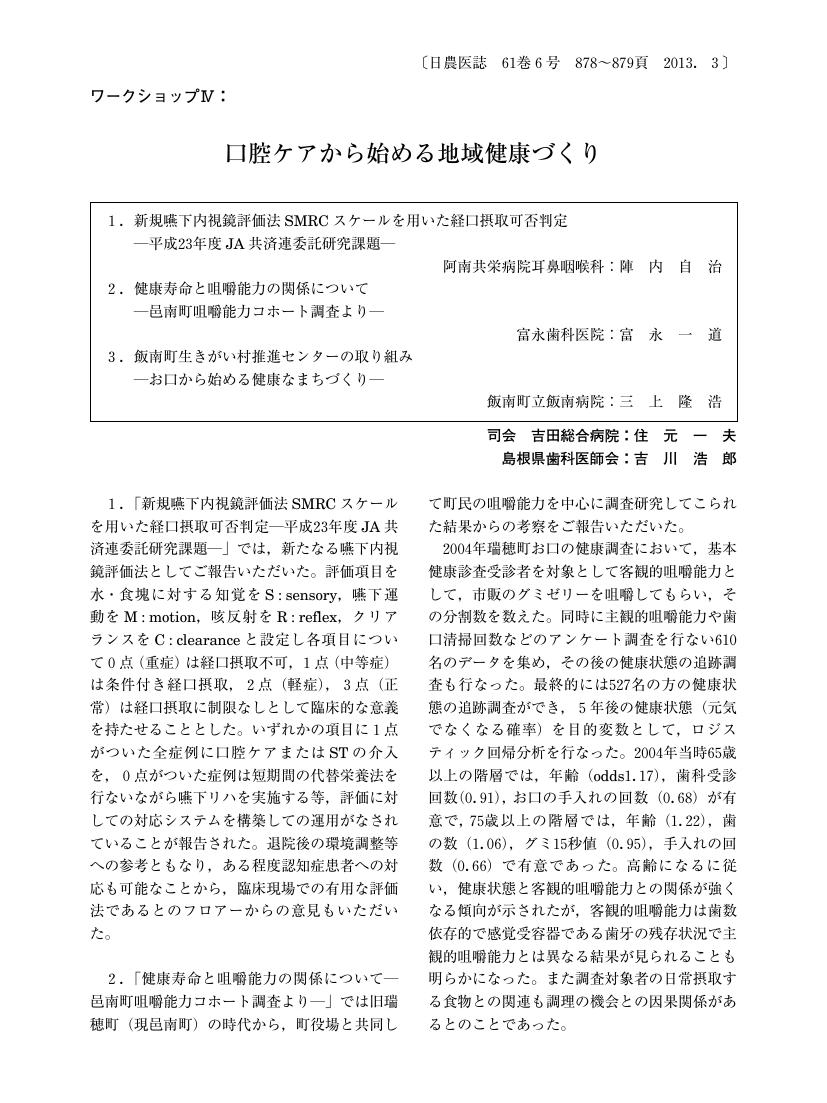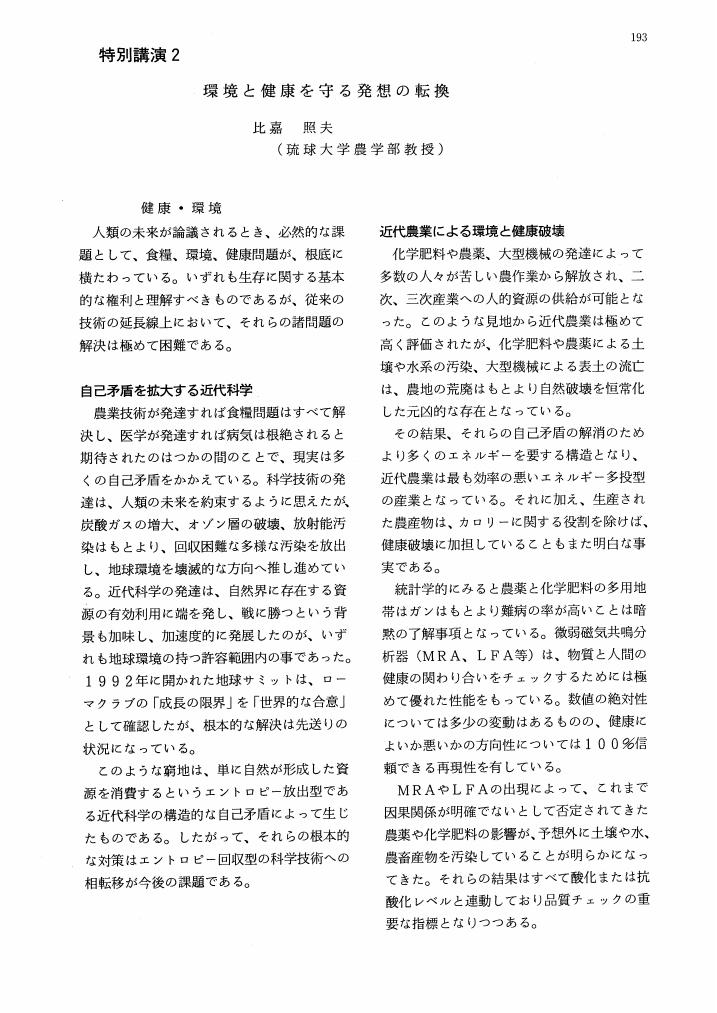1 0 0 0 異なる臨床経過を示したロタウイルス性急性脳症の2例
- 著者
- 渡辺 章充 南風原 明子 黒澤 信行 渡部 誠一
- 出版者
- THE JAPANESE ASSOCIATION OF RURAL MEDICINE
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.5, pp.591-594, 2011-01-30
ロタウイルス感染に伴う急性脳症を2例経験した。<br>〔症例1〕2歳11か月の女児で全身強直間代性けいれんで発症した。人工呼吸管理まで要したが,後遺症なく回復した。<br>〔症例2〕2歳2か月の女児で不機嫌状態が遷延し,脳波の徐波化,頭部MRIで小脳に異常信号を認めた。運動機能は回復したが,高次脳機能と軽度の小脳症状が残った。<br> ロタウイルスによる脳症には,けいれん発作主体のものだけでなく,小脳に主病変を示すタイプがある。前者は診断・治療とも他のウイルス性急性脳症に準ずることで大きな問題はないが,後者は早期診断に苦慮することもあり,また,有効な治療法も確立されていない。
1 0 0 0 健康教育介入による体重減少と代謝症候群改善との関係
- 著者
- 乃木 章子 塩飽 邦憲 北島 桂子 山崎 雅之 アヌーラド エルデンビレグ エンヘマー ビャンバ 米山 敏美 橋本 道男 木原 勇夫 矢倉 千昭 花岡 秀明 井山 ゆり 三原 聖子 山根 洋右
- 出版者
- THE JAPANESE ASSOCIATION OF RURAL MEDICINE
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.649-659, 2004-11-30
- 被引用文献数
- 1 3
農村地域で肥満, インスリン抵抗性, 脂質異常, 高血圧を合併した代謝症候群が増加している。代謝症候群に対しては体重減少が有効とされているが, 白人と日本人では肥満と代謝症候群の関係に差異が見られる。日本人での体重減少と生活習慣変容, 体重減少と代謝症候群の改善についての実証的な研究は少ないため, 体重減少に寄与する要因, 体重減少と代謝症候群改善との関係を研究した。2000~2003年に健康教育介入による3か月間の肥満改善プログラムに参加した住民188名を対象とした。参加者の平均体重減少は1.3kgであり, BMI, ウエスト囲, 血圧,総コレステロール, LDLコレステロール, 中性脂肪の減少, HDLコレステロールの増加を認めた。相関および回帰分析により, 摂取熱量減少, 消費熱量増加が体重減少に寄与していることが明らかになった。一方, 体重変化との有意な相関が認められたのは, 各種肥満指標, 総コレステロール, 中性脂肪, HDLコレステロールであり, 血圧とLDLコレステロールでは有意な相関を認めなかった。体重変化量と有意な相関が認められた血液生化学的検査値の変化量との相関係数は比較的低く, 体重変化量は中性脂肪や総コレステロールの変動の10%以下しか説明しなかった。代謝症候群の改善における体重減少の有効性について, アジア人の民族差に着目した体重減少の有効性に関する実証的な研究が重要と考えられる。
1 0 0 0 グルコマンナンのコレステロール低下作用に関する研究
- 著者
- 高松 道生 柳沢 素子 町田 輝子 松島 松翠 飯島 秀人 中沢 あけみ 池田 せつ子 宮入 健三 矢島 伸樹 佐々木 敏
- 出版者
- THE JAPANESE ASSOCIATION OF RURAL MEDICINE
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.595-602, 1999
- 被引用文献数
- 1
こんにゃくのコレステロール低下作用について検討し, その健康食品としての意義を明らかにする研究を行った。<BR>こんにゃくの成分であるグルコマンナンをチップ化して煎餅状に加工 (以下, マンナン煎餅) し, 総コレステロール200mg/dl以上の当院職員と正常範囲内の当院附属看護専門学校寄宿学生を対象に, 脂質代謝への影響を調査した。毎食後に煎餅を摂取し, 試験期間前後に脂質を中心とする血液検査を行ってマンナン煎餅の脂質代謝への影響を評価した。<BR>その結果, マンナン煎餅を摂取する事によって総コレステロール値の低下が認められ, 試験前総コレステロール値の高い群ほどその低下の度合いが大きかった。HDLコレステロールや中性脂肪への影響は認められなかった事から, マンナン煎餅はLDLコレステロールを特異的に低下させる作用を有するものと考えられた。血算や生化学などの検査値には変化を認めず, 腹満や下痢などの消化器症状が一部に観察されたものの, 重症なものではなかった。一方, 試験前後の体重に差はないものの試験期間中の総摂取エネルギーや脂質摂取は減少しており, マンナン煎餅を摂取することが食習慣に影響を与えた事が示唆される。以上から, こんにゃく (グルコマンナン) は直接・間接の作用でコレステロール, 特にLDLコレステロールを低下させ, マンナン煎餅が健康食品として意義を有するものと考えられた。
1 0 0 0 OA 糖尿病患者における発芽玄米摂取による糖・脂質代謝への影響
- 著者
- 早川 富博 鈴木 祥子 小林 真哉 福富 達也 井出 正芳 大野 恒夫 大河内 昌弘 多気 みつ子 宮本 忠壽 丹村 敏則 岡田 美智子
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.438-446, 2009-11-30 (Released:2010-04-12)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 3 5
発芽玄米の糖代謝・脂質代謝に対する影響を知ることを目的に,糖尿病患者に試験食 (発芽玄米: 白米を1:1に調整) を3か月間摂食させて,その前後で糖・脂質のパラメーターを比較検討した。3か月間の試験食摂取によって,グリコヘモグロビンは,摂取前の6.40±0.23%から6.23±0.19%へと有意な低下が認められた。空腹時血糖値に有意な変化はなかったが,インスリン値とHOMA-IRは低下傾向を示した。T-CHO値,TG値は試験食の摂取によって変化はみられなかったが,LDL-c値は低下傾向,HDL-c値は増加傾向を示し,LDL/HDL比は摂取前の2.03±0.13から,摂取3か月後には1.83±0.12へと有意に低下した。試験食摂取量を多い群と少ない群に分けて検討すると,試験食の摂取量が多い群で,LDL-c値は有意に低下,HDL-c値は有意に増加した。今回,糖尿病患者において,3か月間の発芽玄米摂取によって糖代謝と脂質代謝がともに改善する結果が得られた。これらは,糖尿病患者の食事療法として発芽玄米が有効であることを示すものであるとともに,高コレステロール血症の治療にも有効である可能性を示すものと考えられた。
- 著者
- 桐山 千加子 宇佐美 小夜子 米村 ひろ子
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, 2008-09-30
1 0 0 0 長野県佐久地方におけるマダニ刺こう症とライム病の臨床疫学的研究
- 著者
- 堀内 信之
- 出版者
- THE JAPANESE ASSOCIATION OF RURAL MEDICINE
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.85-95, 2001
- 被引用文献数
- 4
本邦の農山村では, 古くから大型の大豆大までになるマダニ (tick) による刺咬症があり, ときに咬着しているマダニをつまみ取った後に遠心性に拡大する紅斑が出現する症例がみられた。われわれは, 1987年に「マダニ刺咬症の統計」と題して, このような遊走性紅斑の7症例を報告した。ところが同じころ, 馬場等によって妙高高原でシュルツェマダニ刺咬後に生じたライム病の本邦第1例が報告され, 注目されるようになった。われわれは, その後もマダニ刺咬症とライム病の実態調査を続けてきたのでその結果を報告した。1999年までのマダニ刺咬症は, 165例であり, その中で遊走性紅斑を生じたライム病患者が16例であった。外来受診時の状態は, 虫体が咬着したままの症例62例 (37.6%), 虫体を除去した後の症例79例 (47.9%), 遊走性紅斑を生じた症例16例 (9.7%), その他8例 (4.8%) であった。年度別患者数は1994年の18例, 月別患者数は6月の135例・7月の113例, 年齢別患者数は10歳以下の33例・50歳代の32例・60歳代の29例, 咬着部位別患者数は腹部の99例が多いものであった。マダニの除去法は, 医師にて切開又は切除して除去したもの56例, 自分又は家人がつまみ取ったもの94例, 自然脱落したもの7例となった。刺咬マダニの種類は, シュルツェマダニ56例・ヤマトマダニ26例・その他3例となった。ハイリスク集団である営林署職員のアンケート結果と抗ライム病ボレリア抗体の測定をあわせて報告した。
- 著者
- 植松 夏子 柴原 弘明 岡本 妙子 木下 早苗 眞野 香 青山 昌広 西村 大作 伊藤 哲 吉田 厚志
- 出版者
- THE JAPANESE ASSOCIATION OF RURAL MEDICINE
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.764-769, 2012
直腸癌術後仙骨転移による坐骨神経痛に対し緩和ケアチームが介入した。娘の結婚式を控え,早急な疼痛緩和と,レスキューの人工肛門からの投与経路変更が必要であった。投与していたフェンタニル貼付剤25.2mg/72hrを16.8mg/72hrへ減量し,モルヒネ注射薬3.6mg/hrを新たに併用した部分的オピオイドローテーションと,患者自己調節鎮痛ポンプによる経静脈的経路へのレスキュー投与経路の変更により,患者は疼痛なく,家族も安心して結婚式に参加することができた。今回行なった部分的オピオイドローテーションは,①比較的短時間に行なえる,②異なるオピオイドを新たに加えるため鎮痛が期待できる,③オピオイド変更による副作用が全量オピオイドローテーションより少ない,といった利点がある。癌患者の疼痛緩和での薬剤調整は,患者と家族の視点で立案することが肝要である。
1 0 0 0 農村地域に居住する高齢者の幸福感に寄与する活動
- 著者
- 大西 丈二 益田 雄一郎 鈴木 裕介 石川 美由紀 近藤 高明 井口 昭久
- 出版者
- THE JAPANESE ASSOCIATION OF RURAL MEDICINE
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.641-648, 2004-11-30
- 被引用文献数
- 5 1
加齢に伴いこれまで担ってきた家庭的・社会的役割を喪失することの多い高齢者では,活動性が低下しやすく,時に身体的・精神的機能低下を引き起こしてしまうこともある。地域で行われる余暇活動の開発は高齢者の活動性やQuality of Life (QOL) の維持・向上に役立つものと思われるが,こうした余暇活動の効果はまだあまり実証されていない。今回われわれは農村部に居住する424名の高齢住民 (平均年齢71.6±4.8SD歳) を対象に,余暇活動を楽しむことと幸福感等との関連を明らかにするため調査を行った。調査項目として生活環境や,日常生活動作 (ADL) などの身体状況,外出の頻度,余暇活動を楽しいと感じる程度およびPGC主観的幸福感を含めた。この結果,楽しいと思う活動は「入浴」,「食事」,「テレビ」の順であった。余暇活動の中では「食事」や「入浴」を楽しむことがPGC主観的幸福感と正の関連を持ち,逆に「パチンコや麻雀などの賭けごと」を楽しむことは負の関連を示した。「動物の相手」を楽しむ者は閉じこもりが少なかった。PGC主観的幸福感を従属変数とする回帰分析では,人間関係の悩み,「パチンコや麻雀などの賭けごと」を楽しむこと,基本的ADL,体の痛み,独居を予測値とした有意なモデルが構築された。これらの結果は今後地域で高齢者の余暇活動を促進していくにあたり,有用な知見を与えた。
1 0 0 0 OA 採尿後の経過時間と温度が尿検査に及ぼす影響
- 著者
- 仲谷 和彦 柏倉 紀子 黒木 悟 遠藤 正志 杉田 暁大
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.5, pp.789-797, 2016-01-30 (Released:2016-03-16)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
尿検査は, 概ね患者に苦痛を与えることなく検体採取が可能であり, 分析機器の発達により簡便かつ短時間で多くの情報を得ることができる検査である。 しかし, 保存状況で尿成分は変化しやすく, 採尿後速やかな検査実施が原則であるが, 入院患者の場合採取から検査実施まで数時間経過している場合がある。その背景には, 採尿時間が不規則なため, 速やかに検査室に提出されない現状に起因する。 そこで, 特定条件下で実際に患者尿を用い, 経時的変化・規則性について検討した。 さらに, 尿中に高頻度に検出される腸内細菌 (大腸菌・プロテウス菌) が尿糖に及ぼす影響と亜硝酸塩反応の変化についても検討したので報告する。 結果, 尿検査に影響するような生理的・病的成分を含有する尿ほど経時的変化は著明であった。保存が必要な時は, 蓋付容器で冷蔵保存が望ましい。また, 尿中の大腸菌とプロテウス菌では, 解糖作用・亜硝酸還元反応の経時的変化に大きな差が認められた。
1 0 0 0 OA 口腔ケアから始める地域健康づくり
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.6, pp.878-879, 2013 (Released:2013-07-23)
1 0 0 0 OA 由利本荘地区におけるHPV併用検診の結果について
- 著者
- 軽部 彰宏 齋藤 史子 長尾 大輔 田村 大輔 尾野 夏紀 木村 菜桜子
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.1-8, 2014 (Released:2014-07-24)
- 参考文献数
- 12
平成24年度より由利本荘地区 (由利本荘市, にかほ市) で, 細胞診のみによる従来の子宮頸がん検診にHPV検査を併用したHPV併用検診が開始された。1年間で772名がHPV併用検診を受診し, 87症例 (11.3%) がHPV検査陽性であった。その後に精査受診し, 組織診断まで追跡可能であった64症例 (73.6%) の結果について示した。細胞診が正常でHPV検査が陽性であった症例の67.6%にCIN1以上の病変が認められ, CIN2以上が5例発見された。従来の細胞診のみで発見されたCIN2以上は9例であったが, HPV検査を併用することでCIN2以上は14例となった。子宮頸がん検診の精度を向上させるために, HPV併用検診を積極的に取り入れていくべきと考えられた。
1 0 0 0 OA 果てしなき夢-輝く命
- 著者
- 三浦 雄一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.6, pp.925-928, 2015 (Released:2015-06-02)
1 0 0 0 OA 東日本大震災・原発事故による福島県下病院の被災状況
- 著者
- 前原 和平
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.6, pp.802-806, 2013 (Released:2013-07-23)
1 0 0 0 OA エンドリン急性中毒 (自殺) 2例の観察
- 著者
- 加藤 元義
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.4, pp.186-188, 1970-03-01 (Released:2011-02-17)
1 0 0 0 OA 環境と健康を守る発想の転換
- 著者
- 比嘉 照夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.193-194, 1995-09-10 (Released:2011-08-11)
1 0 0 0 JA いずも女性部における健康福祉の視点から組織基盤強化戦略
- 著者
- 中尾 陽 塩飽 邦憲 山根 洋右
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, 2003-09-30
1 0 0 0 OA 高齢者の生活習慣病対策
- 著者
- 林 雅人
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.5, pp.705-711, 2003-01-30 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1 2
高齢者の生活習慣病対策は若壮年とは異なった視点が必要である。BMIについて男性ではやせ群の生存率が低く, 高齢男性群はがん死亡者を除外しても有意に低い。血清総コレステロールについて高齢者男性群は中年群より血清総コレステロール低値群の生存率が明確に低く, 5年以内のがん死亡例を除外してもその傾向は変わらない。この事実は基本健診で得られた高齢者高コレステロール血症に対する食事指導を若年者と同様に行うべきでないことを示している。血清アルブミンと血清総コレステロールは男女, 中年・高齢群すべてにおいて有意に正相関しており, がん死亡例を除外してもその傾向は変わらない。この相関は高齢者程より明確であった。この点からみても高齢者食事指導にあたっては若壮年者と同様に行うべきではない。
1 0 0 0 OA 農村における心疾患の現状と対策
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.258-297, 1983-09-20 (Released:2011-08-11)