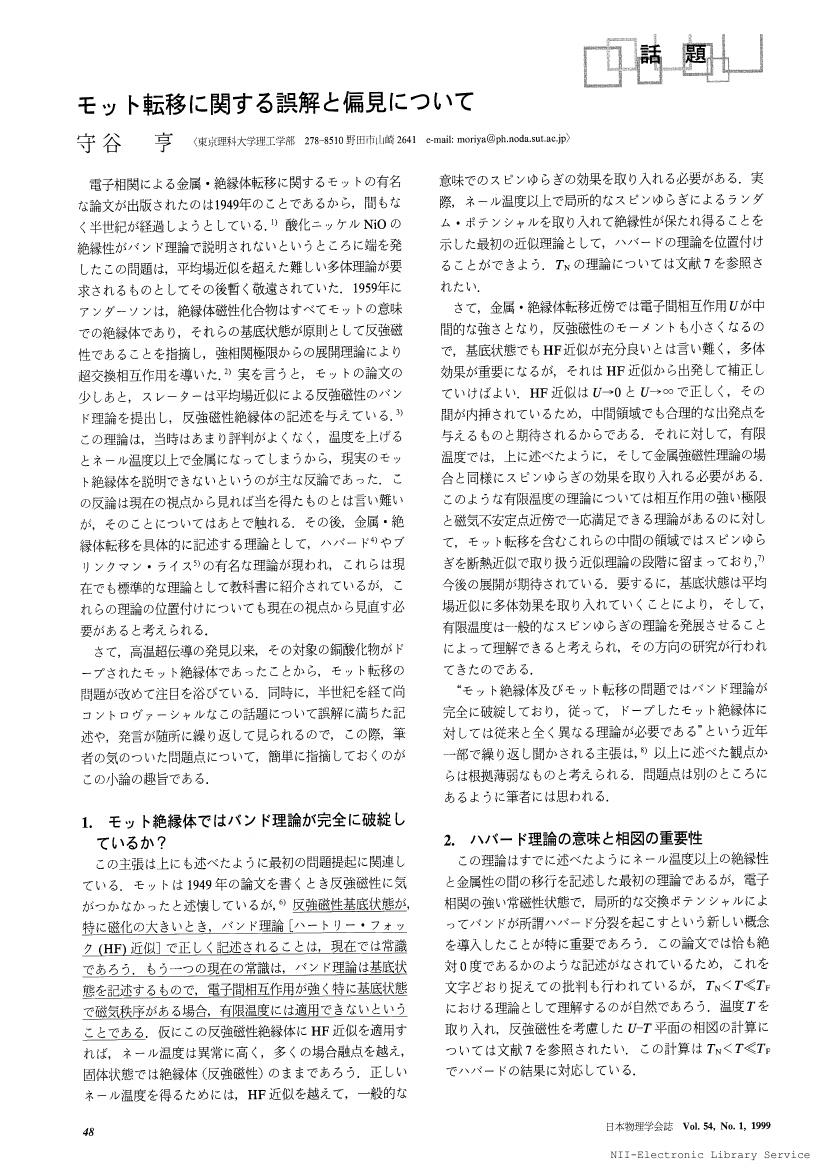7 0 0 0 OA 同位体シフトによる新物理探索――精密分光で迫る基本法則
- 著者
- 田中 実 小野 滉貴 山本 康裕 高橋 義朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.6, pp.355-360, 2022-06-05 (Released:2022-06-05)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
素粒子物理学には,いくつかのフロンティアがある.一つは高エネルギーフロンティアで,高エネルギーの状態から新たな素粒子を発見することが主な目的である.CERNの大型ハドロン衝突型加速器(LHC)が現在の最高エネルギーの実験装置であり,LHCにおける2012年のヒッグス粒子の発見により,素粒子標準模型に登場するすべての粒子が既知のものとなった.もう一つのフロンティアは高輝度(あるいは高強度)フロンティアで,特定の素粒子を大量に生成し,その性質を詳しく調べることで素粒子の相互作用について解明することを主眼とするものである.日本ではKEKのスーパーBファクトリー実験やJ-PARCにおけるK中間子,ミュー粒子,ニュートリノの実験等がこれにあたる.宇宙も素粒子物理のフロンティアであり,インフレーション理論の検証等が行われ,コスミックフロンティアと呼ばれている.これらに加えて,高精度フロンティアと呼ぶべき研究が近年重要さを増している.例えば,標準模型を越える新しい素粒子模型の多くが予言する,電子の永久電気双極子能率の探索が,原子や分子を対象とした高精度の測定に基づいて行われている.このフロンティアは,原子物理学の発展と密接に関連している.かつてはマクロな数の原子集団の測定によって個々の原子の性質が決定されてきたが,実験技術の進歩とともに,少数の原子を対象とした実験が可能になり,1個の原子やイオンをトラップし,単独原子の孤立状態を実現できるようになった.また,多数の原子の低温の孤立集団も実現されるようになり,ボーズ・アインシュタイン凝縮といった量子的なマクロ状態も観測されている.私たちは,原子スペクトルの同位体シフトを精密に測定することで,標準模型を越える新しい物理の探索を行っている.もし,電子と中性子に結合する新粒子が存在すれば,この粒子が電子・中性子間で交換されることでも同位体シフトが起こる.同位体シフトの実験値と標準模型での理論値を比較すれば,原理的には,この効果を検出できる.しかし,同位体シフトの系統的精密測定が行われているカルシウムやイッテルビウムのような電子多体系のスペクトル計算の不定性は,実験精度に比べてかなり大きい.このため,同位体シフト自体の実験値と理論値の直接的な比較による新物理探索は,単純な原子を除いて現実的ではない.そこで,複数の遷移の同位体シフトが満たす線形関係に注目し,新粒子の効果でこの線形関係が破れることを利用して,新物理探索を行った.具体的には,魔法波長の光格子に中性イッテルビウム原子をトラップし,578 nmの狭線幅光学遷移(時計遷移)について,数Hzの不確かさで系統的に同位体シフトの測定を行った.この結果と先行研究のイッテルビウムイオンの411 nmおよび436 nmの遷移の同位体シフトの測定結果を合わせることで,世界初の3遷移間の線形性検証を行った.その結果,線形性が有意に破れていることが分かったが,同時に,この線形性の破れは標準模型で説明されるべきものであることも明らかにした.新物理に由来する非線形性には上限が得られ,これに基づいて新粒子の結合定数に対する制限を与えた.現状では得られた制限は既存の実験のものよりも弱いが,今後の実験精度の向上によりこれを上回ることが期待される.
7 0 0 0 OA ラムダ粒子は,陽子と中性子を区別できるか?――ラムダハイパー核における荷電対称性の破れ
- 著者
- 中村 哲 永尾 翔 田村 裕和 山本 剛史
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.5, pp.287-292, 2022-05-05 (Released:2022-05-07)
- 参考文献数
- 29
陽子と中性子は電荷の有無という大きな違いがあるがほぼ同じ質量をもち,さらに核力に対する振る舞いもほぼ同じである.例えば陽子1個と中性子2個から構成される三重水素(3H)と陽子2個と中性子1個からなるヘリウム3(3He)は鏡映核の関係にあり,ほぼ同じ質量(約2,800 MeV/c2)をもつが,この両者の質量差から,陽子と中性子の質量差およびクーロン相互作用の効果を除外して,核力による3Hと3Heの束縛エネルギー(それぞれ約8 MeV)の差を求めると,わずか0.07 MeV程度しかない.これは陽子・陽子間と中性子・中性子間の核力の強さがほとんど等しいことを示している.このような陽子と中性子の入れ替えに対する核力(そして原子核)の対称性を荷電対称性(Charge Symmetry)という.核子だけで構成される通常の原子核に,最も軽いハイペロンであるラムダ粒子を束縛させたものをラムダハイパー核と呼ぶ.半世紀ほど前に実施された実験結果に基づいて,通常の原子核では良く成り立っている荷電対称性が4ΛH(三重水素にラムダ粒子が束縛した系)と4ΛH(ヘリウム3にラムダ粒子が束縛した系)の間で大きく破れているのではないか,と言われてきたが,その証拠とされる実験結果の一部は統計量,分解能のどちらも不十分であり,ラムダハイパー核における大きな荷電対称性の破れの有無は確定していなかった.この状況を打破すべく,我々は最新の実験技術を駆使した2つの実験をドイツMAMI電子加速器施設と茨城県東海村にある大強度陽子加速器施設J-PARCで行った.MAMIにおいては薄い9Beフォイルに1.508 GeVの電子ビームを照射した.生成されたハイパー核の破砕反応から生じた4ΛHハイパー核は,その多くが標的中に静止して弱い相互作用により4He+π-に2体崩壊する.このとき放出されるπ-の運動量を精密に測定することにより,親核である4ΛHの基底状態の質量を過去の実験より10倍良い分解能で測定することに成功し,電子ビームを用いて生成したラムダハイパー核の崩壊π中間子分光法という新しい実験手法が確立した.この測定により4ΛH,4ΛHeの基底状態(スピン0)のラムダ束縛エネルギーに対して,その存在が示唆されていた大きな荷電対称性の破れが確かに存在することを明らかにした.一方,J-PARCハドロン施設においては,従来の4ΛHeの励起エネルギー測定で使用されていたNaI(Tl)検出器の25倍の分解能をもつゲルマニウム検出器群Hyperball-Jを用いて4ΛHeのスピン1の励起状態からスピン0の基底状態への脱励起に伴うγ線を精密分光することに成功した.この結果から4ΛHeの励起状態(スピン1)と基底状態(スピン0)のエネルギー間隔は従来信じられていた値と大きく異なり,4ΛHと4ΛHeの励起エネルギーに大きな荷電対称性の破れがあることを示した.さらに,励起状態(スピン1)のラムダ束縛エネルギーでは荷電対称性の破れは小さいことも分かった.これら2つの新測定により,質量数4ラムダハイパー核において確かに荷電対称性が大きく破れていることと,その破れ方がスピンに依存するという新たな知見が得られた.この現象はまだ理論的に説明できず,核力(バリオン間力)の我々の理解が不十分であることをさらけ出した.謎の解明に向けた研究が進められている.
7 0 0 0 OA 強相関系の非平衡物理 (解説)
- 著者
- 岡 隆史 青木 秀夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.234-242, 2012-04-05 (Released:2019-10-19)
- 参考文献数
- 48
- 被引用文献数
- 1
非平衡強相関系について解説する.これは強相関電子系の光誘起相転移や非線形伝導などの研究に発し,冷却原子気体における光格子中の非平衡ダイナミックスなどとも関連して,実験・理論が急速に進展している分野である.QEDにおけるシュウィンガー機構など強電場中の場の理論における概念が,物性物理において多体効果を舞台として発展している様子を,物性版"strong field physics"として解説する.
7 0 0 0 蛍光ナノダイヤモンドを用いた量子生体センサー
- 著者
- 鹿野 豊 藤原 正澄
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.10, pp.593-598, 2023-10-05 (Released:2023-10-05)
- 参考文献数
- 47
計算・通信・暗号といった現代の情報社会の礎として情報理論がある.一方,情報社会を担うハードウェアは物理法則に従うデバイスによって構成されているため,物理法則によって制限された情報理論が必要である.中でも,量子力学の法則によって制限された情報理論は量子情報科学と呼ばれ,量子エレクトロニクス技術と融合しながら40~50年かけて発展してきた.デジタル社会の情報処理の最小単位を「ビット」と呼ぶが,同様に量子情報処理の最小単位を「量子ビット」と呼ぶ.一般に,量子ビットは外界環境に対して脆弱であり容易にその状態を変化させてしまう.この性質は量子ビットの品質向上にとっては負の側面であるが,見方を変えれば,環境因子を精密に測定できる能力を保持していることを意味している.そのため,このような物理系の応用は量子センサーと呼ばれている.量子センサーは単一原子レベルでの量子状態操作が可能であることから,従来のセンサーより高感度でかつ高い空間分解能であると期待されている.これらの情報技術や計測技術をまとめて,量子情報技術または量子技術と呼ぶようになった.そして近年,量子計算機の実装を中心に量子情報技術の研究開発が盛んに続けられている.量子情報技術の中でも,室温動作が可能な物理系として注目されているダイヤモンド中の窒素・格子欠陥(NV中心)にある電子スピンは,光検出磁気共鳴法を用いることで,量子状態を可視光で読みだすことができる.また,その量子状態はマイクロ波を印加することで容易に制御できる.ダイヤモンドNV中心の基底状態は電子3重項状態であり,超微細構造を持つ.この超微細構造が磁場,圧力,温度に対して変化するため,ダイヤモンドNV中心は室温で動作する量子センサーとして開発が進められ,理想的な環境において従来技術のセンサーより感度が向上しているということが示されてきた.一方で,生体試料などの実際に調べたい環境において,ダイヤモンド量子生体センサーがどのような性能を示し,これまでに得ることができなかった知見をもたらすことができるかは分かっていなかった.そこで,人工的に作製された蛍光ナノダイヤモンドを量子センサーとして生体試料に微小ガラス管を用いて投入し,生体試料内部の温度を局所的に計測した.具体的には,「生物学研究の未来」として称されることもある線虫(C. elegans)というモデル生物を生体試料として,薬剤投下時の発熱現象を計測した.まだ,薬剤投下時の発熱は分子科学的なメカニズムが解明されていない生理現象ではあるが,局所的な量子生体センサーを用いることで発熱現象自体が線虫内で起こることの証拠を得た.量子生体センサーの研究開発は,純粋なる物理学の基礎研究として捉えるのが非常に難しくなる一方で,他分野への応用を推進していく上で,他分野の未知なる現象を解明するために使われなければならない段階にある.そして,誰かが近い将来『量子情報技術の常識』という教科書を執筆した時, 量子情報技術分野の存在価値の大半が,その分野が他分野に対して果たす役割の大きさに依存することを忘れてはならない. と書き記されているであろう.
7 0 0 0 OA 宇宙原理の観測的検証(最近の研究から)
- 著者
- 柳 哲文 中尾 憲一
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.37-43, 2012-01-05 (Released:2019-10-19)
- 参考文献数
- 14
宇宙原理は現代宇宙論の根幹となる作業仮説であり,その観測的検証は観測的宇宙論において最も大きな挑戦の一つといえるだろう.本稿ではIa型超新星の距離-赤方偏移関係,CMB観測,赤方偏移ドリフトなどを用いた宇宙原理の観測的検証に関する最近の研究について報告する.近年の観測技術の発展は宇宙原理の観測的検証を可能にしつつあり,それゆえ,宇宙原理を前提としない宇宙モデル,すなわち非一様な宇宙モデルの理論的な研究が重要になってきた.このような宇宙モデルにおける観測量について簡単に解説しながら,これまでに得られた制限と将来の展望について報告する.
7 0 0 0 OA テンソルネットワークで格子場理論を計算する――符号問題への挑戦
- 著者
- 武田 真滋
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.3, pp.136-144, 2022-03-04 (Released:2022-04-05)
- 参考文献数
- 39
統計物理系の物理量を計算するうえでモンテカルロ法は非常に有効であり大きな成功を収めてきた実績がある.しかし,この方法ではボルツマン因子を確率として扱うため,もしそれが負または複素数の場合はこの方法はそもそも使えなくなってしまう.これを一般的に符号問題と呼ぶ.この問題は計算科学の様々な場面で顔を出し,多くの研究者を悩ませてきた.実際,この問題に対抗すべく多種多様なアイデアが提案されては結局は失敗するという無残な光景がしばらくの間繰り返され,さらには,符号問題解決という切実な願いを踏みにじるように,この問題はNP困難であることが証明されてしまった.つまり,符号問題を打ち負かそうとどんなに工夫をしようが,一見封じ込めたようにみえたとしても,別の形でしっぺ返しがくることを予見している.ということは,符号問題のために解析することが難しいモデル,例えば素粒子物理学の中でいえば,有限クォーク数密度QCDやカイラルゲージ理論などの非摂動的ダイナミクスを第一原理計算によってうかがい知ることは不可能なのだろうか? もちろん,答えは否である(と考えたい).実際,NP困難性は符号問題に対する一般的な解法の存在を否定しているだけであり,特定のモデルや理論に対する個別の回避法の存在は否定していない.符号問題の回避策の一つとして最近注目を集めているのがテンソルネットワーク法である.その特徴は,特異値分解に基づく定量的な情報圧縮と実空間くりこみ群による物理自由度の粗視化のアイデアを取り入れている点である.物性系では,量子多体系の変分問題を解く方法として,素粒子系では主に,経路積分を直接評価する方法として発展している.一方,テンソルネットワーク法の課題に目を向けると,2つの問題が残されている.1つ目は,高次元系での計算コストが非常に高くなるという問題である.2次元系ではモンテカルロ法と並ぶ,あるいは場合によってはそれを凌ぐような精度を達成しているのに対し,そのコストが次元に関して指数関数的に増大することから高次元系での研究は低次元系ほどは進んでいなかった.しかし,近年,コスト削減アルゴリズムの開発が特に日本を中心として活況を呈しており,現在利用可能な計算資源でも単純な内部自由度をもつ系であれば,3ないしは4次元系における精密計算も視野に入ってきた.今後は,コスト削減のために犠牲となった近似精度の向上が鍵となるであろう.2つ目の課題は情報圧縮の可否の問題である.どのような系でもテンソルネットワーク法を適用すれば情報圧縮が可能であるという保証はなく,現在のところその可否を個々の系で調べるしかない.よって,理論空間の中でモンテカルロ法でもテンソルネットワーク法でもアクセス不可能な領域が存在するかもしれない.それら以外の方法でも解析できないような理論が存在するのだろうか,など計算の可能性という観点から問題を掘り下げるのも興味深い.今後はテンソルネットワーク法を進化させてその実績を積み上げるのはもちろんのこと,その概念的な位置づけの理解を深めていくことも重要なテーマになるであろう.
7 0 0 0 OA モット転移に関する誤解と偏見について
- 著者
- 守谷 亨
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.48-50, 1999-01-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 3
7 0 0 0 OA 機械学習における物理が果たす役割――量子機械学習とその現状
- 著者
- 大関 真之
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.4, pp.194-201, 2021-04-05 (Released:2021-04-05)
- 参考文献数
- 12
機械学習では,入力と出力の関係がよくわからないものに対して,とりあえず自分たちが扱うことのできる簡素な関数を用意する.猫の姿を見て,猫だと認識するのは,入力が画像データであるのに対して,猫だという指摘をする結果をはじき出すのだからよくわからない入出力関係があるのは間違いない.しかしそれをコンピュータが実践できるように扱いがしやすい関数を用意する必要がある.ただし,その関数には変更可能なパラメータを複数含ませておき,できるだけ広い豊富な表現力をもつようにしておく.後で微調整を行い,実際に入力を与えた時に適切な出力が与えられるようにする.関数に変更を加えてなんとか辻褄を合わせるというのは変分法に相当する.変更可能なパラメータ以外にも機械学習では,非線形変換を伴う関数を利用して,その表現能力を増強することができる.ニューラルネットワークが深層化を経て,非常に複雑な非線形変換を獲得するのも,そうした目的があるためだ.非線形変換というのは,ある種の飛躍であり,計算の難しさの象徴として現れる.例えば高校生のときに二次関数まで学んだのちに,三角関数をはじめ,指数関数と対数関数を学び,その豊富な数学の表現力に魅了される.しかし同時にその扱いに厄介さを覚えることもある.ただ慣れてくれば,その扱いもその存在も親しみをもって普段使いをする対象となる.人間というのはなかなか勝手なものである.そうした機械学習の分野で一つ気になる用語が登場しつつある.量子機械学習である.その冠にある量子力学は理解をすんなりと許さない,厄介な対象となる代表例である.交換しない演算子を利用して微視的な自由度の変化を追う際に新しい計算方法や概念を学ぶため,私たちの感覚のアップデートを必要とするというのも大きい.この量子力学は,機械学習とは一切関係のなさそうなものである.しかし人類はそうしたものですら,より豊富な表現力を得るために,機械学習において利用する関数に取り込もうとしている.量子力学では,エネルギーの固有状態を調べるのに,原理的には高次元の行列の対角化を伴い,最終的には数値計算に頼る.また時間発展にしても,ハミルトニアンが指数関数化されて状態ベクトルにかかることにより,そう単純ではない変化を生み出し,やはり数値計算に頼る他なかった.問題設定そのものは単純に行えるとしても単純ではない変化を生み出すのが量子力学の難しさである.しかしこの部分を積極的に利用すれば,機械学習で利用されうる「複雑な非線形変換」を作り出せることが期待される.量子機械学習とはそういう営みであると換言できる.他にもニューラルネットワークでなされる誤差逆伝播法から始まる勾配法による最適化を,運動方程式により駆動される系の変化と捉えれば,その運動方程式をシュレーディンガー方程式に置き換えるなどして量子力学の原理を導入することも考えられる.これも量子機械学習の一つのあり方と言える.こうした自然に量子力学を取り入れようとする発想が出てきた理由は,近年注目される量子コンピュータを始めとして制御可能な量子デバイスの進展があり,実際に動作する量子デバイスを手にしているという現状にある.人類にとって,もはや量子力学は親しみをもって普段使いする対象になりつつあるのだ.
7 0 0 0 OA 量子コンピュータを用いた変分アルゴリズムと機械学習
- 著者
- 御手洗 光祐 藤井 啓祐
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.9, pp.604-611, 2019-09-05 (Released:2020-03-10)
- 参考文献数
- 42
ファインマンが指摘したように,量子系は粒子数に対して指数的に自由度が増えるため,従来コンピュータでのシミュレーションは難しくなる.量子力学の原理によって計算を行う量子コンピュータは,このような問題を根本的に解決することができると期待されている.今では,原子や電子,そして量子化された電気回路など,個々の量子系を精密に制御する量子エレクトロニクス技術の進展に伴って,量子コンピュータの実現が現実味を帯びつつある.現在,Google,IBM,Microsoftなどの巨大IT企業に加え,ベンチャー企業であるRigetti computingなどが量子コンピュータの実現に向けた基礎研究開発を行っており,すでに数十量子ビット程度の規模の量子コンピュータが実現している.さらに,ここ数年で数百量子ビット規模の量子コンピュータが実現されると期待されている.十分に精度の高い操作が可能な100量子ビット程度の系ができれば,スーパーコンピュータを用いても完全にシミュレーションすることは難しく,このような規模でも大きな潜在能力を秘めている.一方で,量子誤り訂正を実装できるほどの規模がないため,複雑な量子アルゴリズムを実装することはできない.このようなデバイスは,Noisy Intermediate Scale Quantum(device)を略しNISQデバイスと呼ばれている.NISQデバイスはノイズの影響から,多くのステップを要するような複雑な量子計算を実行することができない.できるだけ,量子計算をコンパクトに設計し有効活用する方法が求められており,物理分野でも古くから行われてきた,変分法による量子系の解析が注目を集めている.従来のコンピュータ上で実行する変分法では,量子状態を効率のよい試行関数によって表現する必要がある.密度行列繰り込み群やテンソルネットワークなど,計算コストをできるだけ抑えて量子相関を取り込む方法が検討されてきた.それに対して,量子コンピュータ上の量子状態を試行関数として利用すれば,複雑な量子相関を取り込んだとしても,その状態の生成からエネルギーや観測量の評価は,物理法則を用いて効率よく実行することができる.まさに,ファインマンが指摘したように,量子力学で動作する量子コンピュータを用いて変分法の試行関数を表現するのである.このようなアプローチで,量子多体系の基底状態を求める変分法が変分量子固有値法(Variational Quantum Eigensolver, VQE)である.試行関数によるモデル化は,物理分野だけでなく,ニューラルネットワークなどの機械学習においてもよく行われている.最近では,量子多体系をニューラルネットワークで表現したり,物質相を機械学習で分類する,といったアプローチの研究も進んでいる.我々の最近の研究では,教師あり機械学習に量子回路を用いた変分的なアプローチを利用することを提案している.量子ビットに対して指数的に大きな次元となるヒルベルト空間を機械学習のための特徴量空間として利用しようという試みである.また,このような量子コンピュータを用いた機械学習を基底状態などの量子系を学習するために応用する研究も行っている.このように,変分アプローチによる量子古典ハイブリッドアルゴリズムは,NISQデバイスでの利用が期待されており,発展が期待される分野である.
7 0 0 0 OA 機械学習を用いて量子多体系を表現する
- 著者
- 野村 悠祐 山地 洋平 今田 正俊
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.2, pp.72-81, 2019-02-05 (Released:2019-08-01)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 1
量子多体系とは多数の自由度がお互いに相互作用しあう系を指し,そこにおける各自由度の運動は多体の波動関数によって支配される.多体波動関数さえわかってしまえば問題解決であるが,多体系のハミルトニアンの次元は自由度の数に対して指数関数的に増大するため,自由度の数が増えると多体波動関数を厳密に求めることは不可能になる.そのため,多体波動関数をいかに精度よく表現できるか?という問題は,非常に重要な課題になる.この問題に対して新しい風が吹いている.これまで物理的洞察に基づいて波動関数を近似する試みは多くなされているが,それとは逆に対称性などの明らかな拘束条件以外には直観に頼らず,機械学習の力を借りて波動関数を構築しようという動きである.機械学習は膨大なデータセットからその本質的なパターンを抽出する.すなわち,本来の波動関数は指数関数的に大きな次元を持つベクトルとみなせるが,その本質的なパターンを機械学習によって見つけ出し,波動関数の次元よりもはるかに少ない数のパラメータを用いて波動関数を精度よく近似しようという試みである.機械学習の手法の中でも,本稿では,人工ニューラル・ネットワークの一種であるボルツマンマシンを用いた変分波動関数について議論する.ボルツマンマシンは可視(入力)層の自由度である可視ユニットに加え,仮想的自由度である隠れ層の不可視ユニットで構成され,ユニット間が結合(相互作用)を持つ構造をしている.ボルツマンマシンは可視ユニットの状態配置を入力とし,その生成確率分布を学習する機械である.それに対し,多体波動関数は物理的なハミルトニアンの自由度の状態配置それぞれに対して値を与える.波動関数の値が,それらの状態配置に対する(複素数に一般化された)確率であると考えると,物理的ハミルトニアンの自由度と可視ユニット自由度を同一視することで,多体波動関数をボルツマンマシンによって書き下すことができる.すなわちボルツマンマシンをユニット間結合定数などを変分パラメータとする変分波動関数とみなし,物理的ハミルトニアンのエネルギー期待値を最小化するように波動関数を最適化し(機械学習の言語ではこれが学習に対応),未知の基底状態を探索する.最初に量子多体系に適用されたのは,最も単純な構造をしている制限ボルツマンマシン(Restricted Boltzmann machine,略してRBM)である.RBMを用いた変分波動関数は量子スピン系に適用され,その精度の良さが実証された.この研究を皮切りにRBM波動関数の特性が以下のようにわかってきた.i)不可視ユニットの数を指数関数的に増やすとどんな波動関数も表現可能.ii)相互作用が短(長)距離だと,エンタングルメント・エントロピーが表面(体積)則を満たすこと.iii)従来の波動関数法を組み合わせるとフェルミオン系などにも適応可能となりより良い精度が達成できること.iv)隠れ層を一層増やした深層ボルツマンマシン(DBM)にすると関数表現能力が格段に向上する.その性質を用いると,DBMを用いて基底状態の波動関数を厳密に構築できること.ボルツマンマシン波動関数の研究は始まったばかりである.その有用性,より深い学理が近い将来明らかになるだろう.
7 0 0 0 OA 40年前を振り返って(<特集>近藤効果はめぐる : 近藤効果40周年)
- 著者
- 近藤 淳
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.85-87, 2005-02-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
40年前,私は電気抵抗極小の問題を解決しようと努力していた.その当時,電気抵抗極小に関する実験の状況はどんなであったか,理論屋からみて何が困難な点だったか,どんな実験事実が問題解決に重要だったか,ヒントは何だったか,などの経緯を述べてみたい.
7 0 0 0 OA コインに磁場をかけると,どうなる?
- 著者
- 池田 暁彦 松田 康弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.5, pp.318-320, 2018-05-05 (Released:2019-02-05)
- 参考文献数
- 10
話題―身近な現象の物理―コインに磁場をかけると,どうなる?
7 0 0 0 OA 液滴の形状について ―自由エネルギー極小の観点から
- 著者
- 谷林 衛 太田 治
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.3, pp.149-153, 2004-11-15 (Released:2018-06-24)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- 十倉 好紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.98-106, 1999-02-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 39
強相関効果を有する3d電子系遷移金属化合物(おもに酸化物)の金属-絶縁状態転移の特徴を, 伝導電子の輸送特性や伝導度スペクトルを中心として, その典型例について述べる. 特に, 磁気秩序, 電子軌道整列, 電荷整列, バンド幅制御およびフィリング制御によって崩壊する際の電荷ダイナミクスの臨界的挙動を俯瞰したい.
- 著者
- 冨田 博之
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.10, pp.817-818, 1985-10-05 (Released:2020-06-17)
7 0 0 0 OA AGT対応 : 予想から証明へ(解説)
- 著者
- 瀧 雅人
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.6-15, 2016-01-05 (Released:2017-04-22)
- 参考文献数
- 18
遠い未来の論文誌が手に入り,問いの数々への解答が垣間見れたならば,と夢想された事のある方は少なくないのではないだろうか?もちろんこのような事は不可能だが,双対性という不思議な性質は,しばしば「未来の知識を垣間見る」ような感覚を引き起こす.二つの異なる理論が同じ物理を記述しているとき,それらの間には「双対性」(duality)がある,という.ひとたび非自明な双対性が発見されれば,伝統的な手法の射程を大きくこえて理論を理解する事ができる.実際AdS/CFTに代表されるような様々な双対性の発見が,近年の弦理論の発展を牽引してきた.そして2009年,Alday,Gaiottoおよび立川は,超対称ゲージ理論に関する,全く新しいタイプの双対性を発見する.それが本稿の主題「AGT予想(AGT対応)」である.この予想における主役は4次元時空中のN=2超対称理論と,それに付随して定まる2次元の共形場理論であり,それらの分配関数と相関関数が厳密に一致するというのが,彼らの予想である.この数十年の研究により,どちらの理論も,量子効果と対称性による拘束が競合した結果,とても非自明な形で解けてしまう理論である事がわかっている.その両者が実は密接に関係しているという事実は,その物理の重要な「何か」がいまだに理解されていない事を示唆する.これまでにAGT予想に対する数多くの拡張やチェックがなされ,この予想は広汎な理論たちの間に対して成立している一般的な性質だと考えられている.特にGaiottoの発見したクラスSというグループに属した4次元理論であれば,AGT予想が成立している証拠がある.そこで次に理解すべきは,このような現象の起こる物理的なメカニズムである.完全では無いものの,有望なシナリオがいくつかある.その一つは,超弦理論の親玉であるM理論に起源を求める考え方である.M理論には,M5ブレインという6次元的な広がりを持つ高次元の膜的な物体が存在する.このブレインの広がりを2次元と4次元時空に分け,一方をつぶしてしまうと,残された空間にのみ住む理論が得られる.これによりゲージ理論と共形場理論が結びつくという説明法がそれである.M5ブレイン上に励起する物理的自由度に関してはよくわかっていない事が多く,この「導出」は完全ではないが,いくつもの傍証が見つかっている.また興味深い事に,AGT予想を理解する事でM5ブレインに関する理解が進展する可能性もある.AGT予想に関する数学的な理解にも進展がみられる.特にMaulikとOkounkovは,ゲージ理論側を記述するインスタントン解のモジュライ空間のコホモロジーに,2次元共形対称性の表現空間としての構造が入る事を示し,予想の一部の証明に成功した.また逆にAlbaらは,2次元共形対称性の表現の上に,インスタントンモジュライ空間と類似の組み合わせ論的な構造が隠れている事を示す事で,予想の一部を証明した.
7 0 0 0 ソーカル事件
- 著者
- 黒木 玄
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.2, pp.25-28, 1998
- 参考文献数
- 16
6 0 0 0 OA 重力波観測で見えてきた連星ブラックホールの多様性と形成過程
- 著者
- 衣川 智弥
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, pp.228-232, 2022-04-05 (Released:2022-04-05)
- 参考文献数
- 21
2015年9月14日,世界で初めて重力波が直接観測された.重力波の存在が直接証明されたことにより,今後の重力波研究は重力波を用いてどのように天体の物理を解明していくかという段階に切り替わりつつある.まさに重力波天文学の幕開けである.現在稼働している重力波観測器であるLIGO-Virgoによる連星ブラックホールの観測の報告は46件に及んでいる.そのうち,30太陽質量以上の“重い”質量帯のブラックホールの合体が35件も見つかり,最も重いものは合体後の質量が150太陽質量になるものすら見つかっている.なぜ30太陽質量以上のブラックホールを重いと表現したかというと,X線連星内のブラックホール候補天体の質量の見積もりは典型的に10太陽質量程度であり,重力波で観測される連星ブラックホールの質量も同程度だと予想されていたからである.LIGO-Virgoの解析結果によるとブラックホールの質量分布は10太陽質量にピークをもつ右肩下がりの冪関数に33.1+4.0-5.6太陽質量のガウス関数型ピークを加えた冪関数+ピーク分布が最も合っていると報告されている.重力波観測以前の予想とは異なり,幅広い質量のブラックホールが我々の宇宙には存在することが示されている.重力波で観測された幅広い質量のブラックホール形成を説明するため,大きく分けて次の三つの説がある.連星として生まれた恒星のペアが両方ともブラックホールとなり合体する孤立連星起源説,星団という恒星の密集した領域で生まれたブラックホールが重力相互作用でダイナミカルに連星を組み,合体を繰り返していく階層的合体起源説,ビッグバン由来の密度揺らぎの大きな領域が重力崩壊を起こしてできるブラックホールを起源とする原始ブラックホール起源説である.いまだこれらの説に決着はついていないが,孤立連星起源が主に寄与しているのではないかと注目されている.これは宇宙に生まれる大質量の星のほとんどが連星として生まれるため,後天的に連星を組む階層的合体起源などよりも合体率が高くなりやすいからである.孤立連星起源モデルでは,宇宙初期の天体ほど重いブラックホールになりやすい傾向があると示唆されている.また,重力波による連星合体までの時間は数億年から宇宙年齢以上と長いため,宇宙初期から現在までにできた多様な連星が現在になって合体し,重力波で観測される可能性がある.我々は初代星という宇宙最初期(赤方偏移10–50)にできた孤立連星起源の連星ブラックホールの合体が約30太陽質量のピークを形作り,初代星以降に生まれる種族I,II星の孤立連星によってできた連星ブラックホールが10太陽質量のピークを説明できることを連星進化計算により示している.これは宇宙初期から現在までの異なる時代に形成された多様なブラックホールが累積している可能性を示唆している.ただし,LIGO-Virgoによる重力波観測からわかる物理量は主にブラックホールの質量と自転角運動量(スピン)であるが,これらだけではまだ約30太陽質量のブラックホールが本当に初代星起源かは決着がついていない.2030年代の重力波観測の将来計画では赤方偏移10までの初代星起源連星ブラックホール合体が観測できると期待されている.連星ブラックホールの赤方偏移依存性を確かめられれば,初代星起源かどうかが白黒つけられる.初代星は宇宙初期の天体のため,直接観測が難しい.しかし,重力波により,ブラックホールという星が死んだ後に残る「化石」を調べられるようになった.初代星の「化石」として,連星ブラックホールから初代星の特徴を明らかにできるかもしれない.
6 0 0 0 OA 科学における創造性の心理学 [A. B. Migdal]
- 著者
- 土岐 博
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.5-7, 1988-01-05 (Released:2020-04-15)
6 0 0 0 OA Noise-Induced Order : 雑音によって生み出される秩序
- 著者
- 津田 一郎 松本 健司
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.203-207, 1985-03-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 4