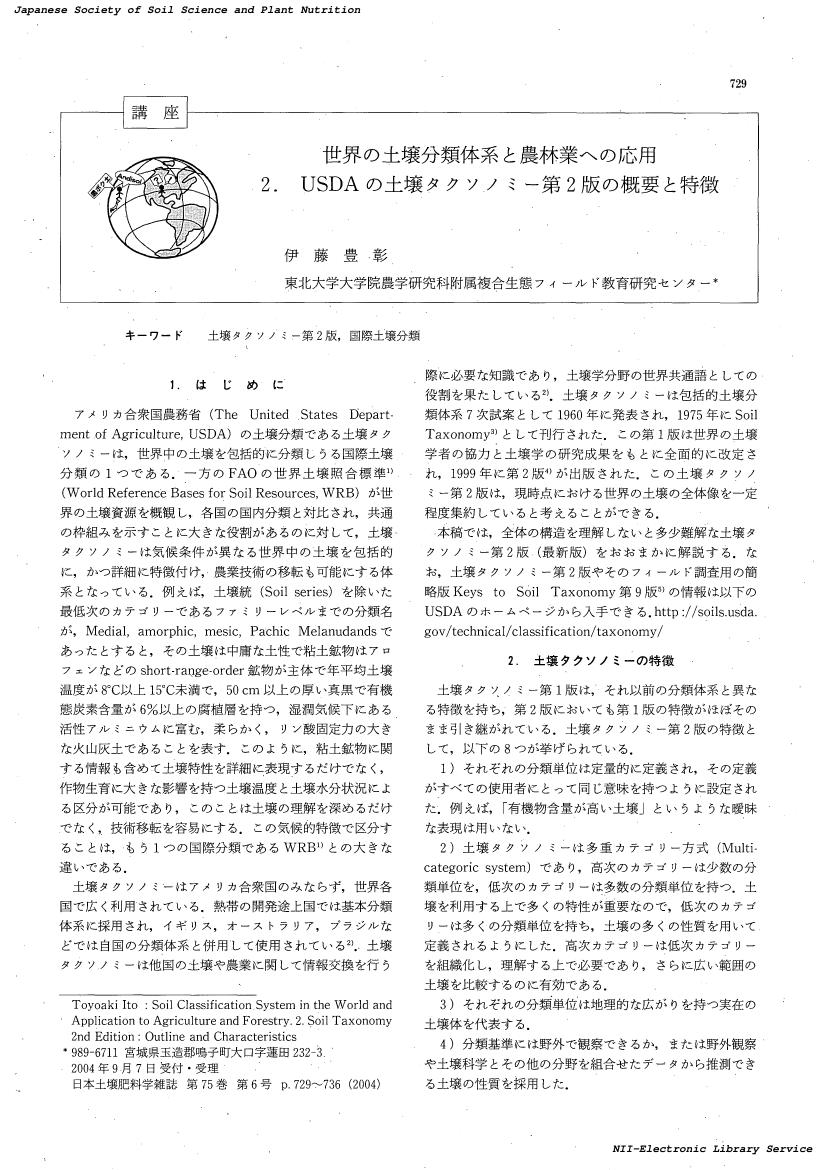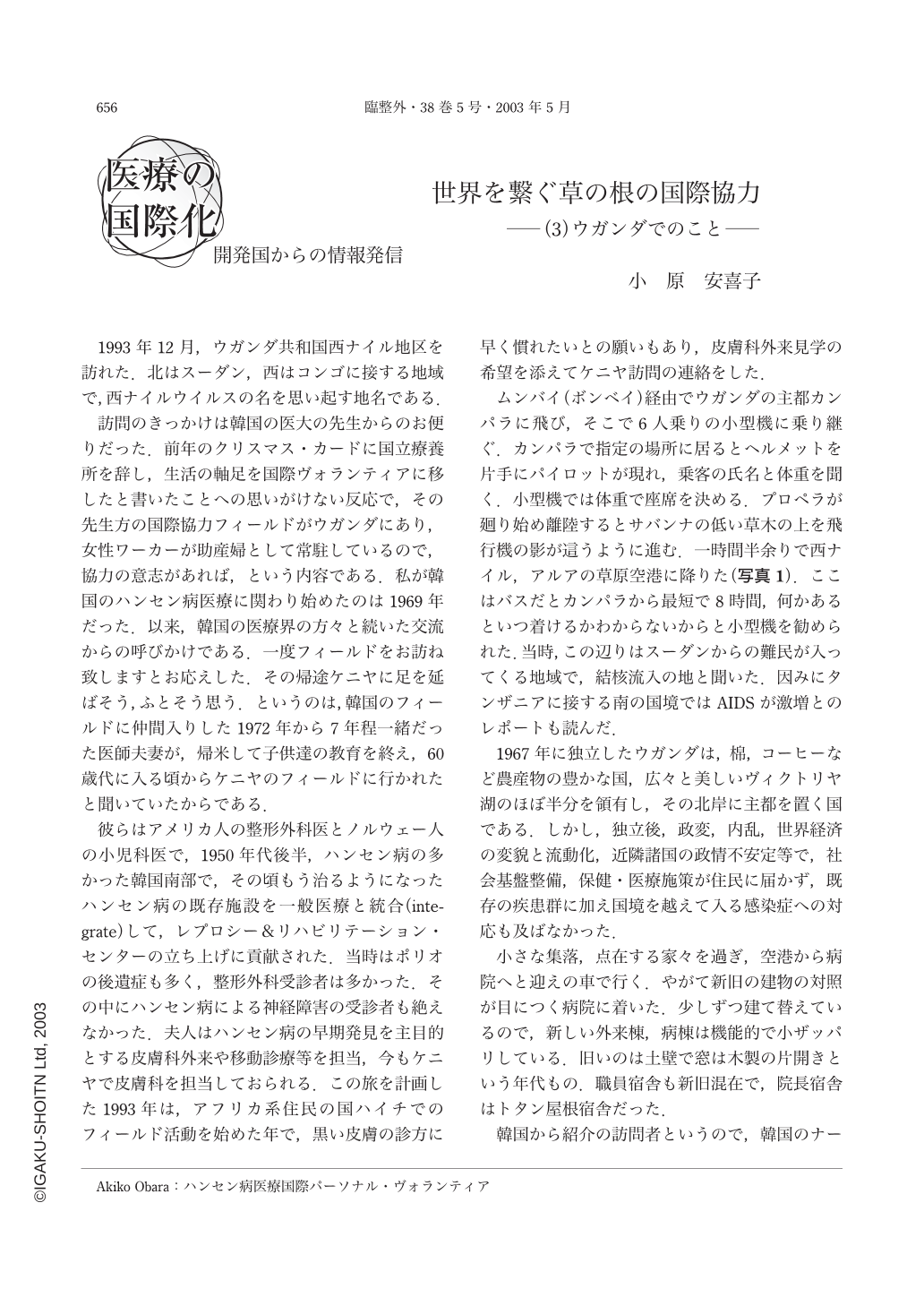1 0 0 0 日本絵画と日本画絵具
1 0 0 0 OA 2. USDAの土壌タクソノミー第2版の概要と特徴(世界の土壌分類体系と農林業への応用)
- 著者
- 伊藤 豊彰
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.6, pp.729-736, 2004-12-05 (Released:2017-06-28)
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA アルミニウムに対する呈色試薬としてのアルミノン(アウリントリカルボン酸)について
- 著者
- 濃野 益人
- 出版者
- 近畿大学理工学部応用化学科吉村研究室
- 雑誌
- 近畿アルミニウム表面処理研究会会誌 = Aluminum finishing society of Kinki (ISSN:02856689)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.21-23, 1968-01-01
1 0 0 0 OA 芸術における必然と偶然
- 著者
- 桑原 俊介
- 出版者
- 国士舘大学哲学会
- 雑誌
- 国士舘哲学 (ISSN:13432389)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, 2014-03
1 0 0 0 OA わが国のバブル経済期以降にみる女性労働者と女性管理者の就業意識とキャリア形成過程の変化
- 著者
- 幸田 浩文
- 出版者
- 東洋大学経営学部
- 雑誌
- 経営論集 = Journal of business administration. (ISSN:02866439)
- 巻号頁・発行日
- no.70, pp.29-49, 2007-11
1 0 0 0 OA 長野県内における小中学校用社会科副読本 : 作成状況と内容構成の分析を通して
- 著者
- 松本 康 篠﨑 正典
- 出版者
- 信州大学教育学部
- 雑誌
- 信州大学教育学部研究論集
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.219-229, 2020-03-31
1 0 0 0 多元論の立場から--「生命科学と人間の会議」総括意見
- 著者
- Hampshire Stuart
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 世界 (ISSN:05824532)
- 巻号頁・発行日
- no.463, pp.p283-289, 1984-06
1 0 0 0 OA 効率的な利水操作と下流河道の生態系保全のためのダム貯水池の低水管理
- 著者
- 渡邉 浩 虫明 功臣
- 出版者
- 水文・水資源学会
- 雑誌
- 水文・水資源学会誌 (ISSN:09151389)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.108-118, 2006 (Released:2006-05-12)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2 1
我が国の多目的ダムの利水操作は, 流量低減時に過少なダム貯留や過大な用水補給が行われ, 効率的なものとなっていない.その理由は利水操作の判断基準が下流基準点における未来事象の流量であるのに, この流量を予め把握して操作を行うことが無いからである. もし, ダム貯留や用水補給が適切に行われれば, 洪水期が終了した後の貯水量の回復を現実の操作に比べ格段に早めることができることが判った. また, ダム建設後ダム下流では, 生態系の保全に重要な非洪水期の中小出水の流下が見られなくなっている. これは中小出水の流下の重要性が認識されず, 実害の無い範囲で最大限の洪水流下を図ろうとすることが無いからである. ダム操作によって低減している中小出水の最大流量を自然状態まで回復できれば, 下流基準点においても最大で2倍の流量になることが判った. 以上の課題を解決するため, 再現した自然流量の時系列から得られる予測流量を正常流量と比較しながら利水操作を行い, また下流河道が安全である限り流量増が続いてもダム貯留をしない低水管理法を提案した. これを基に現実のダム操作の修正を試算し, この方法が有効かつ実現可能であることを検証した.
- 著者
- 近内 亜紀子 浅地 哲夫 能美 仁 小田野 直光
- 出版者
- 火薬学会
- 雑誌
- Science and Technology of Energetic Materials : journal of the Japan Explosive Society (ISSN:13479466)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.3, pp.55-61, 2009-08-31
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 OA 核四重極共鳴を用いた爆発物探知技術の開発(所外発表論文等概要)
- 著者
- 近内,亜紀子
- 出版者
- 海上技術安全研究所
- 雑誌
- 海上技術安全研究所報告
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.4, 2008-03-29
1 0 0 0 核スピンを利用したセキュリティ技術
- 著者
- 赤羽 英夫 糸﨑 秀夫
- 出版者
- 生産技術振興協会
- 雑誌
- 生産と技術 (ISSN:03872211)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.30-35, 2012
1 0 0 0 核四重極共鳴を用いた爆発物探知技術の開発(所外発表論文等概要)
- 著者
- 近内 亜紀子
- 出版者
- 海上技術安全研究所
- 雑誌
- 海上技術安全研究所報告 (ISSN:13465066)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.4, 2008
- 著者
- 山根 典子
- 出版者
- 日本音声学会
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.29-40, 1999-04-30 (Released:2017-08-31)
This article gives an insight into the interface between diachronic grammar and phonology, focusing on the sC clusters in syllable coda position. They may be uniformly assumed to consist of a complex segment, but the historical study of LME and ModE here shows that they behave differently with respect to phonological processes, depending on the place of articulation of the stop consonants. Based on observations of the clusters' relation to MEOSL and GVS, I thus claim that OT gives a principled account for their asymmetry and captures the predictability of diachronic change in a more explicit and natural way than earlier models.
1 0 0 0 OA シンガポール植物園と郡場寛先生(歴史、人物)
1 0 0 0 IR シンガポール植物園と郡場寛先生(歴史、人物)
- 著者
- 金澤 貴之
- 出版者
- 障害学会
- 雑誌
- 障害学研究 (ISSN:18825265)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.63-88, 2007
1 0 0 0 OA 産婦人科からみた心療内科との協働
- 著者
- 小川 真里子 髙松 潔
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.5, pp.455-461, 2019 (Released:2019-07-01)
- 参考文献数
- 26
心療内科医と産婦人科医の双方の対応を要する疾患は多い. また, 心身症患者が産婦人科を初診受診することも日常的にみられる. 例えば, 摂食障害の女性は, しばしば無月経を主訴に産婦人科を最初に受診する. 月経前症候群は, 月経前である黄体期にさまざまな症状をきたすが, 心理・社会的因子が背景にあることも少なくないため, 心身医学的アプローチが有効である.しかし, 実際の臨床現場で心療内科と産婦人科が密に連携し協働している場面はまだまだ多いとはいえない. 考えられる問題点としては, まず, 産婦人科医における心身医学的知識の欠如, 次に, 患者の心療内科受診へのハードル, そして, 心療内科と産婦人科が併設されている病院は少ないため, 物理的に連携することが難しい点などが挙げられる.そこで本稿では, 心身症患者への産婦人科的対応について述べ, 今後どのように協働して治療にあたっていくかを考察した.
1 0 0 0 世界を繋ぐ草の根の国際協力―(3)ウガンダでのこと
1993年12月,ウガンダ共和国西ナイル地区を訪れた.北はスーダン,西はコンゴに接する地域で,西ナイルウイルスの名を思い起す地名である. 訪問のきっかけは韓国の医大の先生からのお便りだった.前年のクリスマス・カードに国立療養所を辞し,生活の軸足を国際ヴォランティアに移したと書いたことへの思いがけない反応で,その先生方の国際協力フィールドがウガンダにあり,女性ワーカーが助産婦として常駐しているので,協力の意志があれば,という内容である.私が韓国のハンセン病医療に関わり始めたのは1969年だった.以来,韓国の医療界の方々と続いた交流からの呼びかけである.一度フィールドをお訪ね致しますとお応えした.その帰途ケニヤに足を延ばそう,ふとそう思う.というのは,韓国のフィールドに仲間入りした1972年から7年程一緒だった医師夫妻が,帰米して子供達の教育を終え,60歳代に入る頃からケニヤのフィールドに行かれたと聞いていたからである.
- 著者
- 平野,洋一
- 出版者
- プラズマ・核融合学会
- 雑誌
- プラズマ・核融合学会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.6, 2011-06-25
1 0 0 0 OA 逆磁場ピンチにおける核融合研究の現状と長期的展望
- 著者
- 政宗,貞男
- 出版者
- プラズマ・核融合学会
- 雑誌
- プラズマ・核融合学会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.12, 2000-12-25
The Reversed Field Pinch (RFP) has been believed to be dominated by anomalous transport due to strong magnetic fluctuations as with other low safety factor systems. However, for the last decade, RFP research has achieved significant progress in understanding its confinement physics. As a result, suppresion of the dynamo-induced fluctuations by controlling the current density profile has realized remarkable improvements in energy confinement time. Issues for near-term RFP research on the part of fusion programs includes active plasma control for confimenent improvement, stable operation for durations far exceeding the field penetration time of the conducting shell, heat and particle control, and possible optimization of the RFP configuration. Long term perspectives are also discussed.