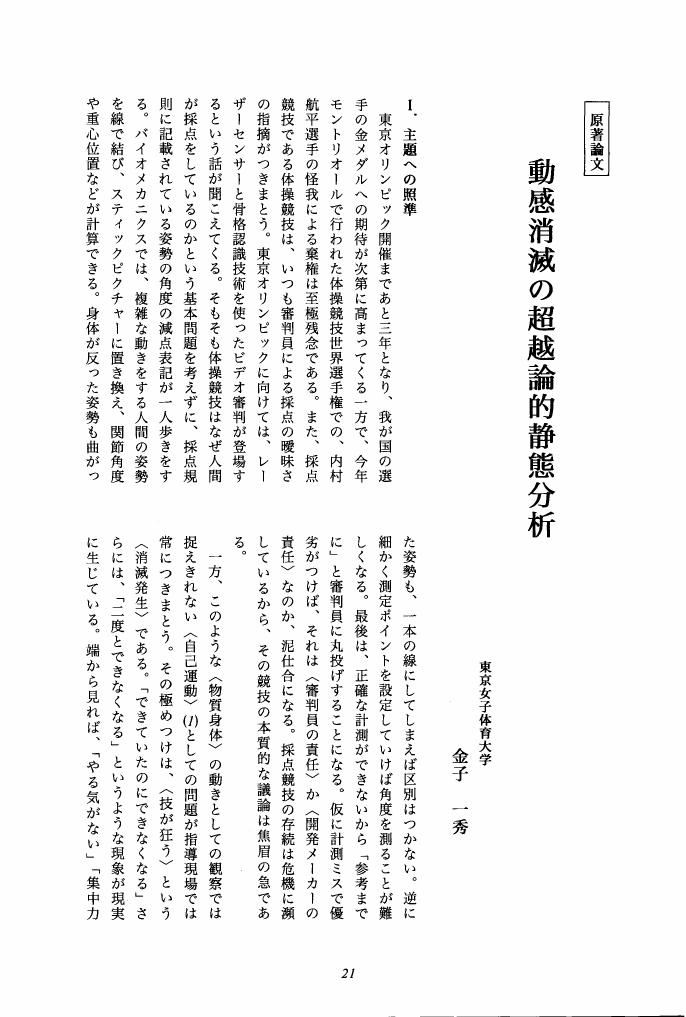1 0 0 0 OA 動感消滅の超越論的静態分析
- 著者
- 金子 一秀
- 出版者
- 運動伝承研究会
- 雑誌
- 伝承 (ISSN:24353175)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.21-40, 2017 (Released:2019-12-16)
1 0 0 0 OA 神は存在するか : 神の存在証明
- 著者
- 本多 峰子 ホンダ ミネコ Mineko Honda
- 雑誌
- 二松学舎大学國際政経論集
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.107-121, 2007-03
1 0 0 0 九州国際大学法学論集
1 0 0 0 OA 国際刑事裁判所規程検討会議の成果及び今後の課題
- 著者
- 竹村 仁美 タケムラ ヒトミ Hitomi Takemura
- 雑誌
- 九州国際大学法学論集
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.1-42, 2010-12
1 0 0 0 IR 国際刑事裁判所規程検討会議の成果及び今後の課題
- 著者
- 竹村 仁美
- 出版者
- 九州国際大学
- 雑誌
- 九州国際大学法学論集 (ISSN:1341061X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.1-42, 2010-12
1 0 0 0 OA 中国ムスリムに対するキリスト教宣教
- 著者
- 松本 ますみ
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.147-171, 2005-09-30 (Released:2018-03-30)
中国ムスリムに対するキリスト教宣教は、19-20世紀半ば、福音主義宣教会の中では大きな課題となった。中国のムスリム人口は当時3000万人とも言われ、インドについで第2位といわれた。植民地主義の時代、他地域のムスリムの大多数が西欧の支配下、すなわち、「キリスト教徒の支配者」の下にあったが、「異教徒」の政権下の中国ムスリムは、福音から最も遠いという点において「問題」であると考えられた。植民地主義がピークに達した1910年のエジンバラ世界宣教会議以降、中国ムスリムに対する宣教も本格化、さまざまなパンフレット、宣伝文書、ポスターの作成が行なわれた。それに対し、ムスリム側も、論駁書、啓蒙書の発行、学校設立などイスラーム復興に着手して対抗を図った。ただ、両者の対立が深刻化しなかったのは、多文化多宗教の共存を旨とする中国ムスリム側の伝統による所が大きい。また、宣教師にもイスラームに深い共感を示した者が存在したことも大きい。
1 0 0 0 宿命論について
- 著者
- 野矢 茂樹
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.47-58, 2004
Fatalism or logical determinism says that the future is determined on a very logical ground. In this paper, examining the fatalist argument critically, I am going to show how we can avoid the fatalist thesis. Aristotle discussed this problem and came to the conclusion that some statements about the future are neither true nor false. Following his suggestion, I farther claim that the future does not exist. That is the reason why any proper name included in a statement about the future has no referent. Therefore, as Aristotle said, statements about the future have no truth value. In the latter half of this paper, I will consider some problems with my claim what does a statement about the future mean and how is the past related to the present?
1 0 0 0 OA 小学校中学校の農繁休暇の展開と地域性 : 松本盆地を事例として
- 著者
- 斎藤 功 Saitou Isao
- 出版者
- 筑波大学地球科学系人文地理学研究グループ
- 雑誌
- 地域調査報告 (ISSN:02894491)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.9-19, 1995-03
1 0 0 0 ふたゝび「継体欽明朝の内乱」について
- 著者
- 林屋 辰三郎
- 出版者
- 青木書店
- 雑誌
- 歴史学研究 (ISSN:03869237)
- 巻号頁・発行日
- no.164, pp.50-52, 1953-04
1 0 0 0 OA "やさしさ"の脱構築? 大平健『やさしさの精神病理』を読む
- 著者
- 新井 克弥 Katsuya ARAI
- 雑誌
- 宮崎公立大学人文学部紀要 = Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.1-15, 2004-03-20
大平健著『やさしさの精神病理』(岩波新書、95)のテクスト・クリティーク。精神科医、大平は、患者との対応の中から、70年代以降、新しい意味を持ったやさしさ=ヤサシサが出現したと指摘する。70年代、やさしさはモノや人個々の性質をあらわす用語から、他者との連帯を志向することばとなったのである。当初、それは、ことばを介した他者介入型の「やさしさ」として出現するが、80年代に入り、”沈黙”を原則とする相互非介入型の”やさしさ”へと転じていく。すなわち、相手の気持ちを察し、相手と同じ気持ちになってメッセージを共有するスタイルから、相手の領域に入り込まないように気づかい、空間を共有するスタイルへの変容である。本稿ではこのような大平の指摘する新しい”やさしさ”を、情報化社会・グローバル化社会におけるコミュニケーションの新しいスタイルと捉え、その可能性について、中野収のカプセル人間論、およびN.ルーマンのダブル・コンティンジェンシー理論を援用しながら考察。その社会的適応性を評価し、解り合えないことを了解し合うコミュニケーション、および共鳴・共振だけで結ばれるコミュニケーションの重要性を説いた。
1 0 0 0 OA 芥川龍之介「湖南の扇」の虚と実 : 魯迅「薬」をも視野に入れて
- 著者
- 単 援朝
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.111-124, 2002-02-28
本稿は芥川龍之介「湖南の扇」をめぐって、作品の構築における体験と虚構化の働きを検証しつつ、玉蘭の物語を中心に作品の成立と方法を探り、さらに魯迅の「薬」との対比を通じて作品の位相を考えるものである。結論としては、「湖南の扇」は、作品世界の構築に作者の中国旅行の体験や見聞が生かされていつつも、基本的に体験の再構成を含む虚構化の方法による小説にほかならない。作品のモチーフは冒頭の命題というよりクライマックスのシーンにあり、作品世界は「美しい歯にビスケットの一片」という、作者の原光景ともいえる構図を原点に形成され、虚構の「事件」が体験的現実として描かれているところに作品の方法があるが、作品の「出来損なひ」はこの方法に起因するものであるといわざるをえない。そして、魯迅「薬」との対比を通じてみると、「迷信」として批判されるはずの人血饅頭の話をロマンチックな物語、「情熱の女」の神話に作り替えられたところに、芥川のロマンチシズムへの志向と「支那」的生命力に寄せる憧れが見て取れる。
1 0 0 0 OA プログラムの静的特性を楽曲で表現する可聴化システムの開発とプログラミング支援への応用
- 著者
- 六沢 一昭 渡邉 彰吾
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 巻号頁・発行日
- pp.4Rin117, 2019 (Released:2019-06-01)
本論文は, プログラムの静的特性を楽曲で表現する可聴化システムの開発とプログラミング支援への応用について述べたものである. ソフトウェアの品質向上を図るためソースコードの静的解析が行われている. 様々な静的解析ツールによる解析結果は画面に出力される(可視化). そこで本研究では音への出力(可聴化)を試みる. 可聴化することでマルチタスクや視覚障害者支援ツールとしての利用が期待できる. 単なる音の羅列や同じリズムパターンによる可聴化は飽きやすいといった問題がある. そこで本研究では自然な楽曲による可聴化を試みる. 自然な楽曲にすることで飽きやすさの改善が期待できる. 本システムはプログラムの1行を1小節として楽曲を生成する. ネストの変化や制御構造, 1行の複雑さなどからコード進行や伴奏, リズムなどを決定する. ソースコードの静的解析はコーディング規約違反に着目する. 本研究ではコーディング規約違反箇所を不協和音で表現する. 学生20名に本可聴化システムを用いて規約違反箇所の検出及び改修を行ってもらった. その結果, 本システムによって検出が容易となったため, 静的解析結果の可聴化の有効性が示された.
1 0 0 0 OA 陸上競技部の合宿練習に関する考察
- 著者
- 塘添 敏文
- 出版者
- 亜細亜大学教養部
- 雑誌
- 亜細亜大学教養部紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.138-122, 1969
1 0 0 0 OA 佐賀県史蹟名勝天然紀念物調査報告
- 著者
- 佐賀県史蹟名勝天然記念物調査会 編
- 出版者
- 佐賀県
- 巻号頁・発行日
- vol.第2輯, 1934
1 0 0 0 巌本善治の小説-その男女観・恋愛観・結婚観の変遷に考えること
- 著者
- 石井 妙子
- 出版者
- 白百合女子大学
- 雑誌
- 白百合児童文化 (ISSN:09163344)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.110-131, 1994-07
1 0 0 0 OA 食品の保温温度が食塩の拡散に及ぼす影響
煮物の味は冷めるときにしみ込むという言い伝えを検証するために,ジャガイモ,ダイコン,コンニャクを2cm角の立方体に成形し,1%食塩水中で食べられる軟らかさまで加熱後,0, 30, 50, 80, 95℃で90分まで保温し,30分後と90分後に外層部と内層部の食塩濃度を測定した。温度降下条件を各設定温度に試料を加熱した鍋のまま移す緩慢条件と,氷水に鍋をつけて設定温度まで下げた後保温する急速条件の2種とした。いずれの条件でも,保温温度が高いほど,食塩の内部への拡散は犬さく,このことは官能評価でも確認された。これらの結果から冷めるときに味がしみ込むということは見いだせなかった。ソレ効果についても検討したが,ソレ効果で煮物の調味料の拡散を説明することはできないことがわかった。冷めるときに味がしみ込むというのは,冷める時間に調味料が内部へ拡散することを言っているのではないかと考えられる。
- 著者
- 西田 善行
- 出版者
- 法政大学大学院
- 雑誌
- 法政大学大学院紀要 (ISSN:03872610)
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.79-93, 2005
- 著者
- Hiroki Oohashi Sadao Hiroya Takemi Mochida
- 出版者
- ACOUSTICAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- Acoustical Science and Technology (ISSN:13463969)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.6, pp.478-488, 2015 (Released:2015-11-01)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1 4
This paper presents a real-time robust formant tracking system for speech using a real-time phase equalization-based autoregressive exogenous model (PEAR) with electroglottography (EGG). Although linear predictive coding (LPC) analysis is a popular method for estimating formant frequencies, it is known that the estimation accuracy for speech with high fundamental frequency F0 would be degraded since the harmonic structure of the glottal source spectrum deviates more from the Gaussian noise assumption in LPC as its F0 increases. In contrast, PEAR, which employs phase equalization and LPC with an impulse train as the glottal source signals, estimates formant frequencies robustly even for speech with high F0. However, PEAR requires higher computational complexity than LPC. In this study, to reduce this computational complexity, a novel formulation of PEAR was derived, which enabled us to implement PEAR for a real-time robust formant tracking system. In addition, since PEAR requires timings of glottal closures, a stable detection method using EGG was devised. We developed the real-time system on a digital signal processor and showed that, for both the synthesized and natural vowels, the proposed method can estimate formant frequencies more robustly than LPC against a wider range of F0.
1 0 0 0 OA 漢晋時期における名謁・名刺についての考察
- 著者
- 呂 静 程 博麗
- 出版者
- 東京大学東洋文化研究所
- 雑誌
- 東洋文化研究所紀要 (ISSN:05638089)
- 巻号頁・発行日
- vol.160, pp.536-564, 2011-12-22
本文以20世紀70年代以來中國江蘇、江西、安徽、湖北、湖南等地所出土漢晉時期謁、刺簡牘實物為中心, 結合相關歷史文獻的記載, 對這一時期的名謁和名刺進行了嘗試性地探討。作為漢晉時期極其流行的社交工具, 謁和刺在形制大小、內容構成、用法特徵以及具體的使用場景等方面, 均存在著很大的區別 : 名謁流行於秦末至三國時期, 其形制規整、書寫規範、內容詳細的特點, 凸顯其在使用過程中的莊重、權貴和禮儀性特徵, 因此在官場社交中頗為流行 ; 名刺至少在東漢時期已經很常見, 這時的刺更為狹長輕巧, 內容趨於簡化和固定, 並且大量出現拜謁者的字, 反映了名刺使用中更加注重反映持有人的“自然”屬性和“私人”屬性, 使用的範圍也從官僚階層擴展到社會更下層的士人、庶民。這種下移的結果是人際關係在更為廣泛和基層的社會群體之間得到了實現, 從而使得士人、庶民階層登上社交政治舞臺, 推動更廣泛的社會變革。
1 0 0 0 OA 漢晋時期における名謁・名刺についての考察 : 近年出土謁刺の分析をめぐって
- 著者
- 呂 静 程 博麗
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- Jiangnan Culture and Japan : A Rediscovery of Resources and Human Exchange
- 巻号頁・発行日
- pp.125-137, 2012-03-23
江南文化と日本 : 資料・人的交流の再発掘, 復旦大学(上海), 2011年5月27日-29日