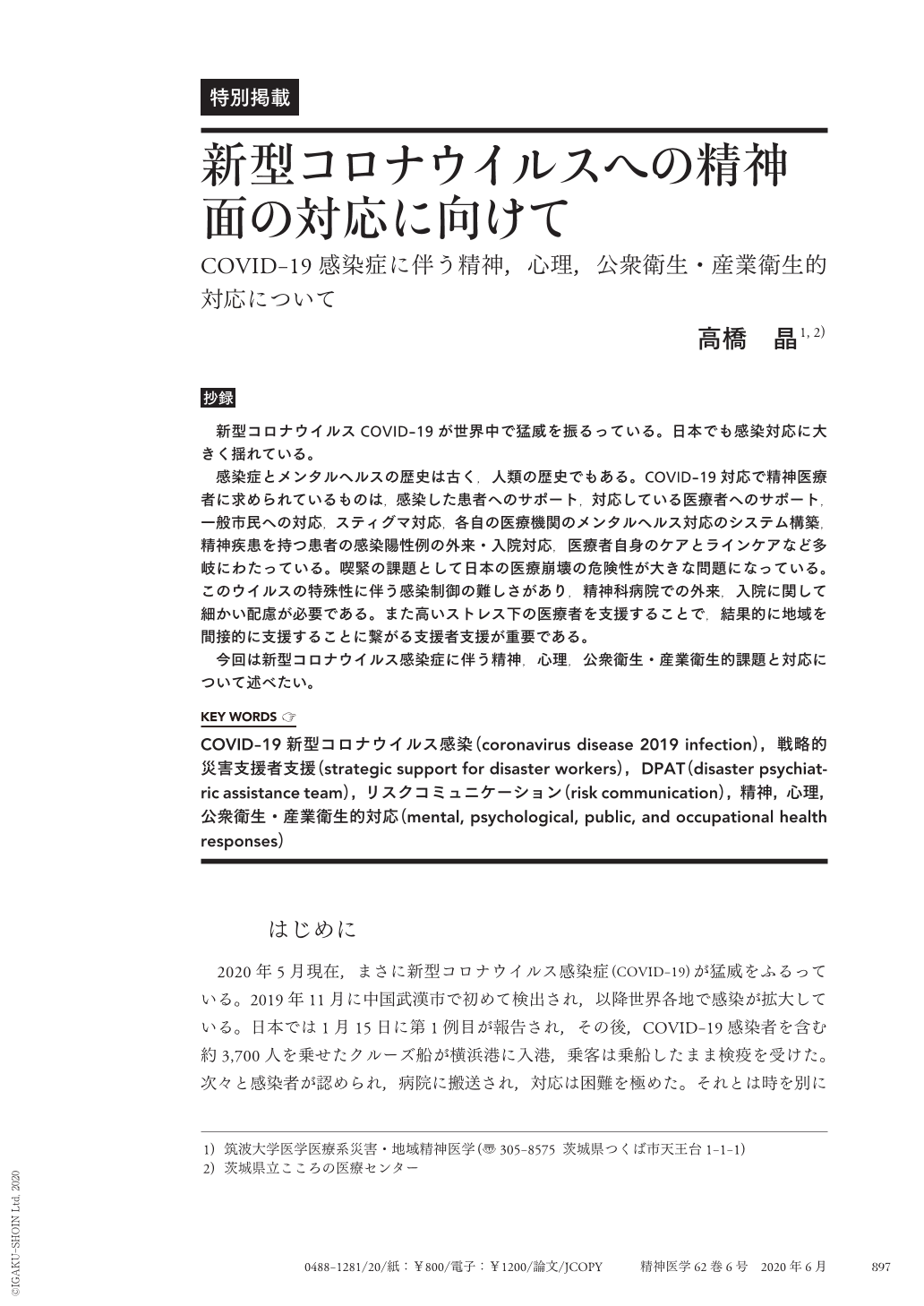抄録 新型コロナウイルスCOVID-19が世界中で猛威を振るっている。日本でも感染対応に大きく揺れている。 感染症とメンタルヘルスの歴史は古く,人類の歴史でもある。COVID-19対応で精神医療者に求められているものは,感染した患者へのサポート,対応している医療者へのサポート,一般市民への対応,スティグマ対応,各自の医療機関のメンタルヘルス対応のシステム構築,精神疾患を持つ患者の感染陽性例の外来・入院対応,医療者自身のケアとラインケアなど多岐にわたっている。喫緊の課題として日本の医療崩壊の危険性が大きな問題になっている。このウイルスの特殊性に伴う感染制御の難しさがあり,精神科病院での外来,入院に関して細かい配慮が必要である。また高いストレス下の医療者を支援することで,結果的に地域を間接的に支援することに繋がる支援者支援が重要である。 今回は新型コロナウイルス感染症に伴う精神,心理,公衆衛生・産業衛生的課題と対応について述べたい。
1 0 0 0 IR 管絃にのせた作中和歌--『うつほ』『狭衣』から中世王朝物語へ
- 著者
- 岡田 ひろみ Hiromi Okada
- 出版者
- 共立女子大学
- 雑誌
- 共立女子大学文芸学部紀要 (ISSN:03883620)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.27-45, 2011-01
1 0 0 0 OA 日蓮宗聖典
- 著者
- 柴田一能, 山田一英 編
- 出版者
- 無我山房
- 巻号頁・発行日
- 1912
1 0 0 0 ビタミンB_1反応性高乳酸血症の病因解析と治療法確立
先天性高乳酸血症は有機酸代謝異常症の中で最も頻度の高い疾患であり、本症の確定診断のためにはピルビン酸代謝関連酵素活性の測定が不可欠である。先天性高乳酸血症の自験例および酵素診断を依頼された他施設例の中で、ビタミンB_1、大量投与により臨床症状の改善と血中および髄液中の乳酸値の低下をきたした13症例の培養細胞について、ピルビン酸脱水素酵素複合体(PDHC)活性の詳細な検討を行った。すなわち反応液中のTPP濃度を一般に用いられる高濃度から組織内の生理的濃度まで変化させてPDHC活性を測定した。そのTPP濃度とPDHC活性との曲線によりPDHCのTPPに対する親和性の低下、すなわちビタミンB_1、反応性の有無を判定した。その結果13例中7例をビタミンB_1反応性PDHC異常症と診断しえた。ビタミンB_1反応性PDHC異常症例はビタミンB_1反応性高乳酸血症例の半数を占めており、本症の頻度が高いことが判明した。さらにそのうち3例の遺伝子解析を行い、3例ともE_1α遺伝子のアミノ酸置換を伴う点変異であった。すなわち2例はエクソン3の変異であり、1例は44番目のヒスチジンがアルギニンに、他の1例は88番目のグリシンがセリンにアミノ酸置換していた。3例目はエクソン8の263番目のアルギニンがグリシンに変異していた。これらの変異に対してはPCRと制限酵素を用いた遺伝子診断が可能であった。これらの方法により、2例は突然変異であり、また1例は母親由来の変異遺伝子によることが判明した。PDHCのTPPに対する親和性が正常であったビタミンB_1反応性高乳酸血症の6例では、PDHCと同様にTPPを補酵素とするαケトグルタール酸脱水素酵素複合体および分岐鎖ケト酸脱水素酵素複合体の異常である可能性があり、今後これらの検討が必要である。
1 0 0 0 OA 幼児の向社会性と親の共感経験との関連
- 著者
- 首藤 敏元
- 出版者
- 埼玉大学教育学部
- 雑誌
- 埼玉大学紀要. 教育学部. 教育科学 / 埼玉大学教育学部 [編] = Journal of Saitama University. Faculty of Education. Science of education (ISSN:03879321)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.121-131, 2006
本研究は、子の気持ちに対する母親と父親の共感経験、および夫婦問での互いの気持ちに対する共感経験を測定した。そして、幼児期の子どもの向社会性として、物語場面での共感反応、および告白遊び場面での向社会的/攻撃的行動を観察し、荷者の関連性を検討した。その結果、幼児の向社会性は親の共感経験と部分的に関連していた。その関連牲は、子どもの性別と共感経験の側面によって異なり、複雑であることが示された。一方、夫婦間の共感経験が幼児の向社会性と有意に相関しており、家族関係のダイナミズムや家族の発達の相互性に関わる知見が見出された。
1 0 0 0 通信制高等学校における生徒の精神健康
- 著者
- 平部 正樹 小林 寛子 藤後 悦子 藤本 昌樹
- 出版者
- 学校法人 三幸学園 東京未来大学
- 雑誌
- 東京未来大学研究紀要 (ISSN:18825273)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.167-178, 2016
<p><b> </b> 本研究では通信制高校の生徒を対象とし、入学前・後の心の問題に関わる体験や、精神健康の実態把握のための調査を行った。対象は、私立の広域通信制高校2 キャンパスに所属する全生徒1,086 人であった。調査票については、基本項目に、通信制高校入学前の体験や通信制高校入学理由が含まれていた。 精神健康関連項目として、現在の悩みに加えて、K6 を用いて精神健康度を尋ねた。結果として、入学前には友人関係や不登校、親との問題を経験した生徒が多かった。通信制高校入学の主な理由については、学力や学習上の理由や、前校での不適応となっていた。現在の悩みについては、将来の進路が高かった。精神健康については、K6 による比較で、日本の同年代の精神健康度よりも低くなっていた。通信制高校生徒の精神健康の維持・向上のためには、それまでの学校体験や、生活背景を考え対応していくことが必要であることが示唆された。</p>
1 0 0 0 OA 手段としての古典学習の検討に向けて ―古典学習現状に関する調査と 2 つの視座をもとに―
- 著者
- 大谷 維吹
- 出版者
- 東京学芸大学国語科教育学研究室
- 雑誌
- 学芸国語教育研究 (ISSN:09139362)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.2-19, 2018 (Released:2019-10-07)
1 0 0 0 OA 高填料充填紙について
- 著者
- 小泉 正弘
- 出版者
- JAPAN TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY
- 雑誌
- 紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.11, pp.1022-1028, 1988-11-01 (Released:2009-11-16)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- Masahiko Ikeuchi
- 出版者
- Applied Microbiology, Molecular and Cellular Biosciences Research Foundation
- 雑誌
- The Journal of General and Applied Microbiology (ISSN:00221260)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.51-52, 2020 (Released:2020-06-17)
- 参考文献数
- 14
1 0 0 0 IR 『山槐記』に見られる百塔参りの一考察
- 著者
- 林 蕙如
- 出版者
- 岡山大学大学院社会文化科学研究科
- 雑誌
- 岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要 (ISSN:18811671)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.137-148, 2012-03
1 0 0 0 OA 予算制約と時間制約,労働と効用に関する一考察
- 著者
- 河野 敏鑑
- 出版者
- 専修大学情報科学研究所
- 雑誌
- 情報科学研究 (ISSN:02866048)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.1-13, 2019-03-01
Along with the aging of society and the progress of information technology, the time people have for the lifetime is increasing. In addition, values have also been transformed, and more people are engaged in production activities (labor) without financial rewards such as development of freeware. We investigate labor supply function under the assumption that labor utility is positive and that consuming goods needs consuming time. In this paper, we show that the market equilibrium is not Pareto efficient under the condition that persons to have disutility for labor and persons to have utility for labor coexist. Furthermore, we show that labor supply function decreases in wage rate when time constraint has meaning. This result maintains whether labor has utility or disutility. Therefore, the well-acquainted assumption that labor supply function increases in wage rate depends on the isolated condition that we ignore the fact that consuming goods needs consuming time and time constraint.
1 0 0 0 OA 国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書
1 0 0 0 OA ニューナショナル第三リードル独案内
1 0 0 0 OA ニューナショナル第四リードル直訳
1 0 0 0 OA 椎尾弁匡師と共生思想
- 著者
- 神谷 正義
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.269-273, 2000-12-20 (Released:2010-03-09)
- 著者
- 森 茂暁
- 出版者
- 青木書店
- 雑誌
- 歴史学研究 (ISSN:03869237)
- 巻号頁・発行日
- no.861, pp.33-35, 2009-12
- 著者
- 高島 彬
- 出版者
- 金沢大学大学院人間社会環境研究科 = Graduate School of Human and Socio-Enviromental Studies Kanazawa University
- 雑誌
- 人間社会環境研究 = Human and socio-environmental studies (ISSN:18815545)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.77-89, 2015-09-28
This article examines the grammaticalization of 'te-aru' constructions in Japanese. In Japanese, 'tearu' constructions can be divided into two subtypes, exemplified in (l-2). The first type (1) is the construction where the patient is encoded by the nominative maker ga. The second type (2) is the one where the patient is encoded by the accusative marker wo. (l) 'X-ga te-aru' construction (2) 'X-wo te-aru' construction Many linguists pointed out that the difference between ga and wo in the constructions affects not only the syntactic aspect but also the semantic one. There are two types of analysis of the different cases in 'te-aru' constructions. In the first type, the constructions are considered to be passive-like sentences (cf. Soejima 2007, Suda 2010). In the second type, constructions are considered to be causative alternations (i.e., the opposition between the intransitive construction is 'X-ga te-aru' and the transitive one is 'X-wo te-aru' ). I will take the latter position one step further and show that it can be analyzed as a matter of grammatical development. In this paper, I will analyze differences in these constructional types as grammatical development from the 'X-ga te-aru' construction into the 'X-wo te-aru' construction. The framework I use to tackle this problem is "specification," which Kuteva (2001) showed as a mechanism of semantic change in grammaticalization. I conclude that specifying the information ( especially, the information of the agent in the event) led to the grammatical development of 'te-aru' constructions.