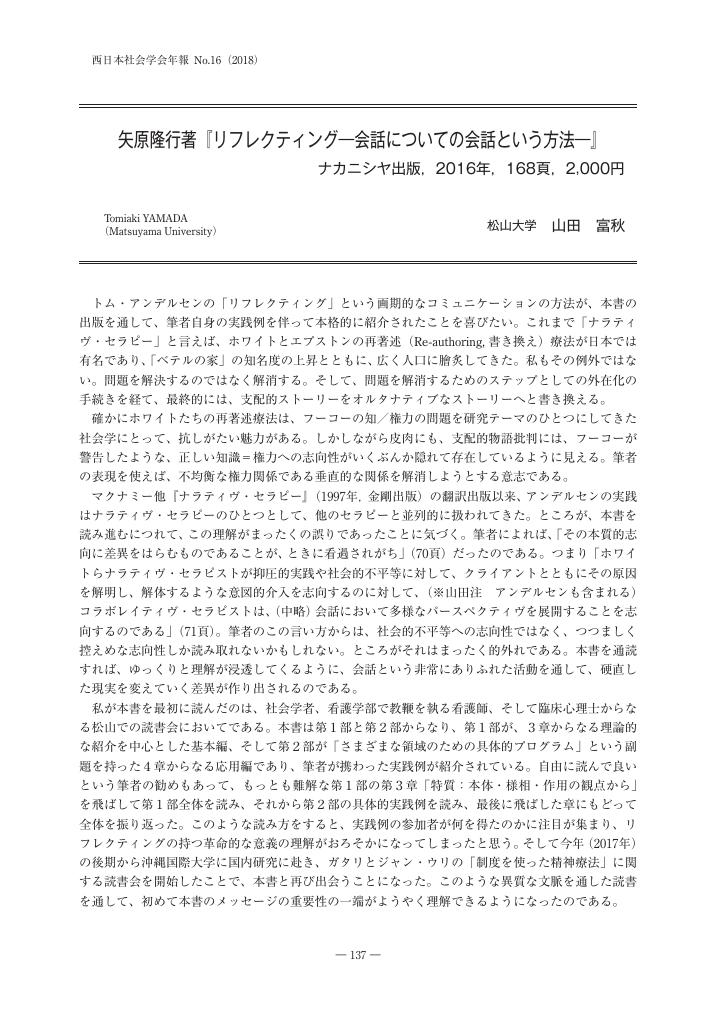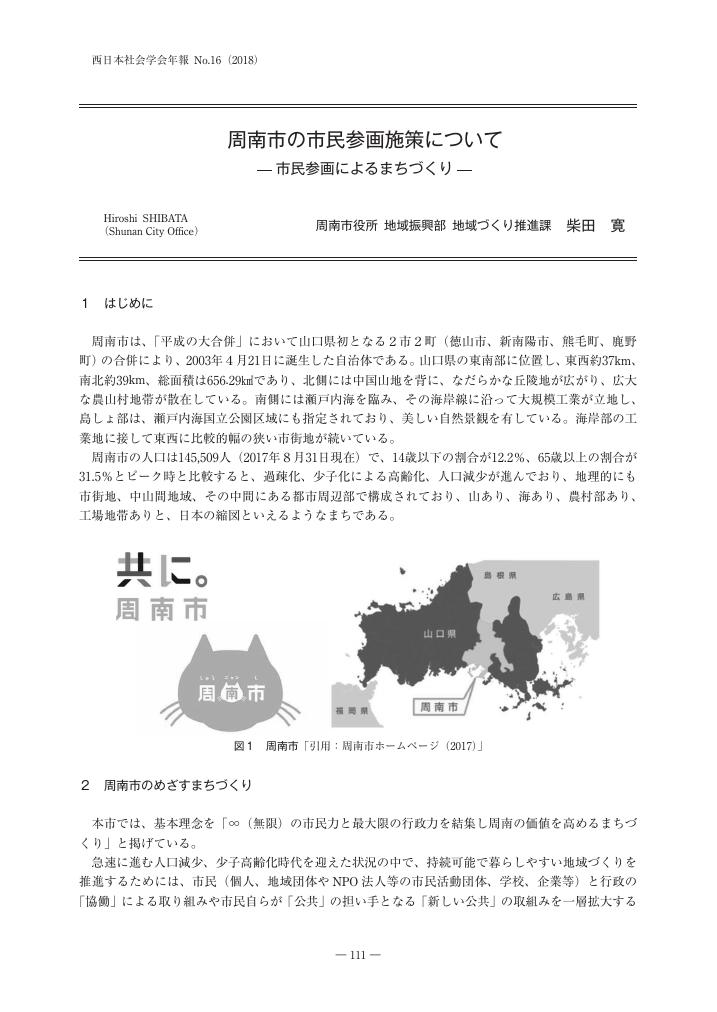- 著者
- 松本 貴文
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.135-136, 2018 (Released:2019-05-21)
- 著者
- 山田 富秋
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.137-138, 2018 (Released:2019-05-21)
- 著者
- 山本 努
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.139-140, 2018 (Released:2019-05-21)
1 0 0 0 OA 解題─観光の社会的効果というテーマ─
1 0 0 0 OA 観光をめぐる自由と不自由 ―ルート観光論からのアプローチ―
- 著者
- 高岡 文章
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.7-19, 2019 (Released:2020-03-27)
- 参考文献数
- 34
観光にはどのような可能性や広がりや自由があるのだろう。観光はどのような意味において狭く暗く不自由だろうか。そして、その自由と不自由はどのようにつながっているのだろう。本稿は観光社会学の視点から観光をめぐる自由と不自由について検討する。その際、ルート概念を導入することにより、「観光すること」をめぐる社会学的探究に新たな視座を提供したい。
- 著者
- 二階堂 裕子
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.47-61, 2019 (Released:2020-03-27)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
グローバル化と国内の労働力不足を背景に、近年、外国人技能実習制度(以下、本制度)による外国人労働者の受け入れが進んでいる。本制度の趣旨は、技能移転を通した開発途上国の経済発展を担う人材育成にある。しかし、帰国した元技能実習生が、必ずしも日本での就労経験を活用しているわけではないのが現状である。そこで本稿では、ベトナム人技能実習生を事例に、本制度を媒介とした技能移転の現状を検討し、国際貢献に向けた課題について考察する。本研究では、ベトナム社会の状況を鑑みて、農業分野における技能移転の可能性に焦点を当てる。そのうえで、愛媛県内の条件不利地域において、1970年代から有機栽培を主体とした環境保全型農業を実践している地域協同組合X の事例を取り上げる。X は、2000年以降、フィリピン人とベトナム人の技能実習生を受け入れるほか、ベトナム南部の都市に有機農業の拠点センターを開設し、帰国した元技能実習生による有機農業の推進を支援している。X の取り組みに関する分析をふまえて、本稿では、真の国際貢献に向けて、技能実習生の帰国後の再就職に向けた支援体制の整備が急務であることを論じる。
- 著者
- 速水 聖子
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.125-126, 2018 (Released:2019-05-21)
- 著者
- 徳永 勇
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.127-128, 2018 (Released:2019-05-21)
1 0 0 0 OA 周南市の市民参画施策について ―市民参画によるまちづくり―
- 著者
- 柴田 寛
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.111-117, 2018 (Released:2019-05-21)
1 0 0 0 OA 「九州つなぎ隊」による過疎・災害・高齢化問題に対する支援活動
- 著者
- 初鹿野 聡
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.119-124, 2018 (Released:2019-05-21)
1 0 0 0 OA 中間支援組織「ふるさと発・復興志民会議」の形成過程とその挑戦
- 著者
- 徳野 貞雄
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.43-59, 2018 (Released:2019-05-21)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
熊本地震発生直後から、半当事者として熊本震災への支援活動とその組織化に取り組んだ筆者の行動記録をベースとした報告である。以下、次のような5つの事象について報告している。1) 熊本震災は「二重の複合型震災」であった。すなわち、4月の地震による震災と6月の集中豪雨による複合震災であり、同時に熊本城や益城町等の「マチ型震災」と県下一円の農山村に広がる「ムラ型震災」の複合震災であった。2) 震災直後の急性期の支援活動は、『震災マージナル理論』とも言える。地域づくり活動を行っていた近接の人々が、自主的に動いて初期の支援活動を始めていた。3) 中間支援団体の形成過程は、5月3日の『熊本・大分新(震)興ネットワーク』(情報プラットホーム)、7月24日に任意団体「熊本復興会議」を結成し、本格的に震災支援活動を初め、2017年4月に一般社団法人化して「ふるさと発・復興志民会議」を立ち上げた。4)【見える震災】 と【見えない震災】を構造的に分類し、その対応主体の相違から復旧・復興の課題を考察している。5) 震災時の「災害ボランティアセンター」に農業支援はなく、制度的不作為を指摘した。また、農家からの農業支援は微弱である。変わって、消費者の農作業ボランティアが活発であることを発見した。
- 著者
- 大畠 啓
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.73-84, 2018 (Released:2019-05-21)
- 参考文献数
- 37
近代社会の複雑性(Komplexität)と、それに由来する危機経験(意味と自由の喪失)を、社会進化や合理化の過程と両立させる形でいかに把握するかという問いは、マルクス主義以来社会理論にとって大きなテーマであった。この問いに応える代表的な試みの一つが、J. ハーバーマスの「システム/生活世界」図式である。この図式は彼の法治国家論の展開以降も、妥当性を保持しうるものだろうか。本稿ではこの問いについて、批判理論の危機診断的観点から考察を深めるための補助的作業として、A. ホネットとA. デミロヴィッチの「システム/生活世界」図式批判を検討した。 まとめるならば両者とも、コミュニケイションに潜む権力関係やイデオロギー性への洞察を、システムと生活世界を分離しない形で先鋭化している。「システム/生活世界」図式から離れて、コミュニケイションに歪みをもたらす複雑性や機制を、システム以外の形で幅広く捉え直す可能性を探求するためには、今後の研究課題として、社会を合理化へと導く公共圏のポテンシャルの活用を阻害する諸要因を、社会理論や法理論のみならず、メディア研究や文化分析も総合する形で解明する必要性があることを確認した。
- 著者
- 周 怡君
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.85-93, 2018 (Released:2019-05-21)
- 参考文献数
- 24
Improving the living conditions and quality of life for persons with disabilities (PWDs) are crucial aspects guiding disability policies in several countries. From the Americans with Disabilities Act (ADA) (1990) to the United Nations Convention on the Rights for Persons with Disabilities (CRPD) (2006), the importance of a rights-based approach to disability policy may be regarded as the most frequently mentioned resolution of the last two decades. The nations participating in the CRPD are required to enforce the content of the convention. However, disability policies have long been seen as an important part of welfare state policies, the characteristics and construction of which are deeply influenced by the financial resources and payment structures of individual countries. Sheltered workshop policies for PWDs are no exception, although these policies do share some similar characteristics across countries, such as a facilities-based working plan and low wages. Thus, it is worth studying how the core values and policy practices identified by the CRPD-such as integration, nondiscrimination, and decision-making with the participation of PWDs-influence the sheltered workshop policies of individual welfare state countries. This article examines the impact of the CRPD on the sheltered workshop policies regarding PWDs in three welfare state nations. Notably, the welfare policy framework and resource allocation patterns of each country affect its sheltered workshop policies more than does their signing the CRPD.
1 0 0 0 OA 台湾における地域包括ケアシステム構築に向けた課題分析 ―「ABC 計画」を中心に―
- 著者
- 荘 秀美 洪 春旬
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.61-71, 2018 (Released:2019-05-21)
- 参考文献数
- 20
台湾では、地域密着型福祉が1990年代初期から導入され、高齢者介護政策に大きく影響した。2016年5月の政権交代で、「長期介護十ヵ年計画2.0」を施行すると宣言した。その中で、「ABC 計画」という施策が提出され、「地域包括ケア」の政策方向を明示した。本論文では、「地域包括ケア」施策として「ABC 計画」のサービス対象、範囲及び推進戦略、政府の役割と機能、民間団体の位置、参入団体間の関係などを明らかにし、その可能性はどうなるのか、その促進要因と阻害要因は何かなどについて分析する。そこで、「地域包括ケア」という「ABC 計画」が追求している目標は明確に定義されておらず、「地域包括(統合型地域介護)」といえば、何を統合するか(対象不明)、どこまで統合するか(範囲不明)、如何に統合するか(推進方法混乱)、統合する条件は何か(財源―コスト、人力などの環境条件)、政府の役割や機能は何か、介護福祉提供者などの民間団体の位置、能力、相互関係などはどうなっているか、など様々な問題が指摘されていた。台湾では、地域包括ケアが導入されたとしても、その限界がどれほど認識されるかは問題である。また、上述した課題のほかに、サービスレベルの地域格差の問題、持続的財源の問題、サービス拠点の拡充など解決しなければならない問題が山積している。いずれにしろ、短期的には、その実現可能性は厳しいと思われる。
- 著者
- 西村 雄郎
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.129-130, 2018 (Released:2019-05-21)
1 0 0 0 OA 在宅ホスピスケアにおけるボランティア活動の諸相 ―インタビュー調査のデータ分析から―
- 著者
- 孔 英珠
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.95-110, 2018 (Released:2019-05-21)
- 参考文献数
- 13
本稿では、在宅ホスピスボランティアの会「A」のボランティア11人から得られた在宅訪問活動における14の事例を検討し、在宅訪問活動の諸相を提示した上で、活動対象者のニーズと在宅ホスピスボランティアの役割について考察を行った。 「A」は、終末期の患者・家族のみならず、神経難病の患者・家族や要介護高齢者・家族も活動の対象者とし、見守りや談話・交流、個別ニーズへの対応、家族に対する支援を行っていた。これらの活動は、在宅医療やホスピスケアを推進しようとする医療福祉機関との連携の中で行われていた。とりわけ医療ソーシャルワーカーが「A」と患者・家族の間でマネジメント役を果たしていることは、ボランティアや患者・家族の双方に安心感を与え、在宅訪問活動がスムーズに行われるための重要な要素となっていた。「A」の在宅訪問活動の事例から、患者・家族には公的サービスや市場では賄いきれない情緒的ニーズ・日常生活支援ニーズがあることが推察され、在宅訪問活動はそのようなニーズへの充足に有効である可能性がうかがわれた。なお、在宅ホスピスボランティアの役割については「患者・家族の全人的苦痛やニーズに寄り添いながら、生活者同士として患者・家族とふれ合う存在である」とまとめることができた。
1 0 0 0 OA 西原村における被災と対応の個別性 ―地域社会レベルと時間の経過を軸に―
- 著者
- 藤本 延啓
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.23-33, 2018 (Released:2019-05-21)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
熊本県阿蘇郡西原村は、2016年の熊本地震において甚大な被害を受けた。本稿は、被災者における被災と対応について、西原村の地域社会空間が持つ特性、および災害発生からの時間の経過に着目しながら、西原村における複数の事例を分析していく。 まずは、災害の初動・応急期対応において、相対的にミクロな地域社会空間では構造的な「強み」が、マクロレベルでは構造的な「弱み」が存在すること、また、時間が経過していくほどに被災と対応の「個別性」が深化・拡大していくことが確認できる。 さらに、この個別性の深化・拡大は、時間が経つほどにミクロレベルにも「弱み」の構造があらわれていくことや、被災者の抱える課題が「みえない」状態に落とし込まれていくことへつながっていることが明らかになる。 これらをふまえ、災害対応・支援への社会学(者)によるアプローチの可能性を考えるならば、被災者の個別性を、対応・支援の枠組みとなる相対的にマクロなレベルにリンクさせること、そのために「みえない諸課題」を「みえる」ようにするための丁寧な調査と分析が、その一端となるであろうことを指摘できる。
1 0 0 0 OA 日常と非日常のはざまで ―由布院温泉にみる震災対応と復興―
- 著者
- 米田 誠司
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.35-42, 2018 (Released:2019-05-21)
- 参考文献数
- 2
人はなぜ旅をするのか。この問いから始まる観光について、日常は非日常と背理的あるいは相対的に概念づけられるものの、地域ごとに異なる日常があり、観光客、観光地に暮らす人々にも日常と非日常があることをまず指摘した。その上で、観光地で災害が発生した場合にどのようなことが起きるのかについて、2016年4月に発生した熊本地震からの復旧と復興について、由布院温泉で検証した。その結果、地震発生により日常と非日常のはざまは一瞬で消失し、住民も観光客も等しく被災者となる中、復旧、復興の活動が行われた。復旧では人材や資材の不足により不便な生活や営業を強いられながら復旧工事を待った一方で、同年7月から実施されたふっこう割施策の効果は大きく、2016年7月から9月の第1期でほぼ例年並みに戻ることができた。詳細には、宿泊業の客数がこの期間まず回復し、その後他業種も客数が回復していった。またマスコミの過剰報道による風評被害が指摘される一方で、九州各地から支援に足を運ぶことが評価されていた。最後に、観光地を抱える地域の防災計画策定では、定住人口だけでなく非定常人口も考慮に入れた防災計画策定を検討すべきであろう。
1 0 0 0 OA 特集解題
- 著者
- 堤 圭史郎
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.1-3, 2018 (Released:2019-05-21)