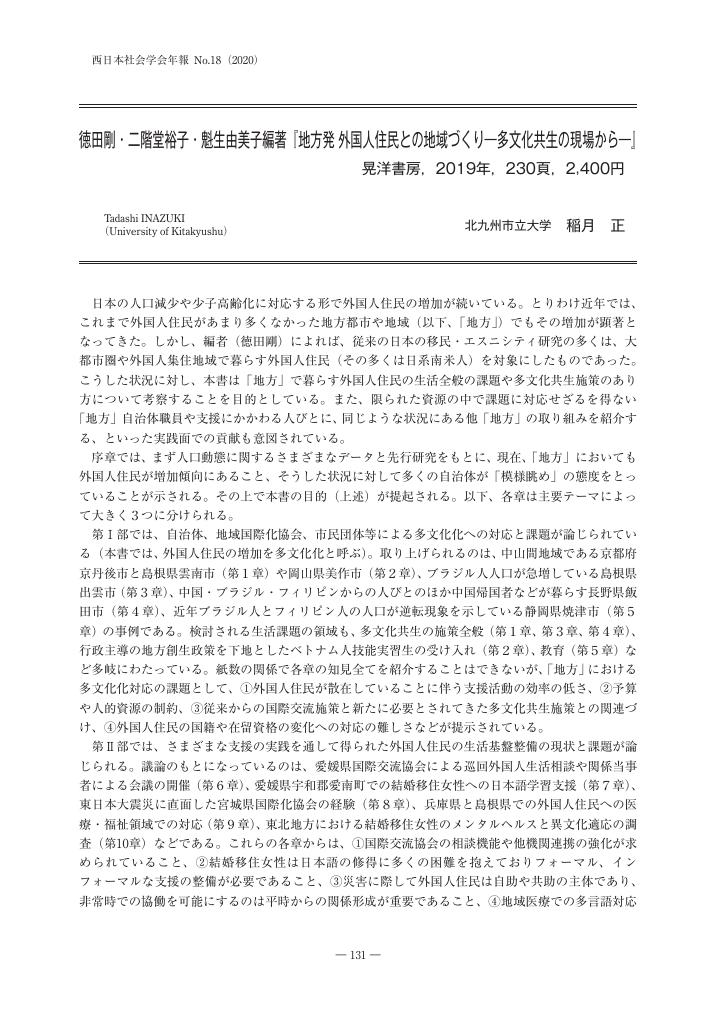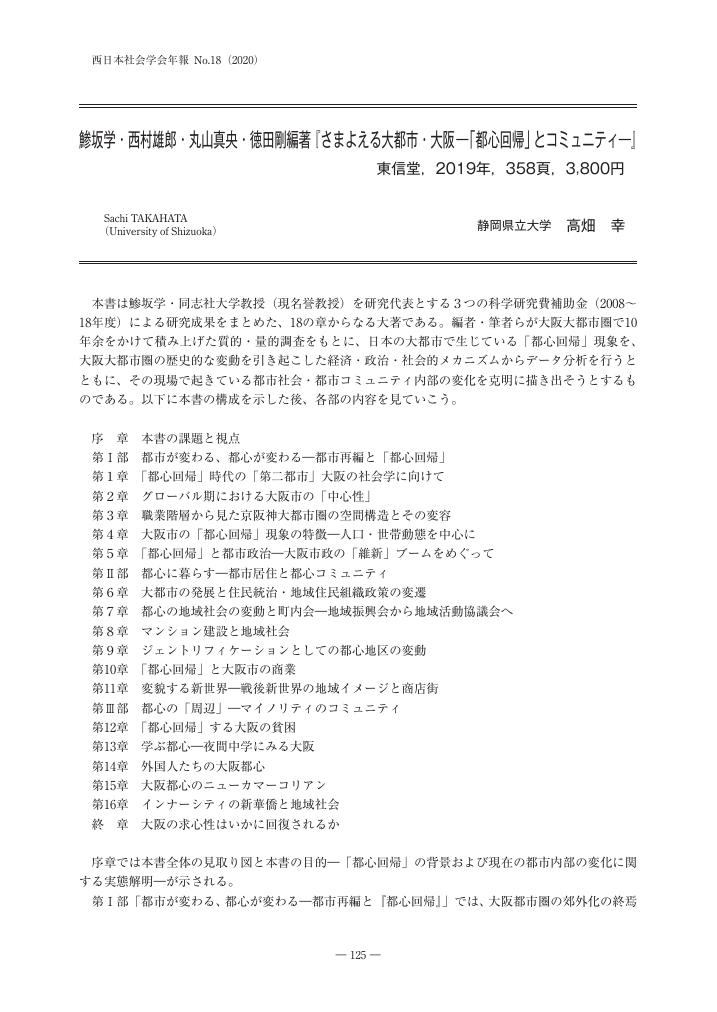1 0 0 0 OA 顔料及び支持体の特性を考慮したパステル画風レンダリング
- 著者
- 村上 恭子 鶴野 玲治
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.89-96, 2002 (Released:2008-07-30)
- 参考文献数
- 13
本論文では、ノンフォトリアリスティックレンダリング技法の一つの展開として、CGによりパステル画風の画像を生成する技法を提案する。 まず三次元オブジェクトをもとに、ベクタ化するための特徴点を抽出し、パステルのストロークモデルを生成する。次に、支持体である紙面の凹凸や、数種類のストローク技法によるパステルへの圧力変化、紙面上の同じ場所に複数の顔料付着した場合の混色などを考慮し、各ストロークごとに顔料の付着モデルを生成する。その後、これらのモデルに対しレンダリングを行う。 このようにして得た画像はある程度パステル画らしい特徴と雰囲気を持ったものであると同時に、視点の移動や画角の変化、光源や対象の移動や変形なども自由である。また、顔料の付着率やストロークの幅といったパラメータを変化させたり、レンダリングの際にぼかし効果(ブレンド)を加えることによって、様々な描画効果を得ることができる。
1 0 0 0 OA モデル駆動による仮想彫刻と仮想木版画
- 著者
- 岡田 稔 水野 慎士 鳥脇 純一郎
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.74-84, 2002 (Released:2008-07-30)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1 2
本論文では,仮想彫刻に基づく仮想木版画の生成法と応用について解説する.提案法は芸術•工芸の模擬を目指した非写実的画像合成法(NPR) のひとつである.一般に絵画などを志向したNPR で用いられている技法は,(a) ABR: 生成外観を模擬したレンダリング手法,(b) PBR: 物理モデルに基づくレンダリング手法,に大別されるが,本論文で解説する仮想木版画は(b) PBR に基づくものである.まず仮想彫刻システムによって仮想版木が生成される.次いで仮想版木,仮想紙,仮想馬連,仮想絵の具により,仮想木版画画像が生成される.このように提案法は木版画の制作工程を重視したものであるため,生成画像は物理的な裏付けを持ち,外観上も良い結果を与えている.また,仮想木版画手法を用いた仮想浮世絵の知的符号化,及びそれを通した仮想彫刻と仮想木版画の問題点と今後の課題についても言及する.
1 0 0 0 OA 木材経年変化のビジュアルシミュレーション法
- 著者
- 尹 新 藤本 忠博 村岡 一信 千葉 則茂
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.3, pp.108-110, 2002 (Released:2008-07-30)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 8 6
素材の経年変化はよく見られる自然現象であるため,金属の腐食や石の風化などの表現法の開発が活発に行われてきている.本論文では,木材の経年変化のビジュアルシミュレーション法について提案する.本文では,まず分枝を考慮した木材モデルの表現手法について述べ,次に木材の色および形状の経年変化を表現する手法について述べる.さらに,これらに基づくいくつかのシミュレーション例により手法の有効性を示し,最後に今後の課題について言及する.
1 0 0 0 OA フラクタル画像符号化のスケーリングパラメータ計算量削減
- 著者
- 原田 雅樹 木本 伊彦 藤井 俊彰 谷本 正幸
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.64-73, 2002 (Released:2008-07-30)
- 参考文献数
- 20
フラクタル画像符号化の高速化を実現するために,以下の二つの手法を提案する.第一の手法では,スケーリングパラメータの計算回数を削減させるために,一つのレンジブロック内の最大振幅と一つのドメインブロック内の最大振幅との比(以下ここではこれを最大振幅比と呼ぶ)を用いる.符号として選択されるドメインブロックにおける最大振幅比はスケーリングパラメータ付近の値をとるため,ある閾値を超える大きな最大振幅比を持つ場合にはスケーリングパラメータの計算を行わない.第二の手法では,スケーリングパラメータそのものの計算量を削減させるために,一つのレンジブロック内の輝度偏差と一つのドメインブロック内の輝度偏差との比(以下ここではこれを偏差比と呼ぶ)を用いる.偏差とスケーリングパラメータとの間には相関があるため,計算量の少ない偏差比に定数をかけてスケーリングパラメータを近似的に求める.
1 0 0 0 OA 連続フレーム画像を用いた反射パラメータの推定法
- 著者
- 張 暁華 中西 良成 小林 希一 三ッ峰 秀樹 齋藤 豪
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.8-14, 2002 (Released:2008-07-30)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 1
カメラの実写映像に基づいた立体物の電子映像部品化を目的として、被写体の表面反射パラメータ、すなわち、拡散反射および鏡面反射パラメータを良好かつ安定に求める方法を開発した。これまでは反射パラメータを求めるに当って、先ず、拡散反射成分と鏡面反射成分を分離してから求めていたが、この場合、被写体が複雑なテクスチャを持つ場合、あるいは、鏡面反射成分が多い場合には分離が良好に行えず、パラメータの取得が困難であった。本方法は、従来の方法と異なり、光源および被写体の色信号を予め知ること無しに、パラメータフィッティング法を用いて一挙に反射パラメータを求めることを特長としている。また、求めた反射パラメータを用いることにより、従来困難であった被写体に対しても拡散反射成分と鏡面反射成分を良好に分離することが可能である。論文では、反射パラメータの取得法の詳細、実験結果、考察等について述べる。
1 0 0 0 OA Webベースの対話型バレエ振付シミュレーション•システムの試作と評価
- 著者
- 曽我 麻佐子 海野 敏 安田 孝美
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.30-38, 2002 (Released:2008-07-30)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2 2
プロ・ダンサーの実演から採取したモーション•キャプチャ•データを利用して,クラシック•バレエの振付をWeb上で対話的に創作し,3次元CGアニメーションでシミュレーションできるシステムを開発した.ユーザにはバレエ教師を想定し,利用目的には,基本ステップの組み合わせをレッスン用に短時間で多数創作することを想定した.基本ステップのアニメーション情報はVRMLで記述し,Javaアプレットで実装したGUIによりWebにおける逐次的な振付の編集・再生を可能にした.システムには振付を支援する機能として,基本ステップのプレビュー機能,速度変更機能,編集機能を実装し,アニメーション出力を制御する機能として,人体モデルの選択,背景の選択,ユニゾンのシミュレーションができるようにした.バレエ教師などによってシステムの評価を行ったところ,実際に使うことのできるレッスン用の振付が本システムで創作できることを確認した.同時に,実用的なシステムとして公開するために改良すべき点が明らかになった.
1 0 0 0 OA Web2.5D用電子カタログシステム実現手法
- 著者
- 寺沢 幹雄 小高 金次 佐藤 創 和田 重久 外山 武徳
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.54-63, 2002 (Released:2008-07-30)
- 参考文献数
- 19
本論文では,実時間視点モーフィングを用いたWeb用立体表示であるWeb2.5Dを実現するための実証実験的電子商品カタログシステム実現手法を述べ,データ自動生成法を提案する.実時間視点モーフィングは未校正カメラで撮影された2視点画像から2次元処理により中間視点画像を実時間で生成する手法であり,本システムでは複数画像に対応することで対象物体の全周表示を可能とした.自動抽出した特徴点に対して,データ作成者が入力した8組以上の対応点から得られるエピポーラ制約に基づいて面情報が自動生成される.オクルージョンにより対応点の自動決定が困難な場合には,レイヤ構造をサポートした専用エディタで修正する.本手法はバナー広告や画面背景にも適用できるため,通信販売,製品説明,電子会議など多くの応用に有効である.静止画像以外の転送データ量は数十キロバイト程度であるため,電話帯域のインターネットでも実用的に利用できる.
1 0 0 0 OA 空間分割シアーワープ法を用いた並列ボリュームレンダリングシステム
- 著者
- 緒方 正人 村木 茂 マ クワンリュー 梶原 景範 劉 学振 越塚 健児
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.1-7, 2002 (Released:2008-07-30)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 1
科学技術上の諸問題を計算機を用いて解き,結果を直感的に把握したいとの要求,あるいは高度医療におけるMRI,CT, 超音波診断装置などのデータの表示,などから大容量の3次元情報を可視化する高速かつ安価なボリュームレンダリングシステムが必要とされている.ボリュームの可視化は, 処理するデータ量が膨大であることから,高速表示には,高価なスーパコンピュータや専用ハードウエアが用いられている.本論文は,市販のPC を複数用いて構成する低価格な高速ボリュームレンダリングシステムを提案し, その性能評価を示す.このシステムの高速化は,提案の空間分割シアーワープ法(Spatially Partitioned Shear-Warp Method)法により達成する.
1 0 0 0 OA リフレクションのための抽象画自動生成ツール - ThinkingSketch -
- 著者
- 美馬 義亮 木村 健一 柳 英克
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.39-45, 2002 (Released:2008-07-30)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 4 1
人間が図柄の構想を行い、コンピュータ上でそれらを表現するというスタイルのツールは広く用いられているが、コンピュータが図柄を生成する作業に関わるようなシステムは少数である。ThinkingSketch は、創造性をもった図柄生成に関する発想を対話的に支援することを目的とする。本システム上では。1)既存の絵画や写真などから生成されたカラーパレットを参考にして、作品の中で色彩を割り当てる。(=色のトレース)、 2)既存の絵画や写真の表現を下地にしてなぞる作業を通じてオリジナルな図形プリミティブを作成する。(=形のトレース)、 3)画面の中に 乱数によるプリミティブを配置する。4)パラメータと生成ルールにより多数の絵画を生成し、構図の構築、評価を繰り返し行う。このような検討作業を通じ、生成ルールやプリミティブのチューニングを行い、望ましいパターンの生成確率を上げる。ユーザはこの過程の中で自己の好む絵画スタイルの存在を意識し、それらを吟味することが容易になる。加えて、このような枠組みは熟練者への表現における生産性向上の支援にも利用可能であることを報告する。
1 0 0 0 OA TVML台本からのマンガ自動生成に関する研究
- 著者
- 長谷川 誠 林 正樹
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.15-21, 2002 (Released:2008-07-30)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
近年、様々な情報伝達メディアの急速な普及に伴い、テレビ番組に関連するコンテンツも多様化し、複数のメディアを通じて楽しむ視聴形態が促進しているため、ひとつのコンテンツからマルチメディアアウトプットを自動的に作る、メディア間相互変換の研究が重要になってきている。本研究では、このメディア間自動変換のひとつとして、テレビ番組台本をマンガという印刷物に変換して提供するアプリケーションについて検討を行った。今回、マンガ生成を行うテレビ番組台本として、テレビ番組記述言語TVML(TV program Making Language)により制作されたものを対象とし、そこから得た情報を解析することで、マンガに使うコマ画像の選定・データ化、マンガを作る際に必要な情報の抽出、マンガ特有の視覚効果であるフキダシなどの生成を行い、それらを組み合わせてマンガ画像を出力するアルゴリズムを提案し、それに基づいてマンガ自動生成システムを構築した。本研究により、マンガ自動生成システム構築へ向けての見通しが得られた。提案したシステムは、テレビ放送のもとになる番組台本を解析することで、マンガという文字と絵によるメディアに変換する試みであり、これにより、テレビ番組のコンテンツをマンガに変換し、自由に携帯し、時間や場所に拘束されずに楽しむという新しい視聴形態を提供する可能性を開くことができた。
1 0 0 0 OA モーショングラフ: 自律型キャラクタの動作生成手法
- 著者
- 齋藤 豪 井元 崇之 中嶋 正之
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.22-29, 2002 (Released:2008-07-30)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2
仮想世界内で自律的に行動できるキャラクタのアニメーションを生成するために、一連の動作すべてを事前に決定しておくことはできない。そこで、キャラクタの様々な状態をノードとし、動作の断片をリンクとするモーショングラフを定義し、任意の次の状態が指示された場合に、自動的にパスを決定して一連の動作を生成する手法を提案する。 さらに重み付きパス探索の手法を用いることにより柔軟なアニメーション生成を可能にする。
1 0 0 0 OA 複数の3次元形状操作を統合した直観的入力ツール
- 著者
- 村上 存 臼井 恵
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.46-53, 2002 (Released:2008-07-30)
- 参考文献数
- 11
導電性弾性材料の塊を構造体かつ3 次元変形センサとする入力装置を用いた,直観的3 次元形状操作インタフェースDO-IT (Deformable Object as Input Tool) を提案する.電気抵抗値を測定するための端子対を格子状に導電性弾性材料の塊に接続し,弾性体に加えられた曲げ,ねじり,押し込みなどの3 次元的変形を,各部の電気抵抗値の変化により測定し,その変形をコンピュータ内の形状モデルに適用する.各端子対における抵抗値の変化パターンと入力装置の変形の関係をニューラルネットワークを用いて学習すると同時に,学習の過程において重要度の低い端子対を検出し除去することによって,適切な端子対の数および配置を半自動的に決定する.これらの学習,最適化によって,プログラムをほとんど書き換えることなく,目的や応用に応じたさまざまな形状の弾性体入力装置や変形の種類に対応することが可能となる.弾性体による変形入力に加えて,実際の応用のために必要となる,さまざまなモード切替,調整などの操作を行なうためのスイッチ,ボタン,ボリュームを統合した,直観的3 次元形状操作のための入力ツールを製作した.提案したインタフェースをコンピュータ・システムとして実装し,実際に操作を行なうとともに,従来のマウスと複数投影図を用いた形状操作方式との定量的比較を行ない,研究の有効性,可能性を検証した.
1 0 0 0 OA 数理的秩序による二次元の構造を基盤とした造形表現において形の配置に不規則性を導入する方法
- 著者
- 上浦 佑太
- 出版者
- 芸術学研究会
- 雑誌
- 芸術学論集 (ISSN:24357227)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.41-50, 2021-12-31 (Released:2021-12-29)
- 参考文献数
- 5
正方格子や正多角形のような数理的秩序による構造(以下、数理的構造)に基づいて形を配置するタイプの造形表現には、恣意や偶然を排した規則的操作による表現と、形や配置をあえて不揃いにする不規則な表現の2種類がある。不規則性を取り入れた表現には図形などの再現的形体のみで構成される作品だけでなく、自然物の形や偶然的行為の痕跡として生ずる非再現的形体を活用した展開もある。しかし、これらを数理的構造に基づく造形の展開として包括的に捉える研究はまだない。そこで本研究では数理的構造に基づく造形の体系化を見据えて、まず不規則性の導入方法を整理することを目的とした。研究対象は最も基本的なアプローチである二次元の数理的構造を基盤とした表現に限定した。調査対象は静止表現に限定し、規則的表現と不規則表現の両方を取り上げた。事例調査をふまえて構造の数理性を活用した配置の特性を整理し、再現的形体と非再現的形体のそれぞれについて不規則性の導入要因を分析した。考察により明らかになった不規則性の導入方法は以下5つである。1)自然物または不揃いな生成物を取り入れる2)偶然性を取り入れた行為の痕跡として直接媒体に定着する不規則形体を取り入れる3)構造の点・線・面の最小単位に対して特定の形または行為を計画的に割り当てるために行うラベリングのプロセスにおいてラベルの分布を不規則にする4)ラベルに割り当てる操作内容に偶然や恣意に基づく不規則な要素を取り入れる5)構造を不規則に変形する不規則性の導入方法を整理したことで数理的構造の応用範囲を俯瞰的に見渡す手掛かりができた。本研究成果は数理的構造を活用した造形を体系化して表現の基盤と展開を拡張する今後の研究のための基礎になる。
1 0 0 0 OA 国内におけるOCWのビジュアルデザインに関する考察
- 著者
- 王 宛亦
- 出版者
- 芸術学研究会
- 雑誌
- 芸術学論集 (ISSN:24357227)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.11-20, 2021-12-31 (Released:2021-12-29)
現在、大学の魅力の伝達や知識の活用などの目的で、大学OCW(Open Course Ware)からの情報発信が行われるようになっている。しかしながら、各大学でのOCW活動を推進していく際、利用が不十分、認知度が低いといった問題があった。本研究では、OCWにおける利用率を向上させる方策の検討を目的として、聞き取り調査と印象評価実験を行った。まずは国内で積極的にOCWの取り組みを進めている4つの国立大学(北海道大学、東京大学、名古屋大学、京都大学)のOCWについて、運営管理側への聞き取り調査を行った。インタビュー結果から、運営管理の現状、ビジュアルデザインへの取り組みなどを確認できた。次に利用者が感じる印象と実際の利用状況を考察するために印象評価実験を実施し、利用者へのアンケートによる評価と、その利用過程における録画データの観察調査を分析した。分析の結果、北海道大学の評価が高かった。その理由は、北海道大学は統一されたビジュアルデザインで、一貫したイメージを打ち出していたからだと考えられた。これらから、4つの大学のOCWについて、利用者が感じる印象と実際の利用状況を確認することができた。さらに、分析と考察を踏まえ、OCWにおける利用者がコンテンツを探す行動には共通の利用経路が存在することがわかった。今回の調査研究を通して、ビジュアルデザインの視点から、次の3点を国内におけるOCWの課題として提示した。1)イメージを探る、2)広報活動、3)インタフェースデザインの改善。
- 著者
- 佐野 広章
- 出版者
- 芸術学研究会
- 雑誌
- 芸術学論集 (ISSN:24357227)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.31-40, 2021-12-31 (Released:2021-12-29)
本研究は、「版画のもつ一枚の絵としての面白さ」を追求した日本を代表する版画家 清宮質文の制作工程を、現代の木版画制作者である筆者の視点で考察し、版表現の豊かな創造性と造形の至高性に迫ることを目的としている。研究は、清宮が残した直筆の資料、雑記帳、雑感録、制作控と現存する版木、先行研究から得た情報を参考に技法と手順を推測し、木版画作品2点の部分的再現実験結果を考察する方法で行った。透明なキリコに宿る儚い光と深く静謐に広がる背景が特徴の《キリコ》は、版の再現実験で、一つの版で摺り方を変え11回の重色を可能にする主版と、2種の凸版を作成した。摺りの再現実験では、2枚の制作控に記載された特殊技法(版面上の絵具を部分的に拭きとる技法、指で押し写し取る技法、水性凹版技法)のほか、筆者が手順を推測した技法(水を摺る技法)など、多様な手順を再現で検証した。蝶のフォルム と無限の色彩的空間が特徴の《蝶》は、版の再現実験で、輪郭に鋭角と緩やかな板ぼかしのほか、摺りや水分量の変化で汎用的に重色可能な主版と、撥水加工を施した版、重色を目的とした凸版を作成した。摺りの再現実験では、類似色の制作控を参考に、筆者が全行程を推測し、掠れた摺りや水分量の多い薄い摺り、輪郭線を描く摺りなど、水分の調整による技法の変化や重色の効果を明らかにした。彫りと摺りを解読し、版画の機能や多様な特殊性を再現することで、現在までに検証されていない、清宮の木版画技法と制作工程を追体験し「版画、のもつ一枚の絵としての面白さ」に迫る実験結果を提示した。
- 著者
- 福本 純子
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.123-124, 2020 (Released:2021-03-31)
- 著者
- 三隅 一人
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.127-128, 2020 (Released:2021-03-31)
- 著者
- 藤本 延啓
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.129-130, 2020 (Released:2021-03-31)
- 著者
- 稲月 正
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.131-132, 2020 (Released:2021-03-31)
- 参考文献数
- 1
- 著者
- 高畑 幸
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.125-126, 2020 (Released:2021-03-31)