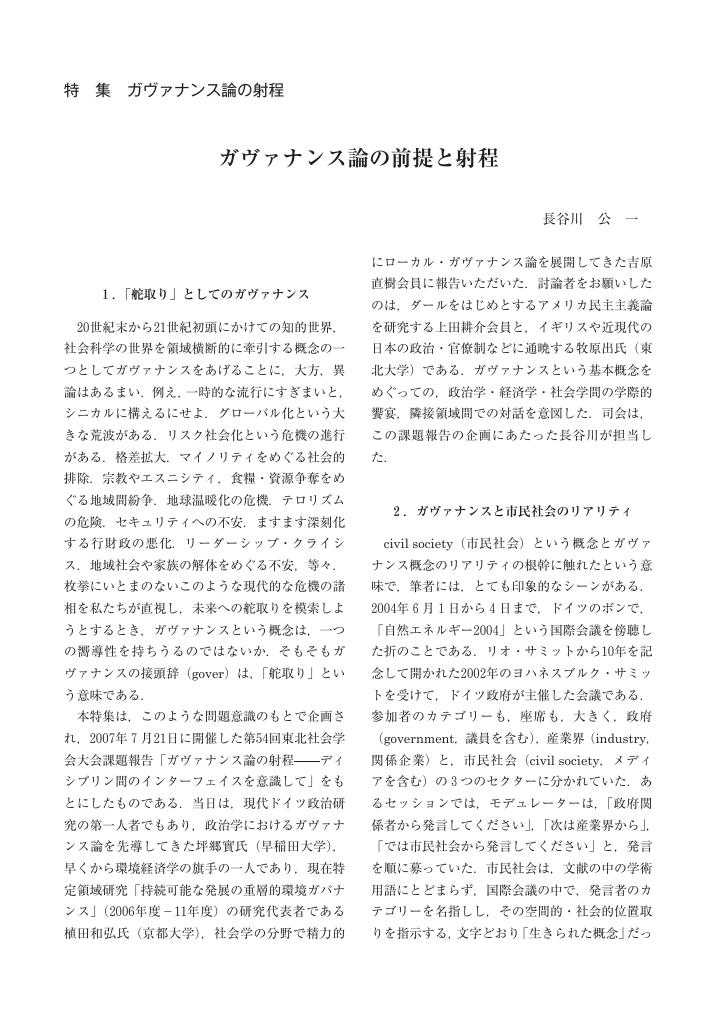2 0 0 0 OA 科学技術のリスクと〈制度的リスク〉
- 著者
- 小松 丈晃
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.5-15, 2013-07-19 (Released:2014-08-31)
- 参考文献数
- 28
本稿では,いわゆる安全神話を形づくってしまう規制組織の構造的な問題について,社会環境的リスク(「リスク」と表記)と制度的リスク(〈リスク〉と表記)の区別に依拠して分析を行い,この両者が,当事者の視点からみると区別しがたくなっているがゆえに,〈リスク〉管理がかえって「リスク」の拡大を招きうることを示す.しかもこうした傾向は,新自由主義的な潮流の中でさらに拡大していく可能性を有する.まず,東日本大震災による原発震災にいたる過程において,安全規制を担う諸組織が,原子力技術の「リスク」そのものの管理を,非難の回避あるいは信頼喪失の回避といった〈リスク〉管理へと(ルーマンの社会システム論でいう)「リスク変換」したことを,指摘する.すなわち,組織システムは,その「環境」に見出される諸問題をそのシステムにとっての〈リスク〉へと変換し,その変換された〈リスク〉に応答するようになる.とはいえ,この「リスク」管理と〈リスク〉管理とは,分析的には区別されうるものの,当事者の観点からは区別しがたく,このことが,本来縮減されるべき「リスク」をむしろ深刻化させる背景ともなりうる.第三節では,C.フッドの議論に依拠して,具体的な〈リスク〉管理の(「非難回避」の)戦略について述べ,こうした二重のリスクの関係に関する研究の必要性を確認する.
2 0 0 0 OA 自治体戦略としての「ローカル・アイデンティティの再構築」
- 著者
- 大堀 研
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.23-33, 2011-07-16 (Released:2014-02-07)
- 参考文献数
- 24
東京大学社会科学研究所の希望学プロジェクト釜石調査グループは,地域活性化に必要な条件の一つとして,「ローカル・アイデンティティの再構築」を掲げた.しかし,調査グループが2009年に調査成果として発刊した書籍では,ローカル・アイデンティティという用語は,地域の個性・らしさという言い換えが示されている以外に,明確な概念規定はなされていなかった.またそれが地域活性化をもたらすという論理は,釜石の事例に関しては検討すべき点が残されている.後者の論点については,筆者の考えでは,岩手県葛巻町,福井県池田町の事例でみてとることができる.葛巻町ではクリーン・エネルギーのまちという新しい要素が導入されたことにより,交流人口が増大している.池田町では,従来の「能楽の里」という自己規定に加え,農村という特性に基づき環境のまちづくりを推進したことから,NPO など各種環境団体が形成されるようになっている.これらの事例を踏まえ,本稿では「地域(社会)」を自治体と規定し,ローカル・アイデンティティは,自治体のキャッチフレーズ等に表示されるものとして捉えた.これを敷衍すれば,ローカル・アイデンティティの再構築とはキャッチフレーズの更新に象徴されるようなものとなり,自治体戦略の一環となる.ただしこの再構築は,自治体行政だけでなく,企業や住民など多様な主体が関与しうるものであり,その意味で偶有的である.
2 0 0 0 OA 父親の不在と社会経済的地位達成過程
- 著者
- 余田 翔平 林 雄亮
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.63-74, 2010-07-16 (Released:2014-02-07)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
本稿の目的は,義務教育修了時以前に父親が不在であること(早期父不在)によって,地位達成にどれほどの格差が生じ,その格差が時代とともにどのように変化してきたのかを明らかにすることである.従来の社会階層・移動研究では,地位達成過程の初期段階で父親がいなかった人々は欠損値として分析から除外されることが多かった.しかし近年,そういった人々の地位達成に着目する動きが見られる. 「社会階層と社会移動調査」を用いて,早期父不在者の教育達成と初職達成を分析したところ,以下の点が明らかになった.(1) 早期父不在者が高学歴化の流れに取り残される形で,短大以上の高等教育機関への進学格差は拡大傾向にあった.(2) 安定成長期以降,早期父不在を経験した人はそうでない人々と比較して,ブルーカラー職として労働市場に参入する傾向が強まり,専門職や大企業ホワイトカラー職に初職で入職できる割合も低かった.(3) 早期父不在者の初職達成上の不利は低い教育達成によって引き起こされていた.
2 0 0 0 OA インフォーマルケア論と相互作用論の視座 ―死と看取りの社会学の展望―
2 0 0 0 OA J. デューイにおける「道徳」と「社会的諸条件」 ―行為と責任に関する所説の検討―
- 著者
- 何 淑珍
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.63-72, 2009-07-19 (Released:2013-12-27)
- 参考文献数
- 8
本稿の課題は,J. デューイの『倫理学』における道徳理論の基礎を明らかにすることにある.先行研究では,社会成員としての個人の行為に立脚し,諸個人の置かれているその場その場の具体的問題に対する行為の結果責任が指摘されている.本稿では,その議論を一歩すすめて,デューイのいう個々の具体的状況とは何を指しているのか,結果責任とはいかなるものであるのか,といった問いをたてて検討をおこなった.そこで,デューイによる過去の道徳理論に対する批判,諸個人の行為を取りまく社会的ネットワークへの注目を考察することによって,個人が直面する具体的状況とは,社会全体と関連する「社会的諸条件」だということを明らかにした.デューイの道徳理論は,個人の行為と「社会的諸条件」との相互規定・循環関係を重視する点が特徴的なのである.
- 著者
- 湯上 千春
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.73-79, 2009-07-19 (Released:2013-12-27)
- 参考文献数
- 34
2 0 0 0 OA 学説研究と数理研究の対話 ―閉鎖・開放・第二次観察―
- 著者
- 小松 丈晃
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.49-52, 2009-07-19 (Released:2013-12-27)
- 参考文献数
- 6
本特集へのコメントである本稿では,古典を読むとはどういうことかをまず見たあとで,各論考の議論内容と関連した二つの論点について(いずれもそれぞれ慎重な議論運びを要するものだが,ごく簡単にのみ)考察する.一つは,専門領域の閉じと開放について,である.専門領域はいかなるかたちで「閉じ」てゆくのかを確認しつつ,それらの領域間での対話の可能性に,触れる.もう一つは,観察の観察である.現代社会においては,数理/非数理を問わず,観察の観察(「第二次の観察」)をその研究においてある程度考慮せざるをえなくなっているのではないかという問題提起を行う.
- 著者
- 牧野 友紀
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.93-103, 2008-07-17 (Released:2013-12-27)
- 参考文献数
- 9
本稿の課題は,昭和恐慌期開拓村の形成過程の特質を,入植に携わった指導者の記録を読解することによって明らかにすることである.本稿では,準戦時体制期において再編された村落秩序の理解をめぐって,国家権力の末端に位置する「中堅人物」のあり方に焦点を絞り,その人物の記録と生活史から見た開拓村の形成過程の特質を明らかにしている.再編された村落秩序は,国家の支配秩序にはらむ論理と農民の生活秩序の論理との衝突というモメントを通して実現されている.そうした観点の下で考察した結果,本事例の指導者は,従来の「中堅人物」理解の枠には収まりきらない存在であることが看取された.さらに,従来の農本主義がもちえなかった,国家権力の末端に位置しながら,現実の国策に抗して農民と農村の存在を確保しようと創意工夫する,パターナリズム克服の試みを見て取ることができた.
2 0 0 0 OA 温泉地のまちづくりを支える社会構造
- 著者
- 金井 雅之
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.83-91, 2008-07-17 (Released:2013-12-27)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 4
どのような社会構造をもつ温泉地でまちづくりへの取組みが盛んであるかを,「橋渡し型」と「結束型」の違いという社会関係資本論の枠組みに依拠しつつ,質問紙調査のデータによって計量的に分析した. まちづくりへの取組みを時間の経過とともに進展していく過程として操作化し,質的比較分析によって分析した結果,つぎの2つの知見が得られた.① まちづくりの初発段階において重要なのは結束型社会関係資本である.② まちづくりの完成段階において重要なのは橋渡し型社会関係資本である. これは,まちづくりの各段階において必要となる社会関係資本の種類が異なることを意味しており,橋渡し型と結束型との関係が単なる二項対立ではなく,時間の経過の中で複雑に交叉しながら創発的にまちづくり活動を促進している可能性を示唆している.
2 0 0 0 OA ネオ古典社会学の企て
- 著者
- 三隅 一人
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.5-16, 2009-07-19 (Released:2013-12-27)
- 参考文献数
- 31
本稿では,古典学説に拠りつつ理論的一般化をはかるネオ古典社会学に,解釈支援型フォーマライゼーションという類型論に焦点をおく理論構築法を組み入れて,事例研究を媒介にして学説と数理の対話を促進する,その可能性と意義を論じる.第一に,役割の学説研究との往還の中から解釈支援型フォーマライゼーションならではの理論化を引き出す,その具体的な過程を例解する.ポイントは類型論の背後にあるプロセスの明示化である.第二に,そこで定式化されたプロセスのモデルを,秩序問題との接合および国際関係という異なる現象への応用を通して一般化し,理論的一般化のための含意を検討する.
2 0 0 0 OA 環境保全政策における「歴史」の再構成
- 著者
- 武中 桂
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.49-58, 2008-07-17 (Released:2013-12-27)
- 参考文献数
- 5
「環境保全」を目標にひとつの空間に多様な立場から人々が働きかけるとき,その空間に求める役割の違いから対立が生じる場合がある.一方,本稿で事例とする蕪栗沼は,地域住民と自然保護団体が求める役割は異なるが,現在,そこに際だった対立はない. かつての蕪栗沼は,草刈り,魚獲り,狩猟の場など,沼の周辺集落の人々の生活の場であった.昭和40年頃を境に,生活における人々と沼との具体的な関係は次第に希薄になったが,沼の周辺水田で耕作する彼らにとって,蕪栗沼は今も「遊水地」として必要である.反面,天然記念物であるマガンの飛来を理由に,自然保護団体は「マガンのねぐら」としての重要性を指摘する.特に1996年,沼の全面掘削の是非をめぐり,地域住民は賛成/保護団体は反対というように,両者間の相違が顕著に現れた. だが,2005年に蕪栗沼と周辺水田がラムサール条約に登録されたのを受け,保護団体が沼への人為的介入の必要を考えはじめた.彼らの認識の変化は,「遊水地」として沼を機能させるために人為的介入を求める地域住民の見解と一致する.これを地域住民の側から捉えると,彼らの発言や作業が,結果的に「マガンのねぐら」として沼のあり方を問う保護団体の理念にも応じているということである.このような地域住民の姿勢は,単に生活における必要な行為としてではなく,ラムサール条約登録湿地に対して,そこで自分たちが築いてきた「歴史」を埋め戻す営為であると提示することができる.
2 0 0 0 OA ガヴァナンス概念への懐疑
- 著者
- 上田 耕介
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.43-45, 2008-07-17 (Released:2013-12-27)
2 0 0 0 OA ガヴァナンス論の前提と射程
2 0 0 0 OA 「動かないムラ」に考える ―他者の「心意」に迫るフィールドワークは可能か―
- 著者
- 松村 和則
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.61-90, 2007-07-20 (Released:2013-10-23)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
「そこにも人は住まねばならない」というテーゼは,琵琶湖―淀川水系という「特殊」な時・空間からうまれた「生活環境主義」というイデオロギーの所産である.もし,「条件不利地域」として日本の山村が見捨てられたならば,人々が棲む空間はこの日本のどこにも存在しないだろう. 大都市圏に棲む人々が山村に関心を持つか否かを問う以前に,森林―山村空間は環境保全をめざすべくしてそこにある.崩壊すべきものとしてのムラ,崩壊したはずのムラ,環境保全主体としてのムラ,時代の変容と共に形容される様は変化したが依然として村落社会研究の中心テーマとしてムラ論もまたあった. 環境保全という課題の前で,山村(ムラ)の主体性論は,新たな課題を背負って登場した.このテーマは,環境社会学研究において所有論,コモンズ論として深まりを見せたが,ムラ人の主体性を創り上げていく「はっきりとした意図を持たない首尾一貫性」(P・ブルデュー)を捉える「手口」が明示されずに来た.鳥越皓之の用語になぞらえれば,「言い分」論を経験論へ再度引き戻してモノグラフィックに記述することになるだろう. 本稿は,以上のような問題意識の元に,環境保全主体としてのムラのリーダーを羅生門的手法で描き,書く主体をもその文脈に埋め込みつつ「動かないムラ」を記述する.
2 0 0 0 OA 「味」の正体―味嗅覚統合への心理物理学からのアプローチ
- 著者
- 小早川 達 後藤 なおみ
- 出版者
- 日本基礎心理学会
- 雑誌
- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.66-71, 2018-12-26 (Released:2019-01-25)
- 参考文献数
- 30
One of the factors that affect the judgment whether signals received by receptors of different sensory modalities belong to the same event is synchrony perception among multiple types of sensory information. In this article, we introduce the simultaneity judgment (SJ) task in cross-modal combinations (especially olfactory-gustatory):(1) development of measurement system for SJ task using olfactory and gustatory stimuli, (2) SJ tasks for three cross-modal combinations (olfactory-visual, visual-gustatory, and olfactory-gustatory), and (3) SJ tasks for olfactory-gustatory combinations under match/mismatch conditions. Taste and odor are important components of flavor. The results of our studies suggested that there is a correlation among match/mismatch between taste and odor, oral referral, and temporal resolution of synchrony perception from the perspective of flavor perception.
2 0 0 0 OA 絵本日本外史 : 巻1-22
2 0 0 0 OA 成人急性リンパ性白血病に対する臍帯血移植の1例
- 著者
- 土岐 典子 齊藤 泰之 入澤 寛之 佐倉 徹 宮脇 修一
- 出版者
- The Kitakanto Medical Society
- 雑誌
- 北関東医学 (ISSN:13432826)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.393-396, 2003-11-01 (Released:2009-10-21)
- 参考文献数
- 10
症例は34歳, 女性.急性リンパ性白血病のため, 2002年5月当院入院.寛解導入療法にて寛解となったが, 1回目の地固め療法後に再発.化学療法にて2回目の寛解となったが, 予後を考慮し, 幹細胞移植を行うべくドナー検索を行った.しかし, HLAmatchドナーは家族内, 骨髄バンクでも見つからなかった.このため2002年10月, 非血縁者間臍帯血移植を施行.前処置は, TBI (total body irradiation) +CY (cyclophosphamide) で, GVHD予防にはFK506+短期MTXを使用し, 細胞数は3.02×107/kgで, HLAは3座不一致 (A locus 2座不一致, Blocusl座不一致) であった.Day22に生着し, 急性GVHDは発症せず, day100で免疫抑制剤を中止した.8ヶ月たった現在, 再発なく外来通院中である.臍帯血移植は, 小児のみでなく, 成人においても有用な治療手段である.
2 0 0 0 OA 急激に加速する人間の活動による気候変動の時代における芸術と環境美学
- 著者
- 伊東 多佳子
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.13-22, 2020 (Released:2020-10-13)
Anthropocene has become an environmental buzzword since the atmospheric chemist, and Nobel Prize laureate, Paul Crutzen introduced it in 2000. The word has soon picked up by internationally well-known curators for the theme of the international art exhibitions in response to an increase in environmental art addressing the crisis of the Climate Change and the threat of biodiversity. As a report for the symposium, “Anthropocene”, I will examine the current various environmental art in the age of climate change, and the evaluation of it from the viewpoint of environmental ethics and refer to the recent debate of environmental aesthetics.
2 0 0 0 OA 色と心 ヘーゲルによるゲーテの『色彩論』の受容をめぐって
- 著者
- 栗原 隆
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.81-92, 2019 (Released:2020-10-14)
Die Besonderheit der “Farbenlehre“ Goethes bestand in der Mischung der Farben und dem Gegensatz von Hell und Dunkel. Hegel, der in seiner „Naturphilosophie“ Goethes “Farbenlehre“ erörtert hat, verlagert später die Diskussion über Farbe zur „Philosophie des Geistes“ und dann zur „Ästhetik“. In der „Ästhetik“ stellt Hegel das Problem folgenderweise dar. „Diese [= Farbe und Colorit] macht erst eigentlich den Maler zum Maler. (...) Die erste ist der Gegensatz von Hell und Dunkel.“ (Ästhetik(1820/21).272f.) Wir können als Hintergrund dieser Darstellung den Einfluss von Goethes „Diderots Versuch über die Malerei“(1799) erkennen. Hegel verlangte von den Malern, das Vergangene und auch das Unsichtbare, das Innere eingeschlossen, darzustellen. Hegel rühmte die Gemälde von Gerard Dou als „der Triumph der Kunst über die Vergänglichkeit“ (Vorlesungen.II,201), weil darin etwas ganz Flüchtiges festgestellt und statarisch gemacht wird. Gerade in den Gemälden von Gerard Dou ist der Gegensatz von Hell und Dunkel auffällig und seine Werke entsprechen also dem Inhalt von Goethes „Diderots Versuch über die Malerei“ und seiner “Farbenlehre“.