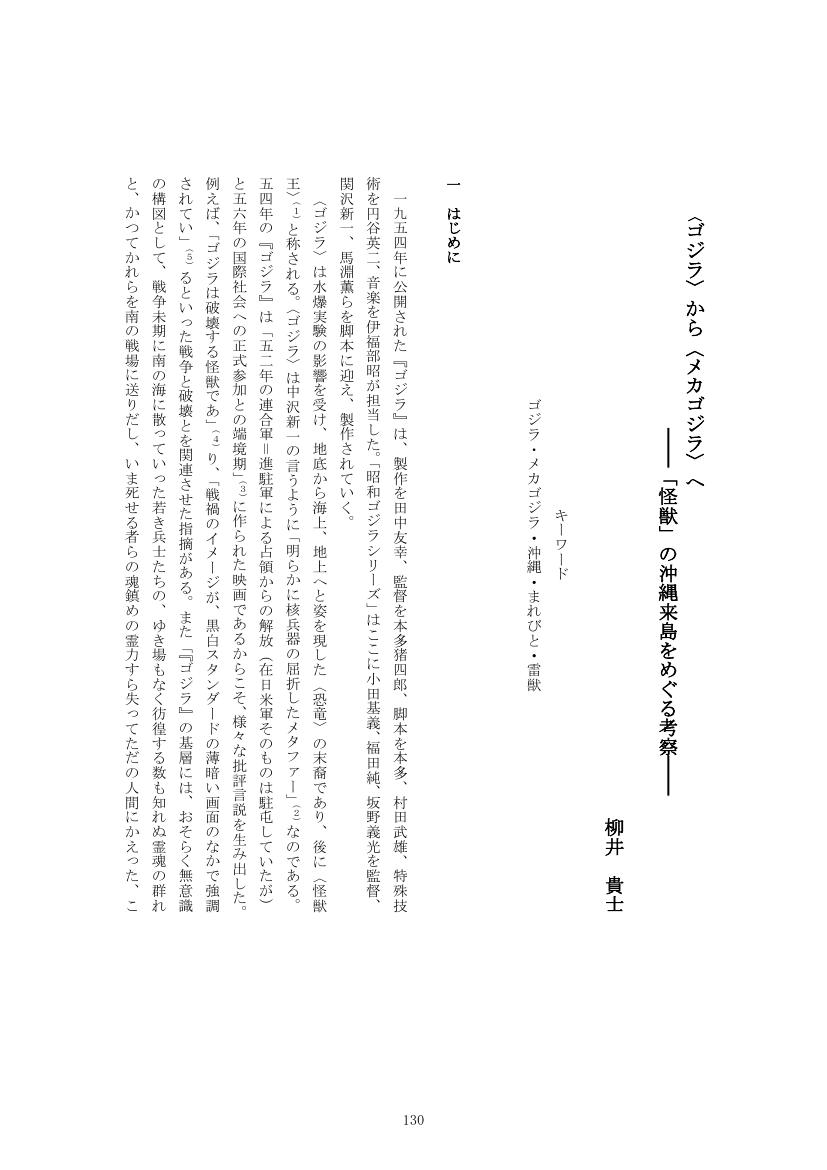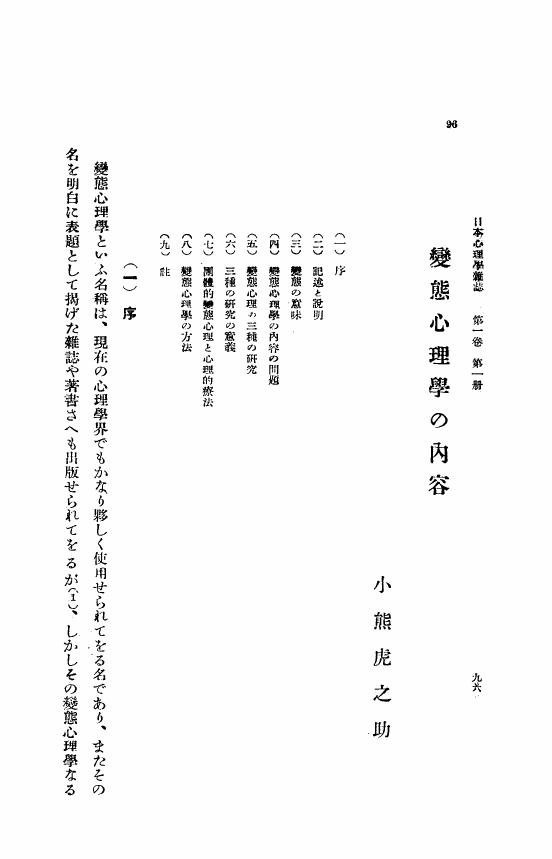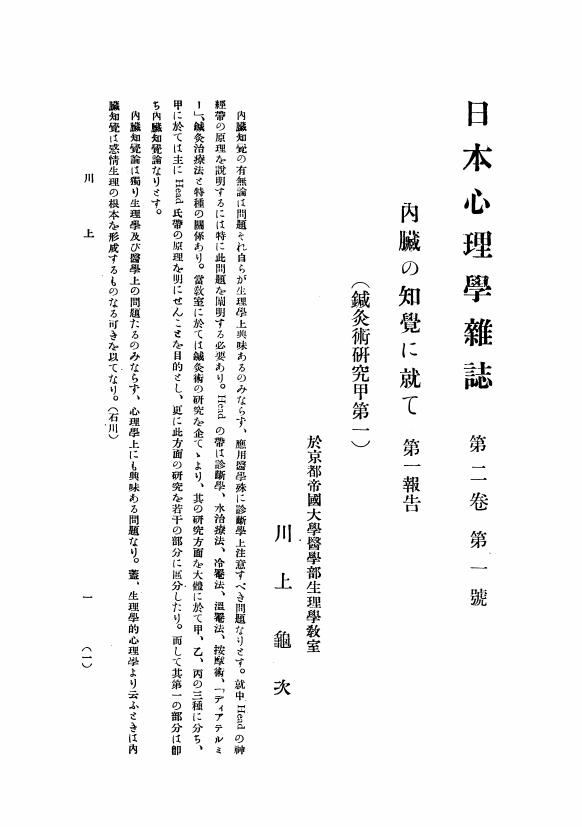2 0 0 0 OA 巻頭言
- 著者
- 有元 健
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.3-6, 2019 (Released:2019-10-21)
2 0 0 0 OA 「連帯」の光と影 第三世界都市バンドンにおける植民地主義とその脱却
- 著者
- 金 悠進
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.47-71, 2019 (Released:2019-10-21)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
1955年、アジア・アフリカ会議がインドネシアのバンドンで開催された。植民地主義に反旗を翻す舞台となった「バンドン」は、しばしば第三世界の連帯の象徴的記号として捉えられる。本稿は、このような反植民地主義の連帯としての「バンドン」イメージを相対化し、よりローカルな文脈から、異なる都市イメージの構築を目指す。具体的には、バンドンの若者たちによる文化実践がなぜ植民地主義の残影を引きずり、いかにしてナショナル・アイデンティティを喪失しつつも西洋の模倣から脱却していったのかを論じる。主にポピュラー音楽を中心に、近代美術やイスラームなどバンドンのローカルな日常の文化実践における特殊性/多様性に着目しつつ、アジア・アフリカ会議の「裏」舞台を描く。上記分析過程を通じて、「インターアジア」におけるカルチュラル・スタディーズの分析枠組みを提示する。 脱植民地主義を掲げる戦後最大の歴史的出来事として、アジア・アフリカ会議が植民地都市バンドンで開催されたという文脈は、現在に至るまで当該都市の文化実践を規定してきた。にもかかわらず、国家の共産主義化、脱植民地主義化と乖離するかのように、バンドンの若者たちが脱イデオロギー的な西洋志向の文化実践に傾注し続ける背景を、近代美術を事例に論じる。さらに、西洋模倣型の実践形態が都市における庶民的・国民的文化の周縁化、ひいては新たな植民地主義への構造的加担に帰結する背景を1970 年代のポピュラー音楽における対抗文化的実践から明らかにする。最後に、イスラームが新たな文化実践の代替的イデオロギーとして台頭することによる「新たな連帯」の萌芽を提示する。
2 0 0 0 OA 統制下の新聞報道について考える 『夢声戦争日記』を出発点に
- 著者
- 内藤 寿子
- 出版者
- アジア・文化・歴史研究会
- 雑誌
- アジア・文化・歴史 (ISSN:24239461)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.113-126, 2022 (Released:2022-03-01)
2 0 0 0 OA 江戸川乱歩の失われた恋愛と、汚された性欲 谷崎潤一郎の恋愛と性欲と比較して
- 著者
- 柿原 和宏
- 出版者
- アジア・文化・歴史研究会
- 雑誌
- アジア・文化・歴史 (ISSN:24239461)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.22-47, 2022 (Released:2022-03-01)
2 0 0 0 OA 〈ゴジラ〉から〈メカゴジラ〉へ 「怪獣」の沖縄来島をめぐる考察
- 著者
- 柳井 貴士
- 出版者
- アジア・文化・歴史研究会
- 雑誌
- アジア・文化・歴史 (ISSN:24239461)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.130-148, 2020 (Released:2020-09-07)
2 0 0 0 OA 日本占領下の北京における日・朝文学者の様相 中薗英助の出会った金史良
- 著者
- 彭 雨新
- 出版者
- 国立大学法人 大阪大学グローバルイニシアティブ機構
- 雑誌
- アジア太平洋論叢 (ISSN:13466224)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.135-146, 2022 (Released:2022-03-26)
This article focuses on the experience of a short stay in Beijing by the Korean writer Kim Sa-ryang(1914-1950?)on his way to escape from Japan and head for the Taihang Mountain region of China to participate in the Anti-Japanese revolution in 1945. According to the records of the Japanese writer Nakazono Eisuke, in May 1945, Kim Sa-ryang, who was about to leave the Japanese-occupied area, chanced to meet Nakazono, who was then a reporter of the Beijing Japanese newspaper East Asian News, at the Beijing Hotel. The two drank freely and talked deeply all night, which left an indelible mark in Nakazono's wartime memory and literary career. Kim Sa-ryang was a very important and special Korean writer in wartime Japan and his Japanese novel In the Light (1939) was once nominated for the Akutagawa Prize. He went to China's liberated areas to participate in the Anti-Japanese revolution in 1945, and reportedly died in the Korean War in 1950. Although Kim Sa-ryang and Nakazono Eisuke only talked for one night in Beijing, the latter had been repeatedly writing about the former in his novels, essays and memoirs from the early postwar period to the 2000s. Therefore, this article will comprehensively review the writings of Kim Sa-ryang by Nakazono Eisuke, analyze the image of Kim Sa-ryang described by Nakazono Eisuke by making reference to the relevant discussions of Korean literature researchers and literary critics Ahn Woosik and Paek Cheol, and then explore the heterogeneous “Korean experience” obtained by Nakazono Eisuke as a witness of the “All Black Age” in the history of literature in enemy-occupied Beijing.
2 0 0 0 OA 朱天心の《古都》における記憶と忘却 ―パリンプセスト、消去、在地性批判―
- 著者
- 呉 穎濤
- 出版者
- 国立大学法人 大阪大学グローバルイニシアティブ機構
- 雑誌
- アジア太平洋論叢 (ISSN:13466224)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.3-20, 2021-03-19 (Released:2021-03-19)
Abstract This essay addresses the problem of memory and forgetting in Chu Tien-hsin's novella “The Old Capital.” In “The Old Capital,” the heroine called “you” is a second-generation mainlander in Taiwan. With the transition of power from mainlander government to inlander government, the heroine has to face the problem of erasure of memory due to the political manipulation in the name of “localization” by the inlander government. This essay reads the heroine's status of existence illustrated in “The Old Capital” by using the critique of place-basedness, a key concept in Sinophone studies. Place-basedness refers to the complex but unique history of Taiwan as a place that allows pluralistic imagination of its inhabitants. By showing both the cultural and political sides of the heroine's peculiar status of existence in Taipei, which is as a minor within the periphery of the greater China, this essay aims to shed light on the tactics of historical narrative of individuals who cannot be identified by relatively stable concepts based on the discourse of “Chineseness,” such as nationalism and languages, thereby providing insight, namely tactics of political intervention of memory and identity formation, into understanding of minor Sinophone literatures.
2 0 0 0 OA アニメーションにおける通称「オバケ」に関する一考察~数学的・物理学的理論の観点から~
- 著者
- 佐分利 敏晴
- 出版者
- 日本アニメーション学会
- 雑誌
- アニメーション研究 (ISSN:1347300X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.3-12, 2021-03-31 (Released:2021-11-06)
- 参考文献数
- 8
アニメーションにおける通称「オバケ」は、作者がアニメーション制作において用いる、仮現運動や動きの錯覚を励起する意味の無い絵として緩やかに定義されてきた。しかし、その定義は生態心理学、数学、物理学の観点からも検証されるべきである。本論文では「オバケ」を以下のように分析し定義し直す。それらは錯覚や仮現運動を作るための意味の無い道具ではなく、「動きを同定するための知覚情報」そのものであり、十分な意味と内容を有しているものである。アニメーションの制作とは、動きを特定する情報を変換する作業であると考えられる。すなわち、制作される動きの情報はそれぞれの動きを時間によって微分した結果もたらされるものであり、それらは時間の矢に沿って並べられたいくつかのフレームにより、映像において再構築されるよう作られたものであると言えよう。そこに錯覚が入り込む余地はないだろう。たとえ一目見ただけでは何が描かれているか分からなくても、それらは制作者が発見した動きを構成するために必要不可欠な情報だと推測される。それは「生命の錯覚(The Illusion of Life)」ではなかろう。
2 0 0 0 OA セル画に関する現象学的・高分子化学的研究を目指して:視覚経験とその物質的リアリティー
- 著者
- キム ジュニアン 三俣 哲
- 出版者
- 日本アニメーション学会
- 雑誌
- アニメーション研究 (ISSN:1347300X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.13-23, 2021-03-31 (Released:2021-11-06)
- 参考文献数
- 23
本研究は、アニメ業界で1970年代から1990年代まで、演出・原画などの仕事に携わり活動した渡部英雄氏が、現役時代から保管していた絵コンテなど膨大な中間素材(以下、渡部コレクション)を本研究者らの所属大学に一任したことから始まる。我々は、アーカイブ化された渡部コレクションのなかで、損傷の危機に瀕しているセル画に注目し領域横断的研究に着手した。それぞれ材料化学とアニメーション研究を専門にする二人の著者は、セル画の保存・管理の意義、プラスティック素材であるセルロイドの開発と変遷の歴史、アニメーションにおける同素材の導入史を考察しつつ、渡部コレクションからのセル画2点に対する物理化学的分析を行った。本稿ではその研究成果を報告し、さらにセルというメディウムに基づいて産業化されたアニメーションを通して人間の視覚はどのように形成され変容されてきたのかという問題を提出し考察する。始まったばかりの研究ではあるが、ある種の文化資源として考えられるセル画の保存・管理に関する知見をアニメ業界をはじめ社会に提供し、同素材の遂行行為者的機能を物質的リアリティーという側面から理論化することを目指す。
2 0 0 0 OA シンポジウム1「日本のアニメーションの“はじまり”」
- 著者
- 木村 智哉 藤津 亮太 木船 徳光 野口 光一 津堅 信之
- 出版者
- 日本アニメーション学会
- 雑誌
- アニメーション研究 (ISSN:1347300X)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.55-75, 2018-03-01 (Released:2021-05-07)
2 0 0 0 OA 休憩制の電信能率に及ぼす影響
- 著者
- 淡路 圓次郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学雑誌 (ISSN:18841074)
- 巻号頁・発行日
- vol.T1, no.2, pp.218-268, 1923-04-10 (Released:2010-07-16)
2 0 0 0 OA 變態心理學の内容
- 著者
- 小熊 虎之助
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学雑誌 (ISSN:18841074)
- 巻号頁・発行日
- vol.T1, no.1, pp.96-128, 1923-01-01 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 26
2 0 0 0 OA 内臟の知覺に就て 第一報告 鍼灸術研究甲第一
- 著者
- 川上 龜次
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学雑誌 (ISSN:18841074)
- 巻号頁・発行日
- vol.K2, no.1, pp.1-27, 1920 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 25
2 0 0 0 OA 感性を反映した構図修正による写真品質向上システム
- 著者
- 家田 暁 琴 智秀 萩原 将文
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.4, pp.163-172, 2010 (Released:2011-03-01)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1 2
本論文では感性を反映した構図修正による,デジタル写真の品質向上システムを提案する.提案システムでは入力画像に適した構図を自動選択し,画像の構図を原画像の印象を保ちながら修正することで,画像の品質向上を行うことができる.修正は4 段階の処理によって行われる.まず,入力された画像から主となる顔,際立つ領域,三角部分,水平線,対角線,遠近法消失点の6 種類の構成要素が検出される.検出された各構成要素の位置や他構成要素との関係から,それぞれの構成要素に適すると考えられる出力構図案が計算される.次にそれらの構図案から,原画像の印象から大きく変わってしまう案が削除される.すなわち,画像に対する構成要素の位置が大きく移動する案が削除される.最後に,残った出力構図案の中から原画像の印象を最も保つことが可能な構図案,すなわち切り出す面積が最も小さい構図案が選択され,その構図案に従い画像の構図修正が行なわれる.ユーザアンケートによる2 種類の評価実験を行った.その結果,提案システムによってユーザにとって好ましい修正が行われること,また既存手法と比較しても好ましい修正が行われることが確認された.
2 0 0 0 OA 音声対話ゲームのためのCGキャラクタの反応的注意生成
- 著者
- 星野 准一 森 博志
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.20-28, 2009 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
近年,ゲームやテーマパークなどで,CGキャラクタと対話をすることでストーリーが進行する,音声対話ゲームが見られるようになってきた.このようなゲームでは,ユーザのストーリー体験を強化するために,自然で現実味のある対話を実現することが求められている.しかし,従来ゲームでは,ユーザの発話内容を認識する間CGキャラクタがレスポンスを返すことができないため,CGキャラクタの反応タイミングが遅く不自然に感じられるという問題があった.そのため,本論文では,ユーザの発話内容を理解し反応する熟考的反応だけでなく,会話状態に連動した注意動作や,ユーザの非言語情報を知覚し反射的に注意を向けるといった,反応的注意動作を生成する手法を提案する.最後に,提案手法を音声対話型ゲームに適用し,従来の音声認識の遅延によって発生していたCGキャラクタの反応動作の遅延が軽減され,CGキャラクタとの対話感が増すことを示す.
2 0 0 0 OA 龍安寺石庭における視覚的不協和について
- 著者
- 望月 茂徳 蔡 東生 浅井 信吉 王 雲 福本 麻子
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.102-110, 2010 (Released:2010-10-01)
- 参考文献数
- 12
UNESCO世界遺産にも登録されている龍安寺石庭は, 15個の石が無名の設計者により一見してランダムに配置されているが,石もしくは石群の配置は基本的に手前からみて奥が鈍角をなす不等辺三角形をなし,基本的に,三石もしくは三石群がそれより大きい一石群をなし,不等辺鈍角三角形が3回再帰的に繰り返される構造になっている.本論文ではまず, それぞれの石もしくは石群のサイズは1/f揺らぎもしくはZipfの法則に従っていることを算出した. さらに, より詳細な配置分析としてアイ・トラッキング実験を行い,石(もしくは石群)から石(もしくは石群)への視線の遷移をリンクとして計測した. 計測したデータよりホットスポット(視線注視分布)図の作成および視線の"PageRank"の算出によって, 視線軌跡ではわかりづらかった, 石庭鑑賞上の視線の乱れが起こる例外的石配置ルール出現箇所において, 視覚的不協和が使われている可能性が高いことを示した.
2 0 0 0 OA スカラ場・ベクタ場同時可視化のための流線自動生成の一手法
- 著者
- 古矢 志帆 伊藤 貴之
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.120-129, 2009 (Released:2009-10-09)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 4 5
スカラ場とベクタ場を同時に,かつ三次元的に可視化する試みは,さまざまな観点から研究の余地があると思われる.例えば気象シミュレーションの分野では現在でも,スカラ場(気温・気圧など)とベクタ場(風向)を二次元的な手法(断面上の等高線や矢印など)で可視化する事例が多い.しかし二次元的な可視化結果からは,気象現象の立体的なメカニズムを理解するのが難しい場合が多い.本論文では,等値面と流線を用いてスカラ場とベクタ場を同時可視化するための,流線自動選択手法を提案する.本手法ではまず,複数の等値面を選択表示する.続いて本手法では,多数の流線を一時的に生成し,それらの見かけを評価し,上位に評価された流線を選択表示する.その際に本手法は,等値面による遮蔽を低減すること,流れ場の特徴を示す渦などの現象を効果的に表現すること,を考慮して流線を選択する.結果として本手法は,視点に依存せずに等値面を選択し,視点に依存して流線を選択する.
2 0 0 0 OA 導電性布素材を用いた「着るピアノ」の設計と実現
- 著者
- 戸田 真志 秋田 純一 大江 瑞子
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.51-56, 2009 (Released:2009-08-12)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1 1
本稿では,ウェアラブル楽器の一環として,あるいはウェアラブルコンピューティング技術のファッション応用に対する具体的実現としての「着るピアノ」について,導電性布素材を用いた新しいアーキテクチャを提案する.提案するアーキテクチャでは「服としての一体感を演出するために,なるべく布素材を用いる」「機能分化により軽量化を図る」「意図しないシーンで音が出ることを防ぐ」「鍵盤レイアウトの自由度を向上させる」の特徴を有し,衣服としての着心地,着るピアノとしての操作性,デザインの自由度などについて大幅な改善を実現したものである.本提案は,「着るピアノ」の改良,ということのみならず,ウェアラブル基盤としての導電性布素材の新しい利用方法を模索するものとの位置づけも可能である.
2 0 0 0 OA 蛍光表示管を用いたボリュームディスプレイと表示データ生成ツール
- 著者
- 山本 欧
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.15-24, 2009 (Released:2009-06-02)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2 2
ボリュームディスプレイは,立体を3次元空間内に直接描画し表示するディスプレイであり,実体感のある立体表示が可能である.このため,科学だけでなくアートの分野においてもボリュームディスプレイの利用が期待される.しかし,従来のものは装置が複雑・高価格であり,アート分野での利用は進んでいない.本論文では,光学系の不要な単純な構造を持ち,市販部品から容易に構成可能なボリュームディスプレイ,およびそのための表示データ生成ツールの提案と実装について述べる.本ディスプレイは,往復運動する蛍光表示管(VFD)上に立体の断面を位置に応じて表示し,残像効果により立体表示を行う.これにより,単色で表示画像は小さいものの,鮮明な立体静止画像および動画像が表示できる.また,表示データ生成ツールは,表示エリアを立体的に指定するフレームにより,本ディスプレイのための表示データを一般の3Dモデリングソフトウェアを用いて容易に作成可能とするものである.