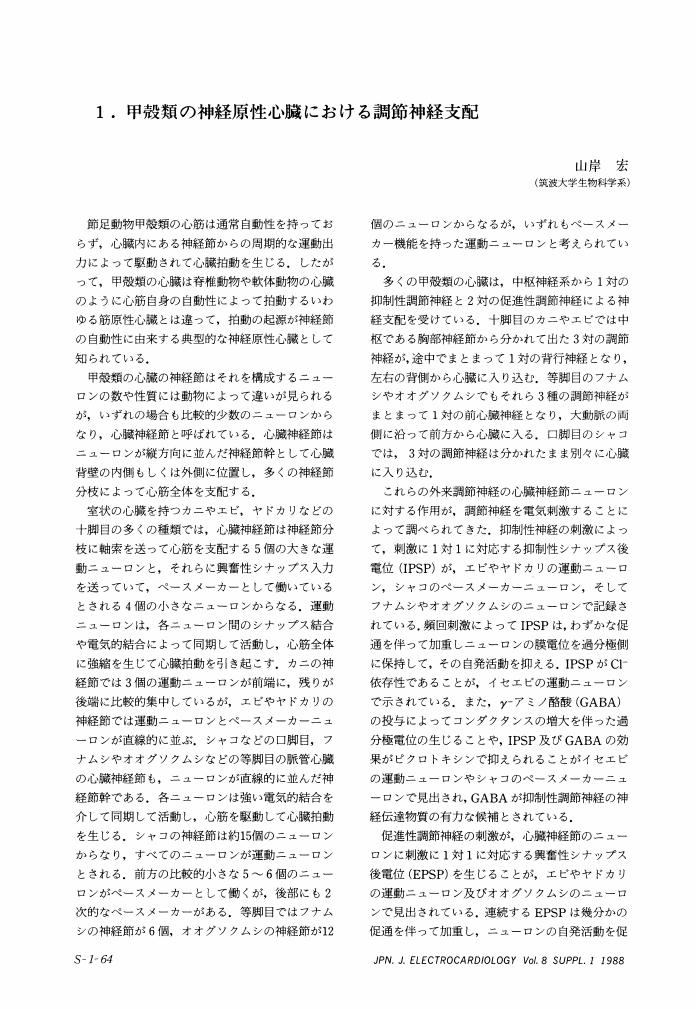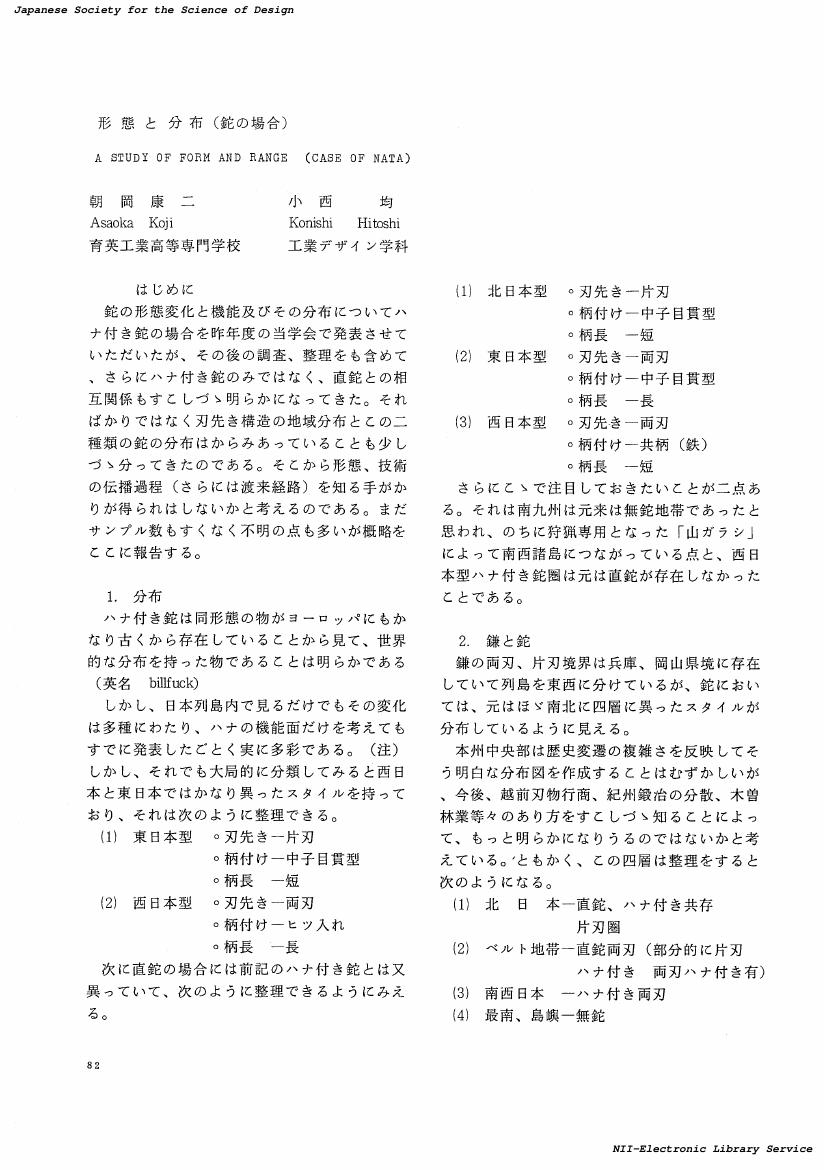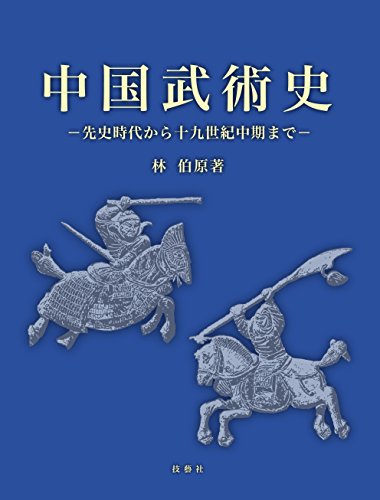2 0 0 0 OA 第14回比較心電図研究会 1.甲殻類の神経原性心臓における調節神経支配
- 著者
- 山岸 宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本不整脈心電学会
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.Suppl1, pp.64-67, 1988-04-30 (Released:2010-09-09)
2 0 0 0 OA 福島県産イナゴの放射性セシウム量および福島県のイナゴ食文化の存続可能性
- 著者
- 三橋 亮太 水野 壮 佐伯 真二郎 内山 昭一 吉田 誠 高松 裕希 食用昆虫科学研究会 普後 一
- 出版者
- [日本食品衛生学会]
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.6, pp.410-414, 2013 (Released:2014-05-12)
福島県では福島第一原子力発電所事故が発生してから,イナゴの放射線汚染を懸念してイナゴ食(イナゴを採集し,調理して食べること)を楽しむ人が減少した。そこで2011年,2012年に福島県各地で採取したイナゴに含まれる放射性セシウムを測定したところ,134Csと137Csの合計放射能濃度は,最高で60.6Bq/kgであり, 2012年に設定された食品中の放射性物質の新たな基準値である100Bq/kgを下回ることが示された。さらに,イナゴは一般的な調理過程を経ることによって,放射能濃度が15.8Bq/kg以下,未処理時の1/4程度まで低下することが示された。
2 0 0 0 OA 形態と分布 : 鉈の場合(第27回研究発表大会概要集)
- 著者
- 朝岡 康ニ 小西 均
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.1980, no.32, pp.82-83, 1980-10-25 (Released:2017-07-25)
2 0 0 0 OA 西川正雄先生のこと
- 著者
- 伊集院 立
- 出版者
- 現代史研究会
- 雑誌
- 現代史研究 (ISSN:03868869)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.75-83, 2008-12-26 (Released:2018-06-28)
2 0 0 0 支那軍はどんな兵器を使ってゐるか
- 著者
- Katsuya Saito Takahiro Miyata Tsubasa Miyauchi Takaki Ichikawa Keita Mayanagi Joji Inamasu Masashi Nakatsukasa
- 出版者
- The Japanese Society for Neuroendovascular Therapy
- 雑誌
- Journal of Neuroendovascular Therapy (ISSN:18824072)
- 巻号頁・発行日
- pp.cr.2022-0009, (Released:2022-07-22)
- 参考文献数
- 20
Objective: We describe a rare case report of micro-arteriovenous malformation (micro-AVM) treated by the endovascular approach in addition with literature review.Case Presentation: A 12-year-old boy presenting with a spontaneous intracerebral hematoma in the left occipital lobe underwent conventional diagnostic workups. The results of initial catheter angiography were considered to be equivocal as the AVM. Superselective angiography (SA) demonstrated a micro or small AVM (single feeder and single drainer type) with an aneurysmal dilatation. Immediate transarterial embolization (TAE) might fail to occlude the whole of nidus area completely, and subsequently, we switched to the surgical exploration of AVM lesion. Intraoperative findings demonstrated that the whole of AVM lesion had already been occluded completely, indicating the complete occlusion by TAE only. Pathological findings of the surgical specimen showed an aneurysmal dilatation was a venous aneurysm with vulnerable vascular wall structure, which was certainly the source of bleeding. Based on the above results, the retrospective revaluation of superselective angiogram permitted us to understand that the nidus of AVM was micro nidus type and TAE had resulted in the complete nidus occlusion.Conclusion: SA is the most useful diagnostic modality to clarify the angioarchitecture of micro-AVM and AVM-related aneurysms. If SA is successfully performed and relatively safe TAE is expected to be possible, the subsequent attempt to do curative embolization as a first-line treatment may be worthy of consideration. However, the surgical procedure should be fully reserved for the possible incomplete obliteration and hemorrhagic complications.
2 0 0 0 OA マムシ咬傷後に横紋筋融解による急性腎不全を併発した2症例
- 著者
- 三浦 洋 早野 恵子 井野辺 義人 福井 博義
- 出版者
- 社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析療法学会雑誌 (ISSN:09115889)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.5, pp.651-655, 1991-05-28 (Released:2010-03-16)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 2
マムシ咬傷による横紋筋融解症から急性腎不全を来たし, 救命し得たもののDIC, 消化管出血等の合併症を伴って重篤な経過を辿った2症例を報告する. 両症例共に受傷後, 広汎な局所病変を呈し, 入院時検査においてBUN, creatinineの上昇と共にLDH, CPKなどの筋由来酵素群の上昇がみられ, さらに血中, 尿中のmyoglobinの高値も認めたことから, rhabdomyolysisによる急性腎不全を発症したと考えられた. 症例1は蛇毒中の血液凝固因子の作用によりDICを併発したことから, また症例2は大量の消化管出血を伴ったことから, いずれも重篤な経過を辿った. 局所病変の強いマムシ咬傷例は, 重篤な合併症に注意して診療にあたるべきと思われた.
2 0 0 0 OA 韓国 海洋廃棄物及び海洋汚染堆積物の管理に関する法律の制定
- 著者
- 中村穂佳
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 283-1), 2020-04
2 0 0 0 中国武術史 : 先史時代から十九世紀中期まで
2 0 0 0 OA 宝塚歌劇における 2・5 次元
- 著者
- 鈴木 国男 Kunio Suzuki
- 雑誌
- 共立女子大学文芸学部紀要 = The Kyoritsu journal of arts and letters
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.37-49, 2020-02
- 著者
- 新倉 貴仁
- 出版者
- 成城大学大学院文学研究科
- 雑誌
- コミュニケーション紀要 = Seijo communication studies (ISSN:02887843)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.189-199, 2020-03-10
2 0 0 0 OA LLC コンバータのソフトスイッチング成立条件について
- 著者
- 浦山 大 平地 克也
- 出版者
- パワーエレクトロニクス学会
- 雑誌
- パワーエレクトロニクス学会誌 (ISSN:13488538)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.25-33, 2015-03-31 (Released:2016-08-03)
- 参考文献数
- 6
The switching of LLC converter becomes hard switching at the time of overload. In this study, we elucidated the mechanism of hard switching and the current path. The reason of hard switching is the commutation of magnetizing current to the secondary side. It is possible to make a judgement whether overload or not from the voltage value at the end of resonance. Voltage value can be obtained from the circuit constants. In this way, it becomes possible to judge the success or failure of soft switching from the circuit constants.
2 0 0 0 OA 刑訴法における「強制処分」についての一考察 : 「強制処分」の意義に関する議論を中心に
- 著者
- 金子 章
- 出版者
- 横浜国際経済法学会
- 雑誌
- 横浜国際経済法学 (ISSN:09199357)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.1-26, 2011-12-25
2 0 0 0 OA 現代日本の宗教と法
- 著者
- 平野 武
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, pp.71-85, 2003-10-20 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 24
2 0 0 0 OA パネルシアターの歴史(1) : 創始者古宇田亮順とパネルシアター
- 著者
- 藤田 佳子 Yoshiko FUJITA
- 雑誌
- 淑徳短期大学研究紀要 = Bulletin of Junior College of Shukutoku (ISSN:02886758)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.181-196, 2013-02-25
パネルシアターは1973年に古宇田亮順が創始して40年が経ち、現場では多方面で活用されてきているが、研究の場ではまだまだ絵本や紙芝居と比べて論文や著作が少ない。ここでは、パネルシアターが誕生するまでを古宇田亮順の半生を振り返ることによりまとめた。第二次世界大戦の少し前に上野の寺で生まれ、物がない時代に育った古宇田は幼少期、工夫をして遊ぶことや紙芝居の面白さに触れる。大正大学に入学してからは、児童研究部に所属し、子どもたちの幸福のために熱心な部員とともに活動した子ども会活動の中で、人形劇等の上演を通して喜んでもらえること、その喜びを共有することを学んだ。そのためにはたゆまぬ努力と研究があった。現状だけでは満足しない古宇田は、失敗を重ねながら遂にパネルシアターを生み出した。そこには、作画の松田治仁との出会いも大きく関わっている。松田の絵を活かすために、そしてお話の構成を膨らますためにと探した結果、1972年パネルシアターに適した素材、不織布(三菱製紙MBSテック130番、180番)を見つける。その不織布をのちに「Pペーパー」と名付ける。その後、30以上の作品を製作した後、1973年に「パネルシアター」と命名して、発表する。このパネルシアターの発見には、古宇田の「人に喜んでもらいたい」「必要なものは必ず見つかるという信念」をもった生き方・考え方があったからこそ生まれたのだと確認した。
2 0 0 0 OA 鉄筋コンクリート柱はり接合部論争の結末 ニュージーランド人による幕の引き方
- 著者
- 青山 博之
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.9, pp.5-16, 1992-09-01 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 2
アメリカ, 日本, ニュージーランドでの鉄筋コンクリート柱はり接合部の耐震設計方法の不統一に端を発した論争を終結させるための三国協力研究が, 1991年に終了した。この総説は, 柱はり接合部論争を生むに至った三国の研究および設計法開発の経緯を明らかにし, 協力研究の内容を概観し, その結論を各国がそれぞれの国の設計規準にどのように生かそうとしているかについて述べたものである。とくにニュージーランドにおける最近の動きのなかに, 実験式 (経験式) から理念に基づく式 (マクロモデルによる理論化) へという研究動向の転換を感じ取ったものである。
2 0 0 0 OA 『若きヴェルターの悩み』におけるオシアンの歌
- 著者
- 林 久博
- 雑誌
- 国際教養学部論叢 = CHUKYO UNIVERSITY SCHOOL OF INTERNATIONAL LIBERAL STUDIES
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.185-186, 2012-03-31