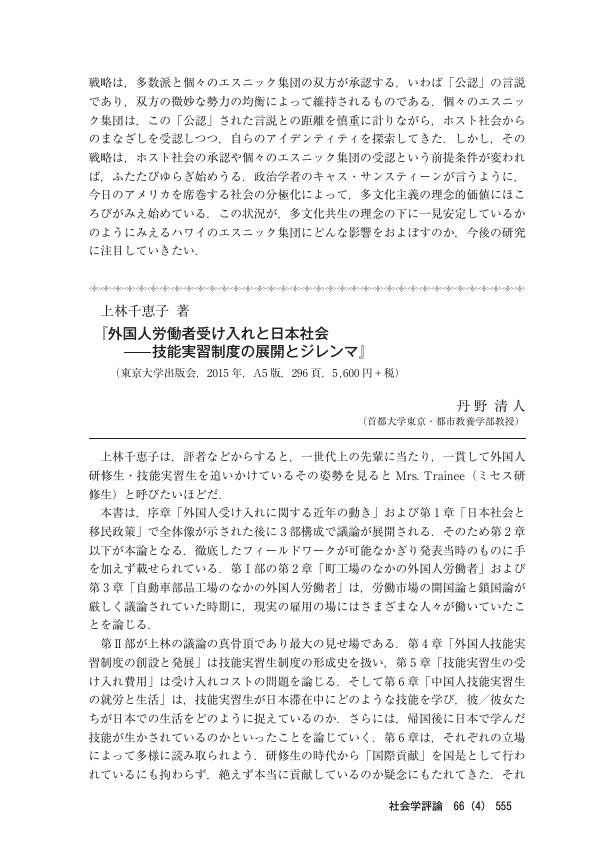- 著者
- 岩城 千早
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.306-320,395, 1987-12-31
本稿は、G・H・ミードの仕事を捉え、その意義を理解していくため、その手掛かりとして、彼の「社会的行動主義」に焦点をあて、そこに彼独自の視点を探る試みである。ミードはシンボリック・インタラクショニスト等によって最も積極的に言及され、「自己」の問題に深く取り組んだ研究者として主にクローズアップされてきた、その一方でまた、彼の「社会的行動主義」が、ワトソンの「客観的に観察可能な行動」のみを扱うという方法論に対して、「客観的に観察不可能なもの-心的なもの」を強調し、観察可能なものを通してそこに到ることを主張する方法論的アプローチとして一般に知られてきた。この重要性を指摘し、「社会的行動主義者としてのミード」を強調する向きも、昨今では自己論議の一方に見ることができる。だが、こうしたミードの主張が彼の仕事をどのように性格づけるものであるのか、という問題は未だ議論の余地を残しているように思われる。社会的行動主義によって、ミードは、観察不可能な領域を擁護したという点で、個人の内的経験に深く踏み込んでいったのでもなければ、また観察可能なものを通してのアプローチを主張したという点で、心理学の自然科学化志向に根ざすワトソンの客観的観察可能性の要求を引き継いだのでもない。「ワトソンの行動主義よりも適切な行動主義」を展開しようとするミードの論理を辿るならば、社会的行動主義は、われわれの相互行為のプロセスをテーマ化するミード固有のパースペクティブとして浮かび上がって来る。
4 0 0 0 行為の記述・動機の帰属・実践の編成
- 著者
- 前田 泰樹
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.710-726, 2005-12-31
- 被引用文献数
- 2 2
社会学にとって人々の行為を記述するとはどのようなことだろうか.この問いは2つの論点に集約されてきた.すなわち「どのような記述をしても不完全さは残るのではないか」という記述の可能性への問いA, 「社会学的記述はメンバーによってなされる記述とどのような関係にあるべきか」という記述の身分に関わる問いBである (Schegloff 1988) <BR>本稿では, まず問いAに対し, 記述の懐疑論には採用し難い前提が含まれていることを論証する.さらに, その前提のもとで見落とされてきた論点として, 実践において行為を記述することは, それ自体, メンバーシップカテコリーへと動機を帰属させる活動でありうる, ということを示す.<BR>次に問いBに対し, H.サノクスたちによる社会学的記述の方針を検討する.まず, メンバーによる記述はそれ目体手続き上の特徴を備えている, ということを確認し, その実践の手続き上の特徴によって制約を受けつつ社会学的記述を行う, という方針を検討する.さらにその検討をふまえて実践の分析を行い, 行為を記述することが動機や責任の帰属といった活動であること, また, その活動が実践の編成にとって構成的であること, を例証する<BR>要約するならば, 行為を記述することは, それ自体, 動機や責任の帰属といった活動であり, その他の様々な実践的活動に埋め込まれている.本稿では, こうした実践の編成そのものを記述していく方針の概観を示す.
4 0 0 0 OA 上林千恵子著『外国人労働者受け入れと日本社会――技能実習制度の展開とジレンマ』
- 著者
- 丹野 清人
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.555-557, 2015 (Released:2017-03-31)
4 0 0 0 家族の個人化(<特集>「個人化」と社会の変容)
- 著者
- 山田 昌弘
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.341-354, 2004-03-31
- 被引用文献数
- 1 13
近代社会においては, 家族は国家と並んでその関係が選択不可能, 解消困難という意味で, 個人化されざる領域と考えられてきた.この2つの領域に, 選択可能性の拡大という意味で個人化が浸透していることが, 現代社会の特徴である.<BR>家族の個人化が日本の家族社会学者の間で考察され始めるのは, 1980年代である.それは, 家族の多様化という形で, 家族規範の弱体化が進んだことの反映である.<BR>考察に当たって, 2つの質的に異なった家族の個人化を区別することが重要である.1つは, 家族の枠内での個人化であり, 家族の選択不可能, 解消困難性を保持したまま, 家族形態や家族行動の選択肢の可能性が高まるプロセスである.<BR>それに対して, ベックやバウマンが近年強調しているのは, 家族関係自体を選択したり, 解消したりする自由が拡大するプロセスであり, これを家族の本質的個人化と呼びたい.個人の側から見れば, 家族の範囲を決定する自由の拡大となる.<BR>家族の枠内での個人化は, 家族成員間の利害の対立が不可避的に生じさせる.その結果, 家族内部での勢力の強い成員の決定が優先される傾向が強まる.家族の本質的個人化が進行すれば, 次の帰結が導かれる. (1) 家族が不安定化し, リスクを伴ったものとなる. (2) 階層化が進展し, 社会の中で魅力や経済力によって選択の実現率に差が出る. (3) ナルシシズムが広がり, 家族が道具化する. (4) 幻想の中に家族が追いやられる.
4 0 0 0 日常経験とシステム理論 (<特集>日常経験と理論)
- 著者
- 佐藤 嘉一
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.35-44,129*, 1986-06-30
日常経験、日常知、日常生活を改めて見直す動きが、近年社会学、哲学、言語学などの諸専門的学問分野で盛んである。社会学の分野では、とくにエスノメソドロジー、象徴的相互作用論、現象学的社会学などの<新しい>社会学が日常生活を問題にしている。本稿で問題にしている事柄は、次の三点である。<BR>一、 社会学の内部で日常経験の世界に関心をむけさせる刺激因はなにか。日常経験へと志向する社会学が<新しい>と呼ばれるのはなぜか。日常経験論とシステム理論とはどのような問題として相互に関連するのか。<BR>二、 一で明らかにした<科学の抽象的現実>と<生活世界の具体的現実>との<取り違え>の問題を、シュッツ=パーソンズ論争を例にして検討する。<BR>三、 ルーマンのシステム理論においても、<科学の自己実体化>の角度から二の問題が論じられている。ルーマンの論理を検討する。
4 0 0 0 OA ルーマンの変貌
- 著者
- 馬場 靖雄
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.17-31, 1988-06-30 (Released:2009-11-11)
- 参考文献数
- 59
従来「解釈学のシステム理論版」だと考えられてきたルーマン理論は、自己言及概念の導入によって大きく変貌した。しかもそれは理論の内容においてのみではない。ルーマン理論は閉じられた自己同一的な体系から、常に自己差異化する運動体へと変化したのである。それゆえ本稿のタイトルは、第一にルーマンは変ったという、第二にしかも今なお変り続けているのだという、二重の含意をもつことになる。この二重の変貌とその帰結を粗描することが本稿の目的である。その帰結とは、社会学の営為全体に対する新しい視角に他ならない。従来「パラダイム」について論じられる時、また「グランド・セオリー」に対して「中範囲理論」の重要性が主張される (あるいは、その逆) 時、一般理論/実証研究というヒエラルヒーがまったく自明視されてきた。理論/実証の往復運動という主張も、このヒエラルヒーを前提としたものであった。これらに代って、理論と実証が相互に反転し続ける循環運動が登場する。また、社会学と社会の関係も、理論とその対象という単純な関係としてではなく、相互に造り/造られるというループのなかで把握されることになる。ルーマンの「システム理論のパラダイム転換」がもたらすのは、新たな内容のパラダイムではなく、パラダイムについて語るのを可能にする思考前提の転換である。それはいわば、パラダイム転換のパラダイム転換なのだ。
4 0 0 0 OA 包摂/排除の社会システム理論的考察
- 著者
- 後藤 実
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.324-340, 2012-12-31 (Released:2014-02-10)
- 参考文献数
- 42
とくに1990年代以降, 多様な分野で社会的排除に関する研究が活性化し, 分析の視座が揃いつつある. そして, 「排除から包摂へ」という方向性が提示されている.本稿では, 社会システム理論に依拠することで, 包括的に近代社会における包摂/排除の形成を考察し, 社会政策学的な関心から行われている研究の不備を補う. そこで, 社会システム理論の観点から包摂問題を論じたT. パーソンズとN. ルーマンの理論を検討する. 両者の議論の吟味を経て, 機能分化した近代社会は, 包摂原理 (形式上の包摂原理) によって存立しており, そのもとで, 組織が排除・選抜を行うことで, 集合的な成果を確保し, 存続していること (作動上の包摂原理) が明らかとなる.ルーマンは, 排除を主題化しつつ, パーソンズ理論の不備, 欠点に対処した. とはいえ, 作動上の論理に即して包摂/排除と平等/不平等とを直接的に関連づけていないという問題点がルーマンの議論に関して指摘できる. そこで本稿では, 機能としての平等/不平等の区別に着目したうえで, 排除のコミュニケーションを問題化し, これが包摂/排除の調整 (調整上の包摂原理) に関与することを近代における包摂原理の複数性に即して考える.近代社会は, 形式上の包摂原理を参照して, 作動上の包摂原理を反省し, 存続に関わる包摂/排除を調整することで, 持続可能性を強化すると最終的に結論づける.
4 0 0 0 OA 障害者/健常者カテゴリーの不安定化にむけて
- 著者
- 後藤 吉彦
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.400-417, 2005-03-31 (Released:2010-04-23)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1
本稿はまず, 身体的損傷 (インペアメント) ではなく社会的障壁こそが障害者にとっての問題=障害 (ディスアビリティ) であると主張する「障害の社会モデル」を紹介し, その功績と意義を確認する.そのうえで, 「社会モデル」に内在する問題-身体・インペアメントについての「生物学的基盤主義」, ひとを障害者/健常者とカテゴリー化することを容認するアイデンティティ・ポリティクス-を批判する.そして, それを補うべく, 障害学, 社会学に必要とされるのは, 障害者/健常者カテゴリーを不安定化させるような取り組みであると指摘し, そのためには「基盤主義」を徹底的に問いなおし, “障害者の身体” や “健常な身体” という概念を脱自然化させて捉えなおす視点が重要であると主張する.本稿の後半では, “健常な身体” の不安定さ, 不可能性を論じたM. Shildrickの著作をとりあげ, さらに, 彼女の議論を参照しながら, 障害者の〈逸脱〉した身体を健常者の〈標準〉なものに近づけるべくおこなわれるリハビリや整形治療について検証する.
4 0 0 0 OA 中野卓編著 口述の生活史
- 著者
- 鶴見 和子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.73-75, 1982-03-31 (Released:2009-10-19)
4 0 0 0 OA The Intermediary Groups in 1791
- 著者
- Shigeki TOMINAGA
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- Japanese Sociological Review (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.509-523, 2000-03-31 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 33
フランス革命は近代の政治文化に大きな影響を及ぼしたが, とりわけ社会学にとって見逃せないのは, 1791 年に立憲議会が取った中間集団にかんする一連の法的措置である.すなわち同年 3 月にはこの国に伝統的に存在してきた同業組合が廃止され, 6 月には労働者の新たな団結が禁止されることは, のちの労働運動史に悪評を残しているが, これらほどには知られていないものの, 5 月と 9 月には「民衆協会」と呼ばれる市民の集会の活動を制限する法令も可決されていたのだった.このときの議会の内外の言説からうかがえるのは, 新たに再生した社会で中間集団が果たしうる役割への, 革命期の人びと (そしておそらくは近代人全般) の無理解ないし敵意にほかならない.個人と全体社会とのみで成り立つ彼らの社会観のなかに中間集団が占める位置はありえなかった.こうして旧来の共同体は完全に消滅すると同時に, 新しく模索されるべき公共空間への道はほとんど途絶えてしまう.この消失と途絶は間接的あるいはネガティヴな意味で 19 世紀以降の社会学の生成と展開の出発点を用意するものであった.もっとも, 社会学の出発点としてのフランス革命に注目する社会学者のうちには, 事実の誤認や規範との混同を犯している者も少なくない. 1791 年の中間集団の運命の根抵にあるものを明らかにし, そこから社会学史の認識に修正を加えることこそが, あらためて公共性の社会学を構築するためにぜひ望まれるのである.
- 著者
- 崎山 治男
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.804-820, 2007-03-31
- 著者
- 佐藤 郁哉
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.346-359,481, 1991-03-31
本論文は、もっぱらトマスとズナニエツキのテクストに沿って、状況の定義概念の初期の定式化とその後の変遷をあとづけ、この概念が、行為主体と「構造」の関連を明らかにする上でもつ「感受概念」としての潜在力を明らかにする。<BR>社会学におけるスタンダードな用語の一つである「状況の定義」は、これまで主に社会的行為の主意主義的な側面を表現する代表的な概念として取り扱われてきた。しかしながら、この概念の初期の定式化の歴史をたどってみると、「状況の定義」は、行為に対する社会文化的な構造の規定性を示す際にも使われていることがわかる。とりわけトマスは「状況の定義」を多義的に使用しているが、これは、様々な行為主体と多様な状況との関連を実証研究を通して明らかにしていく上で彼が用いた効果的な戦略の一つであると考えられる.この「状況の定義」の一見相矛盾する多義的な用法の解明は、現在さまざまな形で試みられているマイクロ社会学とマクロ社会学の統合を進める上で、一つの有力な手がかりを与えてくれる。
- 著者
- 金丸 由雄
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.2-19, 1970-12-30
In his short paper on <I>ASR</I>, 1936, Merton listed extensively various factors to cause unanticipated consequences in purposive social action, and showed a few cases in which certain patterns can be identified among anticipation, action and consequences. This topic was later developed into a Chapter in his <I>Social Theory and Social Structure</I> (1957) as "The Self-Fulfilling Prophecy". <BR>Merton's original paper is important at least in the following senses : Unanticipated consequences are already emerging in anticipation before execution of action, and in some cases, certain patterns among anticipation, action and consequences can be traced. <BR>In order to further develop this topic, which had been suggested by Merton in such extensive scopes, it should be necessary to coordinate the problems from certain view point. The writer of this paper tries to do so, firstly, by reviewing them in terms of role differentiation into "prophet", "actor" and "observer" for anticipation, action and consequences respectively. Then, he focusses those cases enumerated by Merton on the uncertain nature of expectation of actor in anticipating consequences, and points out the peculiar characteristics in the "prophecies" and "basic value" cases as definition of the situation by others. This is the process for the actor to overcome the uncertainty in his expectation of the consquences of the contemplated action. Another possibility to overcome this uncertainty is suggested. It is called "auxiliary means" to strengthen those means already in hand with the uncertain expectation of consequences kept uncertain. With this "auxiliary means" corresponds "auxiliary purpose", which shall be instrumental in producing unanticipated consequences for actor not only in the new "Auxiliary value area" but also in the "original value area" as both are necessarily interrelated. Two propositions are made at the end : First for actor's tendency to depend on the definition of situation provided by others, and Second for actor's tendency to rely on the "auxiliary means" in his uncertain anticipation.
- 著者
- 野村 一夫
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.506-523, 2008-03-31
私は1990年代から社会学のテキストとウェブの制作に携わってきた.その経験に基づいて,2つの問題について論じたい.第1に,社会学テキストにおいてディシプリンとしての社会学をどのように提示するべきか.第2に,社会学ウェブのどこまでが社会学教育なのか.そして,それぞれの問題点は何か.テキスト制作上のジレンマや英語圏で盛んなテキストサポートウェブなどを手がかりに考えると,意外に理念的問題が重要であることに気づく.社会学教育には2つの局面があり,それに対応して,2つの社会学教育的情報環境が存在する.社会学ディシプリン的知識空間と社会学的公共圏である.テキストとウェブという社会学教育メディアも,この2つの局面に対応させて展開しなければならないのではないか.そう考えると,現在の日本社会学において「社会学を伝えるメディア」の現実的課題も見えてくる.
4 0 0 0 OA Laudanの研究伝統論による社会学理論発展法の考察
- 著者
- 太郎 丸博
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.41-57, 2006-06-30 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
1970年ごろに米国で発達した理論構築の考え方は, 理論に対する1つのアプローチを確立した.しかしそれは, 学説研究の価値を不当に低く評価することになっている. Laudanの議論に従えば, 研究伝統の抱える概念的問題を解決したり, 社会学全体を見渡して複数の研究伝統の発展の歴史を概観したり, その長短を判断することを通して, 学説研究は理論を発展させることができる.さらに研究伝統を深く学ぶことで, 解くべき問題をしばしば発見することができるし, 概念的問題の解決の手がかりも, しばしば学説の中にある, しかし, 学説だけを研究しても理論の発展は難しい.概念的問題は経験的問題と密接に連動しており, 経験的問題の解決は, データの収集・分析と不可分に結びついている.概念的問題と経験的問題を同時に追求しなければ, 理論の発展は困難である.理論を発展させるためには, 既存の研究伝統を深く学ぶと同時に, 何らかの経験的問題を追求することが必要である.そのためのコツをあえていうならば, デリベーションと「よい」集団に属して研究することが考えられる.
4 0 0 0 社会科学的概念としての<情報>について : 社会情報学序説
- 著者
- 中野 秀一郎
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.57-70, 1971-07-30
- 被引用文献数
- 1
In the writer's view, the Science of Human Society is divided into four sub-categories : <BR>the science of material property (roughly parallel to economics) the science of social power (roughly parallel to political science) <BR>the science of human bonds (roughly parallel to sociology in the narrow sense of the word) <BR>the science of social information (roughly parallel to culture sciences).<BR>This paper is an attempt to frame a rudimentary formulation of the science of social information as a social science discipline. There is yet no such a trial as to unfold a systematic theory of social information, though, as we see, much research materials as well as theoretical contribution is accumulated in the field of the study of social information phenomena. <BR>The integral theory of social information must include all the theoretical achievement in the study of mass communication, information system science such as MIS, NIS, as well as Marxian ideology theory, Weberian religious sociology, Mannheim's sociology of knowledge, logics, liguistics and structuralism. <BR>The theoretical sub-division of the science of social information is into two : <BR>' object' science type ; according to the kind of social information analyzed<BR>, 'method' science type ; according to the kind of the process in which information is produced, exchanged, accumulated, transformed and consumed. <BR>The fundamental difficulty in this 'underdeveloped' science, in the writer's view, are as follows : <BR>(i) theory-building concerning the possibility and the form of the existence of social information (or human knowledge); the writer defines social information as the total information factual as well as imaginary about the environments in which social actor individual as well as collectivity acts. He thinks that the approach must be biological, neurological, psychological and sociological. <BR>(ii) categorization of various social information ; the writer thinks it is productive to use the categorization, namely cognitive, cathectic, evaluative and directive. <BR>(iii) communication and media are also the items demanding the integral theory. <BR>Seeing the contemporary society, the important problems of social information phenomena, in the writer's opinion, are as follows : <BR>(i) micro information phenomena v. macro information phenomena, concretely how the personal, individual information converts itself into the social, collective decision ? <BR>(ii) elite or professional information v. mass or non-professional information, concretely how democracy is possible with specialization in treating social information ? <BR>(iii) rational, cognitive information v. irrational, evaluative information <BR>(iv) the technical aspect v. the semantic aspect of information <BR>(v) the majority information v. the minority information <BR>Though the points above mentioned do not exhaust all the important problems concerning social information phenomena, the paper being a introductory formulation of the science, further discussion is to be postphoned for the next opportunity.
- 著者
- 三谷 はるよ
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.32-46, 2014
本稿の目的は, 「市民活動参加者の脱階層化」命題が成り立つかどうかを検証することである. すなわち, 資源のある人もない人も等しく市民活動に参加するような状況に変化しつつあるのかどうかを検討する. そのために本稿では, 1995年と2010年に実施された全国調査データであるSSM1995とSSP-I2010を用いて, 社会階層と市民活動参加の関連の動向に注目した時点間比較分析を行った.<br>分析結果は以下のとおりである. 第1に, 1995年も2010年も変わらずに, 高学歴の人ほど市民活動に参加する傾向があった. 第2に, 1995年では高収入や管理職の人ほど市民活動に参加する傾向があったが, 2010年ではそのような傾向はなかった. 第3に, 1995年では無職の人は市民活動に参加する傾向があったが, 2010年では逆に参加しない傾向があった. 本稿から, 高学歴層による一貫した市民活動への参加によって教育的階層における「階層化」が持続していたこと, 同時に, 中流以上の層や管理職層, 無職層といった従来の市民活動の中心的な担い手の参加の低下によって, 経済的・職業的階層における消極的な意味での「脱階層化」が生じていたことが明らかになった.
- 著者
- 京谷 栄二
- 出版者
- 日本社会学会 ; 1950-
- 雑誌
- 社会学評論 = Japanese sociological review (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.338-340, 2016
- 著者
- 松本 康
- 出版者
- 日本社会学会 ; 1950-
- 雑誌
- 社会学評論 = Japanese sociological review (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.256-258, 2016
- 著者
- 石田 淳
- 出版者
- 日本社会学会 ; 1950-
- 雑誌
- 社会学評論 = Japanese sociological review (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.182-200, 2016