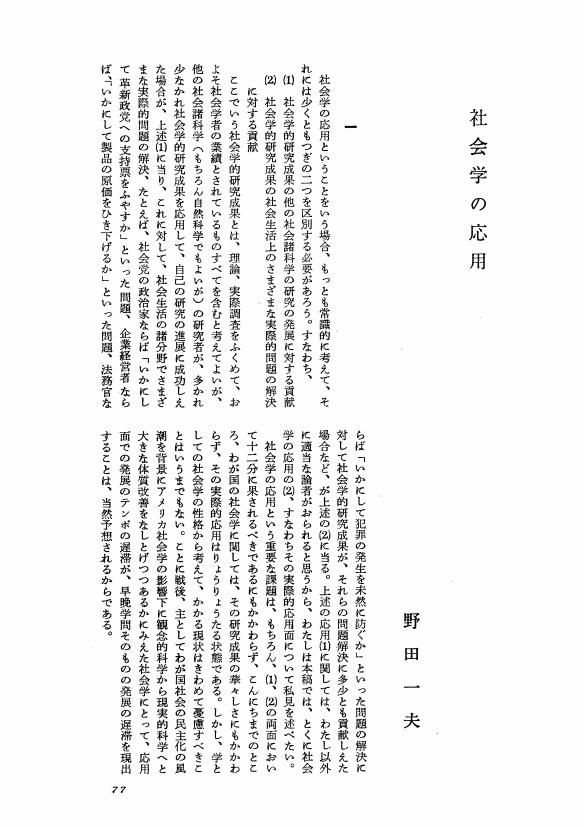- 著者
- 麦山 亮太
- 出版者
- 日本社会学会 ; 1950-
- 雑誌
- 社会学評論 = Japanese sociological review (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.248-264, 2017
- 著者
- 小杉 礼子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.355-369, 2004-03-31
- 被引用文献数
- 1
本稿では, まず, オランダの研究者が設定した集団主義-個人主義の尺度を用いて, 日本の若年大卒者が雇用形態によって職場で求められる個人主義的働き方の程度に違いがあるか否かについて, 大量質問紙調査結果から検討した.ついで, 非典型雇用においては, 一定の職業能力獲得・発揮が見込まれる職務であるか否かが, 個人主義的働き方の実現を左右するという見方から, 非典型雇用での職業能力の獲得・発揮状況を, 別の実態調査から雇用形態別に検討した.<BR>非典型雇用に流入する若年者には個人主義的志向が強いことは指摘されているところであるが, ここでの分析では, 個人主義的働き方を要請する非典型雇用の職場・職務は, 大卒の比較的年長の (経験年数が長い) 男性の職場や派遣社員の場合など, 特定の部分に限定的に存在する可能性が高いことが明らかになった.むしろ多くの若年アルバイトやパートタイマーの職場・職務は, 職業能力の獲得・発揮の機会が限られたものであり, 仕事の自立性や個人の意見の反映などの個人主義的な組織文化が支配する職場とはいえない.<BR>さらに, 非典型雇用での職業能力の獲得・発揮に重要だったのは, 学校教育などの企業外の機関でも幅広い多様な業務の経験でもなく, 就業先企業への長期勤続や企業からの支援を受けることであった.若者が非典型雇用を選択する背景には個人主義的志向があるが, 企業依存性を強めなければ, 職業能力の獲得は進まず, ひいては自立的な働き方も実現できない.この矛盾の克服には職業能力形成のための基盤を社会的に整備していかなければならない.
- 著者
- 田口 ローレンス吉孝
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.213-229, 2017
- 被引用文献数
- 2
<p>「日本人」/「外国人」の二分法に還元されない「混血」「ハーフ」と呼ばれる人々は, 政府・メディアの言説や学問領域においてしばしば不可視化されている. しかし, かれらの存在は日本社会における歴史的背景の中で立ち現われ, 時代ごとに多様なイメージや言説が付与されてきた.</p><p>本稿では, オミとウィナントが用いた人種編成論の視座を援用し, 時期区分と位相という枠組みから戦後日本社会における「混血」「ハーフ」の言説編成を整理し, 節合概念によってその社会的帰結を分析した. 第1期 (1945-60年代) において再構築された「混血児」言説は, 第2期 (70-80年代) に現れた「ハーフ」言説の人種化・ジェンダー化されたイメージによって組み替えられることとなる. 第3期 (90-2000年代前半) では「ダブル」言説を用いた社会運動が展開されるが, これらは当事者の経験を十分に捉える運動とはならなかった. 第4期 (2000年代後半-) には, これまでの「ハーフ」言説が多様化し, 現在の日本社会でナショナリズムや新自由主義, そして当事者によってその意味づけが再節合されつつある. 歴史的な言説編成の中で「混血」「ハーフ」と名指された人々への差別構造が通奏低音となって温存される一方, 当事者の運動によってこれらが可視化され始めている状況を明らかにした.</p>
2 0 0 0 OA 北海道社会学会
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.171-197, 1965-03-30 (Released:2009-11-11)
2 0 0 0 OA 「儒教とピューリタニズム」再考
- 著者
- 佐藤 俊樹
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.41-54, 1990-06-30 (Released:2009-10-13)
- 参考文献数
- 23
「儒教とピューリタニズム」はマックス・ウェーバーの一連の比較社会学の論考のなかでも、最も重要な論考の一つである。だが、そこでの儒教理解、とりわけ儒教倫理を「外的」倫理だとする定式化には問題があり、またウェーバー自身の論理も混乱している。この論文ではまず、儒教のテキストや中国史・中国思想史の論考に基づいて、儒教倫理が実際には「内的」性格を強くもつ『心情倫理』であることを、実証的に明らかにする。なぜ、ウェーバーは儒教の心情倫理性を看過したのだろうか? プロテスタンティズムの倫理と儒教倫理は実は異なる「心の概念」を前提にしている。ウェーバーはその点に気付かずに、プロテスタンティズム固有の心の概念を無意識に自明視したまま儒教倫理を理解しようとした。そのために、儒教を「外的」倫理とする誤解へ導かれたのである。儒教倫理は儒教固有の心の概念を前提にすれば、きわめて整合的に理解可能な、体系的な心情倫理である。それでは、この二つの倫理が前提にしている相異なる「心の概念」とは何か? 論文の後半では、この心の概念なるものの実体が、伝統中国社会と近代西欧社会がそれぞれ固有にもっている人間に関する「一次理論」であることを示した上で、その内容を解明し、その差異に基づいて、二つの倫理とその下での人間類型を再定式化する。そして、それらが二つの社会の社会構造にどのような影響を与えたかを考察する。
2 0 0 0 OA 「移行の危機」にある若者への支援の形成と変容
- 著者
- INOUE Ema
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.222-237, 2016 (Released:2017-09-30)
- 参考文献数
- 40
日本では2000年代から「移行の危機」にある若者が増加し, 危機の一面として, 社会関係資本の観点からの困難が指摘されてきた. しかし, 2000年代から始まった公的な若者支援は, その意義が強調される一方, これら社会的ネットワークをめぐる問題をいかに乗り越えるのか, その戦略は考察されていない. 本稿では, 地域若者サポートステーション事業を対象に, この論点を考察する.本稿ではナン・リンの議論 (Lin 2001=2008) から, 社会関係資本の伝達基盤となる相互行為における①異質的相互行為へのアクセスの困難, ②同類的相互行為の道具的限界という潜在的困難を指摘し, 対処する戦略をみる. ①に関しては, 特にイギリスのコネクションズ・サービスではアウトリーチなどの手段を通じて低減が図られ, 日本でも部分的に実施された. しかし職員との相談 (第1 段階の異質的相互行為) を経ても, 進路決定に必要な次の異質的相互行為をためらう若者の存在が職員に認識され, 自らのもつ資源 (「強み」) の承認を相互に可能にする若者同士の人間関係を構築しうるプログラムが多く実施されるようになった. ②に関しては, 若者同士の人間関係を通じて承認を得た資源を基盤に, 従来の若者の考え方とは異なる視点から, 進路探索に必要な新たな異質的相互行為に役立つ資源を職員が提供する. 本稿では, この同類的相互行為と異質的相互行為が相互補完的な役割を果たす過程を示す.
2 0 0 0 OA 石田淳著『相対的剥奪の社会学――不平等と意識のパラドックス』
- 著者
- 与謝野 有紀
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.435-436, 2015 (Released:2017-03-08)
- 著者
- 杉山 光信
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.57-74, 2008-06-30
この論文では栗原彬の仕事を取りあげるが,それは歴史的現実へのコミットという点でわが国の市民社会論の立場を受け継いでいると考えるからである.栗原彬の仕事はエリクソンのアイデンティティの概念を出発点としている.ふつうアイデンティティは幼児期から老年期に至るまで個人がライフサイクルの各段階での課題を達成するとき確立されると考えられている.つまり個人の心理発達の問題と理解されている.しかし,栗原の理解はこれとちがっている.1960年代アメリカでの公民権運動にコミットするエリクソンに学び,歴史の転換期と青年期の存在証明の探求が出会うときにアイデンティティがもつ衝迫力を中心とするものである.それゆえ栗原にとって,アイデンティティは個人と歴史社会とを同時に視野に取り込むことのできる戦略的概念なのである.このような理解に立って,栗原は昭和前期の政治指導者のパーソナリティや行動と時代を分析してみせる.また高度成長期に豊かさとともに増大する管理社会化のもとにいる青年たちを分析する.そして最近では水俣病未認定患者たちの運動とともにあり,彼らのもとで「存在の現れ」の政治を認めるに至っている.「存在の現れ」とはアレントが『人間の条件』で語る「行為」に近い考えである.以上のような理解のアイデンティティ概念を手に歴史的現実にコミットする栗原彬の仕事は,社会学研究に多くの示唆を与えるものである.
2 0 0 0 現代日本の政治過程 (<特集>現段階における日本社会の特質)
- 著者
- 古賀 倫嗣
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.421-430,493, 1988-03-31
わが国の政治過程を考察するさいもっとも重要なのは、一九五五年社会党統一と保守合同により成立した保守-革新の政治枠組をもつ「五五年体制」の検討である。国民経済レベルでの高度成長とパラレルに、政治レベルでの自民党長期政権が続き、「経済大国日本」を実現させた。ところが、六〇年代後半、高度成長路線は大都市における過密と公害、生活問題を引き起こす。こうした都市問題に対しては、中央より地方での反応が鋭く、七三年には東海道メガロポリスに沿った主要都市に「革新」自治体が誕生した。「地方革新」が「中央保守」を包囲するという政治戦略とともに、対話による行政、市民参加といったその政治手法は選挙以外に政治参加の手段が存在することを現実に示した。<BR>ところで、「革新」自治体の後退は七〇年代末期には始まり、横浜・沖縄・東京・京都・大阪と相次いでその拠点を失った。だが、地方「革新」の崩壊は「保守」の復権ではなかった。今や政治枠組としての有効性を失った保守-革新の図式にかわって「保革相乗り」で登場したのは、「脱イデオロギー」を標榜する自治省 (旧内務省) 出身の行政テクノクラートであった。こうしたタイプの首長を選択した住民の側にも「生活保守主義」という新しい動きがみられたのも、この時期からである、この層は、一般には浮動票層、支持政党なし層と呼ばれるが、彼らは政治的行為の有効性についてきわめて敏感で、どのチャンネルを使えば自己の利益がうまく実現できるかを常に考えるタイプの市民層といってよい。八七年四月、統一地方選挙のさいの「売上税反乱」はそうした一例にすぎない。<BR>戦後長期にわたって政治の基礎的な枠組であった保守-革新の図式は、こんにち中央-地方の図式に編成替えされ、さらに四全総にみられるように、東京-非東京との対立、「地方」内部の矛盾がいっそう深化している。そういう意味で、現代は「巨大な過渡期」なのである。
2 0 0 0 OA 社会学の応用
- 著者
- 野田 一夫
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.3-4, pp.77-84,159, 1960-07-20 (Released:2009-11-11)
2 0 0 0 家族と少子化(<特集>還暦を迎える日本社会)
- 著者
- 稲葉 昭英
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.38-54, 2005-06-30
- 被引用文献数
- 2
未婚化・晩婚化だけでなく, 夫婦出生率の低下も少子化の一因であることが近年の研究から明らかにされている.本研究は, この夫婦の出生率の低下に家族的要因がどのように関与しているのかを検討する.まず, これまで指摘されてきた社会経済要因説, 価値意識要因説, ジェンダー要因説の3つの仮説の論理的な関係を検討し, 子ども数の選好の変化が論理的に重要であることを示す.ついで, 先行研究および出生動向基本調査の結果を検討したが, ジェンダー要因説を支持する結果はほとんど得られなかった.むしろ, 夫婦の出生率の低下は, 子どもの福祉を追求するために子ども数を制限するという選好の変化から生じている可能性が示唆された.最後に行ったNFRJ98 データを用いた乳幼児をかかえた女性の家族役割負担感などについての分析からも, ジェンダー要因説は支持されなかった.育児期には性別役割分業が顕在化するが, そうした課題が夫婦ではなく親族を中心としたネットワーク内で分担されるために, ジェンダー要因説が成立しないことが示唆された. 夫婦出生率の低下は, 家族の新たな変化の帰結というよりは, 性別役割分業にもとづいて子どもの福祉追求を行うという, これまでの家族のあり方に根ざした動向と考えられる.
2 0 0 0 OA 地域文化としてのサブカルチャー
- 著者
- 伊奈 正人
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.77-96, 1998-06-30 (Released:2010-04-23)
- 参考文献数
- 32
この小論は, 「サブカルチャーとしての地域文化」を論じた井上俊 1984, 「地域文化と若者文化」を論じた中野収1990ほか先行する「地域文化論」, および筆者自身が行った映画上映運動についての岡山調査などを手がかりとして, 「地域文化としてのサブカルチャー」について論じようとするものである。まず第一に, 「東京文化」としてのサブカルチャー, それを育む, -村社会や, 地方都市にはない-東京という街の持つ特徴について論じる。第二に, 日本の近代化が行った地域の再編が, 地域ごとの「生のフォルム」を形成しえない中心盲信の「上京文化」「洋行文化」を生み出したことを確認する。 そして, 安直に「地方の時代」を賞揚せず, 根底にある「中心一周縁」の問題を隠蔽することなく視野におさめ, かつ「周縁」の可能性を開示する視点, スタイルの可能性を確認する。そして, 第三に, H・アーヴィン1970, B・シャンクス1988, W・ストロー1991などによりながら, それを可能にする視点として「文化シーン」という概念を導入する。それは, ヴァナキュラーで固定的で伝統的な「地方文化」の「コミュニティ」とは区別されるグローバルで可変的な「もう一つの地域文化」 (伊奈1995) の実体を表現するものである。そして, この視点により「地域文化」の可能性を仮説的論点として提起する。第四に, 一つの例解として, 岡山調査の結果を紹介する。 そして, 地域文化がかかえる困難と, そしてそれがゆえの洗練を明らかにする。
2 0 0 0 OA 遊びの精神と体験選択動機
- 著者
- 高橋 由典
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.39-55, 2016 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 18
本稿は, 井上俊の著名な青年文化研究に含まれる理論的な脆弱さに着目し, 行為論の角度から彼の遊び論を批判的に検討しようとする試みである.周知のように, 井上は1970年前後の青年層を「遊びの精神」によって特徴づけた. 井上の「まじめ―実利―遊び」の区分は, R. カイヨワの「聖―俗―遊」というアイディアを行為論の枠組みに転用したものである. それゆえ井上のいう「遊びの精神」にはカイヨワの影響が色濃い. 首尾一貫した行為論的認識枠組みを構成するためには, カイヨワから離れ, 理念や利害とは異なる第三の動機が何かを徹底して考え抜く必要がある. 本稿はその第三の動機の本体を体験選択とみなし, 井上のいう「遊びの精神」は体験選択動機の一つの表現型であると考える. 井上が遊びの精神という言葉で示そうとしていた内容を, 井上の前提 (行為論の枠組み) を共有しかつ論理的一貫性に注意しつつ突きつめていくと, 体験選択ないし体験選択動機という用語に行き着く. これが批判的検討の結論である. この議論を受けて, 最後に, 人物ドキュメンタリーを素材に体験選択動機の現在が語られる. 体験選択価値が上昇するとともに体験選択自体が変質したというのが, そこで提示される認識である.
2 0 0 0 OA 社会運動の参加/不参加選択をめぐる意味構築
- 著者
- 伊藤 奈緒
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.797-814, 2006-03-31 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
集合目標へ同調した個々人が, 運動参加/不参加へと分岐する要因はどこまで探ることが出来るのか.資源動員論以降の運動研究はフリーライダーの不参加理由を詳細に検討する必要性を訴えてきた.近年では, この選択過程に対し心理的要因を再導入して分析する傾向がある.これらの動向は, 運動を集団内在的に捉えず, 周辺の不参加者や傍観者にも注目し, 運動と社会の関係そのものを考察する必要性を示している.こうした先行研究を受け, 本稿は運動参加/不参加理由の再検討に質的調査を通じて取り組む.事例としてアイヌ民族の権利獲得をめざす非アイヌ民族の運動を取り上げ, 運動参加者と不参加者の双方にインタビューを行った.また安立清史による問題提起に着想を得て, 集合目標への賛意や敵対に回収されない意味構築の場面を考察した.両者による意味構築は, 以前のアイヌ民族の権利運動で支援者が依拠した自己否定の規範意識に関連している.自己否定の理念は, 一般に現在有力な動員資源だと認識されていないが, さらにこの規範意識が参加障壁をも形成している点が明確になった.つまり「軽い参加」を懐疑する不参加者, そして文化的関心と集合目標への共鳴という二重の運動参加動機を保とうとする参加者の姿勢が見出されたのである.ここから, 両者とも自己否定の理念を動員資源として認めていない一方で, 自分と無関係なものとして無視しているのではないという状況が明らかになった.
- 著者
- 栗田 宣義
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.374-391,479, 1989-03-31
- 被引用文献数
- 1
一九六〇年代後半、日本の政治社会は、青年層に主導されたラディカルな抗議活動の高揚とそれに対する強力な社会統制の発動によって織りなされる激突政治の時代を迎えた。一九六八年から一九六九年にかけて、大学紛争は全国的に拡大し、その頂点に達する。このような激突政治の時代に青年期を過ごした世代は、反抗的な政治文化を学習する機会を与えられたのである。本稿は、この世代に焦点を合わせ、彼ら/彼女らの現在に至るまでの持続的な政治的社会化過程を解明する。「一九六〇年代後半激突政治の時代に政治的社会化を受けた者たちは、その後もラディカルな抗議活動に従事し続けているのだろうか?」「現在、社会運動勢力は、彼ら/彼女らのエネルギーに支えられているのだろうか?」これら二つの問いに答えるために、政治世代構成仮説、同時代的政治的体験による社会運動加入仮説、社会運動加入による抗議活動従事仮説、と命名された三つの仮説を提示する。これらの仮説は、本稿で提唱される世代政治的社会化の理論モデルに依拠しているのである。社会運動の水源地である抗議活動支持層を対象としたデータ解析の結果、仮説群は全て支持され、世代政治的社会化の理論モデルの妥当性が確認された。一九六八-六九年世代は、彼ら/彼女らの青年期に生じた大学紛争の激化という同時代的政治的体験の共有と、社会運動加入の両要因からなる世代政治的社会化のフィルターを通過することによって、激突政治志向に傾き、抗議活動に従事していることが明らかになったのである。
2 0 0 0 科学社会学の理論構成 : 制度化の規約
- 著者
- 松本 三和夫
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.30-43,123**-122, 1992-06-30
科学者、科学者の行動、科学者のネットワーク、科学者集団、科学制度、社会システムのすくなくとも六つの活動水準を分析の単位として、どのような型の首尾一貫した科学社会学の理論が構成できるかを吟味し、理論の帰結を科学者集団の制度化論に関連づけて特定する。<BR>一九八〇年代以降、科学社会学は問題ごと、研究センターごとに研究スタイルの細分化が進むいっぽう、分野全体を基礎づける概念や理論にかならずしもじゅうぶんな見通しが得られていない。こうした状況に鑑み、本稿ではまず科学社会学の基礎概念を決め、研究前線における多様な研究動向間の橋渡しが可能なよう、科学社会学の外延を確定する。ついで、科学社会学の課題の内包を内部構造論、制度化論、相互作用論に分節して特定し、科学者集団の状態記述に関するかぎり、各課題が相互に共約可能であることを証明する。<BR>最後に、制度化論を見本例として理論の含意を例示する。とりわけ、制度化がじっさいにどのような起こり方をするかのパターンに関する規約 (制度化の規約) を理論に導入すべきことを提唱する。それを用いて理論を展開し、事実分析にとって有意味な、しかし直観だけではみえにくい逆説的な帰結 (専門職業化が制度化を伴わぬ事例 [ナチズム科学] の存在) が導けることを示したい。
- 著者
- 薬師院 仁志
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.42-59, 1998-06-30
本稿は, フィリップ・ベナールによる『自殺論』 (É.デュルケム, 1897年) の解釈を批判的に再検討する試みである。すなわち, ベナールによる解釈にもとづいて『自殺論』を再構成すると同時に, その限界を示すことを通じて, 『自殺論』という書物のもつ問題構成の重大性を再確認することを目標にしている。<BR>ベナールは, デュルケムの抱く女性にたいする偏見が, 『自殺論』においてデュルケム本来の理論をねじ曲げてしまったと主張する。デュルケムは, 女性もまた男性と同じように「自由への欲求」をもっていたのだという事実を隠蔽するために, 「宿命論的自殺」 (過度の拘束から生じる自殺) を追放してしまったというのである。ベナールは, 「宿命論的自殺」を『自殺論』から救出し, それとアノミー自殺とのU字曲線的関係を, 拘束という変数を軸に再構成したのである。<BR>本稿の課題は, ベナールによるこのような『自殺論』解釈を整理すると同時に, それがいかなる根拠にもとついて導出されたのかを明らかにし, あわせて, それがどの程度の妥当性をもつのかを理論的に検討することである。その際, 特に, ベナールが「集団本位的自殺」を自らの理論から除外したことに注目し, デュルケムとベナールの理論的相違点を明確にしたいと思う。
2 0 0 0 OA 公募特集「現代社会と生きづらさ」によせて
2 0 0 0 生活空間と歴史性の諸問題 : 非行事象を手がかりとして
- 著者
- 安倍 淳吉
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.3, pp.2-21, 1957-07-15
In case we understand the life space in social behavior, it is necessary for us not only to grasp it non-historically, that is, field-theoretically, functionally and situationally but also to comprehend the historical context of the factors functioning in each situation. By what is called a historical approach is meant the grasp of the necessity which exists between situations. Hence, a situational approach can bear out the structural complex of the factors which is inherent in a given situation, and thus it clarifies the specific and concrete meaning of a certain situation by taking into account the interrelationship of person, society, and culture, and enables us to predict its future behavior pattern. <BR>On the other hand, the historical approach presupposes to functionally understand more than two situations. In this sense, these two approaches depend on each other and require the contemporaneousness of each approach so as to make it productive. In the socio-psychological study of delinquency, it is almost impossible to attribute the state of subjective or objective readiness working in delinquent behavior to one specific situation. Only by referring to the other situations which are related to this particular one, it is possible to define the peculiarity of that situation and its life-historical and social-historical implications. And this will in turn lead to a prediction of its future situational pattern.<BR>Moreover, as far as social psychology is concerned, a historical approach does not necessarily mean a macro-level-approach. In social psychology, it is essential to pay attention to a tri-dimensional balanced structure of person, society and culture when each particular situation is historically analyzed. <BR>From this viewpoint, due consideration must be given to a median-level-approach. In other words, in the social-psychological study of delinquents, we are required to make clear, first of all, the social structure of a community or reform school, in which they live day in day out, and at the same time to elucidate the circular connections of delinquent field, correction field, and delinquent or non-delinquent field throughout their lives. <BR>In this manner, the median-level-approach must be said to be the nucleus of the study. Nonetheless, it has to be backed up by a microscopic approach on, one hand, and, on the other, by a macroscopic one. <BR>It must also be added that we understand a historical type of delinquent behavior not by an ideal type but by a realistic and conditionally developmental type.
2 0 0 0 OA K.マンハイムの知識人論
- 著者
- 伊藤 美登里
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.62-76, 1995-06-30 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
著書『イデオロギーとユートピア』に見られる K. マンハイムのペシミズムは, 彼が述べるような次の時代の真理としてのユートピアに導かれて社会を変革し, 形成するという, 「近代史の発展をつらぬく構造形式」が成立しなくなりつつあるという事態, ユートピアの消失という事態にたいする彼の危機感の表明であったが, それと同時にこのユートピアの創造者として, 近代社会において政治的・文化的に圧倒的な優位を誇っていた教養市民層が, 大衆社会の到来とともに没落の危機に瀕し, 「ユートピアの担い手」としての自己像すら危うくなりつつあることへの危機感の現れでもあったと考えられる。イギリス亡命後のマンハイムの理論の変化は, 上述の事態を解決しようとするなかで生じてきたものである. 彼は, 大衆社会において民主主義をうまく機能させる唯一の方法として「自由のための計画」を提唱した. 彼にとってそれは, 近代社会を形作ってきた「近代ユートピア」の存立が不可能となった時代において可能であるところの, 別の型の「ユートピア」であった.また, 「自由に浮動するインテリゲンツィア」にかわって, 「計画者としてのエリート」という役割を知識人に与えることで, 彼は知識人存在の新たな存在形式を創出しようとしたと見ることができよう。