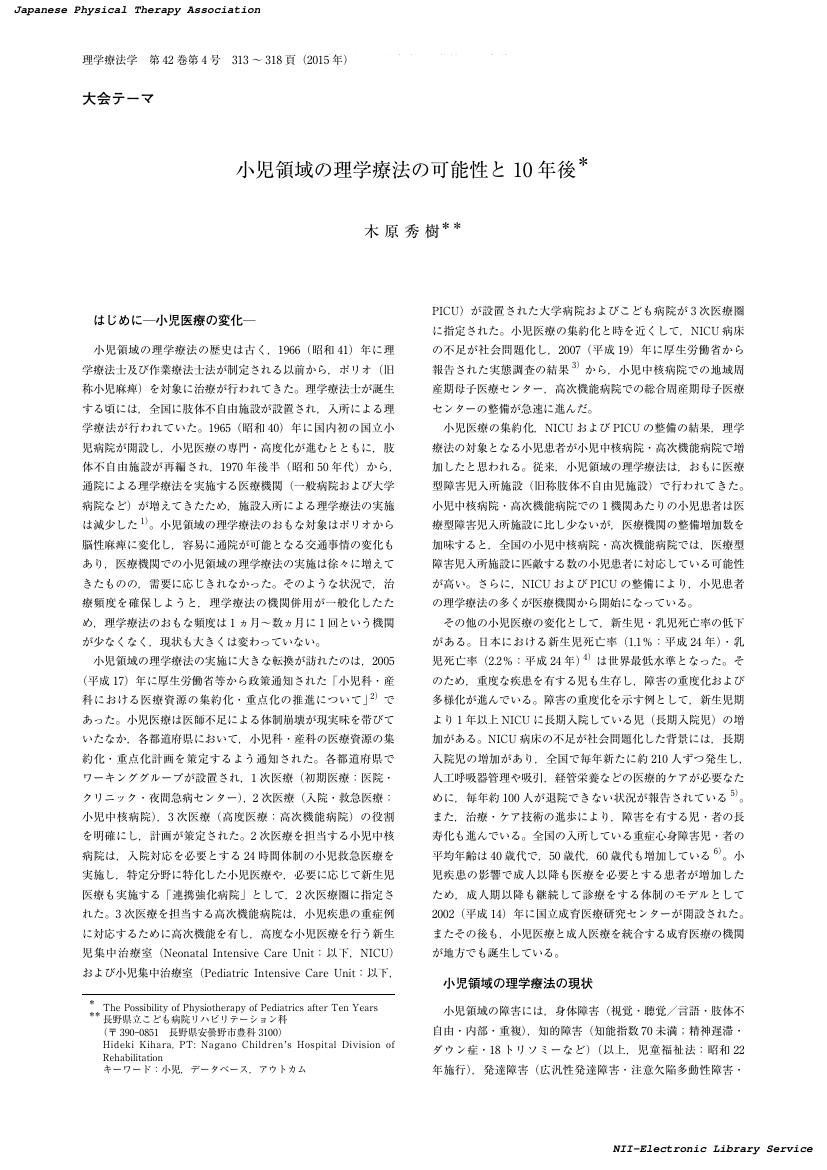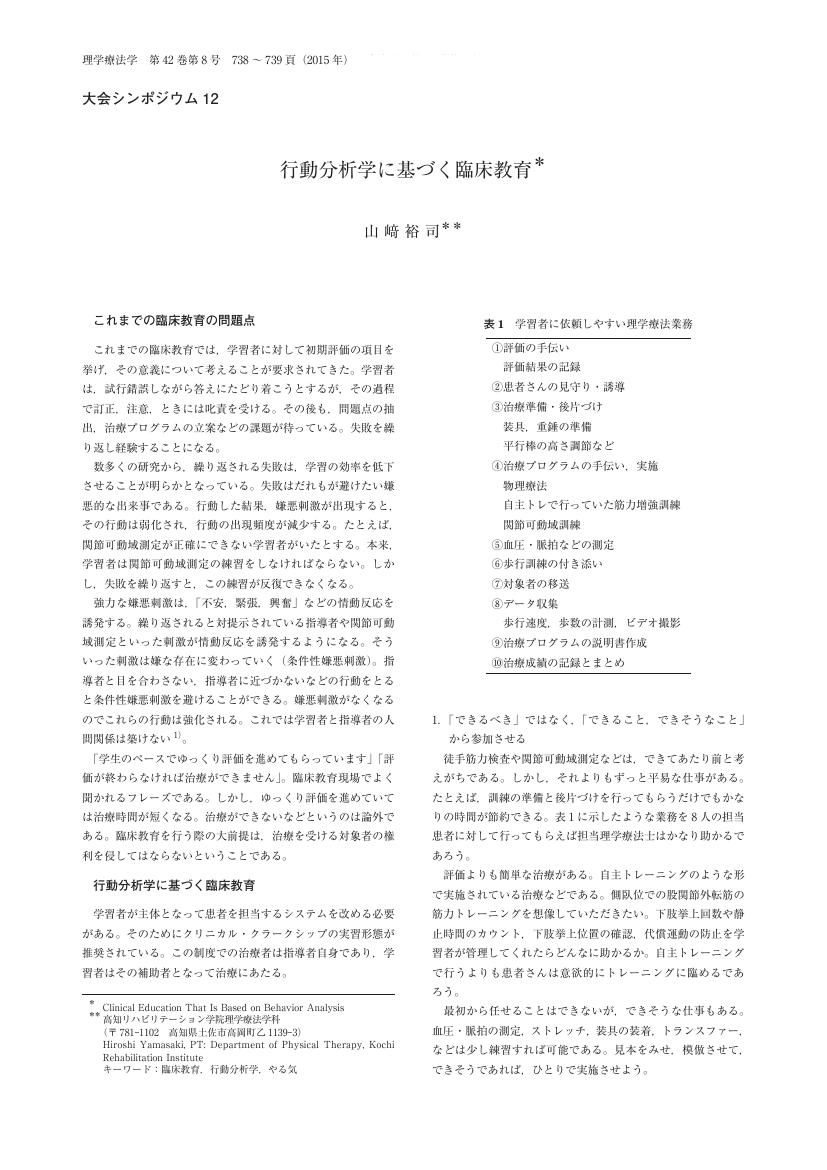1 0 0 0 OA 小児領域の理学療法の可能性と10年後
- 著者
- 木原 秀樹
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.4, pp.313-318, 2015-06-20 (Released:2017-06-09)
1 0 0 0 肩関節周囲筋弛緩のための重りつき振子運動 : 筋電図学的所見
- 著者
- 荻原 新八郎 長田 勉 立野 勝彦
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.6, pp.531-538, 1992-09-01
肩関節周囲炎患者にはたいてい鉄亜鈴またはアイロンを持たせ, アイロン体操と称してコドマンの振子運動を行わせている。その理論は, 重りが肩関節の軟部組織を伸張し, その周囲筋の弛緩を助長させると考えられている。しかし, 重りを手で握ることによる手部・前腕の筋群の収縮が肩関節周囲筋の収縮を生じさせ, それが振子運動の目的を損なうのではなかろうか? 右手首に2kgの重錘バンドを巻かせるか, あるいは同じ重さの鉄亜鈴を持たせ, 振子運動時の三角筋および棘下筋の積分筋電図を比較した。また振子運動の方向別, すなわち前後, 左右, および時計回り分回し運動による比較も検討した。被験者は15名の理学療法学科の男子学生で, 被験者自身も対照群とした。その結果, 積分値はすべての筋において重錘バンドを巻いて振子運動を行うよりも鉄亜鈴を持って行う方が有意に大きかった。振子運動の方向別については, 前後方向の動きの場合には三角筋中部線維の積分値が有意に小さく, 左右方向と時計回り分回し運動の場合には三角筋前部線維のそれが有意に小さかった。棘下筋の積分値はすべての方向の動きにおいて有意に大きかった。この実験の結果, 重錘バンド・鉄亜鈴を用いた振子運動ともに肩関節周囲筋の収縮は生じたが, 前者の場合, その程度が小さいことが判った。したがって重錘バンドを用いる方が目的を達するのに適しているのではなかろうか。また振子運動は前後左右の動きのみ行わせ, 分回し運動は避ける方がよいであろう。上肢の末端部に重りをつけない振子運動時の積分筋電図も以上の結果と比較・検討してみる必要がある。
- 著者
- 中野 知佳 柴 喜崇 坂本 美喜 佐藤 春彦 三原 直樹
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.21-28, 2007-02-20
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,背臥位からの立ち上がり動作パターンの推移を縦断調査により明らかにすることである。健常な幼稚園児17名を対象とし,年少クラス時(平均年齢3歳9ヶ月±4ヶ月)から2年間継続し,計3回,背臥位からの立ち上がり動作をビデオに記録した。そして,立ち上がり動作中の上肢,頭部・体幹,下肢の3つの部位に着目し動作パターンを分類した。その結果,上肢,頭部・体幹の動作パターンの推移では一定の傾向を示し,下肢の動作パターンの推移では,上肢,頭部・体幹の動作パターンの推移に比べ一定の傾向を示さず多様な動作パターンの推移が観察された。そして,動作パターンの変化は年少クラス時から年中クラス時(平均年齢4歳9ヶ月±4ヶ月)の間に生じていた。上肢では年少クラス時から年中クラス時にかけて,17名中9名が左右どちらか一側の床を両手で押して立ち上がるパターンから,片手,あるいは両手を左右非対称的に使い立ち上がる動作に変化し,頭部・体幹では,17名中6名が同様の時期に回旋の少ない立ち上がり動作を獲得した。これらのことから,発達段階における立ち上がり動作の評価には,上肢,および頭部・体幹の運動に着目し観察することが重要になると思われた。
- 著者
- 大江 隆史
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.8, pp.639-640, 2015
- 著者
- 佐藤 三矢 加藤 茂幸 弓岡 光徳 日高 正巳 小幡 太志 酒井 孝文 仁木 恵子
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, pp.E0183-E0183, 2005
【背景】<BR><BR> 痴呆患者に対し、理学療法が移動能力向上に寄与するところは大きく、維持期(慢性期)のリハビリテーションを展開している現場では、下肢筋力増強や立位バランス向上のための運動療法、屋外歩行や階段昇降などの実践的な応用歩行練習が一般的に用いられている。このような運動療法プログラムは全身運動であり、痴呆の中核症状である精神症状や知的障害を予防または改善する効果を指摘する報告は多い。また、痴呆の進行を予防する上で、寝たきりの状態にさせないことを主張している文献も多く、移動能力促進を目的とした理学療法は寝たきり防止の点についても有意義であると考えられる。<BR> このように痴呆性高齢者において、移動能力は重要な意味を持つ行為であり、移動能力向上を目的とした理学療法は、病院や老人保健施設・在宅などで今や普遍的に行われている。<BR> しかし現在、痴呆性高齢者の移動能力とQOLとの関連性について調査している報告は散見する程度である。<BR> よって今回、痴呆性高齢者を対象として「移動能力」と「QOL」を点数化し、相関について調査した。<BR><BR>【方法】<BR><BR> 対象は、介護老人保健施設に入所している痴呆性高齢者85名。本研究は、対象施設の承認を得た後、文書にて家族からの同意が得られた対象者のみに実施した。痴呆性高齢者の移動能力の評価尺度であるSouthampton Mobility Assessment (SMA)日本語版と痴呆性高齢者のQOL評価尺度であるQOL-Dを用いて、対象者の「移動能力」と「QOL」を点数化し、相関関係について調査した。<BR><BR>【結果】<BR><BR> Speamanの順位相関を用いて検索した結果、SMA日本語版とQOL-Dとの間において、有意な相関関係が認められた(r=.471,p>.001)。<BR><BR>【まとめ】<BR><BR> 今回、SMA日本語版とQOL-Dとの間において、有意な相関関係が認められた。よって、痴呆性高齢者の移動能力への理学療法介入がQOL向上につながる可能性がうかがえた。
1 0 0 0 肩関節運動時不安定性を呈する症例の機能的問題点
- 著者
- 尾﨑 尚代 千葉 慎一 嘉陽 拓 大野 範夫 筒井 廣明
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.C1397-C1397, 2008
【はじめに】肩関節の安定化機構は関節構造および筋機能での関節窩に対する上腕骨頭の求心位保持能力およびショックアブソーバーとしての肩甲骨の動きが必要となるが、これらの中の1つでも問題が生じれば肩に機能障害が生じると考えられる。今回は当院診察時の診断補助として用いられるX線像から得られた情報を基に、肩関節の運動時不安定性の機能的問題点について検討した結果を報告する。<BR>【方法】対象は、肩関節の運動時不安定性を訴え、SLAP損傷またはinternal impingementと診断された40例(男性38名・女性2名、右37名・左3名、年齢21.88歳±5.29)であり、全員投球動作を要するスポーツ愛好者である。これらの症例に対し当院初診時に撮影したX線像のうち、Scapula-45撮影法45度挙上位無負荷像を用いて患側の腱板および肩甲骨機能を、自然下垂位と最大挙上位の前後像を用いて鎖骨および胸郭の運動量を、また、最大挙上位像を用いて上腕骨外転角度(以下、ABD)、関節窩の上方回旋角度(以下、上方回旋)および関節窩に対する上腕骨の外転角度(以下、関節内ABD)について計測した。ABD・鎖骨の運動量の変化・上方回旋・関節内ABDについては健患差を、t検定を用いて比較検討した。また、胸郭の運動量は遠藤ら(1996)の報告に基づいて基準点を20mmとし、また鎖骨の運動量については、Fungら(2001)の報告に基づいて基準点を20度として、符号検定を用いて検討した。<BR>【結果】腱板機能は正常範囲であり(0.32±4.86)、肩甲骨機能は低下していた(5.53±7.52)。ABDは患側(以下、患)165.36度±6.33・健側(以下、健) 167.11度±7.30(p<0.02)、鎖骨の運動量の変化は患25.18度±8.30・健22.60度±8.00(p<0.01)、上方回旋は患54.88度±5.25・健52.02度±5.30(p<0.001)、関節内ABDは患110.60度±7.28・健112.85度±17.12(n.s.)であった。また胸郭の運動量は12.70mm±6.47となり、基準点に対して胸郭は動かず、鎖骨は動く傾向になった(p<0.01)。<BR>【考察】今回の結果から、肩関節の運動時不安定性を呈する症例は、肩甲骨を体幹に固定する機能および胸郭の可動性が低下しており、また、上肢挙上角度を得るために、鎖骨と肩甲骨の運動量が大きくなることから、胸鎖関節と肩鎖関節への負担増大が懸念された。今回はX線像を用いた前額面上のみの調査を若者中心に行ったが、野球やテニスなどのスポーツ愛好家の年齢層は幅広い。また、投球障害を呈する症例は数年前と比較して腱板機能は向上しているが肩甲骨の機能低下を呈する者が多いという報告や、加齢と共に肩甲骨や脊柱の可動性が低下するという報告もあり、胸郭の可動性を引き出すことは、運動時不安定感の改善と共に、障害予防の点からも重要と考える。<BR>
- 著者
- 宮本 謙三 宅間 豊 井上 佳和 宮本 祥子 竹林 秀晃 岡部 孝生
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, 2003-04-20
1 0 0 0 OA 42 Barthel Indexにより分類した重症群と軽症群における高齢入院患者の栄養状態の評価について(理学療法基礎系,一般演題(ポスター発表演題),第43回日本理学療法学術大会)
- 著者
- 内山 恵典 森上 亜城洋 西田 裕介
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, 2008-04-20
1 0 0 0 OA 854 高齢者における予測身長を用いた栄養状態の把握および下腿周径とBody Mass Indexとの関係(理学療法基礎系,一般演題(ポスター発表演題),第43回日本理学療法学術大会)
- 著者
- 森上 亜城洋 内山 恵典 西田 裕介
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, 2008-04-20
【はじめに】理学療法評価での栄養評価は、対象者の全身状態を把握すると共に、活動度の把握やプログラムの作成において重要となる。また、理学療法評価の中で広く応用されている栄養評価に Body Mass Index(BMI)がある。しかし、高齢者では脊柱の変形や活動度の低下により適切な身長を計測することは困難なことが多い。そこで本研究では、予測身長を用いてBMIを算出し、身体組成における栄養指標の1つである下腿周径との関係を検討した。さらに、下腿周径は活動度と関連することが知られていることから、Barthel Index(BI)との関係性についても検討した。<BR><BR>【対象と方法】対象は、65歳以上の入院患者24名(男性10名・女性14名、平均年齢80.7±6.6歳)である。対象者(家族含む)に研究内容と倫理的配慮について文書及び口頭にて説明し、研究参加の同意を得た。また、本研究は各施設の倫理委員会の承認を得て実施した。予測身長は、久保らによる回帰式「2.1×(前腕長+下腿長合計)+37.0」を用いた。前腕長は、肘90度屈曲位で肘頭から尺骨茎状突起遠位部までを計測し、下腿長は、膝90度屈曲位で腓骨頭近位部から外果遠位部までを測定した。体重は立位もしくは車椅子対応型体重計にて測定し、予測身長と合わせてBMIを算出した。下腿周径は、腓骨頭から外果中央部の腓骨頭から26%の膨隆部位を測定した。日常生活活動ならびに障害の程度を把握するためBIを用いた。統計的手法にはピアソンの相関係数の検定を行い、5%未満を有意と判定した。<BR><BR>【結果】各項目の平均値を示す。前腕長は22.5±1.8cm、下腿長は29.5±2.2cm、予測身長は146.5±8.1cmであった。BWは45.0±9.8kgであり、BMIは20.8±3.4(男性54±31.4、女性65±35.1)であった。26%下腿周径は28.4±3.8cmであった。相関係数ではBMIと26%下腿周径下腿最大周径はr=0.9であり、男性の26%下腿周径とBIはr=0.64と有意な関係を認めた(ともにp<0.05)。<BR><BR>【まとめ】本研究の結果より、栄養評価であるBMIと26%下腿周径との間には有意な関係性が認められた。このことは、脊柱の変形や活動度の低下等により身長の測定が困難な対象者においても、予測身長を用いることで栄養評価が可能になることがわかる。また、下腿周径は、体重やADLとの相関が高いことが報告されている。本研究においても、男性では26%下腿周径と身体活動状況を反映しているBIとの間に相関関係が認められた。以上のことより、予測身長を用いたBMIは栄養状態を反映し、男性においては26%下腿周径と身体活動状況との間に関係性があることから、26%下腿周径は栄養状態に加え、身体活動状況も反映する指標として、有効な理学療法評価指標になると考えられる。
1 0 0 0 ミラーセラピー運動学習におけるヒト一次運動野機能の役割
- 著者
- 野嶌 一平 美馬 達哉 川又 敏男
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.82-89, 2012
- 参考文献数
- 41
【目的】ミラーセラピー(Mirror Therapy:以下,MT)による運動機能,脳機能の変化を検討するとともに,経頭蓋磁気刺激(TMS)を用いて大脳皮質に直接的介入を行い,MTによる運動学習時の一次運動野(M1)の役割をあきらかにすることを目的とする。【方法】対象は,健常成人12名とし,全例右利きであった。運動課題は30秒間の左手でのボール回し課題とし,脳機能はTMSにより導出された運動誘発電位振幅を指標とした。MTは,左手に重ねられた鏡に映る右手運動の視覚フィードバックを伴った右手での運動介入を行った。その後,大脳皮質の活動性を抑制するcontinuous theta burst stimulation(以下,cTBS)をM1と視覚野(Occipital:以下,OC)に各々2群に分けて実施した。その後,再度MTを実施した。運動機能と脳機能の評価は,各介入後に実施した。【結果】MTにより運動機能と脳機能の有意な向上が見られた。そしてcTBS実施により,M1群でのみ運動機能,脳機能ともに一次的に低下が見られ,再度MTを実施することで運動機能と脳機能の向上が見られた。【結論】MTによる運動機能の向上にはM1の活動性向上が必要である可能性が示唆された。
- 著者
- 森下 慎一郎 瀬戸川 啓 中原 健次 太田 徹 眞渕 敏 海田 勝仁 小川 啓恭 児玉 典彦 道免 和久
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.122-123, 2011-04-20
【目的】造血幹細胞移植患者に対し無菌室内で運動療法を実施し,その効果と安全性を検討することである。【対象および方法】造血幹細胞移植を受けた患者30名(運動療法群15名,コントロール群15名)を対象とした。造血幹細胞生着の有無,生着までの日数,感染症,移植前後の身体機能を評価した。【結果】運動療法群,コントロール群共に造血幹細胞は全例生着し感染症も認めなかった。身体機能は移植前と比べると移植後,筋力,体重,6分間歩行は低下したものの,歩数は有意差がなく,逆に15名中6名は増大した。【結語】免疫機能が低下している期間中でも感染予防を徹底すれば,安全に運動療法を実施できた。しかしながら,移植前と比べると移植後は身体機能は低下していた。本研究では,運動療法群のみ身体機能評価を行っており,今後,運動療法の効果を検証するには無作為化比較試験の実施が必要であると考えられる。
- 著者
- 山本 篤
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, 2013-10-04
1 0 0 0 やる気を引き出す動作練習
- 著者
- 山崎 裕司
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.315-317, 2011
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 行動分析学に基づく臨床教育
- 著者
- 山﨑 裕司
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.8, pp.738-739, 2015 (Released:2016-01-15)
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 運動失調症における躯幹協調機能ステージの標準化と機能障害分類
- 著者
- 内山靖 松田 尚之 菅野 圭子 種物谷 由美 佐野 克哉 長澤 弘 石川 潤 山本 明美
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.313-320, 1988
- 被引用文献数
- 3
運動失調症においては, 種々の協調障害がいかなる能力障害を引きおこすかを整理する事が重要である。このような視点より, 以下の事が結論づけられた。(1)躯幹協調機能は, 移動能力をはじめとするADLとの相関が高く, 機能障害のなかで独立して扱う必要性が認められた。(2)上記に基づき, 躯幹協調機能ステージは, 臨床的にも簡便で正確な評価が可能であった。(3)坐位重心動揺結果は躯幹協調機能ステージとの関係が密接で, 立位重心動揺における結果も含めた解析を行うと, より有効な解釈が可能となった。(4)上記より, 運動失調症における機能障害分類の重要性と, それに基づく合目的理学療法の必要性が示された。
1 0 0 0 脳における平衡機能の統合メカニズム
- 著者
- 浅井 友詞
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.8, pp.538-539, 2013
1 0 0 0 OA 障害者の性機能
- 著者
- 川平 和美
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.6, pp.483-491, 1988-11-10
- 著者
- 尾崎 和洋
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, 2005-04-20
【はじめに】平成15年4月より「支援費制度」が開始された。そのねらいは、障害者の自己決定を尊重し、自らがサービスを選択、事業者と契約しサービスを利用するものである。当センターでは、その制度に対応すべく自己選択、自己決定を容易にする目的で「コース」を設定し社会生活力サポートプログラムを提供しているので報告する。<BR>【コースの紹介】1)仕事に就くコース。2)家庭で暮らすコース。3)ひとり暮らしコース。4)生活と身体を活性化するコース。5)これから考えるコース。6)その他のコース(職業訓練校、療護施設、老人施設など)<BR>【症例】脳卒中左片麻痺(54歳)男、糖尿病:Hba1c9,3%。高次能機能障害(左半側空間失認、注意障害)Br、stage:上、下肢―3、趣味:プラモデル作り。<BR>【経過】平成12年4月入所。FIM:84点。歩行:平行棒内歩行、通常移動車椅子。平成13年2月:歩行約300m可能。7月:室内歩行自立、約1km可能。Hba1c:6,3%。8月:在宅生活希望、オープンカンファレンス開催。平成14年1月:家庭外泊し問題点の把握を行う。3月:ひとり暮らし支援プログラム開始。地域への「外出自立度評価」条件付き自立。8月:歩数計を付け一万歩以上歩行可能。10月:個別浴室で自立入浴開始。12月:JRを利用し姫路へ外出可能。平成15年6月:ひとり暮らし時の糖尿病食の取り組み開始。10月:建て替え中の県営住宅完成、入居可能。12月:JRを利用し尼崎まで外出。平成16年2月:要介護度1が決定。6月:家屋調査、用具(レンタル、購入)居宅介護支援事業所と調整。7月:ひとり暮らし開始。FIM:118点。Hba1c:7,1%。8月:退所後の支援を行う。<BR>【各部署の取り組み】SW:ひとり暮らしについて尼崎市とオープンカンファレンス開催。県住入居手続き。在宅サービスの確認。<BR>PT:歩行能力の向上。JRを利用する外出。糖尿病に対する運動療法と自主トレーニングの定着。個別入浴動作の自立。<BR>OT:生活に必要な物品、糖尿病食、買い物の仕方、ATMの使用、ヘルパー、デイケアの利用内容の検討。<BR>NS:健康状態の定期検査。糖尿病教室。服薬管理。<BR>CW:日常生活、入浴時の援助。調理実習。金銭管理。<BR>【まとめ】1)社会生活力サポートプログラムを提供するには、アセスメントの充実、各部署の役割分担の確認と調整。利用者、家族への説明と同意、契約。<BR>2)今後の課題は利用者のニーズと状況に合わせたプログラム内容の工夫である。他部署との更なる連携。
1 0 0 0 OA 発達障害のリスクを持つ乳児と母親に対するブラゼルトン新生児行動評価を用いた早期介入
- 著者
- 大城 昌平 儀間 裕貴 Loo Kek Khee 穐山 富太郎
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.5, pp.326-332, 2005-08-20
発達障害のリスクを持つ乳児と母親を対象として, ブラゼルトン新生児行動評価(NBAS)を基にした介入(以下, NBAS-based intervention)の新生児行動の発達, および母子相互作用に対する影響を検討した。研究デザインは, それぞれ2週間の観察期間と介入期間の前後比較研究である。対象は長崎大学医学部歯学部附属病院未熟児室で加療した発達障害のリスクを持つ新生児・乳児とその母親13組であった。NBASを用いた介入方法は, NBASのデモンストレーションを母親と一緒に行いながら, 児の行動能力を示し, ハンドリング指導や生活指導などの育児支援を行なう母子介入の方法である。帰結評価には, 1) NBASによる新生児行動の発達評価, 2) NCATS (Nursing Child Assessment Teaching Scale)による母子相互作用の観察評価, 3) 母親の児の取り扱いに対する自信スケール(Lack of Confidence in Caregiving; LCC)の3つの評価尺度を用いた。その結果, NBAS-based interventionは, 母親の児の行動に対する感受性と育児技術を向上させ, 母子の相互作用, 母親の育児の自信と児の行動発達を促進する結果であった。以上の結果から, NBAS-based interventionは発達障害のリスクを持つ児と母親の関わり方や母子の相互作用を促し, 相乗的に児の行動発達も促進する可能性があると思われた。