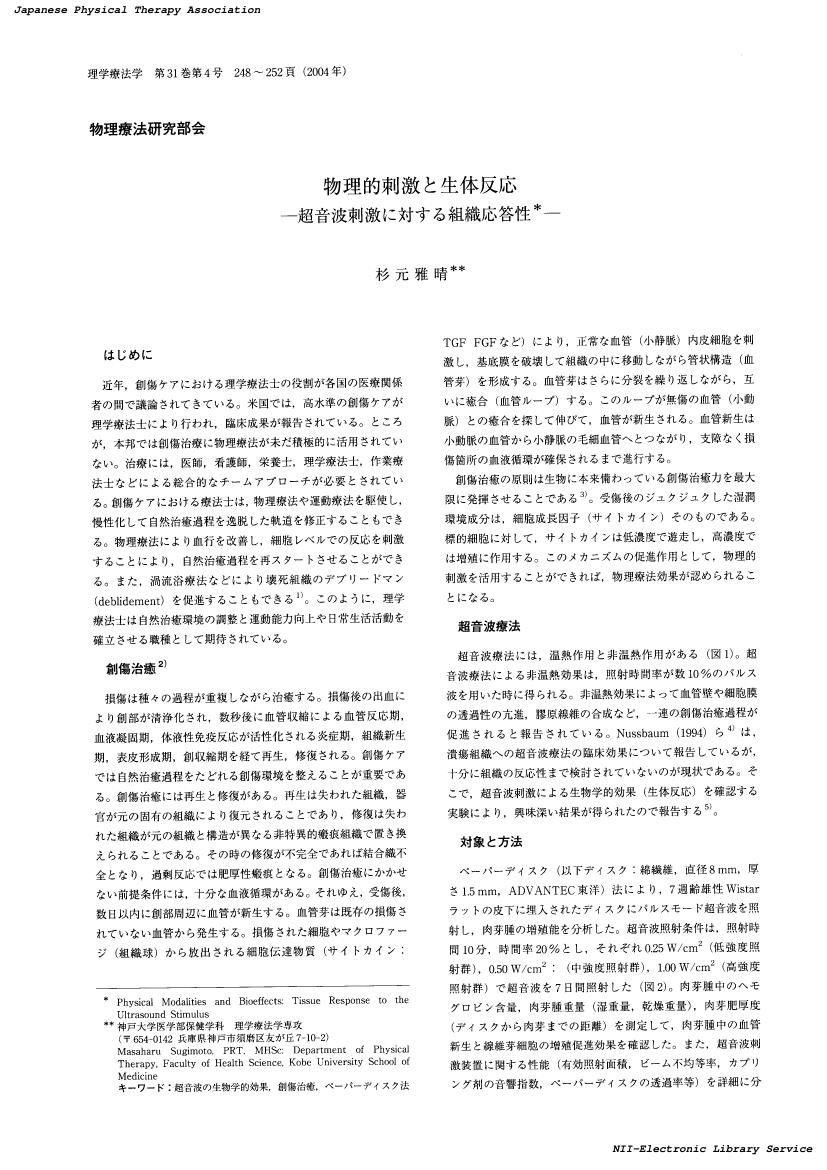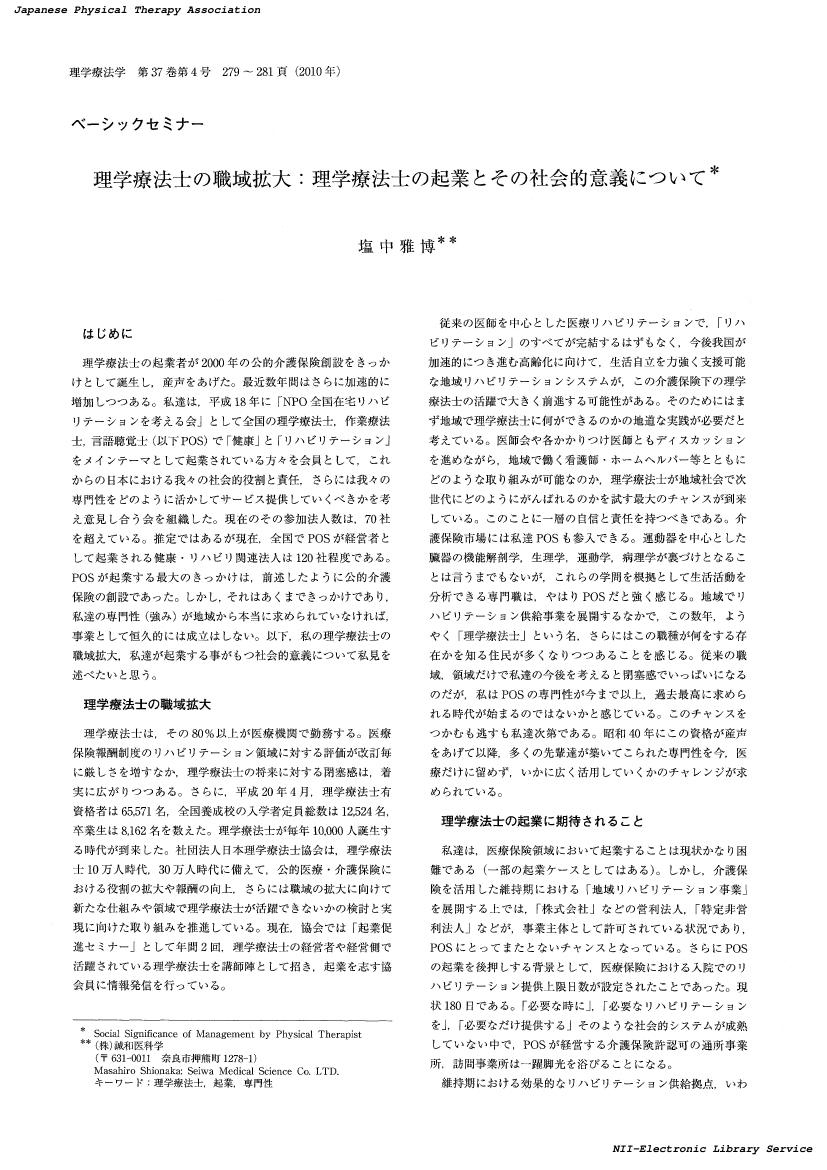1 0 0 0 OA 歩行におけるPhysiological Cost IndexとMETSとの関係
- 著者
- 竹井 仁 柳澤 健 岩崎 健次 富田 浩 齋藤 宏
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.5, pp.294-299, 1993-09-01 (Released:2018-09-25)
- 被引用文献数
- 4
歩行速度と勾配の変化に関して,生理的コスト指数(Physiological Cost Index : PCI)と METSとの関係を検討した。対象は健常男性10名で,MacGregor等による1周30mの8字型平地歩行でPCIを測定した。またトレッドミルを用いた平地歩行,勾配歩行,Bruce法による連続歩行について各々PCIとMETSを測定し比較検討した。PCIと歩行速度との関係は,各負荷とも有意な相関を示した。同速度に対するPCIの値はトレッドミル平地歩行が最も低く,勾配歩行,Bruce法による連続歩行の順に高かった。PCIとMETSとの関係は,勾配歩行で最も高い相関(r = 0.87)を示した。臨床的にはPCIという簡便な方法を用いてエネルギー消費を間接的に推測出来るが,運動負荷方法によりPCIが異なるため,応用するには注意が必要である。
1 0 0 0 OA なぜ英語で論文を書くのか:5 つの動機
- 著者
- Andrew Paul 佐藤 春彦
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.289-293, 2019 (Released:2019-08-20)
1 0 0 0 OA 延髄外側梗塞患者における自覚的視性垂直位と静止立位バランスおよび歩行非対称性の関連
- 著者
- 荒井 一樹 松浦 大輔 杉田 翔 大須 理英子 近藤 国嗣 大高 洋平
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.5, pp.364-371, 2017 (Released:2017-10-20)
- 参考文献数
- 17
【目的】延髄外側梗塞患者において自覚的視性垂直位(以下,SVV)と静止立位バランス,歩行非対称性の関係を検討する。【方法】Body lateropulsion(BL)を呈する延髄外側梗塞患者9 名において,SVV 値と立位重心動揺計の総軌跡長,矩形面積,足圧中心左右偏位および加速度計より算出した歩行非対称性との関係をSpearman の相関係数を用いて検討した。【結果】SVV 値は平均7.4(SD:9.5)度であった。SVV 値と開眼足圧中心偏位とは相関しなかったが,閉眼足圧中心偏位と相関を認めた(r = 0.75, P < 0.05)。また,SVV 値の絶対値は歩行非対称性と有意な相関を認めた(r = –0.78, P < 0.05)。【結語】BL を呈する延髄外側梗塞患者において,SVV 偏位は閉眼の静止立位バランスと歩行非対称性と関連した。その因果関係については今後の検証が必要である。
1 0 0 0 OA 非特異的慢性腰痛を有する患者に対する神経生理学に基づいた患者教育の効果
- 著者
- 三根 幸彌 中山 孝 Steve Milanese Karen Grimmer
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.11145, (Released:2016-03-18)
- 参考文献数
- 43
【目的】非特異的慢性腰痛を有する患者に対する痛みの神経生理学に基づいた患者教育(pain neurophysiology education;以下,PNE)の効果を検討することを目的とした。【方法】英語・日本語の無作為化比較試験を対象として2015年6月5日までの系統的検索を行った。バイアスのリスクの評価にはPhysiotherapy Evidence Database スケールを用いた。データの統合は記述的に行われた。【結果】6 編の英語論文が低いバイアスのリスクを示した。PNE が他の患者教育よりも効果的であるという明確なエビデンスはなかった。また,PNE と他の介入を併用した際に効果が減弱する可能性が示唆された。【結論】PNE を用いる場合は,患者特性と他の介入との相性を考慮する必要がある。将来の研究はこの研究で明らかになった方法論的欠点を解消し,PNE の効果についてより質の高いエビデンスを提示する必要がある。
1 0 0 0 OA 車いすテニスにおけるサーブ動作の運動学的解析
- 著者
- 木村 大輔 岩田 晃 川﨑 純 島 雅人 奥田 邦晴
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.59-66, 2012-04-20 (Released:2018-08-25)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
【目的】本研究では,運動学的視点から,車いすテニス選手のサーブ動作の特徴をあきらかにすることを目的とした。【方法】三次元動作解析装置と表面筋電図を用いて,車いすテニス選手8名による通常のサーブ動作を計測し,一般テニス選手のサーブ動作と比較した。【結果】車いすテニス選手と一般テニス選手のサーブ動作を比較すると,車いすテニス選手では,最大外旋位で肩関節外旋角度が有意に低値を示し,インパクト時では,水平内転角度が有意に高値を示し,外転角度が有意に低値を示した。最大外旋位からインパクトまでのフォワードスイング相における水平内転・内転運動が特徴的であった。【結論】車いすテニスのサーブでは,もっとも肩関節への負荷が大きいとされるフォワードスイング相において,肩関節が固定されず,水平内転・内転運動しており,肩甲骨と上腕骨を安定させた状態での上腕骨の回旋を困難にしている。これより車いすテニスのサーブ動作は肩関節障害の発生リスクを高めることが示唆された。
1 0 0 0 高齢者の介護予防教室への参加・不参加要因に関する研究
- 著者
- 遠藤 寛子 板井 英樹 桜木 康広
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, pp.E0353, 2007
【目的】高齢化が急速に進む中、全国市町村各地域で介護予防対象者に対しての介護予防教室などが2000(平成12) 年の介護保険制度開始から徐々に開始され、2006(平成18)年4月からの介護保険制度の改訂により、現在では一層多く開催されるようになった。しかし、実状として介護予防教室には介護予防を必要としている全ての対象者が参加しているわけではなく、介護予防が必要な方の中でも参加していない方も多い現状がある。そこで、参加していない理由、または参加できない理由について、参加している方と参加していない方の要因を比較検討し、今後の参加率向上に繋がる方法について考察した。<BR>【方法】A県内3市4町各地域の在宅介護支援センターが把握している介護予防対象者(特定高齢者含む)のうち、過去1年間介護予防教室への参加がある高齢者と過去1年間介護予防教室へ参加したことがない高齢者の中から無作為に選んだ230名を対象とした。その対象となった方が登録されている在宅介護支援センターに、厚生労働省推奨の介護予防のための基本チェックリストと独自に作成した介護予防/転倒予防・健康状態に関するアンケート用紙の2種類を郵送または直接訪問し自記式にて実施した。調査期間は平成18年9月から10月の1ヵ月間とした。<BR>【結果】アンケートの回収率は、対象者158通(68.7%)であり、有効回答数は男性27名、女性121名の計148名であった。平均年齢は74.6±6.3歳で、独居世帯は33世帯(21.5%)を占めていた。介護予防教室に参加している方は、女性が圧倒的に多く、頻度が少なくなるにつれて男性の比率が上がってきていた。同居家族の人数による違いは見られず、全く参加していない方は、独居が多い傾向があった。自覚的健康観は、「まあまあ健康である」と感じている人が多数を占めた。また、健康に関するメディアへの関心は、「とてもある」「まあまあある」で、9割以上を占めていた。身体を動かすことや友達の家への訪問は、介護予防教室への参加頻度が上がるにつれ増加傾向にあった。ただし、身体の痛み、身体を動かす機会や自分から人に声を掛ける機会、人見知りや人と仲良くできないことに関しては、あまり差がみられなかった。介護予防教室に言葉や内容、開催の認知については、参加していない人に認知されていなかった。<BR>【考察】介護予防教室への参加要因として、自分の健康観というより、身体を動かすことが好きで他人との交流を目的としていることが考えられた。一方、不参加要因としては、健康に対する意識や関心は高く、それ相応に身体を動かしているものの、教室自体の存在や目的が、各地域で必ずしも周知徹底していないことが考えられ、今後、広報活動や地域でのネットワークづくりの必要性が高いと考える。<BR>
1 0 0 0 OA 腹圧性尿失禁に対する理学療法のエビデンス
1 0 0 0 嚥下と呼吸の相互連関に関する研究
- 著者
- 藤野 英己 祢屋 俊昭 武田 功
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.218-224, 1997
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 3
嚥下第2相では,呼吸運動と特に密接な関係が必要であると考えられている。そこでフォーストランスジューサおよび呼吸ピックアップセンサーを用いて,喉頭運動曲線,呼吸曲線を記録し,嚥下と呼吸の相互連関について検討した。嚥下時には安静呼吸に比較して,小さな呼吸が喉頭挙上に同期して生じた。この呼吸と喉頭運動の時間的相互連関を明らかにすることによって,正常嚥下の生理学的反応を推定した。その結果,喉頭挙上の開始直後に嚥下呼吸が発生し,喉頭が降下開始後に嚥下呼吸は呼息相に移行した。これは喉頭が挙上した後に嚥下呼吸の吸息が生じることによって気道内圧が下降し,気道閉鎖を完全な状態とすることを意味すると推測された。また,"むせ"の状態では嚥下呼吸が喉頭挙上に先行した。さらに,姿勢による影響について背臥位(頸中間位,頸前屈位,頸後屈位)で測定し,比較検討した。一方,この測定方法が嚥下の定量的評価として有用かについても考察を加えた。
1 0 0 0 OA 痙直型脳性麻痺者における足関節等尺性背屈時のH 波の特徴
- 著者
- 楠本 泰士 菅原 仁 松田 雅弘 高木 健志 新田 收
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.168-173, 2019 (Released:2019-06-20)
- 参考文献数
- 15
【目的】本研究の目的は,痙直型脳性麻痺(以下,CP)者における安静時と足関節等尺性背屈時のH 波の振幅値変化の違いを明らかにすることとした。【方法】対象は粗大運動能力分類システムにてレベルⅠ,Ⅱ,ⅢのCP 群14 名と健常者である対照群14 名とした。CP 群では下肢随意性検査を行い,利き足を決定した。両群で利き足でのヒラメ筋のH 波最大振幅値を安静時と等尺性背屈時とで比較した。【結果】対照群は等尺性背屈時にH 波最大振幅値が有意に低下したが,CP 群は振幅値が低下した者が8 名,上昇した者が6 名であり,全体としては変化がなかった。【結論】CP 者は足関節等尺性背屈時にヒラメ筋への相反抑制がかからない者がおり,健常者と比べて脊髄前角細胞の興奮性が十分に制御されていなかった。CP 者の腓腹筋やヒラメ筋のストレッチでは,背屈時のH 波振幅値の上昇と低下に合わせて,相反抑制の効果を組み合わせるか判断する必要性が示唆された。
1 0 0 0 OA 物理的刺激と生体反応
- 著者
- 杉元 雅晴
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.248-252, 2004-06-20 (Released:2018-09-25)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 眼球運動失行を伴う失調症患者(689insT)の臨床症状
- 著者
- 堀本 佳誉 菊池 真 小塚 直樹 舘 延忠
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.B1567, 2008
【諸言】常染色体劣性遺伝性脊髄小脳変性症のひとつである、眼球運動失行を伴う失調症(AOA1)はaprataxin遺伝子の変異により起こる疾患である。この遺伝子の翻訳するタンパクは一本鎖遺伝子損傷修復機能を有することが確認されている。疾患の発症時期は10歳以前であり、発症早期より失調症状が認められ、その後、疾患の進行とともに末梢神経障害が著明となる。成人期AOA1患者の小脳症状と末梢神経障害の臨床症状を知ることは、予後を予測した理学療法を行うために重要である。また、一過性の過負荷の運動は遺伝子やタンパクの損傷を引き起こし、逆に規則的で適度な運動は損傷を一定に保つか減少させることが知られており、AOA1患者の臨床症状における遺伝子損傷レベルを知ることは適切な運動量・強度の処方の上で重要な指標となる。<BR>【方法】対象はAOA1患者(689insT)の姉妹(44歳、48歳)であった。末梢神経症状の量的評価として運動神経伝導速度の計測を行った。対象神経は、上肢は尺骨神経、下肢は腓骨神経とした。重症度は厚生省運動失調調査研究班によるSCDの重症度分類、小脳症状はInternational Cooperative Ataxia Rating Scale、末梢神経症状はNeuropathy Disability Score、筋力評価はMedical Research Council sum score(MRCS)を用い、質的評価を行った。遺伝子損傷レベルの測定は平常時の尿中8-ヒドロキシデオキシグアノシン(以下8-OHdG)濃度測定を行い、40代女性10名(43.3±2.1歳;41~46歳)を対照群とした。各被検者に対し、本研究の説明を行い、書面にて同意を得た。<BR>【結果】神経伝導速度は、尺骨神経では21.2m/s、20.5 m/s、腓骨神経では計測不能で、尺骨神経では20歳代から40歳代の約15年で20m/s程度の低下が認められた。質的評価により、重度の小脳失調と、特に末梢部・下肢に強い筋力低下が認められることが明らかとなった。尿中8-OHdGでは、対照群は3.7±1.2ng/mg、AOA1患者はそれぞれ4.0ng/mg、7.3ng/mgであり、対照群との差は認められなかった。<BR>【考察】成人期AOA1患者の臨床症状の評価により、より早期に小脳症状に対する理学療法のみでなく、末梢神経障害を考慮した身体局所の選択的筋力強化、関節変形・拘縮の予防的運動療法などの理学療法を行うことが重要になると考えられた。平常時の尿中8-OHdGは対照群との差が認められなかったが、過負荷な運動はAOA1患者の病状の進行を助長してしまう可能性があることを考慮すると、今後、理学療法前後の尿中8-OHdGの測定を行う必要があると考える。
1 0 0 0 21. 杉並区住宅改造費助成事業への関わりとその意義
- 著者
- 西ケ谷 節美 堀川 進 金沢 成志 安宅 雪子 森 敏 原 理恵子 大石 早苗 藤本 續
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, 1997
1 0 0 0 ヒール形状の違いが歩行中の膝関節に及ぼす影響
- 著者
- 重枝 利佳 石井 慎一郎
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.A0514, 2008
【目的】近年,ハイヒールやミュールなどを使用する女性が増えてきているが,これらの女性の歩行を見ると,明らかな膝関節の動揺や膝関節痛を訴えることが多い.そこで,三次元動作分析装置を用いて,裸足とヒール形状の違うミュール2種類を使用した時で,平地歩行において膝関節にどのような影響を及ぼすかを明らかにすることを目的とした.<BR>【方法】対象者は,健常女性20名とした.計測条件は,1)裸足,2)ヒール幅1.1cmのミュール(以下,ピンヒール),3)ヒール幅3.3cmのミュール(以下,ヒール)とし,それぞれ平地歩行を3試行ずつ行った.歩行計測には三次元動作分析装置VICON612(VICON PEAK UK)を使用し,Andriacchiらにより考案されたPoint Cluster法を用いて,歩行中の膝関節の屈曲・回旋・内反角度を算出した.分析は,歩行周期中に最も膝関節に動揺が起こるといわれている立脚初期に着目し,各パラメータを裸足,ピンヒール,ヒールの3群間で比較した.<BR>【結果】屈伸角度は,裸足が-20.8±7.7°,ピンヒールが-26.8±6.7°,ヒールが-26.4±8.1°であった.3種間で有意差は認められなかった.回旋角度は,裸足が-4.9±3.1°,ピンヒールが-8.0±3.3°,ヒールが-7.1±3.4°であった.裸足とピンヒール間に有意差が認められた.(p>0.041)内外反角度は,裸足が3.1±2.2°,ピンヒールが6.4±2.8°,ヒールが6.4±2.6°であった.裸足とピンヒール,裸足とヒール間で有意差が認められた.(p>0.004,p>0.003)<BR>【考察】歩行における立脚初期の膝関節は,大殿筋や大内転筋の働きによる大腿骨の外旋と,足関節の内反から外反へ向かう運動が引き起こす運動連鎖による脛骨の内旋によって,内旋位に置かれ動的安定化を図っている.しかし,ミュールを履くことで常に底屈位となる足関節は,踵接地から全足底接地にかけて,足関節の内反から外反へと向かう運動を行う時間を稼ぐことができず,脛骨を直立化させる運動連鎖を起こすことができない.そのため,ピンヒール,ヒールともに内反が大きくなったと考える.これを代償するために,床反力作用点を移動させて脛骨を直立化させる運動連鎖を起こすだけの時間を稼ごうとするが,ピンヒールは一点で接地するため十分な時間を稼ぐことができないのに対し,ヒールはピンヒールよりも接地面積が大きいため,脛骨を直立化させる運動連鎖を起こすことができるだけの床反力作用点の移動が起き,ピンヒールの方が,外旋が大きくなったと考える.<BR>【まとめ】本研究で得られた結果より,ピンヒールを使用することは膝関節にかなりの負担を与えるため,使用しないことが最も望ましい.しかし,近年多くの女性が社会進出することが当然となり,ハイヒールを使用する機会は増えてきている.ハイヒールを履かなければいけない場合は,接地面積の多く取れる,幅の広いヒールを使用すると良いと考えられた.
1 0 0 0 OA 日本における動物に対する理学療法の実際
- 著者
- 依田 綾香
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.8, pp.722-723, 2015 (Released:2016-01-15)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA やる気を引きだす生活支援
- 著者
- 足達 淑子
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.8, pp.486-491, 2014-12-20 (Released:2017-06-10)
1 0 0 0 OA 他者に運動技術を教授することによる即時的な運動学習効果
- 著者
- 川崎 翼 河野 正志 兎澤 良輔
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.306-310, 2017 (Released:2017-08-20)
- 参考文献数
- 21
【目的】本研究の目的は,経験した運動スキルを他者に教授することの即時的な運動学習効果を明らかにすることであった。【方法】参加者は若年成人23 名であり,教授群12 名,コントロール群11 名に分けられた。運動学習課題は,2 つの球を非利き手で回す課題とした。教授群は球回しの練習後,1 分間の球回しパフォーマンスが計測された。この後,球の回し方について教授群は聞き手に教授した。その直後と2 分後に再度,パフォーマンスを計測した。コントロール群は教授群と同様の手続きであるが,教授は行わず科学雑誌を音読した。【結果】教授群のみ球回し回数が有意に増加した。また,教授群はコントロール群に比べて,球回しの改善回数が有意に多かった。【結論】他者に経験した運動スキルを教授することは,即時的に運動学習を促進する可能性が示された。
1 0 0 0 OA 全身性関節弛緩症と足関節不安定性
- 著者
- 大城 昌平 松本 司 横山 茂樹 藤田 雅章
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.5, pp.463-468, 1990-09-10 (Released:2018-10-25)
全身性関節弛緩症(GJL)が足関節不安定性の発症や病態にどのように関与しているか,特に足関節の捻挫既往,及びスポーツ活動の関連について知るため,GJLの58例116足関節を対象に,中等度以上の捻挫既往の有無と3年以上のスポーツ歴の有無について問診し,足関節の機械的不安定性の指標としてストレスX線撮影,機能的不安定性の指標として片脚立位での重心動揺の測定を行った。まず,症例を捻挫既往の有無により2群に分けて検討した。次に,3年以上のスポーツ歴の有無と,さらに捻挫既往の有無により分けた4群について検討した。その結果,GJL,あるいはGJL存在下でのスポーツ活動そのものは足関節不安定性に直接的に関与しているのではなく,捻挫既往の有無が,足関節不安定性の重要な関連因子であることが示唆された。
1 0 0 0 OA 理学療法士の職域拡大
- 著者
- 塩中 雅博
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.4, pp.279-281, 2010-06-20 (Released:2018-09-12)
1 0 0 0 脳卒中患者における自転車動作に関する研究
- 著者
- 今井 一郎 原 久美子 有馬 和美 福室 智美 田中 博 菅谷 睦
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.E1676, 2008
【はじめに】<BR> 臨床現場において脳卒中患者から標準型2輪自転車(以下自転車)に乗りたいという希望をよく聞く.2年前に実施したアンケート調査から,脳卒中発症後自転車を利用しなくなった人の約7割が自転車に乗りたいと回答し,自転車乗車のアプローチの必要性を認識できた.今回は健常者と脳卒中患者に自転車動作の観察と体力テストを行い自転車動作の機能を検討した.<BR>【対象】<BR> 普段自転車に乗車している健常成人23名(男性7名,女性16名,平均年齢44.9歳)と,脳卒中の既往があり屋外歩行自立の 3名(症例A:74歳男性,右小脳梗塞,Br.stage左右上肢手指下肢全て6,症例B:81歳女性,多発性脳梗塞,Br.stage左上肢手指下肢全て5,症例C:74歳男性,右脳梗塞,Br.stage左上下肢3手指5)とした.対象者には本研究について説明し同意を得た.<BR>【方法】<BR> 自転車動作は,走る(ふらつきを観察)・止まる(目標物の手前で止まる,笛の合図で止まる)・曲がる(ふくらみを観察),体力テストは握力・上体起こし・長座体前屈・開眼片足立ち(最高120秒)・10m障害物歩行・6分間歩行を実施した.症例BとCは自転車乗車前に前提動作として,スタンドをしてペダルを回す・片足での床面支持・外乱に対してブレーキ維持を実施した.<BR>【結果】<BR> 前提動作で症例Cは全て不可能であったため体力テストのみ実施した.自転車動作の観察では,健常者12名と症例Aで走行時ふらつきがみられた.症例Bは走行時ふらつきの観察まではペダルに両足を乗せることができなかったが,以降の止まるからはペダルを回すことが可能となった.止まるは健常者・症例共,目標物手前で止まることができ,笛の合図では健常者・症例共,同様の停止距離であった.曲がるは症例A・Bにふくらみがみられた.体力テストでは,症例全員が6分間歩行,症例B,Cは上体起こし,Cは10m障害物歩行が困難であった.実施できた項目も健常者と比べ低下していた.健常者の自転車動作と体力テストの関係では,開眼片足立ち120秒可能者の割合が,走行時ふらつきのあった群で41.7%,ふらつきのなかった群で100%となった.<BR>【考察】<BR>関根らは高齢者に10日間1日2回片足立位訓練を行い片足立位時間の延長と自転車運転動作の向上を報告し,自転車動作についてのバランス感覚の重要性を指摘している.今回は片足立位時間と自転車走行時のふらつきに関係がみられた.これらのことから片足立位バランスと自転車動作に関係があると考えられる.症例Cは重度の左上下肢の随意性低下と感覚障害があり,それが前提動作を困難にしたと推察され,自転車動作には四肢の分離運動機能や協調運動機能が重要と考えられる.小村はBr.stage上下肢4の脳卒中患者が3輪自転車のペダルを改良し乗車していると報告しており,症例Cも同様の方法による乗車の検討が考えられる.また症例Bは途中から走行が可能となったことから,練習での乗車能力の改善が示唆された.
- 著者
- 佐藤 仁 高橋 輝雄 加藤 宗規
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.6, pp.286-287, 2001
- 被引用文献数
- 1
学内において,学生が抱く障害イメージを教員が客観的に把握する指標を見出すことを目的とし,Barthel Index(以下,BI)を用いて検討した。「脊髄損傷に対する理学療法」の授業初日および最終日において,学生33名に対麻痺者に対するイメージをBIで得点化させた。BI平均点は,授業初日50.0 ± 12.4点,授業最終日には77.9 ± 12.4点と増加した(p<0.01)。授業最終日には,上肢機能を要する日常生活活動を自立のイメージとした学生数が増加した。また学生は授業聴講以前より,対麻痺者に対して整容は自立,移動は車椅子というイメージを抱いている傾向にあり,他の教科やマスメディアによる先行学習が形成されていることが推察された。学生が抱く障害イメージを客観的に把握するには,BIがひとつの指標として利用できることが示唆された。