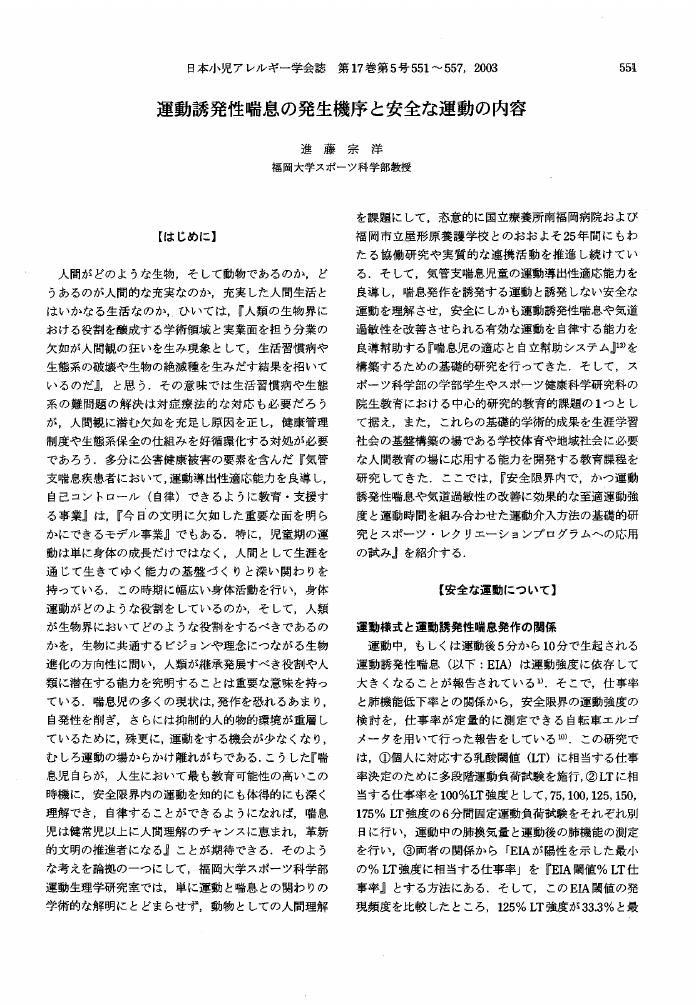1 0 0 0 食物依存性運動誘発性アナフィラキシーの4例
- 著者
- 足立 雄一 五十嵐 隆夫 吉住 昭 萱原 昌子 足立 陽子 松野 正知 村上 巧啓 岡田 敏夫
- 出版者
- 日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.40-45, 1991
- 被引用文献数
- 2
4例の食物依存性運動誘発性アナフィラキシーを経験した. それぞれの臨床症状について検討し, さらに全員に運動負荷を行い, その前後でCom48/80を用いた皮膚テストを実施した. 症例は男児1名, 女児3名. 13-16歳に発症し, 誘因はエビなどの甲殼類が2名, 小麦およびポテトが1名, 小麦が1名であった. いずれもRASTにて特異的IgE抗体を証明し得た. 運動はランニング, バレーボール, 早足歩行であり, 食後10分から2時間に運動することで発症している. 全員に蕁麻疹を認め, それ以外に意識消失や呼吸困難を認めた. 運動負荷のみでは全員無症状であったが, Com48/80に対する皮膚反応は3例において運動前に比して運動後に増大傾向を認めた. 以上より, 本疾患の発生機序としてアレルギー反応の関与が示唆されたが, 運動による皮膚肥満細胞の活性化の可能性については今後の課題である.
1 0 0 0 OA 小児アレルギーとヘルパーT細胞
- 著者
- 眞弓 光文
- 出版者
- 一般社団法人日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.1-6, 1999-06-01 (Released:2010-08-05)
- 著者
- 柴田 瑠美子 古賀 泰裕
- 出版者
- 一般社団法人日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.99-104, 2012 (Released:2012-05-31)
- 参考文献数
- 11
背景:アレルギー疾患の増加には乳児の消化管免疫に関わる微生物の働きの減弱が関連している可能性が指摘されている.そのため,これまでアトピー性皮膚炎における乳酸菌などによるプロバイオティクス効果について多くの検討がなされている.最近,アトピーリスク児におけるオリゴ糖によるプレバイオティクス効果として皮疹発症頻度の低下と腸内ビフィズス菌の増加が報告された.オリゴ糖は難消化性で消化管のビフィズス菌増殖作用がある.目的:オリゴ糖ケストースによる乳幼児アトピー性皮膚炎へのプレバイオティクス効果をRCTにて検討した.方法:食物アレルギーを有する乳幼児アトピー性皮膚炎の便中ビフィズス菌を検査し,12例のビフィズス菌低下児にケストースを12週間投与し,皮疹とビフィズス菌の変化を検討した.29例ではRCTによる効果を同様に検討した.結果:ビフィズス菌は皮疹重症例で低下し,皮疹重症度と逆相関していた.ビフィズス菌低下児へのケストース投与で6週より12週にビフィズス菌増加と皮疹改善効果がみられた.RCTでは,プラセボに比して有意に皮疹重症度の改善がみられ,ビフィズス菌低下群で有意のビフィズス菌増加がみられた.結論:オリゴ糖によるプレバイオティクス効果の機序は明らかでないが,ケストースは腸内細菌叢の健全化と消化管の透過性改善に直接関与する可能性がある.
- 著者
- 渋谷 紀子 斉藤 恵美子 苛原 誠 木戸 博
- 出版者
- 一般社団法人日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.5, pp.530-536, 2020-12-20 (Released:2020-12-20)
- 参考文献数
- 20
【背景】胎内感作の意義はいまだ明らかでない.【目的】新生児血中抗原特異的IgEを高感度測定法により測定し,乳児期の感作および食物アレルギー(FA)発症との関係を明らかにすること.【方法】125名の出生コホート研究を行った.新生児血中抗原特異的IgEを高性能蛋白チップにより測定し,6,12か月時に児のプリックテスト(SPT)を,0,1,6,12か月時に保護者へのアンケート調査を行った.【結果】125例の新生児血のうち,84%で何らかの抗原特異的IgEが検出され,約50%で卵白特異的IgEが陽性であった.新生児血中抗原特異的IgEは,SPTやFA発症と相関を認めなかった.妊娠中の鶏卵摂取量と新生児の鶏卵特異的IgEにも関連は認めなかった.生後早期の湿疹は,単変量解析ではSPTおよびFA発症と,多変量解析ではSPTと有意に関連していた.【結論】新生児血中IgEと乳児期の感作およびFA発症には関連が認められなかった.食物アレルギーに関与する感作は出生後に成立することが示唆された.
- 著者
- 李 崇至 谷内 昇一郎 松井 美樹 多賀 陽子 郷間 環 榎本 真宏 今出 礼 西野 昌光
- 出版者
- 一般社団法人日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.205-213, 2020-06-20 (Released:2020-06-19)
- 参考文献数
- 23
【目的】小児領域におけるアナフィラキシーおよび二相性反応に関しての報告は少なく,詳細は不明である.当院で経験した症例を検討し,二相性反応の実態を明らかにする.【方法】2015年-2018年に当院外来からアナフィラキシーの診断で入院となった201症例を対象とした.患者背景,原因,症状,治療および二相性反応も含めた臨床経過について診療録を用いて後方視的に検討した.【結果】対象は201例.原因は食物158例,薬物2例,動物1例,不明39例であった.初期治療でアドレナリン筋注を行った例は132例(66%)であった.二相性反応は9例(4.5%)であった.二相性反応のリスク因子として月齢(p=0.028)とアドレナリン筋注(p=0.028)に多変量解析で統計学的有意差を認め,オッズ比(95%信頼区間)は1.01(1.0-1.3)と0.19(0.044-0.026)であった.【結論】小児アナフィラキシーにおける二相性反応の頻度を明らかにした.初期治療としてのアドレナリン筋注の重要性を改めて認識させられた.
- 著者
- 村井 宏生 藤澤 和郎 岡崎 新太郎 林 仁幸子 河北 亜希子 安冨 素子 眞弓 光文 大嶋 勇成
- 出版者
- 一般社団法人日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.566-573, 2013 (Released:2013-12-11)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 8 5
【目的】教職員がアナフィラキシーを理解し初期対応を可能にするための教育は学校生活の安全のために必要不可欠である.教職員に対するエピペン®の実技指導を含む講習の有効性を検討した. 【方法】福井市の小中学校教職員を対象に,食物アレルギーとアナフィラキシーに関する講習とエピペントレーナーを用いての実技指導を行った.講習会前後でアナフィラキシー対応に関する意識の違いをアンケート調査により比較検討した. 【結果】講習前には,エピペン®認知度は97%であったが,使用法まで理解している者は29%にすぎなかった.使用に対する不安は,使用のタイミングが82%と最も多く,使用後の保護者からのクレームが68%であった.養護教諭や現場の教諭がエピペン®を施行するとした割合は,講習前の41%,28%から,講習後には63%,48%と著増した.実技指導により使用への抵抗感が軽減したとの回答が増加した. 【結論】講演会に実技指導を加えることは,アナフィラキシーに対する理解を深め,エピペン®使用の不安を軽減する上で有用と考えられた.
1 0 0 0 皮膚とアレルギー
- 著者
- 大矢 幸弘
- 出版者
- 日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.280-287, 2017
<p> アレルゲンの曝露回避はアレルギー疾患治療の基本と思われるが, 発症前の予防効果に関しては実証されていない. 特にアトピー性皮膚炎のように皮膚に炎症のある乳児では, 経口摂取を控えることで免疫寛容が誘導されず意に反して食物アレルギー発症のリスクが高まる. それは経皮感作という現象があるためである. 健常な皮膚は表皮のバリアを形成して外部からアレルゲンなどの異物の侵入を防いでいる. 表皮は下から基底層・有棘層・顆粒層・角層からなり, 角層の天然保湿因子や細胞間脂質そして角化細胞をつなぐコルネオデスモゾームや顆粒層のタイトジャンクションなどが複数のバリア機能を構成しているが, アトピー性皮膚炎の患者ではこうしたバリア機能の低下が認められる. 特に湿疹の重症度が高いほどバリア機能は低下しアレルゲンの感作を受けやすくなる. 健常な皮膚の抗原提示細胞は免疫寛容を誘導するが炎症のある皮膚では逆に感作を促進するため, アトピー性皮膚炎の予防や早期治療がアレルギーマーチの予防には重要と思われる.</p>
1 0 0 0 食物アレルギーの発症予防 ~離乳食早期摂取による経口免疫寛容~
- 著者
- 成田 雅美
- 出版者
- 一般社団法人日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.391-399, 2020-08-05 (Released:2020-08-20)
- 参考文献数
- 38
即時型食物アレルギーの発症予防には,食物抗原への感作予防と経口免疫寛容の誘導という2つの戦略がある.乳児アトピー性皮膚炎患者では皮膚バリア機能が低下した湿疹部位からの経皮感作がおこることが明らかになったが,食物感作の予防に有効な方法は報告されていない.しかし感作が成立後でも経口免疫寛容が誘導されれば食物アレルギーの発症を予防できる.最近のランダム化比較試験のメタ解析の結果,ピーナッツや鶏卵については生後4か月~6か月の早期摂取開始による食物アレルギー発症予防効果が認められている.わが国では数十年の間に鶏卵摂取開始が遅くなり平成19年には鶏卵摂取開始の目安が実情に合わせて7,8か月とされた.その後の知見をふまえ「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定版)」では鶏卵摂取開始が離乳食開始時期の生後5,6か月に変更された.食物抗原の離乳食早期摂取開始は,すでに食物アレルギーを発症した患者での症状誘発などに注意する必要はあるが,経口免疫寛容の誘導による食物アレルギー発症予防が期待される.
1 0 0 0 オマリズマブを投与した小児気管支喘息における呼吸機能の長期経過
- 著者
- 米野 翔太 長尾 みづほ 松浦 有里 星 みゆき 鈴木 尚史 今給黎 亮 小堀 大河 藤澤 隆夫
- 出版者
- 一般社団法人日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.325-333, 2020-08-05 (Released:2020-08-20)
- 参考文献数
- 22
【目的】重症喘息に投与されるオマリズマブが呼吸機能を改善させるか否かの評価は未だ確立していない.オマリズマブの投与を必要とした小児喘息で長期観察できた例で呼吸機能の推移を評価した.【方法】オマリズマブ投与後1年以上の小児気管支喘息患者を対象とし,診療録から後方視的に呼吸機能と臨床情報を収集した.%FEV1の変化量/年は投与前後の期間で,すべての測定データを線形回帰分析で算出した.【結果】対象は10例.オマリズマブ投与前の観察期間が1年以上の6例すべてで線形回帰から求めた%FEV1の変化量/年は負の値であった.1年未満の例は評価しなかった.オマリズマブの投与期間は1年9か月~7年6か月で,変化量が正の値となったのが5例,負の値が5例であった.負の例でも投与前観察期間が1年以上の3例では負の値が軽減していた.投与後に変化量が正に転ずる予測因子は同定できなかった.【結論】コントロール不良の喘息児においてオマリズマブ投与は呼吸機能を改善させるもしくは低下の程度を軽減する可能性がある.
- 著者
- 鈴木 亮平 相良 長俊 青田 明子 赤司 賢一 勝沼 俊雄
- 出版者
- 一般社団法人日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.319-324, 2020-08-05 (Released:2020-08-20)
- 参考文献数
- 12
【背景】Modified Pulmonary Index Score(MPIS)は客観性や再現性に優れた小児喘息急性増悪の評価方法である.MPISは入院を決定する上で有用なツールとなり得るが,評価項目に心拍数が含まれ,発熱の影響を受ける可能性が示唆される.【目的】入院予測のためのMPISカットオフ値が発熱の有無で変化するかを明らかにする.【方法】2013年11月から2018年10月に救急外来を受診した喘息急性増悪患児を対象とし,受診時のMPISと入院の有無との関係を後方視的に検討した.さらに,発熱患者のMPISを体温で補正し,入院との関係性を再度検討した.【結果】発熱患者における入院確率が80%となる受診時MPISのカットオフ値は,体温での補正前は9.7点(95%信頼区間=8.9-11.1),補正後で9.5点(95%信頼区間=8.6-10.9)であった.【結論】MPISは発熱を有する喘息急性増悪患者にも問題なく使用できる評価方法である.
- 著者
- 柴田 瑠美子 古賀 泰裕
- 出版者
- 日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.99-104, 2012
背景:アレルギー疾患の増加には乳児の消化管免疫に関わる微生物の働きの減弱が関連している可能性が指摘されている.そのため,これまでアトピー性皮膚炎における乳酸菌などによるプロバイオティクス効果について多くの検討がなされている.最近,アトピーリスク児におけるオリゴ糖によるプレバイオティクス効果として皮疹発症頻度の低下と腸内ビフィズス菌の増加が報告された.オリゴ糖は難消化性で消化管のビフィズス菌増殖作用がある.目的:オリゴ糖ケストースによる乳幼児アトピー性皮膚炎へのプレバイオティクス効果をRCTにて検討した.方法:食物アレルギーを有する乳幼児アトピー性皮膚炎の便中ビフィズス菌を検査し,12例のビフィズス菌低下児にケストースを12週間投与し,皮疹とビフィズス菌の変化を検討した.29例ではRCTによる効果を同様に検討した.結果:ビフィズス菌は皮疹重症例で低下し,皮疹重症度と逆相関していた.ビフィズス菌低下児へのケストース投与で6週より12週にビフィズス菌増加と皮疹改善効果がみられた.RCTでは,プラセボに比して有意に皮疹重症度の改善がみられ,ビフィズス菌低下群で有意のビフィズス菌増加がみられた.結論:オリゴ糖によるプレバイオティクス効果の機序は明らかでないが,ケストースは腸内細菌叢の健全化と消化管の透過性改善に直接関与する可能性がある.<br>
1 0 0 0 OA 運動誘発性喘息の発生機序と安全な運動の内容
- 著者
- 進藤 宗洋
- 出版者
- 一般社団法人日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.5, pp.551-557, 2003-12-01 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 15
- 著者
- 田代 香澄 大園 恵梨子 大西 愛 佐々木 理代 柴田 富美子 橋本 邦生 坂本 綾子
- 出版者
- 一般社団法人日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.236-240, 2018 (Released:2018-06-30)
- 参考文献数
- 9
ダイエット用食品としてのエリスリトール使用量は近年増加傾向にあり, 小児における即時型アレルギー症状の報告例も散見されるようになった. 今回, 食品のみならず抗インフルエンザ薬タミフル®ドライシロップにも過敏症状を呈した症例を経験したので報告する. 症例は, 9歳女児, 2年前より, 低カロリーゼリー, ガム, 抹茶アイスクリームなどを摂取後に, 眼瞼浮腫, 蕁麻疹, 呼吸困難などの即時型のアレルギー症状を経験していた. また, タミフル®ドライシロップを内服した際にも, 同様の症状が出現していた. 症状誘発した製品に共通にエリスリトールが含まれていることから, 原因物資である可能性を疑い, 99%エリスリトール含有甘味料を用いて, プリックテストを行うも陰性だった. しかし, 経口負荷試験にて総量1g摂取したところ, 眼瞼浮腫と顔, 体幹の蕁麻疹が出現し, エリスリトールアレルギーであると診断した. エリスリトールが, 一般の菓子類や, 医薬品にも含まれていることを考慮し, 小児においても, 注意喚起を続けていく必要があると思われる.
1 0 0 0 OA 小児アトピー性皮膚炎に対する海水浴療法
- 著者
- 秋本 憲一 斉藤 博之 赤沢 晃 橋本 光司 勝沼 俊雄 野々村 和男 海老沢 元宏 永倉 俊和 植草 忠 恩田 威文 福田 保俊 飯倉 洋治
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY OF PEDIATRIC ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.96-100, 1990-08-25 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1 1
重症のアトピー性皮膚炎患児のなかには食物除去療法, 環境整備, 薬物療法, 免疫療法, ステロイド外用療法等を行っても治療に抵抗するものが結構多い. 重症アトピー性皮膚炎患者が夏休み明けに軽快していることがしばしば経験し, 海水浴がアトピー性皮膚炎の治療に役立つのではないかと考え, 昭和63年の夏にアトピー性皮膚炎患児9名を対象に一週間の海水浴療法を経験し, 好結果を得た. 今回行った方法は, 患者を神奈川県二宮町の国立小児病院二宮分院に入院させ, 食物療法, 薬物療法等の治療に加え二宮町の海岸で午前一時間, 午後二時間, 海岸で海水による皮膚の洗浄を行うものである. 僅か一週間の短期間で通常の入院治療より優れた寛解が得られ, 厳格な食物除去療法のような社会的・栄養的な問題, 薬物療法による副反応等の問題がないため, 海水浴療法は重症の小児アトピー性皮膚炎に対して是非試みるべき治療法と考えられた.
1 0 0 0 乳の早期導入と牛乳アレルギー予防
- 著者
- 林 大輔
- 出版者
- 一般社団法人日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.36-40, 2018 (Released:2018-03-31)
- 参考文献数
- 20
母乳栄養とアレルギーの関係について多くの研究が行われ, 完全母乳栄養がアレルギーに防護的であると考えられていた. EAACIは食物アレルギー予防のために生後4~6か月の完全母乳栄養が望ましいとしている. しかし, 人工乳開始時期と牛乳アレルギー発症時期を検討した研究では生後14日以前に人工乳を開始した群で牛乳アレルギーの発症頻度が低下していた. また, 牛乳アレルギー児の哺乳状況の後方視的調査では牛乳アレルギー児で新生児期からの1日1回以上の継続的な人工乳摂取の頻度が低く, 卵アレルギー児の牛乳アレルギー併発と人工栄養の関係の調査でも牛乳アレルギー併発群では生後3か月以内の継続的人工乳摂取の頻度が低かった. これらの知見より新生児期からの継続的な人工乳の摂取が, アレルギー発症を予防する可能性が考えられる. 一方で母乳栄養には感染症やSIDSの予防効果などもあり, 継続的な人工乳の摂取がこれらにどのような影響を与えるかはわかっていない. 乳早期導入の効果・安全性の検証のためさらなる知見の集積が必要である.
- 著者
- 柴田 瑠美子
- 出版者
- 日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.56-60, 2007-03-01 (Released:2007-12-04)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 2
食物アレルギー児は保育園,学校の給食時に症状が誘発されやすく,アナフィラキシーの回避のためには,医療機関との十分な連携が必要である.食物アレルギーの診断を行い,除去食指示書(診断書)により現在の正確な医療情報,誤食時の対応法,アレルゲン除去食品,代替食対応の知識を提供し,全職員・他の児童を含めた食物アレルギー児への理解をはかることが大切である.
1 0 0 0 卵の早期導入と卵アレルギー発症予防
- 著者
- 夏目 統
- 出版者
- 日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.27-35, 2018 (Released:2018-03-31)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
食物アレルギーの発症予防法は, 食物除去から乳児期早期摂取開始へとパラダイムシフトが起こった. これは, 食物アレルギーの原因が経腸管感作ではなく, おもに経皮感作であることが明らかにされ, 経口摂取はむしろ免疫寛容をもたらすことがわかってきたためである. 実際に, 乳児期早期の経口摂取が食物アレルギーの発症を予防できることが明らかにされたのは, 2015年のランダム化比較試験が初めてである. 卵に関するランダム化比較試験は現在までに6研究が報告され, メタアナリシスで早期摂取開始により卵アレルギーの発症が予防されることが明らかにされた. ただし, 実際に予防法を実践する上では即時型アレルギー反応の誘発に配慮する必要がある. 日豪, アジアからの提言で卵アレルギー発症予防の関連部分では, 有害事象を減らすために 「加熱卵」 を 「少量から」 摂取するように推奨し, 摂取開始時期等はアトピー性皮膚炎で層別化されている. しかし, その後の増量方法は明確な記載が少ない. 今後, 増量法, 摂取回数, 継続期間等の検討が行われることを期待したい.
1 0 0 0 玩具を用いた幼児の聴診手技の向上に関する検討
- 著者
- 西藤 成雄
- 出版者
- 日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.267-274, 2008
- 被引用文献数
- 1
<B>背景</B> 幼児の呼気終末で喘鳴を確認するために,玩具を用いた小児の聴診手技の向上について検討を行った.<BR><B>調査方法</B> 風車,吹き上げボール(ボール),象さん吹き上げ糸(ゾウ)の3つの玩具を選び,呼吸音をソノグラフにより解析を行った.また Web ページにてそれら玩具のモニター医師を募集し,77名のアンケート回答が得られた.<BR><B>結果</B> ソノグラフでは,風車は吸呼気比は短くばらつきも最も大きかった.ボールは吸呼気比は最も長いが,ばらつきが大きい.ゾウは吸呼気比は吹き上げボールに及ばなかったが,ばらつきは最も小さい.アンケートでは,呼吸音と喘鳴の聴取においてゾウが最も高く評価された.ボールは取り扱いが難しく誤飲の指摘があった.<BR><B>考案</B> ソノグラフでは,ゾウが規則正しく呼気終末まで努力呼吸を繰り返していると考えられ,またアンケートの総合評価でも聴診の補助具としての評価が高い.本玩具を用いることで幼児でも呼気終末まで喘鳴の消失が確認しやすくなり,より確実に病状の把握ができることを期待する.
1 0 0 0 東日本大震災におけるアレルギー児の保護者へのアンケート調査
- 著者
- 山岡 明子 阿部 弘 渡邊 庸平 角田 文彦 梅林 宏明 稲垣 徹史 虻川 大樹 柳田 紀之 箕浦 貴則 森川 みき 近藤 直実 三浦 克志
- 出版者
- 日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.801-809, 2011
- 被引用文献数
- 10
【目的】アレルギー疾患を有する小児が東日本大震災によってどのような影響を受けたかを調査し,今後の対応を検討する.<br> 【対象と方法】対象は,宮城県立こども病院総合診療科,仙台医療センター小児科,森川小児科アレルギー科を定期受診した402名のアレルギー疾患の小児の保護者.口頭で同意を得た後,外来の待ち時間にアンケート記入を行い,診察時に回収した.<br> 【結果】困った事で最も多かった回答は,それぞれ,気管支喘息では「停電のため電動式吸入器が使用できなかった」,アトピー性皮膚炎では「入浴できず湿疹が悪化した」,食物アレルギーでは「アレルギー用ミルクやアレルギー対応食品を手に入れるのが大変だった」であった.<br> 【まとめ】大震災に対する今後の対応として,気管支喘息では停電の時でも吸入できるような吸入薬や吸入器の備え,アトピー性皮膚炎では入浴できない時のスキンケアの指導,食物アレルギーではアレルギー用ミルクを含めたアレルギー対応食品の備蓄や避難所などの公的機関で食物アレルギーへの理解を深める啓蒙活動が必要と考えた.<br>
- 著者
- 益海 大樹 竹村 豊 有馬 智之 長井 恵 山崎 晃嗣 井上 徳浩 竹村 司
- 出版者
- 日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.262-267, 2017 (Released:2017-08-31)
- 参考文献数
- 16
エリスリトールは低分子の糖アルコールで, カロリーが極めて低く, 甘味料としての需要が拡大している. 症例は10歳女児. 8歳, 9歳時にアイスクリームなどを摂取後のアナフィラキシー歴を3回有していたが, 原因は不明であった. 10歳時, 公園で遊び, 複数の菓子を摂取後に咽頭痛と乾性咳嗽, 蕁麻疹を認め, 当院外来を受診. 菓子内にはエリスリトールとソルビトールが含まれ, アレルゲンの可能性が考えられた. エリスリトールとソルビトールのプリックテストはともに陰性で, 皮内試験ではエリスリトールのみ陽性であった. 両者の食物経口負荷試験を施行し, ソルビトールは陰性, エリスリトールは合計1.7g摂取し30分後に皮膚・呼吸器症状を認め, アナフィラキシーを呈した. のちに実施した好塩基球活性化試験 (BAT) では反応を認めなかった. 近年, エリスリトールによる即時型食物アレルギーの報告例が増加している. 小児で摂取頻度の高い菓子に含有されていることがあり注意を要する. 本症例の糖類摂取における食事指導に有用であった.