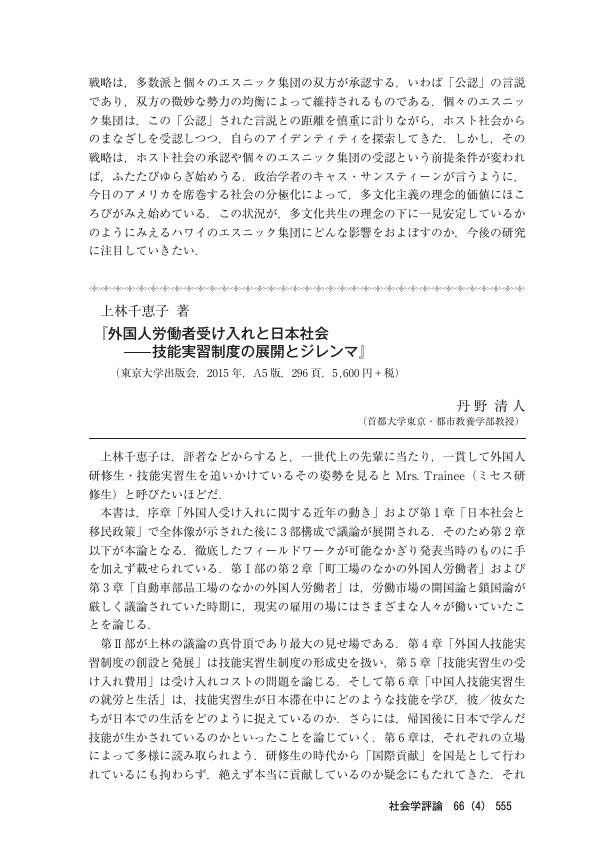4 0 0 0 OA 車内空間の身体技法
- 著者
- 田中 大介
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.40-56, 2007-06-30 (Released:2010-03-25)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
本論文は,日露戦争前後の電車内における身体技法の歴史的生成を検討することによって,都市交通における公共性の諸様態を明らかにすることを目的としている.電車は明治後期に頻発した群集騒乱の現場になっていたが,同時期,法律から慣習のレベルまで,電車内の振る舞いに対する多様な規制や抑圧が形成された.これらの規制や抑圧は,身体の五感にいたる微細な部分におよんでいる.たとえば,聴覚,触覚,嗅覚などを刺激する所作が抑圧されるが,逆に視覚を「適切に」分散させ・誘導するような「通勤読書」や「車内広告」が普及している.つまり車内空間は「まなざしの体制」とでもよべる状況にあった.この「まなざしの体制」において設定された「適切/逸脱」の境界線を,乗客たちは微妙な視線のやりとりで密かに逸脱する異性間交流の実践を開発する.それは,電車内という身体の超近接状況で不可避に孕まれる猥雑さを抑圧し,男性/女性の関係を非対称化することで公的空間として維持しつつも,そうした抑圧や規制を逆に遊戯として楽しもうとする技法であった.
- 著者
- 林 凌
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.107-124, 2018
<p>1960年代日本においては, チェーンストアの急拡大という小売業界の構造変化が生じた. この時期ダイエーや西友などの小売企業は, 全国各地に相次いで店舗を立地した. その結果「安売り」を基盤とした大量販売体制が日本においても生起したのである.</p><p>流通史研究はこうした小売業界の構造変化において, 商業コンサルタントとでも呼びうる職能集団が重大な役割を有していたことを指摘している. だがなぜ彼らは, それまで否定されていた様々な経営施策を肯定的な形で取り上げたのか. この点について, 既往研究は充分な説明を加えているとは言い難い.</p><p>本稿では消費社会研究の知見を分析の手がかりとして, 当時「商業近代化運動」に取り組んでいた商業コンサルタントの「安売り」をめぐる言説に着目し, 以下のことを解明する. 第1に, 商業コンサルタントが「商業近代化運動」において「安売り」を肯定的に取り上げた際に, 「安売り」と「乱売」が「大量生産―大量消費」の枠組みから弁別されていたということを説明する. 第2に, こうした「安売り」という施策の重要性を訴える主張が, 当時の経営学の導入と密接に結びついていたということを説明する. そして第3に, こうした「安売り」をめぐる彼らの実践が「消費社会」の到来という予期を原動力にしており, そのため「消費者」への貢献という規範が, 「安売り」という具体的施策と結びつく形で当時強く示されていたことを明らかにする.</p>
- 著者
- 高山 龍太郎
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.626-628, 2013-03-31 (Released:2014-03-31)
- 著者
- 高艸 賢
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.4, pp.468-484, 2019
アルフレート・シュッツの生世界論は,社会学の研究対象領域の1 つを提示しているだけでなく,社会科学の意味を反省するための手がかりを与えている.本稿の問いは,シュッツにおいて生世界概念は何を契機として導入され,その結果彼の論理はどのように変わったのか,という点にある.その際,シュッツの社会科学の基礎づけのプロジェクトに含まれる2 つの問題平面を区別し,社会科学者もまた生を営む人間(科学する生)だという点に注目する.<br>1920 年代から30 年代初頭にかけての著作において,シュッツは生の哲学の着想に依拠しつつ,生成としての生を一方の極とし論理と概念を用いる科学を他方の極とする「両極対立」のモデルを採用していた.しかし体験の流れとの差分において科学を規定するという方法には,科学する生を積極的には特徴づけられないという困難があった.こうした状況でシュッツは生という概念の規定を見直し,生世界概念を導入したと解釈される.<br>生世界概念の導入によって,日常を生きる人間も科学に従事する人間も,世界に内属する生として捉え直された.私を超越し一切の活動の普遍的基盤をなす世界の中で,生は間主観性・歴史性・パースペクティヴ性を伴う.この観点からシュッツは科学する生を,科学の間主観的構造,科学的状況と科学の媒体としてのシンボルの歴史的成立,レリヴァンス構造による科学的探究のパースペクティヴ性という3 点によって特徴づけた.
4 0 0 0 OA 犯罪者を家族にもつ人びとはいかにしてスティグマを内在化するのか
- 著者
- 髙橋 康史
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.21-38, 2016 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 27
本稿の目的は, 犯罪者を家族にもつ人びとが, スティグマをいかにして内在化していくのかを, 生起される恥の感情に注目しながら明らかにすることである. そこで, 犯罪者を家族にもつ人びとを対象にインタビュー調査を行い, Rachel Condryの「恥の網の目 (web of shame)」を用いて分析を試みた. Condryの研究は, 重大な罪を犯した人の家族らに限定し, その恥の感情を類型化することにとどまっている. これに対して本稿では, 軽微な犯罪も分析の対象に含め, いかにして恥を感じるのかをプロセス的に捉えることを試みた.分析の結果, 犯罪者を家族にもつ人びとが抱く恥の感情は, 他の家族成員の犯した罪の大小に接近するよりもむしろ, 事件前後においての社会における自己の位置づけの落差を認識することによって生起されていたことが明らかになった. 家族らは刑事司法システムにおける警察などとの相互行為のなかで「犯罪者の家族」としてのまなざしを認識しながら, 置かれている状況の変化を自覚していくことになっていた. 以上の分析によって, 犯罪者を家族にもつ人びとの恥の感情は, スティグマをもたない時期の社会的経験によって影響を受けるという示唆が得られた.
4 0 0 0 OA 家族と少子化
- 著者
- 稲葉 昭英
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.38-54, 2005-06-30 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 2
未婚化・晩婚化だけでなく, 夫婦出生率の低下も少子化の一因であることが近年の研究から明らかにされている.本研究は, この夫婦の出生率の低下に家族的要因がどのように関与しているのかを検討する.まず, これまで指摘されてきた社会経済要因説, 価値意識要因説, ジェンダー要因説の3つの仮説の論理的な関係を検討し, 子ども数の選好の変化が論理的に重要であることを示す.ついで, 先行研究および出生動向基本調査の結果を検討したが, ジェンダー要因説を支持する結果はほとんど得られなかった.むしろ, 夫婦の出生率の低下は, 子どもの福祉を追求するために子ども数を制限するという選好の変化から生じている可能性が示唆された.最後に行ったNFRJ98 データを用いた乳幼児をかかえた女性の家族役割負担感などについての分析からも, ジェンダー要因説は支持されなかった.育児期には性別役割分業が顕在化するが, そうした課題が夫婦ではなく親族を中心としたネットワーク内で分担されるために, ジェンダー要因説が成立しないことが示唆された. 夫婦出生率の低下は, 家族の新たな変化の帰結というよりは, 性別役割分業にもとづいて子どもの福祉追求を行うという, これまでの家族のあり方に根ざした動向と考えられる.
本稿はフーコーが『生政治の誕生』で展開した議論を参照し,ネオリベラリズムをアントレプレナー的な主体化をうながす権力として分析するとともに,この権力が作動する条件として,ネオリベラリズムが心理的な暴力を活用する側面に着目する.<br>まずネオリベラリズムを権力ととらえるフーコーの議論から,ネオリベラリズムが主体を自己実現的なアントレプレナーとみなす考え方に立脚している点を明らかにするとともに,アントレプレナー的な主体化にともなうさまざまな問題や困難を指摘する.次にアントレプレナーへのあこがれが,その実現が困難な人々――フリーターなどの不安定な立場の者――にも見られることに着目し,アントレプレナーへの志向がかならずしも実現可能性の客観的な条件に規定されるわけではなく,彼らの現実への不満に根ざしていることを指摘する.最後に,ナオミ・クラインのショック・ドクトリン議論を参照し,この不満(絶望)を生産する権力としてネオリベリズムをとらえなおす.ここからネオリベラリズムの主体が「アントレプレナー」であるとともに「被災者」であることを明らかにし,社会の「心理学化」のもう1つの側面を指摘する.
4 0 0 0 OA ポピュラーカルチャーにおけるモノ
- 著者
- 松井 広志
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.503-518, 2013-03-31 (Released:2014-03-31)
- 参考文献数
- 48
近年, デジタルメディアによるコンテンツ受容に関して, 「物質」の対概念としての「情報」そのものに近い消費のあり方が伺える. しかし, ポピュラーカルチャーの現場では, 物質的な「モノ」という形式での受容が依然として観察される. ここには「ポピュラーカルチャーにおけるモノをめぐる人々の活動」という論点が潜んでいる. 本稿の目的は, この受容の論理を多面的な視点から, しかも日常的な実感に即して読み解くことである. 本稿ではその動向の典型を, ポピュラーカルチャーのコンテンツを題材としたキャラクターグッズやフィギュア, 模型やモニュメントに見出し, これらを「モノとしてのポピュラーカルチャー」と理念的に定義したうえで, 3つの理論的枠組から捉えた.まず, 従来の主要な枠組であった消費社会論から「記号」としてのモノの消費について検討した. 次に, 空間的に存在するモノを捉える枠組として物質文化論に注目し, とくにモノ理論から「あるモノに固有の物質的な質感」を受容する側面を見出した. さらに, モノとしてのポピュラーカルチャーをめぐる時間的側面を, 集合的記憶論における「物的環境による記憶の想起」という枠組から捉えた. これらの総合的考察から浮かび上がった「モノとしてのポピュラーカルチャー」をめぐる人々の受容の論理は, 記号・物質・記憶のどれにも還元されず, 時間的・空間的に重層化した力学の総体であった.
4 0 0 0 OA 再帰性の変化と新たな展開
- 著者
- 中西 眞知子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.224-239, 2013 (Released:2014-09-30)
- 参考文献数
- 65
再帰性 (reflexivity) については社会学では多様な議論が展開されてきた. 再帰性論を社会学の主要テーマにしたのは, アンソニー・ギデンズであった. 彼は, 再帰的近代化論において, 自己再帰性や制度的再帰性など認知的再帰性を論じた. それを批判的に継承し, 独自の再帰性論を提示したのがスコット・ラッシュである. 本稿ではラッシュの再帰性論を基軸に, 再帰性の変化と新たな展開を明らかにする.ラッシュは, ウルリッヒ・ベックやギデンズの再帰性を, 認知的, 制度的な再帰性で, 単純な近代化に結びつくと批判する. 脱組織化した社会において, 非認知的で模倣的な象徴やイメージに媒介された美的再帰性や, 実践の解釈を反映した共有の意味や慣習に媒介された解釈学的再帰性を提唱する. またグローバル情報社会では, 他者との相互反映性において知を行動に結びつける現象学的再帰性の働きに注目する. ラッシュによれば, 社会の変化を反映して再帰性は, 啓蒙思想を源とする合理的な認知的再帰性や制度的再帰性から, 芸術の近代化を源として美意識や共感を重視する美的再帰性や解釈学的再帰性へ, さらにグローバル情報社会で相互反映性において知と行動を結びつける現象学的再帰性へと変化する.情報化や市場化の進展によって再帰性は変化し, 新しい再帰性も生まれつつある. そのなかで筆者は, ラッシュやジョン・アーリらの再帰性論から導かれる新しい市場再帰性に注目した.
4 0 0 0 OA 田野大輔著『愛と欲望のナチズム』
- 著者
- 沼尻 正之
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.733-734, 2013 (Released:2015-03-31)
- 著者
- 中筋 直哉
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.166-168, 2018-06-30
4 0 0 0 OA 近代山村における「空間的実践」
- 著者
- 桝潟 俊子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.535-553, 2010-03-31 (Released:2012-03-01)
- 参考文献数
- 25
福島県下郷町の大内は,江戸初期から,会津西街道の宿駅として栄えた集落である.明治期における輸送・交通革命から置き去りにされた大内は,山間僻地の一寒村として,「循環する時間」を豊かに包み込んだ「生きられた空間」を形成していた.ところが,戦後の経済復興をへて1960年代後半に入った頃から,ダム開発や改正文化財保護法にもとづく「重要伝統的建造物群保存地区」としての選定,観光・リゾート開発など,近代化の波が相次いで大内を急襲し,大内の人びとは翻弄された.本稿の課題は,大内を事例としてとくに宿場保存と観光開発に焦点をあて,大内における「空間的実践」のもとで,近代をどのような差異の次元で囲い込み,近代に抵抗する秩序やシステムがどう示されているのか,探ることにある.この課題に接近するために,近代における大内の「空間的実践」をたどる.観光地・大内の「表象の空間」は,「地域の生活システムの保全を最優先に考える営み」をとおして形成された.その結果として,大内の「表象の空間」には,「循環する時間」が流れる「生きられた空間」が重層的に紡ぎだされていた.大内における「空間的実践」のなかに,「生きられた空間」と「循環する時間」を豊かに包み込んだ「オルターナティブな社会的編成の生産過程」へ接続していく認識回路が見いだせるように思う.
4 0 0 0 OA テーマ別研究動向(障害の社会学)
- 著者
- 後藤 吉彦
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.79-89, 2010-06-30 (Released:2012-03-01)
- 参考文献数
- 50
4 0 0 0 OA 家族の民主化
- 著者
- 阪井 裕一郎
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.36-52, 2012-06-30 (Released:2013-11-22)
- 参考文献数
- 53
- 被引用文献数
- 1
本稿は, 戦後家族研究の再検討を通じて, 「家族の民主化」という理念が, 個人化や多様化によって特徴づけられる後期近代においても, なお重要な理念であることを明らかにするものである.本稿ではまず, 戦後すぐに家族研究の課題として掲げられた「家族の民主化」の理念とその限界を再考する. これまで民主化論には数多くの批判がなされ, 近年の家族社会学でこの用語が理念として取り上げられることはなくなった. しかし, 民主化論に対する批判は, その限界が, 民主化の理念そのものにではなく, 「家族の例外化」という前提にあったという重要な問題点を看過してきた. ここでは, 戦後の民主化論が「家族の例外化」に立脚してきたことを問題化したうえで, 「家族の民主化」の実現の可能性をA. ギデンズの「親密性の変容」や「民主的家族」の議論から探究する. ギデンズの議論にもまた多くの批判が寄せられているが, これらの多くはギデンズの意図を正確に把握していない可能性がある. ギデンズの議論は, 近年高まりつつある「家族の脱中心化」の議論へと接続することではじめて有効になると思われる. そして, 「家族の民主化」という理念が「家族の脱中心化」という理念と相補関係にあることを明らかにする.家族関係と民主主義の原理は相容れないとする前提こそが, これまでの家族論の背後仮説であった. しかし, 必要なのは家族と民主主義の関係を真摯に検討することであり, 「家族の民主化」という理念をとして, 家族社会学の中心的課題へと引きもどすことなのである.
- 著者
- 岩城 千早
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.306-320,395, 1987-12-31
本稿は、G・H・ミードの仕事を捉え、その意義を理解していくため、その手掛かりとして、彼の「社会的行動主義」に焦点をあて、そこに彼独自の視点を探る試みである。ミードはシンボリック・インタラクショニスト等によって最も積極的に言及され、「自己」の問題に深く取り組んだ研究者として主にクローズアップされてきた、その一方でまた、彼の「社会的行動主義」が、ワトソンの「客観的に観察可能な行動」のみを扱うという方法論に対して、「客観的に観察不可能なもの-心的なもの」を強調し、観察可能なものを通してそこに到ることを主張する方法論的アプローチとして一般に知られてきた。この重要性を指摘し、「社会的行動主義者としてのミード」を強調する向きも、昨今では自己論議の一方に見ることができる。だが、こうしたミードの主張が彼の仕事をどのように性格づけるものであるのか、という問題は未だ議論の余地を残しているように思われる。社会的行動主義によって、ミードは、観察不可能な領域を擁護したという点で、個人の内的経験に深く踏み込んでいったのでもなければ、また観察可能なものを通してのアプローチを主張したという点で、心理学の自然科学化志向に根ざすワトソンの客観的観察可能性の要求を引き継いだのでもない。「ワトソンの行動主義よりも適切な行動主義」を展開しようとするミードの論理を辿るならば、社会的行動主義は、われわれの相互行為のプロセスをテーマ化するミード固有のパースペクティブとして浮かび上がって来る。
4 0 0 0 行為の記述・動機の帰属・実践の編成
- 著者
- 前田 泰樹
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.710-726, 2005-12-31
- 被引用文献数
- 2 2
社会学にとって人々の行為を記述するとはどのようなことだろうか.この問いは2つの論点に集約されてきた.すなわち「どのような記述をしても不完全さは残るのではないか」という記述の可能性への問いA, 「社会学的記述はメンバーによってなされる記述とどのような関係にあるべきか」という記述の身分に関わる問いBである (Schegloff 1988) <BR>本稿では, まず問いAに対し, 記述の懐疑論には採用し難い前提が含まれていることを論証する.さらに, その前提のもとで見落とされてきた論点として, 実践において行為を記述することは, それ自体, メンバーシップカテコリーへと動機を帰属させる活動でありうる, ということを示す.<BR>次に問いBに対し, H.サノクスたちによる社会学的記述の方針を検討する.まず, メンバーによる記述はそれ目体手続き上の特徴を備えている, ということを確認し, その実践の手続き上の特徴によって制約を受けつつ社会学的記述を行う, という方針を検討する.さらにその検討をふまえて実践の分析を行い, 行為を記述することが動機や責任の帰属といった活動であること, また, その活動が実践の編成にとって構成的であること, を例証する<BR>要約するならば, 行為を記述することは, それ自体, 動機や責任の帰属といった活動であり, その他の様々な実践的活動に埋め込まれている.本稿では, こうした実践の編成そのものを記述していく方針の概観を示す.
4 0 0 0 OA 上林千恵子著『外国人労働者受け入れと日本社会――技能実習制度の展開とジレンマ』
- 著者
- 丹野 清人
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.555-557, 2015 (Released:2017-03-31)
4 0 0 0 家族の個人化(<特集>「個人化」と社会の変容)
- 著者
- 山田 昌弘
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.341-354, 2004-03-31
- 被引用文献数
- 1 13
近代社会においては, 家族は国家と並んでその関係が選択不可能, 解消困難という意味で, 個人化されざる領域と考えられてきた.この2つの領域に, 選択可能性の拡大という意味で個人化が浸透していることが, 現代社会の特徴である.<BR>家族の個人化が日本の家族社会学者の間で考察され始めるのは, 1980年代である.それは, 家族の多様化という形で, 家族規範の弱体化が進んだことの反映である.<BR>考察に当たって, 2つの質的に異なった家族の個人化を区別することが重要である.1つは, 家族の枠内での個人化であり, 家族の選択不可能, 解消困難性を保持したまま, 家族形態や家族行動の選択肢の可能性が高まるプロセスである.<BR>それに対して, ベックやバウマンが近年強調しているのは, 家族関係自体を選択したり, 解消したりする自由が拡大するプロセスであり, これを家族の本質的個人化と呼びたい.個人の側から見れば, 家族の範囲を決定する自由の拡大となる.<BR>家族の枠内での個人化は, 家族成員間の利害の対立が不可避的に生じさせる.その結果, 家族内部での勢力の強い成員の決定が優先される傾向が強まる.家族の本質的個人化が進行すれば, 次の帰結が導かれる. (1) 家族が不安定化し, リスクを伴ったものとなる. (2) 階層化が進展し, 社会の中で魅力や経済力によって選択の実現率に差が出る. (3) ナルシシズムが広がり, 家族が道具化する. (4) 幻想の中に家族が追いやられる.
4 0 0 0 日常経験とシステム理論 (<特集>日常経験と理論)
- 著者
- 佐藤 嘉一
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.35-44,129*, 1986-06-30
日常経験、日常知、日常生活を改めて見直す動きが、近年社会学、哲学、言語学などの諸専門的学問分野で盛んである。社会学の分野では、とくにエスノメソドロジー、象徴的相互作用論、現象学的社会学などの<新しい>社会学が日常生活を問題にしている。本稿で問題にしている事柄は、次の三点である。<BR>一、 社会学の内部で日常経験の世界に関心をむけさせる刺激因はなにか。日常経験へと志向する社会学が<新しい>と呼ばれるのはなぜか。日常経験論とシステム理論とはどのような問題として相互に関連するのか。<BR>二、 一で明らかにした<科学の抽象的現実>と<生活世界の具体的現実>との<取り違え>の問題を、シュッツ=パーソンズ論争を例にして検討する。<BR>三、 ルーマンのシステム理論においても、<科学の自己実体化>の角度から二の問題が論じられている。ルーマンの論理を検討する。
4 0 0 0 OA ルーマンの変貌
- 著者
- 馬場 靖雄
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.17-31, 1988-06-30 (Released:2009-11-11)
- 参考文献数
- 59
従来「解釈学のシステム理論版」だと考えられてきたルーマン理論は、自己言及概念の導入によって大きく変貌した。しかもそれは理論の内容においてのみではない。ルーマン理論は閉じられた自己同一的な体系から、常に自己差異化する運動体へと変化したのである。それゆえ本稿のタイトルは、第一にルーマンは変ったという、第二にしかも今なお変り続けているのだという、二重の含意をもつことになる。この二重の変貌とその帰結を粗描することが本稿の目的である。その帰結とは、社会学の営為全体に対する新しい視角に他ならない。従来「パラダイム」について論じられる時、また「グランド・セオリー」に対して「中範囲理論」の重要性が主張される (あるいは、その逆) 時、一般理論/実証研究というヒエラルヒーがまったく自明視されてきた。理論/実証の往復運動という主張も、このヒエラルヒーを前提としたものであった。これらに代って、理論と実証が相互に反転し続ける循環運動が登場する。また、社会学と社会の関係も、理論とその対象という単純な関係としてではなく、相互に造り/造られるというループのなかで把握されることになる。ルーマンの「システム理論のパラダイム転換」がもたらすのは、新たな内容のパラダイムではなく、パラダイムについて語るのを可能にする思考前提の転換である。それはいわば、パラダイム転換のパラダイム転換なのだ。