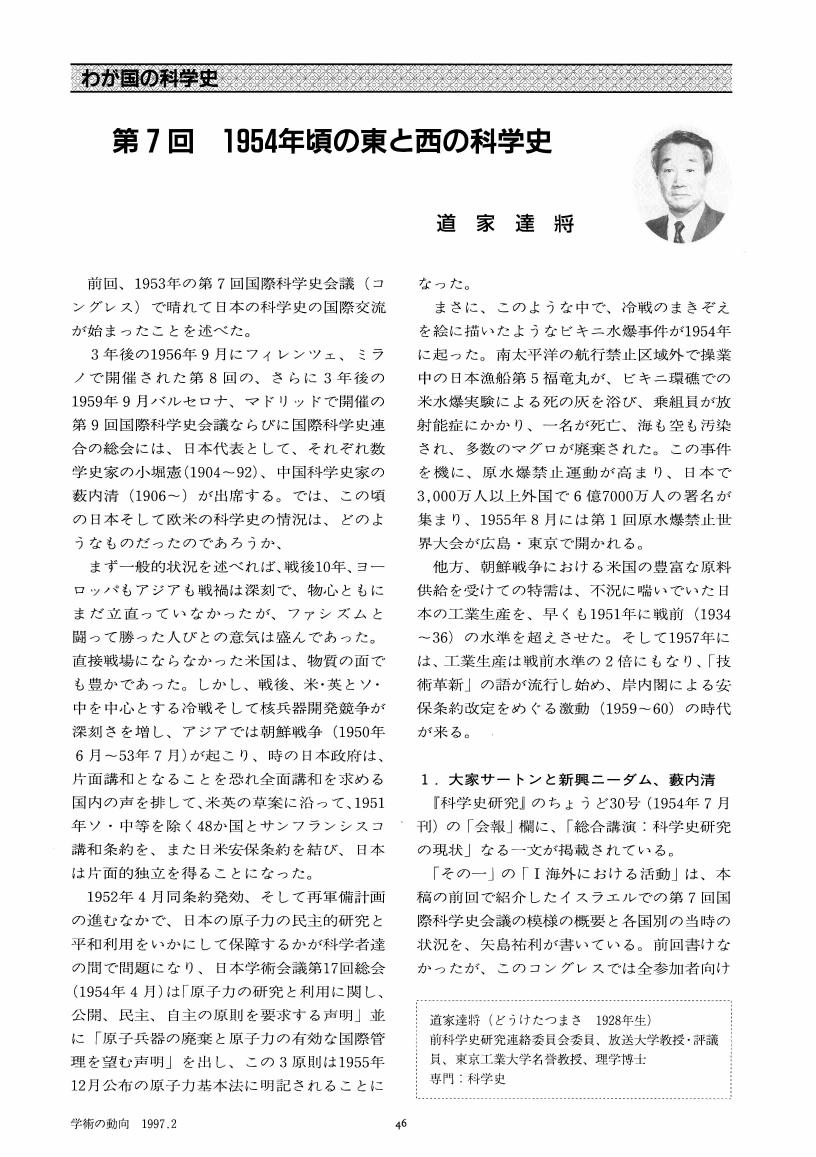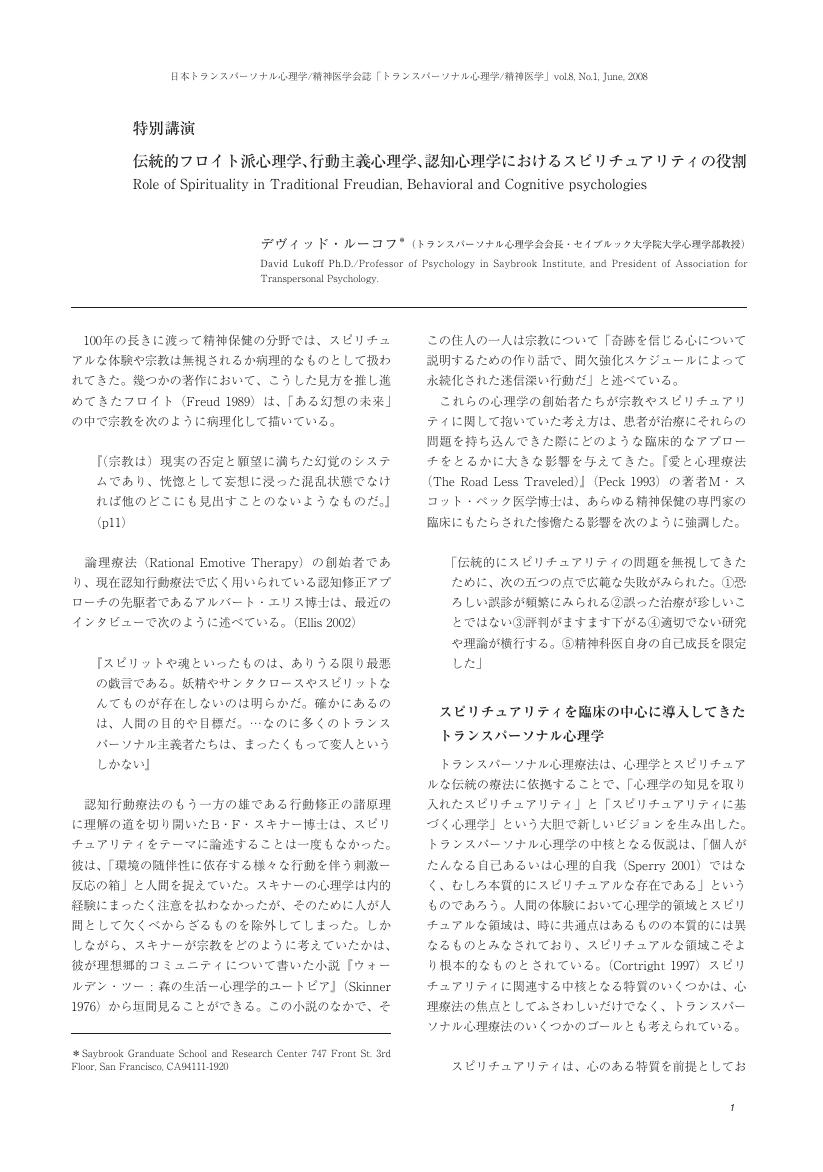1 0 0 0 IR 財政赤字と財政再建--政府予算制約の含意を中心に
- 著者
- 菅 壽一
- 出版者
- 広島大学経済学会
- 雑誌
- 広島大学経済論叢 (ISSN:03862704)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.27-55, 2003-07
1 0 0 0 IR 金融政策運営と信用割当
- 著者
- 藤井 宏史
- 出版者
- 香川大学経済研究所
- 雑誌
- 香川大学経済論叢 (ISSN:03893030)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.4, pp.115-139, 2003-03
1 0 0 0 商業信用の成立条件と信用創造
- 著者
- 中村 泰治
- 出版者
- 浦和大学・浦和大学短期大学部
- 雑誌
- 浦和論叢 (ISSN:0915132X)
- 巻号頁・発行日
- no.40, pp.71-81, 2009-02
1 0 0 0 豊臣政権下の筑前 (特集 福岡藩の研究(4))
- 著者
- 本多 博之
- 出版者
- 文献出版
- 雑誌
- 西南地域史研究 (ISSN:03860965)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.17-69, 1996-02
1 0 0 0 IR 銀行の基本業務と信用創造
- 著者
- 中村 泰治 ナカムラ ヤスハル Yasuharu Nakamura
- 雑誌
- 浦和論叢
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.1-17, 2010-01
信用創造を行うのは商業銀行の大きな特徴であるが、銀行信用の基礎をなす商業信用ですでに信用創造的事態を見て取ることができる。そこで商業信用から銀行信用までを信用創造の発展論として説き、銀行の本質を信用創造機関として説く試みも行われている。しかし、個人の商業銀行の行う信用創造には狭い限界があり、信用創造は大きなものにはならない。したがって、個人の銀行の基本業務は、一方で資金を集め他方で資金を貸し出す金融仲介であり、個人銀行にとって信用創造は基本業務を増幅する二次的業務にとどまるのである。
1 0 0 0 OA 1.心臓リバースリモデリングの臨床的意義とは
- 著者
- 坂田 泰史
- 出版者
- 日本循環制御医学会
- 雑誌
- 循環制御 (ISSN:03891844)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.2-3, 2018 (Released:2018-05-01)
- 参考文献数
- 8
- 著者
- 山本 圭吾 及川 寛
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.4, pp.589-598, 2017 (Released:2017-08-07)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 7
2013-2015年に麻痺性貝毒原因種の出現とアカガイ,トリガイの毒量,毒成分変化を調査した。確認有毒種はAlexandrium tamarenseとA. catenellaで,主毒化原因種は前者であった。アカガイは毒化,減毒が遅く通年毒が検出されたのに対し,トリガイは,原因種終息後は毒が検出されなくなった。毒成分は前者が強毒のGTX2, 3主体で,後半STXが増加した一方,後者はC1, C2主体であった。両種とも原因種増殖期にGTX1, 4が増加したが,トリガイでは毒が速やかに排出されたと推察された。
1 0 0 0 OA 温室植物の話
- 著者
- 羽鳥蓁 著
- 出版者
- 大阪毎日新聞社[ほか]
- 巻号頁・発行日
- 1926
1 0 0 0 OA 南支那及南洋調査
- 著者
- 台湾総督官房調査課 編
- 出版者
- 台湾総督官房調査課
- 巻号頁・発行日
- vol.第106輯, 1926
1 0 0 0 OA 第7回 1954年頃の東と西の科学史
- 著者
- 道家 達将
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.46-51, 1997-02-01 (Released:2009-12-21)
1 0 0 0 OA 伝統的フロイト派心理学、行動主義心理学、認知心理学におけるスピリチュアリティの役割
- 著者
- Lukoff David 村川 治彦
- 出版者
- 日本トランスパーソナル心理学/精神医学会
- 雑誌
- トランスパーソナル心理学/精神医学 (ISSN:13454501)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.1-7, 2008 (Released:2019-09-16)
- 著者
- Kaliyamoorthy Selvam Mari Annadhasan Rengasamy Velmurugan Meenakshisundaram Swaminathan
- 出版者
- The Chemical Society of Japan
- 雑誌
- Bulletin of the Chemical Society of Japan (ISSN:00092673)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.7, pp.831-837, 2010-07-15 (Released:2010-07-15)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 16
Silver-loaded TiO2 (Ag–TiO2) and acidic clay (K10 montmorillonite) composite photocatalyst has been successfully applied for the light-induced conversion of o-phenylenediamine (OPD) and its derivatives to substituted benzimidazoles with various alcohols in acetonitrile using UV-A and solar light. The influence of the various photocatalysts, solvents, and substituents on the yield and selectivity of the products has been investigated. The mechanism of photocatalysis is proposed. Loading silver on TiO2 enhances product yield and selectivity both in UV and solar light. In the presence of primary alcohols, 2-aminothiophenol forms only disulfide and hence Ag–TiO2/clay can be used as a green catalyst for the synthesis of disulfides.
- 著者
- 角藤 智津子
- 出版者
- 全国大学音楽教育学会
- 雑誌
- 全国大学音楽教育学会研究紀要
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.1-10, 2014
1 0 0 0 IR 名古屋における雅楽伝承の一断面 : 幕末から明治へ
- 著者
- 寺内 直子
- 出版者
- 神戸大学大学院国際文化学研究科日本学コース
- 雑誌
- 日本文化論年報 (ISSN:13476475)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.17-53, 2015-03
1 0 0 0 OA シュメール語のVentive ((来辞法)) とIentive ((去辞法)) について
- 著者
- 吉川 守
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, no.73, pp.21-42, 1978-03-31 (Released:2010-11-26)
- 参考文献数
- 26
移動表現において言語主体と移動主体との間に生じる物理的・心理的方向性は, きわめて一般的な言語的視座と考えられるが, 明確な文法現象として範疇化している言語は比較的少数であると思われる。本稿では, アッカド語に認められるVentiveとバビロニアの文法テクストに見られる文法術語Riatum/Sushurtumを手掛として, 従来未解明のまま残されているシュメール語の動詞接頭辞の一部が, Ventive《来辞法》及びIentive((去辞法))を表示する機能を有することを指摘して見たいと思う。
1 0 0 0 OA 教育を通じて企業活動を可視化させる場の提供
- 著者
- 薗部 靖史
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.139-156, 2017-06-30 (Released:2020-03-10)
- 参考文献数
- 31
1 0 0 0 OA 定量化のための数値処理
- 著者
- 犬飼 幸男
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.289-294, 1984-03-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 28
1 0 0 0 あいつぐ経済改革--ユーゴ通信
- 著者
- 丸山 浩行
- 出版者
- 日本社会党中央本部機関紙局
- 雑誌
- 月刊社会党 (ISSN:04351754)
- 巻号頁・発行日
- no.104, pp.105-107, 1966-01
1 0 0 0 生物言語学の展開 : 生成文法から見た言語発生の諸問題
- 著者
- 藤田 耕司
- 出版者
- 生命の起源および進化学会運営局
- 雑誌
- Viva origino (ISSN:09104003)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.104-121, 2003-06-30
- 参考文献数
- 9
Generative grammar constitutes one major branch of theoretical linguistics, but its more important role as biolinguistics can be found in the interdisciplinary field of human biology. By exploring one particular instance of the cognitive faculties of our species, i.e, the Language Faculty (or the Language Organ), researchers in generative grammar/biolinguistics aim to elucidate the fundamental properties of human intelligence, or human nature itself. In this paper, we overview the main topics of generative grammar/biolinguistics to see how deeply they are intertwined with those of modern biology. In particular, we take a new and enlightening look at the familiar issues of the nature, acquisition and evolution of the human language, its universality and diversity, and its economy and redundancy. These are here rephrased in terms of three different levels of genesis of language, i.e., microgenesis, ontogenesis, and phylogenesis, in the hope that their possible unification may be forthcoming.