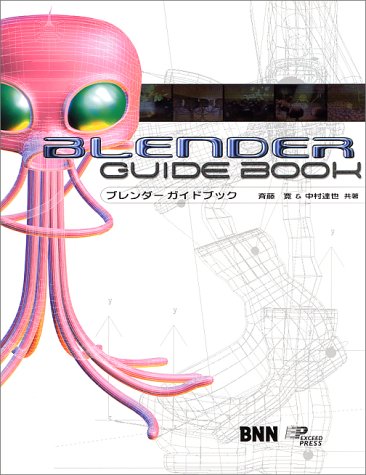2 0 0 0 OA アメリカ 米太平洋軍及び在韓米軍に関する上院公聴会
- 著者
- 新田紀子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 255-2), 2013-05
2 0 0 0 日本語および英語における対称詞の機能ポライトネスとの関連性
- 著者
- 油井恵
- 出版者
- 駿河台大学
- 雑誌
- 駿河台大学論叢 (ISSN:09149104)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.19-30, 2007
- 著者
- 柴田 公博 岩瀬 孝邦 坂元 宏規 瀬渡 直樹 松縄 朗 Hobenard Hohenberger Mueller Matthias Dausinger Friedrich
- 出版者
- 社団法人溶接学会
- 雑誌
- 溶接学会論文集 : quarterly journal of the Japan Welding Society (ISSN:02884771)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.204-212, 2003-05-05
- 被引用文献数
- 4
Welding of Al-Mg and Al-Mg-Si alloys was performed using twin spot beams formed with two Nd: YAG lasers for the purpose of reducing porosities and humping caused due to unstable phenomena of weld bead during welding of aluminum alloys. The relationship between the configuration of the twin spot beam and the quality of the weld beads was investigated using X-ray and high-speed camera observations of the keyhole shapes and weld beads. X-ray observation of the weld beads showed that beam distance had a strong influence on the amount of porosities. At a shorter beam distance, porosities were apt to occurred in the weld. The amount of porosities decreased with an increase of beam distance. Beam distance affects keyhole shapes. The amount of porosities was clearly related to the ratio of keyhole depth to keyhole opening. Larger keyhole opening and/or shallower keyhole depth, smaller amount of porosities caused by instability of the weld pool.
2 0 0 0 ツインテール・アーキテクチャの改良
- 著者
- 亘理 靖展 堀尾 一生 入江 英嗣 五島 正裕 坂井 修一
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告計算機アーキテクチャ(ARC) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.79, pp.7-12, 2007-08-01
本研究室で提案しているツインテール・アーキテクチャでは,発行幅を増やさずにスーパスカラ・プロセッサに演算器を追加することで実質的に発行幅が増えたような効果が得られる.ツインテール・アーキテクチャでは並列にメモリ・アクセス可能なロード命令が増えることで大きな性能向上が得られる.しかし,プロセッサ内のロード命令の数を増やすためにはロードストア・キューのサイズを大きくする必要があり,配線遅延の増大を招く可能性がある.本論文では,ロードストア・キューからアクセス・オーダ・バイオレーションの検出機構を分離し,アクセス・オーダ・バイオレーションの検出をするバッファを別途設けることで,ツインテール・アーキテクチャにおいて,配線遅延の増大を招くことなく,同時にメモリ・アクセスできるロード命令を増加させるモデルを提案する.シミュレーションによる提案モデルの評価では,ツインテール・アーキテクチャにおいてアクセス・オーダ・バイオレーション検出時の再実行方法を理想的にしたモデルとほぼ同等のIPCの向上が得られた.We propose Twintail Architecture, an architecture which gives effect similar to widening issue width but does not lead to greater latency. Twintail Architecture contributes to superscalar processor's throughput by enabling paralell memory access. However, it seems to provoke wiring delay with enlarging the size of load/store queue for the purpose of increasing in-flight load instructions. In this paper, we propose an reasonable model which increases the number of in-flight load instructions, by decoupling the function of access order violation detection from the load/store queue and enlarging a buffer which detects access order violation. Evaluation showed proposed model improves IPC as well as ideal re-execution model.
2 0 0 0 第19(地球回転)委員会 (第13回IAU総会からの報告)
- 著者
- 弓 滋
- 出版者
- 日本天文学会
- 雑誌
- 天文月報 (ISSN:03742466)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.15-16, 1967-12
2 0 0 0 OA スプラインベースドアプローチによる手書き文字画像からの動的書字スキル抽出法
本研究は、スプラインベースドアプローチにより、手書き文字の静的画像から文字筆順を復元し、その復元筆順情報から書字者の書字速度・加速度パターンなどのいわゆる動的書字スキルを抽出するための手法を確立する、ことが目的であった。特に、(A) 手書き文字の静的画像からの筆順復元法の枠組みの開発、(B) 骨格スプラインモデルの理論とアルゴリズムの開発、(C) 動的書字スキル抽出法の開発、といった3つの課題に取り組んだ。特に、課題(B)では、ペンタブレットなどのデジタル機器上での筆記時にしばしば起こる「筆滑り」までを考慮した全く新しい骨格モデリングの手法を開発した。
2 0 0 0 OA リンゴ主要数品種の自家不和合遺伝子型の解析
- 著者
- 小森 貞男 副島 淳一 伊藤 祐司 別所 英男 阿部 和幸 古藤田 信博
- 出版者
- 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.6, pp.917-926, 1998-11-15
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 4 2
'金星'と'レッドゴールド'および'千秋'と'いわかみ'の不和合性を手がかりとして,'デリシャス','ふじ','ゴールデン・デリシャス','はつあき','紅玉','国光','千秋','東光'とそれらの交雑実生を用いて主要栽培品種のS遺伝子型解析を試みた.その結果6つのS複対立遺伝子と7つのS遺伝子型の存在が示唆され,9品種のS遺伝子型を以下のように決定した.(S_Ja, S_Jb)='ゴールデン・デリシャス'(S_Ja, S_Jd)='東光'(S_Jc, S_Jd)='紅玉','ひめかみ'(S_Jc, S_Je)='デリシャス'(S_Jc, S_Jf)='ふじ'(S_Jd, S_Jf)='千秋','いわかみ'(S_Je, S_Jf)='国光'また'東光'のS_Jd因子は'印度'に由来していることが明らかになった.さらに'金星'と'レッドゴールド'のS遺伝子型は(S_Ja, S_Je)または(S_Jb, S_Je)のいずれかであり,'はつあき'のS遺伝子型は(S_Ja, S_Jc)または(S_Jb, S_Jc)と考えられる.
2 0 0 0 佐賀藩銃砲沿革史 : 全
- 著者
- 野地 秩嘉
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネスassocie (ISSN:13472844)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.22, pp.82-85, 2011-12-20
チェーン間の激烈な競争が続く牛丼業界で、トップを走る「すき家」。そこで腕利きと呼ばれる店長は、入社3年目で4つの店舗を管轄する。1店舗の運営とどこが違うのか。
- 著者
- 林田 宣宏 矢向 高弘 村上 俊之 大西 公平
- 出版者
- 公益社団法人精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.11, pp.1834-1838, 2001-11-05
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 12 13
A bilateral robot is one of the remote control robots. By implementing the force feed back, it is possible for the operator to have the sense of the touch. But the force sensor is affected by unknown disturbance such as its temperature variation and so on. For that reason, it is not expected to use the force sensor at the extreme situation. In the sensorless approach, the reaction torque observer is used. But the reaction observer is easy to be influenced of the friction. This makes it difficult to estimate the external force. To address the above issue, this article proposes a twin drive system. This system is composed of two motors and one differential mechanism. It is required to control two motors for two degrees of freedom. To consider the above issue, two virtual motors are proposed. One is deal with the output control and the other is for friction compensation. The twin drive system brings a sophisticated ability to the system, which is a reduction ability of the friction. By using this system, it is possible to realize the remote control robot, where the operator can feel the obstacle which the slave robot touches. This system may help the remote control work more skillfully. The validity of the proposed method is confirmed by the experimental results.
2 0 0 0 OA 国会事故調東京電力福島原子力発電所事故調査委員会調査報告書
- 著者
- 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会
- 出版者
- 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会
- 巻号頁・発行日
- vol.会議録, 2012-06-28
- 著者
- 岡田 玲子 太田 優子 Okada Reiko Ota Yuko
- 出版者
- 県立新潟女子短期大学
- 雑誌
- 県立新潟女子短期大学研究紀要 (ISSN:02883686)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.111-123, 1990-03
幼児栄養をより的確に把握するために,昭和47年,52年,57年および62年度の都市近郊幼児の,食物・栄養素等摂取状況について検討を加えた。対象児は4~6歳児10~25名で四季の各連続3日間(通年12日間)の食物摂取量を個人別に秤量調査し,食品構成目安量ならびに個人別に算定した栄養所要量と対比して,5~15年間の推移の状況を調べ,以下の結果を得た。(1)摂取食品数は,57年度に30種類に至ったが,他は26~29種類であり,動物性食品数は6~7種類で15年間さしたる変動はなかった。(2)食品摂取状況は,15年の間さしたる変動のみられなかったのは豆類のみで,米・穀類,砂糖・菓子・果実・卵類が有意に減少,緑黄色野菜のみが有意に増加して目安量を超えた。62年度に至って卵・乳類が目安量以下に減じ,その摂取割合は75,82%となった。また,穀類のそれは82.2→59.2%に減じた。(3)栄養素等摂取状況は,15年間に適量摂取域内ではあるものの,エネルギー(摂取割合117-102%)と鉄(同108-94%)が有意に減少,ビタミンAのみが有意に増加した。また,ビタミンDの摂取割合は59-17%へ有意に減少した。(4)摂取エネルギー比については,穀類(40→35%)・糖質(59→53→51→54%)エネルギー比は漸減,脂肪エネルギー比(28→32→34→31%)漸増後減少,タンパク質エネルギー比は漸増して横ばいで推移した。(5)動物性タンパク質比は漸増後減少して54.1%になり,摂取エネルギー1,000kcal当りコレステロール・食塩摂取量はやや漸増,P/Sは漸減,Keyの食事因子φ量,Na/K,およびP/Caは漸増傾向をそれぞれ示した。(6)対象児の体位は体位推計基準値に比し,身長(99~110%),体重(94~101%)共に適正範囲にあり,体力評価は中位の成績であった。(7)対象児の平均1日当り歩行歩数は11,011±2,061歩であった。
- 著者
- 高橋 敏行 冨永 悌二 横堀 寿光 吉本 高志
- 出版者
- 日本脊髄外科学会
- 雑誌
- 脊髄外科 (ISSN:09146024)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.1-6, 2001
- 被引用文献数
- 1 2
Cervical interbody fusion cages (CIFC) are currently used for anterior cervical fusion. There are few reports documenting their biomechanical property in the cervical spine. The purpose of the present study is to investigate biomechanical stability of the caprine cervical spine implanted with a CIFC device. Thirty-two spinal units (C3-4 and C5-6) were harvested from 16 fresh-frozen caprine cervical spines. Each spinal unit underwent discectomy and transection of the posterior longitudinal ligament, and then was implanted with single CIFCs, double CIFCs, autograft, or autograft and anterior cervical plate. An iliac crest tricortical bone was used as an autograft. The degrees of displacement of the cervical spine specimens by multidirectional moments in flexion, extension, lateral bending and axial rotation were evaluated using a video-recording. The stiffness against the multidirectional loads was calculated from load-displacement curves. There were no statistical differences in stiffness between the single-cage and autograft groups in flexion, extension and axial rotation. The autograft group showed significantly increased stiffness compared with that of the single-cage group in lateral bending. The stiffness values were far larger in both the double-cage and autogtraft with plating groups than in the other groups in all directions. There were no statistical differences in stiffness between the double-cage and autogtraft with plating groups in flexion, lateral bending and axial rotation. The double-cage group showed significantly decreased stiffness compared with that of the autograft with plating group only in extension. The stiffness values of the single- or double-cage groups would represent the characteristic biomechanical properties derived from the structure and shape of the implants.
2 0 0 0 OA インド洋大津波による図書館,文書館被害と今後の課題
- 著者
- 坂本勇
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- カレントアウェアネス (ISSN:13487450)
- 巻号頁・発行日
- no.286, 2005-12-20
2 0 0 0 OA 学齢期心身障害児をもつ父母のストレス : ストレスの構造
- 著者
- 新美 明夫 植村 勝彦
- 出版者
- 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.1-12, 1984-09-30
先に構成した学齢期心身障害児をもつ父母のストレス尺度(植村・新美、1983)について、その因子構造と、障害児の加齢に伴う変化を明らかにすることを目的として、調査・分析を行った。父母各31下位尺度について、主因子解/バリマックス回転の結果、母親は、問題行動と日常生活、将来不安、人間関係、学校教育、夫婦関係、社会資源、療育方針の7因子、父親は、人間関係全般、現状と将来、社会資源と地域社会、学校教育、問題行動、健康状態の6因子を抽出した。次に、障害児の加齢に伴う因子構造の変化を探るべく、障害児の学年によってサンプルを父母各3群に分け、おのおのの因子構造を比較した。その結果、母親は7因子中5因子、父親は6因子中4因子が、3群すべてに共通する因子と判断された。他の因子については、障害児の加齢に伴って因子構造に変化がみられ、その多くが小学校低学年と高学年の間に起こることが指摘された。
2 0 0 0 Blenderガイドブック
- 著者
- 斉藤寛 中村達也共著
- 出版者
- ビー・エヌ・エヌ (発売)
- 巻号頁・発行日
- 1999
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1925年05月06日, 1925-05-06
- 著者
- 林 史典
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 國語學 (ISSN:04913337)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.109-115, 2000-06-30