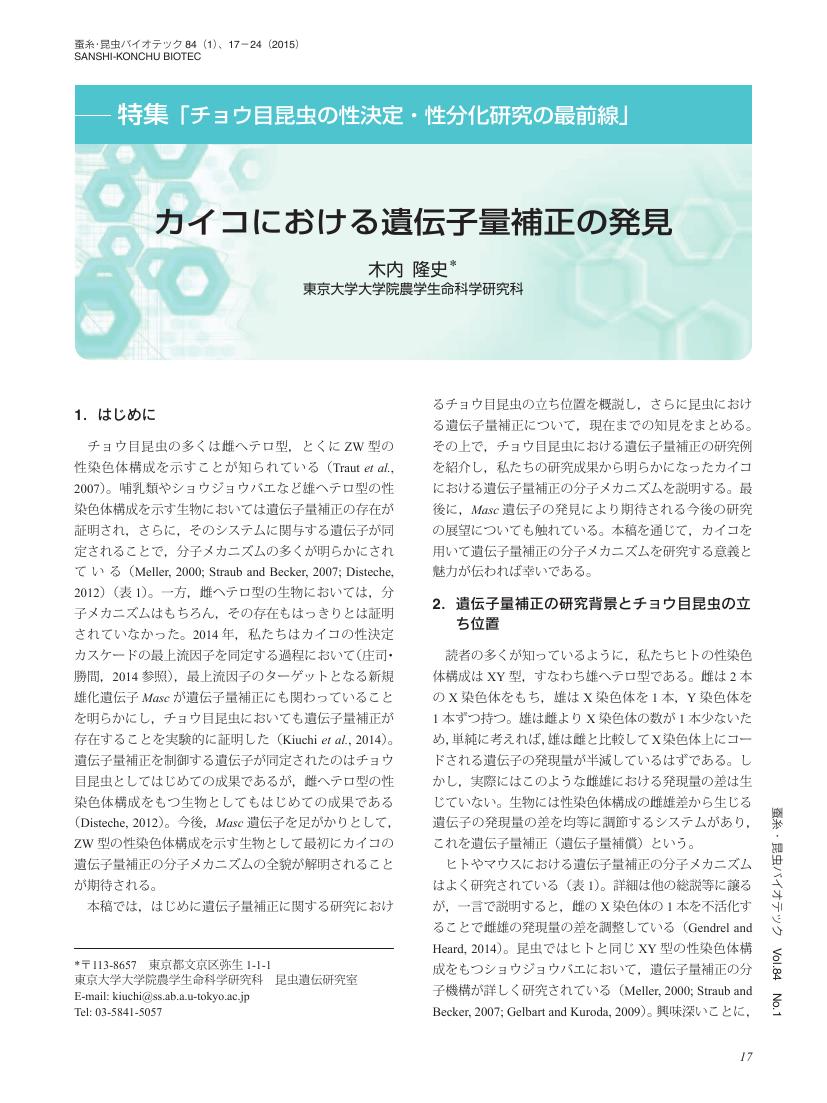9 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1943年09月02日, 1943-09-02
9 0 0 0 落語:塩原多助
- 著者
- 六代目 朝寝坊むらく
- 出版者
- ニッポノホン
9 0 0 0 OA 元治期の幕府財政
- 著者
- 飯島 千秋
- 出版者
- 横浜商科大学
- 雑誌
- 横浜商大論集 (ISSN:02876825)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.49-105, 1988-12-10
- 著者
- 杉本 Bauwens Jessica
- 出版者
- 京都精華大学表現研究機構
- 雑誌
- ポピュラーカルチャー研究 (ISSN:18828426)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.4, pp.28-57, 2008
- 著者
- 小林 健彦 KOBAYASHI Takehiko
- 出版者
- 新潟産業大学附属東アジア経済文化研究所
- 雑誌
- 新潟産業大学経済学部紀要 = Bulletin of Niigata Sangyo University Faculty of Economics (ISSN:13411551)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.41-78, 2015-06
日本列島の中では、文献史資料に依って確認を取ることが可能な古代以降の時期に限定してみても、幾多の自然災害―気象災害、津波や地震災害、火山噴火、伝染病の蔓延等―に見舞われ、その度に住民等を苦しめて来た。現在の新潟県域に該当する地域に於いても、当該地域特有の気象条件より齎される雪害を始めとして、大風、大雨、洪水、旱魃、地震、津波、火山噴火、そして疫病の流行といった諸々の災害が発生当時の民衆に襲い懸かっていた。しかし、民衆はそれらの災害を乗り越えながら現在に続く地域社会を形成し、維持、発展させて来たのである。日本人に依る地域社会の形成は、災害に依る被害とその克服の歴史であると言っても差し支えは無いであろう。筆者は従前より、当時の人々がこうした災害を如何にして乗り越え、対処をして来たのかという、「災害対処の文化史」を構築するのに際し、近年自然災害が頻発している現在の新潟県域を具体的な研究対象地域の一つとして取り上げながら、その検証作業を行なっている処である。本稿では、平安時代より鎌倉時代にかけての時期に発生し、当該地域に甚大な被害を齎したとされる、「謎の巨大地震」に関し、新潟県出雲崎町と同長岡市所在の「宇奈具志神社」に就いて、その事例検証作業と共に、当時の人々に依る対処法とに就いて、検討を加えたものである。
9 0 0 0 OA カイコにおける遺伝子量補正の発見
- 著者
- 木内 隆史
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.1, pp.1_17-1_24, 2015 (Released:2015-07-08)
- 参考文献数
- 51
- 著者
- 中村 友紀
- 出版者
- 日本比較文化学会
- 雑誌
- 比較文化研究 = Studies in comparative culture (ISSN:09140247)
- 巻号頁・発行日
- no.116, pp.11-21, 2015-04-30
9 0 0 0 医療観察法の問題点 : 判断が揺れた人格障害の事例を通じて
- 著者
- 中島 直
- 出版者
- 日本精神神経学会
- 雑誌
- 精神神經學雜誌 = Psychiatria et neurologia Japonica (ISSN:00332658)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.1, pp.32-37, 2008-01-25
- 被引用文献数
- 2
9 0 0 0 OA ルーン文字の起源をめぐって(その2)
- 著者
- 河崎 靖
- 出版者
- 京都大学人間・環境学研究科ドイツ語部会
- 雑誌
- ドイツ文學研究 (ISSN:04195817)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.19-54, 2015-03-25
- 著者
- 杉本 妙子 卜部 玲子 Chen Lan
- 出版者
- 茨城大学人文学部
- 雑誌
- コミュニケ-ション学科論集 (ISSN:1343117X)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.43-63, 2005-09
9 0 0 0 OA 学会誌における若手研究者の実態
- 著者
- 齋藤 圭介
- 出版者
- 関東社会学会
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, no.26, pp.87-98, 2013-09-10 (Released:2015-06-12)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
This paper presents an analysis of a researcher's academic position when getting published in The Annual Review of Sociology and the Japanese Sociological Review during each academic year from 2001 through 2010. The study examines the general situation of young researchers hoping to get published in these academic journals and tries to identify how often their theses are ultimately published. In particular, it focuses on the peer review system in order to understand the strategic thinking that young researchers employ when submitting their theses. By comparing the two journals, this study identifies the problems faced by young researchers and suggests strategies for solving these problems.
9 0 0 0 OA 追悼の建築としての伝記集 : ヴァザーリ『芸術家列伝』再考
- 著者
- 古川 萌
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美學 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.49-60, 2014-06-30
The lives of the artists, or Vite, written by an Italian painter and architect Giorgio Vasari (1511-1574), has been considered as one of the most important works in art historiography. However, since Vasari has shown the development of artistic styles and the triumph of maniera moderna in this work, a simple fact seems to have been overlooked for quite a long time, that this book is substantially a collection of artists' biographies, rather than an extensive treatise on the history of art. This essay returns to the fact, and attempts to reconsider the structure and purpose of this book. Epitaphs and woodcut portraits of artists contained in Vite are examined to demonstrate how Vasari views these biographies as funerary monuments to assure their eternal fame, making the whole book a temple to house them. Through the analysis, Vite will also reveal itself as a tool to promote Cosimo I de' Medici's artistic patronage. This is achieved by echoing the act of mourning their artists, which was practiced by such people as Cosimo il Vecchio de' Medici and Lorenzo de' Medici, consequently emphasizing the continuity from the Florentine Republic era.
9 0 0 0 OA 柑橘果汁の炊飯への利用
- 著者
- 江間 章子 貝沼 やす子
- 出版者
- 一般社団法人日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.198-205, 1990-05-20
- 被引用文献数
- 9
夏みかん及び甘夏みかんの果汁を加水量の20〜60%加え、直接炊き込む方法により炊飯を行った。結果を以下に要約する。1)加熱による色、風味への悪影響はなく、炊き上がった飯はうすいみかん色と適度な酸味を呈し、加える果汁割合を考慮すれば官能的に良好な飯となった。夏みかんでは加水量の40%、甘夏みかんでは60%の添加割合が好ましいものであった。2)果汁を加えた飯は、粘りが強くやわらかい飯となった。また、つやの測定値が高く、顕微鏡観察では飯粒周辺部に濃厚に見える付着物がみられ、つやや粘りとの関係が示唆された。3)飯粒中の酸の浸透状態は果汁割合の多い飯ほど、飯粒表面付近の酸量が多く、この酸の働きにより表面組織の状態にも違いが生じ、テクスチャーなどの差として測定されたと思われる。以上、果汁添加による飯の性状の変化が観察され、食味上、好ましい果汁の添加割合が明らかになった。また、本法による炊飯は簡便であり、果汁を多く使用できるため、炊き上がった飯のみかん色を生かした調理が期待できる。付着性の増加などの特徴を粘りの少ない品種の米や古米に生かすことができればこれらの米の利用価値を高めることも可能であると考えられるため、今後さらに検討を進める予定である。
9 0 0 0 相互結合網構成の並列情報サーバ上のファイル管理
- 著者
- 味松 康行 横田 治夫
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告データベースシステム(DBS) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.1996, no.11, pp.17-24, 1996-01-24
我々は高信頼並列ディスクシステムを構成するためにDR?netを提案してきた。DR?netを用いて並列情報サーバを実現しようとしたとき、DR?net上にファイルシステムを構築する必要がある。DR?netには複数の外部インタフェースがあるため、複数のアクセス要求が並列に出されてもファイルシステムの整合性が失われないようにすることが重要である。また、多数のディスクを均等に使用するために、各ディスクの使用量を均等化する何らかの機構が備わっていることが望ましい。本稿では、ファイルシステムを構成する2つの制御方式について評価を行なう。実験機を用いた評価実験により、それぞれの方式におけるファイルアクセス要求のレスポンスタイムおよびディスク使用量のばらつきを計測する。実験結果は、並列制御方式が集中制御方式よりも短いレスポンスタイムを示すこと、またファイルサイズが大きい場合には、各ディスクの使用量が均等化されることなどを示している。We have proposed DR-nets, Data-Reconstruction networks, to construct highly reliable parallel disk systems. When we use DR-nets for a parallel information server, we must provide a file system on DR-nets. DR-nets have a number of interface nodes, so the file system of DR-nets must care to keep consistency of information of files and disks, even if a number of requests come in parallel. Furthermore, the file system should take care to keep the balance of the number of used blocks within all disks. We evaluate two file system configurations using a DR-net prototype. The results indicate that the distributed configuration has quicker response time than centralized one, and it keeps balanced number of used blocks within all disks when file size becomes large.
9 0 0 0 OA 有害化学物質生物蓄積モデルによるシロギス体内の放射性セシウムの推定
- 著者
- 江里口 知己 堀口 文男 亭島 博彦 中田 喜三郎 高倍 昭洋 田口 浩一
- 出版者
- 海洋理工学会
- 雑誌
- 海洋理工学会誌 (ISSN:13412752)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.35-41, 2014 (Released:2014-06-26)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
We have developed a bioaccumulation model to estimate the concentration of hazardous chemicals accumulated in marine organisms. In this study, we applied this bioaccumulation model to estimate the concentration of radioactive materials in coastal fish. Target substances were radiocesium (134Cs, 137Cs) and the target fish were Japanese whiting (Sillago japonica) in Tokyo Bay. The radiocesium concentrations in sediments and fish were examined by field sampling on July 3 and August 9, 2012 in Tokyo Bay. The time course of radiocesium concentrations in Japanese whiting after the Fukushima Daiichi nuclear disaster was simulated using the model. Our model showed that good results were obtained by using the assimilation efficiency parameter of 10–20%, and radiocesium concentrations in Japanese whiting were about same as the levels recorded in the field sampling (517 days after the disaster). In the Edogawa River and the Arakawa River estuary, where high radiocesium concentrations were observed in sediments, Japanese whiting showed accumulations of 134Cs and 137Cs estimated at 5.0 Bq/kg-wet and 6.5 Bq/kg-wet, respectively.
9 0 0 0 OA 惑星エアロゾル実験の教育的利用:火星の夕焼けは本当に青いのか?
- 著者
- 中串 孝志 古川 邦之 山本 博基 大西 将徳 飯澤 功 酒井 敏
- 出版者
- 日本エアロゾル学会
- 雑誌
- エアロゾル研究 (ISSN:09122834)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.107-112, 2007-06-20 (Released:2007-06-20)
- 参考文献数
- 3
Planetary aerosol laboratory experiments for science education were carried out in a curriculum of Kyoto University. Our goal is to reproduce “the blue sunset” on Mars which are reported from NASA's Mars Pathfinder. In reproducing the rays scattered by Martian atmosphere (dust storm) in a laboratory, the number density of scattering particles has to be as large as possible. Three experiments were conducted in the air and water. Although we were not able to reproduce Martian blue sunset, we elucidated its spectrum. Converting this spectrum to a color in the RGB system, we obtained R = 114, G = 122, B = 192. Though the experiment, we proved that planetary aerosol laboratory experiments are significantly fruitful for science education as well as for science studies. We propose that researchers and lecturers should make active use of planetary aerosol laboratory experiments for science education.