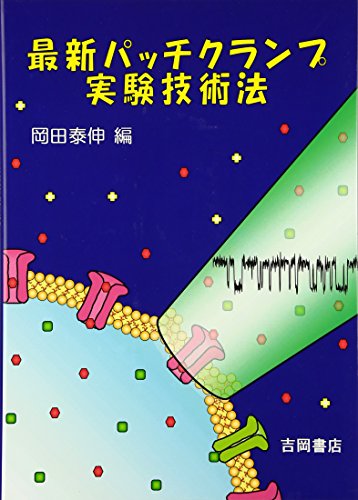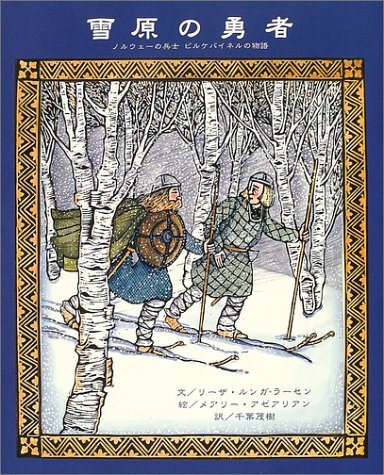1 0 0 0 最新パッチクランプ実験技術法
- 著者
- 山下 由紀子 福井 義一 Yukiko Yamashita Yoshikazu FUKUI
- 出版者
- 甲南大学文学部
- 雑誌
- 甲南大學紀要.文学編 = The Journal of Konan University. Faculty of Letters (ISSN:04542878)
- 巻号頁・発行日
- vol.161, pp.223-230, 2011-03-30
1 0 0 0 IR 独占禁止法違反が主張される国際的民事訴訟事件における準拠法の決定について -準備的研究-
- 著者
- 土田 和博
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 早稻田法學 (ISSN:03890546)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.3, pp.273-290, 2021-07-30
- 著者
- 永野 叙子 小澤 温
- 出版者
- 日本リハビリテーション連携科学学会
- 雑誌
- リハビリテーション連携科学 (ISSN:18807348)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.63-68, 2019-06-30 (Released:2021-02-28)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
【目的】市民後見人の育成の現状と支援課題を明らかにする. 【方法】市民後見人受任累計件数の多い Z 県下12か所の成年後見実施機関に対して, 訪問面接調査を実施した. 【結果】市民後見人の育成は, 市区町村の財政上の自由度にかかわらず実施されてきた. 育成課程は地域の後見ニーズによって多様であったが, 対人援助技術の習得に重きが置かれていた. ただし育成件数は, 二極化の傾向がみられた. 支援では, ケア会議の開催, 同行支援等が実施され, 支援と監督両方の業務を担う職員から負担感が聞かれた. 【結論】実施機関は, 市民後見人の活動報告に対する定期的なフィードバックを推進し, 市民後見人は活動報告に担当ケースの観察, 気づき, 実施内容等の記録を重ねていくことが, 終末期の医療判断や実施機関との情報共有に役立ち, 双方にとって有益である.
- 著者
- 中村 仁威
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 早稻田法學 (ISSN:03890546)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.3, pp.291-315, 2021-07-30
1 0 0 0 IR 民事訴訟のIT化・AI化と審理原則 -コロナ禍が民事訴訟にもたらしたもの-
- 著者
- 西口 元
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 早稻田法學 (ISSN:03890546)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.3, pp.1-41, 2021-07-30
1 0 0 0 OA ICUにおけるせん妄についての苦悩を表出した心臓外科患者の一症例
- 著者
- 江尻 晴美
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.543-547, 2008-10-01 (Released:2009-04-20)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1 1
せん妄は,身体的原因により短期間に発現して時間とともに変動する,注意力や意識レベルの障害と睡眠覚醒障害を伴った認知機能の変化である。今回,ICU滞在中にせん妄を発症した患者において,その後,せん妄に対する患者の思いを直接聞くことができたので報告する。症例は,60歳代前半の男性。修正大血管転位症のため左側房室弁置換術,心房細動根治術を受け,術後2日目よりせん妄を発症した。悲観的,抵抗・拒絶,見当識障害が認められたが,家族が介入すると現実認知が可能であった。術後8日目,「大変見苦しいところをお見せして申し訳ありませんでした」と涙を流した。このときの患者の言動から,見当識障害,会話の障害など,せん妄患者によく認められる現象が患者にとって苦痛で辛いものであることがわかった。看護スタッフはその気持ちを理解して援助する必要性が示唆された。
1 0 0 0 学校をカエル(第13回)#教師のバトン
1 0 0 0 OA 韓国の民主化運動とキリスト教(3): 全斗煥時代
- 著者
- 倉持 和雄
- 出版者
- 東京女子大学
- 雑誌
- 東京女子大学紀要論集 (ISSN:04934350)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.85-119, 2019-03-30
This article aims to figure out the involvement of South Korean Christians in the democratizing movement in the Chun Doo Hwan regime, and to evaluate this involvement from the viewpoints of both the democratizing movement and that of Christianity.After Park Chung Hee’s death, Chun Doo Hwan held political power by suppressing the Kwangju Uprising. His regime was more oppressive than that of Park Chung Hee’s. Some Christians continued the democratizing movement during Chun Doo Hwan’s regime. Non-Christian democratizing movements (which were influenced by Marxism) became more active than that of the Chirstians. Their movement aimed at social revolution because the activists recognized the limitations of a movement in the 1970’s that aimed for Liberal Democracy after the failure of the Kwangju Uprising. After that, their movement became radical and developed an anti-American sentiment because the U.S. had agreed with the suppression of the Kwangju Uprising. These changes impacted upon the Christian democratizing movement. While some Christians maintained their Christian identity, others accepted their radical ideology. However, during the June Struggle for Democracy in 1987 every social movement group and ordinary civilians got together to achieve a system of direct vote for the President, which was the point of success of realizing democracy in Korea. In the June Struggle for Democracy, Christians took on important roles as major members of the National Movement Headquarters for Democratic Constitution which led the June Struggle. Some conservative Christians joined the June Struggle, but other conservative Christians who supported Chun Doo Hwan had been against the democratizing movement.本稿は、全斗煥政権の時期におけるキリスト教の民主化運動への関わりの実態と、これについての民主化運動の視点からの評価、キリスト教の視点からの評価について明らかにしようとしている。朴正煕死後、光州事件を経て政権を掌握した全斗煥は、朴正煕政権にすぐるとも劣らない強権的性格の政権であった。この時期もキリスト教会とキリスト者は民主化運動を継続したが、1980年代の民主化運動においてはキリスト者の民主化運動以上にマルクス主義の影響を受けた非キリスト者の変革的運動が台頭した。それは光州事件の敗北を経ることで1970年代の自由民主主義的な民主化運動の限界を認識したためであった。このため1980年代の民主化運動は急進的となり、また光州事件に米国が加担したことが原因となって反米的となった。このことはキリスト者の民主化運動にも影響を与えた。これまでの進歩的キリスト者はキリスト者のアイデンティティの堅持を主張する者と急進的な非キリスト者の運動を受容していく者とに分かれていくことになった。しかし、1987年6月民主抗争では大統領直接選挙制実現を求める運動にあらゆる多様な社会運動団体や多数の一般市民が結集して民主化を成就させることができた。そのときにキリスト者が中核となった民主憲法争取国民会議がこの運動の主導的役割を果たした。6月民主抗争には保守的であったキリスト教会の一部も合流したが、全斗煥時代にも親政権的で民主化運動に敵対する保守的キリスト教会が存続し続けた。
1 0 0 0 IR 韓国の民主化運動とキリスト教(3)全斗煥時代
- 著者
- 倉持 和雄
- 出版者
- 東京女子大学
- 雑誌
- 東京女子大学紀要論集 (ISSN:04934350)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.85-119, 2019-03
This article aims to figure out the involvement of South Korean Christians in the democratizing movement in the Chun Doo Hwan regime, and to evaluate this involvement from the viewpoints of both the democratizing movement and that of Christianity.After Park Chung Hee's death, Chun Doo Hwan held political power by suppressing the Kwangju Uprising. His regime was more oppressive than that of Park Chung Hee's. Some Christians continued the democratizing movement during Chun Doo Hwan's regime. Non-Christian democratizing movements (which were influenced by Marxism) became more active than that of the Chirstians. Their movement aimed at social revolution because the activists recognized the limitations of a movement in the 1970's that aimed for Liberal Democracy after the failure of the Kwangju Uprising. After that, their movement became radical and developed an anti-American sentiment because the U.S. had agreed with the suppression of the Kwangju Uprising. These changes impacted upon the Christian democratizing movement. While some Christians maintained their Christian identity, others accepted their radical ideology. However, during the June Struggle for Democracy in 1987 every social movement group and ordinary civilians got together to achieve a system of direct vote for the President, which was the point of success of realizing democracy in Korea. In the June Struggle for Democracy, Christians took on important roles as major members of the National Movement Headquarters for Democratic Constitution which led the June Struggle. Some conservative Christians joined the June Struggle, but other conservative Christians who supported Chun Doo Hwan had been against the democratizing movement.本稿は、全斗煥政権の時期におけるキリスト教の民主化運動への関わりの実態と、これについての民主化運動の視点からの評価、キリスト教の視点からの評価について明らかにしようとしている。朴正煕死後、光州事件を経て政権を掌握した全斗煥は、朴正煕政権にすぐるとも劣らない強権的性格の政権であった。この時期もキリスト教会とキリスト者は民主化運動を継続したが、1980年代の民主化運動においてはキリスト者の民主化運動以上にマルクス主義の影響を受けた非キリスト者の変革的運動が台頭した。それは光州事件の敗北を経ることで1970年代の自由民主主義的な民主化運動の限界を認識したためであった。このため1980年代の民主化運動は急進的となり、また光州事件に米国が加担したことが原因となって反米的となった。このことはキリスト者の民主化運動にも影響を与えた。これまでの進歩的キリスト者はキリスト者のアイデンティティの堅持を主張する者と急進的な非キリスト者の運動を受容していく者とに分かれていくことになった。しかし、1987年6月民主抗争では大統領直接選挙制実現を求める運動にあらゆる多様な社会運動団体や多数の一般市民が結集して民主化を成就させることができた。そのときにキリスト者が中核となった民主憲法争取国民会議がこの運動の主導的役割を果たした。6月民主抗争には保守的であったキリスト教会の一部も合流したが、全斗煥時代にも親政権的で民主化運動に敵対する保守的キリスト教会が存続し続けた。
1 0 0 0 IR (甲斐守護)武田・(甲斐河内領)穴山両氏の対身延山政策
- 著者
- 町田 是正
- 出版者
- 身延山短期大学学会
- 雑誌
- 棲神 : 研究紀要/THE SEISHIN : The Journal of Nichiren and Buddhist Studies (ISSN:09103791)
- 巻号頁・発行日
- no.62, pp.53-73, 1990-03-30
1 0 0 0 IR リレーの教材づくりの視点に関する予備的考察
- 著者
- 大田 貢成 宗倉 啓
- 出版者
- 福井大学教育地域科学部附属教育実践総合センター
- 雑誌
- 福井大学教育実践研究 (ISSN:13427261)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.71-75, 2015-02-13
本稿の目的は、リレーの実践を行うための予備的考察として、「スポーツの競争のもつ進歩性と差別性」 という矛盾に焦点を当て、先行教材に学びながら、スポーツを素材から教材へと改変するための視点に ついて検討することであった。その結果、教材づくりでは、勝敗の結果の偶然性だけを手がかりにして 考案しないこと、個々とチームが競争への意欲をかきたてられるような進歩性をいかに保障するかとい う目標を原則にすることなど、12の事項が導き出された。
1 0 0 0 慢性肺性心に移行した炭肺症の1剖検例
- 著者
- 中野 実 阿藤 紀夫
- 出版者
- 一般社団法人 国立医療学会
- 雑誌
- 医療 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.347-349, 1973
1 0 0 0 目取真俊「虹の鳥」の異同
- 著者
- 銘苅 純一
- 出版者
- 大妻女子大学人間生活文化研究所
- 雑誌
- 人間生活文化研究
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, no.22, pp.109-132, 2012
本稿では、目取真俊「虹の鳥」の初出本文と初版本文の異同を調査した。その結果、2004年に『小説トリッパー』(冬号、朝日新聞社)に掲載された初出と、2007年に単行本化された『虹の鳥』(影書房)には、多くの異同が見られた。異同の総数は469箇所で、そのほとんどは初出と初版の読者層の違いによるルビの削除や、若干の加筆修正であった。しかし、特筆しべき点として、姉・仁美が米兵にレイプされるという設定が加筆されていること、仁美・マユ・1995年の少女暴行事件の被害者が重なりをもって描かれることの二点が挙げられる。これは初出の書評などで述べられた、「人間らしく」描かれる仁美が目取真の思想の変化を示唆するといった指摘への反駁によるものと推察される。すなわち、「人間らしさ」を維持した仁美に希望を託すといった安易な評価は、仁美へのレイプという加筆によって拒絶される。
1 0 0 0 IR 高度成長期の自治体と計画--友納県政期(一九六三年四月〜一九七五年四月)の千葉県の場合
- 著者
- 宮崎 隆次
- 出版者
- 千葉大学法学会
- 雑誌
- 千葉大学法学論集 (ISSN:09127208)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.9-48, 2010-07
1 0 0 0 OA 民事調停の基層にあるもの
- 著者
- 平田 勇人
- 雑誌
- 朝日法学論集 = The Asahi law review, Asahi University School of Law (ISSN:09150072)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.1-23, 2011-09-30
1 0 0 0 雪原の勇者 : ノルウェーの兵士ビルケバイネルの物語
- 著者
- スターラ・ソーズソン再話 リーザ・ルンガ‐ラーセン文 メアリー・アゼアリアン絵 千葉茂樹訳
- 出版者
- BL出版
- 巻号頁・発行日
- 2004
- 著者
- 田上 諒 越前 谷博 荒木 健治
- 雑誌
- 研究報告自然言語処理(NL) (ISSN:21888779)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018-NL-238, no.2, pp.1-6, 2018-12-04
本報告では,対訳辞書などの高品質な対訳知識を用いることなく,コンパラブルコーパスから対訳文を自動抽出する手法を提案する.提案手法では,単語分散表現を用いて翻訳行列と類似度計算を行うことで対訳文を抽出する.その際,類似度計算には Earth Mover's Distance を用いる.更に,提案手法では文長の違いを重みとして類似度に用いることで抽出精度の向上を図っている.ニュース記事のコンパラブルコーパスを用いた性能評価実験の結果,全記事の平均の F 値はベースラインで 0.13, EMD のみのシステムと提案手法にける文長を考慮しない場合では共に 0.42,文長を考慮した場合は 0.49 となった.これらの結果から,文長を考慮した提案手法の有効性が確認された.
- 著者
- 林 宏紀 山下 貴宏 吉田 和敬 砂堀 諭 菅沼 大行
- 出版者
- 一般社団法人 日本食育学会
- 雑誌
- 日本食育学会誌 (ISSN:18824773)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.303-312, 2018
<p>We have reported that ingesting vegetable juices before meals might control postprandial blood glucose level for the prevention of diabetes. In this study, two human intervention studies were conducted under the hypothesis that sugar contained in vegetable juices was greatly involved in its action. Firstly, a 200mL of vegetable juice (①), vegetable and fruit mixed juice (②) or a sugar solution consisting of the same composition and concentration as ② (③) was served 30 minutes prior eating rice and compared the effect of each beverage on postprandial blood glucose with that by the same amount of water. As a result, intake of ② and ③ significantly suppressed the elevation in postprandial blood glucose level. In subjects with the top 50% maximum postprandial blood glucose level after ingesting water, the same effect was also observed by ingestion of ①. These results suggested that the suppressive effects of pre-meal ingestion of ① and ② were elicited via induction of insulin by the sugar in the beverages.</p><p>Next, we evaluated the changes in blood glucose and blood insulin concentrations after ingestion①, ②, ③ and a sucrose solution (④, sucrose water) with the same sugar concentration as in ③. As a result, Tmax, the time showing the highest concentration, of blood glucose level was significantly later in ① and ② than in ③ and ④, and Tmax of insulin was significantly later in ① than in ② and ③. We assumed that dietary fiber and/or other substances contained in ① and ② moderate the absorption of sugar, and presumed that the differences observed in this study affected the difference in the effects in the first intervention study. In addition, in the intake of ④, the Tmax of the blood glucose level was significantly faster than that of ① and ②, and Cmax, maximum concentration, of insulin was significantly larger than that of ①. This supposed that frequent ingestion of sugar water was considered to be a higher risk of diabetes than vegetable juices and vegetable fruit mixed juices containing the same amount of sugar.</p><p>As described above, the suppressive effect on the elevation in postprandial blood glucose level by the vegetable juice and vegetable fruit mix juice may be primarily due to the carbohydrates contained in these drinks, and the composition and concentration of carbohydrates might regulate the timing and strength of insulin induction and affect the effect.</p>