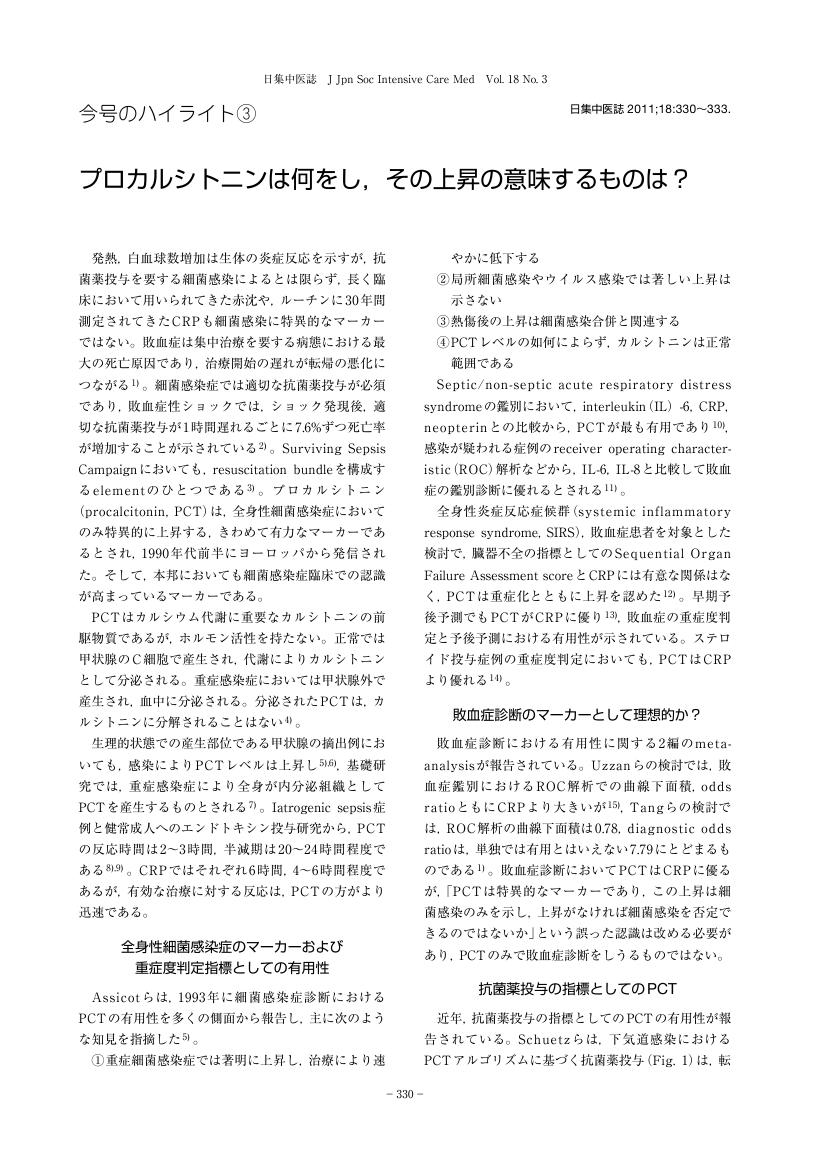7 0 0 0 序 社会的排除/包摂の人類学(<特集>社会的排除/包摂の人類学)
- 著者
- 内藤 直樹
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.2, pp.230-249, 2012-09-30
7 0 0 0 OA プロカルシトニンは何をし,その上昇の意味するものは?
- 著者
- 久志本 成樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.330-333, 2011-07-01 (Released:2012-01-15)
- 参考文献数
- 25
- 著者
- 小野寺 直人 櫻井 滋 吉田 優 小林 誠一郎 高橋 勝雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本環境感染学会
- 雑誌
- 日本環境感染学会誌 (ISSN:1882532X)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.58-65, 2008 (Released:2009-01-14)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 1
岩手医科大学附属病院(以下,当院)では院内感染予防のための新たな支援策として,実施すべき予防策を指標色制定(color coding)により視覚的に周知させることを意図した,当院独自の「感染経路別ゾーニング・システム」を2005年4月から導入した. 本論文では,システム導入の経緯を示すとともに,新たな支援策が各種の感染制御指標に及ぼす影響について,1) 擦式手指消毒薬および2) 医療用手袋の使用量,3) MRSAの発生届出件数,4) 入院患者10,000人当たりのMRSA分離報告件数,5) 院内のアウトブレイク疑い事例に対するICTの介入件数の5指標を,システム導入前(2004年度)と導入期(2005年度),導入後(2006年度)の各年度で比較した. 調査の結果,導入前,導入期,導入後でそれぞれ,1) 擦式手指消毒薬の月平均総使用量は242L, 250L, 235Lと差が認められず,2) 医療用手袋の月平均使用量は261,700枚,338,000枚,410,100枚で導入期・導入後に増加,3) MRSA月平均発生届出件数は23.6±4.3, 20.3±5.5, 19.8±4.6と導入後有意に減少,4) MRSA月平均分離報告件数は21.1±5.1, 14.5±3.9, 13.6±3.1で導入期・導入後に有意に減少,5) 年間ICTの介入件数は7件,5件,3件と減少した.以上から「感染経路別ゾーニング・システム」の導入は院内感染対策の充実,特に大多数を占める接触感染の予防支援策として有効と考えられた.
7 0 0 0 OA 感染症予防と制御を目的とした疾病地図の利用状況と地域差
- 著者
- 荒堀 智彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2020年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.205, 2020 (Released:2020-03-30)
1. 研究の背景と目的 グローバル化が進む現代社会において,世界各地で発生している新興・再興感染症の問題は,公衆衛生上の新たなリスクとなっている.インフルエンザについては,2017年に世界保健機関(WHO)がインフルエンザリスクマネジメントに関する基本方針を発表した.その基本方針の一部には,社会包摂的アプローチの導入が提案されている(WHO, 2017).そこでは,世界レベル,国レベル,地方レベル,コミュニティレベルの各レベルで,経済,交通,エネルギー,福祉などの各分野が協同でリスクマネジメントに取り組むことが明記されている.感染症を撲滅するのではなく,いかにして予防・制御していくのかに重点が置かれ,日常的な備えとして,各レベルにおける効果的な情報配信とリスクコミュニケーション体制の整備が求められている. 世界各国では,感染症の状況把握と分析のために感染症サーベイランスを運用し,サーベイランス情報を地理情報システム(GIS)に組み込んだ,Webベースのデジタル疾病地図の整備が進められている.加えて,それらのツールを利用したリスクコミュニケーションへの応用も行われている(荒堀,2017). 日本では,厚生労働省と国立感染症研究所を中心とした感染症発生動向調査(NESID)が国の感染症サーベイランスシステムとして構築され,1週間毎の患者数や病原体検査結果が報告されている.しかし,NESIDで収集されるインフルエンザ情報は,報告する定点医療機関が5,000と限られており,全国における流行の傾向を知ることには適しているが,地方レベル以下のローカルスケールにおける詳細な流行状況を知ることには適していない.そこで本研究では,日本の各地域における感染症予防と制御に向けたWebベースの疾病地図の利用状況について,調査を行った.2. 感染症専門機関データの収集と構築 本研究では,日本全国の感染症専門機関および地方自治体のWebサイト調査を実施した.調査に先立ち,感染症専門機関および地方自治体のWebサイトのデータ収集を行い,専門機関のデータを構築した.対象となる専門機関および自治体数は82地方衛生研究所,552保健所,1,042医師会,1,977地方自治体である.3. 疾病地図の利用状況 Webサイト調査の結果,地方レベル以下の空間スケールにおける感染症情報を提供している機関・自治体は,332の専門機関および地方自治体のみであった.その内訳は,57地方衛生研究所,116保健所,108医師会,51地方自治体であった.サーベイランスの空間スケールは,一般に,専門機関や地方自治体の管轄に対応している.しかし,医師会は,郡および市の医師会レベル,市区町村レベル,公立学校区レベル,丁目および字レベル,学校施設レベル,病院および診療所レベルなど,さまざまなレベルで提供されていることが明らかとなった.疾病地図による可視化を行っている56の機関および地方自治体のうち,WebGISを使用しているのは3機関のみであり,htmlまたはPDFの画像形式によるものが中心であった. 東京都,愛知県,兵庫県,広島県など大都市を含む都道府県に位置する専門機関や地方自治体においては,保健所レベル以下のローカルスケールのデータを提供していることが明らかとなった.これらの地域に位置する自治体は中核市であることが多く,保健衛生に関する権限委譲に伴う機能の多様化が背景にあると推察される.4. まとめ 調査の結果,日本のローカルスケールにおける疾病地図・WebGISの活用事例は少ないことが明らかとなった.現状では,地図をリスクコミュニケーションに活用するというよりは,情報をWeb上に一方的に流している状態であるといえる.加えて,使用されている疾病地図は,地域特性を反映しているものが少ない.リスクコミュニケーションには,専門家と非専門家(地域住民)との対話が欠かせない要素になる.そのため,リスクコミュニケーションツールとしての対話型地図に関する議論が必要になると考えられる.
7 0 0 0 精神科診療所の立地における大都市集中の意味
- 著者
- 神谷 浩夫
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.221-237, 2002
- 被引用文献数
- 1
これまで日本の医療に関する研究では,社会的な平等性の重視が日本の医療の特色であると指摘されてきた.しかし空間的な観点からみると,自由診療制度を採用している日本では医療資源の地域的な不均衡が生じている.本稿では,精神科診療所の立地パターンを把握し,近年における大都市で精神科診療所が急増している背景とその意味を明らかにしようと試みた.まず,日本の戦後における精神医療の変遷を概観し,現在の精神医療制度が形成されてきた過程を考察した.戦後の日本では「社会防衛」の観点から低コストで患者を収容するために民間精神病院が大量に建設され,その多くは市街地から離れたところに立地した.精神医療が次第に開放医療,地域医療へと向かう中で精神科診療所も増えていったが,それはターミナル駅周辺の地域に開設されることが多かった.1980年代後半に入ると,診療報酬制度の度重なる改訂によって次第に精神科診療所の経営が安定するようになり,診療所の開設が相次ぐようになった.開設された診療所の多くは,従来のターミナル駅指向,駅周辺の商業ビル指向,商業地区.繁華街指向というパターンを強めるものであり,その背景には,利便性を重視して立地する診療所側の要因とともに,通院していることを周囲に知られたくないという匿名性を優先する患者側の要因も存在していた.こうした診療所立地の傾向は,アメリカにおいて精神病退院患者が都市計画規制の緩やかなインナーシティに集積している傾向と類似していた.
7 0 0 0 OA さくら山集
- 著者
- 山川浩 (屠竜子) 著
- 出版者
- 長谷川調七
- 巻号頁・発行日
- 1902
7 0 0 0 OA 咳による空気やエアロゾルの拡散過程の可視化
- 著者
- 朱 晟偉 加藤 信介
- 出版者
- 社団法人 可視化情報学会
- 雑誌
- 可視化情報学会誌 (ISSN:09164731)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.102, pp.180-186_1, 2006-07-01 (Released:2009-07-31)
- 参考文献数
- 18
7 0 0 0 中世後期南都蒐蔵古典籍の復元的研究
- 著者
- 武井和人研究代表
- 出版者
- [埼玉大学教養学部武井和人]
- 巻号頁・発行日
- 2006
- 著者
- 時実 象一
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.206-210, 2017-04-01 (Released:2017-04-03)
全米デジタル新聞プログラム(National Digital Newspaper Program: NDNP)は米国議会図書館(Library of Congress: LC)と全米人文科学基金(National Endowment for the Humanities: NEH)との共同プロジェクトで,1836から1922年までに発行された米国の新聞1070万ページをデジタル化し,Chronicling Americaという検索サイトから提供している。全米40州と自治区が参加している。NDNPの仕組み,記述,Chronicling Americaの検索例,活用例について述べた。またオーストラリア国立図書館が構築したAutralian Newspapers Onineについても述べた。
7 0 0 0 OA 近世以前飯野及国魂史料文書
7 0 0 0 OA 経腸栄養剤の種類と特徴~病態別経腸栄養剤の種類と特徴~
- 著者
- 佐々木 雅也
- 出版者
- 日本静脈経腸栄養学会
- 雑誌
- 静脈経腸栄養 (ISSN:13444980)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.637-642, 2012 (Released:2012-05-10)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 4
経腸栄養剤の種類が多様化し、疾患や病態に応じた使い分けが可能となっている。クローン病の経腸栄養療法、あるいは短腸症候群や膵外分泌不全などの吸収不良症候群における成分栄養剤・消化態栄養剤の使用は病態別経腸栄養法として有用性が確立されており、経腸栄養法が適応となる代表的な疾患である。近年、経腸栄養剤の種類が多様化し、病院で特別食を提供するのと同じように、病態別経腸栄養剤を選択することが可能となった。しかし、医薬品の病態別経腸栄養剤は肝不全用のヘパンED®配合内用剤とアミノレバン®EN配合散の2剤に過ぎず、それ以外は全て食品扱いの経腸栄養剤である。これらは、糖尿病、腎不全、呼吸不全など種々の病態に適した組成となっている。また近年、免疫調整栄養素を強化したimmunonutritionも注目されている。しかし、なかには組成上の特徴だけで病態別経腸栄養剤に位置づけられ、十分なエビデンスがない栄養剤も少なくない。病態別経腸栄養剤の使用においては、個々の症例において確かな有用性を評価して用いるべきである。
7 0 0 0 OA 『百万塔陀羅尼』の語るところ
- 著者
- 勝村 哲也
- 出版者
- 京都大学附属図書館
- 雑誌
- 静脩 (ISSN:05824478)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.1-2, 1998-10
7 0 0 0 OA (1)提言・その1:「生殖関連問題・生命倫理基本法」(中)
- 著者
- 平塚 志保
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.6, pp.427-368, 2005-03-18
7 0 0 0 OA 院政期における「韮」「薤」「蒜」服用の様態
- 著者
- 谷口 美樹
- 出版者
- 富山大学教養教育院
- 雑誌
- 富山大学教養教育院紀要
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.50-69, 2020-03-12
藤原実資(957-1046)の日記『小右記』にみられる薬剤とは、呵梨勒・檳榔子・雄黄・巴豆・紅雪・紫金膏など唐物と称される輸入品であった。一方、藤原頼長(1120-56)の日記『台記』ではそれらを用いる処方例は減少し、薤を頻繁に服用している。また服用する日次について、陰陽師によって占勘されねばならなかった摂関期に比し、院政期では、医師がそれを担うようになる。このような相違を歴史的に位置づけることを目的に、本小論ではまず院政期における服薬の様態を考察する。史料として『台記』のほか、頼長の父である藤原忠実(1078-1162)の日記『殿暦』、頼長の祖父である藤原師通(1062-99)の日記『後二條師通記』などを用いる。薤や韮、蒜などの服用場面、社会的規制の軽重、服用の根拠としての医薬書など、平安貴族社会の身体への取り組みの一端を明らかとしたい。
7 0 0 0 OA イギリス 2018年データ保護法の成立
- 著者
- 芦田淳
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 276-2), 2018-08